1月17日に刊行された集英社新書『「おりる」思想 無駄にしんどい世の中だから』(飯田朔・著)。誰かとの競争に勝って生き残ることを要求される現代社会に対して、自分らしくあるために〝正しいと思われている〟人生のレールやモデルから〝おりる〟ことを模索し提案した一冊である。
そして、この本と似た感じのタイトルの本が2021年に刊行された栗原康さんの『サボる哲学 労働の未来から逃散せよ』である。「おりる」が〝思想〟で、「サボる」が〝哲学〟、その著者同士が対談したら今を生きる人たちにとってきっと興味深い話が出てくるに違いない!ということで、コラボイベントを開催した。その模様をレポートする。
※当記事は2024年6月2日に千葉県佐倉市のときわ書房志津ステーションビル店で行なわれたイベントを再録・加筆したものです。

日野 ときわ書房志津ステーションビル店の日野剛広と申します。ちなみに、飯田さんの『「おりる」思想 無駄にしんどい世の中だから』が本になる際、非常に共感を受けたこともあって、オビに推薦文を書かせていただきました。そういうご縁もあって今日はこの飯田朔さんと栗原康さんの対談イベントになりました。まずはお二人に簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。飯田さんからどうぞ。
飯田 こんにちは。飯田朔と申します。ぼくにとって、この本は初めての著書なんですが、ずっと東京の実家で暮らしてきて、就職もせず、今は30代半ばで、半分引きこもったりバイトしたりしながら生活してきました。コロナ禍以前の2018年に1年間スペインで暮らして、日本に帰国してから集英社の〈新書プラス〉というウェブサイトで、この本のもとになる連載を始めました。それで今年の1月に書籍として出した、という感じです。
栗原 栗原康と申します。ぼくはアナキズムという思想を研究していまして、100年少々前に亡くなった大杉栄や伊藤野枝たちの研究や評伝を書いたり、また、ぼく自身もアナキストだったりするので、その思想を自分が生きたらどうなるかということで、『はたらかないで、たらふく食べたい』(ちくま文庫)とか、今回のイベントのタイトルにもなっている『サボる哲学 労働の未来から逃散せよ』(NHK出版新書)というエッセイ集も書いています。
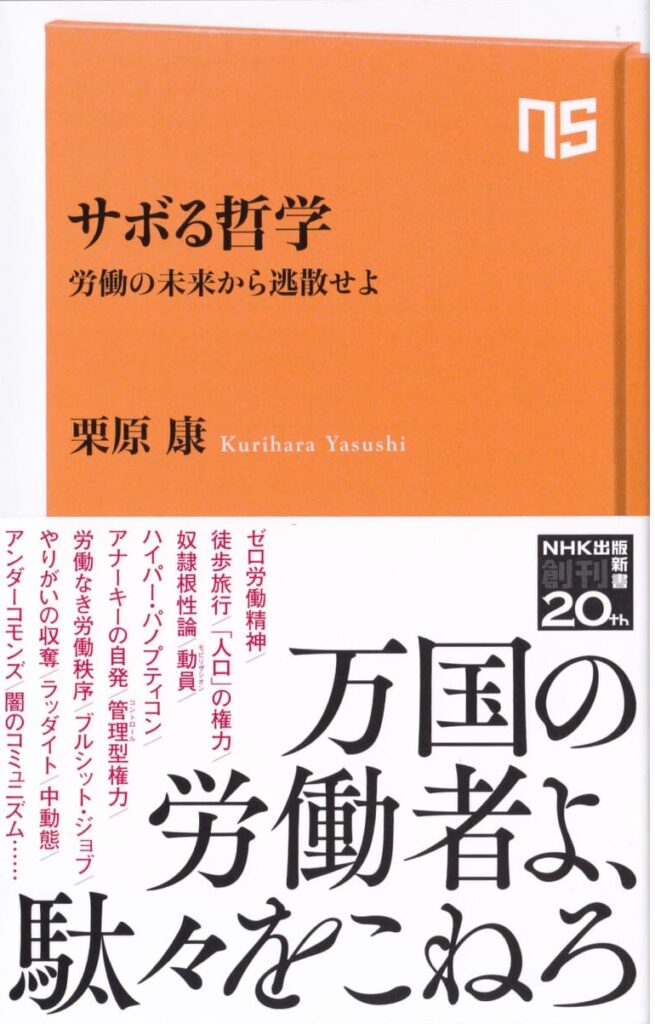
今は週1回だけ金曜日に山形県の東北芸術工科大学で非常勤講師をしています。ぼくが教えているのは文芸学科で、小説家や漫画家になりたい学生たちに思想の話を教えているのですが、「はたらかないで、たらふく食べたい」という言葉は、小説家になりたい子たちには意外と伝わるんですね。大体食えないですから。そんな感じで楽しく和気藹々と授業をやっていて、あと残りの週6日は家にいます。たぶん、飯田さんと同じような生活で、猫好きという共通点もあるので、後でその話もできたらいいかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
日野 というわけで、お二人にそれぞれの作品や作風、人物像などについて、思ったことを話していただきましょうか。では、まず飯田さんから栗原さんについて。
飯田 これまで栗原さんのお名前は色々なところで見かけていたのですが、じつは本を読むのは初めてで、今回『サボる哲学』と新刊の『超人ナイチンゲール』を手に取り、栗原さんの思い描く“アナキズム”とはこんなにのびのびとした思想だったのか、と大いに刺激を受けました。
本の中身に入る前に少し横道にそれたことを言うと、『「おりる」思想」』の中ではぼくよりひと回り上、1970年代後半生まれぐらいの日本の書き手の人たちの本を取り上げて、「今の社会の変な流れや変な仕組みからおりる、という考え方が出てきているんじゃないか」ということを書いてるんですが、そこで取り上げている人たちと栗原さんはちょうど同じくらいの年齢なんですね。
僕自身はアナキズムの本にはあまり馴染みがなくて、唯一読んだことがあるのは大学生時代にカッコつけて買った大杉栄の『日本脱出記』とか『獄中記』くらいで、それはすごく面白かった記憶が残っています。すごくのびのびした人だったんだということが印象的でした。
今回、『サボる哲学』を読んで思ったのは、本の副題に「労働の未来」という言葉が出てくるんですけど、大雑把に言うと「今をどう楽しく生きるかよりも、将来の不安を解消し目標を達成するために今は我慢してがんばりなさい」という労働倫理から体をずらすことについて書かれているのだな、ということでした。
そうやって未来のために働いて今を犠牲にする仕組みや倫理観に対して、サボる身体の対比が描かれる。その中に、歴史の話や栗原さんの生活観や身の回りの話が織り交ぜられて、歴史のようなエッセイのような、そういう一冊になっていると思いました。
日野 栗原さんからご覧になった、『「おりる」思想』と飯田さんはどういう印象ですか。
栗原 飯田さんにお会いしたのは、たまたま知り合いの編集者が「絶対に気が合うと思うから」ということで飯田さんを紹介してくれて、それで『「おりる」思想』を読んだのがきっかけでした。読んでみるとこれがめちゃくちゃ面白くて、考えようとしている問題もほぼ同じかなという印象でした。
飯田さんに「労働の未来から逃散せよ」という副題を紹介していただきましたが、ぼく自身も中学高校時代から「将来はいい就職をしなければならない、そのためにはいい大学に通わなければならない」とがんじがらめになっていくことがすごくキツかったんですね。
アナキズムの思想とは「人に支配されないこと」で、その中に「反労働」という考え方があるんですよ。でも、言葉が硬いし、「反労働をやろうよ」と言ったりすると、「はあ?」みたいな反応をされたりもするので、「はたらかないで、たらふく食べたい」とか「サボる」とか言ってみたんですけど、飯田さんの本のタイトルを見て、「あ、おりる、っていいな」と思ったんですね。柔らかいし、言葉のニュアンスもすごくいい。それで読んで見ると、本当にのめり込んで共感するところだらけでした。
たとえば、序盤の映画批評の中ではプーさんの映画が紹介されていて、その中では子ども時代にプーさんと仲が良かった少年が大人になって、それをユアン・マクレガーが演じているんですが、バリバリのビジネスマンになって働いて疲れきった現在からプーさんのいた過去に引き戻されていく。その作品を飯田さんが紹介していくなかで「クマはわたしなんだ」という一節が出てくる。
実はぼくも『はたらかないで、たらふく食べたい』を書いたときに、「ブタはわたしだ」と言っているんです。家という字は、うかんむりの家屋にブタを囲っているという意味らしいのですが、要するに女子供は男という主人からブタのように飼われる存在だ、ということで、その囲いを突破する開放感を求めていこうよ、ブタ小屋に火を放て、という思いも込めて「ブタはわたしだ」と言っていたんです。それで知人たちから「ブタ様」と呼ばれたりもしたんですが、飯田さんの本を読んでいると「クマはわたしなんだ」と書いていて、「あ、クマ様もいた」と。
飯田 (笑)
栗原 もう1点『「おりる」思想』のすごく面白いところを紹介させていただくと、映画や小説を批評する文章がすごくいいなと思ったんです。というのも、特に文芸批評ってえらそうな人が多いじゃないですか。高みに立って上から目線で批評しているのを読むと、反感しかわかない時があるし、逆にすごく啓蒙的でわかりやすい批評でも、読み手が信者みたいになって、その批評家を崇拝して同じことを語り始めたりするので、批評のある種の権力性に怖さを感じていたんです。でも、飯田さんの場合は、朝井リョウさんの論じ方がすごくいい。
朝井リョウさんを取り上げていくなかで、もちろん批判もしているけれども、飯田さんは朝井さんが考えていないであろうところまで、これはこういう風に読めるんじゃないか、とものすごく熱心に論じていく。そうやって寄り添いながら、飯田さんなりの批判も入ってくる。僕も飯田さんと朝井さんの思考に導かれながら、一緒に読み進むみたいになっていくんです。だから、この『「おりる」思想』の批評の仕方自体が、すごく新鮮で面白いと思って読ませていただきました。
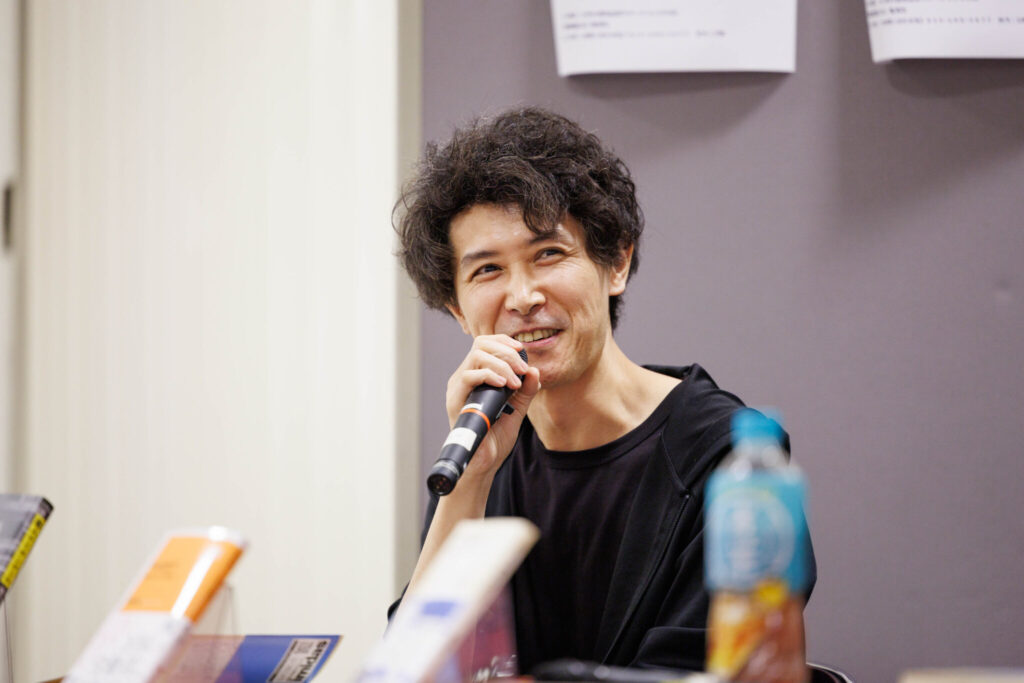
飯田 本の後半部分がまるごと朝井リョウ論で、しかもすごく長いので、本全体のバランスという面では考えるところもあるんですけれども、とりあえず自分自身ではやりきったと思っている面もあります。
映画にせよ小説にせよ、作品を作ることはすごく大変な作業なのに、それに対して映画雑誌や文芸雑誌に載る批評は短かすぎるというか、あっさりしすぎていると思うことがあります。もちろん長くすればいいわけでもないのですが、もっと地道に作品とがっつりと組み合うような、あまりクールじゃない形で批評を書きたいと思いました。とはいえ、栗原さんは「寄り添っている」と言ってくださいましたけど、ずっと粘着しているストーカーみたいな、そういった危うさも自分の中にはあるのかなとも思ったりします(笑)。
栗原 「批評とはストーカーである」っていい言葉ですね(笑)。
『「おりる」思想』についていえば、後半の半分くらいが朝井リョウさんの批評で、これは読みごたえがあってすごく面白かったです。ぼく、実は朝井リョウさんの本をほとんど読んだことがなくて、『正欲』が初めての朝井リョウ作品でした。登場人物たちのさまざまな性的欲望が、ちょっとずつ繊細に絡み合っていく描き方は見事ですよね。
ただ、ぼくが読んだときは「この形式自体が風刺なのかな」くらいに思っていたんです。誰に対しても正しい欲望や性欲というものは存在しないから、「絶対に正しいものなんてない」というメッセージも伝わってくるんですけれども、それをポジティブに捉えているというよりも、なんというか……今の世の中の価値相対主義に対する風刺のように感じたんです。
たとえば、ドナルド・トランプの例が分かりやすいんですが、あれは完全に価値相対主義ですよね。普遍的な価値観として人権や平等が大事とか、差別はいけないとか、そういう絶対的に正しいと言われてきたことに対して、トランプや彼の支持者たちは「そういうのはクソだ」と言うわけじゃないですか。「それは人種差別ですよ」と言われても、「それはあなたが正しいと思っている価値観ですよね」と相対化してきちゃう。朝井さんはそういった風潮を、身近な性欲を題材にして風刺して見せてくれた、と捉えていたんです。
でも、飯田さんはその登場人物たちに目線を落としながら、「自分たちの価値観を突破できない、相対化してしまうってどうなの?」とえぐり出していく。ちゃんと本の中におりていって登場人物たちに寄り添いながら、価値相対化を突破していくことができるのかどうか、とギリギリまで追っていく読み方、批評の仕方だったので、「こういう風に読んだほうが全然面白いな」と感心しながら、「すげえ!ここが読みどころだー!!」って夜中にひとりではしゃぎながら読んでいました。
飯田 朝井リョウの作品では、今の時代に絶対的なものはない、誰もが同意する正しさは存在しない、という相対主義的な考え方が描かれると同時に、それとは反対の、登場人物たちにとって、世の中はめまぐるしく変化するが自分の中でこれだけは変えられない、という譲れなさ、一種のたしかさのような感覚が描かれていて、ぼくは前者と後者は彼の作品の中でぶつかり合う要素であり、後者の方に作品としての可能性があるんじゃないかということを書きました。朝井自身は相対主義的な考え方に含まれる問題をまだ十分には消化しきれていないのではないか、ということがぼくの考えです。
価値相対化といえば、いまの日本の社会ではいろんな場面で強い側と弱い側がいたときに、力関係がごっちゃにされていることがすごく多い気がします。たとえば新聞にAとBの考えを両論併記みたいに載せることは、一見バランスがいいようでいて、実際は有利な立場にいる人と迫害されている人を同列に扱っている。メディアに限らず、普段暮らしていても、そんな力関係がぼんやりしたまま話が進んでしまうことが多い気がして、だからそういうものに対する違和感も、この朝井リョウ論の中に出ていたのかなと思います。
栗原 『「おりる」思想』と同時期に、集英社インターナショナルの新書で、友人の森元斎さんが『死なないための暴力論』という本を刊行しているんですが、彼が書いているのが暴力の言説なんです。暴力といっても、文字通り人をぶん殴るわけじゃなくて、デモをするとか抗議行動を起こすといったことで、海外では人に攻撃は加えなくても警察とバトルになったりすることがあるんですが、日本だと、デモも価値中立的な意見でディスられるわけですよね。たとえば、「安倍政権や岸田政権のやっていることに抗議して民衆の力を振るおう」と言ったとすると、中立ぶった人から「あなたたちの考え方もわかるけれども、たとえ相手が悪いからといって、抵抗に力を振るうのは良くないし、もっと違うやり方があるんじゃないですか」と、ディスられる。違うやり方なんて、ないんですけどね。
いわば、中立ぶった人から「暴力を振るうのはやめろという暴力を振るわれている」ようなもので、この明確な権力関係が見逃されてしまうところが問題だと思うので、『「おりる」思想』は、その問題を明確に捉えているとも言えるかなと思います。
プロフィール

いいだ さく
1989年、東京都出身。早稲田大学在学中に大学不登校となり、2010年、フリーペーパー『吉祥寺ダラダラ日記』を制作。また、他学部の文芸評論家・加藤典洋氏のゼミを聴講、批評を学ぶ。卒業後、2017年まで学習塾で講師を続け、翌年スペインに渡航。1年間現地で暮らし、2019年に帰国。今回が初の書籍執筆となる。
くりはら やすし
1979年、埼玉県生まれ。東北芸術工科大学非常勤講師、政治哲学者。専門はアナキズム研究。主な著書に『サボる哲学 労働の未来から逃散せよ』(NHK出版新書)『はたらかないで、たらふく食べたい・増補版─「負の負債」からの解放宣言』(ちくま文庫)『大杉栄伝 永遠のアナキズム』(角川ソフィア文庫)『村に火をつけ、白痴になれ 伊藤野枝伝』『アナキズム 一丸となってバラバラに生きろ』(岩波書店)『死してなお踊れ 一遍上人伝』(河出書房新社)など。最新刊は『超人ナイチンゲール』(医学書院)。


 飯田朔×栗原康
飯田朔×栗原康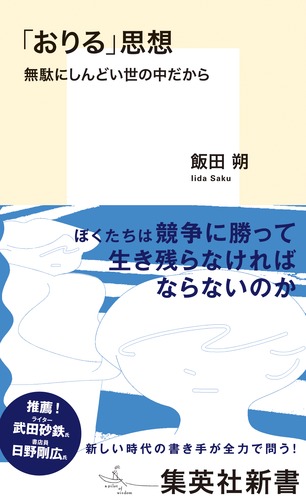










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


