「金がなかったら死ぬ」という恐怖を植え付けられ働かされている
飯田 アナキズムって、栗原さんの本の中で「支配されないことだ」と書いてあって、それを読んで今さらながら「ああそうか、そういう考え方や生き方なんだ」ってわかったんですが、それまでぼくは〈無政府主義〉という訳語での印象を強く持っていました。アナキズムについて「政府なしでどうやって生きていくつもりなんだ……」というような安直な批判がよく投げられていると思うのですが、まあさすがにそこまでではないにせよ、ぼく自身も〈無政府主義〉という訳語が壁になり、なんとなくアナキズムに関する本を読まないできてしまったんです。
最近は栗原さんの本を読んだり、あとはコロナの時期に亡くなったデヴィッド・グレーバーの本を読もうという読書会を知り合いとやったりして、少しずつアナキズムをかじっていくと、資本主義と言われるものや、今の経済の仕組みに自分も呑み込まれている時があるよなぁ、と感じるようになりました。
最近はマルクス主義やアナキズムが再注目されているのかなと思っていたのですが、その理由の一端が今さらながらわかったというか、いま日常を生きていると出くわす「もやもや」としたものについて、その問題の根っこを見据える、大もとのところに切り込んでいく思想なんだなと感じました。

栗原 そうですね。ぼくは人と会ってしゃべると、「あなたもアナキストです、あの人もアナキストです」と言っちゃう方なんですが、「おりる」思想も実はアナキズムなんです。だって、支配しようとする今の世の中からおりよう、と言っているわけですから。だから、飯田さんもアナキストなんです(笑)。
飯田 栗原さんの『サボる哲学』の中では、大航海時代の貿易船のひどい労働環境が、その後の工場労働に引き継がれているとか、アメリカ大陸での奴隷制がその後の資本主義に関係しているという話に興味を引かれました。
奴隷制は今の日本にないはずなんだけれども、社会で自分は不利な立場に立たされているのに有利な立場にいる人たちの弁護をしだす、とか、自分には向いていないのに、あえてその方向に行こうとする、といったふうに、気がつけば自分たちがアリ地獄に入っていくアリになっているような現象がそこかしこに見られます。なんでそうなってしまうのか、という疑問を強く持っていたので、『サボる哲学』で紹介されている様々な本を自分でも読んでみたいと思いました。
栗原 アナキストが資本主義に反対するのは、賃金をもらって労働するというシステムの根っこには奴隷制がある、と考えているからなんです。
奴隷制では、古代から戦争捕虜を奴隷にしてきました。「殺さないでやったから、その恩に報いるために無償で仕えよ」というわけです。最初は抵抗したり逃げたりする人がいても、捕まえられて見せしめに殺される。それで死の恐怖を植えつけられて生死の権利を奪われ、次第に抵抗できなくなって無償で仕えるようになり、人間でありながら捕まえた相手の家畜や所有物になってしまう。
無償で土木工事や農業をやらされたり、戦争に駆り出されるのもキツいんだけれども、それに慣れてしまうことが怖いんだ、と大杉栄は言っています。要するに、奴隷が奴隷でいることに慣れ始めると、「自分たちはご主人様に食わせてもらっている。食わせてもらっている以上は、ご主人様に仕えるのがいいことだ。だからご主人様のために働かなければならない」という道徳が立ち上がってくるわけです。そうなると、働いて「おまえは使える奴隷だ」と褒められたりするとうれしいし、逆に働かない同僚の奴隷がいると、「あいつサボってますよ」とご主人様にチクり始めたりする。そうやって、同じ奴隷同士で上か下かを競いあってしまう。今でもそういう風景ってありますよね。
だから、それは古代の奴隷制に限ったことじゃなくて、近代の賃労働すなわち資本主義も一緒じゃないか、と大杉栄は言うわけです。「金がなかったら死ぬよ」と死の恐怖を植えつけられてしまうと、金をもらわないと生きていけないので工場とか会社で働く。そうすると、お金をくれているご主人様、つまり工場や会社の社長のおかげで生きていけてるんだと思い込むようになる。大杉栄の主張はすごくシンプルで、そういう奴隷根性を打ち砕こう、ということなんです。
そのためには力を行使する。明治大正期は労働法なんてないですから、過酷な労働を不衛生なままやらされているので、「そういう雇い主は一回ぶん殴ってみましょう」と。でも、たいがい負けます。ボコボコにされてクビになるかもしれない。でも、その時には必ず誰かが助けてくれる。共に立ち上がって、一緒に拳を突き上げてくれる人がいる。「負けた時でも意地を張った心地よさが残って、それを手にした瞬間に、あなたは奴隷じゃないよ」と言うわけです。それが大杉栄の労働運動観、ストライキ観です。
ただ、自分たちがブルジョアや資本家に左右されない労働組合や社会主義、アナキズムの運動を立ち上げていくと、今度は「そういう正しいことをやっている集団の価値観」が個人の上に立ってくる場合がある。それに縛られて、そのために何かをしなきゃいけないようになってしまうと、それもまたおかしな話で、いわば奴隷が今度は主義や運動の奴隷になってしまう。だから、そうなったときにどうおりられるのか。そこを考えるのがすごく大切だし、飯田さんがこの本でやろうとしていることもそこなのかな、と読みながら思いました。
飯田 『サボる哲学』と『超人ナイチンゲール』では、どちらも自己と他者の境界が分からなくなる瞬間に着目していると思うのですが、それは「正しい労働運動」「正しいアナキズム」になることから距離を置く、ということとも関係しているんですか?
栗原 そうですね。これも飯田さんが本に書かれていることですが、「世の中のことを気にせず、周囲と同じ価値観じゃなくても好きに生きよう」と言っている人ほど、気づけば、その考えに自分自身が縛られがちじゃないですか。
そこをぶっ壊してくれるのは、ふとしたきっかけやできごとだったり、友達だったりするんでしょうね。それこそナイチンゲールの評伝を書いたときなんて、書く2年前まで全く興味もなかったですから。たまたま医学書院の編集者が「お茶しようよ」「酒飲もうよ」と誘ってくれて、そのときに「〈ケアをひらく〉というシリーズがあるんだけど、ケアという言葉で何をイメージする?」「看護師ですかね」「それだったら、ナイチンゲールがいいんじゃない?」と、ただ一番有名だからということだけで読み始めたら、アナキスト以上に相互扶助の精神を発揮して看護師の集団を作り、どえらいことをバンバンやっていたことを知って、「これは面白い!!」と思って評伝を書くことになりました。
そんなふうに、自分をひょいと横道にそらせてくれるきっかけじゃないけど、自分ひとりではおりられないところを、他人のひとことや出会いで「おりる」ことをやらせてくれる、そういう瞬間があるのかもしれません。
だから自他の区別をせず、他人にふっと影響を受けてしまう、みたいなところをすごく大事にしたいなと考えているんですが、飯田さんは飯田さんで、また別の「おりる」やりかたをされていくんでしょうね。

飯田 たまたま飲んだ友達の発したひとこと、みたいな栗原さんのいまのお話も、それはそれで面白いですね。なんか、ちょっと偉そうな感じですみません(笑)。
というのも、ぼくの本は、「おりる」ためには、自分と他人、社会との「違い」、ズレてしまう部分、社会からはそんなもの捨てろと言われるし、自分でもそうしてみようかと思ってしまう、でもどうしても捨てきれない、いや捨ててはいけない、そういう自分の内部の要素に目を向ける必要がある、ということを書いているからです。自己と他者という対比がはっきりあって、その上で、自己が忘れている、さらに小さな自己に着目するという感じです。
ぼくの場合は大学に進学して初めて不登校になったとき、自分の感覚を殺して無理をして大学に行っているという感覚を強く持ちました。大学であまりなじみのない飲み会に行ったら、顔がすごく痒くなってきて、居酒屋のトイレの鏡で自分の顔が真っ赤になっているのを見て、こりゃだめだ、休もう、と。そこからあまり無理をしないようになりました。
そういう体に現れるサインやクセ、生活リズムというものが、自分でも忘れがちな「小さな自己」だとすると、その一方には無理に適応しなきゃいけない会社や学校、社会という外部がある。そんな対比が頭の中にずっとありました。
とはいえ、『サボる哲学』を読んでいて感じたのは、それとは別に、友達や周りの人との掛け合いや、ふとしたきっかけを通して、何かから「おりられる」こともあるよな、ということでしたね。そもそも批評というのも、自分ではない他人が作った本や映画と取っ組み合いをする中で、自分がそう思ったのか、他人の考えが自分に乗り移ったのか、定かでなくなるような領域に踏み込む、ということもあるような気がします。
栗原 ぼくと飯田さんは10歳違うんですが、飯田さんの大学時代はそれこそ朝井リョウさんの『何者』ではないけれども、大学の中でも、何者かであれ、という雰囲気が広がっていった時期でしょうから、人と会うたびにいつも会話がそんな感じならキツいでしょうね。
ちょうどぼくが卒業する頃からサークルの部室や空間が壊されるようになり、交流スペースもなくされて、授業とサークル活動みたいなものが完全に分断されていきました。飯田さんの年代は、おそらく一番しんどい時期に学生時代を過ごしていたのかなと、ちょっと思いました。
飯田 栗原さんは、奨学金を借りていたんですか?
栗原 学部の頃は親が授業料を払ってくれましたが、大学院は日本学生支援機構に奨学金を借りて635万円、延滞金を入れれば650万円まで借金が膨らみました。学部生で奨学金を借りると400万円から500万円、そこからさらに大学院でも借りたひとは1000万円くらいになるとおもいます。
20代前半の若者が1000万円の借金を抱えて世の中に放り出されるのって、とんでもないことじゃないですか。これもある種の「死の恐怖」ですよね。先ほど、人間が奴隷にさせられる方法は戦争だと言いましたけれども、もう一つは借金なんです。古代からずっと、「借金を返せなかった人間は人でなしだ。だから返せるまで奴隷として働け」という理屈があって、これの現代版じゃないですけれども、学生たちが一度奨学金を借りてしまったら「返済できなきゃ人でなし」と言われるわけです。
実際のところ、海外と比べたら支援機構の催促はぜんぜんゆるいのですが、それでも借りている側には恐怖感があるじゃないですか。そうすると、大学に入って奨学金を借りたら、返すために就職しなきゃいけない。その就職しなきゃいけない、というところに、「カネを稼げる人間にならなければいけない」という「何者かであれ」の論理が入ってくるわけです。そして、それに縛られてどんどん精神的に参ってしまう。飯田さんの年代は、それがいちばん強かった時期かもしれませんね。
そんなふうに奨学金によって生きることが負債化され支配されてゆくことに反対して、僕は仲間と一緒に「借りたモノは返せませーん!!」といって抗議活動もしていました。そんなこともアナキズムの関心とつながっていたのかもしれないですね。
大学のはなしがでたので、もう一点だけ。奨学金を借りないといけないのは、そもそも日本では大学の学費が高かったからです。この数年、それはおかしいと言われて、政府ですら高等教育の無償化を言いはじめていたのに、最近になって、とつぜん東京大学が学費値上げを発表。きっと全国の大学に波及するでしょう。これだけは言っておきたいです。学費を値上げするということは、人間を奴隷化するのと同じことだ。
プロフィール

いいだ さく
1989年、東京都出身。早稲田大学在学中に大学不登校となり、2010年、フリーペーパー『吉祥寺ダラダラ日記』を制作。また、他学部の文芸評論家・加藤典洋氏のゼミを聴講、批評を学ぶ。卒業後、2017年まで学習塾で講師を続け、翌年スペインに渡航。1年間現地で暮らし、2019年に帰国。今回が初の書籍執筆となる。
くりはら やすし
1979年、埼玉県生まれ。東北芸術工科大学非常勤講師、政治哲学者。専門はアナキズム研究。主な著書に『サボる哲学 労働の未来から逃散せよ』(NHK出版新書)『はたらかないで、たらふく食べたい・増補版─「負の負債」からの解放宣言』(ちくま文庫)『大杉栄伝 永遠のアナキズム』(角川ソフィア文庫)『村に火をつけ、白痴になれ 伊藤野枝伝』『アナキズム 一丸となってバラバラに生きろ』(岩波書店)『死してなお踊れ 一遍上人伝』(河出書房新社)など。最新刊は『超人ナイチンゲール』(医学書院)。


 飯田朔×栗原康
飯田朔×栗原康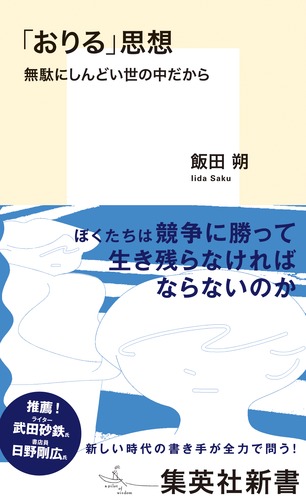










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


