人に素直に依存できる体験を与える――ウディ・アレンをどうみるか
私は、91年から94年まで、アメリカに精神分析を学びに留学したのですが、そこでハインツ・コフートという精神分析学者が提唱した自己心理学というものに出会い、今でも3か月に一度アメリカに通い(と言いながら、コロナで中断し、今はFAXのやり取りになっていますが)、この自己心理学の最高の論客の一人である、ロバート・ストロロウ博士の指導を受けています。
フロイトが打ち出した精神分析は、心の中のコントロールセンターといえる自我という部分を鍛えて、心の自立を目指したものであるのに対し(そのため、精神分析が終結したあとは、分析家に頼ってはいけないというルールになっています)、コフートは、人間というものはそもそも依存的な生き物なので、むしろ自立の強要は不可能なことの押し付けだと主張します。この点が画期的です。
ですので、精神分析のゴールや治療は、精神分析家以外に、周囲の人で上手に依存できる人を探せるようになることだとしています。そして、精神分析が終わっても、たとえばその依存している対象と別れたり、死別したりして不安になったときや、人生上の苦難に一人で対処できないときなどは、また精神分析家のもとに頼りにきてもいいよというのが、コフートの治療技法です。
たとえば、ウディ・アレンという名優・名監督がいます。
アカデミー賞に史上最多の24回ノミネートされ、監督賞を1度、脚本賞を3度受賞しているという最高レベルの俳優であり、監督であり、脚本家である人物です。
彼は、20代から精神分析治療を受けていると公言しています。
現在も精神分析を受けているという話があり、だとすると60年も精神分析を受けているということになります。もちろん、アメリカは、経営者やセレブリティと言われるような人は、自分の精神科医をもつのが当たり前とされるくらいメンタルヘルスに気を遣う国なので、さもありなんということになりますが、精神分析の伝統からするととんでもない話です。
というのも、通常は、5、6年で精神分析を終え、その後は精神的自立をするというのが、典型的な精神分析治療だからです。つまり、アレンは、いつまでも精神分析をやめられないダメ患者、甘えん坊患者で、その治療者(最初の治療者が今も生きていると考えづらいので、途中で変わっていることでしょうが)はいつまでも治せないヘボ医者ということになります。
ところが、コフート学派では、アレンは、治療者に頼りながら、精神的に大きな問題を起こすことなく(アメリカでは離婚は珍しくありません。児童虐待の疑惑はありましたが、訴追はされませんでした)、長年にわたって社会的に成功を収めているので、理想的な患者さんということになります。治療者のほうも、アレンの依存を許しながら、その成功を支え続けてきた優秀な治療者とみなされます。
さて、コフート学派では、精神分析の場で、素直な依存を体験するうちに、最終的には、人間というのは頼ってもいいものだ、信頼してもいいものだと思えるようになることを目標にします。もちろん、世の中には悪い人もいますが、すべてがそうではなく、頼りになる人もいるのだと自覚させるのです。
アメリカ(に限らず、日本も含めて世界中)では、虐待する親が問題になっていますし、日本でも毒親とか、親ガチャという言葉も使われるようになってきました。
親に愛されなかった、親に甘えることができなかった子供は、なかなか人間を信じたり、頼りにしたりできません。ましてや虐待を受けた子供はもっとそうでしょう。
アメリカの精神分析は正式なものだと週に4、5回受けます。私自身もアメリカで経験しましたが、このくらい密に人に自分の悩みを打ち明け、ときに内緒にしていることを話し、それを聞いてもらえると、少なくとも、よほど病理が重い人でなければ、治療者を信頼できる人として体験できるようになります。うまくすれば、ほかの人にも頼ってみようかなと思うようになるでしょう。
金と時間がかかるため、本家といえるアメリカでも落ち目になっているとされる精神分析治療ですが、確かにこのことによって、かなり重いパーソナリティ障害の人が、人に頼れるようになるという点で、今でもこれが必要な人がいると私は信じていますし、それに最も適したのがコフート学派だと言えるでしょう。また、素直に人に頼れないが、社会的・金銭的に成功を収めた富裕層の人にも人気の精神療法になっています。
物質(麻薬や覚せい剤を含む薬物、アルコールなど)や行為(ギャンブル、セックス、買い物など)への依存症を治すためにも、もっとも有効な治療は自助グループとされています。
同じ問題を抱えた人間同士で、自分の弱さをさらけだし、ときにははげましあって、依存症を脱却しようとするものですが、そのいちばん大切なテーマは物質や行為への依存から人への依存に変わっていくことだとされています。
本連載で紹介したさまざまな疎外感は一筋縄ではいかないものばかりですが、それでも素直な依存を体験させることで、自分は一人じゃないんだ、人を頼っていいんだと思えるようになれれば、かなり疎外感を脱却できると私は信じています。
人と接してなくてもいいという開き直り
いっぽうで、森田療法という心の治療法では、「かくあるべし」に苦しむ人を楽にさせることが治療だと考えます。今、国際的にももっとも人気のある認知療法という治療法でも同様の考え方があります。
結婚しなければならない、子供を産まなければならないというような世間の常識(かなり古い常識ですが)に苦しむ人は今なおいます。
そのため、40歳までに結婚して子供を産まなければいけないと女性は焦ることになるわけですし、男性も結婚していないと半端な人間のように自己卑下をする人はかなりの数でいます。
今はダイバーシティという言葉が盛んに使われ、多様な人がいていいし、多様な生き方があっていいという考え方があります。
親友がいなくても、パートナーがいなくても、一人っきりでもいいという開き直りができれば、疎外感に苦しむ人がかなり楽になるかもしれません。
このような「かくあるべし」からの脱却への促しも精神医学の重要な仕事かもしれません。実際、森田療法や認知療法の治療者は、それを日常的にやっています。
たとえば、現在、文部科学省は不登校を悪いこととしないという方向性を打ち出しています(その割には、入試面接や以前も問題にした観点別評価で、不登校を減点の対象にしていることを放任していますが)。
いじめを受けたり、学校の人間関係がつらいなら、学校には行かなくていいということを明言しているのです。無理をして、学校にいき、さらに心の苦しみが増し、自殺するよりましという考え方です。
8050問題が話題になってから、引きこもりが長く続くことに親が焦ることが多くなりましたが(それまでももちろん焦っていたのですが)、私の見るところ、親が焦れば焦るほど、引きこもりの人間は外に出ることが難しくなるという傾向があるようです。
もう引きこもっていてもいいやと親が開き直ったりすると、意外に数か月とか数年のうちに引きこもりが解消するということが珍しくないという話も精神科の仲間から聞いたことがあります。
日本では、集団に入れないとか、友達が少ない、それどころか友達がいない人間を欠陥人間とみる傾向があります。
それが難しい人間には、これが大きなストレスになりますし、上手に周囲と合わせないといけないという気持ちが余計なプレッシャーになります。
一人でもいいんだと思えるようにしてあげることは精神科医や心理のカウンセラーの重要な仕事かもしれません。
私は、さまざまな意味で、コロナ自粛政策に反対してきましたが、唯一の救いは、一人でいることの楽さを多くの人に体験させてあげたことと、テレワークの普及だと考えています。
実は、私はコロナ自粛で、自殺が1万人程度増えるのではないかと思っていました。
というのは、景気が悪くなり失業者が増えますし、日光に当たらないのでセロトニンという神経伝達物質も減る、さらにストレス解消や愚痴をきいてもらうための飲み会なども禁止や自粛というのでは、うつ病が大幅に増えてもおかしくないし、自殺が増えるのも当たり前と思っていました。2011年までは14年続けて日本の自殺者は3万人を超えていたので、そのくらいまで戻っておかしくない(コロナ禍直前の2019年の自殺者は20169人でした)と考えたのです。
ところが蓋をあけてみると2020年の自殺者数は1000人程度しか増えませんでした。コロナ禍は続きましたが、その後も大きく増えていません。
私の考えでは、増えるはずだった自殺者数をなんらかの要因で減らすものがあったということです。それは私の見る限り、テレワークの普及で人間関係のストレスが減ったことだと思っています。
各種調査で、自殺やうつ病の原因の上位に人間関係のストレスがあがっていますし、夏休み明けで学校が始まる9月1日に自殺が急増する9月1日問題が話題になって久しくなりました。
学校に行かなくて済む、会社に行かなくて済むということでストレスやプレッシャーが楽になった人がそれだけ多いのでしょう。
疎外感を覚えている人を楽にするために、会いたくない人に会わなくてすむ勉強や仕事の仕方があるし、無理に人に会ったり、友達を作ったり、人に合わせたりしなくていいということを、コロナ禍を通じて覚えた人が増えたとすれば、それがコロナ禍の不幸中の幸いかもしれません。
ただ、それもいったん外にでると、同調圧力は相変わらずで、マスク使用が個々人の自由になっても、道行く人のほとんどがマスクをしている姿をみると、道遠しの印象はありますが。
一人を楽しむ能力を与える
さて、疎外感というのは主観的なものだという考え方もあります。
確かに大勢友達がいるのに、がんばって周囲と合わせているという人は、実は疎外感を覚えているのではないかというのは、これまで書いてきた通りです。
逆に世間では、独りぼっちと思われている人の中には、それでも自分の趣味の世界などで幸せを感じている人も少なくありません。
私はコロナの自粛政策が嫌いで、この3年間、かなり旅行に出かけましたが、普段なら取れない列車の席が取れるので、それを喜ぶ鉄道オタクの人を大勢見かけました。とくにJR九州の管内には、面白い列車がいろいろと走っていて、その一番前の席に陣取って、この世のものとも思えない幸せな笑顔を浮かべて写真や動画を撮っている人を見かけました。
グリーン席には私とその人しかいないのですから、三脚も立て放題です。
こういう人たちには疎外感は無縁な気がしました。仮に疎外感を持つとすれば、周囲がバカにしたようなことを言うからでしょう。
少なくとも、一人でもいいんだという感覚をもってもらったとすれば、次の我々の仕事は、一人を楽しんでもらうということになるかもしれません。
ゲームを含めて、現代社会には、一人を楽しむツールは数多くあります。
ただ、疎外感を覚えている人の多くは、意外にそういうものを楽しんでいません。
以前、ひきこもりの大家である斎藤環先生から、こういう話を聞いたことがあります。
「ゲームのせいで引きこもりになるという説があるが、それは嘘だ。彼らは、ほかにやることがないからゲームをやるだけだ。その証拠に引きこもりの人は、ゲームをやっているときも、ちっとも楽しそうにしない」
実際、現実を楽しむ能力のようなものがないから、引きこもったり、疎外感を覚えたりするというのは、私の臨床感覚からもしっくりきます。
あれこれと試してもらって、その人が本当に楽しいと思えた時に、やっと疎外感が解決するのかもしれませんが、それは意外に長い道のりかもしれません。
でも、疎外感を覚えている人たちが、人間や治療者を信じていない以上、周囲の人間や医師やカウンセラー側は、きっと楽しんでもらえるものがあるはずだと信じるしかありません。
相手が変わるはずだと信じて、根気よくいろいろとトライしてもらう。それもしようとしないなら、やる気になるまで待つくらいの長い対応が必要だと思えてなりません。
日本に生まれた不幸
ただ、残念なのは、日本には、前述のようにコフート学派の精神分析をやってくれる医者や、その他の手立てで疎外感に苦しむ人を助ける手立てをもっている精神科医がきわめて稀だということです。
全国に82も大学の医学部があるのに、精神科の主任教授が私のように精神療法(カウンセリングなど会話を通じた治療)が専門の大学は一つもありません。
精神科の教授というのは、教授会で決めるのですが、多数決をやると必ずと言っていいほど、脳の研究者のような人が選ばれて、心の治療を一生懸命やってきた人は選ばれません。現在、不戦敗も含めて82連敗というのが現状です。
ゲーム依存症にしても、PTSDにしても、薬では治らない心の病が、むしろ精神医学のメインテーマなのに、ろくに臨床もしないで動物実験ばかりやって教授になった人たちは、人間には心がないと思っているようです。医学生は、原則的に精神医学の講義以外で人間の心のことを習う機会はありません。
おかしな医者が多いから、そうならないように全国82のすべての大学で入試面接が行われているわけですが、人間に心がないと思うような人間に面接で「医者に向いてない」と決めつけられて、医学部に落とされる受験生は気の毒でなりません。面接する側の医学部の教授たちがそういう人間の心の傷つきがわからないのです。教授がこの人は医者に向いていないと決めつければ落とされる入試システムのために、医学部を批判する医者はほとんどいなくなりました。自分の子どもが医者に向いていないと決めつけられるリスクがあるからです。今の医学部の教授たちの人間性を考えると私も十分あり得ると思っています。
入試面接がなかったころは、医学部は比較的学生運動の多い学部でしたが、今は教授が論文を改ざんしようが、研究費を不正使用しようが、みんなが黙っている……。
何が言いたいかというと、入試面接が廃止されない限り、医学部は改革されないだろうということです。ということは、疎外感で苦しむ人が増えても、それを診ることができる精神科医はほとんどいない状態が続くのです。今の精神科医のほとんどは、まともな心の治療のトレーニングを受けていないため、薬で治せない心の病や心の傷にはお手上げなのです。
実際、東北大学に佐藤光源という精神科の教授がいました。15年間の教授在任中に、精神療法の論文には一つも博士号を与えませんでした(私もその被害者です。ちなみに落とされたその論文は自己心理学の国際年鑑で15の優秀論文の一つに選ばれています)。さらに東北地方の精神科の教授戦に影響があった(東北地方の医学部の教授はほとんどが東北大学出身者です)せいか、東北地方の医学部に精神療法の教授はいなくなりました。東日本大震災では多数のPTSDの人が出ましたが、このような徹底した精神療法の排斥や精神療法の指導者不足のため、東北地方で治療できる精神科医は圧倒的に不足したのです(そのため、私はボランティアに行きました)。
これが日本の精神医療の現状なのです。
代わりに、日本では臨床心理士や公認心理師が心のケアにあたっています。公認心理師というのは、やっとできた国家資格です。彼らの多くはスクールカウンセラーなどをやっていますが、大学院を出て、合格率が6割(医師国家試験は9割を超えます)という難関資格なのに、これも厚生労働省か医師会の意地悪のせいか、薄給(年収400万円程度と聞きます)のままです。
それでも、少しずつ開業などして心のケアを行う公認心理師は増えています。
心の病、とくに薬で治らないような心の病を抱える人たちは、それだけでも不幸なのに、日本に生まれたという二重の不幸を抱えることになります。引きこもりがなかなか治らないのもそこに大きな原因があると私は見ています。
でも、疎外感に苦しむ人、あるいは、家族などその周囲の人たちは、あきらめないでそういう心のケアを行う人々に救いを求めてほしいと思います。
私自身、大学院の臨床心理学専攻で長年教員をやっていました。日本の場合、ある学派の精神療法を学んでいる人は、ほかの学派のやり方をあまり知らない人が多いという状況もあります。またカウンセラーというものは必ず相性があるので、すぐに相性のいい治療者に当たるとは限りません。
でも、何人も当たっているうちに必ず、自分に合った治療者が見つかるはずです。
この人は信頼できる、この人といると心が楽になるという治療者を見つけることが疎外感脱出に近づけることは間違いありません。
もちろん、周囲と合わせるのはうっとうしいけれど苦しいほどではない人は、無理に治療する必要はありませんし、一人を楽しめる人はそれでいい。
でも、今、疎外感に苦しんでいるなら、まずは動いてみてほしいのです。
なかなか、人や、そういう治療を信用する気になれないでしょうが、その気になることが、疎外感脱出の第一歩なのですから。
プロフィール

1960年大阪府生まれ。和田秀樹こころと体のクリニック院長。1985年東京大学医学部卒業後、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローなどを経て、現職。主な著書に『受験学力』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『70代で死ぬ人、80代でも元気な人』『70歳からの老けない生き方』『40歳から一気に老化する人、しない人』など多数。


 和田秀樹
和田秀樹
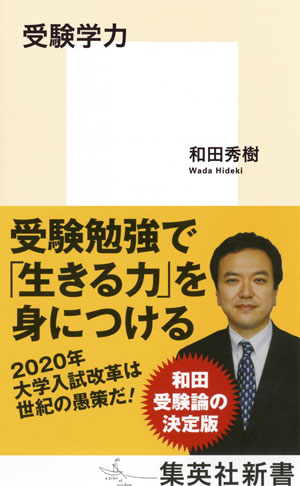










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

