議論に勝つための技術
教養とは、よくわからない概念です。わたしがこの連載で主張しようとしていることは、パーソナル/共同体/環境の3つのスケールを想定し、その循環を把握することで、教養というよくわからないものを捉えなおすことができるのではないかということです。
前回までは、パーソナルなスケールに該当する家政学を概観しました。ここからは、共同体のスケールに該当する「弁論術」を取り上げます。
弁論術といわれて、「ディベート」のことを思い浮かべるかたは少なくないでしょう。ディベートとは、特定のテーマをめぐって賛成と反対の立場に分かれて、本心とは別に「議論に勝つ」ことを目指して議論をすることです。
本心と異なっていても、ディベートの技術に長けていれば、議論に勝つことができてしまう。本心や信念をわきにおいて行うディベートは、その性質から「論破」のための空虚な技術だという考え方があります。ディベートは、知性を悪用するものと考えられ、いわば悪役として扱われることがあるのです。ディベートが悪だとすると、善の側に置かれるのは、その場限りではない永遠普遍の真理を追い求め、その場の議論の相手を説得できなくとも、個人が一生を賭けて思索に向き合う信念や哲学ということになるかもしれません。
修辞学 リベラルアーツの弁論術
かつてアリストテレスは、真理を追い求める「弁証術」と、「弁論術」とを区別していました。字面が似ているので混同しないように注意しましょう。真理を追い求めるのが「弁証術」、議論に勝つ、つまり相手を説得するのが「弁論術」です。
この区別はのちのヨーロッパに引き継がれ、弁証術は論理学、弁論術は修辞学と呼ばれるようになります。論理学と修辞学は、文法学と合わせて、リベラルアーツのなかでも「自由三科」として重要視されました。ここでいう文法学は、中世ヨーロッパのひとびとが理想社会として捉えていたギリシャ・ローマ時代の言葉であるギリシャ語とラテン語を読み書きするための学問です。
文法学を学ばなければ、当時の共有知であり議論の土台だった古典、ギリシャ・ローマの文献を読むことができませんでした。文法学は、現代の感覚でいえば、古典文法とか外国語学という性質が強かったと考えればわかりやすいでしょう。
論理学は、現代の抽象的な記号論理学とは異なり、真理について考えるための技法です。論理学は弁証術を継承し包含していますが、近代哲学の巨人ヘーゲルのいう弁証法とは直接には無関係です。
そして、アリストテレスが弁証術と対比させた弁論術を継承するのが修辞学です。現代のディベートは、修辞学をさらに継承したものだといえるでしょう。
プラトンとソフィスト
アリストテレスは弁証術と弁論術を区別しましたが、どちらが上でどちらが下であるとは言いませんでした。この区別は実はアリストテレスの師であるプラトンの世代から受け継がれたものです。イデア論で知られるプラトンは真理の追究を第一に据え、単なるその場しのぎの「論破」はあきらかに下に見ていました。真理よりもその場その場での議論を優先したひとびとをソクラテスが「論破」してみせる『ゴルギアス』という本をプラトンは書いています。書名になっているゴルギアスとは、ソフィストと呼ばれた弁論術の教育家たちの代表的な人物です。
プラトンの本を読むときに気をつけなければいけないのは、そこに書かれていることは「プラトンが書いていること」だということです。『ゴルギアス』では、ゴルギアスをはじめとするソフィストたちとソクラテスが議論をしています。ここに登場するソクラテスやソフィストたちは実在した人物ですが、『ゴルギアス』という書物の登場人物としてはフィクションの要素を持っています。プラトンによる脚色がどうしても入り込んでいるということです。
アンティゴネー
あなたのお触れは死すべき人間の作ったもの、そんなものに、神々の定めた、文字には書かれぬ確固不動の法を凌ぐ力があるとは考えなかったからだ。この法は昨日今日のものではない、永遠に命を保つもの、いつから現われたか、誰も知りません。私は誰ぞの意向を怖れるあまり、その法を犯して、神々の前で罰を受ける気にはならなかったが、それというのも、当然のことだが、いずれ死ぬことがよく分かっていたからだ。たとえあなたが先のお触れを出していなかったとしても、もし寿命を待たずして死ぬことになろうとも、それは私の得になること。だって、私のように数々の不幸の中で生きる者は、死ねば得をすると、どうして言えぬであろう。
(『アンティゴネ』 ソポクレース 訳 中務哲郎、岩波文庫)
アリストテレスが『弁論術』のなかでたびたび言及している『アンティゴネー』という劇のなかのセリフです。
この作品は、エディプスコンプレックスの元ネタであるオイディプス伝説のオイディプスを父に持つ娘アンティゴネーが主役の物語です。オイディプスは、それと知らずに自分の母親と結婚してしまい、2人の息子と2人の娘をもうけますが、アンティゴネーはその2人の娘のうちのひとりです。オイディプスのあと、交代で王位につくことにした兄たちはやがて争うようになり、片方の兄ポリュネイケスは国外に追放されてしまいます。異国の王女を娶り、祖国に攻め入ろうとしたもののポリュネイケスはもうひとりの兄エテオクレスと相打ちになります。アンティゴネーの2人の兄に代わって国を治めていたクレオンは、祖国に弓を引いたポリュネイケスの遺体を埋葬することを禁じるお触れを出したのですが、アンティゴネーはクレオンの「お触れ」を無視して、兄の遺体を埋葬する儀式をとりおこないます。
複雑な家族関係と、古代ギリシャの死生観が前提になっているので、この物語の何が傑作なのか、すぐにはわからないかもしれません。しかしこの物語は哲学者ヘーゲルや精神分析の理論家ジャック・ラカン、そして近年もジェンダー論の重要な論客として知られるジュディス・バトラーによって繰り返し論じられてきました。国王の「お触れ」に逆らって、家族の遺体を埋葬したアンティゴネーの物語の、何が重要なのでしょうか。
書かれぬ法と書かれた法
アンティゴネーは、さきほど引用した言葉のなかで「文字には書かれぬ」法という表現をしています。これに対して、クレオンの「お触れ」はいわば「文字に書かれた」法ということになるでしょう。この対比は、文字(書字)を批判しながら哲学書を多く残すという矛盾を抱えたプラトンのことを思い出させます。プラトンの師ソクラテスは、書物を残していません。プラトンは、書物を残さなかった師ソクラテスを登場させて、書字を批判する言葉を語らせる書物を書いたのでした。
『ゴルギアス』も、論破術を教えることで名声を得ていたゴルギアスとその仲間をソクラテスが「論破」するという、これまた読みようによっては矛盾した性格を持っていました。ゴルギアスたちは、議会での演説のための技術を教える教師であり、自分自身も見事な演説をしていたと言われます。プラトンは現代の大学(アカデミー)の祖先ともいうべきアカデメイアを創設したことでも知られていますが、プラトンの同時代人で、アカデメイアよりも先に「学校」を開いた哲学者にイソクラテスがいます(ソクラテスとイソクラテスは名前は似ていますが別人です)。
イソクラテスはゴルギアスの弟子のひとりですが、法廷や議会での演説の原稿を書くことで知られていました。イソクラテスは、プラトンのように真理を追い求めるのではなく、人間同士のコミュニケーションを重視しました。良心的ディベート派とでもいえばいいでしょうか。
劇、法廷、議会の時間
イソクラテスの思想は、古代ギリシャ時代が終わりローマ帝国の時代になっても読み継がれました。イソクラテスの思想を継承したローマ時代の哲学者にキケロがいます。そしてイソクラテスとキケロの思想を引き継いだのが、ルネサンスの人文主義の先駆者として知られる詩人のペトラルカです。
プラトンが追い求めたような真理ではなく、誰にでもわかる説得力をイソクラテスは重視しました。そのような実用的な説得を通してこそ、ひとびとの暮らす社会がよりよくなっていくと考えたからです。イソクラテスのこの思想はきわめて人間的(人文的)であり、これが後世の人文主義者に受け継がれていったのでした。イソクラテスの思想は、3つのスケールでいえば、共同体のスケールを重視するものだと言えます。
古代ギリシャには、「クロノス」と「カイロス」というふたつの時間観があったと言われています。クロノスもカイロスもギリシャ神話の神の名前ですが、クロノスは「世界の時間」を司り、カイロスは「その場その場の時間」を司ります。この区別は現代人にはややわかりにくいかもしれません。3つのスケールでいえば、環境のスケールの時間がクロノス、共同体とパーソナルなスケールの時間がカイロスということになるでしょう。時計で計測できる絶対的で客観的な時間がクロノスで、気分によって伸び縮みする相対的で主観的な時間がカイロスです。プラトンはクロノスにおける哲学を志向し、イソクラテスはカイロスを重視した、ともいえます。
先に触れたアンティゴネーの物語では、国家(ポリス)の秩序を代表するクレオンが主観的なカイロスを重視し、人間の死をも含めた客観的な「さだめ」を意識しているアンティゴネーはクロノスを重視していると言えるでしょう。弁論術を単なるカイロス的詭弁として軽視したプラトンとは異なり、アリストテレスはアンティゴネーのクロノス的なセリフをも弁論術として捉えました。アリストテレスは、弁論術を共同体のスケールで捉えていましたが、アリストテレスの考える共同体は、過去を裁く法廷だけでなく、環境のスケールのなかで不確定な未来に向けた決定を行う議会を前提にしているからです。
弁論術は、このカイロスからクロノスへの循環と、またクロノスからカイロスへの循環から、その説得力を引き出しているのです。
現代における弁論術
さて、では現代における弁論術とは何でしょうか。すぐに思い浮かぶのはコミュニケーションのスキル、つまりいわゆる「コミュ力」でしょうか。現代社会で、周囲に馴染めずに孤立してしまうことは恐ろしいことに思われるかもしれません。そこで友達を作り、職場や学校でうまくやっていくための「力」を得たいと考えるのはよくわかります。しかし、その「力」が結局のところ何によってどのように構成されているのかは明確ではありません。
あるいは、今回の冒頭で触れたディベートがやはり挙がるでしょう。コミュ力とディベートは、いっけん関係ないように感じられるかもしれませんが、いずれも現代人のコミュニケーションに関する能力が問われるという点では共通しています。
現代において「リベラルアーツ」を学ぼうとする人は、勤め先や学校での発表、つまりプレゼンテーション(プレゼン)の仕方をまず学ぶことになります。プレゼンのためのスライド資料を作成し、何かをうまく発表することも、コミュ力やディベートとは別のことだと思われるかもしれませんが、その場で求められていることを把握し、自分の立ち位置をアピールするというプレゼンは、コミュ力が発揮される代表的な場面といって間違いありません。
現代の情報環境
現代人はさまざまなテクノロジーに満ちた世界に暮らしています。スマートフォンのメッセージアプリで友人と連絡をとり、暇な時間ができればスマートフォンの動画やゲーム、あるいはテレビを楽しみます。勉強や仕事のときにはパソコンやタブレットのモニターを見つめ、出勤退勤登下校の際の移動は電車やバスに乗り、移動時間もゲームや動画、何かのアプリを使っています。電車やバスもテクノロジーですが、スマートフォンやテレビを見ないで紙の本を読んでいる人もいます。紙の本は、スマートフォンやテレビより前に登場したものではありますが、ほとんどの人が手にしている「本」もまた近代以降に流通するようになった出版産業とテクノロジーに多くを負うメディアであることをここで忘れてはいけません。
コミュ力やプレゼン能力は、テレビ番組やネット上の動画コンテンツと深くつながっています。テレビ番組や動画コンテンツに登場するパーソナリティたちや、彼らが語りかけてくるときに画面にあらわれるテロップやグラフは、数万から数百万の視聴者に向けて、番組や動画の限られた時間のなかで物事を「わかりやすく」伝えているからです。物事を伝えることがコミュニケーションであるとすれば、テレビ番組や動画コンテンツはまごうことなきコミュニケーションであり、数万から数百万の視聴者に短時間で「わかりやすさ」を提供する番組やコンテンツには「コミュ力」があるのです。
無意識とリテラシー
コミュ力について考える際に、テレビ番組や動画コンテンツのパーソナリティやテロップ、グラフなどについて、どうして考える必要があるのでしょうか。それは、メディアを通してわたしたちが触れている映像が、わたしたちの無意識に刷り込まれているからです。わたしたちのうちの多くを占めるひとびとが視聴している番組やコンテンツのパーソナリティの話し方は、わたしたちにとって標準の話し方になります。このことは、テレビやラジオなどのマスメディアが普及して以来、各地の方言が急速に減少しつつあることからも容易に理解されると思います。もとをただせばひとつの都市のいち地域の話し方に過ぎなかった言葉遣いがマスメディアを介して全国に流通した結果、文字通りの「標準語」が生まれたのです。
テレビ番組や動画コンテンツで伝えられた情報を鵜呑みにしないことは、今や当たり前の「リテラシー」と考えられています。この「リテラシー」とは、元々は「読み書き」の能力を指していたことは言うまでもないでしょう。インターネットでのコミュニュケーションについて、自分の身元を容易に明かさない、とか、誹謗中傷をしないといったことは「ネットリテラシー」と呼ばれています。
現代メディアを3つのスケールの循環のなかに捉えなおす
この連載で繰り返し述べている3つのスケールに当てはめてみるとすると、わたしたちを取り巻いているテクノロジーやメディアは、人工的な環境という意味で環境のスケールに該当すると思われるかもしれません。テクノロジーが自然法則や原材料の資源に依存しているということ、また通信インフラのネットワークが地球を惑星規模で覆い尽くそうとしているということを考えれば、たしかに情報環境は文字通り環境のスケールに関係しています。
しかし、マスメディアやさまざまなサービスは、経済的な利益追求のために制作され提供されているものがほとんどです。テレビ番組や動画コンテンツが、ニュースやバラエティのかたちでわたしたち視聴者に情報や娯楽を提供している裏側には、その番組やコンテンツを生み出すための利益追求の仕組みがあります。この利益追求の仕組みは共同体のスケールに該当します。
書物をはじめ、テレビやインターネットなどのコンテンツは、読者や視聴者に情報や娯楽を提供しつつ、その背面にある共同体のスケールを想像させる回路を持っていません。前回まで指摘していた村上春樹や村田沙耶香の作品において、共同体のスケールへの言及が異様なほどに少なかったのはこれが理由です。パーソナルなスケール、つまり読者や視聴者の内心に訴える文学ではなく、企業や行政に関わる人たちのためのコンテンツの場合、そこでは共同体のスケールの話が全面化していると思われがちですが、その背面の仕組みまでは見えません。
テクノロジーやメディアには鏡のような性質があります。たとえばわたしたちは、自分の身だしなみを整えるために鏡を覗き込みますが、そこで見えているのは自分の鏡像だけです。そこではたしかに鏡を見ているはずなのに、わたしたちの目に映るのは自分の鏡像だけなのです。この鏡「そのもの」、もしくは鏡の裏側を見るためには、自分の鏡像(情報、娯楽)から目を逸らして、鏡の横や後ろ側に回り込む必要があります。
メディアの媒介的性質と遮断的性質
テレビ番組や動画コンテンツのなかには、パーソナルなスケールに関わる文学性のあるもの(ドラマ)や、家庭生活のためのTIPSを紹介するものがあります。これは、文学作品や生活術のノウハウについて書かれた書物も同様です。これらのメディア的なものは、情報や娯楽の送り手から、その情報や娯楽の受け手へと、情報や娯楽を伝えるための媒介(メディア)としての働きをしています。問題は、このメディアの媒介という性質に、これまで書いてきたような裏面の仕組みが伴うことです。現代の弁論術は、このメディアの媒介の性質をよりよく扱う術ですが、そのスキルをどんなに高めても、裏面の仕組みにはかすりもしないのです。
ディベート能力やコミュ力、リテラシーを高めても、その、いわば「奥」にある仕組みには到達できない、ということです。現代の弁論術は、現代のメディアテクノロジーという鏡によってカイロスのなかに閉じ込められ、アンティゴネーやアリストテレスが踏まえていたクロノスへと循環することができないのです。
さまざまなメディアとそのテクノロジーは、文字通りの媒介として機能する反面、情報や娯楽を提供する「表側」から、「表側」にアクセスしているひとびとの「裏側」への接触を遮断する機能もあるのです。
次回は、このメディアの媒介的性質と遮断的性質を軸に、引き続き弁論術を論じていきます。
(次回へ続く)

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)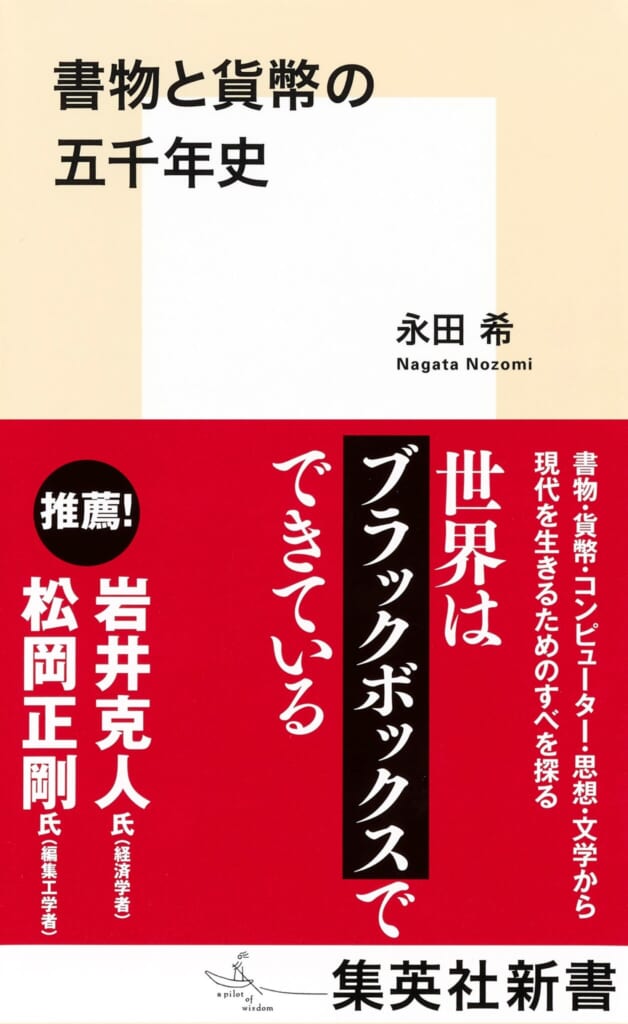










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


