3つのスケール
前回は「教養」を相対的に眺め、捉え直す入り口として「家政学」に着目すると書きました。なぜ家政学は教養を相対化できるのでしょうか。
そもそも家政学とは、料理や家事など、暮らしに密着した知識を体系化した学問です。教養とは対照的に見える家政学ですが、だからこそ、教養を別の視点から眺めることができる。これがわたしの主張です。
教養を捉え直すためには、3つのスケールで考えるのが有効です。ひとつはパーソナルなスケール、次に共同体のスケール、そしてパーソナルも共同体も含み込む、環境のスケールがあります。
家政学ということばは、英語だとホームエコノミクスになりますが、語源的には経済学、つまりポリティカルエコノミーのもとになるオイコノミクス、オイコノミアと共通します。オイコノミクス、オイコノミアはともに、ギリシャ語で「家」を意味するオイコスを扱う学問分野という意味です。
教養を捉えるための3つのスケールを、「家」のメタファーで表現すると次のようになります。パーソナルな「家」はいわゆる家庭や日常生活の現場を指します。これがもっともわかりやすいでしょう。次に共同体のスケールですが、これはポリティカルエコノミーつまり経済学の領域になります。そして環境のスケールの「家」は、宗教的な意味での自然、つまり神が秩序をつかさどる自然を指すことになります。
生態学と翻訳されるエコロジーという学問領域がありますが、このエコロジーという言葉も、やはりオイコスに由来しています。
家とカミ、シモ
自然や神を敬う作法やその思想という環境のスケール(ここにはいわゆる自然科学も含まれる)や、共同体のスケールのビジネスや政治といった知識は、いわゆる「教養」のイメージと相性が良く感じられるでしょう。しかし、プライベートなスケールの話となると、途端に「教養」の威光から離れた日陰の領域に思えてきてしまう。
教養を身につけた人物は、物事の道理をわきまえており、ものの良し悪しを判断できる分別のある人だと考えられています。社会階層の上層にはそのような教養人がふさわしいとされ、教養のない下品な人たちは社会の下層にいる、これは仕方ないということになります。一方、家政学が扱う掃除や料理は、共同体のスケールから家のなかの日陰においやられ、社会的に立場のない、下層の仕事として位置付けられてきました。下品なシモの心配のない、上品なカミの領域だけが、共同体のスケールには開かれているのです。ただし、3つのスケールは、ピラミッドのような階層構造ではないことに注意してください。掃除の結果としてパーソナルな家の外へと廃棄されるゴミは、環境のスケールへと送り返されていきます。シモを抑圧した共同体の領域のさらに上位にある神秘的な領域つまり「自然」は、パーソナルなシモのさらにシモに接続されています。
この循環関係が3つのスケールのあいだに結ばれていることが重要です。
教養ということばは、ドイツ語のビルドゥングや英語のカルチャーの訳語として日本では使われ始めました。ビルドゥングは、乳幼児が大人へと成長していく様子を意味しています。これは、開拓(カルティベーション)に通じるカルチャーが、非文明圏を文明化し、文明の光で野蛮の地を照らすこと、野蛮人を文明人へと教化することとも対応しています。
大地に這いつくばる四足歩行の動物のような赤子に対して、二本の脚で立ち上がる大人になること。動物のような暮らしをしている非文明人ではなく、「人間らしい」暮らしをする文明人になること。教養という言葉の由来には、シモからカミへ向かうこのような志向性があるのです。
今回も、村田沙耶香の『コンビニ人間』と村上春樹の『1Q84』を参照しながら、カミとシモの分断と、循環する3つのスケールを見ていきます。
『コンビニ人間』と『1Q84』にとっての3つのスケール
コンビニエンスストアは、食料品や日用品を24時間いつでも手軽に買える環境を実現します。このことは、かつてあった各家庭独自の「家庭の味」を後退させ、全国の味覚を画一化させるものだと考えることもできます。もっとも、流通の限界からコンビニエンスストアは全国に満遍なく出店しているわけではありません。実は同じコンビニブランドでも、地域差はあります。それでも、外食チェーン、冷凍食品(冷食)やインスタント食材の普及によって、各地域の味覚が画一化しつつあることは間違いありません。このことを逆手にとって、各地域の名物料理があらためて注目を浴び「ご当地グルメ」なるものも登場してきました。これはコンビニエンスストアやスーパーマーケットが発達する前に消費の象徴だった、百貨店で開催される物産展の企画に足を運べば容易に触れることのできるものです。
コンビニエンスストアや外食チェーン、冷食は、ビジネスモデルや生産拠点、材料などの面からグローバリズム(共同体のスケール)を代表するものだと言えます。これに対して、「ご当地グルメ」や「家庭の味」はローカルな魅力(パーソナルなスケール)を体現している、とひとまずは言えるでしょう。しかし、「ご当地グルメ」も「家庭の味」も、材料レベルでみればグローバリズムの影響を無視できなくなります。
たとえば、『コンビニ人間』で古倉が作った「餌」にはジャガイモが含まれています。ジャガイモは原産地が南アメリカ大陸であるだけでなく、現在の日本では自給率が7割程度、つまり3割近くは輸入品になっています。また、味付けに使われている醤油の原料になる大豆はほぼ輸入品です。『1Q84』で天吾が作る料理は、おそらく意図的に多国籍です。まず彼が料理をしているときのBGMは、イギリスのロックバンドであるローリング・ストーンズ。ピラフはトルコ料理が有名ですが、トルコの周辺国のギリシャからインドまで広く食べられており、フランス料理にも取り入れられています。味噌汁は日本料理です。醤油と同じく味噌にも使われている大豆は自給率が低いのですが、天吾は国産大豆にこだわっているかもしれません。カリフラワーの原産地は地中海沿岸と言われています。カレー・ソースのカレーはインドを連想させるでしょう。カレーの風味の中心になるターメリックというスパイスはインドが主要輸出国ですが、中国やインドネシアなどで広く栽培され輸出されています。
そもそも、農作物を育てるために使用される化学肥料には20世紀前半にドイツから普及したハーバーボッシュ法という技術が欠かせません。仮に天吾が国産大豆にこだわっていたとしたら、彼の作る味噌汁に使われる味噌は、化学肥料を使わない有機農法によるものだった可能性もあります。それでは、調理に使用するガスや、オーディオ機器を動かすための電気はどうでしょうか。日本のエネルギー自給率は1960年代までに急激に下落しています。家庭ガスの主原料である天然ガスはオーストラリアなど各国から、発電のためのウランや燃料も輸入にたよっています。
このように、パーソナルなスケールには、意識しようにも把握し続けるのが困難なほど複雑にグローバルな共同体の要素が組み込まれています。ローカルでパーソナルなスケール(家庭)に、グローバルな共同体のスケールで物資を届けるためには、世界各地に拠点を持つ企業のネットワークが必要になります。また、国をまたぐ流通には、国家間のさまざまな規制が影響します。また、いかに企業が努力をしても、惑星規模の天候不順や資源の枯渇があれば、共同体のスケールは根底から揺らぎます。環境のスケールが、共同体のスケールに影響を与える状況です。コロナ禍のような感染爆発や大恐慌や戦争も、共同体のスケールと環境のスケールが互いに影響しあうケースだと言えるでしょう。
数えられるものと数えられないもの
近代経済学を確立したアダム・スミスは、主著『国富論』において、商品の価値はそもそもその商品を生産する労働に由来すると考えました。これを労働価値説と言います。ここでアダム・スミスが想定しているのは『国富論』というタイトルに国家(国民)という共同体が含まれていることからもわかる通り、共同体のスケールです。これに対して、上野千鶴子が参照したシャドーワーク論の提唱者たちはパーソナルなスケールと共同体のスケールのあいだの軋轢を論じたと言えます。マルクスは、アダム・スミスから労働価値説を引き継ぎましたが、『資本論』のなかで労働価値と商品の価格が無関係になってしまうことを示しました。共同体で通用する貨幣で価格をつけられる賃労働(共同体のスケール)と、値段をつけられないことはないが無償で行われて然るべきと考えられてきた無賃労働(パーソナルなスケール)が、マルクスにおいても乖離していたのです。古倉も天吾も、「餌」や「料理」を振る舞う際に貨幣での対価を求めていませんし、それを読者は不思議には思わないのです。したがって、パーソナルなスケールで行われる「労働」は、共同体のスケールから切り離されたシャドーワーク(影の労働)とみなされるのが当たり前ということになります。白羽の言う「ムラの掟」が現代でも有効なのだとすれば、女性は家(パーソナルなスケール)を守り、男性は家の外の共同体のスケールで貨幣を稼いでくることが「当たり前」なのです。企業や国家は他の企業や他の国家より貧しくなるのを避けるために、できるだけ労働者を働かせることになります。そして労働者はより多く働き、より多く稼ぐために、パーソナルなスケールでは生活を無償で安定させることに努めるのです。より抽象的に言えば、共同体のスケールでは商品の価格や賃金のような数えられるもの(可算的なもの)が、パーソナルなスケールでは数えることができないもの(不可算なもの)と引き換えられているとも言えるでしょう。
グローバリズムと「惑星的」
インド出身の思想家ガヤトリ・スピヴァクは『ある学問の死』で、企業や国家のあいだで繰り広げられる共同体のスケールが世界を覆った結果としてグローバリズムを捉え、英語やフランス語のような欧米の言語がもっとも通用しやすいものとして優勢になっていると指摘します。その結果、欧米から見て辺境に位置する地域の文化が、欧米の言語を操る人々によって都合よく解釈されてしまうといいます。これに対してスピヴァクは、グローバルという欧米中心の捉え方ではなく、惑星的(プラネタリー)な態度を提案しています。スピヴァクのいう「惑星的」という態度は、英語で論文を書かなければ世界で通用しないとか、欧米の大学や企業の給料が他の地域の大学や企業の給料よりも高いということを問題視し、相対化しようとする試みだといえるでしょう。
西洋の植民地主義に続く近代文明が序列化した、宗主国(文明国)と植民地(発展途上国)の関係は、本国の文明化を受けた文明人と、文明人から教化を受ける現地人という上下関係に対応します。そして、グローバルな共同体の言語による「文明」から遠くに生きることを余儀なくされる人々は、共同体から疎外されシモへと追いやられます。スピヴァクはそのようなシモへと追いやられた人々の言葉に目を凝らし、その声に耳をそばだてようとします。
スピヴァクのいう「惑星的」とは、共同体のスケールを批判的に捉えるためにきわめてパーソナルなスケールを意識しようとすることであり、カルティベーションの侵略を受ける側、つまり環境のスケールを意識した概念なのです。
「世界システム論」という概念を提唱したことで知られるアメリカの歴史家イマヌエル・ウォーラーステインは『史的システムとしての資本主義』という著書で、人類史において性差別や人種主義がどのように成立してきたかを簡潔に論じています。ウォーラーステインはこの『史的システムとしての資本主義』の冒頭で、資本主義が「万物を商品化」しようとしてきたと述べています。シャドーワーク論という問題提起によって、家事労働もまた賃労働としてみなすべきだと考えるのであれば、パーソナルなスケールに押し込まれていた家事もまた、労働力として共同体のスケールに切り出されていくべきだということになるでしょう。
実際、掃除、洗濯、料理、病人や老人子供の世話というパーソナルなスケールの作業は、商品として売買可能な技術として扱われることがあります。その技術を体系化し、洗練しようというのが、19世紀末から20世紀前半のアメリカを中心に成立した文字通りの「家政学(ホームエコノミクス)」だったのです。
少し考えれば誰でも気がつくことですが、家事と総称される諸々の作業は、個別に商品化はされていました。
たとえばフランスのリアリズム作家エミール・ゾラが19世紀後半に著した小説『居酒屋』で描いた「洗濯女」たちは「洗濯」を仕事にしていました。
中央の通路の両側にある洗濯台に沿って女たちが並び、腕を肩のところまであらわにし、首をむき出し、からげ上げたスカートの下からは色模様の靴下や大きな編上靴を見せていた。彼女らは洗濯棒で激しく叩いき、笑い声をあげ、騒ぎのなかで反り返って何かを叫んだ。盥の底に身をかがめた。彼女らは卑猥で、荒々しく、体をよろめかせながら、驟雨にでも濡れた者のように、膚を赤くして湯気をたてていた。湯桶が運ばれて来て、どっとあけられると、彼女たちの周囲にも下にも、大きな流れができた。活栓は開かれたままで、高いところから水を流していた。洗濯棒の飛沫、布をゆすぐ水滴、彼女らが歩きわたる水溜りは坂になった舗石の上に小川をなして流れていった。そしてこの叫び声や、調子を合わせて叩く音や、雨のつぶやくような響きや、湿った天井の下で消えていく暴風雨のような騒音のただ中にあって、右手の蒸気機関は、細い露で真っ白になって、怠ることなく、息をはずませ、唸っていた。はずみ車の踊る振動は、この異常な喧騒に秩序を与えているようにも思われた。
(『 居酒屋』(上) エミール・ゾラ、斎藤一寛 訳、グーテンベルク 21)
『居酒屋』に登場する洗濯女たちの仕事は、汚れた衣服を預かり洗浄する過酷で卑猥な「シモ」の作業だったのです。
ホームエコノミクスとしての家政学は、ホームつまり「家」の内部にこれらの技術を体系化して取り込もうとする運動でした。
いま「主婦」というと、「夫、妻、子供」で構成される核家族で、パブリックな職業を持たない妻を指します。しかし、「主婦」ということばは、もともとは使用人を抱える上流家庭にあって、家事を担う使用人たちを文字通り「主」として束ねる存在を指していました。ホームエコノミクスは、そのような上流家庭が近代化の過程のなかで解体され、核家族という単位へと再構成される際に、新しく家事を担うことになった主婦たちが学ぶべき学問でした。それと同時に、まだ解体途中でもあった上流家庭に家事担当者(メイドなど)として雇用されるための職業訓練のカリキュラムとしても機能したのです。
「老婦人」と主婦
村上春樹『1Q84』には、青豆に仕事を依頼する「老婦人」が登場します。「料理をする青年」である天吾とは対照的に、「老婦人」には自分で料理をしている描写がありません。「老婦人」は調理どころか、調理場から食卓まで料理を運ぶ配膳すら第三者に委任します。「老婦人」とその来客のための料理の配膳を担うのは、タマルという屈強な中年男性です。タマルは、「老婦人」が暮らす麻布の高台の「柳屋敷」のセキュリティを担当している、とされます。
「老婦人」は、作品中では詳しく語られませんが、天吾以上に社会とうまく付き合える人物として描かれています。「老婦人」は事業経営に天賦の才があるらしく、彼女の資産は苦も無く増殖を続けています。「老婦人」は経済的な才能だけではなく、文化的にも教養のある人物という印象を与えます。資産家であり、かつ教養人でもある「老婦人」は、だからこそ、というべきか、家事の実務には手を出さないのです(『1Q84』の後に村上の書いた『騎士団長殺し』に登場する免色という男性は経済力もあり教養もありつつ、大きな屋敷に独りで住み、自分の世話を自分でします。村上作品における裕福なキャラクターの系譜を辿るのは面白そうですが、本稿ではいったん『1Q84』だけに集中します ※1)。
「老婦人」の経済力は、しかしアダム・スミスのようなポリティカルエコノミーの力ではありません。『1Q84』での政治性はむしろ、この作品のもうひとりのヒロインである「ふかえり」の父親たちの宗教的組織のほうに担わされています。村田の『コンビニ人間』をみてみると、この作品にもアダム・スミス的なポリティカルエコノミーの力を持つキャラクターは登場しません。白羽が想像的な「ムラ」を語り、「老婦人」や『騎士団長殺し』の免色のような成功者に憧れるだけです。『1Q84』でも『コンビニ人間』でも、描かれるのはホームエコノミクスとその残骸だけであり、ポリティカルエコノミーについては語ることを禁じているかのようです。
※1 村上春樹作品では『ねじまき鳥クロニクル』に登場する綿谷登(ノボル)は経済学者であり、また国会議員選挙に出馬し政界を目指すキャラクターでもあります。ポリティカルエコノミーに関連する人物ではあるのですが、3巻からなる『ねじまき鳥クロニクル』でノボルの経済学の思想的な側面や具体的な政策はほとんど描かれません。この連載ではやはり深追いすることはできませんが、ノボルは東京大学経済学部を卒業したのちにアメリカのイエール大学に留学した経験があります。この経歴は思想家の柄谷行人を彷彿とさせます。
なぜ家政学なのか
ここで再び、なぜ家政学から教養を相対化できるのかという問いに戻りましょう。
家政学は、教養を相対化するための3つのスケールのうち、パーソナルなスケール、つまりホームエコノミクスだけがクローズアップされています。つまり、パーソナルなスケールから他のスケールへの回路が閉じられていること。教養を捉え直すために家政学から始めるということは、上方(カミ)への志向性をまとった「教養」に下方(シモ)から、あるいは横から、後ろ(メタ)からアプローチすることになります。
「個人的なことは政治的である(The Personal is Political)」という言葉があります。また、近年は環境問題を政治経済に関連させて捉える考え方が普及しています。そして、エコロジーは20世紀から草の根の運動として営まれてきました。消費者を教育するものとして家政学が体系化されてきたことを考えるとき、3つのスケールは循環を構成するのです。教養という言葉と、またその教養のイメージからかけ離れたものとしての家政学という領域を、ともにこの循環のなかで捉えることが肝心なのです。
次回は、いったん家政学から離れます。日本語の教養に対応する欧米の言葉のひとつに、リベラルアーツ(自由技芸)がありますが、次回はこのリベラルアーツを構成する科目である「弁論術」を取り上げます。雄弁術、修辞学とも呼ばれる弁論術を現代において捉え直すことで、教養や家政学はどのように3つのスケールの循環のなかへ開かれていくのでしょうか。
(第3回へつづく)
参考文献
『史的システムとしての資本主義』ウォーラーステイン、川北稔 訳、岩波文庫、2022年刊
『居酒屋』エミール・ゾラ、斎藤一寛 訳、グーテンベルク 21、2011年刊
『ある学問の死 惑星的思考と新しい比較文学』ガヤトリ・スピヴァク、上村忠男 鈴木聡 訳、みすず書房、2004年刊
『ジャガイモの世界史 歴史を動かした「貧者のパン」 』伊藤章治、中公新書 、2008年刊
『カレーの歴史 (「食」の図書館) 』コリーン・テイラー セン、竹田円 訳、原書房、2013年刊
「「主婦」ということば ― 明治の家政書から ―」 広井 多鶴子、群馬女子短大『国文研究』、2000年刊

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)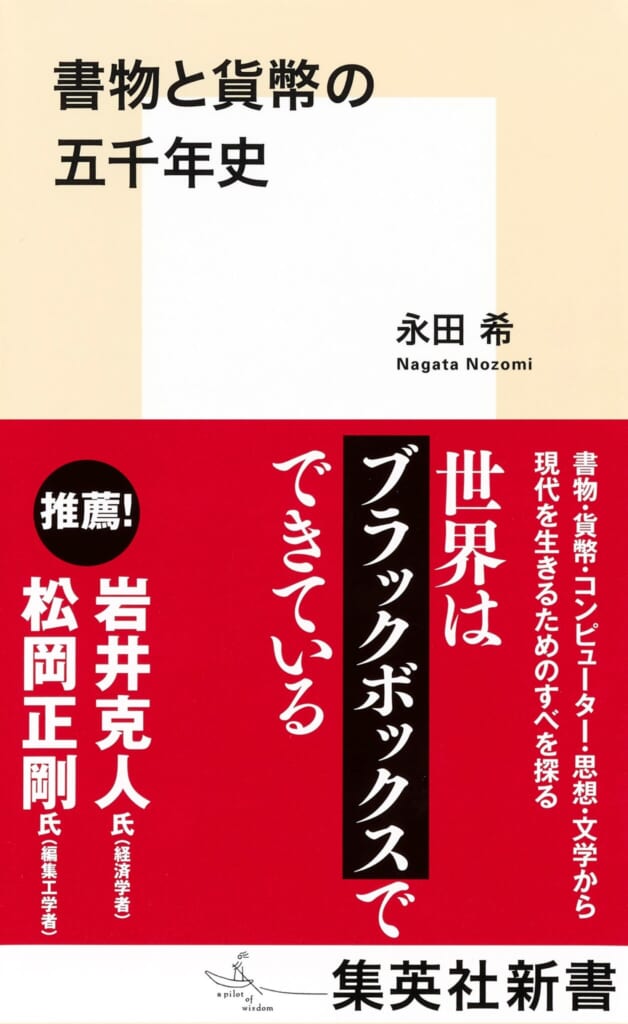










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


