県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦から80年。ふたたび沖縄が“要塞化”される今、「自分の街が戦場になる」とはどういうことか考える
 林博史×川満彰
林博史×川満彰1945年3月末からの約3ヵ月間、沖縄には米軍が上陸して激しい地上戦が繰り広げられ、軍民合わせて20万人もの命が失われた。戦後も長らく沖縄は米軍に支配され、日本に返還後も多くの米軍基地が存在している。
また、最近では近隣諸国を仮想敵として、全国で自衛隊基地の強靭化や南西諸島へのミサイル配備が進行中だ。
狭い国土の日本が戦場になるとどうなるのか?――沖縄戦の悲劇の構造を知ることで、その実相が見えてくる。
沖縄戦研究の第一人者・林博史氏は、膨大な資料と最新の知見を駆使して『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』を上梓した。
その林氏との共著『沖縄県知事 島田叡と沖縄戦』(沖縄タイムス社)を昨年2024年に刊行した沖縄戦研究者の川満彰氏が、多大な犠牲を生んだ沖縄戦の背景と、新たな戦争を防ぐために何が必要かについて語りあった。
構成=稲垣收
沖縄が再度“要塞化”されつつある今こそ、沖縄戦について知ってほしい
川満 この『沖縄戦』は本当にすばらしい本だなとつくづく実感しています。林先生が2001年に出された『沖縄戦と民衆』(大月書店)は2002年に伊波普猷賞(*1)を受賞されましたが、あの本はいまだに私たち沖縄戦研究者にとってバイブル的な扱いなんです。
今回のこの本はそれをさらにブラッシュアップし、2001年からこれまでの間に蓄積された資料を追加して書かれていますね。本の帯に「膨大な史料と最新の知見で編み上げた沖縄戦史の決定版!」とありますが、まさにその通り。これから沖縄戦を学んだり研究したりする人や、今学んでいる人たちにとっても、新たなバイブル的存在になるだろうと思います。
*1:沖縄研究の父と言われる伊波普猷の業績を顕彰し、沖縄タイムス社が創刊25周年を記念して1973年に創設した賞

私は今、沖縄戦について、より多くの人たちに知らせたい時期だと本当に思っています。沖縄は新たに“要塞化”されつつある。自衛隊の南西諸島への配備(*2)が着々と進んでいるのです。そして、住民の避難計画を国と当事者である各自治体の首長が率先して行っている。これはまさしく沖縄戦をほうふつさせるものです。
戦争はいったん始まってしまったら、もう止めることができませんから、そういったことを問題視しないといけない。だからこそ今、沖縄戦について知り、語ることが非常に必要なのです。
あと一点は、最近の中谷防衛大臣の発言(*3)です。中谷大臣は、沖縄戦で総司令官だった牛島満の辞世の句を、「あれは平和を願う辞世の句だ」などという本当に訳の分からない解釈をしました。こういう行為は戦争を正当化する言葉につなげられていきます。ですから、「あの辞世の句は何だったのか?」ということも含め、今こそ改めて沖縄戦を学ぶ必要があるのです。この本はそれに最適な本だと思います。
*2:米中対立が進む中、2000年代以降、政府は抑止力強化のための「南西シフト」を掲げ、2010年に那覇駐屯地を拠点とする陸自第1混成団を第15旅団に増強。日本最西端の与那国島には2016年に沖縄本島以外で初の陸自部隊を配置。奄美大島、宮古島、石垣島にも基地を新設。ミサイル配備も進めている。
*3:沖縄戦を指揮した第32軍牛島満司令官は、米軍の攻撃を受けて首里城地下司令部から南部へ撤退、持久戦に持ち込もうとして、多くの兵士および民間人の犠牲者を出した。彼は1945年6月23日に自決する直前、「秋待たで 枯れ行く島の 青草は 皇国の春に 甦らなむ」という辞世の句を詠んだが、この句が陸自第15旅団(那覇駐屯)のホームページに掲載されており、「皇軍を美化するものだ」「沖縄戦の犠牲者に対する配慮がない」等の批判を浴び一時取り下げられたが、ホームページのリニューアルに際し再掲された(現在の掲載の表記は「秋を待たで 枯れゆく島の青草は 御国の春に よみがえらなむ」)。これに対し、中谷元・防衛大臣は「先の大戦において犠牲になった方々に心からの哀悼の意を表して、その教訓を活かしてこれからの平和をしっかりと願うという歌と受け取っております」と発言し、陸自のホームページから削除しない方針を示した。
日本全土が沖縄戦のような戦場になる可能性がある
林 ありがとうございます。沖縄戦の研究に関しては、まず沖縄の研究者の方たちがリードしてきて、その成果が1980年代、90年代に出ました。軍の視点からでなく沖縄の住民の視点から、住民の犠牲の実相を非常に詳細に明らかにされる仕事が出てきた。それで「沖縄戦って、こういうものだったのか」というのが明らかにされてきました。
ただその後も、さらに調査や研究が進んでいます。それを私は川満さんに先ほど紹介いただいた『沖縄戦と民衆』などで書いてきたんですが、あの本は2001年刊行で、もう24年前になる。この間、「沖縄県史」の沖縄戦編が発表されたり、様々な成果が出てきています。にもかかわらず、それら新しい調査や研究を反映して「沖縄戦とはこういうものなんだ」とわかりやすく読めるような本が全くなかった。そのため、いろんな人と話をしていても、沖縄戦がかつての古いままのイメージで語られている、と感じることがありました。そこで、ぜひ一冊、そういう新しい成果をまとめたものを、できるだけ多くの人に読めるような形で出したかった。
それと同時に、沖縄戦がもう本当に過去のものであればいいけれど、先ほど川満さんも言われたように、この間の米軍や自衛隊、日本政府、日本社会全体の動きを見ていると、沖縄だけでなく、日本全土をもう一度戦場にすることを想定したことがどんどん行われてきています。これはもう沖縄だけの問題じゃなく日本全体に関わる問題なのです。すると「沖縄戦から何を学ぶのか?」ということが極めて重要になるのですが、そこが全然、論及されていません。しかし沖縄戦のような悲惨なことを二度と繰り返さないためには、沖縄戦からもう一度学び直す必要がある。これは現在の日本の状況から見て、極めて重要な課題だと思います。

特に、沖縄戦の中で住民が多く犠牲にされた一つの要因が、「軍民一体」あるいは「軍民が混在している」という状況の中で、住民を保護することが全く行われないまま戦闘が行われた。そこの教訓というのはすごく大きいはずですが、それは今、全然顧みられていません。
普通の民間の人々が住んでいるところのすぐ近くに、自衛隊が新たに基地を配備していく。現在の日本では、もうすでに自衛隊基地や米軍基地と民間の地域が隣接、混在している。こういう状況で戦争があったらどうなるのか? 沖縄戦というのは、まさにそういう戦いだった。その意味でも、沖縄戦から何を学ぶのかが緊急の課題なのです。そういうこともあって、沖縄戦についてできるだけ多くの人に読んでもらえるような本を、ともかく早く書かないといけない、と思った次第です。
川満 本書のポイントとしては、まずは林先生の広い角度のある書き方です。こういう書き方は、私たち歴史学的に沖縄戦を追求してきた人には、実はなかなかできない、というのが率直なところです。私たちは「住民対日本軍」とか「官の役割」とかいうことで「戦争責任がみんなある」ということをよくやっていたんですが、林先生の場合、タイトルで言えば、「死を拒否した人々」、「生きることを選んだ民間人」や「助かった人たち」とか「生きようとした防衛隊員」などのように、これまで書かれてきたものから抜け落ちていたものをきれいにグルーピングして、「なぜ彼らは助かったのか」というところなどをきちんと取り上げているんです。まさしく沖縄戦の全体像を表すようなグルーピングの仕方で、これに私は「ああ、そうなんだよな」と思いました。本書を通して、こうした側面に自分の思考がこれまでなかなか及ばなかった、という非常に反省するべき点が明らかになりました。
私は一つのことを追求すると、そこにずっと焦点を当てしてしまいがちなのです。たとえば日本軍の起こした住民虐殺の理由として、「住民たちが陣地構築などに動員されて軍事機密を知っていたので、住民の口からそれが米軍に漏れることを危惧していたからだ」という議論がある。しかし林先生は、「背景には、それが確かにあるかもしれないけれど、それだけではないだろう」ということを明確に書かれています。本当にそのとおりです。
私自身はいろんなものに書く際に、それをあまりにも強調し過ぎていたな、と大きく反省しています。頭の中には「それだけじゃない」というのがあるんですが、書く際に、どうしてもそこを強調し過ぎて……。林先生のそういった書き方を読んで、これから私たち、特に私は、「もう一回ちゃんと見据えて物を表現しないといけないな」と反省しています。
「国の言うことを信じていれば死ぬしかない」という沖縄戦を経験して
戦後、沖縄は民衆の社会運動で傑出した地域となった
林 私は『沖縄戦と民衆』以来、沖縄戦の中で生き抜いた人々、あるいは、生きようとしたけれども残念ながら亡くなった多くの人々に、すごく関心を持っています。理由の一つは、本土からたくさんの人が沖縄に行って、たとえば、ひめゆりの平和祈念資料館や摩文仁の平和祈念資料館に行く。そこで「沖縄の人々というのは当時の軍国主義の中でそれを信じ込んでいて、かわいそうな犠牲者だったね」という感想だけで終わってしまう。本土の人々が持っている沖縄戦のイメージは、そういう受け止め方がすごく多いのです。しかし「かわいそうだったね」で終わってしまっていいんだろうか、と思うのです。
私は沖縄の中から考えているというより、東京に住んでいて、日本全体の視点から日本国家が沖縄を犠牲にしたという観点で、沖縄を外から見ているんですけども、戦後の沖縄は、実は1950年代以降、島ぐるみ闘争(*4)をはじめとする闘争や、日本への復帰運動、その後のいろんな運動を含めて、おらく日本全体の中でも人々の、民衆の社会運動として、すごく傑出した地域だと思うんです。
その沖縄の人々の主体性というか、積極的に生きようとしている力、あるいは「自分たちの社会を変えていこう、自分たちの未来を自分たちで切り開こう」という力がどこから生まれてきたのかを考えてみると、沖縄戦というのが極めて重要なのではないかと。
もともと近代の沖縄では、実は社会運動はすごく弱かったんですね。それがなぜ戦後、これだけの主体的な力を作ってきたのか? それは沖縄戦の中で「日本という国家の言うことを信じていれば、もう死ぬしかない」という状況に追い込まれた、その中で生きようとした人たちがいたからだと思うんです。
国家の言うことを信じていれば死ぬしかないけども、そこで「生きよう」という選択をして、自分たちの頭で考えて行動し、生き抜いてきた――そういう沖縄の人々の主体性を、もっと評価したい。むしろ本土の人間こそ、この沖縄の人々の自立した考え方や行動から、もっと学ぶべきだ、という思いが私にはあって。
いろいろな人々の体験記をずっと読んできて、どうやってその人々が生き延びたかを見ていくと、自分たちで考えて、選択をした。たとえば、「捕虜にならずに自決しろ」と言われていたけれど、みんなで米軍に投降するとか、主体的に「生きる」ことを選択してきた。もちろんその陰には、生きようとしながらも、生きられなかった人もたくさんいたのですが……。

生き抜いた人々の生き方からもっと学ぶことができるんじゃないか、学びたい、という、そういう思いでこの本を書いたんです。そして逆に、「生きようとした人々、生きたいと思った人々をなぜ死に追いやってしまったのか? なぜ殺してしまったのか? そうさせたのは何だったのか?」ということをやっぱり突き詰めたい、と。「なぜ20万人が犠牲になったのか」と今回の本のサブタイトルにも付けましたが、そこをきちんと明らかにし、そこから学ぶ必要があるという思いで、生きようとした人々のことをかなり詳しく取り上げました。
*4:1956年、アメリカ施政権下の沖縄で起きた、軍用地をめぐる市民の大規模闘争。54年に米側が軍用地料を10年分一括で払うと提示したが、これを「土地の買い上げ」と見た住民は反発し、方針撤回を求めた。だが米側は土地の強制収用を開始し、住民の抵抗が激化。56年6月、米軍による軍用地政策をほぼ是認する米議会の勧告が出されると沖縄各地で反対集会が開かれ、日本復帰運動とも相まって激化、同年夏の「島ぐるみ闘争」に発展した。
川満 本当にそうなんですよね。私は15年ほど名護市の教育委員会で沖縄戦の『市史』を作るために編集作業と調査をやっていました。その中で体験者の話を非常に多く聞かせてもらい、学ばせてもらいました。その体験者は、生きているからこそ語れるわけですが、生きている人たちのまわりでも、親戚とか地縁の方がたくさん亡くなっていらっしゃる。だから、生きている人たちから「亡くなった人たちがどういう人たちだったのか」を聞くことも非常に大切だと思って、必ず聞こうとしてきました。つまり、平和の礎(*5)に名前を刻まれている人たちが実際に生きていたんだということを、どうやって今の人たちに伝えることができるのかを意識してやってきました。
ただ、「生き残った人は、なぜ生き残れたのか?」という視点が、私自身には足りなかったと思います。林先生のこの本を読んだり、『沖縄戦と民衆』を読み返したりして、あらためてまた目が開けた感じがあります。
生き延びた人たちがなぜ生き延びることができたのかを考えることは、今につながっていくんです。「これから戦争をしないためには、どうするべきなのか?」というところで、非常に大きな教訓になる。
これから、戦争を体験した人たちは少なくなっていくでしょうが、生き残った人たちが体験について書いたり、私たちも聞き取りをさせてもらっていますので、なぜ彼らが生き残れたのか、どういうふうに生活していたのかということは、何度でも振り返ったほうがいいと思います。
*5: へいわのいしじ。国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなったすべての人々の氏名を刻んだ祈念碑。1995年に建てられた。
単に「戦争は嫌だ」というだけでなく、
「犠牲を大きくさせたものは何だったのか?」を見ることが大切
林 「生き延びた」ということと、「生きようとしたけども死んでしまった」ということも含めて、なぜ20万人が犠牲になったのか? 確かにこれは戦争の中で亡くなっているのですが、今、日本社会においては「戦没者のおかげで今日の平和がある」とか「日本の繁栄がある」というように、「戦没者のおかげで」という言い方をします。でも、たとえば沖縄戦で亡くなった20万人は、本当に戦争や戦闘で亡くなった人ばかりなのでしょうか?
たとえば住民は、避難するためにガマ(自然の壕)の中に隠れています。そこにアメリカ軍がやって来て、外から「出てきなさい。出てくれば助ける」というふうに呼びかけるわけです。出ていけば助かるわけです。1945年当時の世界の国々を見ると、民間人がそういう状況で出ていけば保護されるのが当たり前の時代でした。だから、呼びかけに応じて出ていけば、みんな助かったわけですね。
ところが当時は兵士だけでなく、たとえ民間人でも「捕虜になってはいけない」「捕虜になるぐらいなら自決しろ」と言われていた。そのせいで、たとえばガマの中で手榴弾を爆発させて死んでしまった人が少なくありません。
あるいは、自決までしなくても、米兵の呼びかけにずっと応じず出ていかなければ、米軍はガマの中に誰がいるか分からない。もし日本兵が潜んでいると、後から出てきて自分たちが攻撃されてしまうので、ガマを一つひとつ手榴弾や爆雷、あるいはガソリンを流し込んで火をつけて、全部潰していった。それで殺されてしまった。こうして亡くなった人たちも、「戦争の犠牲者」という言い方で、ひとくくりにしていいのでしょうか?

この人たちは、「戦争」ではなくて、当時の大日本帝国――あるいは天皇制国家と言い換えてもいいと思うんですが――日本という国家によって、死を余儀なくされたわけです。決して「戦争によって死んだ」わけじゃない。そういう人々が実は膨大にいるのです。
たとえば、日本軍が首里から南部に撤退します。首里が陥落するという時点で、この沖縄戦という戦闘自体の決着は、もう誰の目にも明らかでした。日本の第32軍の司令部の者たちも皆わかっていた。そこで降伏していれば、おそらく20万人の犠牲者のうち半分以上が助かっていたでしょう。少なくとも戦闘があれほど長引かなければ……。戦闘が長引いたせいで、たとえば山の中に逃げて食糧がなくなって餓死したり、マラリアにかかって亡くなった人もたくさんいるのです。首里で戦闘が終わっていれば、20万のうち半分以上は助かったはずです。それなのに、そのすべての犠牲者について「戦争のせいだ」と言って片付けてしまうと何も学ぶことができません。「なぜ当時の日本国家というものが、そこまでして人々に犠牲を押しつけたのか?」それを考えることが大切なのです。
これは住民の犠牲だけじゃなく、日本軍の兵士もそうです。兵士たちも、武器も弾薬も食糧もなくなったら手を挙げて降伏し、捕虜になれば命が助かったはずです。しかし日本軍ではそれが許されなかった。あれほど多くの人が犠牲になったのは、当時の日本という国家のそうした仕組み、そういう考え方に原因があるはずなんです。
ですから、戦争から学ぶというのは、単に「戦争は嫌だ」とか「戦争をやってはいけない」という感情的なものではなく、具体的にその中で「犠牲を大きくさせたものは何だったのか?」を見ることです。そして、そういう犠牲を生んだ社会の仕組みや考え方を変えて、そういうことが二度と起こらないような国の仕組みを作ることです。
今の日本は自衛隊という一つの軍事組織を持っています。自衛隊を軍隊と見るかどうかは議論がありますが、軍事力を持った組織であることは間違いない。その自衛隊が人々を本当に保護するような、守るような組織になっているのかどうか? そこをきちんと総括して、沖縄戦で起きたようなことを二度と起こさないような政治や社会の仕組みにし、行政組織も軍事組織も、そういうふうに変えていかないといけないのです。
しかし終戦後の日本は、そうしたことを全く放棄して、「戦争が悪い」ということで全部処理してしまった。これは沖縄戦だけじゃなく、戦後日本社会の戦争に対する捉え方のすべてをもう一度根本から見直さないと、現在の日本の軍事化の中で、また同じことが繰り返されてしまう恐れがあります。
生きようとしたけど生きられなかった人々の問題は、そこにもつながっていくと思います。
(後編に続く)
プロフィール

(はやし ひろふみ)
1955年、神戸市生まれ。現代史研究者、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(社会学博士)。関東学院大学名誉教授。主な著書に『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』(集英社新書)、『沖縄戦と民衆』『沖縄戦が問うもの』(大月書店)、『沖縄戦 強制された「集団自決」』『米軍基地の歴史 世界ネットワークの形成と展開』『帝国主義国の軍隊と性 売春規制と軍用性的施設』(吉川弘文館)、『朝鮮戦争 無差別爆撃の出撃基地・日本』(高文研)、『BC級戦犯裁判』(岩波書店)等多数。

(かわみつ あきら)
1960年、沖縄県コザ市生まれ。沖縄国際大学非常勤講師。2006年、沖縄大学大学院沖縄・東アジア地域研究専攻修了。 著書に『陸軍中野学校と沖縄戦』(吉川弘文館)、『沖縄戦の子どもたち』(吉川弘文館)他、共著に『戦争孤児たちの戦後史1 総論編』〈共編〉(吉川弘文館)、『沖縄県知事 島田叡と沖縄戦』(林博史との共著、沖縄タイムス社)などがある。
県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦から80年。ふたたび沖縄が“要塞化”される今、「自分の街が戦場になる」とはどういうことか考える


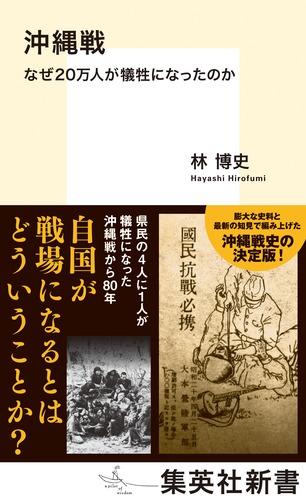
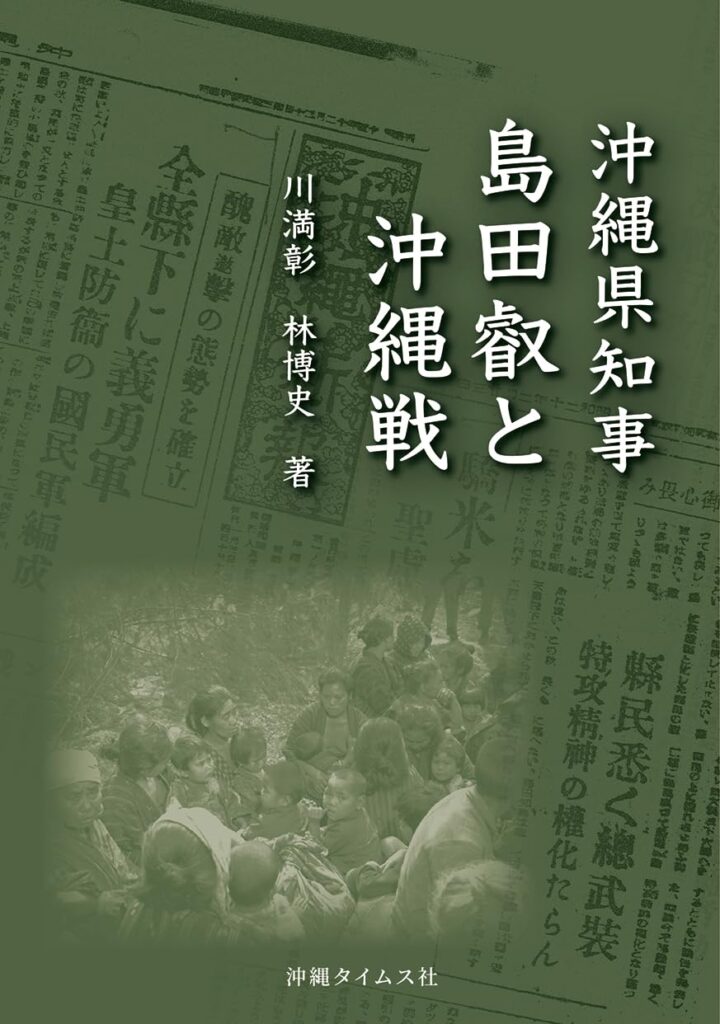





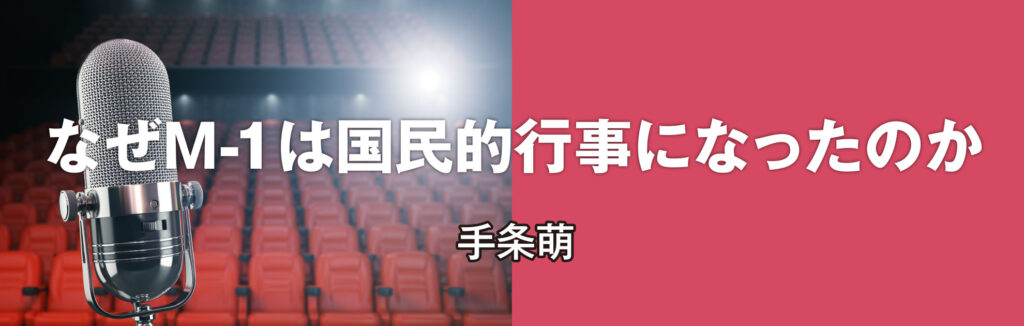







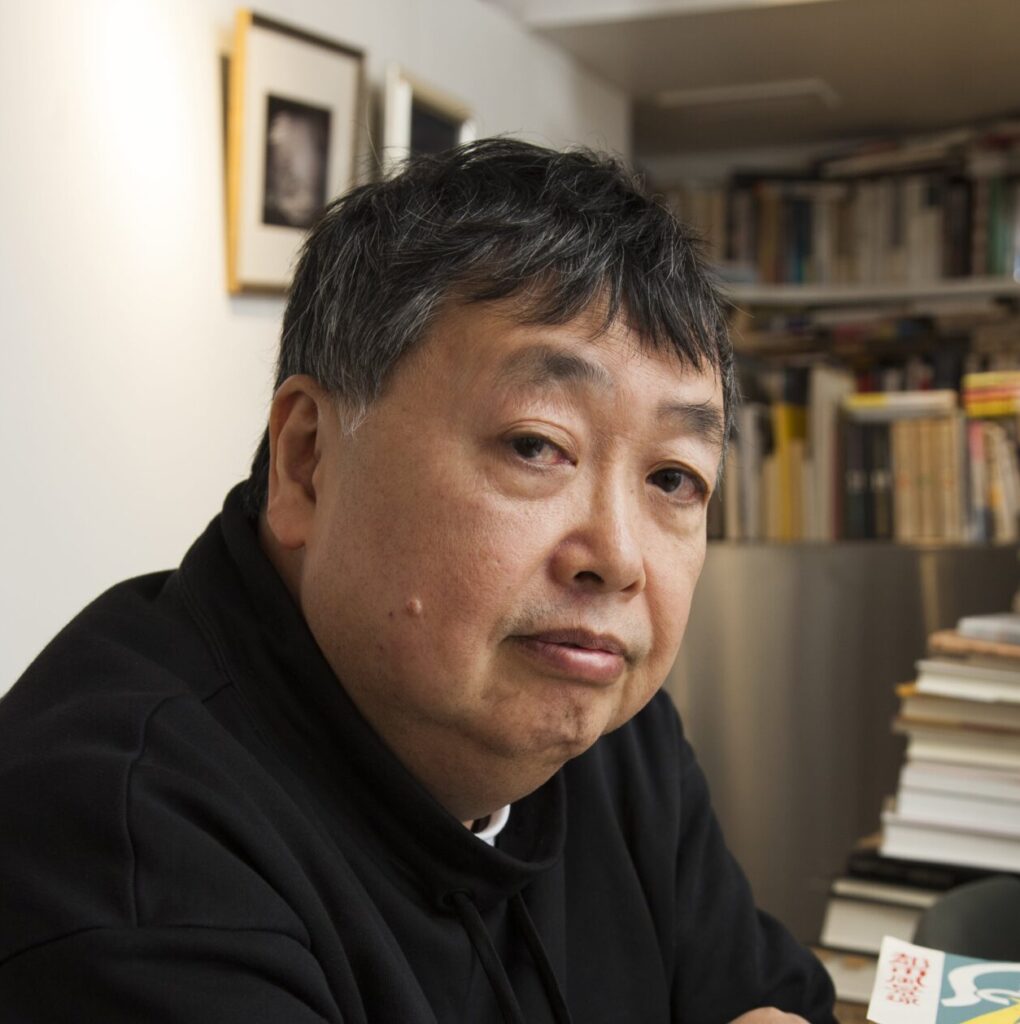
 大塚英志
大塚英志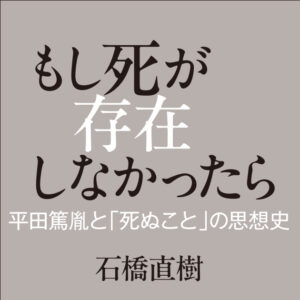
 石橋直樹
石橋直樹