「子どもを持たない」という宣言
アメリカの政治家で、とくに若い女性に影響力のあるアレクサンドリア・オカシオ=コルテスによる2019年のInstagramライブ。彼女が現在の地球の状況を考えミレニアル世代が子どもを持たないことを選択肢に入れるのは「legitimate=正当」である、つまり社会の規範に基づく妥当な判断であるというニュアンスで語ったとき、世界中で安堵した女性が多くいたという(The Guardian、2019年5月12日)。
いまの世界で「子どもを産んでいいのだろうか」という思いを抱えるミレニアル世代、Z世代は数多い。イギリスではまさに「バースストライカー」、産むことをストライキする女性たちが2019年頃から現れた。この流れは世界中に飛び火し、カナダ、アメリカ……次々と自分は「バースストライカー」であると名乗ったり、SNS上で#をつけて共鳴者を呼びかけたり、団体を設立したりしている。彼女たちは、地球が悲鳴をあげている状態のなかで、大人が解決の道筋を示さず放置するなら、私たちは子どもを持たないと宣言した。ある意味、自分の身体を使った強烈な抗議活動である。
オカシオ=コルテスの発言は、この地球の危機的状況が自分の身体や人生設計にまで影響を及ぼすことは当然だと認めてくれた、とバースストライカーたちは感じただろう。産むことを悩む彼女たちにとっては、自分たちの真摯な悩みを正面切って受け止めてくれる人がいると、背中を押されたのだと思う。
実際にアメリカでは4年連続で出生率が下落し、2018年はこの32年で最も低い水準だった(Wall Street Journal、2019年5月19日)。晩婚化や経済的な問題などさまざまな理由があるが、気候変動がその一因といわれている。
また、ニュースサイトのビジネスインサイダーが実施した調査では、「子どもを持つにあたって気候変動が子どもに及ぼす影響を考慮に入れるべき」という考え方について、「大いに同意」「同意」「やや同意」と回答したアメリカ人が全体の3割近くにのぼった。ミレニアル世代の回答者に絞るとその割合はさらに高く、18~29歳の38%近く、30~44歳では24%が同意した。
気候変動が理由による出生への意識低下の流れは、おそらく2019年9月にグレタ・トゥーンベリさんがノーベル平和賞の候補となった時期と重なっている。グレタさんは、その一年ほど前から気候変動の危機的状況を訴え、この現状を解決しようとしない国家、政治家、企業、つまり大人たちを痛烈に批判した。グレタさんが訴えた気候変動デモ「フライデー・フォー・フューチャー」は、185カ国400万人に広がり、たとえばドイツ・ハンブルグでは10万人もの若者を動員し、街を埋め尽くした(NHK BSスペシャル「経済思想家・斎藤幸平 脱成長への葛藤」より)。こうした流れのなかでバースストライカーたちは、より主張を先鋭化させ、気候変動対策に手をつけない政治家や企業家の喉元に、自分の身体、つまり子どもを産まないという選択のナイフを突きつけようとしたのだ。彼女たちは留保を付けるのも忘れない。私たちがそうするということであって、すでに子どもを持っている人、持とうとしている人、各人の自由は侵さない。産まない選択をしろと、皆に訴えているわけではない、というのだ。
国家に利用されてきた「母性」
日本をはじめ全世界で少子化は進み、経済格差や社会の不安定化など各国によって事情は異なるが、女性たちがシステムに利用されることから意志的に降りる選択をしたという見方もできる。イギリス在住の作家であるブレイディみかこさんは、それを「女たちのテロ」と呼んでいた。子どもを産むことは、歴史的に長らく国家に利用されてきた。国家は社会要員を必要とし、戦争が始まれば兵力がいる。子を生み、家庭内でケアを担い、社会要員を生み出してくれる女性は、「女性には本来『母性』があるでしょう?」という呪いの言葉とともに、資本主義、家父長制に利用されてきた。「女性は子を産む機械」「高齢女性は子を産まない(だから社会の役に立たない)」など、政治家の女性の生殖をめぐる乱暴な発言はあとをたたないが、その歴史は長い。
イタリアの思想家、シルヴィア・フェデリーチは『キャリバンと魔女 資本主義に抗する女性の身体』(小田原琳・後藤あゆみ[訳]、以文社、2017年)で、その流れは中世からはじまっており、魔女裁判とは、女性にしかけられた戦争だったと定義した。資本主義の成立過程で魔女が殺されたが、魔女たちは薬草の知識などを駆使して自ら出産や堕胎をコントロールし、女性自身の手で女性の身体の選択を担う人々だった。それが、封建制が解かれ市民が都市に流れて資本主義の基盤ができあがる過程で魔女は殲滅され、その代わり国家が産む/産まないを含む女性の身体を管理することとなった。そうして家庭内でケアを行う主婦が生まれたというのだ。
魔女殺しと主婦の成立、つまり女性の身体の管理は、資本主義の成立過程において歩みを共にしている。戦争が始まれば国家動員として男性の兵力が必要で、そうした国家的な危機にこそ女性の「母性」はもてはやされ、母性が備わっているから女性は自然に子どもを産んで育てるべきだと流布される。現在日本の一部の政治家が「母」を称揚するような発言を繰り返すということは、国家が戦争への準備に無意識的に入っている、と見ることもできる。
先進国で世界的に少子化の動きが加速しているのは、そうした国家的な管理システムから女性たちが降り始めた、ということなのかもしれない。もうシステムに自分の身体を利用されたくない、他の誰かに自分の身体の選択肢を渡したくない。70年代に起こったウーマン・リブの主訴であった「女性の身体を女性自身の手に」という中絶擁護の活動と、少子化の動きは無意識的につながっているだろう。
また、妊娠出産という問題の前に、アセクシュアルやアロマンティックなど、恋愛や性交渉を拒絶する流れもある。男女共に自分の身体的な欲求を、他人の価値観に明け渡したくない、「普通」や社会規範から自由でいたいという想いがその根底にはある。生々しい身体接触のない文化があらゆるところで広がってきたことも影響しているかもしれない。
いずれにせよ、女性が自分の身体を使って、「今の世界を変える気がないなら私は子どもを産まない」、つまり国家に貢献することも社会のために市民の母数を増やす協力をすることも拒否する、と宣言したことに、私自身は「なんという抗議活動が出現したのだ」と、驚嘆した。
バースストライカーになった理由
一人のバースストライカーの発言を見てみよう(TRT “BIRTH STRIKE: Can Going Childless help the Planet?”)。両親が環境活動家である20歳のイギリス人女性は、将来にわたって自分は子どもを持たないと決めているという。それは個人の選択というよりは、社会を動かす人々が一向に気候変動問題の解決に向かっての道筋を示さないので、そのことへのプロテストで「産まない」と宣言している。しかし子どもは好きだし、親戚の子どもを見ると文句なく可愛いと思える。決して子どもが嫌いなわけではない。それと大切なことは、いまいる子どもを否定するつもりはなく、子どもを産もうとする女性たちの意志は全面的に支持すると話す。
彼女は「一人っ子推進」団体の代表と討論を促されていた。世界には、世界規模の人口バランスを実現するために、一人っ子を推進しようとする団体がある。現在世界人口は82億人だが、地球の規模を考えると本来は20~30億が世界が持続可能になる魔法の数字らしい。この数値に到達するためには、もし今後すべての人が一人っ子を生んだとしても100年くらいかかるが、それでも一人っ子を積極的に推奨しよう、とその団体トップの中年男性は主張していた。
バースストライカーの20歳の彼女は「私は人に指図はしない。自分は生まないと決めたけど、誰か他人に、一人っ子にしておいた方がいいとか、産むななどと指図はしない。それは大きな違いだ」と一人っ子団体の代表に反論していた。それに自分がバースストライカーになるのは「人口問題ではない」と明言した。
「人間一人で、生涯に60トンの二酸化炭素を排出すると言われます。一人産むと、世界の子の質に影響すると、世界人口をコントロールしようとする人たちは言うが、本当だろうか?と思う。そもそも、そんなふうに世界の人々に平等に財を分配できていないだろう、と。トップ富裕層22人で、アフリカの全女性の収入と同じだと言われています。子を一人産むと、世界の子の質に影響を及ぼすと言うのなら、それは人口問題ではなく世界のバランスの問題、つまり資源を分配できているのかという問題ではないでしょうか」
一人っ子推進団体の主張があまりにも稚拙で横暴なので、真っ当な議論とは言えないが、20歳のイギリス人の彼女は、至極冷静に世界を見渡し反論していた。子どもが悪なのではなく、問題はそんな社会を作った側、つまり私たち側にあるのだ。世界の富の分配を誰が支配しているのか、それを決定しているのは誰かという問題なのだ、と彼女は主張していた。
炭鉱のカナリアの役目
実際、人口削減は効果のない戦略であることが証明されている。米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA)に掲載された2017年の研究では、出生率と死亡率を調整することで、地球規模の人口変動に関する様々なシナリオが検討されている。報告書は、世界中で一人っ子政策を実施したとしても、2100年までに世界人口が大幅に減少することはないだろうと結論付け、むしろ「持続可能性に向けたより迅速な成果は、天然資源の消費増加を反転させる政策と技術から生まれるだろう」と提言している。
子どもを1人減らすことが、個人が二酸化炭素排出量を削減する最も効果的な方法であるという議論があるが、二酸化炭素排出による地球温暖化の危機は個人の選択によって緩和できる段階をはるかに超えている。すでに人口問題も二酸化炭素排出量の削減も、個人でなんとかできるものではなく、より大規模なグローバル企業や国家単位で解決にむけて努力しなければ達成しないということだ。バースストライカーたちがすごいのは、それをわかって、むしろ危機的状況を知って欲しいと、炭鉱のカナリアの役目を自ら背負っていることなのだ。
イギリスでバースストライキ団体を設立した代表者の言葉を引いておこう。この団体は、来たるべき「気候崩壊と文明崩壊」に備えて子どもを持たないと決めた人のためのボランティア団体だ。「環境危機の深刻さを理由に子どもを産まないと決めた」人の「個人的」な決断を、戦略的に「政治的」なものにするために設立したという。わずか2週間で140人が集まり、その全員がイギリス人女性だったという。設立当初集まった人からは、誰にも話せないと思っていた。声をあげてくれてありがとう、という声が上がったという。
すでに何人かのバースストライカーたちの言葉で見てきたとおり、バースストライカーは反出生主義とは異なり、他人に子どもを持つことを思いとどまらせたり、すでに子どもを持つ人々を非難したりするのではなく、この地球の危機の緊急性を伝えることが目的だと話す。
「バースストライクを通して問題を解決しようとしているのではなく、私たちは情報を世に広めようとしている」、これが彼女たちの真意なのだ。
世界の不正義へのヴィヴィッドな抗議
ほかの理由でバースストライカーになった人もいる。
カナダのドキュメンタリー映画「The Climate Baby Dilemma」Victoria Lean監督(邦題「私は子どもを持つべきか 気候変動世代のためらい」2024年1月19日、NHKにて放送)に出演していたバースストライカーであるカナダ人女性は、ハッシュタグで理解者を募り団体を設立したが、一方で批判も受けて炎上し、SNSを閉鎖していた。彼女はのちにこう述べていた。
「カナダに住む白人である自分が母親になれば、その権威的立場を使用することになる。カナダには迫害されてきたファーストネーションズ(カナディアンインディアン)が多数いる。彼女たちはカナダ政府によって子を産むことを禁じられ、限られた収容所での暮らしを強いられた。彼女たちがいま自分たちの祖先を残そうと積極的に子どもを産もうとするのは当然のことだ。だからこそ迫害の歴史をもつ国の自分、それも白人である自分が、母親になり子を増やすことは、国家的差別体系の再生産というか、特権乱用に感じてしまう。子どもを持ちたくないという気持ちの背景にはそんな思いもある」
若さゆえに社会正義が先鋭化し、彼女自身の人生の選択にまで影響を及ぼしてしまっている。しかし彼女を行き過ぎだと、揶揄することはできない。
バースストライカーの彼女たちはヴィヴィッドに世界の不正義に抗議していた。自分の身体の選択を、政治的なプロテストに使っているのだ。「個人的なことはすべて政治的である(The personal is political)」は、第二波フェミニズムを牽引した有名な標語だが、時代を経て彼女たちは、より先鋭化した形で「個人」を「政治」にまで高め、社会に抗っていた。
永遠に成長を続けることが前提の今の経済システムでは、人口は増やしていかなければいけない。経済成長を基本に置いた社会では、女性はどこかで産むことをシステム側から要請され続ける。仕事との両立? 家事の時短?……、出産と女性の自立は自己責任となり、よけいに女性を縛りあげている。すべては、人間がこの経済システムの駒となって、生きる意味を自分の力で主体的に見出しづらい社会であることが原因だろう。
世界の富の分配が平等ではないと訴えたバースストライカーのイギリス人の20歳の女性は、世界がもしまあまあ完璧な状態なら、産むと決断するのでは? いつか産まなかったことを後悔するのでは? と問われ、こう答えた。
「後悔するかもしれないしわからない。ただ、子を産んで後悔することの方がもっと怖い。望んでいるものを子に与えられないかもしれない。産んだあと後悔するくらいなら、生まない後悔の方がいい」
望んでいるものとは、安全な地球環境だろう。どこに住んでいても地球の環境は年々その安全がおびやかされている。彼女は人間がゆるやかに絶滅するようなイメージさえ抱いているのかもしれない。
「子を持つ意味」の変化
では一方でそんな世界でも子を持つことの輝きとは何か。かつて少女時代に国連でスピーチを行って世界にその存在を知らしめた環境活動家セヴァン・カリス=スズキさんは、子どもを持つことで、むしろ未来への責任が増したと話す(“The Climate Baby Dilemma ” A film by Victoria Lean)。
子どもの存在は未来そのもので、将来の地球の姿をより具体的に想像させ、環境活動への切迫感が増したというのだ。
その意味では、自分自身を何かの当事者であり、何かのマイノリティなのだと思う人にとっては、子どもをもつ意味が少し変化するかもしれない。
「子を産んで後悔することの方がもっと怖い。望んでいるものを子に与えられないかもしれない。産んだあと後悔するくらいなら、生まない後悔の方がいい」と20歳の女性は語っていたが、それは徹頭徹尾子どもという存在を、自分の想像できる範囲のなかに置き、あり得るべき可能性を制限したなかで語っているにすぎない。子どもとは一人の他者であり、その子の幸福や価値観を、親でさえ予測可能なものとして計ってはいけない。その子が望むものがどんなものなのかは、はかりしれない。地球の未来を本当に変えようとする子が生まれるかもしれないし、ただ、母親の顔を見続けたい、そう思うような子が生まれる可能性だってあり得るのだ。
自分なりの「子を持つ意味」を構築する行為、システムに利用されない私なりの「母」の意味を掴み直すことは、この現代においてむしろ非常にアナーキーな営みなのでは、ともいえる。
世界の問題はさまざまにある、優先順位は人それぞれだ。しかしどの問題もだからといって待ってはくれない。数年放置すれば、もっと悪い事態になる。つまりどの時代にも多くの心配があり、その心配の総量で言えば、世界はとっくに崩壊しているだろう。
希望とは、未来は予測不可能だということそのものなのかもしれない。それは子どもの存在自身とも言い換えられるだろう。
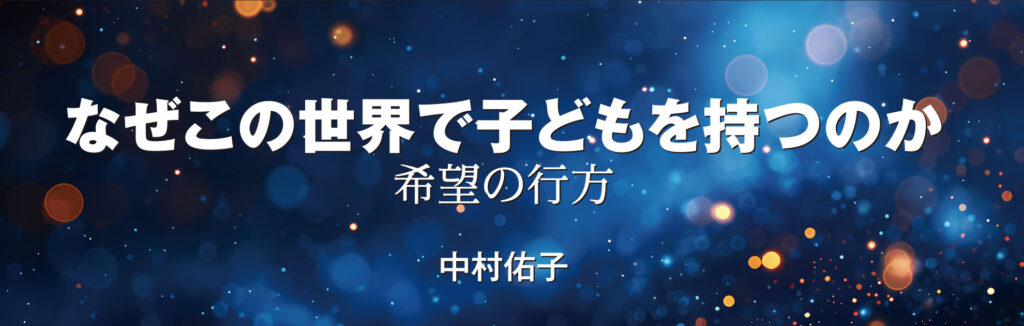
世界各地で起きる自然災害、忍び寄る戦争の気配やテロの恐怖、どんどん拡がる経済格差、あちこちに散らばる差別と偏見……。明るい未来を描きにくいこの世界では、子どもを持つ選択をしなかった方も、子どもを持つ選択をした方も、それぞれに逡巡や躊躇、ためらいがあるだろう。様々な選択をした方々のインタビューを交え、世界の動向や考え方を紹介する。
プロフィール
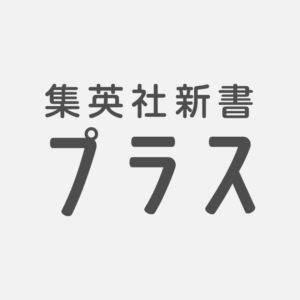
1977年東京都生まれ。作家、映像作家。立教大学現代心理学部映像身体学科兼任講師。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』が、著書に『マザリング 性別を超えて<他者>をケアする』『わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅』がある。


 中村佑子
中村佑子










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


