『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられた 現代の災い「インフォデミック」を考える』(集英社新書、2023年)著者の批評家・片岡大右さんによる特別寄稿。
本書は、東京オリンピック・パラリンピック開会式の作曲担当として発表された小山田圭吾(コーネリアス)の炎上騒動を考察した一冊だったが、すでに現在小山田は国内外で幅広く精力的に活動をおこなっている。
今回、その小山田をはじめ坂本龍一やブライアン・イーノが作品を発表した「AMBIENT KYOTO」、そして今春のアンゼルム・キーファー展「ソラリス」といった、すべて「京都」を舞台に開催された注目すべきアート展を批評した。
「モダン都市」としての京都
本稿執筆の現在、新宿・歌舞伎町ではフランス/スイスの映画作家ジャン=リュック・ゴダールの最後の長編作『イメージの本』に基づくインスタレーション展が開催されており(8月31日まで)、筆者は内覧会を訪れて簡単な紹介記事を発表した(※1)。歌舞伎町の猥雑きわまりない通りを抜け、高度成長期に建てられた城館風の赤い雑居ビルに入ると、4階建ての全フロアを用いてゴダール作品の映像・音響素材を再構成した展示が繰り広げられているというのは、実に独特の体験だった。
(※1:片岡大右「断片の織りなす森を歩く──新宿・王城ビルのゴダール展」、「webふらんす」2025年7月10日。)
伝え聞いたところでは、このゴダール展を日本で開くに際して、当初は京都のどこかの寺を会場とする案もあったが、却下されたのだという。京都の寺と歌舞伎町。対照的な、けれどもそれぞれのかたちで日本を代表するものと言えるかもしれない二つの空間のうち、後者が選ばれたわけだ。
たしかに、外国の芸術家が日本で何かをしようというときに、首都・東京ではなく古都・京都に舞台を求めるというのは、今日では決して珍しくない、ありふれてさえいる選択だろう。そうした提案がなされたことも、それがあえて退けられたことも、筆者としてはよく理解できる。
しかし同時に思ったのは、京都という選択は決して寺やその他の「伝統的」な空間を選ぶことに限定されるものではないだろう、ということだ。もちろん寺や神社や庭園の文化的価値を否定しようというのではない。けれどもその一方で、明治以来の京都はまた、深い伝統に支えられた土地に新たな文化をどのように導入していくかという、近現代日本の本質的な問いが切実に探究された都市でもある。
じっさい、今日の京都は歴史的古都の面目を保つと同時に、近現代建築の宝庫としての一面を持つ。2021年9月25日-12月26日に京都市京セラ美術館で開催された「モダン建築の京都」展は、この後者の側面に注目し、明治・大正・昭和の「モダン建築」を通して京都の魅力を捉えなおす意義深い展覧会だった。
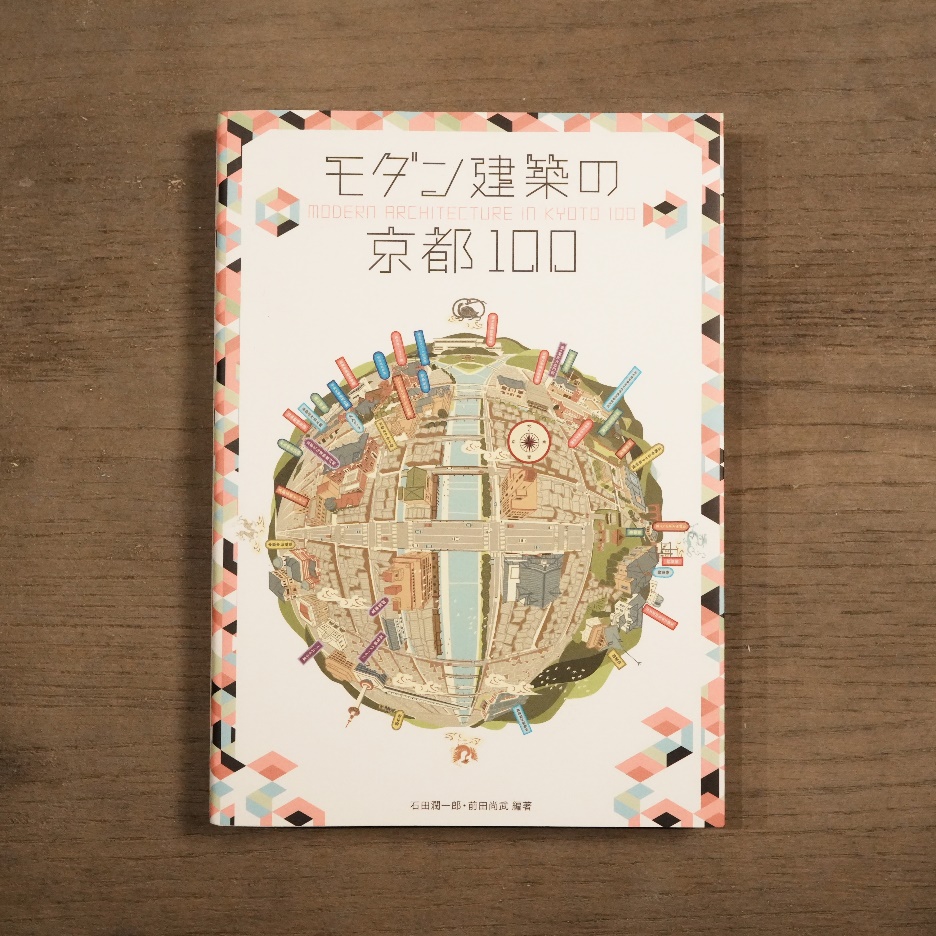
そしてこの展覧会の翌年、2022年6月3日-9月3日に、英国の著名なミュージシャンであり、ヴィジュアル・アーティストとしても知られるブライアン・イーノの大規模な個展が、「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」と題して開催された。会場に選ばれたのは、京都中央信用金庫 旧厚生センター。京都駅にほど近いモダン建築だ。このイーノ展の成功を受け、翌2023年には「AMBIENT KYOTO 2023」が開催、こちらでは複数のアーティストが参加し、新たな会場も追加されたけれど、同金庫のこの旧厚生センターも引き続き用いられた。
京都とオリエンタリズム
ブライアン・イーノの名声は何より、アンビエント・ミュージックのパイオニアとしての業績に結び付いている。そのイーノを特集することで始まり翌年にも引き継がれた「AMBIENT KYOTO」は、京都を舞台とすることにより、「アンビエント」というコンセプトと日本文化、とりわけ伝統的なそれとの類縁性を示唆する企画だったと言えるだろう。音楽誌『ele-king』が2023年のイベントに合わせて『アンビエント・ジャパン』と題する別冊を刊行したのは、こうした企画趣旨に共鳴してのことだった。
その『アンビエント・ジャパン』では、デイヴィッド・トゥープが取材されている。ミュージシャンであり音楽批評家でもあるトゥープの著書『音の海』(原著1995年、日本語版は佐々木直子訳、水声社、2008年)は、アンビエント・ミュージックを含む現代の音楽的感性の発展を、1889年のパリ万国博覧会におけるドビュッシーとジャワのガムラン音楽との出会いという出来事以来の大きな流れとして描き出した著作だ。
アンビエント・ミュージックに至る流れと東洋の結びつきを強調するなかで、同書におけるトゥープは日本の文化伝統を、とりわけ京都という場所に引き寄せて幾度か取り上げている。トゥープ自身の京都旅行は、禅寺や石庭、また二条城の二の丸御殿といった伝統的な名所旧跡をめぐるものとして回想されているし、そして何より、ブライアン・イーノが奈良県吉野郡にある天河神社に招かれて行った1989年の伝説的な奉納演奏を取り上げるくだりでは、「京都に近い天河神社」と記されている。日本的伝統の本拠地を京都に求めたいという西洋の眼差しの強力さがうかがえると言えるだろう。
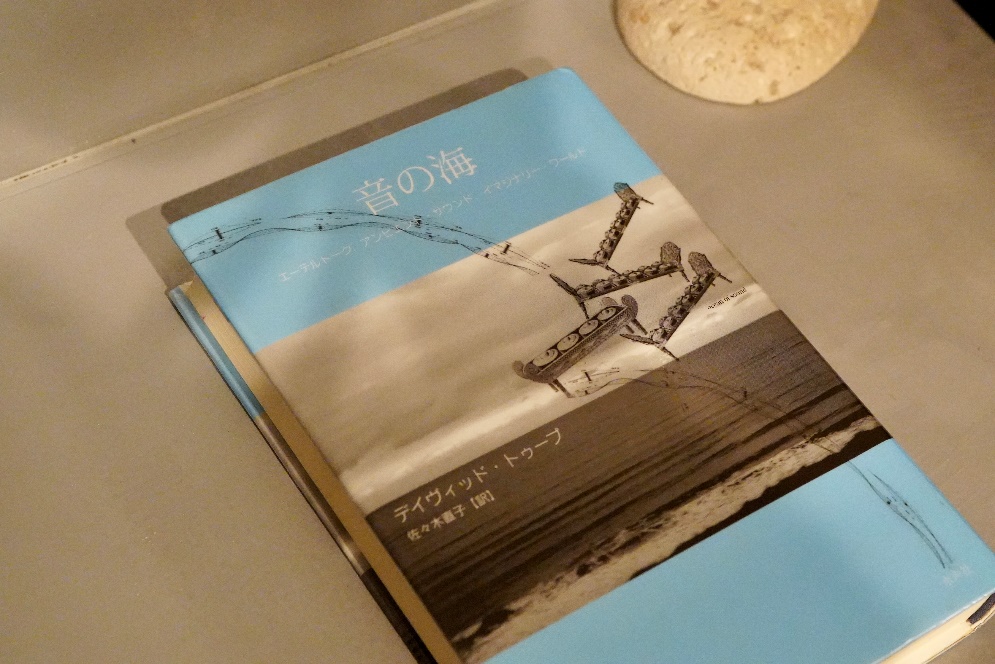
こうした眼差しを「オリエンタリズム」に属するものとみなすのは一定の正当性があるにしても、それをどう評価すべきかは難しい問題だ。トゥープ自身は、親交のあった坂本龍一――2018年の共同ライブパフォーマンスは、『Garden Of Shadows And Light』(2021年)として音源化されている――の追悼文のなかで、この日本の友人を「オリエンタリズムにもかかわらず、そしてオリエンタリズムゆえに成功を収めた」音楽家であると評しつつ、そんな坂本が私的な談話で漏らした不満を思い起こしている。「東洋のものが好まれているけれど、それはやはりレイシズムだと思う。違っているからこそ好まれているわけだから」――坂本はこのように語ったのだという(※2)。
(※2:“Life, Life: David Toop remembers Ryuichi Sakamoto,” The Wire, April 2023.)
しかし坂本龍一は、こうした海外とりわけ西洋からの眼差しの画一性に閉口した面はあったにしても、彼自身、東京藝大の学生時代から西洋音楽の行き詰まりを意識して民族音楽に目を向けていたのだし、晩年にはいっそう東洋の諸伝統への関心を深めていったことは、没後に書籍化された『坂本図書』(空里香監修、バリューブックス・パブリッシング、2023年)を見るとよくわかる。
2005年には東山・法然院、2007年には大徳寺(養徳院)と、「庭園シリーズ」と銘打って京都の寺でのライブを試みるなど、21世紀の坂本は京都との関りを深め、最晩年には京都に自邸を構える構想もあった。こうした選択が、京都が体現しているように見える「違い」に惹かれてのことだったのはたしかであるとしても、それをオリエンタリズムに、さらにはレイシズムに帰するものとして片づけてしまうなら極論がすぎるというものだろう。
二条城のアンゼルム・キーファーと『陰翳礼讃』
じっさい、京都の寺や史跡がもつ力を否定しても始まらない。今年で言うなら、現代美術家アンゼルム・キーファーの大規模な個展「ソラリス」が元離宮二条城を舞台に開催され、本質的にヨーロッパ的な芸術家とも見えるこのドイツの巨匠の作品と日本の史跡との相性の良さが、訪れる人びとに強い印象を与えたばかりだ。

《オクタビオ・パスのために》
キーファーは、自身の絵画作品に金箔を用いるようになってから、ギャラリストのファーガス・マカフリーを通して狩野派の屏風を知り、日本への関心を新たにしたのだという。「ソラリス」展開催に際して寄せられたこの美術家のコメントには、「狩野派の屏風の緑青を帯びた輝かしい金」と並べて、「古き日本の室内装飾をめぐる谷崎の忘れがたい回想」への賛辞が記されている(※3)。ここで示唆されているのはもちろん、谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃』だ。同書は伝統的な日本美を論じた書として世界的に読まれている。
(※3:Lisbeth Thalberg, “Anselm Kiefer at Nijo Castle, Kyoto, 2025,” Martin Cid Magazine, March 26, 2024.)
ただし、かつて加藤周一が指摘したように(『日本文学史序説』)、「暗がりの中に美を求める傾向が、東洋人にのみ強い」という谷崎の断定の行き過ぎを認めるには、ヨーロッパ中世の大聖堂の暗がりに輝くステンドグラスを思い出すだけで足りるだろう。したがって、谷崎のこの随筆の主張をすべてそのまま受け取ることは難しい。
しかしそれは逆に言えば、『陰翳礼讃』は単に日本固有の美を論じた書としてのみならず、同時代のモダニズムの美学との類縁性を含め、日本の外における美的感受性との共鳴に開かれた書として読みなおすことができる、ということでもある。西村将洋『谷崎潤一郎の世界史――『陰翳礼讃』と20世紀文化交流』(勉誠出版、2023年)は、この点を探究して、同書のもつ「横断する力」を強調している。
キーファーによる『陰翳礼讃』への言及、さらにまた二条城という会場の選択は、ヨーロッパの芸術家の異なる文化伝統との出会いの産物であるのと少なくとも同じ程度に、彼我の歴史的・空間的隔たりを超え、何かが横断的に共有されたことのたしかな証しであるのかもしれない。

中央の《ソラリス-ハリー》は坂本龍一エステイト蔵
プロフィール

片岡大右(かたおか・だいすけ)
1974年生まれ。批評家。専門は社会思想史・フランス文学。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。単著に『隠遁者,野生人,蛮人――反文明的形象の系譜と近代』(知泉書館)、『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか 現代の災い「インフォデミック」を考える』(集英社新書)、『批評と生きること 「十番目のミューズ」の未来』(晶文社)。共著に『共和国か宗教か、それとも』(白水社)、『古井由吉 文学の奇蹟』(河出書房新社)、『加藤周一を21世紀に引き継ぐために』(水声社)、訳書にデヴィッド・グレーバー『民主主義の非西洋起源について』(以文社)、フランシス・デュピュイ=デリ、トマ・デリ『アナーキーのこと』(左右社)がある。


 片岡大右
片岡大右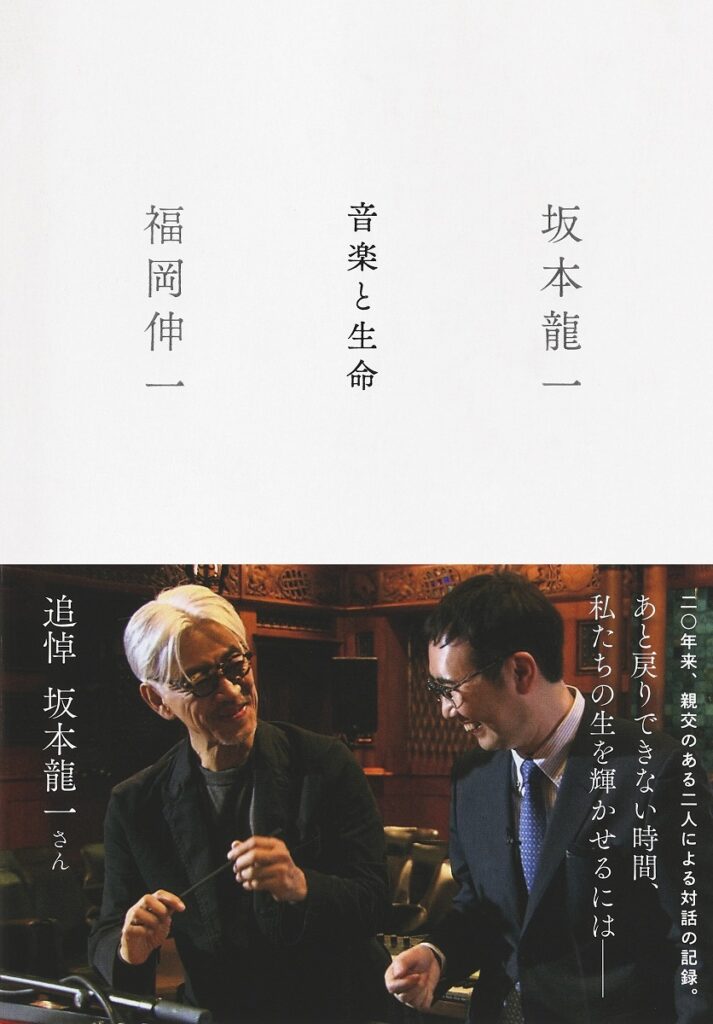
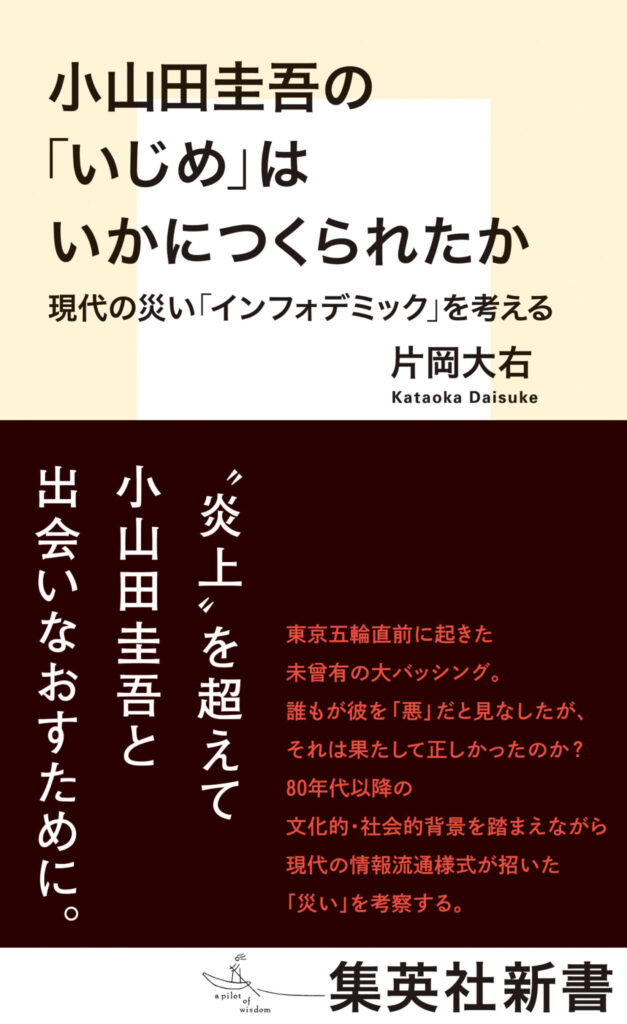










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


