自分の平熱が38度になってしまったら……
気候変動の影響は、もう説明するまでもないだろう。夏はフライパンの上にいるようだし、冬は冬でどか雪が降る。豪雨被害は、あとからあとから止まることを知らない。40度を超える気温では植物もうまく育たず、食糧危機のリスクもすぐそこにあるといわれている。異常さは日々の生活に振りかかり、もうこれまで通りの生活は成り立たないと多くの人が感じている。
ある気候変動の活動家の女性は、今の地球の現状をこう説明した。
「地球もひとつの生命体ですよね、つまり有機体であり、私たち人間の体のようなもの。体には平熱がありますよね。例えば私の平熱は36.5度ぐらい。その平熱が1度上昇して37.5度になったのを想像してみてください」
いま地球の平均気温は産業革命前と比べ、1.5度上昇している。地球の体調とはつまり、常に風邪をひいていて熱がある状態だ。
「常に37.5度ある状態って、結構しんどいじゃないですか。今、1.5度上昇しているということは地球の平熱が38度なんですよ。微熱をゆうに通り越していて。で、豪雨による大洪水とか、夏に雪が降るような、そんなおかしなことが世界各地で起きていて、その深刻さも頻度も年々加速していっている。それが今の状態です」
この説明は、気候変動のプロフェッショナルである彼女がNGO活動のなかで、一般の人に活動に参加してもらうために、気候変動の危機感をどう伝えるのか思案して繰り出した語り方だという。地球はずっと熱があるような状態だ。36度台だった平熱が、38度台が普通ということになっているんだ。この感覚的によくわかる説明に、私はすっかり魅了されてしまった。
自分の平熱が38度になってしまったら、それは本当に困る。ときおり風邪をひいて、そのくらいの熱になるだけで、節々は痛いし、よく歩けないし、食欲も落ちる。普段通りの物の考え方もできない。それが毎日になるのだ。地球はいまそんな症状を抱えているし、原因ははっきりと人的理由にあること、二酸化炭素を始めとする人間の排出する温室効果ガスのせいであることは科学的に明らかになった。
「ホットハウス・アース・シナリオ」
人間が産業革命を起こして以降の時代である「人新世」が、地球の根本を変えている。このまま平均気温が上昇すれば、近い未来に、悪影響は連鎖的に暴走するスイッチが入ってしまうと危惧されている。一度その点を通り過ぎれば、もうどんなに努力をしても、快適に暮らせる地球に後戻りができなくなる。ホットアース=温室の地球になってしまうという「ホットハウス・アース・シナリオ」という予測もその一例だ。
「今の状態は、私たちの体でいうと、頑張って汗を出すとか、ぼろぼろの中でも今ある体温調整機能を使って体温を何とか本来の平熱まで下げようとしている状態。でもこのまましんどい状態が続いて、さらに体温が上がり続ければ、例えばもう汗が出なくなる、みたいに、体の体温調節機能そのものが壊れてしまう時が来る。そうして、体の熱を逃せなくなった状態に地球がなってしまったら起こると言われているのが、ドミノエフェクトで崩壊に向かうとか、ホットハウス・アース・シナリオとか。それが起こってしまった後には、どんなに頑張っても、もともとの元気な自分に戻ることはまずできない。何とか生命をしつらえても、今までみたいに壮快に生きることはできなくて、すごくリミテーションが多い中で存続していくしかない。でも、今ならまだちゃんと汗も出るし、いろんなファンクションが機能しているから、ちょっとずつ平熱を37.5度、36.5度と、すごい時間をかけて戻していけば、またいつものあなたに戻れるかもしれない。もしくは36度台は無理でも、37度が平熱ならまだ何とか、いつもだるいけど、人生送れそうじゃないですか。今なら戻れる、まだチャンスがある、いつも、その危機感と希望がどうしたら伝わるかな、と考えながら説明しています」
平熱が上がるということは、ただ熱の問題だけではない。自律的に作動している地球のエコシステムが根本的に壊れると表現しても過言ではない状態だという。
気候変動の活動家にとっては、企業や国家に働きかけることが急務であると同時に、この危機感を一般の人ともシェアしなければならない。しかし世界中で緑の党など、環境保護を訴える政党の支持には陰りが出ており、経済格差が広がる中で、皆自分の目の前の生活に精一杯で、気候変動の解決にむけて情熱を傾ける余力はないように見える。それでも地球は待ってくれない。切迫感はいや増している。
自分の人生に責任を持つこと
今回取材をさせていただいた釧路実日子さんは、そんな切実な状況のなかで、外国に本部を置くNGO団体の日本支部で、 地域の人たちと一緒に気候変動を考えるプロジェクトを企画運営している。
気候変動活動家のなかには、今の地球の状態を憂い、子どもを持つことを躊躇する、あるいは持たないと決めている人もいる。前回取材した宮田美里さんがそうだった。そんななか、釧路さんは逆で、むしろ子どもを持とうと決め、第一子である3歳の女の子を育てながら、取材した日は第二子を妊娠中だった。
周りの気候変動活動家のなかには産まない選択をする人もいるであろう。釧路さんはなぜ産むことに踏み切ったのだろう。
「いくつか柱があるなと思っていて、ひとつはまず、気候アクティビストの人が産まない選択をするときは、近代化された生活を送るグローバルノース(*グローバスサウスに比して使われる言葉で、欧米や先進工業国を指す)の人が一生に排出する二酸化炭素の量。それは膨大。そこに人が1人増えることは、気候危機を加速してしまう、とも言える。もうひとつは、いまの激動の社会に産んで子どもを幸せにできるかという不安と、それが分からないのに産むのは無責任じゃないかという想い。活動家たちは、いまの気候危機がどれだけ緊急で、どれだけスケール感的にやばいか、またそれが自然界だけでなく、政治や世界情勢をどれだけ不安定かさせるかを一般の人よりもよくわかっているからこそ、こういった考えに辿り着くのだと思う」
と、まずは「産まない」選択をしている彼女たちを慮った。釧路さんはブログでも、子どもを産まない選択した人は「理にかなっていると言えますし、私はそう決断する人に心からリスペクトを感じています」と書いていた。
その上で「責任」――自分の人生の「責任」、親になる「責任」、気候変動を解決しようとする「責任」――について、別の角度から言葉にしてくれた。
「自分の人生に責任を持つこと、自分の人生の『幸せ』に責任を持つことは、自分にとっての意味だけではないと思っているんです。なぜかというと、私がしようとしている活動は、多くの人がその輪に入ってこそ成り立つものです。市民運動は、ある意味数が勝負なところがあります。めちゃくちゃ多くの人でなくても良いけれど、ある一定数の人が参加してくれてこそ、成功できる。よく、3.5%って言われますよね。だからこそ、一般の多くの人に、今のこの状況を変えようという気持ちになってもらいたい。そのときに中にいる人が幸せに生きてジョイフルでないと、参加したいと思わないんじゃないかな、と。気候変動のことに関わることであなたの人生がすごくシリアスになり、やりたいことをやる時間もなくなります、という雰囲気が伝わってきたら、あんまり参加したくないですよね? 一人一人の人間はすごい想像力と知性があるんだということを信じているから、社会問題に現時点ですごく興味のある人じゃなくても、ぜひ一緒に活動したいと思ってます。今の生き方を大きく変えて筋金入りの環境アクティビストになってくださいというよりは、自分の人生で新しい考えや人に出会うチャンスがあって、今無理なく使える時間の中で少しずつ参加してほしい、そんな感じで誘いたいって思っています。そういう小さなお誘いをするときに、中の人が幸せじゃないとうまくいかないと思うんです」
釧路さんにとっては、子どもを産むことは幸せと直結しており、自分が幸せでいなければ運動を引っ張っていけないと感じた、ということだと思う。活動の真ん中にいる人こそ、自分が幸せでいることを追い求めることと「活動」が不可分につながっている、そういうヴィジョンを示さなければいけない。これもひとつの「責任」のとり方なのだ、とお話を聞いていて感じた。
生命自体に価値がある
とはいえ釧路さんにとっても、子どもを産むことが「幸せ」だと感じるまでには、長い道のりがあった。釧路さんは、国際系の高校を卒業してから、アメリカに渡り、大学で環境学、後に、演劇学を学んでいた。アメリカでさかんだった環境活動にも興味があったが、卒業後は誘われるままにアメリカの前衛演劇の俳優として舞台に立っていた。くっきりした二重まぶたにキュートな口元、外見もキャラクターも日本人離れした印象のチャーミングな方だ。頭の回転が早いのだろう、早口でご自分の考えを述べるが、言葉選びは常に慎重で繊細、人を惹きつける方だ。舞台に立ったら、さぞや魅力的だったろうと思う。
アメリカの演劇界にいたとき、周りにはゲイやクイアの友人も多く、ステップファーザー、マザー、兄弟姉妹がいるのは全く珍しくなく、精子バンクの制度を使って家族になる人の姿を間近で見ていた。いろんな男性とお付き合いをしてもうまくいかないことが多く、だんだんと自分は結婚しないだろう、けれども子どもは欲しくなるかもしれない、将来シングルマザーになるかもしれないと思うようになった。そのために、20代のころから3、4年は働かなくても暮らせるよう、準備資金を貯めていたという。
非常に計画的で自立心にあふれているが、実はとてもつらい時期もあった。ただそんななかでも、生まれてこないほうがよかったという、反出生主義的な考えには侵されなかったという。
「10代のころ、人生を終わらせたいなと時々思うくらいつらいダークな時期が長くあったんです。すごく孤独も感じていたし、私の人生は表面的には順調に見える部分もあったと思いますが、自分自身がどんどん壊れていっているような感覚がありました。そういう究極の葛藤の中でも、どこかで、しんどくてもいいんだというか、ハッピーじゃなくても、生きる価値があるというか、生きること自体、生命自体が、価値があるということだけは、自分にとっては確信のようにありました。世の中がこれからもっともっと不安定になっていく中で、今のこの時代を生きていく子どもをどんなふうに育てたいかというところはすごく考えます。大変な世の中になっていくとき、その中で、自分らしく、幸せに生きて行ける人、そして世界の大きな変化の数々が、一部の人でなく、多くの人にとって良い変化になるよう動ける人になったら良いなって思います。そのためには、自分の力で考えていけるようになること、人とつながる力を持っていること、無条件の海のようなリラックスした自信みたいなものがあることが大事だと感じますね。それは、どんな子どももきっともともと持っている力や性質で、私の親としての役目は、それが成長する中で奪われてしまわないようにサポートしていくことだと感じています。大変な世の中になっていくからこそ、子ども時代に、人間とこの世界の素晴らしさをいっぱい味わってほしいな、って思いますね」
「何よりも大きな冒険に見えた」
釧路さんは小学生のころから優等生で、何をやらせてもよくできた。きっと読んでいる皆さんの学校にも学年に1人はいたであろう、優秀で美しく思いやりあふれる学級委員タイプの「あの少女」だ。幼いころから人一倍正義感があり、学校で納得できないことがあった翌日、突然学校に行けなくなったりした。友人たちのいじめや、それにまつわる先生の正義や不正義の恣意的な濫用に耐えられず、深く傷ついた。きっと成長が早かったのだろう。人間関係のさまざまな欺瞞や嘘を、早くから感じていた。それがきっと気候変動をはじめ、環境問題へのヴィヴィッドな感受性につながっているのだろうと思えた。
父親は製薬系の大企業に勤め、転勤が多かった。中学までは全国を転々としたが、常に成績は良く、推薦で国際系の高校に入って留学の道が開けた。
米国の演劇界を一旦出て帰国した釧路さんは、フリーでテレビや映画のプロデューサーの仕事をしはじめる。とくにヨーロッパのクリエイターが日本で撮影したり創作したりするプロジェクトを支えた。やがてボランティアで参加していた気候変動問題に取り組む国際環境NGOから、正式にスタッフに応募してみないかと誘われた。
そのころだった。釧路さんはいまのパートナーと出会った。ブラジル人で、国際的な医療系NGO団体に所属する技術士だった。はじめて誰かとパートナーとなる未来が見え、子どもを持つことを現実的に考え始めたとき、釧路さんのなかで何かが変わった。
「何よりも大きな冒険に見えたんです、親になるということが。しかも、自分の体を通して、おなかの中で子どもが育つということが本当に興味深く思えて、絶対それを体験してみたい、と強く思ったんです」
外国を渡り歩き、人よりずっと人生の「冒険」をしているように見えた釧路さんだが、回り回って、自分の体で起こす「冒険」に身を投じてみたいと思えたのだという。
ではいざ産むとなったときに、気候変動も戦争のリスクも高くなった世界で子どもを持てば、自分が子ども時代に楽しんでいた季節を楽しむ行事を子どもは楽しめないかもしれないし、自分が経験した同じ楽しみを子どもは得られないかもしれない。そんな世界に産んでいいのか、親としてその責任をどう捉えるかという問題が一方である。そのことをぶつけてみた。
「私の場合は、自分の子どものころの幸せの要は全然そこじゃない、という気がしていて。自分にとってもそうじゃなかったから、ほかの人にとっても、自分の子どもにとってもそうじゃないんじゃないかという思いがあったのかもしれないです。すごく愛されていることとか大切にされていることが要なんじゃないかな。子どもは大人になるまでサポートが必要ですよね。生き生きと生命を謳歌して日々を送っていくために、誰かが全力でサポートしてくれている。そこに幸せがあると思うんです。夏にプールに入れるかとか、安全でオーガニックな食べ物が食べられるかとか、それはできればもちろん食べさせたいけど、幸せかどうかは、何かそこじゃないという思いがあります。あと、グローバルノースの日本に住んでいる私からすれば、世界はどんどん大変になっていっている、ということになりますが、もともと気候危機が私たちの身の回りでこんなに話題になる前から、安全な環境にない地域で育っている方たちはいつの時代も多くいたわけで、じゃあ、その人たちはそんな世界に生まれてこないほうがよかったのか、と言ったらそうじゃないと思うんです。そこはすごく引っかかるなと思っていて。世界は今まで常に多くの人にとってかなり過酷な場所で、もう既に大変な世界だったわけですよね。日本にいる私が気候危機をここまで肌で感じられるようになる前から、12歳で売春して家族を養なうのが珍しいことではないような、大変な状況は世界中にありますよね。でもその社会の子どもたちの生命がないほうがよかったかというのは、勝手に決められない。すごく人生が大変でも、幸せや生きがいを、感じられるか、何に自分が生きていることの喜びや価値を感じるかは、同じ状況でも反応が違うと思うんです、人によって」
社会を変えたいと思っている性分
この議論は、第3回の反出生主義の回でも詳しく前述したが、「生まれてこないほうがよかった」という反出生主義を論駁できるとしたら、どんなに相対的に不幸に見えたとしても、その人にとっての絶対的価値は計り知れない、その人の人生を勝手に想像して存在の否定をしてはならない、という議論につながる。だから反出生主義によって子どもの生誕を否定するのは、その子の絶対的価値、その子が育てていくであろう個人的な志向をあらかじめ排除しているので、多くの倫理的反論が存在する。
気候アクティビストは、地球環境のまったなしの状況を、切迫感をもって誰よりも感じている。だからこそ産まれる子どもにとって世界はどんな風に目に映るのかつきつめて考え、自然に釧路さんは反出生主義への論駁に近似していったのだと感じた。
さらに釧路さんは、いまの世界情勢をもっと冷静に見渡しつつ、強烈な希望を掲げた。
「歴史的にみても、人類の社会構造って飽和状態になって崩壊しないと、次のものがやってこないですよね、残念ながら。だから、一面では、資本主義が崩壊に向かっていく中で、いろんなことが表面に出てきて、悪化している部分もあるけど、もともと悪い部分が表面に出てきただけというところもいっぱいあると思うんです。そのなかで私の、社会を変えたいと思っている性分としては、多くの人が苦しんでいる状況をチャンスという言葉で表現したくないんだけど、でもより大きな変化への可能性がいままさに存在してる。状況が悪化したからこそ、より多くの人が気づいて、変えようねという機運が高まってきている。決して、しんどくないわけでないんですが、まさに生きるに値する時期だ――私はそういう気持ちでいますね」
「生きるに値する時期」という言葉に胸打たれた。世界が崩壊するとき、ジャンヌダルクのように旗をもって、それでもへこたれずに前に出るのは釧路さんのような人なのかもしれないとも思えた。
「あとはやはり、もう残念ながら超長期戦なんです、気候変動問題は。私が死んでからも続けなくてはいけなし、次の世代へバトンを、というときに、気候アクティビズムを生涯かけてやる人の下で子ども時代を過ごす人が、次のジェネレーションにいっぱいいることはポジティブなことだと思うんです。その変化のために産もう、というのもすごくありますね。娘に必ずしもフルタイムの気候アクティビストになってほしいとは思っていないけれども、あらゆるエコシステムが繋がっているように、自分もこの社会も繋がっていて、自分の人生を楽しんで伸び伸び生きていくことと、この世界を変えていくことがほぼ一緒のことだというのを、私と一緒に育つ中で当たり前のこととして身につけてくれたらいいな、と」
「希望を失わないための努力を絶対にやめない」
この連載は主に「産まない」ことを選択した、選択しようとしている女性たちにインタビューしながら、今の世界を考えたい、危機的状況にある世界をもっと感じたいと思って始めたものだが、今回釧路さんという「産んだ」女性を取材したいと思ったのは、ひとえに気候変動アクティビストが子どもを産むことはどういうことか、という興味からだった。釧路さんの答えには、未来への能動的な関わりが見てとれる。そこにはやはり、もう地球の状況は何かを待っているような状態ではない、という切迫感があった。
「今まで社会活動みたいなものには全然興味なかったんだけど……という人が今どんどん気候変動やフェミニズムの活動に参加してきてくださっています。数で言えば、まだまだ少ないかもですが、増え方は今までの比ではありません。こんなに大変な世の中になるのを、私はただ黙って見ていたくない、そう思う人が増えている。気候変動という現実が自分にとってめちゃくちゃ悲しいこととして目の前にあって、だけど何も諦めたくない、自分を被害者に感じたくないという感情もあります。諦めないことが、その解決にポジティブに貢献するという信念みたいなものがあるから。そして今の時代に子どもを持つということは、希望を失わないための努力を絶対にやめない、というコミットメントだと思っています」
悲観的なことを言い連ねることは簡単なことだ。いまはむしろ希望を語ることに大変な努力がいる。たぐい稀なポジティブな思考で、強く明るい力を放つ釧路さんだったが、信じられる未来がその手につかめそうな、たしかな具体的な力というものが、人を動かすときには必要だ。未来のヴィジョンを指し示すというのは、そういう態度そのものを指すのかもしれない。そのヴィジョンのなかに、子どもを産むという「冒険」が入っているということが、今回の取材ではたいへんに強いメッセージとなった。
私自身も2人の子を産んで実感している。ひとりの子が持っている可能性は爆発的な力だ。それも一人一人がまったく異なる。世間の常識に食いつぶされることもあるだろう、社会の構造に押しつぶされることもあるかもしれない。しかし本来は生命の可能性というか、未来を信じる力は一人一人に標準搭載されている何かなのだ。
地球環境だけでなく、社会も経済も絶望しようと思えば、簡単に絶望できてしまう状況にある。とはいえいつの時代もそうだった。私たちが子どものときは大気汚染もいまよりずっと酷く、世界の核汚染も今より強かった。草一本生えないと言われた広島はいま緑の街だ。そこで元気に育った子どもたちは先代の被爆者たちの代わりに体験の語り部を担おうとさえしている。次世代の子どもたちが世界とつながろうとする感覚は、もしかしたら私たちとはまったく違うものになるかもしれない。未来は読めないのだ。それを釧路さんに感化され、「生きるに値する時期」と呼んでみたい。
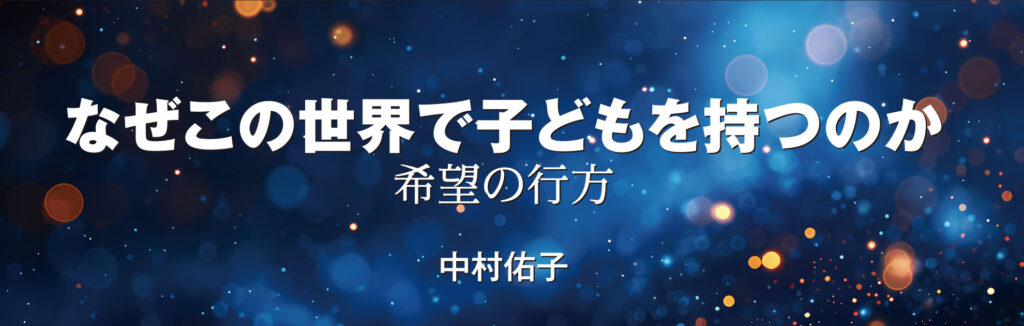
世界各地で起きる自然災害、忍び寄る戦争の気配やテロの恐怖、どんどん拡がる経済格差、あちこちに散らばる差別と偏見……。明るい未来を描きにくいこの世界では、子どもを持つ選択をしなかった方も、子どもを持つ選択をした方も、それぞれに逡巡や躊躇、ためらいがあるだろう。様々な選択をした方々のインタビューを交え、世界の動向や考え方を紹介する。
プロフィール
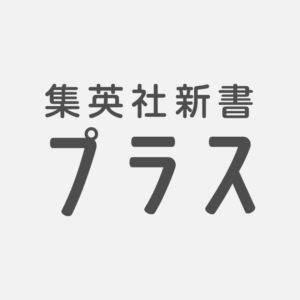
1977年東京都生まれ。作家、映像作家。立教大学現代心理学部映像身体学科兼任講師。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』が、著書に『マザリング 性別を超えて<他者>をケアする』『わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅』がある。


 中村佑子
中村佑子













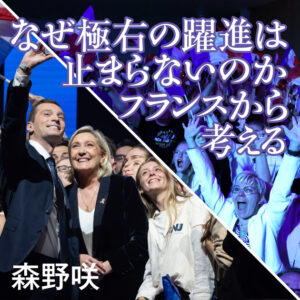
 森野咲
森野咲