パンデミックで壊滅的になった映画と映画館
カンヌ国際映画祭での監督賞受賞から10ヶ月、日本では待ちに待った公開となった『別れる決心』だが、韓国ではすでに配信が始まってしまった。
「Netflixで少しずつ見て、ちょうど半分まで来た」
韓国人の友人に言われた時は、ショックだった。彼女は映画が大好きで、話題作は封切り目がけて駆けつけた人だったのに……。
「でも大丈夫、ちゃんと見るから。そしたら感想を語り合おうね」って、もちろん、それでもいいのだけど。
もとから韓国は劇場公開と配信の同時スタートというサービスもあった国だし、映画公開から6ヶ月での配信開始は仕方ないとは思いつつも、それでもやはり少し残念な気がする。せめてこの作品に限っては映画館で見てほしかったと、少し恨めしい気持ちになった。
「パンデミックで壊滅的になった映画と映画館を守る」
「映画は映画館で見よう」
パク・チャヌクはカンヌの受賞インタビューなどでも再三訴えてきた。日本では韓国映画は元気モリモリというイメージもあるようだが、パク・チャヌク監督をはじめ、映画関係者はかなりの危機感をもっていた。だから彼はカンヌから帰国した足でソン・ガンホと一緒に大統領官邸に行って、「映画業界を支援してほしい」という要請もしたのだ。
日本で考える以上に、パンデミック下の韓国映画業界は大変だった。韓国政府の新型コロナ対策は徹底しており、その行動制限は日本よりもはるかに厳しかった。映画館の多くが開店休業状態となり、さらに映画の製作中止や延期が相次いだことで、制作現場も人材の多くが大盛況のドラマのほうに流れてしまった。
昨年4月にやっと多くの制限が解除されて、夏以降には映画館にも人が戻ってきたが、それでもまだパンデミック前の約半分だという。若い人々はいいのだけれど、くだんの友人のような40代以上の大人たちが問題だった。
「コロナのせいで映画館に行くのが億劫になってしまった」
彼女たちこそが韓国映画を支えてきた。『シュリ』(1999年、カン・ジェギュ)や『JSA』(2000年、パク・チャヌク)で韓国映画のビッグウェーブが始まった時に20代だった人たち。もちろん仕事も家庭も今が一番忙しい時だと思うから、一本の映画を分けて見るのも仕方ないかもしれない。
ただし不景気な話ばかりではない。2022年の韓国映画は記録的なヒット作も生み出した。マ・ドンソク主演のアクション映画『犯罪都市2』(イ・サンヨン監督)は観客数1200万超で殿堂入り。人口5000万人の国で1200万人とは恐ろしい数字なのだが、韓国では時々こんな「1000万映画」が登場する。
『別れる決心』のために、何度も映画館に行く人々
『別れる決心』はそういうタイプの映画ではない。
観客数は昨年末までに198万人。7月の時点では収益分岐点である150万人が越えられるか心配されていたが、熱心なファンに支えられてロングランに持ち込めた。
そもそもパク・チャヌクの映画はみんなでこぞって見に行く「国民的映画」のようなものではなく、映画好きのための映画。もっと言えばパク・チャヌク好きのための映画かもしれないし、繰り返し何度も見たくなる映画である。
6月末にソウルの上映館で行われた監督のトークイベントは、そんな若い映画ファンでいっぱいだった。
「何回見ましたか?」の質問に、「2回見た」「3回見た」「もっと見た」と、ほぼ全員が複数回見ていた。かくいう私はまだ2回、あのBTSのRMはなんと5回も見たそうだ。
「BTSの彼には知人を通して試写会の招待券を送ったのですが、何かの手違いで届かなかったみたいですね。自分でチケットを買って見てくれたようです」
パク監督はそんなことも言っていたが、RMの立場からすればメディア関係者が集まる試写会よりも、ひとりでゆっくり見たほうが気楽だろう。
複数回見たという人が多いのは、一度見ただけではよくわからないし、もっとわかりたいと思うからだろう。この映画のミステリーは犯人探しだけではない。最大のテーマは2人の関係性、「愛」の謎解きをしたい。それはいつ始まって、どう展開していたのか。
映画を見ながらあらためて思ったのだが、2時間余りの「映画館の時間」が心地よい。スマホも切って、作品にだけ集中する時間は心のデトックスだ。そのために『別れる決心』はとてもよい。
「特殊効果や派手な場面のない映画こそ、映画館で見るべき」という意見をよく聞いたが、全面的に賛成だ。ジェットコースターに乗るような爽快感はないが、自分の心の動きに寄り添うことができる。
映画の舞台、イポという海辺の街
公開直後の映画でもあるし、ネタバレがないように最大限の注意を払いたい。その上で今回も映画の背景にある韓国社会について、一般的な映画評ではあまり触れられないことなども書いていこうと思う。
映画の舞台となっているのは、韓国南部にある釜山と「イポ」という街だ。釜山は実在の街だが、イポは実際の韓国地図にはない架空の街である。
イポは原子力発電所のある街だ。主人公の刑事ヘジュン(パク・ヘイル)は平日は勤め先の警察署がある釜山で暮らし、週末だけはイポに来て夫婦の時間を過ごす。
原発で働く妻はエリート技術者であり、「全国で最年少の原子炉監督」と報道もされたようだ。夫婦には寮生活をする中学生の息子がいるが、「妻に似て理系」であるために勉強が忙しく、映画には登場しない。
韓国にはこうした「週末夫婦」は少なからずいて、映画の中にも「週末夫婦の10組に6組は真剣に離婚を考えている」というセリフが登場する。しかしふたりの夫婦関係は盤石だという前提で、映画はスタートする。
全てに明確な理系の妻に従う夫も生真面目な性格だ。仕事も家庭も定規で線を引くように几帳面にこなしてきたのだが、ある事件をきっかけに眼の前の風景がぼやけていく。
映画はその事件から始まる。定年退職した元出入国管理局の職員が、山登りに行って山頂から転落した。彼には若くて美しい妻ソレ(タン・ウェイ)がいた。
主人公のふたりは担当刑事と被害者の妻として出会った。
「中国人だから韓国語が苦手です」
アクセントのある、いかにも外国人とわかる韓国語で彼女は話す。
「山から帰らない時は心配しました。ついに死ぬのかと」
「ついに?」
この「ついに」という単語は随所に登場するのだが、彼女の使い方は少し不自然だ。間違ってはいないのだが、韓国人ならこういうふうには使わない。そこで刑事はわざと言う。
「僕より韓国語は上手ですね」
外国人が話す少し変わった韓国語。その微妙なズレが映画の重要なメタファーとなっている。どう受け取っていいのか戸惑う刑事のもやもやとした思いは、そのまま深い霧になって視野を妨げる。
イポは霧の深い街である。韓国の地名で「ポ(浦)」つくのは海辺や川辺を意味している。この映画の主題歌も『霧』である。
映画のきっかけとなった名曲『霧』
「中国人の妻」は訪問介護の仕事をしている。韓国でも介護職は日本と同じく慢性的な人手不足で、その大部分は外国人労働者の仕事となっている。彼女たちは一つの国で暮らしながらも影のような、身近にいながらも顔が見えない存在である。そんな存在が映画のヒロインとして登場したことは特筆すべきことであり、それについても後でふれたいと思う。
訪問介護先の高齢女性は身体が不自由であり、介護の人が来るのを待ちわびて暮らしている。そんな彼女の友だちはスマホである。声をかけて、曲をリクエストする。
「ねえSiri、歌をかけて、チョン・フニの『霧』」
韓国人なら誰もが知る韓国歌謡の名曲中の名曲である。1967年に同名映画の主題歌としてリリースされたのだが、映画よりも曲の方が大ヒットして、当時まだ16歳だったチョン・フニはスターとなった。
パク・チャヌク監督も幼い頃からこの曲が大好きだったという。この曲を主題歌にできる映画を作りたいというのが、『別れる決心』のそもそものきっかけだった。
高齢女性のスマホから始まり、映画の様々なシーンにこの曲が挿入されているのだが、驚いたのはエンディングだ。衝撃的なラストシーンの後、エンディングロールとともに主題歌が流れるのだが、そこではチョン・フニの声に男性の声が重なっている。完璧だ、と思った。
どこかで聞き覚えのある声なのだが、誰だかわからなかった。映画館から出て急いで調べたら、ソン・チャンシクであることがわかった。彼もまた韓国人なら誰もが知る韓国フォークの大御所であり、大ヒット曲『鯨とり』(1975年)を歌った人だ。
彼も若い頃この『霧』をカバーしており、それを知ったパク・チャヌクは映画のためにふたりにデュエットを切願したという。
ソン・チャンシクは二度にわたる喉の手術をしており、「もう昔の声は出ない」と固辞したそうだが、それをチョン・フニが説得した。そうして実現したのがエンディングのデュエットだ。パク・チャヌクは「生涯の夢が叶った」と喜び、また韓国のテレビ番組でもふたりを呼んでスタジオでのライブを実現させた。
この映画について書くにあたり、この『霧』にあたる曲は日本では何だろうと、ずっと考えていた。同時代の日本で女性歌手のヒット曲といえば、由紀さおりの『夜明けのスキャット』(1969年)とか青江三奈の『伊勢佐木町ブルース』(1968年)あたりが有名だろうか。
ただ『霧』はそれよりもはるかに、韓国の人々にとっては「ソウルソング」であったことが、今回の映画を通して再認識された。これまでも多くの人がカバーしてきたし、BoAのバージョンなども知られていた。そして、今また新たなデュエットが生まれた。
もともと映画音楽だった『霧』は、そこから国民的なヒット曲となった。それが巡り巡って映画のアイディアとなり、再び映画音楽となって蘇る。その大衆芸術のリレーに参加できたことを、パク・チャヌクはとても喜んでいた。
年末に開かれた韓国のアカデミー賞と言われる「青龍映画賞」で、『別れる決心』は最優秀作品賞を始め主要6部門の全てを受賞した。映画祭のステージでチョン・フニがこの曲を歌った時、主演女優賞を受賞したタン・ウェイは会場で涙を流していた。
中国人女性と韓国人男性の恋愛
タン・ウェイとパク・ヘイル。カンヌ国際映画祭に『別れる決心』が『ベイビー・ブローカー』(是枝裕和監督)と並んで出品された時の感動は、このキャスティングのせいもある。
長年のパク・ヘイル推しというのもあるのだが、それよりも中国のスター女優がパク・チャヌクの映画に出て、ソン・ガンホやIUが是枝監督の映画に出るというハイブリッドが嬉しかった。欧米では見慣れた光景でも、やはり東アジアの映画人が国籍を超えてカンヌの舞台に並ぶ図は壮観だった。もちろんカンヌだけじゃないし、アジアだけじゃないが、それでもアジア映画の長い共同作業の時間を思うと感無量である。
韓国人と中国・香港映画との関係は深くて長い。まだ下積み時代のジャッキー・チェンが韓国で活動していたことはよく知られており、ワールドスターになった後の彼も、韓国を訪れるたびに過去の思い出と感謝を韓国語を交えて語っていた。また独裁政権下の厳しい検閲や日本映画上映禁止の時代には、香港映画がある意味ではハリウッド映画以上に韓国で大衆的な人気を得ていた。
2000年以降に数々のヒット作を生み出した韓国ノワールの監督たちは、いずれも香港映画の影響を強く受けており、作品にもそのオマージュが盛り込まれている。例えば韓国ノワールの第一人者ユ・ハ監督の『マルチュク青春通り』(2004年)は監督自身の自伝的要素が強い作品と言われるが、主人公の高校生を演じるクォン・サンウがブルース・リーに傾倒してヌンチャクを振り回すシーンが印象的だ。映画の中で当時の男子高校生たちが「小龍か、成龍か」と、香港の二大カンフー・スターを巡って言い争う様子も微笑ましい。
カンフー映画や香港ノワールは特に男性に人気があったが、女性たちの中にも香港スターのファンは多く、『チャンシルさんは福が多いね』(2019年、キム・チョヒ監督)のような女性監督の映画にも、いきなりレスリー・チャンの幽霊が登場したりもする。
日本にもかつて香港映画ファンは多かったが、おそらく韓国での人気はそれ以上であり、2000年代に入ってからは、韓国映画の側からの共演オファーも続いていた。
今回のような韓国人と中国人の恋愛を素材にした映画としては、セシリア・チャンとチェ・ミンシクが共演した『パイラン』(2001年、ソン・ヘソン監督)を皮切りに様々な作品が出ているが、いずれも韓国人男性と中国人女性という組み合わせが多いようだ。これはおそらくアジア市場における「韓国の男性スター」の集客力が関係しているのだろうが、やはり中国女性への憧れもあるのだと思う。
タン・ウェイは以前にも『レイトオータム』(2010年、キム・テヨン監督)でヒョンビンと共演しているが、この時のタン・ウェイのキャラクターにも、寡黙ながらまっすぐな強さがあった。この作品も古い韓国映画の名作『晩秋』(1966年、イ・マニ監督)のリメイクであり、「大人の恋愛を描いた」と評されている。
ただ『レイトオータム』の舞台は米国シアトルであり、韓国人も中国人もアジア系マイノリティという「ある意味で平等な立場」だった。それは親族を頼って韓国にやってきた末に偽装移民となったパイランや、韓国で父親ほどの年齢の男性と結婚した『別れる決心』のソレとは立場が違う。
在韓外国人、マイノリティとしてのソレ
ソレはあくまでも在韓外国人というマイノリティの立場であり、韓国社会の一般的な認識では「弱者」である。一方で、刑事であるヘジュンは圧倒的な「強者」の立場なのだが、その強弱の関係がゆらいでいく。愛はスリリングだ。
現実の韓国社会で暮らす中国人女性といえば結婚移民としてやってきた妻であったり、すでに述べたように介護職や家政婦、飲食店などで働く低賃金労働者が多い。
韓国で「結婚移民者」というのは在韓外国人の在留資格を表現する言葉でもあり、韓国政府の統計によれば2021年現在で約16万8000人となっている。そのうちの8割が女性である。
国籍別では「中国」(約4万6000人)が圧倒的に多く、次に「ベトナム」(約3万8000人)、そして「日本」(約1万4000人)、「フィリピン」(約1万2000人)が続く。
中国国籍者の中には「朝鮮族」(1万4000人)と「それ以外の中国人」(3万2000人)がいて、最近は後者の方が多くなっている。「朝鮮族」の場合は韓国人と同じ民族であることから、現在では特別な就労ビザが得られるため、以前のように結婚までして移住する理由がなくなった。そのために結婚移民の率は減ったのだと分析されている。
映画『別れる決心』の中では、ソレの背景が説明される場面がある。
「2015年8月17日、海洋警察は中国からの貨物船による不法入国者を摘発しました。他の37人は追放されたが、ソレさんだけ残った」
「母方の祖父は満州朝鮮解放軍のケ・ボンソク氏、祖父は建国勲章、独立功労者」
また映画の公式ホームページの登場人物紹介では、ソレについて次のように記されている。
「中国人だが、母方の祖父は朝鮮半島の独立運動家であり、自分の先祖の歴史と祖父に誇りを持っている」
中国朝鮮族と独立運動
中国人だが、母親の祖父は朝鮮半島の独立運動家。その祖父は満州にいた。
旧満州は現在の中国東北地方である。中国の少数民族のうち朝鮮族は約200万人といわれるが、その大部分は遼寧省・吉林省・黒竜江省の「東北三省」に暮らしている。北朝鮮との国境近くの延辺には朝鮮族自治州もあり、そこでは朝鮮語による学校教育も行われている。その地域における朝鮮系の人々の歴史は古代に遡るが、近代においては日本帝国主義の影響も大きい。
映画との関連でいえば、日本の植民地時代に独立運動家たちは、国内での弾圧から逃れて中国での活動を広げていった。ソレのように、その独立運動家の直接の子孫にあたる人々もいるし、朝鮮族の間にはコミュニティ全体として独立運動を支えたという自負心もある。
韓国が中国との正式国交を結んだのは1992年だが、その前後から朝鮮族の人々の一部が韓国に出稼ぎに来るようになった。当時の韓国にはまだ外国人労働者を正式に受け入れる法制度がなく、不法滞在のような形になる人々も少なくなかった。
当初は「同じ民族」「独立運動を支えた人々の子孫」として歓迎された朝鮮族の人々だったが、当時の中国と韓国の経済格差は両者の間に上下関係を作った。
さらに韓国政府はIMF危機のさなかの1998年に、海外で暮らす韓国系(主に米国系韓国人)の人々からの支援を得ようと「在外同胞特別法」という法律を設定したのだが、それがまた差別的なものだった。法律は韓国内での居住やビジネスの自由を保証するものだったが、そこから中国やロシアに住む「同胞」は除外されてしまったのだ。
「金持ちの国に住む子どもと貧乏な国に住む子どもを差別する祖国」と朝鮮族の人々は激昂し、韓国政府と韓国人に対する不信感をつのらせた。
法的な未整備状態は、韓国で働く朝鮮族の人々の立場を不安定にし、そこにつけこんだ悪徳ブローカーによる詐欺事件なども頻発した。先に紹介した『パイラン』や、『海にかかる霧』(2014年、シム・ソンボ監督)などはこの時代をモチーフにしている。『海にかかる霧』は実話ベースであり、2001年に起きた密航船事件がもとになっているのだが、犠牲者たちがどれだけひどい目にあったのか、リアルな映像は正視できないほどだ。
その後に、韓国政府は何度かの法改正を通して朝鮮族の人々への差別解消に努力したのだが、現実の韓国社会では今もまだ様々な問題が残っている。滞在や就労は合法化されても働ける場所は限られており、韓国という階層社会の中での地位は決して高くはならない。
映画『別れる決心』には、ソレが祖父の遺骨を山に埋めるシーンが出てくる。全体の流れとの関係性は見えにくいのだが、ここはとても重要な場面だと思う。
韓国には現在、約60万人の朝鮮族の人々が暮らしていて、ひとりひとりには大切な個人史がある。ところが彼らの多くは顔の見えない存在であり、映画などでもそれが丁寧に扱われることはなかった。
韓国映画で消費されてきた、ステレオタイプの在韓中国人
映画はむしろ、差別に加担していた。
これは以前から散々言われてきたことだが、韓国映画における在韓中国人・朝鮮族の描かれ方はとても偏っていた。『悲しき獣』(2010年、ナ・ホンジン監督)、『ミッドナイト・ランナー』(2017年、キム・ジュハン監督)、『犯罪都市』(2017年、カン・ユンソン監督)等、いずれもスター俳優が出演する大ヒット作なのだが、それらに登場する朝鮮族の人々といえば、常に「密航者」や「不法滞在者」、「麻薬の密輸」や「臓器売買」などの犯罪者として登場するケースばかりだった。
外国系マフィアを巨悪に仕立て上げるのは、エンタメとしては「お手軽な手法」なのかもしれないが、いくらなんでも韓国映画はひどすぎたと思う。なかでもソウル市内のチャイナタウンを悪の巣窟のように描いた『ミッドナイト・ランナー』は、映画の中のセリフに露骨な憎悪表現などもあり、見ていて声を上げてしまうほど驚いた。
さすがにこの映画は当事者である中国系の人々から訴えられて裁判に至った。裁判所の指示に従い制作者は謝罪をしたが、すでに損なわれてしまったイメージを回復するのは難しい。ちなみにここに登場するチャイナタウンは、以前この連載でとりあげた仁川のチャイナタウンとは違い、1990年代半ばから朝鮮族の人々などを中心に形成された新しいチャイナタウンだ。従来の在韓華僑をオールドカマーとするなら、ニューカマーの街という言い方ができるのかもしれない。
悪のイメージを押し付けられたニューカマーの男性たちに比べると、女性たちはまだましだったのだろうか?
朝鮮族女性のヒロインといえば、『ダンサーの純情』(2005年、パク・ヨンフン監督)が有名だ。こちらもまた「偽造パスポート」で入国した女性なのだが、その役を演じたのは当時大人気だった「国民の妹」ムン・グニョンということで大いに話題になった。
この原稿を書くにあたりもう一度見直して見て、とても懐かしい気持ちになった。たしかにあの頃は朝鮮族の若い女性といえば、「田舎から出てきた遠い親戚の子」みたいなイメージがあった。それを守ってやる正義の味方としての韓国男性という構図は、今だったらウケないだろうなと思う。
『別れる決心』への、1つの視点
異色だったのは2016年に公開された『Missing:消えた女』(イ・オンヒ監督)である。日本語タイトルは『女は冷たい嘘をつく』となっているが、これは原題からも内容からもかけ離れている。なんでこんなタイトルになっているのか謎すぎる。
これは韓国では珍しい女性のツートップ映画であり、ひとりはドラマ制作会社に務めるシングルマザー、もうひとりが中国人のベビーシッターという組み合わせだ。
韓国では介護職と同様、家政婦やベビーシッターも、主に外国人労働者の仕事である。特に富裕層ではなくても、住み込みや通いの家政婦さんを雇う人が結構いて、その際には低賃金で働いてくれる外国人女性が好まれる。このあたりの事情はシンガポールなどに近く、日本とはかなり違う。
映画に出てくるシングルマザーは子どもの親権をめぐって訴訟中であり、孫を渡すまいとする義母との関係なども丁寧に書かれている。さすが女性監督の作品だと思わせる視点が随所にあり、フェミニズム映画としても大変な秀作だと思う。また韓国の農村における結婚移民者への暴力や人権侵害についても言及してあり、日本語版のタイトルからは想像もできない意欲作である。
この映画もミステリー仕立てであり、当初の予想とは全く違った方向に物語は展開していく。事件の鍵を握るのは中国人ベビーシッターのハンメなのだが、そもそも彼女は中国人なのか、同胞である朝鮮族なのかもわからない。
物語はこの人物の謎を解いていくという、まさにミステリー映画の王道をいくのだが、その際に大雑把なステレオタイプはむしろ邪魔になる。人々の予想を裏切りながら事件は解決に向かい、それと同時にハンメという女性の謎も解かれていく。その時、映画のテーマもはっきりと浮かび上がり、スッキリとする。
そこが『別れる決心』とは違う。『別れる決心』は一度見ただけでは、スッキリとはしない。最後まで見ても、ソレという女性の謎は解けない。
『別れる決心』は、これまでの韓国映画のステレオタイプとの、文字通りの決別だったと思う。この映画のヒロインは朝鮮族ではないし、完全な外国人としての中国人でもない。そして、その真っ直ぐな眼差しは、人々のあらゆる先入観や願望をすり抜け、逆に制圧するほどの強さを持つ。そもそも人間はミステリアスなものなのだ。それでも手がかりがほしいと、何度も映画を見てしまう。パク・チャヌクという人が描こうとした人間は、いったいどんな姿なのか。映画の中でヘジュンはしきりに目薬をさしている。そうすれば目の曇りがとれるのか。霧が晴れれば、何かが見えるのだろうか?
冒頭に「映画は映画館で」と書いたものの、これを書きながら旧作などは完全に配信に頼っていた。映画館でも見られるし、配信でも見られる。やはり映画にとって良い時代になったのだと思う。それでも『別れる決心』は映画館で見ることをオススメしたい。
プロフィール



 伊東順子
伊東順子
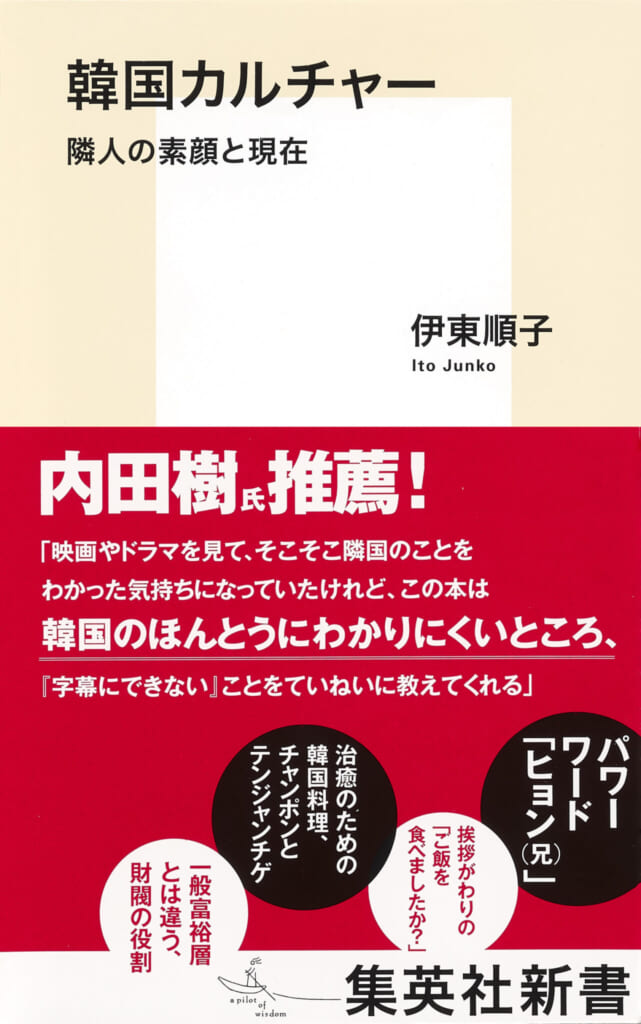













 大塚英志
大塚英志

 三宅香帆
三宅香帆