服薬は助けにはなったが、息苦しさは治まらなかった。ために私はまず、コールセンターに電話をする。
「こういう症状があり、基礎疾患もあるのですが、どういう選択が考えられますか?」
「では、この番号へ掛けてください」
教えられたのは、まさに「帰国者・接触者相談センター」の番号だった。
ただ、相談センターの電話は、まったく繋がらなかった。タイミングもあるのだろうが、繋がるまでに二日を必要とした。
係の人は、丁寧に話を聞いてくれたあとで、
「帰国者、あるいは発症者との濃厚接触がなければ、PCR 検査は出来ません」
と言った。
ならば、どういう状況なら検査を受けられるのだろう。
「肺炎と診断されたら、もう一度お電話ください」
どこか覚悟を感じさせる口調だった。答えもあらかじめ決まっていたような気がする。
おそらく、キャパシティを超えているのだ。検査を受けさせたくても、彼らにはできないのだと思う。
日本では、一日の検査数は多い日でも、8千件ほどにとどまっている。政府が声高に「一日2 万件」と繰り返しているのは知っている。だが、それは遅々として実現しない。結果、多くの人が心配と不安を深く抱え込むのである。
電話を切る際、私は言った。
「皆さんもお疲れでしょう。どうぞお大事に。頑張ってください」
最前線に立つ現場は、重たく疲弊している。彼らがいてくれて、私たちは救われているのだ。どんな場合であっても、伝えるべきは感謝だ。それしかない。
私は今も微熱が続き、ときどきひどい息苦しさに見舞われる。カルテのある大学病院からは、「喘息の症状」と言われた。自分でもそう理解している。
だが、万が一、新型コロナであってはいけないから、外出自粛を自らの責任としている。これが、私の過ごした最近の「ひとつき」である。
プロフィール



 宇都宮直子
宇都宮直子
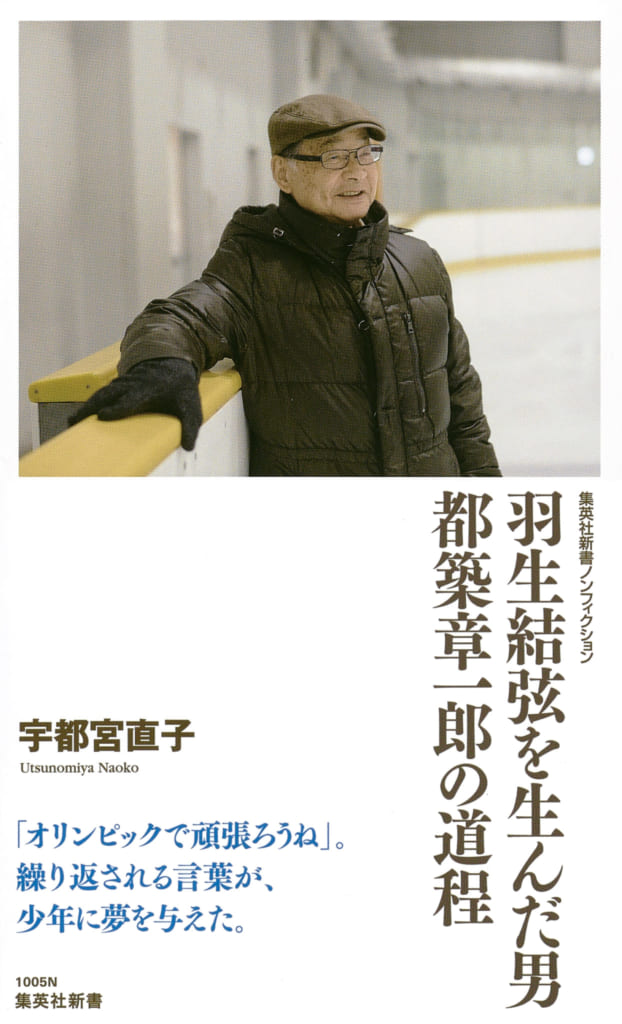










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


