前回(第5回)、脂肪が蓄積する部位によって、「皮下脂肪」「内臓脂肪」「異所性脂肪」の3種類があること、そのうち、内臓脂肪と異所性脂肪が蓄積すると非常に危険であることを伝えました。
危険な理由は、糖尿病、脂質異常症、高血圧、脂肪肝などを引き起こし、いずれも動脈硬化をまねいて心筋梗塞や脳卒中で倒れる可能性があるという、近い将来のストーリーが待っているからです。
また、脂肪とは「脂肪細胞」のかたまりであり、ひとつひとつの脂肪細胞には「中性脂肪」がたっぷり含まれているのでしたね。中性脂肪の含有量が多いほど脂肪細胞は肥大化し、数も増えて脂肪としてどんどんたまっていきます。
おなかの中の腸の周りに蓄積する内臓脂肪や内臓そのものにつく異所性脂肪の細胞からは、悪玉と呼ぶ数種のホルモンや生理活性物質が分泌されます。それゆえに、「健康減量」を考える際には、脂肪の中でも皮下脂肪ではなく内臓脂肪を減らすことが重要です。
減らさないとどうなるかを具体的に知っていただくために、患者さんの数が多い生活習慣病について、これだけは知っておきたいというポイントをこれから簡潔に述べておきます。今回は、前回の中性脂肪や内臓脂肪型肥満の話の流れから、「脂質異常症」という病気の実際を直視しましょう。
「健康診断で、中性脂肪やコレステロールの数値が高いから脂質異常症だと言われた。体調はまったく悪くないのにびっくり」と嘆く人はとても多いのです。それに、実は脂質異常症は、50歳以上の女性に急増することも各医学会が警告しています。
■実はコレステロールや中性脂肪には役割がある
脂質異常症とは、血液中の「脂質」である「コレステロール」(詳細は後述)や「中性脂肪(トリグリセリド)」(第5回参照)などが基準値をはずれた状態をいいます。これまでにも述べたように、脂肪の蓄積が要因となる糖尿病、高血圧、がん、認知症、脂肪肝、睡眠時無呼吸症候群などと同じく、生活習慣病のひとつです。
コレステロールも、中性脂肪と並んで健康診断や一般的な血液検査での項目のひとつなので、なじみのある成分でしょう。世間の情報から悪者という印象があるかもしれませんが、実際にはそればかりではありません。
コレステロールは全身の細胞膜をつくり、体内でつくられるステロイドホルモンやビタミンDの原料となり、また脂肪の消化やビタミンの吸収を促す胆汁酸の原料ともなっています。それに、皮膚や髪をなめらかに維持する役割もあるのです。
中性脂肪のほうは前回、体温を一定に保持し、また、エネルギー源として貯蔵され、糖質が不足したときの補助として作用すると述べました。いずれも、ヒトが生きていくうえで重要な役目を担っています。
■コレステロールや中性脂肪が血管をむしばみ「動脈硬化」に
しかし、中性脂肪やコレステロールが血液中に増えすぎたときには、健康を脅かすほどの大きな問題が生じます。
これらが血管の壁にたまると炎症が慢性的に起こります。すると血管の内壁が硬くなり、やがては図1のようにかたまり(プラーク)をつくりはじめるのです。その結果、血管内が狭く流れが悪くなったり、内壁に血栓(血のかたまり)ができたりします。これが「動脈硬化」です。
血管をゴムホースに例えると、古くなってカチカチに硬く、ヒビ割れもあり、内側にはゴミやほこりがたまって水が流れにくい、流れが止まるイメージです。
実際、動脈硬化を起こしている血管では、血管壁のかたまりが突然に破裂してその部分が完全にふさがったり、一部がはがれて血栓となり、血液の流れが詰まったりします。つまり、生活習慣病では何が致命的かと言うと、この動脈硬化なのです。その点を認識しましょう。
図1を見てください。心臓を取り巻く太い血管(冠動脈。冠状動脈ともいう)で動脈硬化が生じると、心筋梗塞(こうそく)や狭心症の発作を引き起こします。また、脳の血管に発生すると、脳梗塞や脳出血になります。
いずれも命に関わる病気です。助かっても心臓や脳に障害が残り、話しができなくなる、手や足が麻痺(まひ)するなどのケースも少なくありません。
では、そうなると症状はどうなのでしょうか。実のところ、脂質異常症だと診断されたとしても、こうした発作などの深刻な病気を発症するまでは痛くもかゆくもないので、無自覚であることがほとんどです。
血液検査をしない限り、自覚も発見もできません。だからと言って脂質異常症を放置すると、動脈硬化から心臓や脳の重大で怖い病気をまねく可能性が高くなることをくり返し強調しておきます。
図1 脂質異常症を放置し動脈硬化が進むと…

■女性ホルモンの低下がコレステロール急増の引き金に
厚生労働省が毎年実施する人口動態統計の2023年(令和5年)の概況では、日本人の死因の1位はがんで、2位は心臓疾患、4位は脳血管疾患です(3位は老衰、5位は肺炎)。心臓疾患と脳血管疾患には、先述のように動脈硬化が深く関係していて、その原因のひとつが脂質異常症です。
また、厚生労働省が同年に実施した「国民健康・栄養調査」によると、総コレステロール値が 240 mg/dl 以上の者の割合(脂質異常症が強く疑われる割合)は成人女性が23.1%、成人男性が10.1%です。これを日本の人口規模で推計すると約1,700万人に脂質異常症が疑われることになります。
多くの人が興味を持たれるのは、「中年以降では、なぜ女性のほうがそんなに増えるのか」という点です。
男女とも、血液中の中性脂肪もコレステロールも、加齢とともに量が増加していきますが、とくに女性の場合は更年期の前後から脂質の中でもコレステロールが増加し、高齢になるにつれてさらに増えていくことがわかっています。
その理由は、女性ホルモンの「エストロゲン」の分泌量にあります。第5回で、「内臓脂肪は男性に多いが、50歳以降の女性では蓄積しやすくなって『隠れ肥満』が急増する」と伝えました。中性脂肪もコレステロールも同じことが言えます。
エストロゲンはコレステロール代謝に影響を与え、LDLコレステロール(いわゆる悪玉。後述)を減少させる作用があります。そのため、20~30代ごろの女性は、男性に比べてコレステロールの数値が低めに維持されているわけです。
しかし、女性は50歳前後からそのエストロゲンの分泌量が急激に低下するために、コレステロールが分解されにくくなり、必然的に血液中のLDLコレステロールが急に増えていくのです。
具体的には、LDLコレステロールの量は約20%ほど高くなり、さらに60歳ごろの平均値では男性を上回ります。
■血管の敵か味方か…「3つの脂質」
次に、脂質異常症と診断される基準を知っておきましょう。はじめに、血液中の3種類の次の脂質とは何かを把握してください。健康診断の血液検査の項目にありますね。動脈硬化を予防するうえで、これらの数値が診断基準のポイントとなります。
「LDLコレステロール」(Low density lipoprotein/低比重リポタンパク質。悪玉)
「HDLコレステロール」(High density lipoprotein/高比重リポタンパク質。善玉)
「中性脂肪」(トリグリセリド)
もうひとつ、特定健診での血液検査では「Non-HDLコレステロール」の数値が表示される場合があります。これは、総コレステロールから善玉のHDLコレステロールを引いたもので、悪玉のLDLコレステロール測定の限界を補完し、動脈硬化のリスクをより正確に評価するものです。
「総コレステロール」という項目もありますが、検査によっては表示されない場合があります。2006年までは総コレステロールの数値が「脂質異常症」の診断基準として用いられていましたが、以降は上記の種類別の数値とほかの項目も考え合わせて診断するようになっています(後述)。
<豆知識> コレステロールの悪玉・善玉の実態
血液中のコレステロールの20~30%は食事からとり入れられ、70~80%は肝臓でつくられ、その量や割合は体内で調整されています。
LDLコレステロールを悪玉、HDLコレステロールを善玉と呼んでいますが、実はコレステロールそのものは同じ成分の物質です。では何が違うのでしょうか。
コレステロールは脂質なので水には溶けないため、その表面は「リポタンパク質」という物質でおおわれて血液に乗って運搬されています。
リポタンパク質は体内にいくつかの種類が存在し、そのうちの「低比重リポタンパク質」をLDLと、「高比重リポタンパク質」をHDLと呼びます。LDLとHDLという呼称は、それぞれの略称でもあります。
そしてLDLは、粒子が小さくて酸化しやすい性質があります。ということは、血管壁に侵入しやすくて、その場で蓄積されやすいわけです。そうなると炎症が生じ、動脈硬化が進みます。悪玉と呼ばれる理由はこの点にあります。
LDLコレステロールの数値が基準より高い場合は、炎症から動脈硬化を起こす可能性が高い、あるいはすでに起こっていることを意味します。
一方、HDLのほうは、全身の血管の酸化したコレステロールを回収して肝臓に運びます。古く腐りかけのゴミを掃除するイメージです。そのため、善玉と呼ばれます。
HDLコレステロールの数値が基準より低い場合は、そのゴミ掃除の能力が下がっているということを意味します。
図2 LDLコレステロールとHDLコレステロール

■「脂質異常症」診断基準がアップデート…最新の指針は
脂質異常症の診断基準は、動脈硬化のリスクをより正確に判定するために、ここ数十年で大幅に改訂されてきました。検査結果を見て、「項目が変わった?」と思われることもあるでしょう。それはこうした理由によります。
まず日本動脈硬化学会が示す現在の診断基準は次のとおりです。脂質の異常を4つのタイプに分類し、空腹時の血液を検査していずれかに該当する場合に「脂質異常症」であると定義しています。
脂質異常症とは、以下の4つ、「高LDLコレステロール血症」「低HDLコレステロール血症」「高トリグリセリド血症」「高Non-HDLコレステロール血症」の総称です。
<脂質異常症の4種の診断基準> 空腹時採血・単位はmg/dL
●LDLコレステロール(悪玉):140以上 高LDLコレステロール血症
120 ~139は境界域高LDLコレステロール血症
●HDLコレステロール(善玉):40未満 低HDLコレステロール血症
●中性脂肪(トリグリセリド):150以上・随時採血で175以上 高トリグリセリド血症
●Non-HDLコレステロール:170以上 高Non-HDLコレステロール血症
Non-HDLコレステロールとは、総コレステロールからHDLコレステロールを差し引いたもので、動脈硬化のリスク評価に用いられる。
150~169は境界域高Non-HDLコレステロール血症
見かたを変えると、悪玉のLDLの基準値は「140未満」、善玉のHDLは「40以上」、中性脂肪は「150未満」、Non-HDLは「170未満」であれば、基準値内なので異常なしとなります。血液検査の結果が手元にあれば確認してください。
さらに、医学的指標では、悪玉と善玉の数値のバランスが重要になります。そこで2021年ごろから、治療の現場では新しい指標が使われています。
血液検査結果に「L/H比」(LDL値÷HDL値)の記載があれば注目してください。記載がない場合はご自身で計算しましょう。これは、動脈硬化のリスク評価において有用だとして医療界では現在、広く認識されています。
一般には「LDL/HDL比が2.0未満が望ましい」とされ、「1.5以下ならバランスが良い状態」で、「2.5以上であると悪玉の比率が高く動脈硬化が進行しやすい」ことを示します。
また、中性脂肪が増加すると、悪玉のLDLコレステロールが増えて、善玉のHDLコレステロールが減少します。
病気の評価では、医師が各数値のバランスに加え、血圧、糖尿病、肝臓の機能の数値など全体を診て判断しますが、とくに動脈硬化と密接に関係するLDL(悪玉)コレステロールの数値による評価を重視しています。
例えば、HDL(善玉)コレステロールが高くてLDLコレステロールが正常範囲のケースでは、総コレステロールの数値が高くても脂質異常症と診断されないことが多いです。
しかし、Non-HDLコレステロールの確認や、まれですが遺伝的な病気でHDLが異常高値を示す病態もあり、その場合はHDLが高くても動脈硬化が起こりやすいとされます。総合的なリスク評価(家族歴、動脈硬化性疾患の既往、糖尿病など)も重要になるわけです。
脂質異常症は、かつては「高脂血症」と呼ばれていました。しかし、善玉であるHDLは数値が低いほど動脈硬化の原因となるため、2007年に日本動脈硬化学会が「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」を改訂し、診断名を脂質異常症と変更しました。
同時に、LDL(悪玉)コレステロールの増加、HDL(善玉)コレステロールの減少、中性脂肪の増加を含めて診断するようになっています。ただ、いまでも高脂血症と呼ぶ医療関係者や患者さんも多く、どちらも同じ病気のことです。
2012年には、LDLコレステロールやNon-HDLコレステロールに「境界域」の基準値が設けられました。これによって早期の治療が必要なケースがより明確になったのです。
2022年には中性脂肪の検査においては、空腹時だけではなくいつでもよい「随時採血」の基準値が新たに追加されました。健診や人間ドックでの利便性が向上したと言えます。
また上記の<診断基準>どおり、随時採血時に中性脂肪が175以上の場合も脂質異常症と診断されます。
■「肥満で脂質異常症」には特徴がある
4つの種類がある脂質異常症の中でも、肥満の場合は、善玉が減少する「低HDLコレステロール血症」と、中性脂肪が増加する「高トリグリセリド血症」が発生しやすいことが確認されています( ※1)。
とくに日本人は欧米人に比べて、これら2つの病気が動脈硬化の主な原因になっていることも明らかになっています(※2)。
その理由は、糖尿病の主な原因となる「インスリン抵抗性」にあります(第3回参照)。インスリン抵抗性があると、インスリンの働きが悪くなるために肝臓がエネルギーをうまく利用できなくなり、糖を中性脂肪(トリグリセリド)として蓄積しようとします。
その結果、中性脂肪の生成と血液中への放出量が増加し、一方で脂肪細胞からも脂肪酸が大量に放出されて肝臓に取り込まれ、中性脂肪がさらに増加します。
中性脂肪の増加は、HDLコレステロール(善玉)を生成する力を低下させるだけでなく、HDLを分解しやすくします。そのため、結果として低HDLコレステロール血症を引き起こし、動脈硬化のリスクを高めるのです。
善玉と悪玉のこっちがこうだからあっちはどうだとか、それはそうではないなどと混乱されるかもしれません。肝心なことは、脂質異常症を改善する、予防するには、内臓脂肪を減らすこと、これに尽きます。
それには、食事の内容や頻度、運動の量や頻度、睡眠の質や時間などを見直す必要がありますが、具体的な方法については後の回で述べます。効率的に健康減量をするためには、まずは、自身のおなかに蓄積された内臓脂肪がどれほど危険であるか、脂質異常症の場合は血液がコレステロールと中性脂肪でどろどろになっている状態だと医学的に理解しておくことがカギとなります。
次回は、インスリン抵抗性が強くかかわる糖尿病と高血圧、太り過ぎ、内臓脂肪、肥満の関係について紹介します。
参考
※1 Diabetes, Obesity and Metabolism, 2004; 6(6): 456-462.
※2 Ueshima H, Sekikawa A, Miura K, et al. Comparison of Atherosclerotic Risk Factors in Japanese and American Men: The Era of Serum Cholesterol Lower Than 180 mg/dL. Annals of Internal Medicine. 2002;137(8):602-613. doi:10.7326/0003-4819-137-8-200210150-00007
構成:阪河朝美/ユンブル

現在、世界ではダイエット目的にて、自由診療での「やせ薬」の購入や個人輸入によるニーズが急増している。もちろんそれは、日本も例外ではない。こうした動きを背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつある。しかし、果たして健康への影響はどうか。人体にとって必要な減量とは何か、どうすれば減量できるのか、減量治療の最前線から、それらを紹介する。
プロフィール
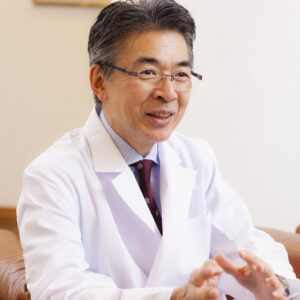
大阪府生まれ。医学博士。日本糖尿病学会専門医。日本臨床内科医会専門医。大阪府内科医会名誉会長。日本臨床内科医会副会長。全国臨床糖尿病医会理事ほか。医療法人弘正会ふくだ内科クリニック院長。滋賀医科大学卒。大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、ハーバード大学・ジョスリン糖尿病センターに留学。所属学会:日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床内科医会、日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本老年病学会、全国臨床糖尿病医会。著書に『糖尿病は自分で治す!』『糖尿病は「腹やせ」で治せ!』『専門医が教える 糖尿病ウォーキング!』『専門医が教える5つの法則 「腹やせ」が糖尿病に効く!』『専門医が教える 糖尿病食で健康ダイエット』ほか。医学会、一般向き講演、テレビ等のメディアでの出演も多数。


 福田正博
福田正博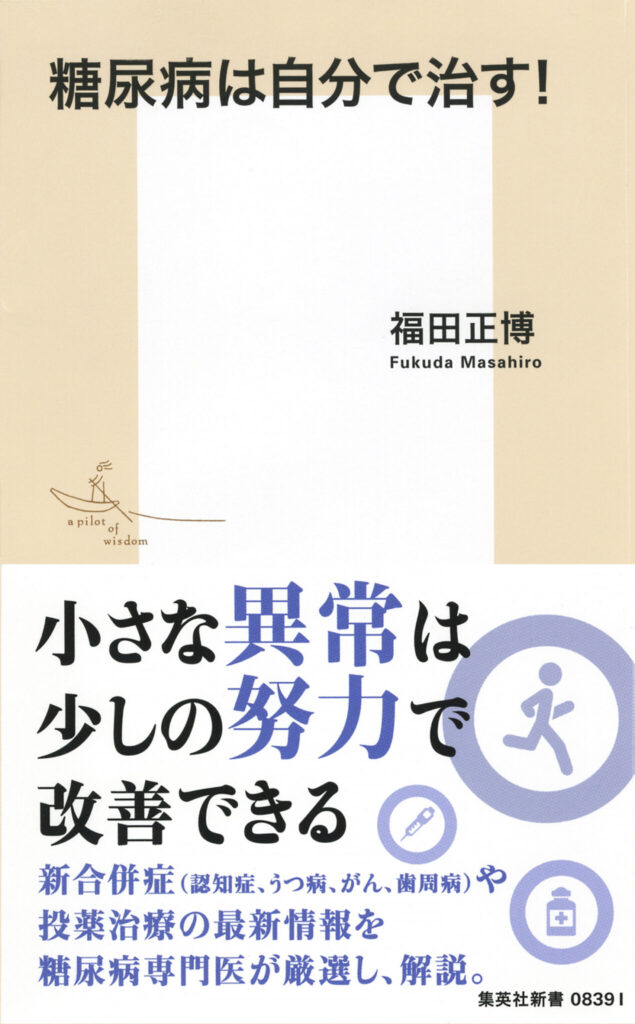










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


