韓国人も知らない? 済州島の「サムチョン」
さて、このチュニおばさんは、ドラマの中では「チュニ・サムチョン」と呼ばれていた。この「サムチョン」という言葉が、ドラマの中ではもっとも重要な済州島方言である。重要だから1話と2話の両方で、画面の脇に韓国語の字幕解説が出ていた。
「サムチョン:男女の区別なく年配に対する、親しみをこめた呼称」
つまり女性なら○○おばさん、男性なら○○おじさんといったニュアンスだ。
わざわざ字幕解説が入っていたのは、標準韓国語で「サムチョン」は、親の独身の「男兄弟」を指す言葉だからだ。漢字で書けば「三寸」(参考までに、いとこは「四寸(サチョン)」)。ところが済州島では血縁関係も性別も関係なく、目上の人に対しては親しみを込めてみんな「サムチョン」と呼ぶのだという。
韓国は長い儒教的な伝統があり、親族名称における男女の区別は厳格である、親族以外の目上の人に対しても男性なら「アジョシ」、女性なら「アジュンマ」と区別される。これは日本の「おじさん」と「おばさん」と似たようなニュアンスだ。ところが、済州島の「サムチョン」は、おじさんにもおばさんにも区別なく使用される。
これは一般の韓国人にとっても意外な使い方だし、性別にがんじがらめに言語習慣の中では、ものすごく新鮮な響きでもある。ドラマ『私たちのブルース』は、この「サムチョン」という言葉に済州島のアイデンティティを求めているようだ。血縁も性別も関係なく、サムチョンを敬い、やがて自分も敬われるサムチョンになる。ドラマはこの言葉などを通して、共同体の死生観を再構築している。
もちろん韓国人全員が解説字幕を必要としたわけではない。すでに済州島のサムチョンの意味を知っている人も多いし、この言葉を聞いて『順伊(スニ)サムチョン』という有名な小説を思い出した人もいる。ドラマの放映が始まった頃、オンライン上にはその本やそこに登場する4・3事件(米軍政下の済州島で起きた民衆蜂起。徹底した武力鎮圧により島民に多くの犠牲者が出た)に関する書き込みがあり、「ああ、やはり」と思った。
この小説は日本でも『順伊おばさん』というタイトルで翻訳書が出ており、オールド韓国文学ファンの中には読んだ人も多いだろう。訳者は『火山島』などの著作で知られる金石範。97歳の今も、現役作家として済州島についての物語を書き続けている。
『順伊(スニ)サムチョン』は韓国で1978年に単行本になった直後、出版停止になったことがあるという。斎藤真理子著『韓国文学の中心にあるもの』によれば、当時はタブーとなっていた4・3事件にふれたことで、著者である玄基榮 (ヒョン・ギヨン)はKCIA(中央情報部)に引っ張られて拷問もされたという。
ドラマの本筋ではないので、これに関しては稿を改めることにするが、「済州島を舞台にしたドラマ」といった時に、韓国人の中にはこうした現代史の事件を真っ先に想起する人もいる。そのことは日本でドラマを見る人たちも、知っておいたほうがいいと思っている。
『私たちのブルース』にも様々な理由で家族を失った人々が登場する。済州島の暮らしがどれほど厳しかったか、それを表現するタッチは、驚くほど粗い。そのザラザラとした質感は意図的なものだろう。その一方で、空も海もブルーの色は明るい、済州島ブルーが広がっている。
済州島を去った人と残った人
このドラマは済州島を舞台にしたオムニバス形式のドラマで、主な登場人物14人が主役を入れ替えながら、全20話をリレーしていく。中心となる物語は8つだが、「私たち」というタイトルにあるように、いずれも人と人の関係性が主語になっている。
たとえば第1話の「ハンスとウニ」は初恋の人との再会物語だ。二人は済州島にある高校の同級生だったが、卒業後にハンスはソウルの大学へ進学、両親を早く亡くしたウニは弟たちのために地元に残って働いた。
ドラマはそのハンスが務めている銀行の支店長として故郷に単身赴任するところから始まる。もうすぐ50歳という年齢。ウニは初恋の人との再会に胸を踊らせるのだが、ハンスはそれどころじゃない深刻な家庭問題を抱えていた。
ウニ役には映画『パラサイト』のお手伝いさん役などで知られる個性派女優イ・ジョンウン、ハンス役には往年の二枚目俳優チャ・スンウォン。いきなり大物登場なのだが、このチャ・スンウォンが長身を折り曲げて演じる、情けない男の役柄はなんともいえない。
ドラマはいずれの物語でも、現在と過去の回想シーンを織り交ぜながら進むのだが、ウニが回想する高校時代は愉快だ。
たとえば、ある日、子豚を抱えたウニが通学バスに乗り込むと、同じく麻袋一杯のゴマを抱えたハンスが乗っていた。二人とも家が貧しく修学旅行に行くためのお金がない。そこで家にあるものを、お金に変えようとしたのである。当然ながら同級生は二人をからかうのだが、ハンスはひるまない。自分を守り、ウニも守る。以来、ウニはハンスにぞっこんになってしまうのだ。
二人の年齢設定はもうすぐ50歳となっているから、高校時代といえば1990年代の初頭である。たしかに当時の済州島はまだ貧しかったと思う。火山島であることから農業に適した土地は少なく、70年代に始まったミカン栽培が軌道に乗るまでは、海の仕事に頼るしかなかった。今では済州島名産として名高い豚も、当時は今のように注目されていなかった。
今や幾つもの鮮魚店やカフェのオーナーとなり、むしろ人を援助する側になったウニにとっては、過去の貧困はすでに笑い話だが、ハンスにとってはそうでもない。妻と娘をアメリカにゴルフ留学させているハンスは借金まみれで、過去の郷愁に浸るような余裕は全くないのだ。済州島を出たハンスと済州島に残っていたウニ。二人の立場逆転物語は面白かった。
「ハンスが勝手すぎてムカつく」という感想には同意するが、本人もあれだけボロボロになったのだし許してあげようと、鈍感なチャ・スンウォンの顔を思い出すと……。うん、たしかにムカつくかな。
それにしてもだ、この物語に登場する男たちは揃いも揃って、なんでこんなに情けないのだろう。特にウニの同級生の中高年の皆様。若い世代の男たちは素敵なのに、これは作家の依怙贔屓じゃないかと思ってしまう。
「でも、済州島の男って昔からそうでしたよ。」
父親が済州島出身の友人(50代)は、子供の頃に会った親戚の人々のエピソードなども話してくれた。そして「たしかに親世代に比べたら、従兄弟たちは真面目かもしれない」とも言っていた。
プロフィール



 伊東順子
伊東順子
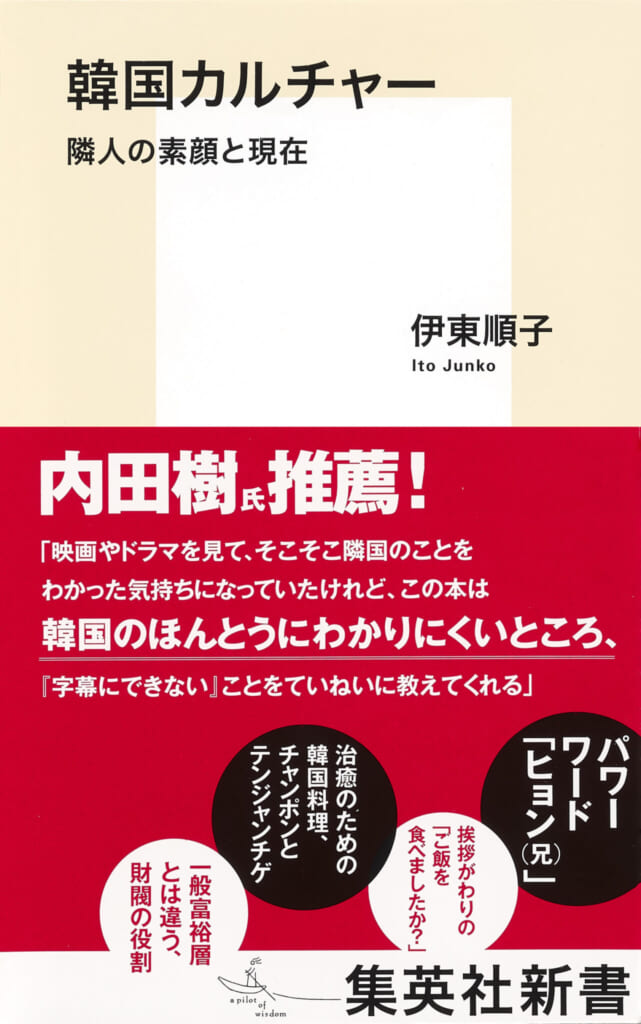












 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

