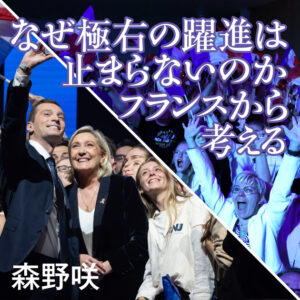分断と衝突を繰り返すアメリカ。今や国民の多くが「数年以内に内戦が起こる」との恐怖を抱いている。そうした時代の変化に伴い、民主主義と国民国家の在りかたに向き合ってきたアメリカ文学も、大きな分岐点を迎えている。 本連載ではアメリカ文学研究者・翻訳家の都甲幸治が、分断と衝突の時代において「アメリカ文学の新古典」になりうる作品と作家を紹介していく。
今回紹介するのはSF作家テッド・チャンの傑作短編「大いなる沈黙」「あなたの人生の物語」。
この宇宙に人類以外の知的生命体はいるのか。ある程度の知性を持ち合わせているというだけでなく、言語を複雑に操り、意思の疎通をし、神話や歴史を持つところまで到達したものが存在するのだろうか。これは科学における長年の問いである。もちろん、地球上にそうした生物は見当たらない。だからこそ、現代科学は宇宙に目を向ける。
プエルトリコのアレシボ天文台も、そのような探求のひとつの表れである。科学者たちは、直径約300メートルという巨大な電波望遠鏡で宇宙からのメッセージを受信しようと努めるだけでなく、人類はこうした存在だ、という情報を遠く宇宙空間に発信した。1974年にヘルクレス座の球状星団M13に向けて送信されたアレシボ・メッセージのことだ。そして、どこかに潜んでいるかもしれない知的生命体からの応答を待っている。
だが、本当にそうだろうか、と短篇「大いなる沈黙」(『息吹』所収)でテッド・チャンは問いかける。たとえば、アレシボ天文台に近い熱帯雨林に住むオウムたちが、実は人類に匹敵する知的生命体だったとしたらどうだろう。しかも、人類に滅ぼされないために、密かに彼ら独自の言語で語り合い、文化を形成し、口承という形で歴史を刻んできたのだとしたら。
これはそこまで突飛な仮定ではない。ヨウム(アフリカ西海岸の森林に住む大型のインコ)のアレックスの持つ知性を30年にわたって研究したアイリーン・M・ペパーバーグ博士の著書『アレックスと私』(ハヤカワ文庫)によれば、アレックスは100の単語を用いて人類とコミュニケーションでき、2歳児の感情と5歳児の知性を持っていたとある。ならば、人類の言語や歴史、文化までも理解し、独自の哲学的思考をめぐらすことさえ可能なオウムの存在を仮定してみてもいいではないか。
「大いなる沈黙」の語り手は一匹のオウムだ。プエルトリコの熱帯雨林に住む彼は、まさに我々こそが、広大な宇宙空間に人類が探している知的生命体である、と語る。だが、数千年にわたってともに暮らしてきたオウムと人類は、最近まで互いの知性に気づかなかった。それは、知性の形があまりにも異なっていたからだ、とオウムは言う。
それも無理はない、というのがオウムの考えだ。なぜならオウムのほうでも、自分たちとは振る舞いの違う人間に、まさか知性などあるはずがない、と最近まで信じてきたからだ。けれども、ペパーバーグ博士の努力によって、そうした無理解の壁は突き崩された。30年の研究を通して彼女は、アレックスが抽象的概念をきちんと把握しているということを、他の科学者に納得させることに成功したのである。「ペパーバーグは、アレックスがただたんに聞いた言葉をくり返しているだけでなく、自分がしゃべっている内容を理解しているのだと、科学者たちを納得させた」(385ページ)。
オウムと人類の共通点は何か。それは、耳で聞いた音声を正確に理解しながら、繰り返し発声できるという能力である。オウムも人類も、この能力を使って豊かな文化を築いてきた。そしてまた、口を使ってさまざまな音を形作ることには非常に強い喜びが伴う、とオウムは論じる。だからこそ、たとえばヒンドゥー教においては、真言を唱えることで世界を強化することができるという信仰が存在した。そしてまた、「オーム」という音節には、過去、現在、未来に存在するすべてが含まれると考えられている。
このままオウムと人類の相互理解が進んでいくのか。事態はそう楽観的ではない、とオウムは言う。アレシボ天文台からも分かるとおり、人類の目はいまだ宇宙のはるか彼方へと向けられている。そしてまた、人類は熱帯雨林を破壊し続けており、そのためにオウムたちはどんどん数を減らしている。このペースで行けば、おそらく近いうちに熱帯雨林は完全な沈黙に包まれてしまうだろう。まるで、この広い宇宙空間のように。
そのとき失われるのは、オウムたち自身だけではない。オウムたちの言語や儀式、伝統が、人類に解読されることなく消滅してしまう。いや、気づかれることなく消え去るとすれば、消滅したという事実すら消滅してしまうのだ。ここには、虐殺の徹底した形が存在する。そして、かつて地球上にオウムたちの文明があった、という事実も永久に消え去る。
この事態を前にして、オウムは人類に怒りに震えているのか。そうではない。自分たち以外の生命に対して限りなく不注意である人類に対し、オウムがかける言葉はアレックスと同じである。死の前の晩、アレックスはペパーバーグ博士に言った。「いい子でね、あいしてる」(392ページ)。そして、同じ言葉を、この語り手のオウムも人類にかける。これ以上、愛情のこもった、悲しい表現があるだろうか。
本作「大いなる沈黙」は、もともと短篇小説として書かれたのではない。ジェニファー・アローラとギレルモ・カルサディーラという2人の芸術家が共作したインスタレーションに添える言葉として、テッド・チャンが依頼されて執筆したものである。その作品では、アレシボ天文台の電波望遠鏡の映像と、その近くの熱帯雨林に住む、絶命寸前のオウムの映像が映し出された。そして、テッド・チャンの言葉は、「種と種のあいだを橋渡しする一種の通訳」(578ページ)の視点から語られたものとして構想されたのである。
このインスタレーションがどのようなものだったかは、YouTubeにアップされた映像でうかがい知ることができる。曲線と直線が組み合わさり、精巧に作られた金属製の巨大な電波望遠鏡と、枝の上で辺りをきょろきょろと見回しながらさえずるオウムたち。両者は極端なまでの対比を感じさせる。しかもこの話には後日談がある。2020年12月、ケーブルの切断によって、電波望遠鏡の上に吊るされていた900トンのプラットフォームが落下し、電波望遠鏡は轟音をたてて崩壊した。この様子もまた、YouTube上の映像で見ることができる。もう遠くを見るのはやめて、身近な存在にきちんと目を向ける時代なのではないか。この偶然の事故は、人類にそうした気づきを促しているように思える。
この短編からエコロジー的な意図を読み取るのはたやすい。出発点となったインスタレーション作品を見ても、それは伝わってくる。莫大な資金とテクノロジーを望遠鏡に費やすのならば、その予算のほんの一部でもオウムたちの保護に使うべきではないだろうか。なぜ人類はなぜそうした決断ができないのか。その問いが、作品を通じて雄弁に伝わってくる。
だが、本作から読み取れる含意は、そこにとどまらない。むしろ、こうした小さな声の響きは、アメリカ史を通じて続いてきたのではないか。知性を持ち、独自の歴史や言語を育んできたオウムたちの姿は、突然現れた白人たちに土地を奪われ、自分たちの言語や文化を消し去られた、数多くのネイティヴ・アメリカンの人々を思い起こさせる。
それだけではない。奴隷として連れてこられた黒人たちもまた、アフリカの言語や文化を一度は抹消された。そして現在まで、世界各地からの移民たちは、できるだけ自分たちの背景となる文化を捨て、白人文化に融合することで、アメリカ社会から人間として認められようとし続けてきた。
言い換えれば、アメリカ史おいて常に、中心となる白人たちの文化以外の、マイノリティの声や文化は抹消されてきたのだ。だがそれでも、か細いが力強い声として、マイノリティの文化が受け継がれてきたことに、現在注目が集まっている。ならばテッド・チャンの本作は、常に存在し続けてきたもう一つの声に光を当てていると言えるだろう。そして、アメリカ合衆国における文学の意義もまた、そうした声を掬い上げ、伝えることにある。
この作品を書いたテッド・チャンはどういう人物なのだろうか。彼は1967年にニューヨーク州ポート・ジェファーソンで生まれた。台湾出身の両親は二人とも外省人で、中華民国政府の移動に伴い、家族とともに台湾に渡った。そのあと両親はアメリカに移住し、そこでテッド・チャンが誕生したのである。彼は両親の方針で、英語中心で育った。そのため現在、中国語はほとんど話せず、中国系アメリカ人のコミュニティとの関わりもあまりない。
ブラウン大学でコンピュータ・サイエンスを学び、テクニカルライターとして長い間働いてきた。同時にSF作家を目指していた彼は、クラリオン・ワークショップでオクテイヴィア・バトラーに指導を受けたこともある。1989年には短篇「バビロンの塔」(『あなたの人生の物語』所収)を発表した。その後、極端に少ない作品数にもかかわらず、ネビュラ賞やヒューゴー賞、ローカス賞といったSFの賞を次々と受賞した。さらに、2024年には純文学の賞であるペン/マラマッド賞も受賞し、現在ではSF作家としてだけではない広範な評価を得ている。
テッド・チャンは、そのキャリアの非常に早い時期からSFの世界で高い評価を得てきた。だが、彼の作品が一般の読者にまで広く知られるようになったのは、短篇「あなたの人生の物語」がドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の映画『アライバル』(邦題『メッセージ』)の原作となった後ではないだろうか。エイリアンの搭乗した大量の宇宙船が突然、地球に現れるという内容でありながら、落ち着いた雰囲気の本作品は、映像も音楽も美しい。特に、オープニングとエンディングで流れるマックス・リヒターの瞑想的な曲「オン・ザ・ネイチャー・オブ・デイライト」に僕は心を奪われてしまった。
ある日突然、地球上に卵を縦に長くしたような形の巨大な宇宙船が複数、現れる。どうやらそれには宇宙人が乗っており、彼らは人類と何らかの交流を持ちたがっているらしい。急遽、言語学者が集められ、世界の様々な地点で彼らとのコミュニケーションが試みられる。胴体に脚が七本生えた、巨大なタコのような宇宙人はヘプタポッドと名づけられる。彼らは音声を発して人類に意思を伝えようとするが、発声器官の構造が異なっているため、彼らの発する音を人類はきちんと意味として受け止めることができない。
音声言語以外にも、彼らには書字言語がある。指先から炭のようなものを発してスクリーンに円形に描かれた彼らの文字は、細かい線が複雑に入り組んでいる。はたしてこれは音を表すのか、あるいは音とは関係なく、意味のみを表すのか。言語学者たちは、そうした基本的なことすら掴めない。けれども、彼らとの対話を繰り返しているうちに、徐々に彼らの書き言葉が読めるようになってくる。
彼らの文字が最初に読めなかった大きな理由は、思考法の違いにあった。人類は時間の中で一歩一歩ものを考えていく。だから、誰にとっても一瞬先は空白であり、最大限の自由を持って未来を選択していかなければならない。だが、ヘプタポッドたちはそうした思考法を取らない。まるで世界の因果関係をあらかじめ知っている全能の神のように、彼らはすべての時代のあらゆる出来事がどうなるかをあらかじめ掴んでいる。言い換えれば、どの瞬間も彼らの前には現在としてあるのだ。だからこそ、どのような内容も文字としては同時に描かれることになる。そして、主人公である言語学者もまた、ヘプタポッドの言語を学ぶことで、すべての時間を行き来できるようになる。
ヘプタポッドとの行き違いの果てに、中国は彼らとの戦争を決意する。彼らを止めるために、言語学者の主人公は、未来から得た電話番号を使って、中国の将軍に働きかける。言うなれば、彼女はヘプタポッドから得た知識を使って世界に平和をもたらすのだ。まるでそのことに満足したかのように、ヘプタポッドたちの宇宙船は突然、地球から去る。
映画版を見てから、原作である「あなたの人生の物語」を読むと、まるでテッド・チャンの短編が映画の種明かしであるように見えてくる。もちろんこれは誤解なのだが、文学の楽しみ方の一つだとは言えるだろう。まず、ヘプタポッドが地球に現れたとき、なぜ言語学者が連れてこられたのか。そのことについて、主人公はこう語る。「未知の言語を習得する唯一の方法はそれを母語とする相手と交流することであり、それはつまり、質問をしたり会話をしたりといったことをするという意味なの。それ抜きでは、どうにもならない。すなわち、エイリアンの言語を習得したければ、実践言語学の修練を受けている人間が――わたしでもいいし、ほかのだれかでもいいけど――エイリアンと話をしなくてはならないということ。録音物のみでは足りないの」(181ページ)。
言い換えれば、相互的なコミュニケーションの場に身を置かなければ、相手の言語を理解できるようには決してならないということだ。こうした認識は、語学習得において非常に有効なものだと思える。だが、なぜそうなのか。おそらく、録音や録画された教材だけでは、あらかじめ自分が持っている認識の枠組みから人間は出られない、というのがその答えなのだろう。しかし、同じ場にいて、手探りでなんとか交流する方法を探し続ける過程において、おそらく人間はそうした枠組みから知らず知らずのうちに外に出ることができる。それは相手も同じことだ。
ここまで考えてきて、おそらくテッド・チャンはこの作品において、さまざまな分断や誤解、コミュニケーションギャップを乗り越える方法について語っていることに気づく。もちろん、ヘプタポッドと人類というのは、その極端な例になる。だが、たとえば現代社会において、政治的な党派が違えばコミュニケーションが不可能なほどに分断は広がっている。あるいは、文化や歴史の違いによって、すんなりと理解できない人々が容易に悪魔視されるのが現代社会なのではないか。テッド・チャンは、そうした対立をいったん抽象化した上で、対話の場作りから始めてみようと、我々に呼びかけているように思える。
そのことを踏まえると、本作に登場する、逐次的な意識と同時的な意識という二つのあり方は、アルファベットで一音ずつ順番に記述される西洋世界と、絵文字が抽象化された漢字のように、瞬間的に概念が視覚に飛び込んでくる文字を用いる東アジアの世界の比喩になっているとも言えるのではないだろうか。
「大いなる沈黙」では、オウムの言葉にきちんと耳を傾けたのはペパーバーグ博士一人だった。しかもそれは、アレックスの死によって中途半端な形で終わってしまった。遅かれ早かれ、熱帯雨林のオウムたちは声を聞かれることなく、消え去ってしまうのだろう。だが、「あなたの人生の物語」では状況が違う。理解できない存在ときちんと向き合い、なんとかコミュニケーションしなければ、世界戦争が始まり、おそらく人類は消え去ってしまう。
そして、このSF的な設定は、現代において決して空想的なものではない。そのことを我々は、世界各地で頻発する戦いを見てよく知っている。だからこそ、テッド・チャンは現代において極めて重要な書き手なのだ。
(次回へ続く)
参考文献
テッド・チャン『あなたの人生の物語』浅倉久志他訳、ハヤカワ文庫、2003年
テッド・チャン『息吹』大森望訳、ハヤカワ文庫、2023年

分断と衝突を繰り返すアメリカ。今や国民の多くが「数年以内に内戦が起こる」との恐怖を抱いている。そうした時代の変化に伴い、民主主義と国民国家の在りかたに向き合ってきたアメリカ文学も、大きな分岐点を迎えている。 本連載ではアメリカ文学研究者・翻訳家の都甲幸治が、分断と衝突の時代において「アメリカ文学の新古典」になりうる作品と作家を紹介していく。
プロフィール

とこう こうじ
1969年、福岡県生まれ。翻訳家・アメリカ文学研究者、早稲田大学文学学術院教授。東京大学大学院総合文化研究科表象文化論専攻修士課程修了。翻訳家を経て、同大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻(北米)博士課程修了。著書に『教養としてのアメリカ短篇小説』(NHK出版)、『生き延びるための世界文学――21世紀の24冊』(新潮社)、『狂喜の読み屋』(共和国)、『「街小説」読みくらべ』(立東舎)、『世界文学の21世紀』(Pヴァイン)、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社)など、訳書にチャールズ・ブコウスキー『勝手に生きろ!』(河出文庫)、『郵便局』(光文社古典新訳文庫)、ドン・デリーロ『ホワイト・ノイズ』(水声社、共訳)ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(新潮社、共訳)など、共著に『ノーベル文学賞のすべて』(立東舎)、『引き裂かれた世界の文学案内――境界から響く声たち』(大修館書店)など。


 都甲幸治
都甲幸治









 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理