私が政界を離れてから、来年でちょうど30年になる。自民党を離党して新党さきがけを結成し、96年の総選挙当時は自民・社会・さきがけの連立政権で国務大臣・経済企画庁長官を務めていた。その後は、大学に勤務するかたわらさまざまなメディアを通じて発言を続けてきた。
折から今年は昭和100年、戦後80年の大きな節目の年となっている。
しかし、この記念すべき年に氾濫しているのは“劣化”の二文字である。経済の劣化、社会の劣化、科学技術の劣化、なかんずく行政の劣化と政治の劣化が叫ばれて久しい。このような劣化現象は、単に肌感覚のようなものではなく、具体的な経済指標やグラフで示されているから否定しようがない。
戦後日本経済の最盛期は80年代と言ってよいだろう。経済企画庁長官を5回も務め、戦後の経済運営の基軸となってきた宮澤喜一首相は私に「その頂点は1985年当時」と明言していた。要するにドル高是正の“プラザ合意”が日本経済劣化への折り返し点ということだろう。
長い眼で見れば、一国の盛衰、経済の盛衰は避けられないと言える。しかし、日本経済の最盛期を10年間としても、その短さは異例ではないか。全般的な
やはり、やるべきことをやらなかった。やるべきではないことをやった。今、この大きな転換点でそれをきちんと整理し解明する必要がある。
私は「平成の二大改革の失敗」が特に日本の衰弱、劣化を早めたと受け止めている。
二大改革とは、小選挙区制を導入した“政治改革”と無原則な省庁再編に逃げた“行政改革”のことを言っている。実は私は当初の段階でこの二大改革の真っ只中にいたので、その経過をよく知る一人と思っている。
30年を経て現行の選挙制度と省庁体制には多くの欠陥が指摘されて新たな大改革の必要性が議論されている。たとえば、小選挙区制は政治の世襲化を促進し、有為の人材が政界に出ることを困難にしているし、経済企画庁の廃止によって、中長期の経済の展望がおろそかにされている。
そんな視点から、令和の大改革の緊急な必要性を読者の皆さんと探ってみたいと思う。
特に、はびこる既得権益への挑戦を課題としていくつもりである。そのことを念頭に、現状の政治や経済に一言啓上していきたい。
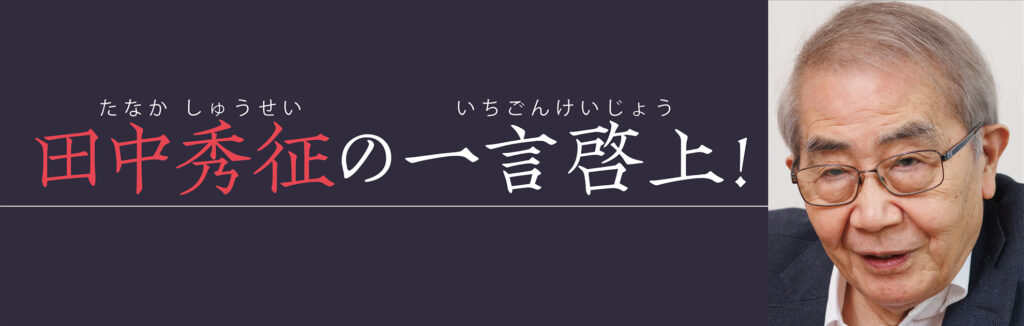
裏金、世襲、官僚機構の腐敗・暴走…政治と行政の劣化が止まらない。 この原因は1990年代に行われた「政治改革」と「省庁再編」にある。 その両方の改革を内部から見てきた元衆議院議員の田中秀征が、当時の舞台裏を解説しながら、何が間違っていたのかを斬りつつ、 今、何を為すべきなのかを提言していく。
プロフィール

(たなか しゅうせい)
1940年、長野県生まれ。東京大学文学部西洋史学科、北海道大学法学部卒業。83年に衆議院議員初当選。1993年6月に新党さきがけを結成し代表代行、細川護熙政権の首相特別補佐、第1次橋本龍太郎内閣で経済企画庁長官などを務める。福山大学経済学部教授を経て現在、客員教授、石橋湛山記念財団理事、「さきがけ塾」塾長。
著書に『石橋湛山を語る』(佐高信氏との共著、集英社新書)『自民党本流と保守本流』(講談社)『新装復刻 自民党解体論』『小選挙区制の弊害』(旬報社)『平成史への証言』(朝日新聞出版)など。


 田中秀征
田中秀征









 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


