福島第一原子力発電所事故から10年。テクノロジーと社会の関係を考察し続けてきた哲学研究者・戸谷洋志さんの『原子力の哲学』(集英社新書)が昨年暮れに刊行されました。
本書は、原子力(核兵器と原発)をめぐる7人の哲学者の考えを紹介し、それぞれの人と思想の関係を明らかにしながら、原子力の脅威にさらされた世界はどのようなもので、そうした世界に生きる人間はどのように存在しているのか、その根源を問うていく一冊です。
その著者とは『漂泊のアーレント 戦場のヨナス――ふたりの二〇世紀 ふたつの旅路』(慶應義塾大学出版会)の共著者でもある百木漠さんを、今回の対談相手にお迎えしました。
百木さんの専門であるハンナ・アーレントは原子力というものをどのように捉えていたのか。そして、二項対立をこえる対話の可能性などについて語り合いました。
※3月1日に本屋B&Bさんで開催された配信イベントを記事化したものです。


■全体主義と原子力
戸谷 昨年の12月、集英社新書から『原子力の哲学』という本を上梓しました。20世紀の哲学者たち7人が原子力の問題をどのように考え、それを自らのメインとなる思想とどういうふうに関連づけていたのかということを思想史的にたどった本です。
原子力が哲学の観点から語られるイメージはあまりないかもしれませんが、実はマルティン・ハイデガーやハンナ・アーレント、ジャック・デリダなど、第一級の哲学者たち、思想家たちが同時代の出来事としての原子力の問題と向き合い、さまざまな言葉を紡いでいます。それをたどっていくことで、福島第一原発事故から10年を経た私たちの現在地を照らし出すことができるのではないかと考えました。
また、7人の学者をただ並べるのではなく、誰が誰にどんな影響を与えたのか、あるいは後の世代がどういうふうに前の時代の哲学者を乗り越えようとしたのか、思想史的な系譜を描き出そうとも試みました。原子力と人間の関係を哲学的に問い直したいという人、また現代の哲学者たちが原子力について何を考えていたのか知りたいという人にも楽しんで読んでいただけるのではないかと思います。
今日は、ハンナ・アーレントの研究者である百木漠さんにお越しいただいています。まず、本書を一読されての率直な印象をお聞かせいただけますか。
百木 非常に面白く読みました。どの哲学者もそれぞれ個性があって面白いのですが、やはりテキストをいきなり読もうとするとなかなか難しい。それを戸谷さんが非常に分かりやすく、現代の問題と結びつけながら解説してくださっている。それぞれの原子力に関する思考と、哲学のエッセンスが理解できるという意味でも、非常に有用な本だと思いました。
1〜5章までは、ハイデガー、ヤスパース、アンダース、アーレント、ヨナスと、ドイツ系の哲学者が続きますね。ドイツでのナチズム台頭とホロコーストは、原子爆弾の投下と並んで20世紀を象徴する出来事だと思うのですが、それを経験している彼らはみな、戦後、原子力の問題と全体主義の問題を結びつけながらそれぞれの哲学を展開していますね。その点が非常に興味深かったです。
もちろん、全体主義の問題と原子力の問題とは性質が異なるのですが、20世紀という時代を生きた彼らにとっては、どうしてもその二つの問題を結びつけて考えざるを得ないところがあったのだと思います。終戦でナチズムの危機はひとまず去ったけれど、本質的な危機は去っていない。何か別の形で全体主義やホロコーストのような問題が回帰してきかねないという感覚が常にあったのではないでしょうか。
一方、6章・7章のデリダとデュピュイはフランス人で、年齢的にももう少し下ですね。彼らももちろん全体主義の問題は踏まえていると思いますが、もう少し我々に近い現代的な感覚を持っているように感じました。たとえば「破局」というものをどう考えるかというときに、全体主義よりはもっと21世紀につながる新たな危機を見据えているように思います。そういう20世紀の思想の流れが見えるのが、非常に面白いと思いました。
■私たちが守るべきものは何なのか
戸谷 原子力の問題と全体主義の問題は複雑に絡まり合っていますね。特にヤスパース、アーレント、アンダースにおいては、ここが一つのキーワードになってくる気がします。
ヤスパースは、全体主義に対抗するためには核兵器を手放せないという立場です。つまり、たしかに核兵器が使用されれば人類の生命が失われてしまうかもしれないけれど、核兵器を民主主義の国々が手放してしまったら、全体主義国家──彼は当時のソ連を念頭に置いているのですが──の世界支配を許すことになって、生命ではなく自由が失われてしまう。生命か自由かの二者択一を我々は迫られているというわけです。
そのヤスパースをはっきりと批判しているわけではないけれど、ちょうど反対のことを言っているように思えるのがアーレントです。核兵器の脅威とは生命を失うことではなく、自由を失うことである。つまり、最終戦争の脅威を突きつけられることによって、生命の存続が人類にとっての第一の優先事項になり、結果的に人々の公共世界における自由を掘り崩すことになると言っているんですね。
アンダースは、もっと明確にヤスパースを批判しています。核兵器があれば全体主義に陥らないというヤスパースの主張に反対し、国際安全保障が核兵器に依存しているこの事態そのものが一つの全体主義なんだと指摘する。そして、全体主義に抵抗するためにこそ核兵器を放棄すべきだという方向性に向かっていくのです。
このあたりの哲学者たちは、全体主義の脅威を経験しているからこそ、原子力と全体主義の絡まり合った関係性を避けて通れない論点としたのだろうと思います。一方デリダやデュピュイは、原子力について論じている時代そのものが、チェルノブイリ原発事故やなんですよね。そういう意味で、百木さんがおっしゃるとおり論点の移り変わりがあると思います。
百木 あと印象的だったのが、この本で扱われている哲学者たちが必ずしも核兵器や原発を正面から否定していたわけではないということです。もちろん、批判的な視点はみな持っているし、それぞれのやり方で深く哲学的に思考しているのですが、実は単純な「反原子力」ではないんですよね。
そのなかではアンダースが一番分かりやすく、今でいう反核・反原発に近い立場なのでしょうが、他の哲学者たちはみんなもっとひねった思考を展開していますね。ヤスパースは核兵器や原子力の危険性を指摘しつつも、単純にそれらを放棄することはできないと言っているし、ヨナスも「我々は未来世代への責任として、最悪の未来を常に想定しないといけない」ということを言いながら、原発の利用に関しては現実的な立場に立つ、と言っていますね。
核兵器や原発について否定的に述べる場合も、ただ大量破壊をもたらすから、放射能が怖いから、といった単純な回答ではありません。ハイデガーは核兵器よりも核の平和利用のほうがいつ危機を引き起こすか分からないと述べているし、アーレントは核兵器によって政治や公共性が失われることが大きな問題だと主張するし、デリダは核によって記憶やアーカイブが失われることの意味を考えている。それぞれの哲学者が何を守ろうとしているのか、未来世代なのか、公共性なのか、記憶なのか、人間らしさなのか。その違いが際立ってくるのが面白いなと思いました。
戸谷 僕も、この本を書くときには、「原発推進か脱原発か」という二項対立にはあまり飲み込まれないようにしたいと思っていました。単純に今ある原発、今ある核兵器をどうするのかというだけではなく、原子力という強烈なテクノロジーの光にかざすことで、私たちが生きている世界において何が大切なのか、人間はどうあるべきなのかが見えてくるのではないか。そこを問い直したいと思って書いたのがこの本なんです。
■「奇跡」と「出生」
戸谷 僕からも、百木さんにいくつかお聞きしたいと思います。
アーレントは『政治の約束』という著書の中で、核兵器の登場によって戦争のやり方が変わり、それによって人間の自由が破壊されている、この状況を変えられるのは「奇跡」だけだと書いていますね。そして、奇跡とは一人ひとり違った個性を持つ人間が誕生してくることによってもたらされるものだというのですが、アーレントはそれによって本当に状況を変えられると思っていたのでしょうか。具体的に言うなら、核廃絶のようなことが本当に可能だと思っていたのか、百木さんはどうお考えですか。
百木 そうですね。アーレントのいう「奇跡」とは、神の力のようなことではなく、誰も予想していなかったような新しいことを始められる人間の潜在力のことです。人間は、どんな状況にあってもその力を常に持っている。そしてそれは、この世界に常に新しい命が生まれてくることによって保証されているというのがアーレントの考えなのですね。著書『全体主義の起源』の最後でも、全体主義への対抗になるものとして、そうした始まりに希望が託されています。
アーレントの「出生」の概念については、私自身もいまだに掴み切れていないところがあるのですが、ヨナスはこれを非常に高く評価していました。人間の自由や可能性は、新しい命が常に生まれてくることによって保証されている、そのことを指摘したのはアーレントの慧眼だ、と書いています。同じドイツ生まれのユダヤ人でありながら、それぞれに展開した哲学や思想にはかなり対照的なものがある二人ですが、出生に大きな可能性を見出すという点では共通しています。
一つの仮説ですが、そこには宗教的な背景があるのではないかと思います。熱心なユダヤ教徒だったヨナスと、アウグスティヌスを通じてキリスト教神学を研究していたアーレント。新しい命が生まれてくること自体がこの世界に福音をもたらすものであり、そこに我々は希望を見出すべきなのだという宗教的な感覚に、二人の主張の源泉があるのではないかと考えています。この点については、戸谷さんとの共著『漂泊のアーレント 戦場のヨナス』で私なりの仮説を書きました。
では、アーレントは「人間が新しいことを始める力」によって本当に核の全廃が可能だと考えていたのかどうか。これはよく分かりません。ただ、「活動」がもたらす「始まり」に彼女が希望を見出そうとしていたのは確かだと思います。一方で、ユダヤ教やキリスト教のような宗教的背景を持たない日本の我々が、そのような思想をそのまま引き継げるのかどうかというのは、また別に考えてみなければならない問題です。
戸谷 なるほど。また、僕は本の中で、アーレントの哲学から導き出されてくる、原子力の脅威を乗り越えていくための処方箋の一つが、領域横断的な「市民としての対話」ではないか、と書きました。これについてもご意見をお聞かせいただけますか。
百木 戸谷さんが書かれているとおり、アーレントは領域横断的な対話を非常に重要だと考えていました。
たとえば科学者は、自分の職業的関心から無限に科学的な可能性を追求していく。それは科学者たちの宿命なのだけれど、ではそれによって開発された科学技術をどのように使うのか、あるいはその開発をどこまで進めて良いのかという点については、科学とは別の領域での判断が必要です。そして、それは市民の公共的な討議によって決められなくてはならない、というのがアーレントの考えでした。だからこそ、領域横断的な話し合いが重要であり、そこには、科学者も科学者としてではなく市民の一人として参加しなくてはならない。
科学技術の利用については科学者にすべてを任せるのでなく、ある種の人文学的な力をそこに関与させていく必要があるというのはデリダやデュピュイも論じていることですね。アーレントも基本的には同じ立場なのですが、ただし、そういう領域横断的な対話をやってみて、それによって合意に到達できるかどうかはやってみなければ分からない、というのがアーレントのスタンスだと思います。話し合えばうまくいく、というほど彼女は楽観的ではない。領域横断的な対話が重要なことは間違いないけれども、それで皆が納得する合意に到達できるかどうかは分からない。それでもやってみるしかない、と。
戸谷 アーレントの書くものって全体的に、「ここで甘い言葉を言ってくれたら話が締まるのに」というところで、すごく現実的な終わり方をするというところがありますよね(笑)。
■立場を超えた対話は成立するのか
戸谷 その「対話」についてなんですが、先日、『不安の時代の抵抗論』(花伝社)という本の著者である社会学者の田村あずみさんと対談させていただいたんです。彼女は福島第一原発事故後の脱原発デモのフィールドワークをされていて、あの運動はもともと社会運動をしていたような人たちではない、いわゆる「一般の人々」が盛り上がった、日本社会においてはすごく久しぶりの運動だったんじゃないか、とおっしゃっていたんですね。
彼女の話ですごく印象的だったのが、デモに参加していた人たちがいい意味で決して一枚岩ではなかったということ。原発に対しての思いも結構さまざまで、政府や東京電力への怒りに駆られて来たという人もいれば、未来世代に対する申し訳なさから参加したという人もいる。一つのイデオロギーで固まっているのでなく、生活者としてのさまざまな視点が交錯するような対話の場がそこにあったというんです。
後には「反自民」の色が強い官邸前デモが勢いを増す中で、そうした雑多な性格は徐々に薄れていったそうなのですが、3・11直後のデモの中にあった多様性というのは、領域横断的な対話の一つの可能性だったんじゃないか、と思いました。
百木 面白いですね。たしかにあの脱原発デモは最初のころはかなり雑多で、いわゆる左翼的な反原発派だけでなく、「美しい日本を守るために原発はやめるべきだ」と主張する保守派の人もいたし、普段はあまりデモや政治的行動に参加しないような人たちも結構いましたよね。
戸谷 一方で、結局それは脱原発派の中での領域横断であって、原発推進派と脱原発派の間では、なかなか対話が行われないというのが、僕の正直な実感でもあります。
以前、経済産業省の外郭団体である原子力発電環境整備機構(NUMO)が開いた「対話型説明会」の記録を読んだことがあります。官僚と専門家が全国各地で、地域住民に向けて放射性廃棄物の最終処分場の安全性について説明するのですが、やはり一方的に「教える」という構図になりがちで、双方向的な対話にはなっていないように感じました。もちろん、やらないよりはいいと思うんですが。
特に印象的だったのが、青森県の六ヶ所村での説明会で、参加した住民が「政府の言ってることはまず信用できない」「科学的なことだけ言われても信用できない」と言っていたことです。その気持ちはすごくよく分かる一方、だったら何を信用できるんだろうとも思える。このすごく深い断絶、分断みたいなものを乗り越えていくにはいったいどうしたらいいんだろうと思いました。僕自身、「哲学カフェ」という催しを通じて、テクノロジーに関する領域横断的な対話を実践しようとはしているのですが、原発のような現実の問題についてはなかなか歯が立たないところがあるんですよね。
そうした状況を、百木さんはどうお考えですか。3・11からのこの10年間、特に原発事故を受けて日本社会は少しは変わったのでしょうか。
百木 脱原発を主張する人たちと原発維持を主張する人たちの間で対話が持ちにくい、その間に深い断絶があるというのは、非常に大きな問題ですよね。
一口に原発維持派といっても、そこにはいろんな立場があるはずです。原子力技術は人類の叡智の一つなのだから開発を続けるべきだという人もいれば、日本の国家戦略のために核兵器を作る技術的可能性を残しておくべきだという人もいれば、将来的には脱原発が望ましいけれども現実的にすぐには無理だろうからとりあえずは原発存続という立場の人もいるでしょう。
原発に賛成か反対かという二項対立にしてしまうと、その辺りの違いが見えにくくなってしまいます。例えば、穏健な「ひとまずは原発継続派」の人などは、「脱原発派」の人との対話の可能性はもっとあるはずです。でも、そこがなかなか交わりにくい。
2010年代の前半は3・11の記憶やショックが強かったこともあってか、多少はそうした領域横断的な対話の試みがあったと思うんです。しかし、2010年代後半は、安保法制問題や森友加計学園問題など、安倍政権をめぐる政治問題が多すぎて、原発をめぐる議論も「反安倍か親安倍か」という二項対立の図式に回収されてしまった感があります。対話可能性が薄れて、「やっぱり選挙で数を取るしかない」というポピュリズム的な論調が強まってしまったのは残念なことだったと思います。そこを、もうちょっと別のやり方で切り開いていけないだろうか、という思いはありますね。
アーレントが『政治の約束』のなかでソクラテスについて書いています。ソクラテスは古代ポリスの中で、周囲の人たちにしょっちゅういろんな議論をふっかけていたんですよね。結果として、ソクラテスを通じていろんな意見をもつ人たちが集い、酒を酌み交わしあいながらの議論が起こっていた。アーレントは、それを高く評価しているんです。
現代にも、そうした「対話の媒介」になる人や場所がもうちょっと生まれてくるといいんじゃないかなと思います。SNS上の議論はどうしても単純な二項対立に陥りがちですが、そうではない形の議論の場をどうやったら作り出せるか。そのときに、ソクラテスのような人が「媒介者」になることによって、異なる立場の人たちが意見を交換しあう場を作っていくことができないか。それによって、政治と哲学の交わる場をもっと作っていけないか、と。
■原子力の脅威とは何か
戸谷 質問にも少しお答えしていきたいと思います。
Q ヨナスは「を意識することが重要である」と言いながら、他方で「原発については私は完全に実用主義的な立場である」とも言っています。これは果たして一貫していると言えるのでしょうか。
戸谷 ヨナスは第二次世界大戦終結の直後、解放軍の一員としてドイツに駐屯していたときに、ヤスパースと会ってこんな話をしているんです。「私は日本に原爆が落とされたのはもちろん痛ましいことだと思っているが、しかし原子力の平和的利用については大変な希望を抱いている」。他の発言や書いているものからも、ヨナスは原発に対してはかなり楽観的だったと言わざるを得ないでしょう。ちなみに、ヤスパースも原発にはかなり楽観的な立場だったので、「確かにそうだ」というような返事をして、会話は終わっています。
しかし、一方でヨナスは「原発は人類に恩恵をもたらすけれど、大きな脅威ももたらすかもしれないのであって、その運用についてはきわめて慎重でなければならない」という主張もしている。彼の考える原子力の脅威とは、単純に原発事故で大きな被害が出るということではなく、原子力によって社会が豊かになる一方で、気候変動など予期せぬ形の「副作用」が起きてくることだったのだと思います。
つまり、今見えている危険によってではなく、誰もまだ気づいていない副作用が積もり積もって、いつか予想しない形で噴出して取り返しのつかない破局を呼ぶかもしれない。だから原発そのものよりも、それが組み込まれている科学技術文明全体の構造に目を光らせるべきだとヨナスは考えていたのではないかと思います。
百木 たしかに、未来世代への責任をと言っているわりには、それと対照的に、現代の我々が考えていることにかなり近いことを言っているなと感じたのがアンダースでした。
彼の言う「プロメテウス的落差」──人間が自ら製造するものとそれに対する想像力との間に落差がありすぎるために、人間は原子力に対してまともに思考することすらできないという問題──などは、今の我々にもまさに当てはまる話ではないでしょうか。原発の稼働と事故による破局は隣り合わせなのに、なぜか我々はその危機に不感症になってしまっているというギャップの問題ですね。アンダースはこれを「アポカリプス不感症」とも呼んでいます。3・11の直後は、原発をめぐる議論も盛り上がりを見せていましたが、それも徐々に下火になってしまった。アンダースの指摘は正しかったんじゃないかと感じさせられます。
彼は、核兵器や原発に対して一貫してストレートに反対の立場を表明しています。しかし、今となっては、実は彼が言っていたことこそが21世紀を生きる我々の感覚に最も近かったんじゃないか。今の日本でアンダースの著作はもっと読み直されていいはずだと思っています。
戸谷 ヨナスとアンダースとでは、想像力についての考え方に大きな違いがあるんですよね。
ヨナスは、すでに危険だと分かっているものは、避けることができるからもはや危険ではない。むしろ、今安全だと思われているものに対して想像力を働かせて、そこに隠れている危険性を感じ取ることが必要だと言っています。だから、原発のようにすでに一定のリスクが明らかになっているテクノロジーについては、楽観的だったのかもしれません。
アンダースの場合は逆で、私たちが危険だと分かったつもりになっているものに対して、「本当の危険性を分かっていない」と考えるわけです。つまり、原爆は危険だとみな言うけれど、それによってもたらされる破壊の実像を我々は想像できない、そのことのほうが本当の意味で危険なんだ。だから、原子力に対して想像力を拡大していくことが重要だと言っているんです。
百木 なるほど。そう説明されるとどちらも分かるところがありますね。すでに危険だと分かっているものと、まだ危険と思われていないものと、そのどちらに本当の危機を感じるかという点に、二人の思考の違いがあるわけですね。
■核の影響は、領域も時間も超えて広がる
Q 南太平洋での核実験による被曝など、「グローバルヒバクシャ」への視点はどうなっているのでしょうか。
百木 ヒバクシャというのは、広島や長崎で原爆に遭った人だけではなく、核実験や原発事故で被曝した人、原子炉や核廃棄場で働いていて被曝した人、ウランの採掘に関わる労働者なども含めてヒバクシャなんだということですよね。
これについてもアンダースが、「原子力の技術に関しては、実験と本番の区別がない」と言っていたことを、戸谷さんの著書を通して知りました。核の開発自体が常に何らかの被害を生み出すのであって、「あくまで実験」という言い訳は原子力技術についてはあり得ないというわけです。
これも、まったくそのとおりだなと。第五福竜丸事件がその典型ですが、たとえ核実験を周囲に誰も住んでいない砂漠のような場所でやったとしても、放射性物質は何万年も残り続ける。ウラン採掘現場の労働者の被害も深刻です。そうした場面での被曝が、何らかの形で未来世代に影響や被害を及ぼしてくる可能性もありますよね。だから、原子力の問題はグローバルな視点と未来への視点の両方で考える必要があるのだと思います。
戸谷 アンダースが言っているのはまず、核実験の影響は空間的な限界を超えていくということ。国とか共同体とかの領域を超えて拡散していってしまうということですよね。たとえばチェルノブイリ原発事故でも、当時のソ連だけではなくヨーロッパ全土、さらには地球上全体に放射性物質がまき散らされたわけです。
また時間的にもそうで、放射性廃棄物の放射線量が自然由来の放射線レベルに下がるまでには10万年かかるといわれています。だから、放射性廃棄物の最終処分場って、10万年間の貯蔵に耐えるように設計しないといけないといわれてるんですよね。仮に、ある国が今ここに放射性廃棄物を埋めたとしたら、放射能の影響はその国が滅びた後の次の国の人々にまで及ぶ可能性があるわけです。
そんなふうに、空間的にも時間的にも、核というのは人間の処理能力を超えたテクノロジーなんだとアンダースは言っているんです。
百木 ヨナスの言う「未来世代への責任」の話とも関わってきますよね。ヒバクシャについてはグローバルに、空間的な領域を超えて考えなくてはいけないと同時に、何万年後の他者もまたヒバクシャに含めて考えないといけない。こうした問題は人間の処理能力や思考能力を完全に超えているわけです。このように「人間の身の丈」を完全に超えているということが、原子力問題の一番の根幹ではないでしょうか。■
執筆/仲藤里美
撮影/三浦咲恵(戸谷洋志さん写真)
(プロフィール)
戸谷洋志(とや ひろし)
1988年東京都生まれ。哲学研究者、大阪大学特任助教。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現代ドイツ思想を軸に据え、テクノロジーと社会の関係を研究。著書に『Jポップで考える哲学――自分を問い直すための15曲』『ハンス・ヨナスを読む』、共著に『僕らの哲学的対話 棋士と哲学者』、『漂泊のアーレント 戦場のヨナス――ふたりの二〇世紀 ふたつの旅路』がある。
百木 漠(ももき・ばく)
1982 年生まれ。社会思想史専攻。現在、立命館大学専門研究員。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。単著に『アーレントのマルクス――労働と全体主義』(人文書院)、共著に『漂泊のアーレント 戦場のヨナス』(戸谷洋志との共著、慶應義塾大学出版会)、『アーレント読本』(日本アーレント研究会編、法政大学出版局)、『生きる場からの哲学入門』(大阪哲学学校編、新泉社)などがある。
プロフィール

戸谷洋志(とや ひろし)
1988年東京都生まれ。哲学研究者、大阪大学特任助教。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現代ドイツ思想を軸に据え、テクノロジーと社会の関係を研究。著書に『Jポップで考える哲学――自分を問い直すための15曲』『ハンス・ヨナスを読む』、共著に『僕らの哲学的対話 棋士と哲学者』、『漂泊のアーレント 戦場のヨナス――ふたりの二〇世紀 ふたつの旅路』がある。
百木 漠(ももき ばく)
1982 年生まれ。社会思想史専攻。現在、立命館大学専門研究員。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。単著に『アーレントのマルクス――労働と全体主義』(人文書院)、共著に『漂泊のアーレント 戦場のヨナス』(戸谷洋志との共著、慶應義塾大学出版会)、『アーレント読本』(日本アーレント研究会編、法政大学出版局)、『生きる場からの哲学入門』(大阪哲学学校編、新泉社)などがある。


 戸谷洋志×百木漠
戸谷洋志×百木漠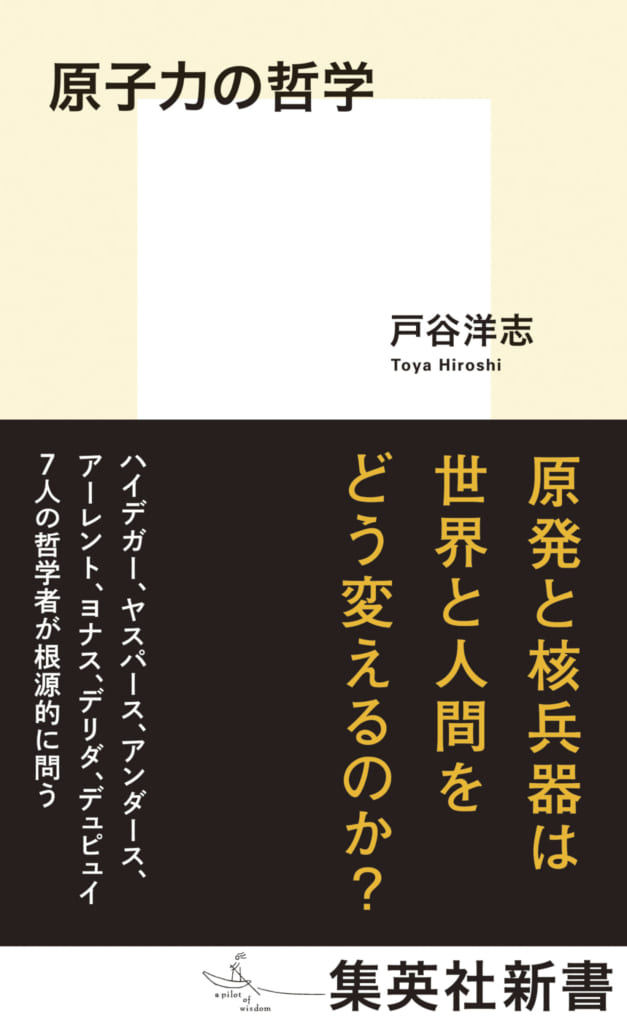










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


