わたしたちの社会はテクノロジーの発達によってもたらされた、さまざまな深刻な問題を抱えています。
気候変動、放射性廃棄物の処理、生殖細胞へのゲノム編集……。
現在世代は未来世代に対しての倫理的な責任をどのように考え、どのように実践したらよいのでしょうか。
それらの問いを考えるための一冊が、戸谷洋志さんの新刊『未来倫理』です。
本書の刊行を記念して、政治学者の藤井達夫さんをお迎えしました。
藤井さんは『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』において、世界中をポピュリズムが席捲する中での民主主義のあり方を根源的に考察しています。
未来世代に影響を及ぼす問題の解決を考えるときに、合意形成という点ではどうしても民主主義の問題に突き当たらざるを得ないのではないでしょうか。
最新の倫理学と政治学の知見をぶつけ合う中から見えてくる、「未来世代と民主主義のゆくえ」は――-。


「現代世代」の「未来世代」に対する責任をどう考えるか
藤井 戸谷先生の新刊『未来倫理』を読ませていただきました。私たち「現代世代」が、これから生まれてくる「未来世代」に対して負う責任をどう考えたらよいのかというのは、倫理学のみならず政治学においても今、非常に注目されているテーマですね。その中で争点となっている問題がほぼ網羅され、研究者ではない一般の人たちにも届く形でまとめられていて、非常に意義のある本だと思いました。
中でも、未来倫理に関する6つの理論をまとめた第三章は読み応えがありました。「功利主義」「責任原理」など、どれもすでに濃密な議論の蓄積があり、一つずつ語るだけでも1冊本ができてしまうようなテーマです。それをすべて具体的な例を挙げて解説されるというのは、研究者としてなかなか勇気が必要だったのではないでしょうか。
戸谷 ありがとうございます。私のもともとの専門は責任原理を唱えたハンス・ヨナスで、契約説や功利主義は研究対象ではありませんでした。この本を書くために自分なりに勉強してまとめたのですが、それぞれの分野の研究者からはいろいろと異論があるだろうことは予測しています。
未来倫理に関する議論を見ていて、契約説の研究者はあらゆる問題を契約説で解決しようとするし、功利主義が専門の人はあらゆる問題を功利主義で考えようとするという傾向を感じていました。もちろん、どの理論も普遍性を求めはするのですが、同じ世代間正義の話でも何について語るのか──放射性廃棄物についてなのか、ゲノム編集についてなのかによって、人々が納得しやすい理論は違ってくるのではないかと思うのです。
さらに、共同体主義や討議倫理といった、一般読者にはあまり知られていない理論からの未来に対する考え方も紹介したいという思いがありました。そこであえて批判を受ける覚悟で、思い切ってこの形にしたわけです。
藤井 現代の民主主義は、主義主張や価値観の多元性を前提にしています。だから、みんなで議論することが重要になるわけです。そうした立場からすると、戸谷先生の手法は有益だと言えると思います。つまり、さまざまな議論があって、考え方の違いによって論争も起きているということを出発点に、どの理論が正しいかではなく、ある理論からすると物事はどのように問題化されるのかに注目するんですね。
「この問題についてはこの理論でこう答えられますよ」と、具体的なケースや状況に応じたメリットやデメリットを説明してくれている戸谷先生の本は、非常に実践的だと思いました。たしかに、各分野の専門家からはいろいろと意見が出るかもしれませんが、そもそも書いている目的が違うということなんだと思います。
ポスト・トゥルースの時代と「想像力の拡大」
藤井 その上でお聞きしたいのはまず『未来倫理』の中で述べられている「想像力の拡大」についてです。未来倫理について考えるためには未来がどのようであるかを分かっていなければならない。しかし未来を科学的に予見することはできないから、想像力を意図的に拡大して、未来の姿を予測する必要があるというお話でした。
これ自体は非常によく分かりますし、たしかに必要なことだろうと思います。ただその一方で、「ポスト・トゥルース」という時代状況を考えると、「想像力の拡大」をそれほど楽観視していいのだろうかという疑問もわいてくるのです。
「ポスト・トゥルース」とは、世論形成や政策決定において科学にもとづく客観的な事実よりも個人の信念や情緒などが影響力を持つ状況を意味します。トランプ前米大統領はポスト・トゥルースを代表する人物だと言えるでしょうが、彼への支持の広がりを前提とすると、おっしゃるような「想像力の拡大」がむしろ、未来倫理の否定に向かうこともあるのではないでしょうか。たとえば気候変動についても、あれは腹黒い科学者の嘘であり、そんなものは起こりっこないという言説がありますね。実際、トランプ政権時代のアメリカはパリ協定を離脱しました。そこから考えると「気候変動は起こらないんだから、未来世代のことなんて考えなくていい」ということになってしまう可能性もあるのではないかと思うのです。
つまり、想像力の拡大が、科学のポピュリズム化をもたらすかもしれない。この危険性についてはどうお考えですか。
戸谷 おっしゃるとおり、そうした時代状況を前提にしなくてはならないということは私も承知しています。その上でお答えすると、本の中で書いた「未来を予測する上では、科学的な実証性は捨てて想像力に頼るべきだ」というのは、たしかに先鋭的な主張かもしれません。しかし、放射性廃棄物の最終処分場建設、あるいはゲノム編集のような、配慮しなければならない未来が100年先、1000年先にまで及ぶケースでは、やはり科学的な予測には限界があるだろうと思うのです。
そして、未来を「配慮」する際には、そのテクノロジーが科学的にどのように環境を変化させるかだけでなく、人々がそれをどう使うかということも重要になります。しかし、それは科学的にはなかなか検証できません。たとえば放射性廃棄物の最終処分場なら、保管の安全性は科学的に検証できても、その廃棄物が地元の共同体にとってどういう意味を持つのか、社会的にどんな影響があるのかは科学では分からない。こうしたレベルでの未来予測に関しては、やはり想像力に頼らざるを得ないのではないかと思います。
もちろん、科学的なエビデンスは重要ですから、両面が必要です。ただ、私があえて想像力の面を強調して書いたのは、日本の科学技術に関する公共政策の中で、こうした想像力をめぐる議論が著しく欠如しているのではないかと感じるからです。最終処分場建設についての住民説明会などでも、専門家からの説明は「いかに安全か」に終始していて、住民の人生が処分場建設によってどう変わっていくかに対する配慮がないように思えます。
たとえ不完全であっても、住民とともに共同体の未来を一緒に考えていく、想像していく。そうした制度を実装していかないと、長期の未来に及ぶ公共政策を国民の理解を得ながら十分に行うことはできないのではないかと思います。
藤井 科学的な予見性に限界があるというのはそのとおりですね。特に、ゲノム編集のようなバイオテクノロジーが社会にもたらす影響の予測はほとんどできていないし、気候変動についてもこの先どんなことが起こるのか正確には分かっていない。もちろん、何かが起きたときに損害を補償するための公的な制度もありません。
テクノロジーが人々の生活や共同体のあり方に及ぼす影響は科学的に説明不可能だというのは、おっしゃるとおりだと思います。科学では十分に分からないこと、説明できないことがあるからこそ、科学的な専門知と民主主義的な決定プロセスとをどう組み合わせていくかが重要になると考えています。
未来世代を、正しく「代表」するということ
藤井 もう一つお聞きしたいのが「代表」についての考え方です。民主主義に関する議論では「代表」という制度がかなり重視されます。そして未来倫理を考える場合でも、「代表」を想定しなければ、未来世代の利害関心や意思を政策決定プロセスに組み込むことはできないだろうと思います。
そうすると、代表とは何なのか、未来世代を誰が正当に代表しうるのかという議論が出てきますね。この問題については本書ではそれほど言及されていなかったと思うのですが、いかがお考えでしょう。
戸谷 現代世代が未来世代を配慮して意思決定をする場合には、未来世代の利害を予見して代弁するという形を取るしかないでしょう。そのときには、当然ながら「本当に正しく代弁できているか」についてのチェックがなされる必要があります。でなければ、それはむしろ現代世代の利害だけに基づいた意思決定でしかなくなってしまうからです。
ところが、現在世代と未来世代との間にある時間的な構造が、その「チェック」を不可能にします。たとえば現在世代において「生殖細胞のゲノム編集によって生まれる子どもは大きな苦痛を被るだろう、だからゲノム編集はすべきではない」という主張がなされ、ゲノム編集が行われなかったとします。しかしそうすると、ゲノム編集によって生まれる子どもは実際にはこの世界に存在しないことになる。結果、その子たちが本当に苦痛を被るかどうかは誰にも分からない、現代世代による「代弁」が正しかったかどうかを判定する基準そのものがなく、チェックのしようがないという状態が生じ得るわけです。
そう考えると、現代世代が代弁している内容の正当性をいかに担保するのかというのは非常に難しい、なかなか答えの出ない問題だと思います。ただ、その中でも一定の指針をお示しすると、私の専門であるハンス・ヨナスが「恐怖に基づく発見術」ということを言っています。これは、未来を予測したときにあり得るさまざまな可能性の中で、最悪のものを回避できるように未来世代への配慮をすべきだという主張です。
人間が何を幸福だと思うのか、何を善とするのかは、その文化や社会によって変わる。けれど、何が最悪なのか、何がもっとも避けるべき事態なのかについては、時代や文化を超えて一定のコンセンサスがあるのではないか。従って、テクノロジーがもたらす「最悪の事態」を探しだし、それを回避するような形で意思決定をしていくべきではないかというのがヨナスの主張です。
私自身は「何が最悪か」というのも時代によって変わると思うので、ヨナスの手法によって常に正しく未来世代を代弁できるとは考えていません。ただ、少なくとも「未来世代の幸福」を目指すよりも「最悪を回避する」ほうが、望ましい代表のあり方といえるのではないかと思います。
藤井 ありがとうございます。いずれにせよ、「未来世代の代表者」抜きで、現在の人間がさまざまなことを決定していくことについてはやはり問題があるでしょうね。未来倫理を考える上では、「代表」という制度を活用しながら、現代世代と、未来世代の「代表」との議論の中で合意を達成していく、そうした考え方が重要になってくるのだと思います。
構成/仲藤里美
※[後編]につづく
プロフィール

戸谷洋志(とや ひろし)
1988年東京都生まれ。哲学研究者、関西外国語大学准教授。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現代ドイツ思想を中心にしながら、テクノロジーと社会の関係を研究。著書に『ハンス・ヨナスを読む』『原子力の哲学』『ハンス・ヨナス 未来への責任』『スマートな悪』、共著に『僕らの哲学的対話 棋士と哲学者』『漂泊のアーレント 戦場のヨナス』など。新刊に『未来倫理』がある。
藤井達夫(ふじい たつお)
1973年岐阜県生まれ。西洋政治思想、現代政治理論、東京医科歯科大学教授。早稲田大学大学院政治学研究科政治学専攻博士後期課程退学(単位取得)。近年研究の関心は、現代民主主義理論。 単著に『〈平成〉の正体――なぜこの社会は機能不全に陥ったのか』(イースト新書)、共著に『公共性の政治理論』(ナカニシヤ出版)、『日本が壊れる前に-「貧困」の現場から見えるネオリベの構造』(亜紀書房)など。新刊に『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』がある。


 戸谷洋志×藤井達夫
戸谷洋志×藤井達夫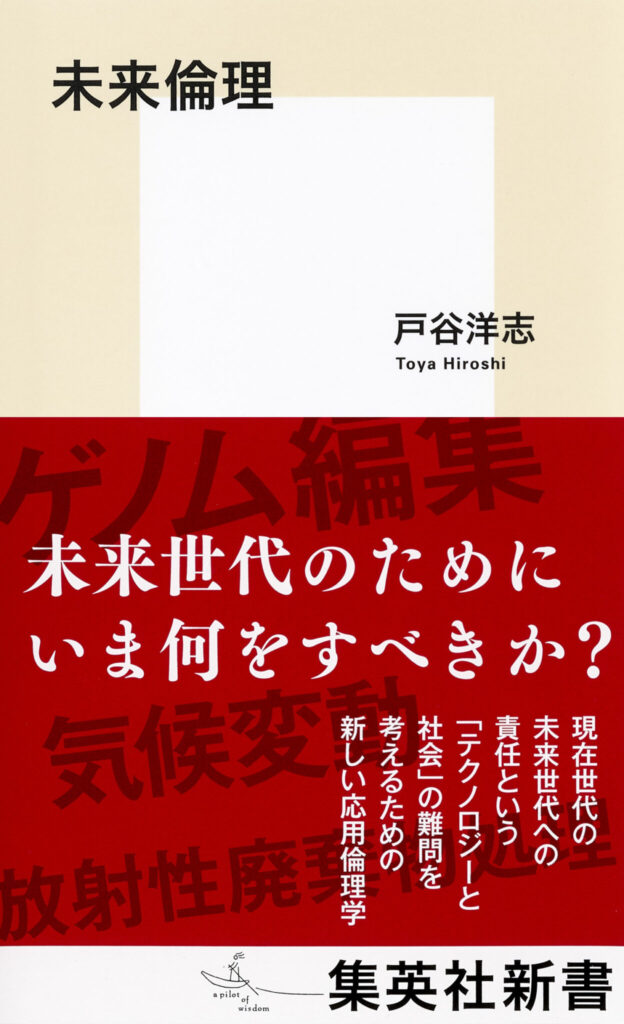










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


