2020年6月に刊行され話題を呼んでいる新書『ことばの危機』(東京大学文学部広報委員会・編)。前年の10月に行われたシンポジウムを基にした同書は、昨今の大学入試改革・学習指導要領改訂における一連の「国語」改革に対して、その問題点に鋭く切り込んでいる。
同書はどのような問題意識のもとで生まれた、いかなる書籍なのか。著者の一人である、英文学者の阿部公彦氏(第一章執筆担当)にご紹介いただいた。
———————————————————————————————————–
東大の中でもおとなしい文学部。力をふるって何かをする学部ではないと見られており、「何を考えているかわからない」と言われることもしばしば。理系とくらべたら予算規模は「ゼロの数が2つか3つ違う」とされ、学内政治の嵐とも無縁。教員は日々、キャンパスの美しい木々や岩や水を嘆賞しています。
しかし、今回ばかりは黙っていられませんでした。すでに社会に蔓延しつつあった「ことば」に対する誤解、無理解、鈍感さ。これがいよいよ教育の現場におよび始めたのです。
「これは、ほんとうにやばい」
発端は学習指導要領改訂に伴う「論理国語」なる科目の誕生でした。あらためて確認してみると、「え?」と驚くべきことが進行している。「論理」「実用」「読解力」といったことばが歪んだ意味で使われ、奇妙な教育政策が進みつつあったのです。
新書『ことばの危機』は、ふだんはおとなしい文学部が、哲学や文学、語学の知見を生かしつつ、少々声を大きくして語ったシンポジウムの内容を、改めて書籍としてまとめた一冊です。
以下、この本を一緒につくってくださった先生方について紹介しながら、それぞれがご担当された各章の読みどころについて、簡単に解説していきたいと思います。
まず、トップバッターは安藤宏さん。新書では「はじめに」と「おわりに」を担当されました。

安藤宏氏(写真提供:東京大学文学部広報委員会)
たまたま2019年の段階で広報委員長でいらした安藤さん。国文学で近代文学の研究を一手に引き受けておられると言ってもいいくらい、重要な立場でいらっしゃる方ですが、その安藤さんが柱になってシンポジウムをやろうと声を掛けられました。それによって実現したのが、2019年10月の文学部シンポジウム『ことばの危機』です。
ちなみに、シンポジウムは2時間ほどでしたので、今回の本にするにあたって原稿をかなり書き換えて、新しくつくり直したと考えて良いでしょう。
そんな安藤さんの一部のご著書を挙げておきます。主著は、非常に重厚な『近代小説の表現機構』(岩波書店)。ただし、まだ安藤さんの本を読んだことがない方は、ちくま新書の『太宰治 弱さを演じるということ』や、岩波新書の『「私」をつくる――近代小説の試み』あたりから入るのが良いかなと思います。前者は太宰の自意識に関して、当時かなり新しい知見をもたらしたことで有名です。そして後者が安藤さんの最新著ですが、「私小説」という一種のモードが生まれるに至るまでの日本近代文学の流れを、外側から解説・分析したという本ですね。
改めて、話を「国語」問題に戻しましょう。ご存じのように、その国語改革の問題が色々と取り沙汰されるようになって、最終的に一番騒ぎになったのは「記述式」でした。現在のセンター試験に代わって新・大学入試共通テストが導入されることになりましたが、そこで記述式を取り入れるかどうかが議論の的になった。結局、採点の公平性を担保できないという理由で中止になりましたけども、実はその一歩前に「国語の科目の再編成」などの問題があったんですね。
まずは安藤さんご執筆の「はじめに」より引用をしながら、重要な論点について簡単に整理しておきます。
“「新テスト」に関しては、(中略)より根本的な問題は、「実用」と「情報処理」に力点が置かれるあまり、本質的な思考力、つまり言葉を通して世界の成り立ちを考えていく「人文知」がなおざりにされてしまう点にこそある。”
高等学校「国語」の「新学習指導要領」。その内容は「新テスト」の趣旨とまさに連動するもので、「実学」重視の論理が前面に打ち出されています。
『ことばの危機』では、「実用」を重視する新・共通テストのモデル問題として、平成29年度に公開されたいくつかの設問例を巻末資料として収録しています。行政関連の文章や生徒会規則といった「実用的な」文章を読ませたうえで設問に答えさせる内容で、従来のセンター試験で出題された評論文や小説の読解問題と大きく異なるのは一目瞭然です。
さらに、こうした「実用」重視の方向性は、学習指導要領改訂における「国語」の科目編成にも絡んでいました。
“ポイントは新たに設定された科目編成にあるといってよいでしょう。単純化して言うと、従来の「国語総合」(高校一年)が「現代の国語」と「言語文化」に、「現代文」(高校二・三年)が「論理国語」と「文学国語」に分かれることになったわけです。”
“その区分けの要点は、「現代の国語」「論理国語」では「実用的な文章」「論理的な文章」を扱い、「言語文化」「文学国語」では「文学的な文章」を扱う、とされている点にあります。”
このような変化を受けて、問題をやや単純化して「論理国語と文学国語を分けるのはいかがなものか」であるとか、あるいは「国語の時間に文学が教えられなくなる。これは文学の危機だ!」という議論になりがちです。しかし、実はもうちょっと深い問題があるのではないか。安藤さんはそこを鋭く指摘されています。
“おそらく新指導要領の一番の問題点は、世に存在する文章を「実用的な文章」「論理的な文章」「文学的な文章」の三つに区分けできるという前提に立ち、「実用」「論理」をセットにして「文学」と区別している点にあるのではないでしょうか。”
以下は、2019年の8月に、日本学術会議で開かれたシンポジウムの中で安藤さんが発せられた問いです。
“行政が「論理的な文章」と「文学的な文章」の線引きなど、できるんですか?”
これは非常に重要な問いかけではないでしょうか。そもそも「論理的な文章」が何を指すのかが、よく考えるとわからないという問題もありますが、もっと別のレベルで、そもそも文学をきっちりと枠にはめこめるのか、という話があるわけです。もともと文学というのは、わけのわからないところからムニュムニュ出てくるもので、明確にその領域を確定するのが難しい表現形式なのではないか。そのようなことは、恐らく多くの方が感じていると思うんですね。
もちろん現実問題としては、本屋さんに行けば小説のコーナー、実用書のコーナーという仕方でジャンル別に区分けされています。しかし、あれはあくまで便宜的なもので、それを安易に「国語」の中に持ち込んだりしたら、その便宜的な区分けに過ぎないものが変に固定化されてしまうのではないか。
そういう問いを立ててくださった安藤さんが、今回も中心となってこのシンポジウムを企画されたということです。
プロフィール

1966年神奈川県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科教授。1997年、ケンブリッジ大学大学院英語英米文学専攻博士課程修了。専門は英米文学。著書は『文学を〈凝視する〉』(岩波書店、サントリー学芸賞受賞)、『史上最悪の英語政策――ウソだらけの「4技能」看板』(ひつじ書房)、『理想のリスニング:「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界』(東京大学出版会)など。


 阿部 公彦(あべ まさひこ)
阿部 公彦(あべ まさひこ)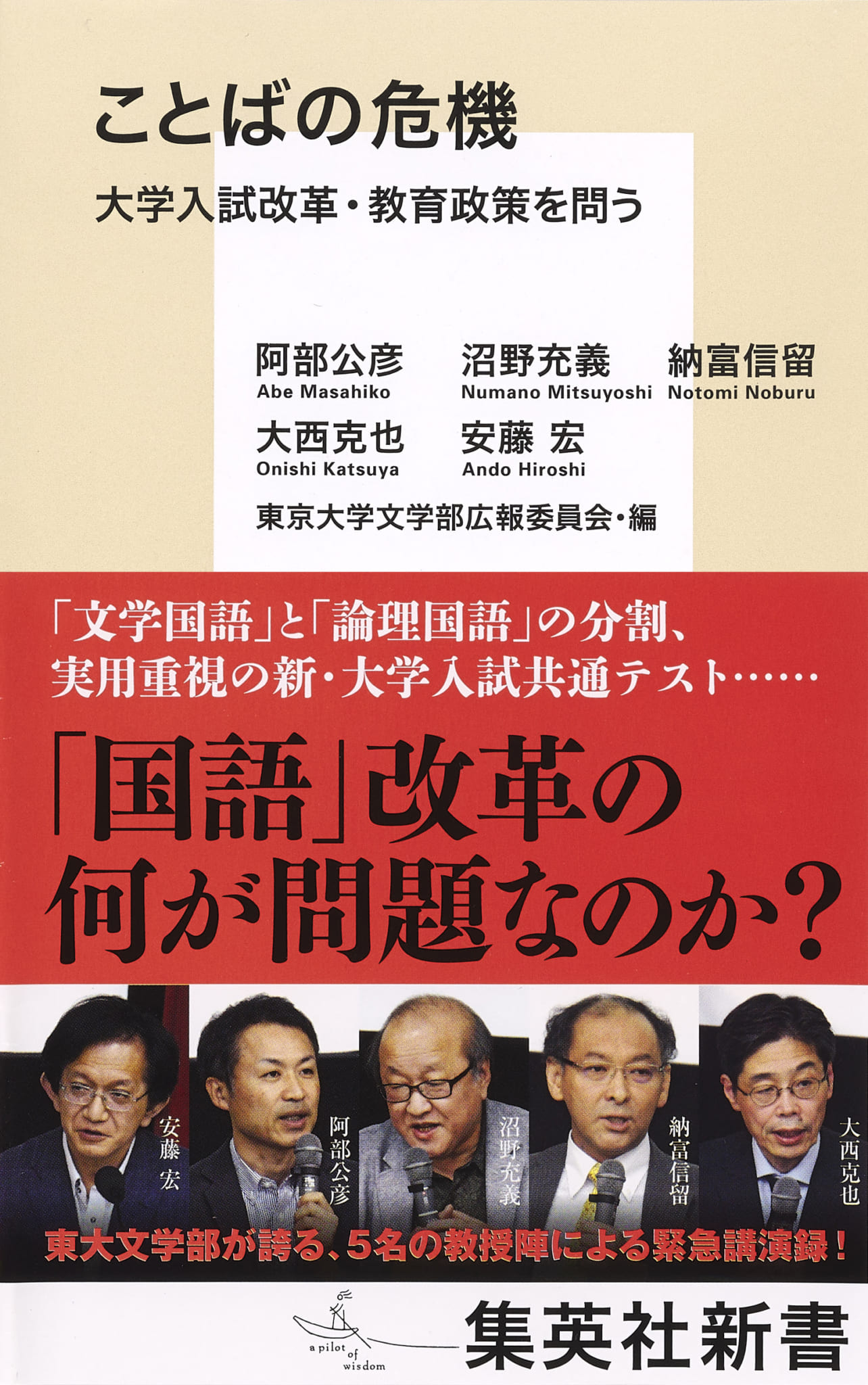
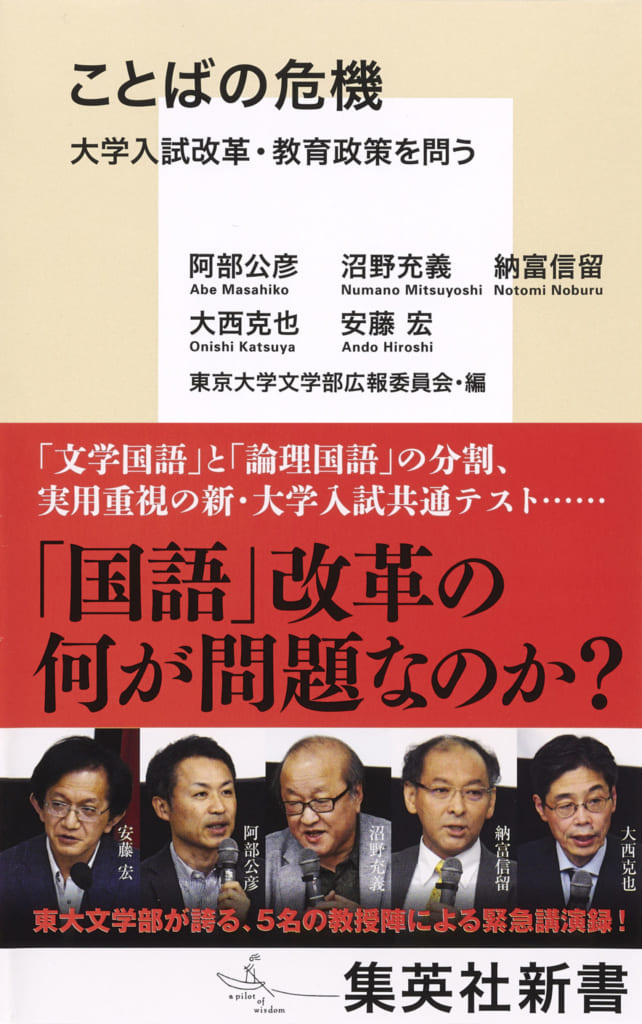










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

