『世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか』(光文社新書)や『独学大全』(ダイヤモンド社)といった書籍のヒットに代表されるように、ここ数年ビジネスパーソンの間で「リベラルアーツ」や「独学」という言葉が流布している。しかし、そこで言われるような「リベラルアーツ」とはどのようなものなのだろうか。そもそも、学問とは複雑化するなかでその内実がわからなくなってきた「ブラックボックス」なのではないか。
2021年9月に刊行された『書物と貨幣の五千年史』(集英社新書)で、人間社会にあふれるブラックボックスを明らかにしていった著述家・書評家の永田希氏は、そのような状況をどのように捉えているのか。『文系と理系はなぜ分かれたのか』 (星海社新書) の著者で科学史の専門家の隠岐さや香さんとともに考えます。
(本記事は4月23日土曜日に本屋B&Bで開催された同タイトルのイベントの内容を再編集したものです)

隠岐さや香氏(左)と永田希氏
「文系と理系」は実存的な問題?
永田 さっそくですが、隠岐さんには『文系と理系はなぜ分かれたのか』というご著書があります。「文系と理系の分岐」という問題に興味をもたれたそもそものきっかけを伺うところから始めたいと思います。
隠岐 自分自身が高校のとき、授業選択で迷ったんですよ。もともと国語の点数はよかったんですが、物理もわりと好きだったんですね。つまり興味のあるものと得意なことが違った。いまから思えば文系の価値をどこか信じていないところがあって、サイエンスのほうがかっこいいと思っていた。しかし、大学に入ったら、文系とされている学問に「こんな楽しいことも勉強していいの?」と思えるものがたくさんあることを知り、自分がはまり込んでいた価値観を振り返る機会になりました。
もう一つはジェンダーに関わる話ですけど、やっぱり女の子は数学ができない、だから馬鹿なんだと思われている気がしていました。それに反発してフェミニズムの本などを買ってみたり。そんなことがいくつも重なって、大学院に進んだ20世紀の末頃までその問題が自分のなかでずっとわだかまっていたという感じですね(笑)。
永田 文系と理系は単に「分かれている」だけではなく、「理系のほうが文系よりもすぐれている」というイメージが存在している。しかも、このイメージにはジェンダーも結びついている。そのことを徐々に発見していったんですね。
隠岐 さらに実存的な苦しみもありました。自分自身の知性を疑わなきゃいけないような状況がなぜ生まれたのか、その成り立ちを知りたい思いが強かったんです。
永田 僕は小学生のころ、物理学者になろうと思っていたんです。でもその夢を結局はあきらめることになりました。計算問題がとても苦手で、気が付いたら理系というものに苦手意識を抱いていたんです。物理学にかぎらず、サイエンス自体は好きで、その手の本も今でもよく読むんですが、いざ「試験」のような場面になると「答え」が出てこない(笑)。出てこないというか、脳なのか心なのか、とにかく自分のなかに邪魔をする何かがあって、わざと余計な計算をしてしまっているような感じがあります。
隠岐 私の場合、親が悪気なくそういうことを言ったんですね。母親はいわゆる優等生だったんですが、「数学だけは弟にかなわなかった」という話を何度か聞かされた。実際、叔父は大学で理系に進学し、母は文系に進みました。いちばん決定的だったのが数学のテストでパニックに襲われたことです。心臓がどきどきしてきて、本当に頭が真っ白になった。さきほど永田さんも、試験になるとうまく答えが出てこないと仰ったけれど、私も本当にそれと同じ症状があって。あとから見れば「なんでこれが解けなかったんだろう?」というような問題なんですよ。でも数学の試験の前は異様に緊張するようになってしまったんです。
永田 すごく生々しい話ですね。去年、数についての文化史が綴られた『数の発明』(みすず書房)という本を読んでいたら、こういうことが書いてありました。数学に苦手意識をもつ人は、計算式を見ただけで脳の中に「もう嫌!」というパターンが出るらしいと。後天的な問題なのか遺伝のせいかはよくわからないけれど、もしかすると、僕や隠岐さんの脳内にもそういう計算式嫌いのパターンが形成されてしまっているのかもしれません(笑)。
隠岐 あれは何なんでしょう(笑)。私の場合、一人で問題に取り組んでるときは大丈夫なんです。でも自分を試されてると思うと、まるで誤作動が起きたみたいに頭が真っ白になる。そういうときに理解を阻む数式みたいなものこそ、永田さんがご著書で論じたブラックボックスですよね。

学問そのものがブラックボックス
永田 僕は文系と理系どちらの学問もブラックボックスとして捉えています。現代日本で普及している「科学」という訳語は、さまざまな「科」目に分類して諸事情を分担して「学」び、研究していくシステムの存在を前提にしている。科学という言葉は「人文科学」「自然科学」「社会科学」というように、いわゆる「理系」に限定されないものです。でも隠岐さんの本に、明治時代には科学や学問を意味する英語のscienceを「究理」と翻訳していたと書いてありました。「究理」という訳語では、科目ごとに分担して研究するということよりも「理(ことわり)」を追究するイメージのほうが強くなってしまう。日本での西洋科学の受容においては、この分科の仕組みが最初は捉えにくいほど新鮮だった。欧米文明に触れ始めた頃の近代日本の事情がある一方で、欧米ではかつてscientistとはマニアックなことに入り込んでしまう人、いまで言う「オタク」に近いニュアンスで捉えられていたことがあるそうですね。
隠岐 たとえば内科医はphysicianで、音楽家はmusicianでしょう。でも歯医者はdentistと呼ばれる。そして科学者もscientistで歯医者と同様に-istと呼ばれる。-istは抽象的なものを探究する人にはつけられない傾向があるのに、scientistにはつく。すごく変な言葉なので、当時はこう呼ばれると侮辱されたと感じた人もいました。
永田 近代以前の日本では、アマチュアの研究家たちがいろいろなことを知るのが楽しくて、全国の好事家とネットワークを作っていった。彼らは、裕福な家庭に生まれついたり、才気を買われて大商家に雇われて事業を成功させてからリタイアしたり、自由気儘にそれぞれの知の体系を作っていた。もちろん時代ごとの権力との関係は無視できませんが、欧米の教会や大学のような全体性はありえなかった。いまも、日本に限らずアマチュアの研究家はそうした存在ですが。明治以降の、大学や近代政府による富国強兵政策が推進されるより前にあったそういうディレッタント的な世界に、僕は少し憧れがあるんです。
隠岐 西洋の科学史でも、科学者のあり方はそれが基本です。チャールズ・ダーウィンは大学で教えたことが一度もありません。彼はジェントルマン階級で、有名な陶器メーカーのウェッジウッドの事業主も親戚にいた。土地をたくさん持っているから、まったく働かなくていい。
永田 うらやましい(笑)。
隠岐 ダーウィンは若い頃にビーグル号という海軍の船で世界一周して、そのときにガラパゴス諸島に寄港した経験が進化論につながるんですが、論文を発表するまでずいぶん時間がかかっている。それまで何をやっていたかというと、社交をしてるんですよ。ジェントルマン階級は社交が家業(笑)。好事家の協会、いまでいう学会のような集まりにもよく出ていたところ、自分がガラパゴス諸島でみてきたのとよく似た話を聞いた。じゃあ自分も急いで論文をまとめなきゃ、ということで進化論の論文を書き始めたと言われています。
永田 いまでは大学が学問を支える最大の制度になってしまったけれど、学問はもともと制度的ではない「社交」みたいなところからはじまっている。学問とは何かという話になるとややこしくなりますが、「学問」という言葉は、ある研究領域を指し示す「学」という言葉と、その研究領域を生み出す「問い」から構成されています。学問とは、新しい「問い」によって、先行する研究領域(「〇〇学」)の内部にたえず新しい研究領域が生成される入れ子構造になっていると言えるのではないか。「問い」は、それまでは認識されづらいブラックボックスを発見し、それを解き明かそうとする行為です。学問がブラックボックスだ、と僕が主張しているのはそういう入れ子構造の性質を指しているところがあります。興奮してわけのわからないことを話してるかもしれませんが(笑)。
隠岐 いえ、面白いです。
永田 学問に権威が伴う以上、ブラックボックスを作れる、つまり権力を作れるということだと僕は考えています。それを解くことができれば権力を解体できる。解体されたブラックボックスを使えば、解体できたところまで遡って、そこからその領域を再構成する可能性がある。もちろんブラックボックスを解き明かして自分のものにすると、今度はそれを使って権力を行使する側にも回れる。学問について考えるときは、つねにそのことを意識すると面白いと思うんです。
かつてリベラルアーツ(自由技芸)と呼ばれていたものがなぜ「自由」と関係のあるものだとされていたのか、いまではわかりにくくなってしまったけれど、現代でも人がリベラルアーツを求めたり、その言葉に肯定的なニュアンスを感じたりするのは、世の中にある権力と結びついたブラックボックス的なものを学問によって読み解き、自分の力にすることをつうじて自由になりたいと期待しているからじゃないか、と思うんです。

宗教改革と科学革命
隠岐 いまの話をうかがって、永田さんが選ばれたブラックボックスという言葉は、直感的に把握しやすくてとてもいいな、と思いました。人が支配されるときには、かならず情報の非対称性がある。たとえば、かつてキリスト教徒の大半はラテン語が読めなかった。教会で聖職者のラテン語による説教を聞いているだけだから、呪文みたいなものでも信じてしまう。プロテスタントによる宗教改革は、普通の人が聖書を読めるようにすることが最初の一歩でした。
永田 そう、情報の非対称性がある。宗教はものすごくわかりやすい喩えですね。「ありがたいおはなし」は意味がわからなくても、いや意味がわからないことによって信仰を集め、権力を帯びていく。
隠岐 永田さんのこの本では「リバースエンジニアリング」というキーワードも出されていますよね。ブラックボックスがどうできているのか、その仕組みを解体しながら理解し作り替えていけば、ブラックボックスそのものはなくならないにせよ、それに支配されている状態からは脱することができる、と。
永田 そのとおりです。
隠岐 現実の宗教改革にも、恐らくそういうところがあったと思います。それまでは謎めいた言葉であった聖書の文言を、文献を照らし合わせることで、キリストが語ったもともとの言葉まで探り、それを各地のローカルな言語に翻訳して信者が一人で聖書を読めるようにした。まさにリバースエンジニアリングです。事実、宗教改革は科学史にもきわめて大きな影響を与えました。
たとえばフランシス・ベーコンはイギリス人のイングランド国教会信者、つまり宗教改革をされた側ですが、彼は新しい知識が必要だといって自然科学の探究を奨励した。中世にはスコラ哲学というカトリック教会がアリストテレス哲学をもとに体系化した学問があったけれど、ある種の知識には歯止めがかけられていた。たとえば自然界の探求をしすぎると人は傲慢になるとして、カトリック本来の教義では自然科学が奨励されなかった。ところがガリレオのような人が出てきて、望遠鏡で天体観測を行ってアリストテレスの説を否定したり、地動説を支持して聖書に書いてあることはどうやら違うと言いだす(笑)。面白いのは、ベーコンがこうした人々に対しても聖書を使って反論したことです。彼は聖書の文言を読むのは神学者に、自然という別の「神の書」を読むのは自然科学者に任せればいいとして、聖書を否定せずに神学者と科学者の分業を肯定したのです。その結果イギリスは自然科学の研究に開かれた国になり、ニュートンの頃までは世界のトップランナーでした。
他方でフランス革命の少し前になると、ディドロのような人たちがフランスにも出てきて、知の集大成みたいな『百科全書』という大事典を作った。彼ら自身はプロテスタントではありませんが、プロテスタントから大きな影響を受け、カトリック教会に反抗して一部は無神論的にさえなっている。その結果、『百科全書』は発禁本になっちゃうんですが(笑)。
永田 中世は秘教的でよくわからないことを言っていた人たちが権力を持っていた時代で、そのブラックボックスを読み解きオープンにしていくことで近代が訪れる。この考え方はある程度までは妥当だと思うんですが、実際問題として、近代を経過したはずの現代、平等はいまだに実現してないじゃないですか。むしろ、平等になることをやめよう、という路線の発言力がいまだに強い。平等じゃないほうがいい人って、いったいどういう人なのか、僕は子どもの頃からずっと謎なんですよ。間違いなく、そいつらはブラックボックスの中にいる(笑)。
隠岐 (笑)。ちょっと話はズレますが、自分の研究のなかでたまたま「修身」という言葉の由来を調べたことがあるんです。戦前戦中の道徳の授業のことですが、これはもともと英語のmoral scienceという言葉の翻訳として選ばれたという経緯があります。それは置いておくとして、当時の保守派の人が書いた「修身」本がネットで読めるんですが、「修身」の歴史を少し調べると、大正時代に私がとても苦手なタイプの理論がいっぱい出てくるんですよ。そこから感じられたのは、彼らのなかにある直感的な恐怖でした。
永田 当時、「修身」の必要を説いていた人たちは何かに恐怖を感じていた、と。
隠岐 そうです。説明がちょっと難しいんですが、いまだに保守派がよく言う「家族が分解すること」への恐怖と似た感じですね。意外かもしれませんが、明治の頃は小学校の教科書に完全に西洋式リベラリズムの思想が入っていたんですよ。でもそれではどうもうまくいかなくて、大正に入る頃に儒教などの考えを取り入れて「一億愛国」みたいな方向に行く。自分が「個」だという感覚がなくて、より大きなものが自分も妻や子どもも一緒に抱え込んでくれているように感じているから、「私」の一部であるはずの妻や子がその一体感から離反して行ってしまうことに恐怖を感じるのかな、と想像しながら読みました。
永田 それはすごく面白いですね。
隠岐 私がまったく勘違いしてるだけかもしれないですが(笑)。

拡散しすぎたリベラルアーツ
隠岐 永田さんの本でもジャック・ラカンの話をされていますが、彼が理論化した想像界・象徴界・現実界のうち、想像界では母子が分離していないとされます。分離した独立の人格について考えるのは面倒なことで、不安にもなるし、思考のリソースを食うことです。子どもにはできません。ひょっとすると、危険の多い社会では大人もそれが難しくなるのかもしれない。保守的な人は家族をもつことにこだわりますが、そういうとき想像界の中で自分と家族が一緒になっているんじゃないかという気がします。それは多分、リソースが少ない社会だと合理的な思考法なのでしょう。たとえば技術が未発達な社会だと、自分が狩りに行ってる間は誰かに子どもを見てほしいなど、一定のニーズが実際にあるから、それも込みで「家族は一つの生き物だ」みたいな考えに染まれる人の方が楽に生きられるのかもしれない。そんなことを思いながらそのテキストを読んでいました。
永田 ようするに家族もブラックボックスなんですよね。あまりにもとってつけたような話になってしまいますが(笑)。なんでもブラックボックスじゃないかと。
隠岐 でも実際、ブラックボックスの最たるものですよ。
永田 建築物としての「家」もまさに箱ですしね(笑)。人口統計学者のエマニュエル・トッドがかつて提唱した、文化圏によって家族の類型が異なるという考え方があります。トッドの提唱したいくつかの類型には、日本が該当するとされているものがあります。もちろんそれはずいぶん現実と違うことを言っているので気をつける必要があるんですが、「類型がある」という考え自体は面白い。自分の家庭はトッドの類型で言えば何々の類型に当てはまるな、というふうにパターンや枠をうまく使うことで、かえって自由になれるかもしれないな、って。
隠岐 類型論自体、人間の知性のジレンマなんです。なにごとにも類型化しないとわからないことはあるけれど、現実は必ず類型を裏切っていく。私の専門のまわりでも資本主義の類型論のようなものがありますが、どれも完全な正解には行き着かない。
永田 類型やパターンは、ある程度の幅の中での説得力しかもたない。でもそれを認識できるようになるのも大事ですよね。せいぜい「人生において大事なものは何か」とか、そういうレベルの話ですけど(笑)。
隠岐 リベラルアーツの話が出てくるのも、そういう幅みたいなものが意識されてるときでしょうね。ただ、いまは「リベラルアーツ」の意味があまりに広がってしまって、正直、困ることもあるんですよ。文系と理系の本を書いたときには、本当に「文系と理系の歴史」をやろうとしたんです。リベラルアーツについて何か話してくれと言われるとは想像していなくて、ああ、そこが繋がるんだと最初は驚いたんです。文系と理系、両方の知識を浅く知るみたいな感じでつながったのかな、と思ってリベラルアーツをめぐる過去の論争を調べたら、思ったとおり、ありとあらゆる論争がすでになされていた。いろんなことを知るという方向のリベラルアーツもあれば、知識はいいから論理的に考えるのがリベラルアーツだと言う人もいて、ああ、リベラルアーツという言葉自体がブラックボックスなんだな、と(笑)。
永田 確かにそうですね。
隠岐 そんななかでも、このあたりがリベラルアーツの定義の最大公約数かな、と思ったことがあります。ある企業のかなりキャリアも積んだ方から講演依頼をされたんですが、なぜ私にリベラルアーツの話をさせたいのかわからなかったので、くわしく話をうかがったんです。その方が言うには、海外でかなり難しい環境問題にかかわる事業を展開していると地元の環境団体が非常に反対してくる。科学的には大丈夫なやり方があっても、それだけでは説得できるかわからない不透明な状況がある。そんなときにどうするのがいちばんいいのか。それはどんな専門書を読んでも書いてない、と。専門知だけでは答えが出せない不透明な状況は日常にいくらでもあって、そのときに自分にとっての許容範囲のなかで確度の高い結論が出せるような思考の素養みたいなものを、その方はリベラルアーツと呼んでいたんです。
永田 語源に遡れば、「リベラルアーツの定義」をいちおう確定させることはできるじゃないですか。でも、その起源から現在までの時間的距離の間にやたらと枝分かれしていて、ミッシングリンクみたいなものもある。そのどこまでがリベラルアーツなのか、というと……。
隠岐 歴史がジグザグしすぎているんですよね。そういうとき、私はよく共和政ローマの哲学者、キケロの話を使うんです。キケロの時代には、人間(自由市民)と奴隷とがはっきり分かれていた。当時の自由市民は主に男性で、リベラルアーツには人が奴隷に命令できるような教養というイメージがある。そうした意味でのリベラルアーツ観はいまの世の中にとってあまりよくないから、私はそのままとり入れたくはないんです。
あとの時代になると、リベラルアーツはアメリカ合衆国におけるゼネラルエデュケーション、つまり民主的な社会における公教育の話になる。本当に枝分かれがものすごくて、さらにキケロの時代の前には古代ギリシア人にとっての「円環的な教養」、つまり成人になるために必要な欠けるところのない文化的知識のことだった。これがエンサイクロペディア、つまり百科事典の語源です。でもそれをローマに輸入するときに、キケロがいろいろとつけ足してしまった(笑)。
永田 リベラルアーツという言葉一つ取ってみても、いろんな経路を辿っていて定義できない、あるいは定義が定義にならないわけですよね。

「すぐ使える学問」の先鋭化?
隠岐 いまの話でとくに問題なのは、百科全書的な知識を教えるという部分なんです。「リベラルアーツによって知の見取り図を与えてくれ」という場合、結局のところ、百科全書的な視野を与えるのが目的なんですよ。
永田 ある意味、幕の内弁当的な感じのものを求められるということですね。
隠岐 そうです。リベラルアーツと言われたとき、勝ち組らしい教養のあるパーティートークをするための知のパッケージを下さい、のような意味になることがあるのです。それは簿記のようにすぐに役に立つものではないけど、他者に対する威信を示す、すなわちマウンティングに使えるという意味で間接的には役立つ武器のようなものです。しかし、そうした方向性に対する強い批判もあります。もっと具体的に言うとそうした方向でも役立たない類の人文学をやるべきだと考える人たちがいるんですね。いわゆる実学じゃなくて……。
永田 虚学(笑)。
隠岐 うっかりすると反体制的だったり、さすがに反社会的とまではいわなないけれど、いわば秩序攪乱的な、奴隷が主人に対して異議申し立てをするようなタイプの思考法を教える、という意味でリベラルアーツと言っている場合がある。逆にいえばどちらにしても、すぐに役立つ系の知識、たとえば簿記の初級をリベラルアーツとして教える講座は少ないんですよ。だったら「簿記」と言えばいいから(笑)。
永田 たしかに(笑)。
隠岐 具体的な職業のにおいがしちゃダメなんです。つまり、リベラルアーツが「すぐに役に立たないもの」に対して与えられるアンブレラタームになっていて、その内実が何なのかについては対立が隠されている。その中でも「勝ち組トーク」に役立ちそうな内容を教えるものに対して最近、主に人文系の人が悪口で「ネオリベラルアーツ」と言うことがあるんです。それこそ、マーケティングがどうすればうまくいくかをパワポでプレゼンするとか、そういうふうな感覚も含めて(笑)。
永田 でも逆に、ネオリベラルアーツなら僕はちょっと講義してみたい気がします。滅茶滅茶すぐ使えます、という名目で(笑)。
隠岐 私も、もし自分が教えるとしたらとはよく考えます。なんとなく直感ではわかるけど……。
永田 多分、まずは面接の際のドアからの入り方とか(笑)。
隠岐 あるいは名刺の渡し方とか(笑)。でも具体的に考えるとかなり難しい。たとえば名刺にしても、すぐに名刺を渡さない文化の国だってあるでしょう。日本人はなにかというとすぐ名刺を渡してくる、という笑い話をどこかで見たことがあります。
永田 本にも書きましたが、名刺といえば映画『アメリカン・サイコ』で三人のヴァイス・プレジデントが名刺を互いに見せ合うという、すごく有名な下らないシーンがあります(笑)。ところで「国や文化によって違うからいつでも名刺が正解だと思うなよ」と教えるのはネオリベアーツなのか、それともリベラルアーツなのか。
隠岐 そういう講義なら私もやってみたいですね。本気で職業にはしたくはないけれど、それが何なのかを考える面白さは、ちょっとあるかも(笑)。
永田 ネオリベラルアーツなんていう悪口が言われる以上、それはすでに存在している。まあ、ネオリベという言葉自体、最近はあまり聞かなくなった気もしますが、かつて「ネオリベ」と揶揄されていた界隈でこそ、いまリベラルアーツがとても求められている。それを指してネオリベラルアーツと呼ぶのであれば、とてもよくわかる感じがします。
隠岐 問題はその内実ですね。悪口として聞いてたときはわかっていた気がしたけど、だんだんよくわからなくなってきました。
永田 ぜひ、隠岐さんにはそこにもっと踏み込んで行っていただきたいです。今日はありがとうございました。
構成:仲俣暁生
撮影:内藤サトル
プロフィール

永田希(ながた・のぞみ)
著述家・書評家。’79年コネチカット州生まれ。『週刊金曜日』書評委員。『ダ・ヴィンチ』でブックウォッチャーの1人として毎号選書と書評を担当。書評サイト「Bookニュース」主宰。『このマンガがすごい!』『図書新聞』『週刊読書人』などに執筆。単著に『積読こそが完全な読書術である』(イースト・プレス、2020年)、『書物と貨幣の五千年史』(集英社、2021年)。現在、鋭意新著の準備中。Twitter:@nnnnnnnnnnn
隠岐さや香〈おき・さやか〉
1975年、東京生まれ。東京大学大学院教育学研究科教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。博士(学術)。広島大学大学院総合科学研究科准教授、名古屋大学大学院経済学研究科教授を経て、現職。専門は科学史。日本学術会議連携会員。著書に『科学アカデミーと「有用な科学」――フォントネルの夢からコンドルセのユートピアへ』(名古屋大学出版会)、『文系と理系はなぜ分かれたのか』(星海社新書)、共著に『「役に立たない」研究の未来』(柏書房)など多数。


 永田希×隠岐さや香
永田希×隠岐さや香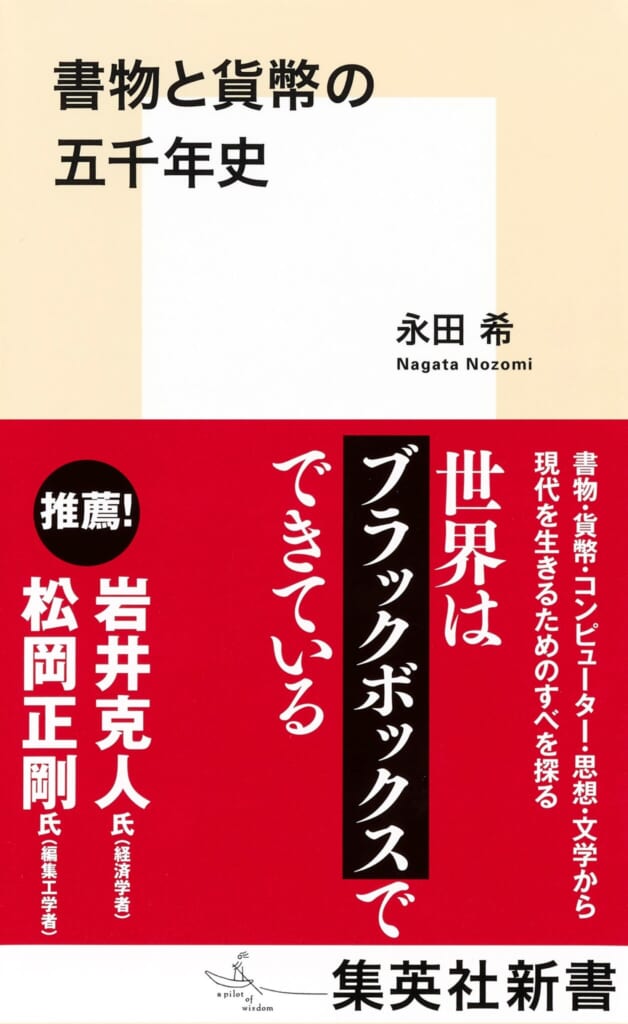










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

