コロナ禍を経て、急速な成長を遂げたゲーム産業。e スポーツの浸透やYouTubeにおけるゲーム実況のブームのみならず、米大統領選のキャンペーンに「どうぶつの森」が用いられたり、オリンピックの開会式にゲーム音楽が使用されたりするなど、その影響力は現実の社会にも及んでいる。
そうした状況を受けて、批評家の藤田直哉氏は、大人気ゲームの読解を通して、陰謀論、分断、叛乱、新自由主義、家族といった重要なテーマを考える新書『ゲームが教える世界の論点』を上梓。
本記事では、ジョン・デューイや鶴見俊輔といった思想家の研究だけでなく、現代のメディアについての論文や論説もある哲学者、谷川嘉浩氏をお迎えし、いまゲームを語ることの意味、そして今世界のサブカルチャーに起こっている変化について、『Detroit: Become Human』や『The Last of Us Part II』を通して考える。

「弱毒化したリアル」としてのゲーム
谷川 この本では、「ゲームが時代を映す鏡である」というテーマも繰り返されています。もちろん、現実のほうがゲームよりも情報量が多いので、ゲームは、現実の複雑性を縮減し再編集した形で映し出している。前半では、シミュレーターとしてのゲームという観点から話を聞いたので、後半では、この社会反映論的な見方に注目してみたいと思います。社会を反映した作品を検討することの魅力について聞かせてください。ダイレクトに社会を検討することとは違った魅力があると思うのですが、藤田さんはどう考えていらっしゃいますか。
藤田 物語というのは、ある種、現実を構造化して、モデル化して、情報を縮減して、わかりやすくすることで我々に何かを教えてくれる装置だと思います。そして、ゲームの場合も、使命感を持った人たちが社会をモデル化して、何かを伝えようとしていることがあるわけです。たとえば、アメリカのデトロイトを舞台に、アンドロイドたちが「差別」される世界を描いた『Detroit: Become Human』などは完全にそうで、貧富の差、あるいは産業構造が転換することによって置き去りにされた労働者たちが反逆してきて、その中で差別が過激化してみたいな現状の問題をわかりやすく伝えてくれるものですよね。ラストベルトなどで、現実に起こっていることの寓話ですね。それはある種の啓蒙というか、教育的な意図で作り手がやっているんだと思います。
谷川 私は社会反映論的な議論にふれるときにいつも思い出すのが、鶴見俊輔さんとも親交のあった作田啓一さんという社会学者の議論です。彼のロジックをすごく切り詰めて言うと、「ある種のフィクションは、現実を蒸留された形で見せてくれるから、ストレートに現実を分析するよりも、一層鋭い現実の理解をもたらしてくれる」というものです。現実を生のまま見ようとしても仕方がなくて、むしろ物語であるとか、何かを濃縮したものにふれるほうが、かえって現実がよく見えるということを言っていて、それに近いのかもしれませんね。
藤田 そうですね。現実の世界って、言語や概念で構造化されていないと、もやもやで曖昧で、何が何だか分からないですよね。始まりも終わりも、原因も結果も因果もない。でも、それを言葉や概念で分節し、モデル化し、縮減し、単純化し、誇張することによってわれわれは認識できるようになり、理解できるようになる。多分、それがナラティブの効果であり、必要性だったり、有用性なんでしょうね。
谷川 なるほど、よくわかりました。
藤田 最近、「弱毒化したリアル」という言葉をよく使うんですよ。現実をそのまま摂取するとキツすぎるような内容を、ある程度フィクション化して柔らかくして摂取することで、予防接種になる部分があると思うんですね。例えば、内戦や虐殺の実態を実写で直接見るのはエグすぎてキツい。でも、それをアニメーションとかにすると、もう少しソフトに受け止められることがある。宮崎駿のアニメ作品なんてまさにそうで、一見するとかわいいキャラが動いてるように見えて、実はあれは災害の話だったりするわけです。そういう、複数のレイヤーで提示することで、ある種の現実的なものというか社会のものを意識させることが出来るんじゃないかなと。
実際、うちの大学で学生たちに、ドキュメンタリーやシビアな社会派映画などを見せたりすると、エグすぎて受け止められなくて、落ち込んじゃったりするわけですよね。あるいは気候変動のような未来の話だったり、社会の差別の話だったり、今もどこかで大変なことがあってみたいなことを聞くと、逆に気分が滅入って、心が閉じちゃうこともあるわけです。考えたくないし、考えてもどうしたらいいか分からないし、言われれば言われるほど、怖いし不安になっていく。で、結果としてInstagramとかをずっと見るみたいになってしまう。それは僕もよくわかるんですよ。僕自身がそうなることもありますから。『はだしのゲン』を読みたくないってのも、そういうことなんだろうかなと思いますね。
じゃあ、そこまで気が滅入らない、トラウマにならないように、ソフトな表現をするということもありうると思うんですよ。社会や世界にこういうことがあるよってことを知ってもらいつつ、それを受け止める心の弱さをも受け止めるような、そういう表現の可能性もあるんじゃないかなと思うんです。昨年自分が出した『新海誠論』(作品社)と今回の本にはそういう問題意識があります。「ソフト」とは言っても、差別による大量虐殺や死体の山を埋めるシーンなどを、ロボットや宇宙人に置き換えて実際に描くわけだから、結構エグいとは思いますけどね。
谷川 なるほど。自分なりに地図を持って現代を歩かないと迷子になっちゃうってことですよね。ただ歩けとだけ言われても途方に暮れる。でも実は日々接しているアニメやゲームが、その地図になるかもしれないということを読者に知ってもらえたらいいですよね。
藤田 気候変動で人類は絶滅するし、少子高齢化で日本経済は衰退するとか、言われても、やる気がなくなるじゃないですか。
谷川 気候変動や貧困、少子高齢化みたいな社会課題って個人だけで解決しようがないですからね。企業や自治体、国家、あるいは国家間のような中規模以上のスケールで取り組みが広がらないと効果が上がらないものばかりです。
藤田 だから無力感や不安が強くなっていくんですよね。しかし、皆が目を逸らしては余計解決しなくなることもたくさんある。そういう問題を、分かりやすく構造化しモデル化し、エンターテインメントとして伝えることで、世界をよく変えていける可能性はあるんだと思う。

単純化、数値化される時代に、いかに複雑さをそのまま伝えるか
谷川 デカすぎる問題に途方に暮れるでもなく、流行りに乗って情報として物語を扱うでもなく、リプレイや語り直しを解釈することに取り組んでもらうためにどうすればいいかというと、恐らく、世間とかアテンションエコノミーからうまく距離をとるということなのではないかと思います。物語を咀嚼し、吟味する上で、物語に没頭するということが必要ですから。
藤田 そこは逆説なんですよね。他者に開かれすぎると、同調や受け売りで、すごく浅くなってしまうことがある。その接続過剰を切断し、閉じることで深いレベルにまで到達すると、結果として外に開かれていくこともある。本書で紹介したゲームは、そのような「閉じながら開かれる」ところにアプローチしようとしているところに、可能性があるのだと思う。
―SNSとかでも、本当は各々が勝手に好きなことを書けばいいはずなのに、世界に見られるって思った瞬間にそれを意識してしまう構造がありますよね。
藤田 特に最近Twitterがインプレッション数を表示するようになったじゃないですか。
谷川 あれはえぐいですね……。前のツイートより閲覧数が多いか少ないかを気にしなさいと言っているような設計ですから。
藤田 あれはまさにゲーミフィケーションですよね。ゲームの、のめり込ませるための仕組みって、成果とかリアクションが数値されて分かりやすく脳内報酬系を刺激することですからね。我々は、ゲームをしていなくても、もうゲーム的なものに操作されているわけですよね。いくら書いてインプレッション得ても、SNSが広告料で儲かるための無償労働をさせられているようなものなのに。
谷川 相互評価や競争を促すようなユーザーインタフェースによって、言葉選びとか、語るトピックが無自覚のうちに変わりますよね。SNSは、自覚できないくらい自然に自分の言葉を変えているはずです。Twitterをやる前後でもそうだし、インプレッション数の表示が出る出ないの前後でも、自分の言葉遣いには、気づけないくらい些細で、しかし重大な変化があるはずなんですよ。

藤田 もう変わっているんだろうな、と感じますよ。人々が感情的で短絡的になるとか、論理や証拠が通じなくなって情動で判断しがちになって陰謀論が流行るとか。ポストトゥルースの原因はSNSだと思いますよ。そしてそれは人文的なものの危機の原因でもあります。複雑なこととか、難しいこととか、曖昧なことをTwitterでつぶやいても人気は出ませんよね。文学的で複雑な話もバズらないですよ。すると、書かなくなっていくし、考えなくなっていきますもの(笑)。
谷川 そうですね。私はTwitterで議論することは諦めています。物語が情報やコンテンツになるのと同じで、人とつながるための言葉もまた、単なる情報やネタとして扱われてしまうので。
藤田 だから、僕は、Twitterでバズったときのほうが危機感を覚える時があったりします。「これってすごく単純化しているんだな」って気づくんですよ。で、逆に自分が大事だと思うことを書くと、全く盛り上がらなくて悔しくなる(笑)。そうやって、反応が来ることの快楽にハマって駄目な道に行った人も多いと思いますよ。
複雑で曖昧なことを知らせるということは大事なんだけど、複雑で曖昧なことは広がっていかないし、伝わらない。この状況にどう介入するかっていうのを考えないといけない。だから、逆にいかにバズらない言葉を言うかみたいなのが大事かもしれない。
谷川 いかに人の目や人気とは関係のない水準で言葉を練り上げることができるか、ですよね。あるいは、リアクション目当てで何か言おうとする「浅ましい自分」とうまく付き合えればいいですよね。それは私にとっても難しいですが(笑)。
藤田 しかし、バズらなければ届かず、伝わらず、世の中は変わらない。さあ、どうする、というところの勝負かなと。
ー今の話を聞いていて、本の第四章でも触れられていた『The Last of Us Part II』というゲームを思い出しました。本作は前作の主人公のジョエルが、彼に父親を殺されたアビーという少女に報復を受けるところから始まります。そして、ジョエルとともに旅をしてきた少女、エリーがアビーたちに復讐をする、というストーリーです。あれはまさに、二人の人物を中心にどちらの立場にも正しさがあるという複雑さをそのまま作品に落とし込んだものですよね。
やはり作り手側も、単純な二項対立にならないように、物事の複雑さをそのまま表現しようとする動きがあるのでしょうか
藤田 映画もそうですよね。『ジョーカー』(2019年)とかも結局、彼が正義なのか悪なのかは見えない。やはりエンターテイメントの作り手たちは、社会の全体を見ながら、この分断と対立の状況にどう介入するかってことを考えてるんでしょうね。で、ゲームのほうが、操作キャラとプレイヤーが一体化するわけだから、情動的に激しい体験をさせることができるわけです。
谷川 最初はエリーとアビーの視点が頻繁にスイッチするんだけど、しばらくエリーの視点で長らくプレイして感情移入をしていて、自分の行為に疑問が生まれた辺りで、また視点がアビーに切り替わったりして……。その視点移動が巧みなんですよね。敵味方とか、どこどこに属している人だといった単純な判断が徹底して破壊される体験の連続なので、プレイしていて辛くなります。でも、それはネットニュースや動画配信みたいに2、3日で忘れるコンテンツではなく、ゲームを通じてシミュレートすることに意味がある体験でした。
藤田 クリアするために殺さなきゃいけなかった敵のキャラクターが実は妊娠していたことをあとで知らせるとか、殺した相手がデートしているところをプレイさせるとか、なかなかシビアな経験をさせていましたね。殺してきた敵キャラが、実は内面も生活もある「人間」だと後から伝え、加害を反省させ自覚させようという狙いだと思いますが、プレイヤーたちが感情的に反発した理由もよく分かります。
ゲームの持っている暴力性自体を批判するゲームって結構増えていますよね。僕の最初の単著である『虚構内存在』って本では、「ゲームの中のキャラとか虚構の中の存在は、どうせ存在してるわけじゃないから、何をしたってかまわない」みたいなことを書いていましたが、これらのゲームはそれへの批判に見えます。ぼく自身も、これらのゲームに反省させられて、考え方を変えてきた部分があるかもしれないですね。
谷川 大いに共感します。『スマホ時代の哲学』(Discover21)での立場でもあるのですが、フィクション内の存在であっても、その人の経験を真剣に受け止めるなら、その人は自分の心の中に住まうようになる。一概に言えない現実を反映した作品に接することで、大切に思いたくなる存在が出てくるというのは、大事なことだと思います。

フィクションの持つ本当の可能性とは?
藤田 現実世界におけるゲーミフィケーションで言うと、Qアノンのような陰謀論者を見てると、社会的に不遇な人たちがやっぱり多いように見えるんですよ。無力感とか、不遇感とか、社会に対する違和感があって、その上で、世界をよくするとか、巨悪と戦うとか、そういうロールプレイをして自分の人生に意味を与えたいと思っているように見える。それが集合的に行動して、まるでオンラインゲームのようにみんなが集団が一体となるような感覚があるんです。証拠を集めて謎を解いてラスボスを倒す、みんなでレイドバトルしている感覚ですよね。
ゲームが内省を始めて批評的になっているのも、このような「現実」におけるゲーミフィケーションの影響はあると思う。自分の人生や死とかに、意味を与えたいとか、あるいは無力じゃないと感じたいという「ナラティヴ」の機能がここでは悪用されているように思う。屈辱を感じてたりする人たちは、ホワイトトラッシュだとか、負け組だって言われたりするわけで、そういう人々が自分たちを肯定し自尊心を得るためにナラティブ、フィクションを必要としてしまうという現実そのものは否定しちゃいけないと思うんですね。だけど、ナラティヴとゲーム的なシステムが、ここでは非常に安易に、水が低い方に流れるような低劣さと俗悪さで使われているわけで、これは批判しなければならない。
谷川 真面目に勉強していて、世界を憂いているんですよね。その方向性が変だったりするだけで。
藤田 ゲーミフィケーションやナラティヴ自体が悪というわけではなくて、たとえば、SGDsとか気候変動対策に用いられればいいわけです。一人一人が地球を救うヒーローになれる、という物語で、無力感を克服させるようなナラティブだってあるはずなんですよ。SDGsへの貢献をポイント化してレベルを表示するとかね。Qアノン的なものに吸引される人たちを、もっと本当に必要で、本当に役に立つ方向に包摂するようなゲーミフィケーションを誰かが作ってくれればいいのに。
谷川 そうなんですよね。『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』という本で出てきた話なのですが、高等教育(大学教育)って社会化された自分を相対化するプロセスじゃないですか。この対談の言葉でいうと、「自己反省」のことです。でも、今は高等教育の価値が疑われているし、国家予算面でもガリガリ削られ続けていることを踏まえると、自己反省より前に大切なことがあるんじゃないかという話になった。それは何かというと、ちゃんと社会化するということ、「あなたはこの社会の一員です」という包摂のプロセスがうまくいっていない。社会化のプロセスが機能不全を起こしているなら、「自己反省とか自己相対化って大事だよね」と口にするだけで話は片付かないわけですね。
藤田 なるほど。
谷川 これは、フィクションにどんな人物がどうやって描かれているかという問題、つまり「表象」の問題につながっています。人種やジェンダーなどの、いわゆるマイノリティの問題だけでなく、貧困とか、先ほどのホワイトトラッシュの問題なども、ここに関わってくるはずです。
具体的には、ゲームの中に「自分みたいなキャラクターがいる」と感じられるとか、人物が多面的に描かれているとか、そういった丁寧な描写は、「自分は社会に排除されていない」「自分は無力じゃない」という感覚を抱くきっかけになるし、私はゲームにそういう力があると思います。例えば、ベセスダのゲームで遊んでいると、はちゃめちゃな多様性や逸脱ぶりに、私は心底救われた思いがするんです。ベセスダのゲームに、そんなことを言っている人はネットでも少ないですが(笑)。
藤田 そうですね。ゲームも含めて、サブカルチャーとか初期のインターネットっていうのは、社会的に逸脱して、社会の中でうまくいかない人たちに対するオルタナティブな居場所だったり、あるいは存在の意義を与える装置だったりしたわけですよね。最近の異世界転生モノとかだって、ちょっと現実の中でうまくいかない部分がある人たちに対する代償的な満足を与える側面もあるじゃないですか。
ただ、そういうサブカルチャーのナラティブこそが問題を起こしているというのも確かにあって、特に68年的なカウンターカルチャーの精神の焼き直しというか、権威なり、権力みたいなものを疑い、知識人を疑い、社会の体制を疑った時代からある、「懐疑せよ」みたいな思想が、今は反転して利用されてるわけですよね。そして陰謀論や、反ワクチン運動みたいなものに繋がっちゃう。
逸脱者とか、あるいは社会の主流の中で居場所がない人たちを慰撫するための物語自体が、これだけの影響力を持った時代に、サブカルチャー自体がその在り方を問い直さなきゃいけなくなっているんだろうなって感じがしますね。しかし、「萌え絵」を焼く焼かないの騒動もそうだけど、サブカルチャーや、それを必要とする人を否定し、非難してもどうにもならない。どうしようもなく救われない境遇があり、サブカルチャーなどのフィクションによってしか救われない人もいるわけで、そのことはしっかりと共感的に理解し、境遇自体を改善する方向に社会全体で考えなければならない。その上で、ゲームを含めたサブカルチャーは、自分がどのような役割を担っていくべきなのかを、新しく考え直していかなければいけないのでしょうね。
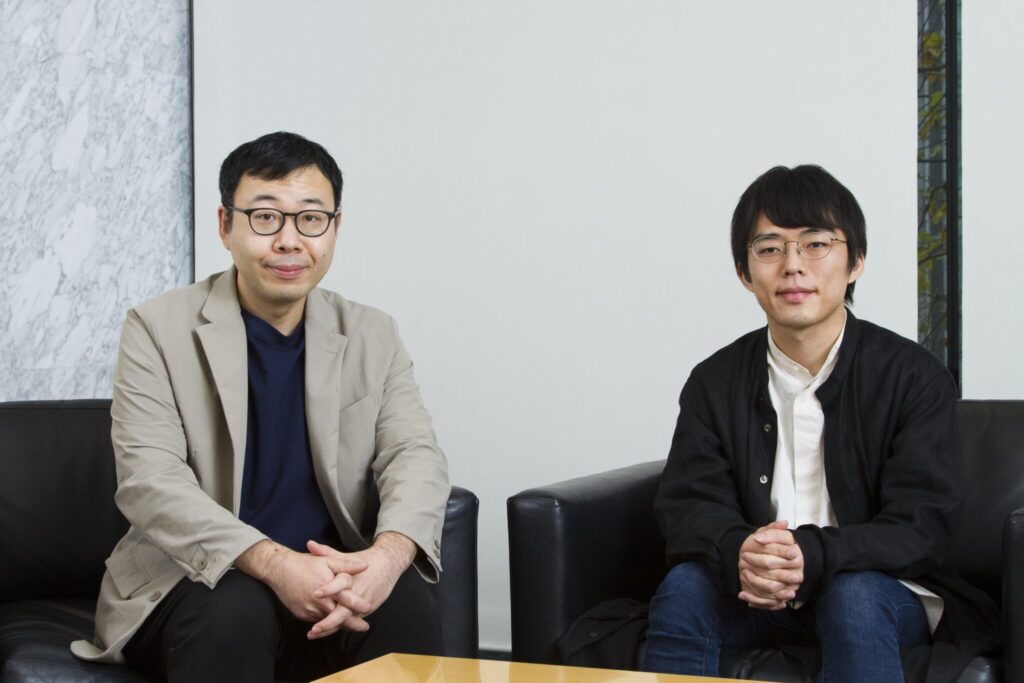
(取材・構成:ノイ村 撮影:内藤サトル)
プロフィール

藤田直哉(ふじた なおや)
批評家。日本映画大学准教授。1983年、札幌生まれ。東京工業大学社会理工学研究科価値システム専攻修了。博士(学術)。著書に『虚構内存在』『シン・ゴジラ論』『攻殻機動隊論』『新海誠論』(作品社)、『新世紀ゾンビ論』(筑摩書房)、『娯楽としての炎上』(南雲堂)、『シン・エヴァンゲリオン論』(河出新書)、『ゲームが教える世界の論点』(集英社新書)、『百田尚樹をぜんぶ読む』(杉田俊介との共著、集英社新書)ほか。
谷川 嘉浩(たにがわ・よしひろ)
哲学者。1990年兵庫県に生まれる。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科特任講師。
単著に『スマホ時代の哲学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『鶴見俊輔の言葉と倫理』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学』(勁草書房)。共著にWhole Person Education in East Asian Universities, Routledge、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる ―答えを急がず立ち止まる力』(さくら舎)などがある。


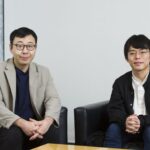 藤田直哉×谷川嘉浩
藤田直哉×谷川嘉浩










 佐藤喬×谷川嘉浩
佐藤喬×谷川嘉浩




 三上智恵
三上智恵