『自転車泥棒』『道』『情事』『山猫』『荒野の用心棒』『木靴の樹』『ニュー・シネマ・パラダイス』『ライフ・イズ・ビューティフル』『君の名前で僕を呼んで』……
映画好きなら一度は聞いたことのある名作が数多く存在するイタリア映画は、50年代から70年代にかけては、日本でも絶大な人気を誇った。2001年から始まった「イタリア映画祭」は今もなおその人気は健在で現在まで続き、ゴールデンウィークに毎年のべ2万人を動員している。
2月17日に刊行された書籍『永遠の映画大国 イタリア名画120年史』では19世紀から現代までの120年を、約800の作品とともに通覧。イタリア映画の歴史を紐解く1冊となっている。
本記事では、著者の古賀太氏とイタリア研究者の岡本太郎氏が対談。「イタリア映画祭」を立ち上げた二人が、イタリア映画の特色を、地方色、監督、撮影、音楽などの観点から語りつくす。
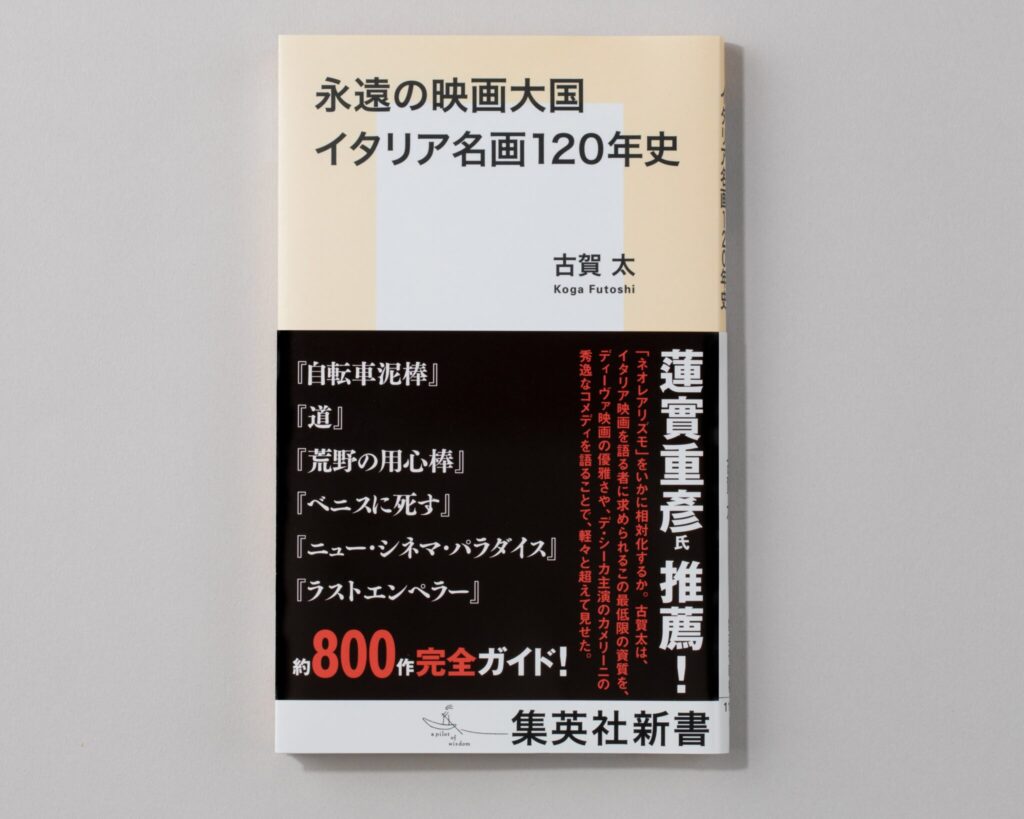
20年以上続く「イタリア映画祭」
岡本 古賀さんの『永遠の映画大国 イタリア名画120年史』は、120年にわたるイタリア映画の歴史がとてもわかりやすく書かれていますね。簡潔でもったいぶったところがなく、僕も勉強になりました。
古賀 僕の方こそ、岡本さんに教わったことがなければこの本が書けませんでした。岡本さんには2001年に「イタリア映画祭」を開催したときに、上映作品の選定から監督たちのインタビュー、通訳までお世話になりました。イタリアはフェリーニ、ヴィスコンティ、ロッセリーニなど世界的な監督を数多く生み出している映画大国ですが、90年代に入る頃は日本で上映されるイタリア映画が少なくなっていたので、現地に住んだ経験のある岡本さんの知識と情報に助けられました。
岡本 80年代からイタリア映画の勢いは少し落ちていましたが、いい作品は生まれていた。それをまとめて紹介する機会ができて、うれしかったですね。当初イタリア映画祭は1回限りと聞いていたので、まさか今までつづくとは思っていませんでした。毎年作品をセレクションする過程で僕も学びがあって、それをまた次の映画祭に還元できたのもありがたいです。
古賀 僕自身もこんなに続いたことに驚いています。第1回目は映画を見ることでイタリア各地の風景や地域性も楽しめるようなラインナップにして「イタリア旅行 90年代秀作選」とサブタイトルをつけたんです。それも功を奏したようで、映画ファンのみならずイタリア旅行に関心がある観客が集まってくれた。もともと展覧会の企画にも携わっていた僕からすると、第1回イタリア映画祭の観客は展覧会の客層に似ていました。年齢の高めな富裕層ですね。

イタリア映画は撮られた地方ごとに光景が違う
岡本 第1回目のラインアップはまさに映像でイタリアを巡るという要素がありましたが、それはそのままイタリア映画の特徴でもありますね。
古賀 そうそう、地方色が実に豊かなのは、イタリア映画の特徴でもあり、イタリアという国の特徴でもある。現在のイタリア共和国が誕生したのは19世紀後半で、それまでは各地で小国がひしめき合っていました。日本で言えば明治維新の頃に統一された新しい国ですから、今でも地方ごとの特色が残っているんですね。
岡本 街並みそのものも違います。ローマには古代ローマ時代の遺跡がそこかしこに残っていますし、フィレンツェにはルネッサンスの建造物、ミラノはゴシックのドゥオモで有名ですし、中部は中世の雰囲気がそのまま残っている町がいくつもあって。
古賀 ロベルト・ロッセリーニの『戦火のかなた』を見ると、それがよくわかる。連合国によるイタリア解放のエピソードをシチリア、ナポリ、ローマ、フィレンツェとイタリア半島を北上する形で描いていますが、土地ごとの光景がまるで違う国のようですよね。
岡本 監督も自分の出身地にこだわっている人が多い。たとえば『ラストエンペラー』などで世界的な成功を収めたベルナルド・ベルトルッチも、初期の頃は故郷のパルマに根差した映画を何本も撮っていました。第1回イタリア映画祭で言えば、カルロ・マッツァクラーティ監督の『聖アントニオと盗人たち』と、エドアルド・ウィンスピア監督の『血の記憶』が、監督の故郷を描いた作品でした。マッツァクラーティ監督は北イタリアのパドヴァ出身ですが、彼は風景に感情をこめるのがすごくうまくて、故郷に対する監督の愛情を風景に語らせています。風景が登場人物と同じレベルの人格みたいなものをもっているという作品は、イタリア映画に多いですね。
ウィンスピア監督は南部にあるプッリャ州サレントの小さな町の出身で、一貫してサレントの映画を撮っています。『血の記憶』も、サレントならではの風景や風習のなかで物語が展開されていました。
古賀 ある地域を舞台にした作品では方言も多用されるので、イタリアでの上映時にイタリア語の字幕がついていることもありますね。ルキーノ・ヴィスコンティ監督の初期の作品『揺れる大地』では、シチリアの貧しい漁村に暮らす人々の過酷な暮らしが描かれていましたが、セリフはすべて方言なので標準イタリア語のナレーションがついていました。
岡本 たしかにイタリアは土地によって街並みだけでなく、方言も違うし、人の気質も違う。それを見るのも、イタリア映画の大きな楽しみですね。

監督によって「イタリア」のイメージは変わる?
岡本 イタリア映画の特質には、監督の個性もあります。一人一人が独自の世界観をもっていて、型にはまらず自分の眼を通して好きなように描いている。文学作品や実際に起きた出来事をドキュメンタリー風に撮る作品もたくさんありますが、そこにも監督独自の解釈が表れています。ヴィスコンティの『山猫』は、イタリア統一戦争を背景にシチリア貴族が没落していく姿を描いた作品ですが、歴史上「イタリア統一の立役者」と位置づけられているガリバルディを、「北部から来た乱暴者」というイメージでとらえていました。
古賀 イタリア語でリソルジメントと言われるイタリア統一運動を描いた作品は、けっこうありますね。2010年に統一150周年を記念してつくられたマリオ・マルトーネ監督の『われわれは信じていた』もそう。
岡本 あの作品では、ガリバルディと並んでイタリア統一の立役者とされているマッツィーニが、ほとんどテロリストのように描かれていました。時代考証より、監督の視点に重きが置かれているんですね。
マルコ・ベロッキオ監督は、1978年に当時の首相アルド・モーロが極左組織の赤い旅団に誘拐、殺害された事件を題材に『夜よ、こんにちは』を撮りましたが、この作品は途中からファンタジーの世界に入ってしまう。事実を追求していくのではなく、こういう解釈も成り立つ、という見せ方をしています。リアルな事件を取りあげながら、次第にファンタジーになるというのもイタリア映画の特徴ですよね。
古賀 そうですね。40~50年代は現実をそのまま描写したネオレアリズモ(新しいリアリズム)映画の全盛時代でした。代表的な作品をあげると、ロベルト・ロッセリーニ監督の『無防備都市』や『戦火のかなた』、ヴィットリオ・デ・シーカ監督の『自転車泥棒』などですね。僕はネオレアリズモがイタリア映画の原点だと考えていて、そのリアリズムの伝統は今も受け継がれていると思っています。ただネオレアリズモ以降の作品は、リアリズムを追求しているうちファンタジーの要素が入り込んでくる。フランスのリアリズム映画にはファンタジーの要素は見られないので、これもイタリア映画の特徴ですね。
岡本 そうそう。フェデリコ・フェリーニ監督も最初はロッセリーニの『無防備都市』の脚本を書くなどネオレアリズモから出発しましたが、徐々に彼の「心の眼」みたいな描写がでてきて、ファンタジーに近づいていった。初期作品の『道』にしても、現実なのかファンタジーなのかわからないところがあります。
イタリアの有名な文学者にイタロ・カルヴィーノという人がいて、彼も自らのパルチザン体験をもとにしたネオレアリズモ小説からからスタートして、だんだんファンタジー作品も書くようになった。現実の辛い出来事を想像力でふくらませて夢のある世界に発展させる、というのがイタリア人は好きですよね。
古賀 それはありますね。2000年以降で言えば、ジャンフランコ・ロージ監督がレアリズムにファンタジーをプラスしたドキュメンタリー作品を撮っています。ローマ市内を取り巻く環状高速道路の周辺に暮らす人々を映した『ローマ環状線、めぐりゆく人生』もそう。最近ではイラクやシリア、レバノン、クルディスタンなど紛争が長年つづく地帯の人々を追った『国境の夜想曲』が日本でも公開されました。
岡本 ロージ監督にインタビューしたとき、何故ドキュメンタリーばかり撮るのか聞いたら、「ドキュメンタリー映画と劇映画の違いを感じたことがない」と言っていました。ドキュメンタリーには撮る監督の視点が入っているので、同じ現実をとらえても映像にはその監督なりのドラマ性があるという意味だと、僕は解釈しています。
古賀 なるほど、そうですね。

イタリア映画は監督不在でも完成する?
古賀 イタリア映画を語るときに欠かせないものに、映像の美しさがありますね。
岡本 イタリアの映像はすごいです。古くはミケランジェロ・アントニオーニやフェリーニ映画の撮影監督をしていたジャンニ・ディ・ヴェナンツォや、ピエル・パオロ・パゾリーニやセルジョ・レオーネの映画を撮影したトニーノ・デッリ・コッリ、ほかにもジュゼッペ・ランチ、カルロ・ディ・パルマとか名撮影監督がたくさんいる。カルロ・ディ・パルマはアントニオーニのカラー作品で腕を奮い、後年はアメリカでウディ・アレンと組んでいました。
古賀 ディ・パルマはベルトルッチの『ある愚か者の悲劇』も撮影していますね。
岡本 そう、1作だけベルトルッチと組んでいました。でもベルトルッチ作品の撮影監督と言えば、やはりヴィットリオ・ストラーロですよね。『暗殺のオペラ』以降ずっと組んでいたストラーロの感覚は素晴らしいんですが、あの映像は監督がベルトルッチだったからこそ撮れた。
古賀 撮影監督があまりにうますぎて、見終わったあと映像だけが印象に残ってしまうということはありませんか?
岡本 ありますね。ストラーロとランチは油絵のようなまったりした美しい映像を撮るんですが、作品によっては絵が勝ちすぎてしまう。
古賀 ということは、一流の撮影監督を、監督が使いこなせていないと。
岡本 その通りですね。フェリーニの『8 1/2』の硬い感じの映像はディ・ヴェナンツォでなければ表現できなかったと思いますが、彼が撮影したほかの作品には映像が勝ちすぎているものがけっこうあります。映画の物語より自分が撮る映像に興味が傾いてしまったのでしょうね。
近年の映像監督ではルカ・ビガッツィが随一ですが、何人かの監督に取材したところ、ビガッツィとディ・パルマは物語のなかで自分が撮る映像がどういう意味をもつのかを意識しながら撮影している、と言っていました。
古賀 なるほど。それにしてもイタリア人は映像のセンスが抜群ですね。これは映画の歴史が始まる前から脈々と受け継がれてきたものだと思います。
岡本 そうですね。マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督の『輝ける青春』などの脚本を書いているサンドロ・ペトラッリャが、「イタリア映画は脚本があってまともな撮影監督がいれば、監督不在でも完成する」と言っているくらいです(笑)。

傑作を支えた作曲家 エンニオ・モリコーネとニーノ・ロータ
古賀 イタリア人は映像と同じように音楽のセンスも素晴らしい。それも映画によく活かされていますね。60年代から70年代初めにかけて日本で大ブームになったマカロニウエスタンも、音楽が実に効果的、印象的でした。まあ、マカロニウエスタンは、イタリア映画だと思わずに見ていた人が多いかも知れないですが。
岡本 僕もマカロニウエスタンはマカロニウエスタンとして見ていました(笑)。監督と作曲家という組み合わせでは、『荒野の用心棒』や『夕陽のガンマン』を撮ったセルジョ・レオーネ監督とエンニオ・モリコーネのコンビが素晴らしい。モリコーネは非常に多作な人ですが、レオーネ監督の作品には特に感情を揺さぶる曲を提供していました。
古賀 レオーネとモリコーネはローマの小学校で同級生だったんですね。
岡本 そうそう、「お前が学校でいびきをかいて寝ていたのを知ってるぞ」という、レオーネがモリコーネに書いた葉書きが残ってる(笑)。レオーネ監督は登場人物のキャラクターで音楽をつけるんです。『ウエスタン』でジェイソン・ロバーズが演じたシャイアンの音楽をモリコーネに頼むときは、「ディズニーの『101匹わんちゃん』のイヌの感じ」みたいな説明をしたとか(笑)。
『ウエスタン』は冒頭から14~5分、3人の殺し屋が駅でじっと人を待っているシーンがつづきますが、その間音楽は一切流れない。レオーネがモリコーネにそのシーンを見せたら、「風や風車の音そのものが音楽になっているから、ここに音楽をつける必要はない」と言ったらしい。
古賀 『ウエスタン』はレオーネの頂点だと僕は思っています。日本では誰もレオーネを「大監督」と言わないけれど、もっと評価されてもいいですよね。
岡本 レオーネは大監督ですよ。イタリアの監督は顔のクローズアップで登場人物の内面や物語を語るのがうまいですが、レオーネはその最高峰だと思う。「飢え」や「渇き」のような感情まで見事に表現できる作家です。マカロニウエスタンだけでなく、アメリカのギャングを描いた『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』も素晴らしい作品でした。
古賀 あの映画ではモリコーネが先に曲をつくり、出演者のロバート・デ・ニーロたちはその音楽を聴きながら演技をしたそうです。多分俳優はやりにくかったと思いますが(笑)。最近、ジュゼッペ・トルナトーレが監督したドキュメンタリー『モリコーネ 映画が恋した音楽家』が公開されたので、若い人たちにもぜひ見てほしいです。
岡本 イタリア映画の作曲家では、モリコーネとニーノ・ロータが別格ですね。ロータの場合は、フェリーニ監督作品の音楽と、ほかの監督に提供する音楽、たとえばヴィスコンティの『山猫』とかフランシス・フォード・コッポラの『ゴッドファーザー』では曲調がぜんぜん違う。フェリーニはあまり細かい要求をしなかったようですが、ロータがフェリーニの意図を汲んで、音楽だけでフェリーニ映画だとわかるスコアを書いていたんです。ロータは繊細で優しい人だったような気がします。
古賀 オペラの伝統があるイタリアでは、映画にも一般の人がオペラを歌うシーンがよくでてきますね。ヴィスコンティの『郵便配達は二度ベルを鳴らす』やフェリーニの『青春群像』にも地方都市のオペラ大会のような場面がでてきた。
岡本 『青春群像』でオペラ歌唱を聞かせたのは、フェリーニの弟リッカルドでしたね。各地方に音楽院があるイタリアには音楽の素養がある人が多いし、ロータもオペラやクラシック曲を多数作曲しています。モリコーネも映画音楽をある程度つくったら自分の好きなオペラを書くと言っていましたが、『続・夕陽のガンマン』の音楽なんか、すでにオペラですよ。
古賀 たしかにモリコーネとロータは別格で、2人とも故人ですが、メロディを聴いただけで映画のシーンが浮かぶ素晴らしい作品をたくさん残しましたね。
岡本 現在もルドヴィコ・エイナウディなど優秀な映画音楽の作曲家がいますが、レオーネのマカロニウエスタンにおけるモリコーネの曲のような、高らかに歌いあげる音楽は少なくなりました。
古賀 時代に沿って映画自体が変わっていくことによって、音楽の使い方も変化してきましたね。
今のイタリア映画は「犯罪映画」が多い
古賀 さきほど岡本さんは「80年代からイタリア映画の勢いが落ちてきた」とおっしゃっていましたが、今世紀に入る頃からまた活気がでてきていますね。近年の映画で、何か特徴的なことは感じますか?
岡本 犯罪映画がやたらとつくられていますね。2008年に制作された『ゴモラ』がイタリアで大ヒットしたあたりからかな。『ゴモラ』はマッテオ・ガッローネ監督の作品で、ナポリを拠点とするマフィア組織「カモッラ」を題材にしています。原作はロベルト・サヴィアーノのノンフィクション本(邦題『死都ゴモラ』)で、市の有害廃棄物処理業を牛耳っているなど、カモッラが社会や経済に深く入り込んでいることが、映画でもリアルに描かれている。この映画には非職業俳優が多く使われていますが、そのなかには実際の犯罪者もいるんです。俳優と非職業俳優を混ぜて使う映画はイタリアに多いんですが、ガッローネ監督はそれがうまい。非職業俳優ともフランクに接しながら「リアル感」を引きだすんです。
古賀 『ゴモラ』はカンヌ映画祭でグランプリを獲りましたが、画面を通して登場人物たちの不安が伝わってくる重い作品ですね。ガッローネ監督が2018年につくった『ドッグマン』はドッグサロンを経営する温厚な男と、ひどく狂暴な彼の友人を中心にした映画ですが、これもまたずっしり重いというか、怖い。
岡本 ほんと、見たあと食事が喉を通らないぐらい怖かった。これが実際の殺人事件をベースにしてつくられたと思うと、余計に怖い。ガッローネ監督自身は、フランクでにこやかな人なんですけどね。
古賀 俳優でもあるミケーレ・プラチド監督が撮った『野良犬たちの掟』も犯罪映画ですね。ローマの不良少年たちが成長してギャングになる物語で、2007年の「イタリア映画祭」で上映したときは『犯罪小説』というタイトルでしたが、その後劇場公開されるとき『野良犬たちの掟』とタイトルが変わった。これも実話なんです。
岡本 実話の犯罪映画が多い。新しい作品では、2017年に制作された『シシリアン・ゴースト・ストーリー』が、90年代初めにシチリアで起きた少年の殺人事件を描いています。少年の父親はシチリアマフィアのメンバーで、仲間を裏切って警察に協力したら息子が見せしめに誘拐されてしまうという悲惨な事件なんですが、映画では原作にはでてこない少女を登場させて、ファンタジーをまじえた素晴らしい作品に仕上げています。監督はファビオ・グラッサドニアとアントニオ・ピアッツァという2人のシチリア人で、ルカ・ビガッツィの映像も最高です。
古賀 現在のイタリアの映画を代表する監督と言えば、先ほど話題にでたマッテオ・ガッローネと、パオロ・ソレンティーノあたりでしょうか。
岡本 そうですね。ソレンティーノ監督は、ガッローネ監督とは対照的に、華麗なる映像をつくり込むタイプです。音楽との合わせ方もうまいし、見る者をあっと言わせる力をもっている。2013年の『グレート・ビューティ― 追憶のローマ』では、ローマでの優雅な生活が描かれてフェリーニの『甘い生活』へのオマージュでもあるのですが。イタリア映画界におけるフェリーニの影響は巨大ですね。
ガッローネ、ソレンティーノに加えて、アリーチェ・ロルヴァケルも現在の代表的な監督だと思います。若い監督でまだ作品は少ないんですが、長編2作目の『夏をゆく人々』でカンヌ映画祭のグランプリを受賞しました。トスカーナ地方で養蜂を営む家に生まれた少女の物語で、半自伝的な作品と言われていますが、これも途中からファンタジーになっていく。僕が見るところ、ロルヴァルケルの作品がいちばんフェリーニっぽいですね。
古賀 なるほど。久しぶりに岡本さんとじっくりお話しして、イタリアが今も映画大国であることが改めて確認できました。今日はありがとうございました。

(取材・構成:浅野恵子 撮影:内藤サトル)
プロフィール

古賀太(こが ふとし)
日本大学藝術学部映画学科教授。専門は映画史、映画ビジネス。1961年生まれ。国際交流基金勤務後、朝日新聞社の文化事業部企画委員や文化部記者を経て、2009年より現職。著書に『美術展の不都合な真実』、訳書に『魔術師メリエス』など。現在も続く「イタリア映画祭」を2001年に立ち上げ、同年に「イタリア映画大回顧」、2004年には「ヴィスコンティ映画祭」を企画。「イタリア連帯の星」勲章騎士章を受章。
岡本太郎(おかもと たろう)
一九六〇年東京生まれ。早稲田大学文学部卒業。東京大学大学院イタリア文学科修士課程修了。旅・映画・音楽を中心とするライター、翻訳家、非常勤教員。また、写真も手がけている。


 古賀太×岡本太郎
古賀太×岡本太郎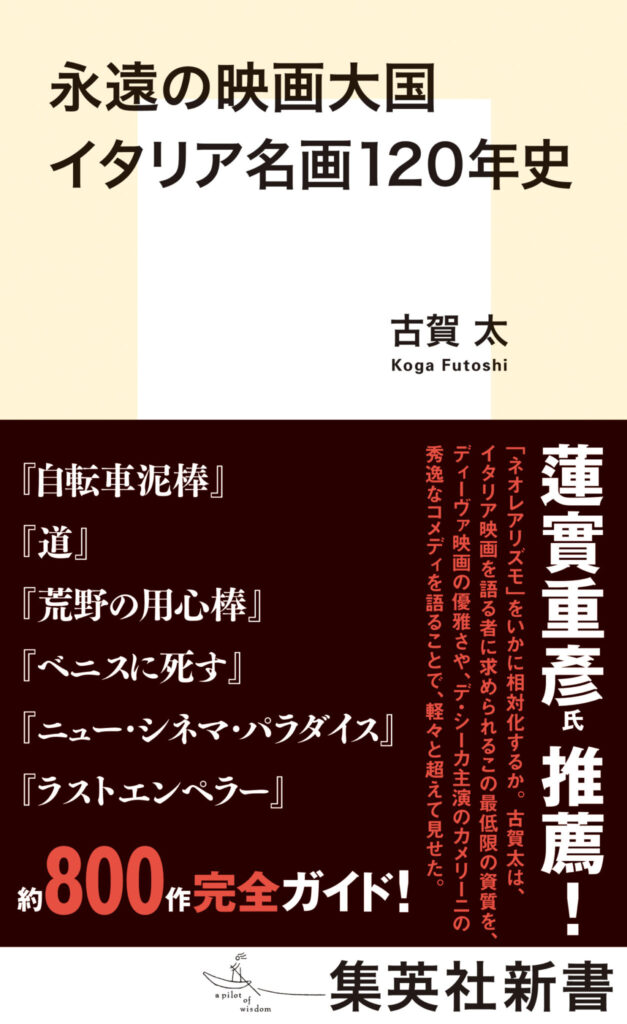










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

