数多くの名作が生まれ、日本映画にも多大な影響を与えたイタリア映画。しかし、ここ日本ではハリウッド映画、フランス映画、韓国映画に比べて、その歴史や魅力が振り返られる機会が少ない。
2月17日に刊行された書籍『永遠の映画大国 イタリア名画120年史』では19世紀から現代までの120年を、約800の作品とともに通覧。イタリア映画の歴史を紐解く1冊となっている。
本記事では、日本大学芸術学部映画学科の教授を務める著者の古賀太氏と、『ヴィスコンティを求めて』をはじめとしてイタリア映画についての文章を数多く残している映画評論家の柳澤一博氏が対談。イタリア映画は日本でどのように受容されてきたかを振り返る。
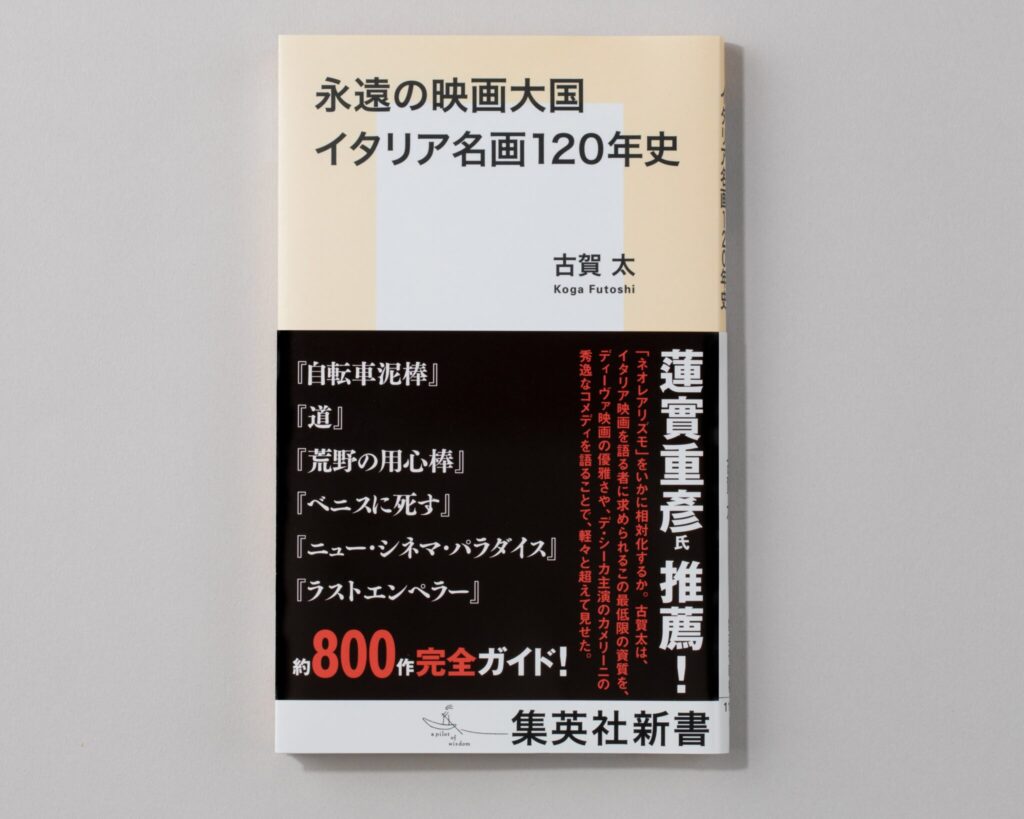
今の学生はイタリア映画を知らない
柳澤 古賀さんは10年ほど前から大学で映画を教えていらっしゃるそうですが、今の学生たちはイタリア映画をどうとらえていますか?
古賀 残念ながら学生にはあまりリスペクトされていないんです。21世紀に生まれた学生は、イタリア映画が年間70本も80本も上映されていた黄金期を知らないし、作品も監督もほとんど知らない。彼らにとってアメリカ映画の次に身近なのは、韓国映画や中国映画のようです。
柳澤 授業で題材にしているのは、どんなイタリア映画ですか?
古賀 去年は著名な監督の初期作品を多く取り上げました。たとえばルキーノ・ヴィスコンティの『夏の嵐』、『揺れる大地』、ベルナルド・ベルトルッチの『革命前夜』、『暗殺の森』、ロベルト・ロッセリーニの『無防備都市』や『戦火のかなた』、あとピエル・パオロ・パゾリーニの『アッカトーネ』とか。
柳澤 50年代から60年代の名作ばかりですね。その時代のネオレアリズモ映画は演技が今よりオーバーでしたが、学生たちにはどう映るんだろう?
古賀 演技に関しては「ちょっとやり過ぎ」という感想がありますね。あと、戦争を背景にした映画や宗教的、思想的な映画は今の学生たちにいま一つ伝わらない。ヴィスコンティ作品でも、19世紀にオーストリアがヴェネツィアを併合した時代を舞台にした『夏の嵐』は人気がなかった。敵国の兵士に恋をして狂うヴェネツィア女性貴族の姿は、今の若い人には理解されなかったようで。
柳澤 ああ、今どきは恋に狂うこともないのかもしれないですね(笑)。でも、戦争は現在もつづいているし、舞台をロシア占領下のウクライナに置き換えて見れば、リアリティが増してあの映画をもっとよく理解できるかもしれません。
古賀 たしかに。でも、第二次世界大戦末期のイタリアをリアルに描いた『無防備都市』や『戦火のかなた』にも、あまり反応がなかった。ロッセリーニ作品は、第二次大戦後にイタリアの難民キャンプにいるリトアニア女性を描いた『ストロンボリ』も見せたんですが、やはり関心は薄かったですね。
柳澤 ロッセリーニは『神の道化師、フランチェスコ』が若者にも受けるんじゃないですか? 宗教的ではありますが、洗練された映画ですし。
古賀 いいですね、あの映画。おかしさもあるし、すごく深い。柳澤さん、今度授業に来て解説してくださいよ。
柳澤 いえいえ、とんでもない。ヴィットリオ・デ・シーカ作品は取り上げないんですか?
古賀 あ、デ・シーカが意外と人気なんです。去年『自転車泥棒』と『ウンベルトD』を見せたら、両方とも評判がよかった。40年代後半から50年代にかけての戦後復興期の話なんですが、それが現在の学生に受けている。貧しさゆえに自転車を盗んだり、定年まで勤めあげても年金で暮らせない人たちの物語が「身につまされる」と言うんです。ヴィスコンティ作品にしても、貧しい漁村が舞台の『揺れる大地』にはみんな感動していましたね。
柳澤 貧しい戦後復興期の描写が今の時代に共感を呼ぶなんて、ちょっと複雑な気がしますね。映画は教室のスクリーンで見るんですか?
古賀 そうしたいんですが、90分授業で全編みられる映画は少ないので、作品を決めて家で見てきてもらいます。アマゾンに月額500円の学生向け映画見放題プランがあって、学生にはその会員になってもらう。学生が家で見てきた作品の大事な場面は、ブルーレイを使って学校でも大画面で見せています。
柳澤 へえ~、今はそういう授業の進め方もあるんですね。
古賀 ヨーロッパ映画を知らずに育った学生たちも、映画の歴史がわかるようになるとゴダール作品などフランスのヌーヴェルヴァーグ映画を見るようになります。そこで僕は、「こういう自由な作風の原点はイタリア映画にあるんだ」と学生にイタリア映画を勧めるわけです(笑)。
柳澤 なるほど。ほかに評判のよかった作品というと?
古賀 ベルトルッチの『暗殺の森』は、みんな「かっこいい!」と驚いていました。70年代のイタリア映画は色がきれいですし、『暗殺の森』はそのうえスタイリッシュでストーリーが謎めいていて、人気があります。

イタリア映画の黄金期は70年代
柳澤 古賀さんの「イタリア映画愛」はすごいですね。それが講義や今回の新書に結びついている。意外なことにイタリア映画史の本は、今までに1953年と1976年の2冊しかでていませんでした。そのうち1976年の方はイギリス映画とイタリア映画の本なので、古賀さんの本は貴重です。サイレント映画から現在の映画まで順を追って辿ることで、イタリアの現代史も見えてきますね。映画は社会を映す鏡でもありますから。
古賀 柳澤さんには今回の本もゲラの段階でチェックしていただきましたね。大学生の頃からイタリア映画を愛していた僕にとって、映画評論界で唯一イタリア映画を専門にしていらした柳澤さんは「先生」なんです。イタリア映画の情報が書かれている文章を見ると、ほぼ全部に柳澤さんの署名がついていた。
2001年に「イタリア映画祭」と並行して「イタリア映画大回顧」を開催したときは、カタログ本に原稿を書いていただきましたね。あの文章を読んだときは、非常に驚きました。それまで僕は、「黄金期」と呼ばれたネオレアリズモ時代の映画にばかり目が向いていたんです。ところが柳澤さんが、「70年のイタリア映画は、多才な映画作家の才能が開花した、もうひとつの黄金期ではないかと思う」と書いていらして、ハッとしました。
柳澤 ネオレアリズモの映画は確かに素晴らしいけれど、ちょっと画一的で、教条主義的な傾向がありましたよね。70年代に入ると、ネオレアリズモ映画を撮っていた監督が円熟期に入って個性的な作品を発表したり、新しい才能が現れたりします。ヴィスコンティの『ベニスに死す』は第一級の芸術作品で、強い感銘を受けました。ほかにフェリーニの作品では『ローマ』や『アマルコルド』、『カサノヴァ』、それにベルトルッチの『暗殺の森』、『ラストタンゴ・イン・パリ』、カヴァーニの『愛の嵐』も70年代を代表する作品ですね。
古賀 たしかに70年代には監督の個性が際立つ作品がたくさん生まれましたし、スケールも壮大で豪華な時代でした。80年代に入ってもその流れはあって、ベルトルッチの『ラスト・エンペラー』などは、まさに大スペクタクル映画ですね。
柳澤 一方でイタリアには、社会派の映画も多い。面白いことに、ネオレアリズモの時代から70年代、80年代にかけて活躍した監督の大半は、左翼のシンパなんです。彼らは中産階級出身のインテリでした。ヴィスコンティは北イタリア有数の貴族の家系に生まれながら共産党員でした。フランチェスコ・ロージもベルトルッチも左派の映画監督で、社会主義的なイデオロギーを映画に込めていましたね。しかしそれが単なる左翼映画にはならず、国際的な大スターが出演する娯楽作品に仕上がっている。ベルトルッチの『1900年』なんか、ロバート・デ・ニーロ、ジェラール・ドパルデューという米仏のスター俳優を起用して商業映画に仕立てていますが、ファシズムを強烈に批判していましたしね。
古賀 反ファシズムというのは、たしかに往年のイタリア映画の大テーマでした。イタリア映画はやっぱり歴史や社会の学びにつながりますね。

80年代の「ヴィスコンティ・ブーム」の背景
古賀 柳沢さんはイタリア映画のなかでも特にヴィスコンティ研究の第一人者ですが、ヴィスコンティとの出会いがイタリア映画との出会いでもあったんですか?
柳澤 はい。17歳でヴィスコンティの『ベニスに死す』と出会って、人生が狂いました(笑)。まともな職業に就かないで、名画座を巡ってヴィスコンティ作品はもちろんイタリア映画を見まくっているうち、それが仕事になったんです。
古賀 ヴィスコンティ映画のどこにいちばん惹かれたんでしょう?
柳澤 まず映像の美しさですね。カメラワークも素晴らしいんですが、そこに映しだされるセットや衣装がまた豪華で、オペラの国の美的感覚に圧倒されました。出演している俳優陣も素敵でしたね。
古賀 イタリア人監督のなかで日本ではヴィスコンティがいちばん有名だと思いますし、80年代に大ブームが起きました。でもそれは、ヴィスコンティが亡くなったあとだったんですよね。
柳澤 そうなんです。70年代、僕は日本の映画配給会社にヴィスコンティの魅力を懸命に説いて回ったんですが、全然理解してもらえませんでした。「この映画に何の意味があるの?」という反応で。でも当時の映画会社は鷹揚で、ヴィスコンティの『ベニスに死す』や『地獄に堕ちた勇者ども』のスチール写真を大量に焼いてくれました。その膨大なスチール写真をシーン順にならべて楽しんだものです。当時はビデオがなかったので、映画を所有することができなかったので。
古賀 へえ、それはまた貴重な体験をしましたね。ヴィスコンティのブームがやってくるのは、79年に公開された『家族の肖像』が記録的なヒット作になったのがきっかけでした。つづいて『ルードヴィヒ』、『イノセント』が公開されてまたヒットしたので、さらに古い作品も紹介されて、遂にはPARCOでヴィスコンティの展覧会まで開かれた。
柳澤 そうでしたね。ヴィスコンティ自身は76年に亡くなったので、『家族の肖像』も日本では死後に公開されたんです。
古賀 80年代から日本は景気が上向いてバブルに向かいましたが、その時代の空気のなかで、ヴィスコンティの貴族的で耽美な世界が受けたんでしょうね。
柳澤 まさにそう。いくらヴィスコンティの代表傑作でも貧しい漁師を描いた『揺れる大地』では、当時の日本ではヒットしなかったでしょう。それにしても、ブームのおかけで17作すべてが日本で公開されたのはうれしかったです。ほかのイタリア人有名監督で全作日本公開された人は少ないですものね。
古賀 ヴィスコンティのほかはフェリーニとベルトルッチだけです。
柳澤 有名監督作品だけでなく、イタリア映画には日本未公開の傑作もたくさんある。それを思うと、未公開作品も網羅している古賀さんの本はとても意義がありますね。
古賀 ジャンルで言うと、「イタリア式喜劇」と呼ばれていた作品は、半分以上日本未公開です。
50年代後半から60年代に数多くつくられていたんですが、日本では喜劇は受けないと思って配給会社があまり輸入しなかった。
柳澤 喜劇で日本公開されたのは、マルチェロ・マストロヤンニなど有名な俳優が出演している作品が主でした。そのマストロヤンニが出演した『イタリア式離婚狂騒曲』は面白かったけど。
古賀 ピエトロ・ジェルミ監督の傑作ですね。出会ったばかりの男2人が車で疾走するディーノ・リージ監督の『追い越し野郎』も抜群に面白かったけど、評価されませんでした。今公開したら、多分若い層にも受け入れられると思うんですが。
僕がいちばん好きなのは、マリオ・モニチェッリ監督の『戦争・はだかの兵隊』です。第一次世界大戦下の物語で、大傑作なんですが、日本ではまったく評判になりませんでした。
柳澤 『明日に生きる』もモニチェッリ監督で、マストロヤンニがでていましたね。工場の労働運動の話で、僕は今まで見たイタリア式喜劇のなかで、あれがいちばんいいと思うけど。
古賀 たしかにいい作品ですけど、喜劇にしてちょっとはまじめすぎますよね。でもまあ、イタリアの喜劇は最後に主要な人物が死んだり、不幸になったりする作品が多い。戦後、国が急激な経済復興を目指すなかで、頑張って生きる人々をシニカルに描いて笑いを誘うのがイタリア式喜劇なんです。
柳澤 映画を見るときは、やはりそういう時代背景を知っていたほうが深く味わえますね。

自由な雰囲気が名作を生む
古賀 僕がイタリア映画のつくり方で不思議に思っているのは、1本の映画に脚本家が何人もいることなんです。作品によっては6人も7人も脚本家がクレジットされているので、どういう風に仕事を進めていくのだろうと思って。
柳澤 そう、ヴィスコンティ作品にも特に初期は脚本家がたくさんいました。どうやって分担していたんでしょうね。
古賀 ヴィスコンティ映画に関しては、以前スーゾ・チェッキ・ダミーコさんにお会いして、聞いたことがあるんです。
柳澤 えっ、すごいなあ! 彼女はヴィスコンティ映画には欠かせない人で、ほかにも多くの名作に関わっている大脚本家ですよ。
古賀 ええ、2010年に96歳で亡くなられましたけど、生前取材することができたんです。ヴィスコンティが映画をつくるときは、まずダミーコさんを呼んでストーリーや構想を話すんですって。彼女はそれをもとに骨格をつくり、自分の知らない世界がでてくるシーンは、別の脚本家に頼んでいたそうです。
柳澤 「ドイツ文学には造詣が深くないから」と言って、いわゆるドイツ三部作(『地獄に堕ちた勇者ども』、『ベニスに死す』、『ルードヴィヒ』)の脚本執筆を断ったとか。でも、『ルートヴィヒ』(※初公開時の題名は『ルートヴィヒ 神々の黄昏』、復元完全版は『ルートヴィヒ』に改題)だけはヴィスコンティに懇願されて、脚本に加わったとか。
古賀 ヴィスコンティ自身もいつも脚本に加わっていましたし、イタリア人監督はほぼみんな脚本を書いていますね。フランス映画の場合はプロの脚本家だけが書いていたんですが、フランソワ・トリュフォーやジャン=リュック・ゴダールなどヌーヴェルヴァーグの監督たちが反旗を翻して、監督も脚本を書くようになった。イタリアのネオレアリズモ映画の制作方法を、フランスが後追いしたんです。
柳澤 イタリアの監督たちは、脚本家からスタートする人も多いですね。作風が違う監督同士が脚本や原案担当、助監督という形でつながりをもっていたり、意外な仲間関係が見られる。
古賀 そうそう。レオーネ監督の『ウエスタン』は、ベルトルッチとダリオ・アルジェントを呼んで原案をつくった。のちにイタリアンホラーの巨匠になるアルジェントが、マカロニウエスタンの原作をつくっていたのも面白いですね。
柳澤 要するに、イタリア人はみんなで集まってわいわいやるのが好きな国民なんですよね。フェリーニも常連俳優のマルチェロ・マストロヤンニたちと年中集まって楽しんでいたし。
古賀 さっき話題にでたヴィスコンティの脚本づくりにしても、仲間とコモ湖の別荘に寝泊まりして、毎日ご馳走を食べながらつくり上げていた。そういう自由な雰囲気のなかで名作が生まれていたんですね。

スペクタクルとスターの不在
古賀 80年代以降のイタリア映画については、どう思われますか?
柳澤 往年のようなスペクタクル作品をつくる監督はジュゼッペ・トルナトーレぐらいになって、大スターもいなくなりましたね。監督が作家に近い存在になって、まじめに人間を見つめるような作品が多くなってきた。
古賀 トルナトーレの『ニュー・シネマ・パラダイス』やロベルト・ベニーニの『ライフ・イズ・ビューティフル』など、世界的にヒットする作品は10年に一度くらい生まれていますが、大作は少なくなりました。いい監督は登場しているんですが、日常を誠実に描く作品が多いですね。
柳澤 それが僕には寂しいんですよ。今、世界中の社会が閉塞しているから、せめて映画ではとてつもない夢を見たい。映画では大ウソをついてもはったりをかましてもいいから、スペクタクルな作品をつくってほしんいです。
それにしても、改めて振り返ってみると、イタリアは本当に映画大国ですよね。アメリカやフランスも映画大国ではあるけれど、イタリアはトーキーの時代からあらゆるジャンルの映画が揃っていて、監督も俳優もスタッフも優秀な人を輩出しつづけてきた。その理由を古賀さんはどう考えていらっしゃいますか?
古賀 イタリアは映画に向いている国、なんだと思います。地方ごとに異なる美しい風景、文化的な背景、音や美に対する感性、すべて揃っている由緒正しい映画大国ではないでしょうか。
柳澤 さすが! 素晴らしい締めくくりの言葉ですね。
古賀 いやいや、今思いついただけです(笑)。今日はありがとうございました。

(取材・構成:浅野恵子 撮影:内藤サトル)
プロフィール

古賀太(こが ふとし)
日本大学藝術学部映画学科教授。専門は映画史、映画ビジネス。1961年生まれ。国際交流基金勤務後、朝日新聞社の文化事業部企画委員や文化部記者を経て、2009年より現職。著書に『美術展の不都合な真実』、訳書に『魔術師メリエス』など。現在も続く「イタリア映画祭」を2001年に立ち上げ、同年に「イタリア映画大回顧」、2004年には「ヴィスコンティ映画祭」を企画。「イタリア連帯の星」勲章騎士章を受章。
柳澤一博(やなぎさわ かずひろ)
1954年生まれ。映画評論家。2001年、イタリア貿易振興会よりライフインIスタイル賞(映画部門)受賞。


 古賀太×柳澤一博
古賀太×柳澤一博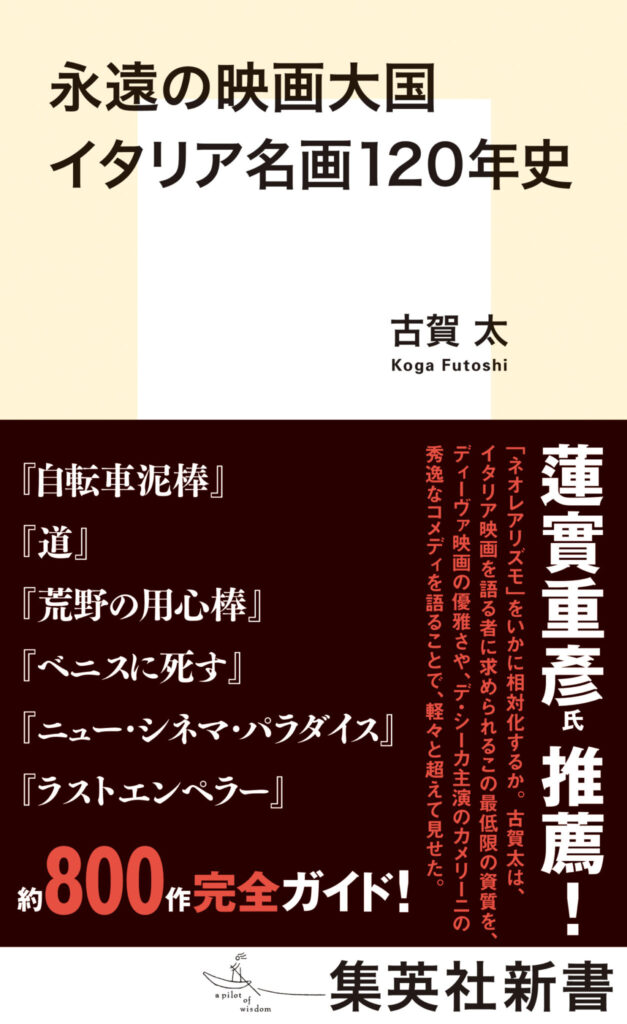










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

