いま就職先として人気を博している「コンサル」。その人気の裏側から、現代のビジネスパーソンが感じている「安定したいから成長したい」という空気を解き明かしたのが『東大生はなぜコンサルを目指すのか』である。
本記事では著者のレジー氏と、人材育成・組織開発を専門とする坂井風太氏とともに、数字や肩書にとらわれない生き方を考える。
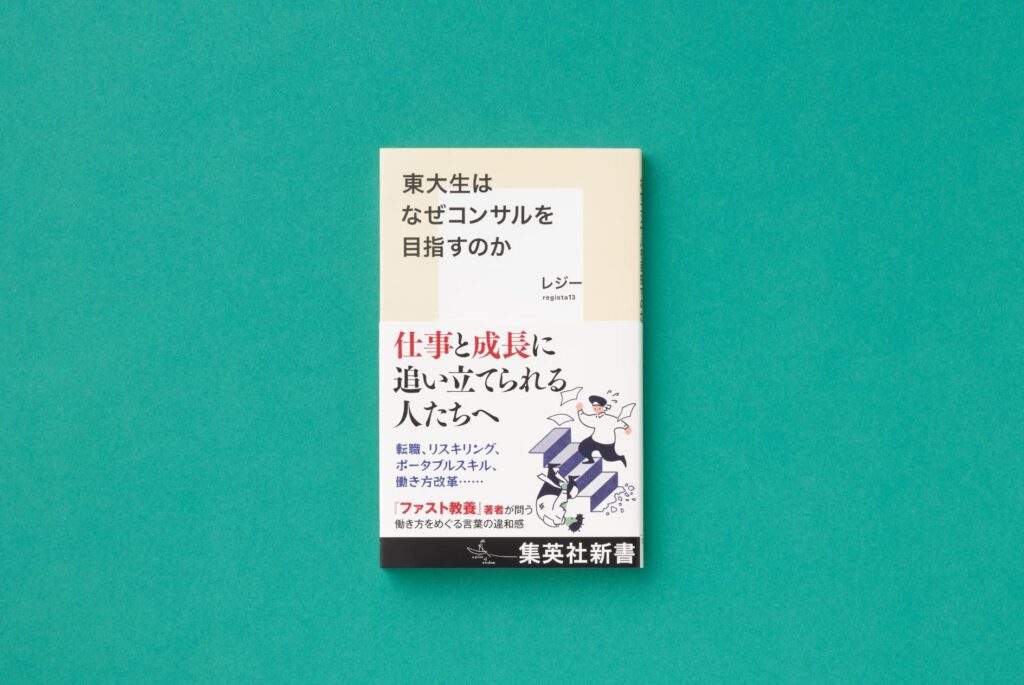
新しい宗教としての「成長」
坂井 現代の社会を見ていると、「成長」が「新しい宗教」になっていると思うんです。他の価値観や思想を持っていないから、それを信じるしかない状態になっている。それこそ、SNSを開けば「成長教」の実践者がいっぱいいます。そのひとつの現象が「〇〇フォロワーまであと何人です、フォローお願いします」と言っている人。あれは、一体何がしたいんだ、と思っていて。
レジー 「アカウントを育てる」ってやつですよね。
坂井 そうです。アカウントを育てる前に、自分の思想を育てる方が先のはずです。
レジー 前著の『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』でオリエンタルラジオの中田敦彦についていろいろ書きましたが、彼はなんだかんだ言っても人気タレントとしての地位があったのに、YouTubeに主戦場を移してからはその登録者数を増やすのに血まなこになっていました。「数字が増える」という目に見える結果が生む快感に囚われているわけですよね。
そう考えると、数字の力って本当に怖いと思います。カウントされると増やしたくなるし、人と並べられるとどうしても上回りたくなる。今ではあらゆるものが定量化される時代なので、数の圧力に包囲されてる状況ですよね。
坂井 僕の場合はXをマーケティングの道具だと割り切ってやっている側面があります。なので、特に「自分を知ってほしい」という気持ちも、実はありません。
レジー そこに関しては僕は逆かもしれないです。「レジー」という名前自体がSNSから生まれたものとも言えるし、こうやって対談の場なんてものを用意いただけるのもSNSがあったからこそなので、「マーケティングの道具」というような割り切りはできないんですよね。愛憎入り混じった感情というか。
坂井 なるほど。面白い。SNSだけじゃなくても、数値の快楽にハマっている人って永遠に月商マウントしてるじゃないですか。でも、その時点で「品がない」という状態になってしまう。月商以外に自尊心を保てる場所があれば、わざわざ喧嘩しないんじゃないかなと思います。
レジー そうなんですよね。「品がない」、今の時代にすごく重要なテーマだと思っていて。「それって品がないからやめたほうがいいよね」という考え方自体が失われているとよく思うのですが、数字で換算できるものが価値のすべてであるという考え方と密接につながっているように感じます。
坂井 そう思います。「品がない」とは何なのかについては、もう一冊本が書けるんじゃないですかね。

「ブランディング」の誤解
坂井 今の話を聞いて思ったのが「ブランド」のことです。ブランドも似たようなものだと思うんです。僕はブランド物に、今のところ興味が持てないんですよ。その理由を考えると、僕は「人に説明しやすいものはあまり価値がない」と思っているからだと気付いたんです。今まで話してきた問題の根源はそこなんじゃないかなって。フォロワー数マウントも、コンサルを目指すのも就職ランキングの上位を目指すのも、人に説明しやすいもので揃えた人生を目指してるんですよね。
レジー その話は重要ですね。まさに、説明可能な指標を並べることをセルフブランディングと呼ぶ向きがあるじゃないですか。自分も仕事で関わっていた時期があるのですが、ブランドって「作るもの」というよりも「背中からにじみ出てくるもの」だと思うんですよね。
坂井 ああ、分かります。
レジー イメージが蓄積された結果として「この商品もしくはこの人といえばこういうことだよね」となるのがブランドの本質で、重要なのは普段の立ち振る舞いから醸し出されるもののはずです。キャリアの話でよく言われる「セルフブランディング」についてもそこが取り違えられていることが多いです。関連する話だと、よくベンチャー企業の経営者とか広報の人とかが「リブランディングしました」みたいなこと言ってるのがあまり好きじゃないんですよね。
坂井 まさに、セルフブランディングは「醸し出る」ものですね。
レジー そうです。「リブランディングしました、ってそれを決めるのはお前じゃないだろう」と(笑)。
坂井 多くのスタートアップがやっているのは、小手先リブランディングじゃないのかって思うところもあります。カッコいいムービーを作っていても、裏で不誠実な対応をしている社長・社員をよく見ますし。
レジー もちろん、企業としてビジョンを作ることは重要だと思いますが、それがイコールブランドの刷新とはつながらないですよね。
キャリアの話に関してもこういう問題はよく生じていると思います。本の話に引き付けると、 コンサルという「 職業のアクセサリー」を身に付けたらそれがブランドになると思っている人が多い。実際はそんなことはなくて、そこで何をなすかとセットじゃないとブランドにはならないわけですが。
「説明しやすいものに逃げるな」
坂井 僕は「分かりにくいもののほうが面白いだろう」と考えていて。思想の無さを隠すために、人に説明しやすい経歴や数字を揃える人生に何の意味があるのかなと思ってるんですよね。分かりやすい価値は、長期的に見るとあまり意味がないんですよね。他のものと比較しやすいから賞味期限が早いんです。
レジー 「すぐに役立つものはすぐに役に立たなくなる」という話ですね。『ファスト教養』でも触れました。
坂井 そうです。「説明しやすいものに逃げるな」が僕のテーマなんですよね。これには理由があって。前職のDeNAはKPI主義だったのですが、実際のサービスに一切触ってない人がKPIの設計をしているシーンをよく見ました。よ。一丁前にリーン・マネジメントの本とかを読んでくるんですが、その前にプロダクトを触れよ、と思ってしまう。
レジー プロダクトが使われる現場への理解がない状態でKPIがどうとか言っても机上の空論でしかないですよね。
坂井 彼らは理性とか知性を履き違えている。測定しやすいものイコール知性だと思ってんですが、それは意味がないんです。僕がそう感じていたときにアドルノ=ホルクハイマーを読んでいて、その中で「道具的理性」という言葉が批判的に出てくる。それで、自分の違和感はこれだなと思ったんです。目的を達成する最短ルートを導き出す理性が「道具的理性」で、いわゆる「説明しやすいもの」です。彼らは理性をそう捉えていた。数字化しやすいものが正義で理性だと思ってるのは滑稽ですよ。
レジー 「数値化」とか「客観性」とかはそれこそコンサルの仕事術といった文脈でよく出てくる話ですが、結局それもあくまでも一つの指標でしかないというスタンスは重要だと思います。
坂井 複雑な全体を分かりやすい部分に分けて理解しようとする、要素還元主義の暴走ですからね。仕事の現場でも「これってどうやって数字で測るんですか」と言ってる人は、多分自分の思想がなくて、何も考えてないんだろうと思ってしまいます。
レジー (笑)。その仕事の本質ではなく、説明しやすさの話だけになっているんですよね。
坂井 こういうKPI的な数値にこだわる現場にいたからこそ、説明しやすいものに対してアンチテーゼ的なポジションを取っているのかもしれないですね。
説明しづらいものと向き合い続けるために
レジー 実際、坂井さんに「どうやって数字で測るんですか?」という疑問が投げかけられてきたときは、どう返答するんですか?
坂井 「説明指標としてはこうですが、それはあくまで説明指標なので実態ではないと思います」と返しますね。
レジー なるほど。説明しづらいものを説明しづらいまま捉え続けることは体力が要るじゃないですか。特に、会社だと最終的に収益という数字がゴールになるわけで、そこに背を向けるのは難しい。でも、あくまでも数字は何らかの活動の結果であって、むしろその活動の中身に目を向けることこそ大事という認識を組織として持つ必要があるのかもしれないですね。
坂井 それと、そもそも多くの人が説明しやすいものに飛びつくのですが、本当に儲かるものは、本来説明しにくいはずじゃないですか。だから逆に「説明しにくいもの」はチャンスだと思っていますね。
レジー まだみんながその価値に気付いてないということですもんね。
坂井 そうです。それと、長期的に見れば「説明しづらいもの」を大切にすることがプラスになるんだ、という遅効性の価値を信じることが大事だと思います。SNSの投稿も、一番手軽に伸ばせるのは引用投稿じゃないですか。流行っている動画の引用投稿ばかりしている人がいますけど、これは遅効性の価値ゼロです。なぜなら自分でコンテンツを生み出す力がないから。自分でコンテンツを生み出す力が落ちるから、長期的に見ると、その人の中で何かが廃れていくんすよね。
レジー 「説明しづらいもの」や遅効性の価値を信じるのは本当に重要だと思います。じゃあ、どうやってそれを信じるかというとき、本にも少し書いているのですが、やはり「自己満足」みたいなものが大事だと僕は思っています。本当に自分の観点で良いと思うことを大事にするのが重要だと思う。ビジネスの世界だと少し前からN1分析といった形で「特定の個人」の重要性が言われていますよね。でもその割には、1人の価値観に立脚して何かを行うことへの許容度は高くない気がしています。だから、まず自分がどう思うか、ということから始めていけると、違う物差しを持てると思っています。

「居場所」を見つけること/作ること
レジー それと「SNSに載せない」ことも自分を見失わないために大事だと思う。数字で比較される磁場に載らない空間を持つことが重要ですよね。よく思うのが、サウナが好きな人たちはSNSを見なくていい場所に強制的に入ることでリラックスしているはずなのに、いざサウナを出たらすぐにそれをSNSに載せちゃうっていう。
坂井 あれ、意味がわからないです。本当にサウナ好きな人は、SNSやってないんじゃないですかね?
レジー 確かに(笑)。数字に絡めとられない場所を自分でいかに作るかが大事だと思います。
坂井 僕は、職場の組織作りを仕事にしているんですが、「成長」とかをずっと言ってるい人たちって、表ではそう言ってるんですけど、裏では結局、居場所が欲しいだけ、っていうのもよくあるんですよ。
中間共同体が消えてしまって「会社にいれば安心」とはならなくなったんですよね。地縁社会から切り離され、中間共同体からも切り離され、会社でも居場所を見つけ辛くなってしまった。社会学者のジクムント・バウマンが指摘したリキッドモダニティの状態ですよね。
レジー だからこそスキルを持って自分のキャリアを切り開け、みたいになってるけど、それだけでは不安になりますよね。
坂井 そうです。だから心の底から市場価値を上げなければいけないと思っているわけではなくて、本当に欲しいのは居場所なはずなんです。
レジー いまだに「エヴァンゲリオン」のテレビシリーズ最終回が説得力を持つことの証左ですね。
坂井 「ここにいていいんだ、おめでとう」で終わるのが未だに力を持っちゃう理由がすごく良くわかる。
だからこそ、自分の居場所というか、自分だけの時間を取り戻そう、という話なんですよね。それこそレジーさんは本の最後でジョブクラフティングについて書いてましたが、居場所もあるものではなく作るものだと思うんです。
レジー そうですね。居場所もきっと身近なところから作れますよね。
(構成:谷頭和希)
プロフィール

レジー
批評家・会社員。1981年生まれ。一般企業で経営戦略およびマーケティング関連のキャリアを積みながら、日本のポップカルチャーについての論考を各種媒体で発信。著書に新書大賞2023入賞作『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)のほか、『増補版 夏フェス革命 -音楽が変わる、社会が変わる-』(blueprint)、『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア、宇野維正との共著)。X(旧Twitter) : @regista13。
坂井風太
さかいふうた Momentor代表。1991年生まれ。DeNA新規事業部でのインターンを経て、2015年DeNAに新卒入社。DeNAトラベル(現エアトリ)に配属後、16年にゲーム事業部、17年に小説投稿サービス『エブリスタ』に異動。サービス責任者、組織マネジメント、事業統括を担当。19年にエブリスタならびにDEF STUDIOSの取締役に就任。20年にエブリスタ代表取締役社長、経営改革とM&Aなどの業務を経験。22年8月DeNAとデライト・ベンチャーズ(Delight Ventures)から出資を受け、人材育成・組織強化をサポートするMomentorを設立。


 レジー×坂井風太
レジー×坂井風太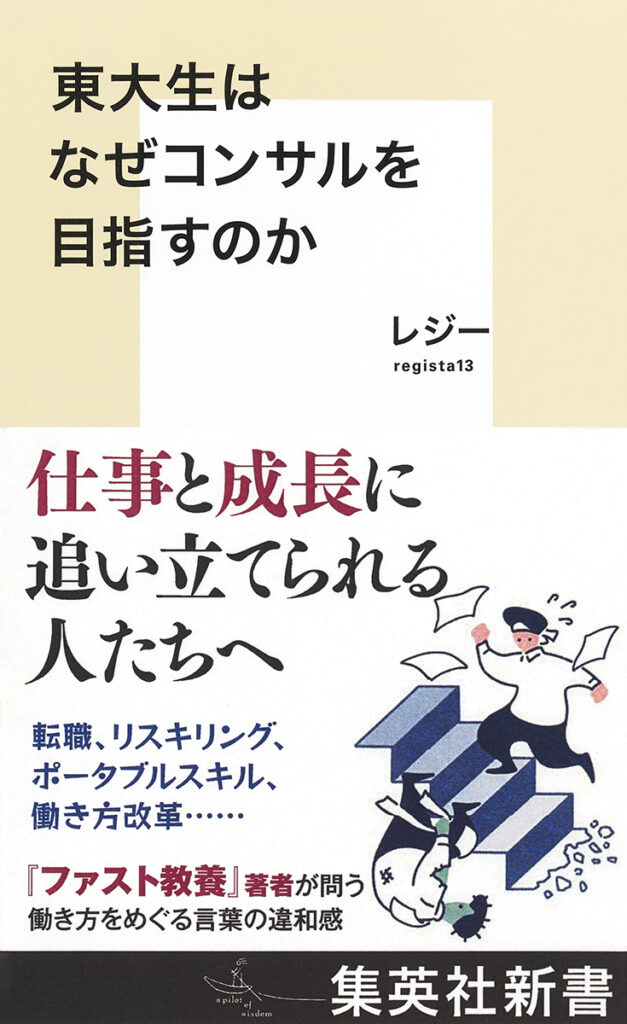










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


