大学時代に石牟礼道子の『苦海浄土 わが水俣病』との出会いで、文学への考え方が一変する衝撃を受けたという田中優子氏。10月に上梓した『苦海・浄土・日本 石牟礼道子 もだえ神の精神』は、水俣病闘争の側面以外、今まであまり語られなかった石牟礼文学を多様な視点から分析、考察し、その本質に迫る、評伝的文明批評です。
今回は人気ネット番組、【佐高信の隠し味】「学術会議と近代と石牟礼道子」(デモクラシータイムス)*1での佐高信氏との対談をウェブ用に編集、記事化したものです。田中氏とも共著『池波正太郎「自前」の思想』のある佐高氏との対談は、学術会議問題の真っ最中になりました。テーマは、石牟礼道子と近代から、傷つき痛みに耐える人の傍らでなすすべもなくただ身もだえするほかない人々への共感を経て、やはり学術会議問題へ。
今、権力と学問の世界の間で何が起きているのでしょうか?
構成=稲垣收/撮影=丸谷嘉長(佐高)、岩根愛(田中)
政治家に対してその都度言うべきことを言わないと
向こうは「何を言ってもいいんだ」となってしまう
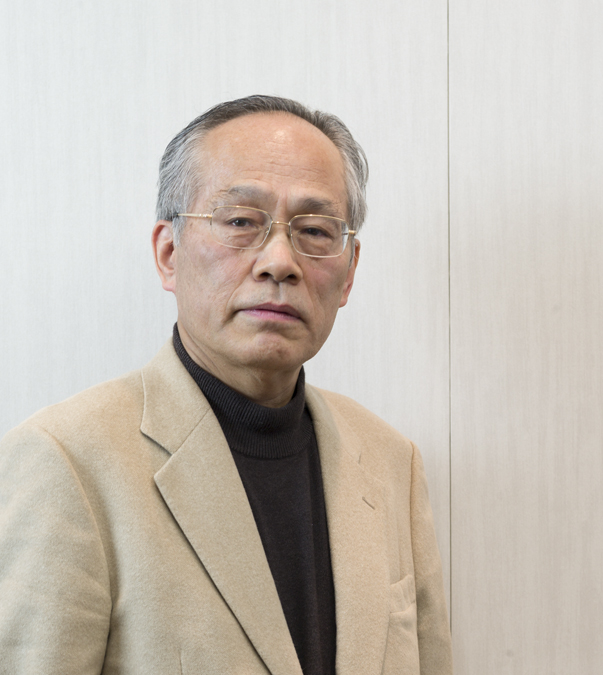 佐高 今日は法政大学総長の田中優子さんをお招きいたしました。今回、新しく総理になった菅義偉が、学術会議のメンバーのうち6人の任命を拒否するというとんでもないことをやって、それに対して田中さんは、非常に早い段階で抗議のメッセージ(*2)を寄せた。菅って人は法政大学の卒業生だし、いろいろ大変ではなかった?
佐高 今日は法政大学総長の田中優子さんをお招きいたしました。今回、新しく総理になった菅義偉が、学術会議のメンバーのうち6人の任命を拒否するというとんでもないことをやって、それに対して田中さんは、非常に早い段階で抗議のメッセージ(*2)を寄せた。菅って人は法政大学の卒業生だし、いろいろ大変ではなかった?
田中 出した後が大変でしたね。
佐高 自分の判断で出したの?
田中 そうです。周囲に文章の推敲や確認はしてもらいましたが。遅らせるわけにはいかない。いち早く出さねば、と。
法政大学に大学憲章というのがあって、その精神を守るためには放っておけない。今までいくつも総長メッセージを出してきたから、一貫性を持たせなければならない。そうしないと大学の理念や憲章が骨抜きになります。まず、それが一つの理由です。
もう一つは、今回の菅総理の任命拒否に関して「教養がない」とか「学問を侮辱している」とか、いろいろなことが言われていますが、そういうイメージが法政大学にもつきまとってしまう可能性がある。これは大学の名誉を傷つけることになるので、その二つの理由で、とにかく早く出すという決断をしました。
しかしその後、卒業生から批判や反発がありました。「大学のホームページに、どうして総長の個人の考えを載せるのだ」というのが複数寄せられたんですが、今まで総長メッセージをいくつも出してきて、そういうことを言われたのは初めてです。やはり初めて卒業生が首相になったということで、ものすごく喜んでいる方たちは、いらっしゃるんです。喜んでない方たちもいらっしゃいますが。喜んでいる方たちにとっては、突然冷や水を浴びせられたような気持ちになる、と。気持ちは分からないわけではないけれども、やっぱり出さざるを得なかった。
佐高 それと、以前に法政の教授に対してある一件があって、それに対するメッセージでもあるわけですね。
田中 2018年にその件でメッセージを出しています。裁量労働制のデータのありかたについて、求められて国会で専門家として意見陳述した本学の教授に対し、国会議員から根拠を示さない非難があった。また別の教員については、科学研究費に関して国会議員から、やはり根拠を示さない非難があった。科学研究費がどういう仕組みで採択され、どう配分されて、どうやって動いていくのかということを何も御存じない方たちからです。政治の現場から出てくるわけですから、やはり萎縮を招く。放っておけないと思いました。その都度、言うべきことは言っていかないと、「根拠なく何を言ってもいい」というふうになってしまう。「こういうことは、これからも放置できない」とその時に発信したのですが、今回も同じように、放置できないと思いました。
佐高 同窓とか同郷だと、他の大学の総長や学長が言うより、田中さんには圧力が来たんだろうなと、密かに心配しておりました。でも田中さんは萎縮とはほど遠くて、きちんと発言されたので、私は大いに拍手を贈っておりました。
石牟礼道子の本の朗読を聞いて
方言の力に衝撃を受けた
佐高 今回田中さんがお出しになった『苦海・浄土・日本 石牟礼道子 もだえ神の精神』と同じ集英社新書で、田中さんと私の『池波正太郎「自前」の思想』という名著があるんです(笑)。二人で池波正太郎や藤沢周平についていろいろしゃべってきたわけですが、今回の石牟礼道子さんも、秩序とか常識とか、そういうものを飛び越えている人ですね。そういうところに田中さんは興味を持って、石牟礼さんと50年も付き合っておられると。
 田中 はい。私が法政大学1年生のときに、古代文学者の益田勝実先生の授業を取っていたんですが、ある日、授業で突然、石牟礼道子が前の年に出したばかりの『苦海浄土 わが水俣病』(講談社、1969年刊)を取り上げて、朗読し始めたんです。これに非常に衝撃を受けましてね。
田中 はい。私が法政大学1年生のときに、古代文学者の益田勝実先生の授業を取っていたんですが、ある日、授業で突然、石牟礼道子が前の年に出したばかりの『苦海浄土 わが水俣病』(講談社、1969年刊)を取り上げて、朗読し始めたんです。これに非常に衝撃を受けましてね。
『苦海浄土』って熊本方言というか水俣方言で書かれているんです。方言の持っている物凄い力であるとか、言葉の力、それに大変衝撃を受けて「世の中にこういう文学があったのか」と思って。それで読み始めて、何かあるたびに、ずっと石牟礼さんについて考えてきた。
それから、編集委員を務めている『週刊金曜日』のお世話で、ようやく対談ができました。その前に渡辺京二さん(*3)ともお目にかかった。渡辺さんは法政大学の卒業生なんですが、そういう縁もあって、石牟礼さんにだんだん近づいていくことができた。お目にかかって、それをまた自分の中で反芻(はんすう)してという、そういう繰り返しがあって、初めて本が書けました。
おっしゃったように、石牟礼さんって社会の常識だとか、特にエリート階層が言うこととか、何も念頭に置かないんです。基本になっているのは自分の子ども時代です。小さい頃に水俣の何ヵ所かを移動していらっしゃるんだけど、その場所で何を知ったか、どういう経験をしてきたのか、特にご自分の祖母のこと、そういうことが軸になって、世の中や自然や世界を見ているんですね。
だから、チッソ(*4)の問題だけじゃないんですよ。私たちはどうしてもチッソの問題、水俣病の問題から石牟礼さんに近づいてしまうけれども、石牟礼道子全集を読んでいると、チッソの問題って、その中の本当に一部分で、全体としては、前近代に生きている人。前近代って、どういう物の感じ方をして、どういう価値観なのか、それを体現している人が本当に目の前にいるということが私には衝撃でした。
佐高 田中さんはあまり方言というのに、成長過程で接することがなかった?
田中 なかったですね。横浜の生まれですから、「~じゃん」とかの横浜的表現は多少ありますけど、そのぐらいで。
佐高 なるほど。それと大学1年の頃は真面目に講義に出ていた?
田中 講義そのものが少なかったです。1970年代で、学生運動で大学のロックアウトやバリケード・ストライキがまだ続いていましたので。でも授業が全部ないという状況ではなく、もう再開していたんです。私は勉強が面白くてしようがなかったので、とにかく出られるものは出ました。
佐高 でも、当時の法政大学総長だった中村哲(あきら)さんには紙つぶてを投げた?(笑)
田中 そうです。それは日々、両方共存しているわけです。時々、三里塚(での成田空港建設反対闘争)に行ったりするわけですから。授業にも出るけど、三里塚にも行く。集会で紙つぶても投げるし、でもゼミにも出ると。それが自然な状態じゃないですか。
佐高 ああ、そう(笑)。
石牟礼道子さんは、女性がなかなか生きにくいあの時代に、女の人の道筋というか一つの型というか、モデルみたいなのを切り開いていった人でもありますよね。この本には、石牟礼が詩人の高群(たかむれ)逸枝(いつえ)(1894~1964年)が書いた『女性の歴史』と出会って感動したという話も出てきますが。
田中 日本の女性解放運動って、すごく面白いと思うのは、高群逸枝につながるまで、平塚らいてう(1886~1971年)がいるわけですよ。平塚らいてうがやったことは、いわゆる政治的な女性解放運動じゃないわけです。人にはそれぞれ才能というものがあるんだ、その才能を拓きましょうね、あなた方にもそれはできます、と言っただけなんです。だけど、それが女性たちにたいへんな反響を生んでしまった。「元始、女性は太陽であった」という、らいてうの有名な文章がありますが、古代の女性はそうだった、今でもできるんだ、と言ったわけですよ。
それは当時、明治時代の女性たちもどこか感じていたことをズバリと言われたわけで、地方からたくさんの女の人が、感化されて東京に出てきた。その一人が私の祖母です。そういう始まり方をして、後に市川房枝と一緒に活動して政治運動に入っていくんだけれども……。片方で高群さんとか石牟礼道子とか、古代の女性像、前近代の女性像というものは手放さずに来ている、という気がします。
佐高 政治運動というより生き方を変えていく。でも、高群逸枝にも石牟礼道子にもサポートする男が出てくる。
田中 そうなんです。それが羨ましいですね(笑)。
佐高 なかなかできないですよね。高群逸枝も熊本あたりだっけ。
田中 そうです、そうです。
佐高 やっぱりあの辺、ちょっとあやしい感じが……。
田中 前近代のコミュニティーが残っていたんじゃないかという気がするんですよ。石牟礼さんの作品を読んでも、近代社会の中で何かに追いつかなきゃならない、というような考え方はそもそも持ってない。むしろ共同体の中で生きていく。その共同体というのは自然も含み込んだ共同体。
けれども男女ということになると、女性にあらゆることが押しつけられるような世界でもあるわけだから、矛盾はしているんだけど。男と女ということでもなく、家庭の中の役割ということでもなく、「それでも共同体は大事だ」という考え方を持つに至るんですよね。基本になっている「共同体感覚」を持っているんだと思う。
石牟礼さんは「近代って何だろう、とずっと考えていました」とおっしゃっていて。そういう場所に育った人たちって、近代社会になじめない、「何を自分が求められているんだろう」って、最後まで納得がいかないという感覚があったんじゃないかと思うんですよね。
方言を捨てさせる近代と
方言の持つ力
 佐高 私が山形から出てきたときに一番感じたのは、「近代というのは方言を捨てさせられるということ」なんですよ。「方言と言うのは、すさまじく恥ずかしいものだ」として。山形県鶴岡市で育った加藤紘一(元衆議院議員、元自民党幹事長)が、山形から麹町(こうじまち)中学に転校してくるんですね。そして教科書を読まされて、いきなり笑われるんです。特に女生徒からね。それが物凄く残る。方言というのは、私なんかも、すごく苦労しました。叩かれるわけ。言葉一つ一つに「えっ?」とか言われる。寮では庄内弁が飛び交っているんだけど、大学に行くと自分でもおかしいような標準語を使わなきゃならない。
佐高 私が山形から出てきたときに一番感じたのは、「近代というのは方言を捨てさせられるということ」なんですよ。「方言と言うのは、すさまじく恥ずかしいものだ」として。山形県鶴岡市で育った加藤紘一(元衆議院議員、元自民党幹事長)が、山形から麹町(こうじまち)中学に転校してくるんですね。そして教科書を読まされて、いきなり笑われるんです。特に女生徒からね。それが物凄く残る。方言というのは、私なんかも、すごく苦労しました。叩かれるわけ。言葉一つ一つに「えっ?」とか言われる。寮では庄内弁が飛び交っているんだけど、大学に行くと自分でもおかしいような標準語を使わなきゃならない。
田中さんは逆に、方言に衝撃を感じたというけど、こっちは方言を捨てなきゃ暮らしていけない。その意味で私なんかは、石牟礼さんのものに「もっともだ」と思う側面と、違和を感じる部分もあって。ちょっと巫女(みこ)さん的側面があるでしょう、石牟礼道子。
田中 ええ。
佐高 巫女的側面というのは、地方ではもっとすごい形で個人を縛るものとなってくるんですよ、封建社会ということも含めて。予言とか。
田中 なるほど、なるほど。
佐高 「都市は人間を自由にする」という言葉がありますけど、都市では匿名になれる。ところが田舎では匿名になれない。だから「匿名にしない親密性」というのと、息苦しさもある。田中さんが「共同体」というふうにこの本で書かれていますが、そこしかないんだろうとは思うんだけれども、すんなり頷けないものがある。
田中 よく分かります。
佐高 石牟礼道子という人のある種の役割と、「これはどういう形で切り拓いていくのか」ということが、次のテーマとして残る感じが、この本を読んだときにしましたね。
田中 石牟礼さんはほとんど東京にはいらっしゃらない、ずっと熊本、水俣にいらっしゃった。しかし自分が共同体だと思って暮らしているところが分裂するわけですよね。水俣病患者というのは、当初ものすごい差別の対象だったわけだから。チッソに病気にされたというだけではなく、地元を割ったことでもあった。共同体の破綻というのを見てきているわけです。
でも、考えてみれば近代社会というのは、常に共同体を破綻(はたん)させてきた。地方の中でもそれをやってきたわけです。たとえば法律で方言を禁じているわけではないけれども、全体を統合するような形で、それ以外のものを排除するという、そういう力が働いてしまっている。
こういうものが近代社会だから、ある意味で水俣病の側に立つことによって、そういうものへの抵抗の力というのは付けてきたんだと思うんです。
でもおっしゃるように、そのまま私たちがそれをできるのかとなると、運動のあり方だとか、物の考え方として、そのままは受け取れない。私は巫女にはなれない、ということも含めて。
日本社会の中での女性の立つ位置というのは、実はまだまだそんなに変わってないです、政治の世界でも企業でも。それを巫女的なもので乗り越えられるのかというと、決してそうではない。そういうところを「未来に向けるなら何が必要なのか」と、改めて考えなければならないんだろうと思いますね。
佐高 ただ、もちろん方言とか共同体が、抵抗のある種の拠り所になる側面はまだまだ多くて。例えば軍隊というのは、方言を許していては命令が通じない。だから方言を強制的につぶしていく。特に沖縄なんかで「方言札」(*5)というのがあった。方言をつぶすというのは、煎じ詰めれば軍隊のためですね、ある意味。だから逆に私は「方言力という力」なんてことを言ったこともあります。それは十分に抵抗の力になり得るし。
映画監督の羽田(はねだ)澄子(すみこ)さん(*6)と対談したとき聞いた話で、気難しいおじいちゃんが、看護婦さんとかがいろいろ話しかけても口聞かなかったんだけど、同郷の看護婦がいて、あるとき何気なく方言で話しかけたら、口を聞いたというの。方言にはそういう力があるわけ。閉ざされたものを開くとか、忘れていたものを思わず答えさせてしまうとか。
私も方言というものには、懐かしさはもちろんあるけど、ただ、そこに浸っていたら生活できなかったという葛藤があって……。
田中 分かります。共同体に腰を落ち着けて生きていくということが、だんだんできなくなってきますよね。
佐高 そう。
田中 本当にやむを得ず都会に出てきたり、あるいは出てこなくても東京的なるものの中で生きていく。企業に入るとか、学校に入るとかしながら生きていかざるを得ない。そのとき言葉というのは象徴的なものですよね。たぶん言葉だけじゃなくて、子どものときの暮らし方だとか、感性だとか、いろいろなものを自分で抑圧しながら、私たちは過剰適応しているんですよね。
佐高 ああ、はい。
 田中 そういうことを考えると、自分が生きるために何を自分で抑圧しながら生きてきたのかということを、個々人がもう一度ちゃんと見なきゃならない。自分の中を見なければならないんだと思うんです。やっぱりその葛藤がない人はいないんじゃないかと思うんです。
田中 そういうことを考えると、自分が生きるために何を自分で抑圧しながら生きてきたのかということを、個々人がもう一度ちゃんと見なきゃならない。自分の中を見なければならないんだと思うんです。やっぱりその葛藤がない人はいないんじゃないかと思うんです。
それで石牟礼さんだって、例えばよくお書きになるのが数字のことです。数字が苦手で、自分は場所もどこにいるのか分からないし、数字も分からないし、年代順に物を考えられないし、時間順に整理できない、と。でも、それなのに本を書けるというのは、それを支える人がいるからですよね。葛藤を抱えながらそばにいる渡辺京二さんのような方がいらっしゃるから。
苦しんでいる人のところに駆けつけ
気持ちを寄せていく「もだえ神」
佐高 田中さん、「もだえ神」という表現で何をあらわそうとしたの?
田中 「もだえ神」というのは、石牟礼さんがよく使っている言葉で、苦しんでいる人を見たときに、自分のことのような気がして、とにかくそこに駆けつけるけれども、ほとんどの場合に何もできない。何もできないけれども、一緒に気持ちを寄せていく。もだえるような気持ちとして寄せていくという、それをやる人のこと。そういうふうに動いてしまう、そういうふうに生きてしまう人のことをもだえ神っていうんです。だから、いろんなところにもだえ神的な人というのが、石牟礼さんの書くものに登場してきます。
佐高 それは胎児性水俣病の人とか含めて?
田中 含めて。あと小説の中で言えば、『春の城』という、これは天草の話なんだけど、天草四郎をもだえ神的なる人として設定しているんです。つまり自分のことではなくて他人のことに強い共感能力を持っている人と言えばいいんでしょうか。
佐高 ああ……。
ところで田中さんは、胎児性水俣病患者の坂本しのぶさんなんかの年齢なのね?
田中 そうです。胎児性水俣病の患者たちというのは、私とほぼ同世代なんです。「自分も生まれる場所がちょっと違っていたら、こういう事件の中の当事者になるんだ。そういう時代なんだ」と感じましたね。東京にいると分からないけれども。でも、そういうことが、実はいろんなところで起きている。
共感力というのが人間の中にはあって、それが強い人、弱い人ってあるんじゃないかと思うんです。そのときに相手が考えていること、言おうとしていることが、自分の言葉として出てきてしまう。石牟礼さんってそういう人なんだと思うんです。
あと半年で総長は辞めます
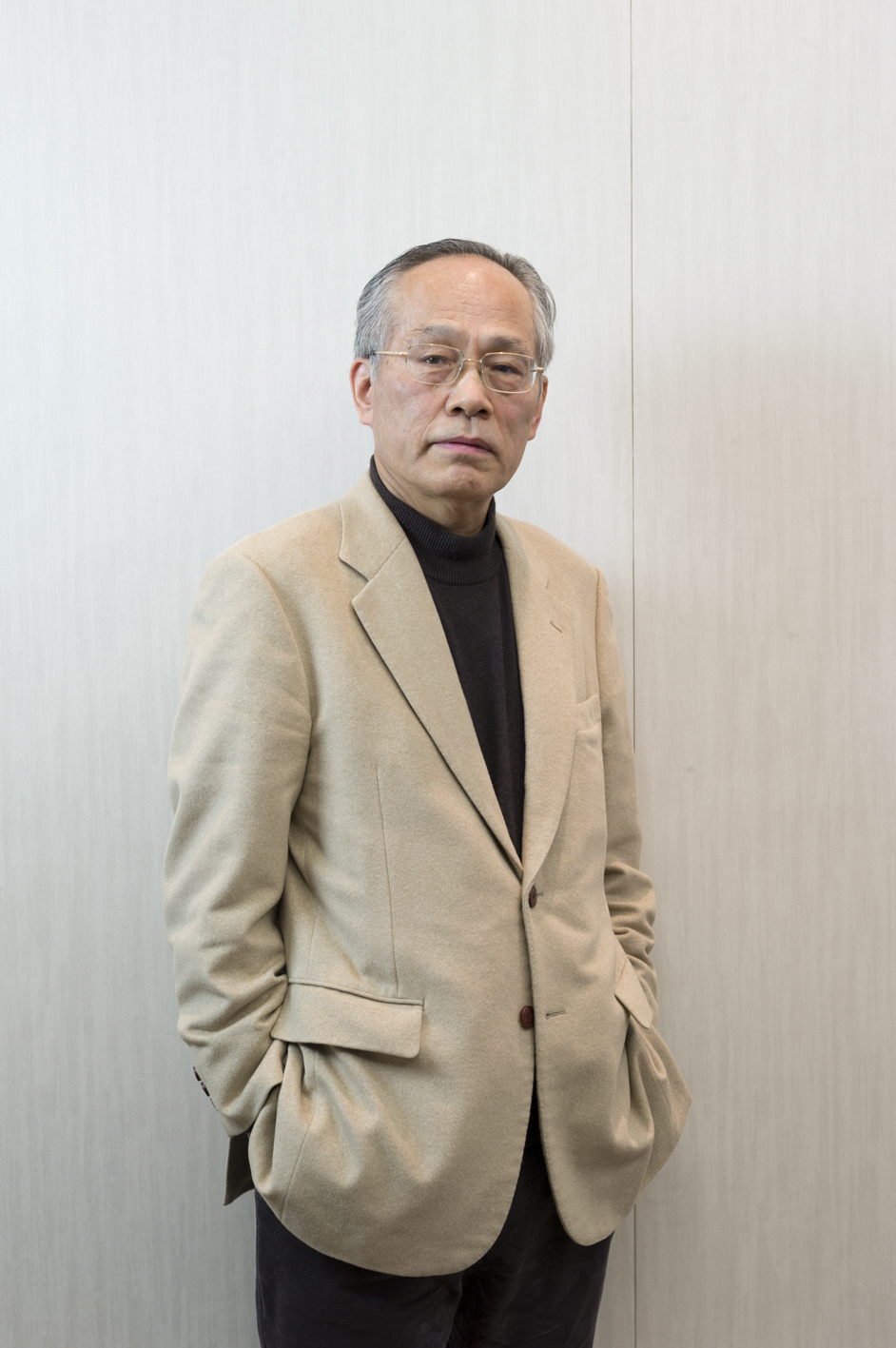 佐高 菅義偉って人も、竹中平蔵とか高橋洋一とかの金勘定しかできないような学者を相手にしていると、「学者ってこういうものだ」と思ってしまって、ある種の深遠さみたいなものが分からないと思うんだよね。
佐高 菅義偉って人も、竹中平蔵とか高橋洋一とかの金勘定しかできないような学者を相手にしていると、「学者ってこういうものだ」と思ってしまって、ある種の深遠さみたいなものが分からないと思うんだよね。
学者というのはしかし、戦い方が一番ヘタな人たちでしょう。
田中 ストレートに戦うだけですからね。
佐高 ストレートに戦うなら戦うで、座り込みでも何でもやればいいんだけれども。学者は、戦うにも理屈が必要な人たちだから。それだと向こうに負けちゃう。
田中 そうか。情念で戦うということはないです。確かに。
佐高 それこそ、石牟礼道子を読まなきゃダメだな。そこが田中さんなんかも結構困っているところじゃないかと思うんだけど。
田中 困っているというか、私はどちらかというと情念で戦っちゃうタイプなんだけど、それを抑えなければならないという立場に置かれているわけです。論理的に説明する必要があるし、説明できない戦いは、やはりすべきでない。
学者って、いろんな役割をしながら、しょっちゅう「自分は、ここでは何を抑え、何を説明しなければならないのか」ということを考えながら行動しているところがあると思うんです。それが自分自身をつまらなくさせていくというのかな。私も自分についてそういうふうに思いましたから。「やっぱり自分の何かが失われていくんだろうな」と思ってますね。
佐高 まあしかし、よく残ってますよね、コントロールされない部分が。
田中 コントロールしきれないというか(笑)。
佐高 いやいや、総長職という、いわば管理職だよね。それを続けながら、あなたの中に非管理職的側面がよく残っていると思いますよ。
田中 はい。それはよかった。あと半年で終わりますから。
佐高 ああ、そう。
田中 次の立候補者が決まりました。まだ選挙は終わっていませんが。
佐高 ああ、そうなの。
田中 ですから、来年の4月からどう生きるか、今まで表現してこなかったものをどう言語化するかということを考えています。
今回の任命拒否問題、全然進展もしてないし、説明がなされたということもないし、これからどうなるのか分からない。これから研究者や物書きにはいろんなことが起こるんじゃないか。自分の身にも降りかかるんじゃないかと思います。でも、それはたぶん学問の世界だけじゃなくて、どんどん他のところに飛び火していくんだろうなと思っています。
― 了 ―
*1 【佐高信の隠し味】「学術会議と近代と石牟礼道子」(デモクラシータイムス)
https://www.youtube.com/watch?v=hfDQgC8ZTvg&t=2175s
*2 法政大学HPの【総長メッセージ】日本学術会議会員任命拒否に関して
https://www.hosei.ac.jp/info/article-20201005112305/
*3 渡辺京二:1930~。評論家・思想家。石牟礼道子の『苦海浄土 わが水俣病』の原稿を編集者として受け取って以来、2018年に石牟礼が亡くなるまで、原稿の清書や身の回りの世話などサポートを続けた。
*4 チッソ㈱:「水俣病」の原因を作ったとされる工場廃液を海に垂れ流した「新日本窒素肥料」の後継会社。
*5 方言札:標準語を話させるため、生徒が学校で方言を話すと「方言札」と書かれた木の札を首からかけさせた。特に沖縄で行われた。
*6 羽田澄子:1926~。映画監督、脚本家。監督作品に「村の婦人学級」「痴呆性老人の世界」「歌舞伎役者片岡仁左衛門」「平塚らいてうの生涯」などがある。
プロフィール

佐高信(さたか・まこと)
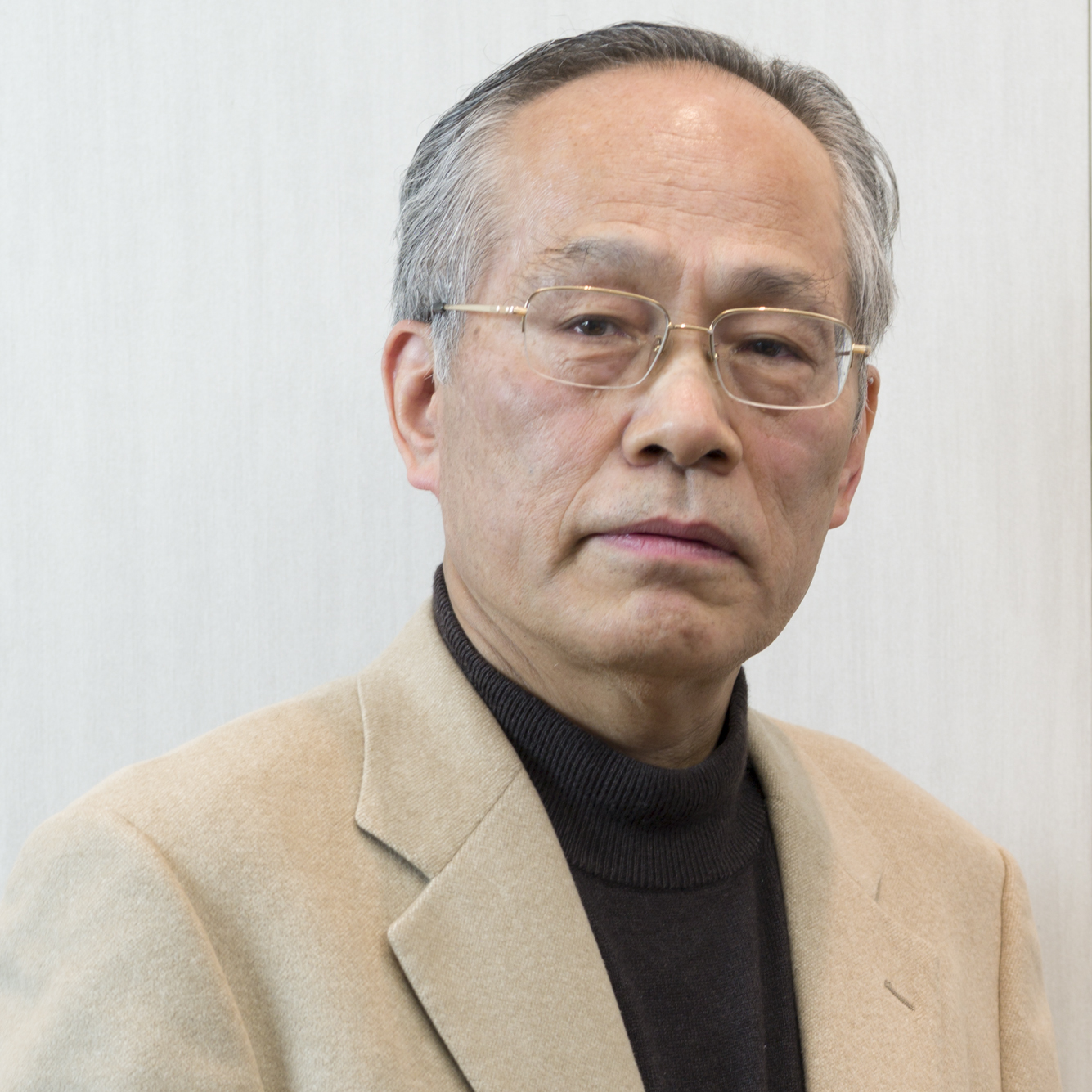 1945年、山形県酒田市生まれ。評論家。慶應義塾大学法学部卒業。高校教員、経済誌編集長を経て、現職。 「憲法行脚の会」呼びかけ人の一人。「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」共同代表。 著者に『池田大作と宮本顕治』『自民党と創価学会』『竹中平蔵への退場勧告』『いま、なぜ魯迅か』、共著に『保守の知恵』『安倍政権を笑い倒す』『戦争と日本人』『原発と日本人』『国権と民権』など多数。
1945年、山形県酒田市生まれ。評論家。慶應義塾大学法学部卒業。高校教員、経済誌編集長を経て、現職。 「憲法行脚の会」呼びかけ人の一人。「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」共同代表。 著者に『池田大作と宮本顕治』『自民党と創価学会』『竹中平蔵への退場勧告』『いま、なぜ魯迅か』、共著に『保守の知恵』『安倍政権を笑い倒す』『戦争と日本人』『原発と日本人』『国権と民権』など多数。
田中優子(たなか・ゆうこ)
 江戸文化研究者。法政大学総長。1952年神奈川県生まれ。著書に『江戸の恋』『樋口一葉「いやだ!」と云ふ』『江戸を歩く』『未来のための江戸学』『世渡り 万の智慧袋』『グローバリゼーションの中の江戸』『芸者と遊び 日本的サロン文化の盛衰』等多数。
江戸文化研究者。法政大学総長。1952年神奈川県生まれ。著書に『江戸の恋』『樋口一葉「いやだ!」と云ふ』『江戸を歩く』『未来のための江戸学』『世渡り 万の智慧袋』『グローバリゼーションの中の江戸』『芸者と遊び 日本的サロン文化の盛衰』等多数。


 佐高信×田中優子
佐高信×田中優子











 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

