——新自由主義という「自己責任」論が生きづらい社会をつくった
4月9日、統一地方選前半戦の41道府県議選の投票が行われ、翌10日に改選定数の全2260議席が確定した。41道府県のうち、24県で定数の過半数を占める形で、自民党が半数を超える1153議席を獲得。一部地域を除いては自民党一強で前半戦は幕を閉じたと言える。
遡ること3カ月前、岸田文雄首相が年頭の記者会見で「異次元の少子化対策」を掲げ、話題となった。3月末に発表された少子化対策の具体的なたたき台では、「共働き・共育て(ともそだて)の推進」が掲げられ、育休の充実(育児休業の給付金を一定期間、手取り収入の実質10割)、誰でも通園制度(就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる制度を検討)、放課後児童クラブの受け皿の拡大等の案が提示された。なかでも育休の充実については、4月1日より施行された「育児休業取得状況の公表の義務化」(※1)同様に、男性の育休取得率拡大が大きな目的と据えられている。
たたき台を取りまとめた小倉將信少子化担当大臣は、「国を挙げて少子化という最重要課題に取り組んでいかなければいけない。この6~7年がラストチャンス」だと危機意識を強調したものの、果たして、これらの対策が日本の少子化を食い止めることになるのだろうか——。
3月某日、こうした政府の動きに対し、保育や非正規雇用の問題と向き合い続けるジャーナリスト・小林美希氏と、フェリス女学院大学文学部英語英米文学科助教で新進気鋭のアメリカ研究者・関口洋平氏は「育休を取得しただけで終わってしまっては意味がない」、「『異次元の少子化対策』が“選挙前のアピール”で終わらないとことを祈りたい」——そんな懸念を口にしていた。
ふたりはそれぞれ新刊『年収443万円 安すぎる国の絶望的な生活』(講談社現代新書)、『「イクメン」を疑え!』(集英社新書)を上梓したばかり。両書を通して見つめた日本の現状はどんな様相なのか。対談から両氏の懸念を紐解いていく。
(※1)常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、 義務育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられるというもの。
キラキラエリートがロールモデルだった「イクメン」

関口洋平氏(以下、関口) 今回上梓した新書は、10年前に書いた博士論文をベースに、2年ほど前から新書として書き進めてきたものなんです。僕が追いかけてきた「イクメン」と呼ばれるキラキラした人たちが現代の日本社会における表の顔だとすると、その裏には小林さんがずっと書かれてきた低所得層の女性たちがいる。表ばかりを見ていては本質を見失ってしまうのではないか、ということを伝えたかったので、今日お話しすることができて本当に光栄です。
小林美希氏(以下、小林) ありがとうございます。関口さんは、著書の中で「イクメン」という言葉が高学歴なエリート層の男性をターゲットにしていて、育児に関する情報は低所得者層の父親にこそ必要なのではないかと説かれていましたよね。私が追いかけてきたテーマと交差する部分が多分にあるなと、興味深く拝読しました。
——お互いの新刊をご覧になられたなかで、特に印象的だった、共感した部分はどのような点でしたか?
小林 いくつも気になるキーワードがあったのですが、特に勉強になったのは、新自由主義(※2)とジェンダーの視点が実はとてもクロスしているものだった、表裏一体の関係だったんだという点です。私が取材をしてきた保育の民営化問題(※3)の背景にも、2000年以降の新自由主義があったんだということがわかりました。なかなか語られてこなかった新しい視点をいただいたなと感じています。
関口 小林さんの本のなかでは新自由主義という言葉はそこまで多用されていないものの、追求されてきた問題の背景には新自由主義の文化や政策がほとんど絡んでいて、そこに20年以上前から声を上げられてきたんですよね。
『年収443万円』のなかでもつらい状況に置かれた方々が登場します。エピソードを読みながらやり場のない気持ちになってしまうのは、おそらく彼女たちが社会のなかで「孤立」しているからではないかと思うんです。新自由主義にはいろんな側面がありますが、なかでも大きな側面のひとつに「人を孤立させてしまう」という面があるのではないかと僕は考えています。
小林 「新自由主義というイデオロギーが『自己責任』を強要し、私たちを孤立させて社会を解体する傾向を持っている」と、著書のなかでも指摘されていましたね。個人の能力次第になりすぎている、と。
関口 はい。そこに僕自身も問題意識を持っていたので、小林さんが新自由主義のなかで苦しまれてきた一人ひとりにすごく丁寧にインタビューをされて、声を拾い上げてこられたという点に、『年収443万円』を通して改めて感銘を受けました。
(※2)なるべく政府の役割を小さくし、市場の自由競争を重んじるという、「新しい自由主義」の考え方。インフラをはじめ、公共サービスを縮小させて、民営化を推進。また規制緩和をすすめ、社会保障も縮小する傾向にある概念を指す。岸田首相は、自民党総裁選に立候補する際に「新自由主義からの脱却」を掲げている。
(※3)現在地方自治体によって行われている公立保育所の運営を民営化する過程で生じている問題のこと。小泉内閣以後の官業の民営化の方針に伴い、保育園不足と待機児童の解消を目的として各自治体で進められてきたが、一方で保護者の保育料以外の経済的負担が増加する可能性や、ビジネス色が強くなったことで近年閉園・事業撤退する法人が出てくるなど、「公立保育所民営化問題」として注視されている。
「働き方の多様化」という責任の押し付け

関口 もうひとつ、新自由主義には、「柔軟な働き方」の実現という思想が根底にあると思うのですが、小林さんの本を拝読していると、柔軟な働き方は労働者にとってまったく利益になっていないというか、むしろそのために苦しめられている部分が多いという事例がたくさん出てきます。新自由主義の「見せかけの姿」を改めて考えさせられました。
小林 「働き方の多様化」というと聞こえはいいですが、結局それって責任も押し付けるということなんですよね。逆を返せば社会のサポートをいかに少なくするか、ということでもある。育児休業も、歴史を遡ると「保育所をつくるためにはコストがかかるから、預けないように育休を拡大したのではないか」という指摘もありました。
実際に、私が20年くらい前に保育園の民営化の是非について取材をしていたなかで識者から出てきた視点は、コストがメインだったんです。何歳児を何人に預かるのにいくら費用が必要で、税金がいくら必要で、だから民営化を進めるべき、という論ばかり。国の負担を減らして個人の負担を増やすという解決策の提示に、「冷たいな」と感じていました。
関口 “コスパ”を検討した結果、個人に委ねていくというのはまさに新自由主義の落とし穴だなと、僕は小林さんの本から学びました。
小林 関口さんの著書では、物事を効率で検討せずに、女性の働きが正当に評価されるべきだといった主張が中に書かれていて、「あ、やっぱりそうだよね」と確信が持てました。
何かを推進していく際には、いろんな人を説得するためについつい経済効果みたいな「数字」を言いがちじゃないですか。私自身も、そう言わなかった、書かなかったことはゼロではないんですよね。でも、数字だけでは測れない部分がたくさんあると、最近私も改めて感じていたところでした。
例えば、共働きが増えたのは経済的な理由でダブルインカムでなければ家計が苦しくなってしまうからという見方がありますが、労働組合のある調査で、結婚、出産を経て「できるなら自分の希望として働きながら子育てをしたいと思う」という女性が、10年前ですでに5割いたことがわかっています。「経済的な理由」で働きたいと言っていた方は3割に満たなかった。10年前にはもう意識はもう変わっていて、女性たちはやむなく働くんじゃなく、当然のこととして「働きたい」んですよね。であれば、その視点でいろんなものを組み立てていかないと、権利が守られないものになってしまう。本質を覆い隠してしまうような議論を展開してしまっては、結局「見せかけ」の策しか取れませんよね。
関口さんが指摘されていたように、「イクメン」の代表例が大企業のスーパーエリートや部長やマネージャークラスの男性だとしたら、それは一般化できる視点ではありません。その人たちを基準に物事を進められては、「そうではない人」たちを排除することになってしまう。
関口 おっしゃる通りだと思います。非正規雇用者が年々増えているなかで、結婚できる割合もすごく低くなっている現実がある。その時に、一部のエリート層である「イクメン」をロールモデルとして少子化対策を行なっても参考にはならないですよね。
小林 一部のエリート層・高所得者層は結婚も出産もしていますからね。人口動態調査を見ると、夫と妻になった方の婚姻前の仕事を見ると大企業や士業など、高所得層の方々の婚姻率が高いことがわかるデータがあります。同時に、第一子が生まれたときに女性が仕事を持っていた割合というデータも人口動態統計から出てくるのですが、専門職と事務職が多い傾向にあります。その専門職も、医師や教員、会計士など、高所得な職種が多い。事務職も、生き残れるのは秘書や企画など、特異性のある事務職の方という印象を受けます。つまり、満足のいくように結婚して出産して働いているのは、キラキラしたエリート層のみという状況が透けて見えてくるのです。
だからこそ、結婚することができない、子どもをつくることができない層に目を向けることは重要だと思います。そもそも私は少子化の解決には「正社員9割」の実現が必須だと考えているんです。女性はずっと半数くらいの方が非正規雇用という状況が続いてきました。20代以外の働く世代については女性の4〜5割が非正規雇用。男性についても働き盛りの25~34歳、35~44歳の非正規雇用労働者が、バブル崩壊前の3%程度からそれぞれ、約15%、約9%に拡大しています。めったにいなかった働き盛りの男性非正規雇用労働者が、いまや10人に1人はいるというわけですから、「収入が不安定で結婚できない」という声は無視できませんよね。
関口 同時に、なかなか正社員になれないという状況が常態化してしまうことで、非正規雇用者の意識も上がらなくなってしまっていることも見過ごせないなと思います。「イクメン」のようなキラキラした男性像は自分たちには縁がないことととらえて、別の世界の話のようになっていってしまっている。本人が諦めてしまうと、状況を変えることがますます難しくなってしまうんですよね。
一方で、諦めてしまう気持ちもよくもわかるんです。個人の問題というよりも、社会の構造的な問題だなと感じます。
小林 そうですよね。これだけ少子化問題や労働問題がニュースで取り上げられて身近なものになっていても、非正規の女性がいざ妊娠すると、「うちは育休取れませんから」という職場もいまだに存在する。そう言われてしまっては「仕方ない」と諦めて辞めていく人が多いのも事実ですもんね。
以前お話をうかがった某有名大学の講師をしている女性は、非常勤だったために夏休み中に出産できるように計算して妊娠しないといけないとおっしゃっていました。産みたくても、自身のキャリアとの天秤で諦めないといけない方々もいるんです。取材をしていると、育休を安心して取ることができて、育児が落ち着いたところで職場復帰を果たせるというのはまだまだ恵まれた企業内の話なのかなと思わざるを得ないことが多々あります。
相反するケアの価値観と資本主義の価値観

——関口さんと小林さんは、子育てと仕事の両立について、同じような問題意識をお持ちです。一方で、その問題を発信するアプローチの違いが興味深いと感じました。関口さんはアカデミアの視点から、資料やデータ、史実を読み解くことで考察を積み上げ、小林さんはジャーナリストの視点でデータから読み取れる現状を分析しつつも、生の声を拾い上げることに重きを置かれて取材を続けておられます。それぞれのアプローチの仕方について、どのような必要性を感じていらっしゃるのでしょうか。
小林 私の場合は、まだ統計や調査の対象になっていないような現場の声を集めていって、そこに関連するデータがあれば「客観的な事実」として引用していく手法を用いています。現場から上がってくる事実から目を背けてしまう層に対して、納得性を持たせるためにデータは必要だと考えているんです。その積み重ねのなかで、この集計データがないと問題が見過ごされてしまうんじゃないか、という気づきを得ることも少なくありません。
専門家の皆さんがその穴に気づいて、研究をしてくださるといいなと思って、問題点を提起するようにしています。逆に専門家の皆さんの研究結果に気付かされることも多々あり、今回の関口さんの本も、冒頭でお話ししたように新たな視点を頂戴するきっかけとなりました。
また、少子化問題について諸外国との制度や保育の違いについて書いていらっしゃる方はいらっしゃるのですが、そこに文化的違いを持ってきて比較するというアプローチはとても面白いなと思いました。たしかに、人間の生活習慣や考え方には文化という素地が大きな影響を与えているということを改めて感じて、今後取材をしていく際に、関口さんにもご意見をいただけると嬉しいですね。
関口 僕は自分のアプローチという点でいうと、今回の本を執筆するにあたって研究データをベースに社会問題に切り込むことの難しさを感じました。僕は専門がアメリカ研究なので、映画も文化も扱うし、歴史的な面や社会学的な面を扱うこともあって、どちらかというと複合的に考察してきました。今回の本は、そのなかでも映画を中心に取り上げて、「イクメン」という文化の違和について分析したのですが、それだけがメインになってしまうと、どうしても僕自身の主観から何かを切るような、上から目線になってしまうんですよね。
だからこそ客観的な、例えば分析する映画が日本ではどのように評価されてきたかというような視点を取り入れたりもしたんですが、それも限界がある。
小林さんのアプローチというのは僕のそれとは対照的で、自分が切るというよりは、人々の生の声をすくい上げていくなかで伝えていくというものなので、読んでいてすごく納得するところがありました。同じテーマを扱っていても、このアプローチの違いによって本の方向性はまったくの別物になるでしょうし、僕もやってみたいなと思いましたね。
——読者と実際に話ができない分、誤読されてしまうこともあり得ますし、関口さんの立場から「この映画は女性が観たらどう感じるんだろう」と否定的に捉えた作品が、当の女性にも人気だったりと、こちらの意に反する反応が返ってくることもありますもんね。
関口 小林さんの書著のレビューを読んでいた際にも、「これは誤読だな」と思うものがたくさんありますよね。
小林 ありますね。なので、レビューサイトはもう見なくなりました(苦笑)。
関口 例えば典型的だなと思ったのが、『年収443万円』を読んで事例として登場した人たちについて、「この人はこれが悪い」とか「こういうことを選択すればそんなことにはならなかった」といったレビューがついているんですが、本で伝えたかったことはそういうことではないと思うんです。もちろん個人が間違った選択をすることもあるでしょうけど、何かゲームをしていたとして、こういうふうにプレーしたらもっと上手にクリアできるよという議論がしたいわけではなく、そのゲームのルール自体がおかしいんじゃないかという問題提起をしているわけで、これこそが新自由主義の影響だと思うんですよね。
小林 「自己責任」という新自由主義ですよね。ただ、結局は人はひとりでは生きていけないという基本的な話だと思うんです。特に日本は群れて生きてきた歴史や文化がずっと継承されてきていることを考えれば、子育ての問題にかかわらず、社会のシステムとしてのケアは必要なんです。加えて、人は移動しやすいもの——進学したり、転職したり、引っ越したりと、属する組織や地域が変わることで、そのケアが損なわれないようなシステムを整えていくことが重要だと思うんです。だからこそ、ルールをつくっている国がベースにそうしたシステムを組み立てていくべきじゃないかなと、私は思います。
関口 まさにその通りだと思います。フリーライター・武田砂鉄さんの著書『父ではありませんが 第三者として考える』(集英社)のなかで、「子育て」というものに関する違和感について書かれていて、共感する部分がありました。政府が徐々に子育て支援に力を入れるようになってきたこと自体はよいことです。ただ、そうした政策が「少子化対策」を目標としていることには違和感を覚える方もいるのではないでしょうか。「少子化対策」がゴールになってしまうと、どうしても子どものいない男性や女性の肩身が狭くなってしまう。「ケアが必要だから」子育てを支援するというのと、「少子化対策として必要だから」子育てを支援するというのでは、意味が違ってくると思うんです。
小林さんが指摘されたように、ケアというのは誰にとっても必要なものです。子育てに限らず、介護も障がいを持つ人も、誰もがケアされるしくみが大切なんですよね。なので、少子化対策や子育てという枠組みのなかでだけでなく、もっと大きな、社会という枠組みのなかでケアの価値を高めていく、ケアに対する認識を改めていく、ということが重要なのだと思います。
ただ、小林さんが著書で書かれていた通り、ケアというのは目に見えないし数字では測れない。契約通り何時から何時まで一緒に付き添っていたから大丈夫というものではない。一方、資本主義は効率重視で無駄な動きを削ぎ落して、コスパを追求していく。数字やお金など目に見えるものが大きくモノを言うんですよね。。例えば保育園でも、民営の企業だけに任していては、利益を追いかけてしまい子どものケアがおろそかになってしまう側面がどうしても出てきてしまう。そこには、資本や市場だけではない別の何か——国家だったり、自治体だったり、あるいはもっと大きな社会だったりで支えていくしくみが必要ではないでしょうか。
人は皆非効率であることを思い出す意味

小林 自分自身が子育てをしたり、周囲で子育てをしている人を見守っていたりすると、人間=赤ちゃんや子どもってなんて非効率的な存在なんだろうということに気付かされますよね。大人なら目的地に向かってまっすぐ進むのに、小さい子どもたちは石があったとか、アリがいたとか、花が咲いていたとかでうろうろしながら、寄り道しながらなかなか目的に到達しない。でもそれが本能なんだということを、誰もが経験するのに、私たちは忘れてしまうんですよね。20〜40歳くらいで出産を経験したり、周りに子どもが増えたりする意味は、もしかしたらそこにあるのかもしれないと思います。
やがてくる老後に対する心の準備だったり、他者の苦労に対する想像力を働かせたり、そのきっかけのひとつが子育てなんじゃないかなと思います。そこから目を背けて、雇用が分断され、女性に大幅に増えた非正規の妊娠解雇といったことが起き、職場に妊娠や子育てをしながら働いてる人がいなくなる。いないとその人たちの大変さがわからなくなってしまうので、いろんなことに想像力が欠けていく。結果、いま、みんなが生きづらくなっている。大事なのは「イクメン」がスキルアップだとかそういうものではないんだよ、という関口さんの指摘から、改めて考えさられたなと思います。
関口 本のなかではいろいろ書きましたが、もちろん僕自身のなかにも効率を重視する考え方ってすごくあるんです。例えば子どもに勉強を教えていても、これをやると効率悪いから、こっちをやりなさいと頭ごなしに言ってしまったり……。そういうしみついてしまっていることが、日常的にあるんですよね。だから、まったく人ごとではないからこそ、新自由主義の問題というのは根深いのだと改めて感じます
——他者の価値観を知り、自身の価値観をアップデートさせていくために、おふたりの新刊は子育て中の当事者以外の方々にもぜひ読んでほしいと思いました。自分の身に置き換え、誰にでも起こり得るという想像力を養うきっかけに、両書がなるのではないかと思います。
小林 ありがとうございます。私も、今日の対談を通じて、広くいろんな方に読んでほしいなと、改めて思いました。育児とか関係ない人にこそ、読んでもらえると嬉しいですね。
きっと、「新自由主義的な感覚が自分にもしみついてきたな」とか、何か気づくきっかけになると思うんです。新自由主義による弊害がいま、大きく表出してきていることは事実です。それが、私たちの息苦しさとか行き詰まりの原因になっているかもしれない、ということに目を向けてもらいたいですね。
関口 そうですね。僕としても、男性で子育てをしている当事者にももちろん読んでほしいのですが、それだけではなく、母親である女性の方々にも読んでほしいし、育児をしていない人にも読んでほしい。すべての人にとって、育児だったりケアというものを、社会のなかでどんなふうに位置づけていくかという、議論の取っかかりになるといいなと思って書いた本でもありますので、ぜひ、手にとってほしいですね。

プロフィール

ジャーナリスト。
1975年茨城県生まれ。水戸第一高校、神戸大学法学部卒業後、株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部記者を経て、2007年よりフリーのジャーナリスト。就職氷河期の雇用、結婚、出産・育児と就業継続などの問題を中心に活躍。2013年、「「子供を産ませない社会」の構造とマタニティハラスメントに関する一連の報道」で貧困ジャーナリズム賞受賞。著書に『ルポ 正社員になりたい』(影書房、2007年、日本労働ペンクラブ賞受賞)、『ルポ 保育崩壊』『ルポ 看護の質』(岩波書店)、『ルポ 産ませない社会』(河出書房新社)、『ルポ 母子家庭』(筑摩書房)、『夫に死んでほしい妻たち』(朝日新聞出版)ほか多数。最新刊に『年収443万円』(講談社)がある。

フェリス女学院大学文学部英語英米文学科助教。
1980年生まれ。東京大学大学院人文社会研究科にて修士号、ハワイ大学マノア校アメリカ研究科にて博士号を取得。東京都立大学人文社会学部英語圏文化論教室助教を経て現職。2018年、アメリカ学会斎藤眞賞受賞。専門はアメリカ研究。特に、アメリカ文化における家族の表象について研究している。著書に『「イクメン」を疑え!』(集英社新書)。


 小林美希(こばやし・みき)×関口洋平(せきぐち・ようへい)
小林美希(こばやし・みき)×関口洋平(せきぐち・ようへい)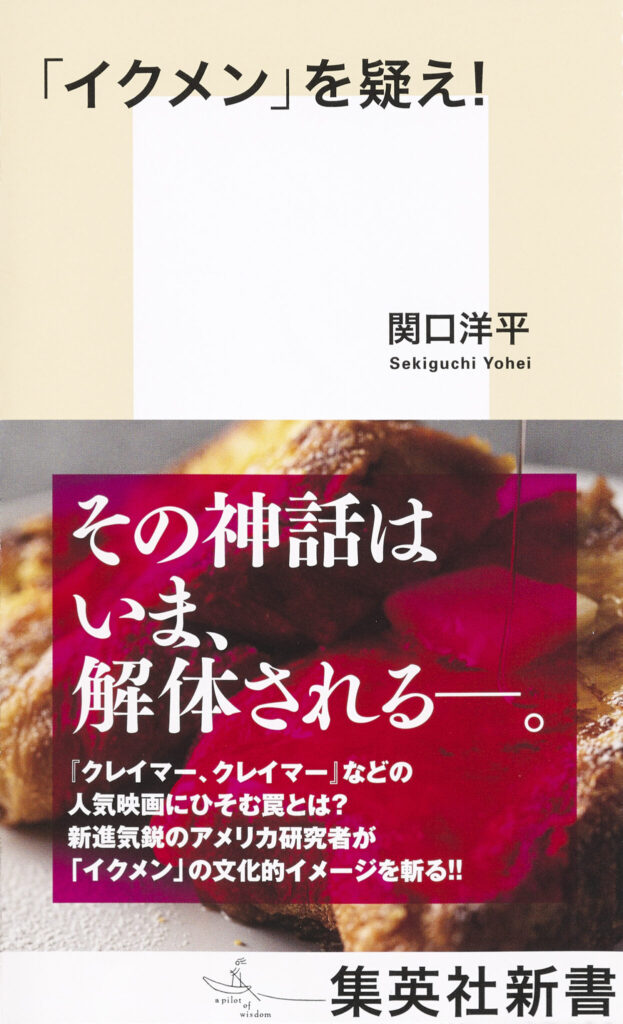












 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

