
自発的な対米従属を戦後七〇年あまり続ける奇妙な国・日本。この呪縛の謎を解くカギは「国体」にあった!
そう喝破する、若き政治学者・白井聡氏が五年ぶりに書き下ろしを上梓しました。「戦前の国体=天皇」は、敗戦をはさんで「戦後の国体=米国」へと変容した。この衝撃の新刊について、著者・白井聡氏が、思想家・内田樹氏とともに、議論します。
構成=水原央/撮影=祐実知明
「菊と星条旗」の嵌入
内田 白井さんの新刊、『国体論 菊と星条旗』は、日本社会の歪みの根幹を見事に解析してくださった、非常に爽快な論考です。ひろびろとした見晴らしを提示してくださったことに、一読者としてお礼を申し上げたいと思います。
白井 光栄です。『永続敗戦論』を書いてから数年の間、天皇とアメリカの関係を考えてきました。戦後日本の対米従属の特殊性とは、つまるところ、天皇制の問題であるという命題を証明することが、この本の課題でした。
内田 読みながら思い出したことがあります。日本人のなかの「アメリカ崇拝」がどうやって生まれたのかについてのひとつの仮説です。例えばここに横須賀出身の政治家がいたとします。少年時代、ふるさとは帝国海軍の鎮守府だった。でも、久しく仰ぎ見ていた日章旗の代わりにある日そこに星条旗が翻るのを見る。そのときに、彼の心の中である種の詐術が行われた。「旗を仰ぎ見る」という行為そのものは変わることなく継続し、旗の図柄だけが変わる。そして、この二つは実は同じ一つのものなのだと自分に言い聞かせる。実際にそれまでもこれからも基地は住民にとってはオフリミットの空間だったし、帝国海軍に依拠して成り立っていた港町の経済は、戦後は第七艦隊に依拠していたわけですから、「同じものだ」と強弁すればできないことはない。それに類することは戦後日本中で起きたのではないかと思います。「忠誠の対象がある」という心の構造そのものには手をつけず、忠誠の対象だけを入れかえる。そういう詐術を敗戦後、多くの日本人が無意識に行ったのではないか、そういう仮説です。
白井 「菊と星条旗」という言葉で表したかったのはそういうことです。戦前の日本国の最強のイデオロギーは、日本は天皇を国父とする大きな家族なのだ、という国家観でした。これが、いわゆる「国体」というやつです。一般的な認識では、敗戦によってそうした「国体」は解体されたことになっている。しかし、「国体護持」を唯一の条件として降伏は行われたし、敗戦後に昭和天皇は在位し続けた。その際に決定的な役割を果たしたのはアメリカだった、ということは誰でも知っている常識です。しかし、このことが、現実政治をはじめ、さまざまな領域に対してどれほど大きな意味を持っているのか、多分これまで十分には考えられてこなかったのだろうと思います。言い換えれば、対象化できないほど深く、「アメリカなるもの」は戦後の日本人の生活にも内面にも食い入った。二〇世紀は「アメリカの世紀」だったからということだけでは説明がつかないような食い入り方をした。それはつまり、戦前の天皇制に代わるものとして入ってきたんじゃないのか。
だから、内田先生がおっしゃったような、なにかを頼みとしてしか生きていけないような、臣民的精神性も維持された。こうして出来上がった体制を「戦後の国体」と今回の本では呼んでいるわけです。ただし、当然この新しい国体は、戦前のそれと大きく変わった部分がある。決定的な違いは、その頂点にアメリカが鎮座していることです。内田さんがよく「戦後日本の基礎的国家方針は《対米従属を通じた対米自立》だった」とおっしゃいますが、この方針がおおよそうまく機能していた時代、つまり冷戦構造と経済成長が続いていた時代が終わってから、この構造の問題が否応なくわれわれに突きつけられるようになってきた。
だから、われわれの社会は天皇制のまずい部分を克服したつもりになっているけれど、実は違う。「戦後の国体」に縛られている、という主張が今回の本の大きなポイントです。「菊と星条旗」が結合してできたピラミッドが「国体」になってしまい、そのうえ、その事実から懸命に目をそらしている。というか、天皇は見えるけれど「天皇制」はモノじゃないので、意識しない限り見えませんからね。この奇妙な「国体」の歩みと本質を腑分けしていかないことには、日本に未来はない。その腑分けこそが、今回の本を書くにあたっての動機でした。この社会の歪みをただすには、まず病識がなくてはなりませんからね。
内田 菊と星条旗、つまり天皇とアメリカが、完全に嵌入してしまっていることを白日のもとにさらした意義は大きいですよ。アメリカが徹底的に合理的に思考して、天皇制を道具として占領を遂行したというのは、当たり前と言えば当たり前の政略だし、アメリカが日本の宗主国であることも「それは言わない約束」だった。そこに容赦なく光を当てた、この『国体論』は、実にすぐれた一冊だと思いますよ。
八紘一宇とブラザーフッド

白井 日本の対米従属の醜怪さが最もよく現れるのが政治の領域ですが、小泉純一郎が首相だったときに、ブッシュ(ジュニア)大統領の前でおどけて、エルヴィス・プレスリーの物まねをしましたよね。あの映像を見たとき、何とも言えないおぞましいものを感じたわけです。
内田 安倍首相は、アメリカの連邦議会で演説したときに、キャロル・キングの「You’ve Got a Friend」の一節を引用をして、アメリカとの「トモダチ」性を強調したことがありましたけれど、小泉純一郎のエルヴィスと安倍晋三のキャロル・キングは構造的には同じだと思う。日米の「トモダチ」関係は「ブラザーフッド」ですけれど、実はこの言葉は日本のアジア侵略のキーワードでもあったんです。日本人が朝鮮や中国の侵略を正当化するときに「日本が兄で、アジア諸国はその弟」という「兄弟関係」の図式を利用した。アジア諸国民にあれほどひどいことを平気でやれたのは「教化的善意によるもの」という正当化ができたからです。未知の他者に対して暴力をふるうためにはそれなりのロジックが要りますけれど、「身内」相手なら問答無用。なにしろ「兄弟愛ゆえ」なんですから。DVと同じです。
白井 兄弟愛の押しつけか……。
内田 東京裁判のときに、「八紘一宇とは何か」と問い詰められたとき「Universal Brotherhoodである」と日本側は言い抜けしようとしたことがありました。「トモダチ」「身内」なのだから、「目上のもの」にはひたすら従属すべきであるというロジックを掲げてかつて日本はアジア侵略を行った。そして、戦後はそのロジックを反転させて、アメリカがどれほど強圧的でも、それは「トモダチ」だから、「兄弟愛ゆえ」なのだという言い逃れを今度は自分に適用した。
白井 なるほど。敗戦後、アメリカを長兄として自分を二番目、アジア諸国を三番目以下の弟なんだと認識するようになったと。明治レジームがつくった家族国家論を地球規模に拡大して、近隣に大迷惑をかけ、懲りずにまた同じロジックで世界情勢を無理矢理解釈し、頓珍漢な外交を繰り広げている。
内田 媚米と嫌韓・嫌中は構造的には同じです。
白井 弟の背が伸びてきて追い越されそうなので半狂乱になっている。
内田 沖縄もそうです。自民党政権が沖縄に対してあれだけひどいことができるのは、沖縄を「身内」だと思っているからです。
国民国家の形成に
失敗した日本
白井 しかし、『永続敗戦論』以来ずっと言っているのですが、この日本の特殊な対米従属レジームはもうもちません。安倍政権は、この柱が抜けた建物を何としても立たせ続けようとしてきた。安倍を支える、あるいは振り付けをしている、永続敗戦レジームの支配層は、このレジームを維持するためなら、手段を選ばないだろうと思うのです。このことが、安倍政権の五年間ではっきりしたことのひとつだと思う。その究極の手段が戦争です。朝鮮半島問題が解決しても、中長期的には東アジアの情勢は不安定さを増しそうだ。仮に、例えば、局地的な紛争が起こり、数百名なり、数千名単位の犠牲が日本に出た場合、一体これが、誰のせいにされるかといったら、多分、護憲派のせいにされるんですよ。つまり、我々が糾弾されて、魔女狩りに遭うんです(笑)。長年、九条のような不条理な条文を変えることに反対し続けてきたやつらのせいだとね。

内田 限定的な、彼らにとって「適正」な規模の被害で収まる程度の戦争がベストのシナリオなんでしょうね。支持率が低迷していたジョージ・W・ブッシュでさえ戦時大統領のときは90%の驚異的な支持率を得たわけですから。
白井 今の日本の市民社会の倫理的な脆弱性を見ると、戦争になったら手がつけられない興奮状態になるでしょうね。
内田 今の政府でしたら、危機的な状況に遭遇したら、「誰のせいか」というふうに敵を名指して、国民を分断することしかできないでしょう。国家的危機だからこそ、団結が必要なのに、立場の違いを超えて国民を統合できるシンプルで雄渾な物語は今の政府には絶対つくることができないです。
白井 そういうなかで、今上天皇が国民統合のために必死になっている姿勢は際立っています。内田さんは天皇主義者宣言をなさいましたね。
内田 プラグマティックに考えたら、天皇制は国民に残された貴重な政治的資源ですから。
白井 「戦前の国体」は、昭和の時代に至って国民統合装置として破綻しました。それを反復するかのように、いま「戦後の国体」が国民を統合するどころか、統合を破壊するように機能している。そのなかであの「お言葉」が出てきたわけで、「国民統合」が強調された。だから、あのとき起きたのは「天皇自身による天皇制批判」だったのだと徐々に気づいてきました。たぶん、日本は戦前も戦後も、ナショナリズムは形成したけれど、国民国家の建設には微妙に失敗していて、まともな統合原理をつくれなかった。だからもう一度やり直す必要が出てきている。
統合がボロボロになった状態の象徴が安倍政権であったのでしょう。この政権が支持されてきてしまったのは、日本人が生き物として終わっているということなんですよね。生き物の最大の本能として生き残るということがあるはずなのに、その本能が働いていないわけだから。
人間そのものを
ダメにする「国体」
内田 「国体」が人間をダメにするわけですね。
白井 そうなんです。作家の石川好さんから聞いた話ですが、江戸末期の漂流民、たとえばジョン万次郎のような人たちを調べてみたら、カウボーイと決闘したりして、結構ワイルドに生きていたというんですね。ステレオタイプの、おとなしくて控えめな日本人像とは、全然違うという。とすれば、控えめな日本人というのは、「天皇の臣民」化された後のものなんじゃないか。だから、生き物レベルでおかしな状況にまでなっているのは、近代天皇制の帰結であろう、と言えると思うんですよね。つまり、依然として問題は「国体」であり、天皇制なのです。
内田 どの国もそれぞれに固有のねじれた政治制度を持っています。この世にパーフェクトな政体なんて存在しない。差があるとすれば、その固有の仕方で不出来な政治制度がいかなる必然性があって生まれたのかについて分析できるかどうか、その欠陥の多い政治装置をそれなりに安定的に操作できる技術を持っているかどうかによるのだと思います。計量的でクールな知性があれば、どんな政体だってそこそこうまく機能させられるはずです。でも、知性がなければ、どんなすばらしいシステムを設計しても失敗する。
白井 そうですよね。
内田 ソ連だってシステムそのものは見事なんです。でも、ロシア独特の歪みを勘定に入れ忘れた。だから、皇帝や貴族や富農を殺した後に、独裁者と特権階級がそれに取って代わっただけだった。自国の政体を修正して、使い勝手のいいものに手直ししてゆくというのは国民の義務ですけれど、そのためには冷静な自己分析力が要るんです。日本の場合は、この本で言う「菊と星条旗」が政体の所与の条件になるわけです。この所与の条件を、白井さんがされたように、まずは客観的に、価値中立的に記述する。そこからしか話は始まらない。
白井 今回の仕事が、日本社会の客観的理解の役に立つことを願っています。
内田 僕が白井さんを高く評価するのは、研究の動機が愛国心だからです。白井さんは愛国者なんですよ。どうすれば日本国民がこれからの危機の時代を生き延びてゆけるか、それを本気で心配している。僕もその点では同じです。もちろん安倍も、その政権の支持者たちも主観的には愛国者のつもりでいるのだけれど、彼らには日本人全員に取り憑いている国民的な「病」を分析できるだけの知性がない。反知性主義的な愛国心は病を深めるだけなのです。
2018年「青春と読書」5月号「対談」より
プロフィール

白井 聡(しらい・さとし)
 1977年東京都生まれ。政治学者。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位修得退学。博士(社会学)。専攻は政治・社会思想。京都精華大学人文学部専任講師。『永続敗戦論―戦後日本の核心』で、石橋湛山賞、角川財団学芸賞、いける本大賞を受賞。
1977年東京都生まれ。政治学者。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位修得退学。博士(社会学)。専攻は政治・社会思想。京都精華大学人文学部専任講師。『永続敗戦論―戦後日本の核心』で、石橋湛山賞、角川財団学芸賞、いける本大賞を受賞。
内田 樹(うちだ・たつる)
 1950年東京都生まれ。思想家・武道家。東京大学文学部仏文科卒業。専門はフランス現代思想。神戸女学院大学名誉教授、京都精華大学客員教授、合気道凱風館館長。著書に『街場の天皇論』『ローカリズム宣言─「成長」から「定常」へ』、共著『アジア辺境論 これが日本の生きる道』等多数
1950年東京都生まれ。思想家・武道家。東京大学文学部仏文科卒業。専門はフランス現代思想。神戸女学院大学名誉教授、京都精華大学客員教授、合気道凱風館館長。著書に『街場の天皇論』『ローカリズム宣言─「成長」から「定常」へ』、共著『アジア辺境論 これが日本の生きる道』等多数


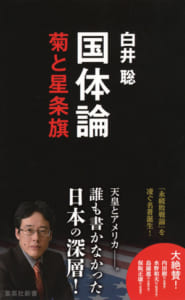











 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

