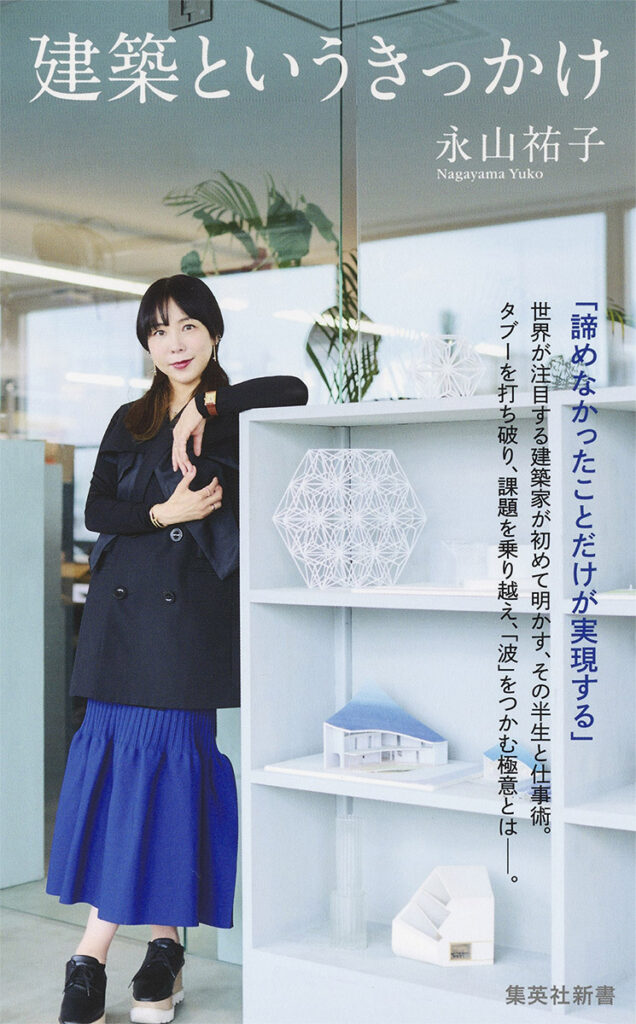
「諦めなかったことだけが実現する」(『建築というきっかけ』より)。
万博パビリオン、東急歌舞伎町タワーなど次々と話題の設計・デザインを手がけ、今、もっとも世界が注目する建築家・永山祐子氏による初の新書『建築というきっかけ』が8月8日(金)に刊行されます。
本書は自身の半生を辿るとともに、手がけた作品やプロジェクトにまつわる知られざるエピソードをドキュメンタリー的に綴ります。タブーを打ち破りながらプロフェッショナルであり続けるための仕事術についても初めて明かした一冊です。
その内容と読みどころをひと足早く皆様にご紹介したく、発売日までの期間限定にて「第五章 建築を信じる」を全文公開いたします!
第五章 建築を信じる

◆仕事と育児
豊島横尾館は、息子と娘の誕生という生命のつながりにもシンクロする、記念碑的な仕事になりました。同時に、年子の子ども二人を抱えて、自分の事務所を回していくという、いよいよ大変な局面の始まりでした。
当時の典型的な一日は、次のようなものです。
朝七時に起きて、家族が起きる前に朝食の用意。九時までに子どもたちを保育園に送り、私は十時に荻窪の事務所に出社。事務所の内外でフルに働いた後、十九時に保育園に迎えに行って、帰宅して夕食。その後、子どもたちをお風呂に入れて、寝かしつけているうちに、私も疲れて一緒に寝てしまう。夜中に起きて、残った仕事をしてから就寝。そして朝が来て、同じルーティンが始まり……以下同じ。掃除、洗濯、保育園の用意、自分自身の用意、なかなか思うようにはいきませんでした。
長男の誕生前から、長女が三歳になるまで、私たち一家は阿佐ヶ谷の実家に同居させてもらいました。母からサポートを受けてはいたものの、四月生まれの上の子は、当時の制度上、翌春の入園となったため、一年間は保育園に入れませんでした。そのころ、朝いちばんにすることは、電話を四台並べて、一時保育を確保することでした。下の子も生まれ月のタイミングが合わなくて上の子と同じ保育園に入れられず、違う園に通いました。上の子とお迎えの時間がズレていたので、まず下の子をお迎えに行って事務所に連れていき、子どもを膝に乗せながら所内の打ち合わせをして、その後に上の子を別の保育園まで迎えに行く。そんな日々が続きました。上の子が生まれてすぐの時は、事務所の隣のマンションに新たに「子育て部屋」を借りて、事務所と行き来していましたが、なかなかの綱渡りでした。
建築家としてのクリエイションはもちろん、事務所の経営、家事、子育てと何重もの役目は、やはり肩に重く、タフにならざるを得ませんでした。
アーティスト活動とデザインの仕事を並行していた夫は、子どもが誕生するタイミングで、「アーティスト活動に重きを置きたい」と、宣言していました。となると、私が働かなくちゃ……となります。アトリエ系の建築家は経済的な苦労がつきものですが、アーティストも不安定さでいったら負けていません。仕事が立て込む中で「もうダメかも……」と、震えることは何度もありましたが、一晩寝て朝になれば何とかなるさ、と自分を奮い立たせていました。
仕事と子育ての両輪を回せたのは、周囲の協力があってこそでしたが、私自身の考え方と仕事のやり方を、ドラスティックに変えたことも大きかったと思います。
何よりの変化は「人に任せる」ようになったことでした。それまでの私は時間の限りを仕事に使っていましたし、考え始めると周囲が見えなくなってしまうタイプでした。子育てという新しいタスクが入ってくると、その方法では事務所運営は行き詰まってしまう。そこからは担当スタッフに実務的な部分はある程度任せて、私は発案と総合的なディレクションを行う体制に組み直しました。
私にとって事務所は机に向かう場ではなく、ディスカッションと意思決定を行う場と決めて、あらゆる情報を効率的に聞いた上で判断し、ものごとをスピーディに決めていくように心がけました。そのためには、常に思考を整理しておくことも必要でした。
たとえば、それまでは作図やプレゼン資料なども私が全体を構成して細かい部分まで手を入れていましたが、それは担当スタッフに任せることができる仕事です。スタッフを信頼して仕事を任せていくと、人は育ち、事務所全体が体力のある集団に変わっていく。その姿を目の当たりにしました。はじめは、やむを得ず任せるという感覚でしたが、フタを開けたら、スタッフは四人から七人になり、仕事の件数も増えるという逆の展開になりました。
この経験は、建築家として次のステージに進む上での基盤となりました。建築は大きなお金が動くものなので、予算とスケジュール管理、それをスムーズに実行するための人間関係の構築、時代の読みと、すべてに対する目配りが求められます。もうここで手詰まりかという場面に遭遇し、諦めそうになる瞬間が何回もあります。
建築家のスキルとは、設計力、そして、それをどのように実現まで持っていくかの実現力の二つ。どうにか走り抜けながら、手探りの中で自分なりのやり方を身に付けてきました。諦めなければならない局面に立った時でも、もしかしたらうまくいく方法がほかにあるかもしれない。そう思い直して、あらゆる角度から検討を行います。その時に気をつけるべきは、独りよがりな思いで、誰も望まない方向に話を強引に推し進めていないか、ということです。また、やる意味があることならば、協力者が現れて道はおのずと開けることも、実感しています。
◆立場を越えて
建築は一人ではつくれず、チームによって成り立つもの。だからこそ、あらゆる局面でコミュニケーションが肝になります。コミュニケーションと一言で言っても、バックグラウンドの違い、相手の置かれた状況など、全体の様子や立場の違いを理解し、慮ることが求められます。
建築業界で働いていると、「女性差別は感じませんか?」とよく聞かれます。建築の現場は何しろタフなところで、昔から男性中心の業界ではあります。
私自身は女子校から女子大という環境で育っていたので、大学を卒業するまで、男女差別というものは、あまり意識することがありませんでした。変な話、自分が女性である、という意識すらなかったのです。青木さんの事務所に入っても、その感覚は変わりませんでした。仕事仲間は男性が多かったのですが、特に男女で違う扱いを受けることもなく、それぞれの個性の方が前に出て尊重されるような環境でした。
ただ、現場に行くと、「え、本当に関係者?」という顔をされることはありました。大学を出たてで、さらに童顔だったので、「そこの女の子、工事現場に入っちゃダメだよ〜」と、注意をされるような感じです。私自身もはじめてのことだったので、「私、担当者なんです」と言いながら図面を見せ、指示を行っても、我ながら説得力は乏しいよな、と思っていました。
それよりも現場で使われる建設用語がいちいち新鮮で、聞いた言葉をそのままカタカナにしてメモばかり取っていました。時には聞き間違いの言葉もあり、事務所に戻って先輩の高橋さんに聞いて笑われたりもしていました。そのように、修業時代は青木さんや先輩たちの後ろ盾もあり、女性という理由で不利な思いをしたことはなかったのです。
性差をはじめて意識したのは、独立した後です。そのころは、女性で建築家であることを珍しがられました。スタートして最初の半年は私一人の事務所。その後、スタッフに入ってもらって四人体制になった時も、女性だけのチームでしたので、打ち合わせの席などで、「(建築家の)先生はこの後に来るんですか?」と言われ、「私です」と伝えると、「えっ」と驚かれることが、ままありました。今はたいていのクライアントが事前にネット検索してご来社されますが、当時は検索の習慣もなく、初対面で挨拶すると驚かれるので、名乗ってから相手の驚く顔を見て気まずくならないように、下を向いて三秒数えてから顔を上げていました。
若い時は特に設計図通りの施工をお願いしても、「こんなことはできない」と、現場の方に言われることもありましたし、そんな状況をどうにか変えたいと、もがいている時期もありました。そこから得たコミュニケーションの要点は、やはり相手の立場に立って考えることでした。
「こんな図面じゃ、工事なんてできないよ」と言われた時でも、真っ向から反論はしない。かっとなって衝動的に反論したとしても、何も得るものはありません。一時はスッとしたとしても、後で必ずイヤな気持ちと、現場が終わるまで続く関係を少なからず壊してしまった後悔が、自分に降りかかります。とにかく冷静さを保つことが大切です。
そういう経験をするたびに、相手と一定の距離を置いて観察する習慣が身に付いていきました。自分の中で距離をうまく取れれば、冷静さを保てます。相手の言い分も聞いた上で、「では、少し考えてみます」と、いったん引く。そして、頃合いを見計らって、しれっと同じ要望の図面を出し直す。「時と場所を改める効用」というものがあるのです。冷静になれば、解決方法が向こうから出てくることもあります。
常に気をつけているのは、相手を尊重することと、プライドを傷つけないことです。自分のやってきた仕事に誇りがあればこそ、不意にプライドを傷つけられると、頑なになってしまうことは起こりえます。みんなの前で言い負かしたり、意地の張り合いをしたりもしません。力比べをしても本来の目的には到達しないことを理解して、ちゃんと机の上で語り合えるようリセットします。
もちろん筋の通った意見には、きちんと耳を傾けます。相手の思いを尊重しつつ、こちらのリクエストをお伝えしていくようにします。「勝ち負け」ではなく、最終的に信じた建築が実現するゴールを目指して、粘り腰でやっていく覚悟は必要です。
さまざまな現場をスタッフに任せるようになってからは、厳しい指摘が私にではなく、スタッフに向くようにもなりました。そのような時は、責任者として私が話し合いに臨みます。
一度、相手があまりにも非協力的だったので、本心から「じゃあ、やめましょうか?」と口をついて出てしまったら、「いやいやいや」と、急に態度を翻されたこともありました。案件が取りやめになったら、その人だって上から怒られるわけです。
さまざまなシチュエーションがありますが、どんなにイヤなことを言われても、「何かの事情でこんな言い方になっているけれど、この人の本来の思いは何だろう?」と、その言葉の裏の思いを想像できれば、心を落ち着けることはできます。相手から見た景色を想像し、その立場になって言葉の裏側を想像してみる。裏側が分かったら、相手が気にしている部分をていねいに解決していくように努めます。
相手をリスペクトして、一緒に同じ目標を目指すことの意義を見出せた時に、関わるみんなが、それぞれの立場で大きな力を発揮してくれます。その時は感謝の気持ちを言葉にして伝えます。建築ができ上がった時に、みんなで喜ぶ瞬間は格別です。そのために建築をつくっていると言っても過言ではありません。
◆現場で人とつながる
現場での人間関係は、なかなか一筋縄ではいかないこともありますが、本当は人間くさくて、面白い場面も多いです。だから私も続けていられるのだと思います。
たとえば「女神の森セントラルガーデン(現・アルソア女神の森 シンフォニアガーデン)」(山梨県、二〇一六年)のプロジェクトでは、二千平方メートルに及ぶ外壁に、特殊な塗装手法で「森綾模様」という、この施設のためにつくったオリジナルパターンを塗っていく必要がありました。
特殊塗装の中村修平さんがレシピをつくり、現場で複数の職人さんが実際に塗っていくことになりましたが、途中で手が変わってしまうと模様の雰囲気も変わってしまいます。その時は一人の職人さんが「全部自分がやるよ!」と申し出てくださり、全体を同じテイストで見事にまとめ上げることができました。
二〇二四年のアンテプリマのローマ店内装では、壁面を細かいドレープのパネルで構成することにしました。しかし、このパネルをどのようにつくるかについては、なかなか決まらず、困りました。すると、イタリアの施工者側から「自分たちの木の加工技術を使えばできる」という提案がありました。以前に同じ店舗の内装を手がけた時に、最後まで責任を持ってくれない施工者に手を焼いた経験があったので半信半疑でしたが、今回は自分たちの仕事に誇りを持って、提案をしてくれる施工者に出会えました。
別のブランドショップのファサード用に、特殊な外部ファブリックもイタリアの工場でつくったことがあります。このメーカーのイタリア人社長も、以前の現場ででき上がってしまった私のイタリア人観を覆してくれる働き者でした。日本だと建築家に対してそこまで言わないような意見でも、あらゆる角度からバシバシと言ってきます。それはひとえに、よい作品にするため。そういった職人魂、プロフェッショナルの心意気に触れるような、建築現場ならではのやりとりは楽しいものです。
現場でのコミュニケーションとは少しズレますが、日本の地方など共同体が強く残る場所でのプロジェクトは、私のような建築家が壇上でコンセプトを語るのでなく、地域伝来の風習やお祭りを一緒になって楽しむ方が、理解や結束を得られることがあります。
通常、建築の説明会は公民館などで行われることが多く、どうしても住民の方と建築家が相対する構図になりがちです。東京から来た〝建築家先生〟が、はたして自分たちの声に耳を傾けてくれるのだろうかと、住民サイドは意見を言うにもかしこまってしまいますし、建築家だって「いったい、何を言われてしまうのだろうか」と、身構えてしまう部分があります。
たとえば豊島横尾館は、すでにでき上がっていたほかのアート施設と違って、集落の真ん中に立地するので、地域のご理解をいただくことがとても大切でした。
この時は福武財団の計らいで、説明会の代わりにリノベーション工事中の古民家の敷地で上棟式の伝統行事「餅まき」を行い、私も特設の足場の上から餅をまきました。この島にこれほど住民の方が集まっている光景をはじめて見たという人がいるくらい、みなさんが集まってくれました。そのタイミングで美術館のコンセプト説明をさせていただくと、みなさんとの距離が一気に近づきました。
その後、近くの中学校の体育館で池のタイル貼りのワークショップを三日間開いた時も、地元から多くの参加があり、「ここは自分たちの美術館だ」と、思っていただけるようになりました。
建築家がどれほどかっこいい言葉や模型を示したとしても、建築とはリアルな物体に着地するので、現場でのコミュニケーションがいちばん理解し合える方法だと思います。
また、建築はどんなに構想を練り上げたとしても、実現に至らないことが大半です。事務所で手がけているプロジェクトも、常に浮き沈みがあります。話がいきなり止まってしまう案件もあれば、みんなの頑張りでゴールまで着々と進むものもあります。そして、どの過程でも想定外のことは必ず起こります。
一つひとつの進捗に一喜一憂するのではなく、遠くから海を眺めるような気持ちで、それらの波をとらえることも大切です。たとえば一つの案件が膠着状態に陥っていても、引いた視点で全体を眺めて、うん、海面はまあまあだな、と思えれば、あたふたせずに船を進めていくことができるのです。
クライアントからの厳しい意見は、むしろ作品の完成度を高めるチャンスです。最初は多少凹みますが、経験を積むうちに、新しい視点をもらえたから、これをきっかけにもっとよくしていこうと思えるようになりました。そのようなやりとりをさまざまな案件で同時に続けていくことは、かなり疲れることでもありますが、行き詰まったら一晩眠れば心機一転、必ず打開策は出てきます。
◆不安はブラックボックスに
とはいえ、仕事では自分を責めてしまうこともありました。その時に私の気持ちを救ってくれたのは、意外にも日本の伝統的な方法でした。
第三章で述べた、独立後に遭遇したトラブルもそうですが、人生に波があるのは普通のことです。しかし、当時はそうしたイヤなことが続けて起こっていて、かなり落ち込みました。友人にその話をしたら、「厄年なんじゃない?」と言われました。それまで厄年などを信じたことはありませんでしたが、その時は精神的な支えを求めていたので、「え、厄年のせいにしてもいいの!?」と、目からウロコが落ちる思いでした。ずっと自分を責めていたのに、目の前に現れた「厄年」というブラックボックスにイヤなことをしまえば、苦しさから逃れられる。それでいいんだよ、と言われた気がしました。
だったらお祓いだということで、早速、母とともに地元・阿佐ヶ谷の神明宮にお参りに行きました。かつては天祖神社という名前だった神明宮では七五三を祝っており、高校時代にお正月の三が日だけ巫女のアルバイトをしたこともあって、なじみの深い神様です。なぜかその時はガムラン音楽が流れていて、妙にエキゾチックで神秘的な雰囲気も漂っていました。
神殿でお祓いをしていただくと、これでもう大丈夫と心がスッと軽くなり、日本の伝統的な精神浄化システムのすごさを認識しました。理不尽な何かが我が身に起こった時、自分を責め続けなくてもいいように、神様がブラックボックスを用意して、そこに悪いものを全部入れて捨ててくれる。それは先人が積み上げてきた大きな知恵なのかもしれません。
京都に住む友人は、「京都のおばあちゃんは、何でもかんでも『八卦さん』に聞きに行く」と言っていました。八卦とは占い、易のことです。じつはこれも人間関係が密になりやすい古いまちならではの、すぐれたシステムなのですね。たとえば、知り合いから気の進まない話を持ち掛けられたけれど、面と向かって断っては、角が立つ。それで「ありがたい話やねんけど、八卦さんにおうかがいしたら、今はあかん言うとんねん」と、占いのせいにしながら、やんわりと断っていく。私がイヤなのではなくて、八卦がダメだと言っているということで、人間関係が丸く収まっていくのです。
すべてを自分のせいにしなくてもいい。そういう「頼り方」もあるのだと気付きました。
◆建築という「趣味」
建築家の仕事は現場と切り離せないので、国内、海外問わず出張がひんぱんにあります。頭と身体をフルに使って、一日の終わりにはくたくたに疲れてしまうことも多いのですが、子育て中だと、ゆっくり眠ることはまずできません。
出張中ではなく、東京にいるのであれば、オフの時間はそれこそ子どもと一緒に過ごしたい。海外出張の時は、逆に子育てとは切り離されているので、それを言い訳にして空き時間にマッサージに行ったりしますが、私はお酒も飲まず、とりたてて趣味もない人間なので、子どもとの時間が気分転換そのものになります。
結局、仕事から疲れて帰ってきて、子どもたちとテレビを見て、あははーって一緒に笑って、そして川の字で寝る(時々キック、パンチを食らいますが……)ことが、いちばんリラックスできます。
一度、仕事でリゾートホテルに泊まっていた時に、午前中が空いているから、リゾートホテルっぽいことをしよう!と思い立って、プールサイドのデイベッドに寝そべって、トロピカルジュースを注文したことがあります。
リゾートホテルのプールサイドでトロピカルジュース……は昔からの夢でしたが、私の場合は十分で飽きてしまいました。ジュースなんてあっという間に飲み終えてしまうし、その後は、手持ち無沙汰でいたたまれず、iPadを開いて仕事に取りかかっていました。そもそもリゾートホテルにチェックインした時も、くつろぐどころか、部屋の隅々をチェックするという癖が出てしまいます。私はリゾートホテルや温泉でゆっくりするというスキルを持ち合わせていないのです。ゆっくり一人でリラックスするにも、スキルが必要だと思いました。
高校生のころの「冬眠時代」を思い出すと、今のワーカホリック的な動きは、自分でも信じられないのですが、自分のどこかに高校時代の私のような怠け者が潜んでいるから、気をつけないとまた怠け者になる、という強迫観念があるのかもしれません。小学校の時に飼っていたハムスターが回し車に乗って、ずっと走り続けていた姿を時々思い出します。
私にとっていちばん苦手な質問は「趣味は何ですか?」です。答えを持たない自分が面白くない人間のような気がして、昔は適当に答えていました。たまたま前日の深夜にゼリーをつくった話を持ち出したら、「お菓子づくりが趣味なんですね!」と反応されて、曖昧に答えた話を当時のスタッフにしたところ、「ウソじゃん!」と笑われたこともありました。
やっぱり仕事がいちばん好きで、打ち込めます。特に子育て中だと、家事以外の雑用も際限なく湧き上がってきて、仕事に打ち込める時間がこの上なく貴重なものになります。事務所に行くと「わあ、これで仕事に集中できる」とマインドが切り替わって、ますます仕事に打ち込むことになるのです。
スタッフを抱えての事務所経営は、山あり谷ありで、今に至るまで、どうにかこうにか乗り越えてきた、というぐらいの感覚ですが、建築というものは、完成した時の喜びが、もうとてつもなく大きい。自分の作品が世に出たということよりも、一緒につくった人たちと一緒に喜べるということが、すごく楽しい。みんなで頑張った、よかった、というその瞬間が最高に幸せで、つらさ、苦しさ、しんどさが、そこで全部リセットされて、また次の仕事に臨んでいけるのです。
建築という「趣味」は、一度知ってしまうとやめられなくなってしまいます。
◆ドバイ万博日本館
二〇一八年、次の節目となるドバイ国際博覧会(ドバイ万博。コロナ禍で当初予定の一年後、二〇二一年に開幕)日本館のデザインアーキテクトに公募で選ばれました。その後、NTTファシリティーズ、Arup(アラップ)のエンジニアリングチームとの協働で進めることになりました。
設計に臨む時は、どのプロジェクトでも、その土地のコンテクスト(文脈)からどのようなストーリーが描けるかを大切にしています。
ドバイへ現地視察に行った時は、まだ砂漠で何もないところに、日本館の敷地として、角地に変形台形の区画がありました。日本館はまだテーマが決まっていませんでしたが、万博全体には「Connecting Minds, Creating the Future」というメインテーマが設定されていました。建築のコンセプトはこのメインテーマから「Connect(コネクト)」としました。
公募の時から私には、ここで実現させたい三つの「コネクト」の要素がありました。
一つは、環境装置としての建築。ドバイのあるアラブ首長国連邦(UAE)は高温多湿の砂漠気候で、建物の冷房設備に多大なエネルギーを費やしています。さらにUAEをはじめとするアラブ諸国では、水の確保が深刻な都市課題で、自然の水源に恵まれた日本の風土とは対照的です。中東には「バードギール(採風塔)」と呼ばれる古くからの建築様式があり、それが天然の冷却装置として長い年月にわたって受け継がれてきました。
UAEの都市部では現在、海水から生成した淡水が重要なインフラになっていますが、その技術の多くは日本からのものです。中東伝統の「風」のシステムと、日本の風土と技術を象徴する「水」を用いて、建築全体のシステムと形をデザインできるのではないか。そんな着想がありました。
二つ目は、イスラム文化と日本文化との関係性の表現です。日本の伝統文様にはイスラムの文様に通じる幾何学模様や唐草模様が見られます。それらは古墳時代にシルクロード経由で日本に伝わったのではないかと想像しています。
つまり千五百年前からイスラム諸国と日本は「コネクト」していたのではないだろうか。そう考えました。幾何学模様は自然の摂理と無限の宇宙を表し、その繰り返しによって、空間そのものの強い構成要素にもなります。日本の建築でも組子のような装飾など、各所に幾何学的な繰り返しが見られます。そのような伝統文様のモチーフを、現代ならではの工法と素材を使って取り入れることで、時間、空間、国境を超えたつながりが表現できるのではないかと考えました。
三つ目は、まさに万博の開催意義につながっていく、未来の世代に向けたメッセージです。UAEは未来を担う若い世代が多いことが特徴です。他方、世界経済フォーラムが発表するジェンダーギャップ指数では日本もUAEも公募当時は百位以下にあり、その解消は両国にとって大きな課題でした。ドバイ万博では、あらゆる年代、ジェンダー、国籍の人が集える場を提供したいと思いました。
◆白銀比、水、麻の葉、アラベスク
前述したように、通常、私たちが建築を設計する時はコンテクストを読むところから始めます。周囲の環境はどうなっているか? 周りに建つ建物はどういったものか? この場所の歴史は? ドバイの日本館の敷地は? そういったことを調べていくのですが、ドバイはどの情報も希薄な砂漠地でした。敷地自体がまだインフラも何も整っていない場所であり、何を手がかりにしたらいいのか戸惑いました。
そこで日本ではあまり使ってこなかった「絶対比率」を使おうと考えました。たとえば砂漠に立つピラミッドは黄金比(近似値は五:八)の建築として知られています。ドバイでは、古来の日本で使われてきた白銀比(近似値は五:十二)の二等辺三角形が、台形の敷地にピタリとハマりました。二等辺三角形を台形にはめると、余白に別の小さな二等辺三角形ができるので、そこに水盤を配置しました。そうすれば、角地の立地に対して、どちらの方向から見ても外観がよく見えるようになるのです。
次のキーワードは、もちろん「水」です。万博に合わせてUAEがドバイの人たちに行ったアンケートでは、日本の魅力として「美しい四季」と「先端技術」が回答のトップになっていました。その二つの要素に関わるのが「水」です。
ドバイの年間降水量は日本の二十分の一。砂漠地帯の中東と、梅雨がある日本では気候に大きな差があります。ドバイでは足りない水を水技術でつくり出している一方、水源が豊かな日本では、水の災害に直面することも多々あります。極端に違う土地だからこそ、ひとくちに「水」といっても表現が変わります。建物前面の水盤は、周囲の光景をゆらゆらと水面に映し込む水鏡ですが、同時に海側から吹く偏西風を気化熱で冷やして、建物に流し込むことで、涼しさをもたらす機能も担うのです。
文化的なつながりとしては、「文様」が媒介になります。建物の前面を覆うファサードは、日本の伝統的な「麻の葉文様」を三次元化して、構造体としました。麻の葉文様は三角形で構成されたシンプルな幾何学模様です。だったら三角形トラスの構造形式が可能になるかもしれないと発想し、そこから構造体に発展させました。すると正面からは麻の葉文様、斜めからは「アラベスク」のように見える複雑な幾何学模様になります。このようにして、二つの伝統的な文様を一つのファサードの中に表現しました。
この立体格子には小さな白い膜を張っていき、日差しを遮る環境装置としました。これにより、木漏れ日のような光が生まれます。また、日本伝統の折り紙のイメージも託しました。折り紙は相手への敬意から始まった礼法という由来があるので、まさに人々を迎えるファサードにふさわしい。白い膜は光をきれいに反射するので、光の演出がしやすくなることも利点でした。特に夜のライトアップでは、昼間とはまた別の幻想的な眺めを浮かび上がらせます。
ここでは照明デザイナーをお願いする予算がなかったので、照明計画は現地の電気施工担当の方と私たち設計チームで考えました。開幕ひと月前に現場に飛んで、水盤脇にテーブルをセット。インド人のプログラマーが、私たちの要望をその場でコンピューターに打ち込んでいきながら、最終的な光のシーンをつくり上げていきます。彼らはとても優秀で、私たちの細かな要求に一生懸命応えてくれました。
立体格子の組み立てには、ドイツのメロ社のボールジョイントというシステムを使っています。ボールジョイントを使うと、部材をプラモデルのように組み立てていくことができます。現地の職人さんの技術が分からなかったので、プラモデル的な組み立て法は、期間や予算を守るためのリスク管理やクオリティコントロールの面でもプラスになりました。
もう一つ、このボールジョイントを使ったのには大きな理由がありました。
私は、一過性のパビリオンをつくることに、建築家としての責任を感じていました。建築は環境に大きな負荷をかけて完成するものです。どんなに工夫を凝らしたパビリオンも、万博の会期が終わったら、建物が解体され、部材が廃棄されておしまい。そうやって万博は、五年ごとにぶつ切りで終わってきました。
ファサードにボールジョイントを使えば、ドバイ万博が終わった後に、それらをいったんバラバラにして別の場所に運び、もう一度組み立て直すことが可能になります。そうすれば後に避難所のテントや、暑いドバイの日除けとしてリユースできるのではないか─その思いは、二〇一八年に行った最初の提案から盛り込んでいました。
思いはその後、二〇二五年開催の大阪・関西万博につながっていくことになりました。
◆大阪・関西万博「ウーマンズ パビリオン」
ドバイ万博の後に、大阪・関西万博で私は「パナソニックグループパビリオン『ノモの国』」と「ウーマンズ パビリオンin collaboration with Cartier」の二館のデザインを担当することになりました。
ドバイ万博は中東、アフリカ、南アジア地域で初となる万博でした。そこに出展したウーマンズ パビリオンは、一八五一年から続く万博の歴史上、はじめて女性のエンパワメントをテーマに、企業と政府が共同出資したもので、カルティエと万博公社の共同出展のパビリオンでした。大阪・関西万博では、カルティエとともに、内閣府、経済産業省、
2025年日本国際博覧会協会が連携・協力しての出展です。
カルティエ ジャパンプレジデント&CEOの宮地純さんとは、ドバイ万博以前にカルティエ現代美術財団が主催した展覧会のオープニングレセプションでお会いしていました。宮地さんとはすぐに打ち解けて、ドバイ万博にカルティエもウーマンズ パビリオンというかたちで関わっていること、それを大阪・関西万博に何らかのかたちで継承していきたいと思っていることを知りました。
その思いは、まさにドバイの日本館を大阪・関西万博にリユースできないかという私の考えと一致するものでした。国連が定めた「持続可能な開発目標(SDGs)」というキーワードが全世界に広まり、日本ではSDGsで掲げられた十七の目標のうち、特に「5」の「ジェンダー平等を実現しよう」と、「12」の「つくる責任 つかう責任(サステナビリティ)」が弱い点とされていました。この二つの解決をゴールにすることは、大きな意義があると感じました。
日本館のファサードのリユース。そしてウーマンズ パビリオンの理念の継承。入れ物と中身という最高のマッチングで、それら二つをドバイ万博から大阪・関西万博にもつなげたい。この時、何かが始まりそうな予感がしました。
宮地さんとはじめてお会いした時に、世の中にはこんなにパワフルなママがいるんだと、親近感が湧きました。宮地さんは三人の息子さんがいるワーキングマザーで、宮地さんも私も自分のスタイルで仕事に邁進してきたタイプです。
公募を経て大阪・関西万博のウーマンズ パビリオンの設計者に選ばれた後、リユースのプロジェクトを進めていくために、宮地さんとはお互いの時間の許すタイミングでオンラインミーティングを重ねました。時には画面上にお互いの子どもたちが入ってくることもありました。
互いに理想を高く掲げて取り組んだリユースプロジェクトでしたが、理想を現実にしていくことには、さまざまな困難がありました。
最初のハードルは、解体後に部材をいかに日本まで運ぶかです。国の予算は、建物を建て、解体し、更地にするところまで。部材をていねいに解体して、ドバイから大阪に運び、保管するお金はどこにもありません。思い悩みつつ、ドバイ万博日本館を施工した大林組に相談したところ賛同を得て、ファサード部材を入札によって国から取得し、ていねいに解体するところまでを担ってくださることになりました。大林組の大林剛郎会長、万博の現場監督を務めていた真田久親さん、そして万博プロジェクトを統括されていた赤松真弥さんをはじめとするみなさまに協力していただきました。赤松さんはゼネコンでは珍しい女性管理職で、自らの思いもあってウーマンズ パビリオンのコンセプトに賛同し、大きな力を貸してくださいました。
◆仲間が増えていく
ここからプロジェクトは大きく前進していきました。
次のハードルは、大阪に運んだ後の保管場所の確保です。ここは物流会社の山九から貴重な協力をいただきました。山九の中村公大社長とオンラインでお話をして、画面ごしに「うちしかできないでしょうから、やりましょう!」という言葉をいただいた時、画面に映っている中村さんが神々しく見えました。
さらにテクニカルなハードルがあります。一万パーツにものぼる部材は、じつはそれぞれに仕様が細かく違っています。たとえばスチールパイプは構造体として経済設計となっており、見た目は同じ径のパイプに見えても、力のかかるところについては肉厚につくられているのです。経済設計とは、建築コストを考えつつ費用を削減しながら設計することです。
はじめに、大阪の倉庫に運ばれた一万点のパーツの種類を細やかにチェックして、次の現場で間違いなく使用できるように管理する必要がありました。それこそ部材のナンバーが「6」か「9」か分からないような、初歩的な問題解決からのスタートです。最終的に部材一つひとつに二次元コードを貼り、大林組のビジュアル工程管理システムによって、どこにどの部材が使われているかが分かるような、徹底した管理体制を整えることができました。それはさらに次のリユースも見越したものでした。
ドバイ万博では台形の土地に二等辺三角形の建物を配置していましたが、大阪・関西万博のウーマンズ パビリオンの敷地は間口が狭く奥行きの深い、いわゆるうなぎの寝床のような形でした。まったく違う形状のファサードに適切な部材を当てはめて、構造的に適合しているかを検証していくプロセスはまさにパズル。パズルを進める際には、リユースの意義、そしてコスト面の両方から「新しい部材はつくらない」というルールを決めていました。この工程だけでも約三ヶ月を要するもので、ドバイ万博で設計エンジニアリングを担当されたArupの徳渕正毅さんと天野裕さんが協力してくださいました。
ウーマンズ パビリオンは最終的に、京都の町屋のように半外部の細長い通り庭や、中庭、風を感じるテラスを設けた、ドバイとは異なる建築になりました。
さまざまな方のご協力で実現することができた万博のリユース建築。日本の法規では、海外で製作、使用された構造部材を日本の建物にリユースすることは原則として認められていません。今回は万博の仮設パビリオンということで可能になりました。お祭りであるとともに、実装実験の場でもある万博の意味が、ここで発揮されました。
今でもこんな大それたことが、よく実現したなと奇跡を感じています。奇跡はみんなの思いと行動から。そのことを実感しています。
◆パナソニックグループパビリオン
大阪・関西万博での、もう一つのパビリオンが「パナソニックグループパビリオン『ノモの国』」です。「ノモの国」でも大林組とタッグを組んでコンペに参加し、採択していただき、パビリオンをデザインしました。
ノモの国の公募では、クライアントの意図として「アルファ世代の子どもたちのための館である」という一文が記されていました。アルファ世代とは、一般的に二〇一〇年から二四年ごろに生まれた世代を指します。まさに私自身がアルファ世代の子どもを育てている親であり、思わず共感を覚えました。
このテーマは、パナソニック ホールディングスの関西渉外・万博推進担当参与(当時)である小川理子さんが、子ども時代に訪れた一九七〇年の大阪万博で「科学者になる」という自分の夢を決めた経験から出てきたそうです。
私自身も万博は次の世代、子どもたちのためのものであると考えています。ドバイ万博の開催期間はコロナ禍と重なっていましたが、その中で私はどうにか自分の子どもたちをドバイに連れていくことができました。その経験は子どもたちにとってよい刺激になったと思っています。
ノモの国は公募段階では具体的な設計ではなく、コンセプトを提案することになっていました。プレゼンテーションにあたって急遽、「絵」が必要になり、夜中に「子どもたちのためのパビリオンって、どんな形だろうか」と考えをめぐらせました。将来に向けてどんどん変容していくであろう子どもたち。まだまだ変わっていく途中だから、何の形か分からない形。生物のように細胞が集まり、柔らかな皮膚のように蠢く建築……。まるで子どもの絵のようなファーストスケッチを描きました。
プレゼン当日には、このスケッチほぼ一枚と、私の熱い思いで臨み、小川さんが「このスケッチには子どものワクワク感が表現されている」と共感してくださいました。プレゼンの後、近くの喫茶店で、ドバイ万博日本館リユースでご一緒していた赤松真弥さんたち大林組チームとお茶を飲んでいる時に電話があり、採用の決定が告げられて、みんなでガッツポーズをしたことを覚えています。
◆スケッチを形にする
最初に描くファーストスケッチ通りに建築をつくることは、じつはとても難しい作業です。構造や法規などいろいろな条件の中で、建築として成立させなければなりません。パナソニックグループのパビリオンでは、子どもが描いたようなスケッチを大人たちが寄り集まって大真面目に実現させていくという、難題に立ち向かうプロセスがありました。
苦戦したのは、ぐにゃぐにゃと曲がった構造の実現です。細胞のように単純な形のパーツが集積することで全体をつくることができないか。そう考えながら、構造的に合理性があり、単純で美しい形を見つけるのに三ヶ月の試行錯誤がありました。
最終的に、少し捻った丸い輪を反転してつなげていく「バタフライモチーフ」を構造体にしました。バタフライモチーフは、パビリオンのテーマである人の営みの循環(三百六十度)と、自然の営みの循環(三百六十度)を合わせた「七百二十度の循環」を表しています。構造解析によって検証を繰り返し、部位ごとに必要な強度を持った三種類の径のスチールパイプで構成されています。
直径一メートルから一・五メートルのバタフライモチーフには、ピンク、紫、青という三色の金属をスパッタリング(蒸着加工)したオーガンジーを張りました。この布は光のあたり方によって玉虫色に色が変わります。
フレームに張ったオーガンジーは、のれんのように下部を開放することで、風を受けてはためきながら、さまざまな色、光とともに表情を変えていくようにしました。万博会場の夢洲は海上の埋め立て地で、海から吹き抜ける風が特徴です。その風を積極的に取り込むことで、建物に躍動感を与えたかったのです。昼間は硬い建築の表面が、生き物のように動く様子が面白く、夜はLEDでさまざまにライトアップされた眺めが、違った表情を見せます。
オーガンジーの制作は、青木事務所時代からお世話になっているテキスタイルデザイナーの安東陽子さんにお願いしました。たくさんの試作品をつくり、現地のモックアップに実際にかけて試しながら、使うものを決めていきました。
金属スパッタリングをかけると、もとの布色とはまったく違う色に仕上がりますので、サンプルを見ないと仕上がりが想像できません。安東さんにしても、オーガンジーは通常、舞台衣装に使う素材で、建築の外部に使うのははじめてのこと。万博開催の六ヶ月という期間限定だからこその選択でしたが、風の強い場所なので補強には苦心しました。一方で、ある程度布が風化していく姿も、生物的なあり方を想起させて、それもいいかなと思えました。
ノモの国は最終的にファーストスケッチとかなり近いイメージに仕上がりました。これは、なかなか珍しいことです。
◆「自分ごと」として
ウーマンズ パビリオンは幾何学的なパーツで構成されており、構造システムが見えやすい建築です。対して、ノモの国は一瞬では構造システムが見えにくい自由な形で、自分の中では「対をなす建築」になっています。
二つのパビリオンのテーマは、それぞれ「女性」と「子ども」。どちらも私にとっては身近なテーマで、まさに自分ごととして取り組むことができました。自分ごとで取り組んだのは、私だけではありません。関係する多くの方々が自分ごととして取り組んでくださった結果、それらの力が大きく実を結びました。
万博に限らず、あらゆるプロジェクトの成功は、まさにこの「自分ごと」にあるのではないでしょうか。意義は誰かに与えられるものではなく、それぞれが自分で見出すもの。意義を見出したら、今度はそれを実行に移す。じつはとてもシンプルなことのように思います。
なお、この二つのパビリオン建築はそれぞれ2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)屋内出展施設、企業パビリオンへとリユースされることになりました。
永山祐子『建築というきっかけ』(集英社新書、8/8発売)より
プロフィール

建築家。
1975年、東京生まれ。
1998年、昭和女子大学生活美学科卒業。青木淳建築計画事務所を経て「永山祐子建築設計」設立。
主な作品に〈ルイ・ヴィトン大丸京都店〉〈豊島横尾館〉〈JINS PARK前橋〉〈ドバイ国際博覧会 日本館〉〈東急歌舞伎町タワー〉〈大阪・関西万博〉のパビリオンなど。
日本建築家協会JIA新人賞、WAF2022優秀賞ほか受賞歴多数。


 永山祐子(ながやま ゆうこ)
永山祐子(ながやま ゆうこ)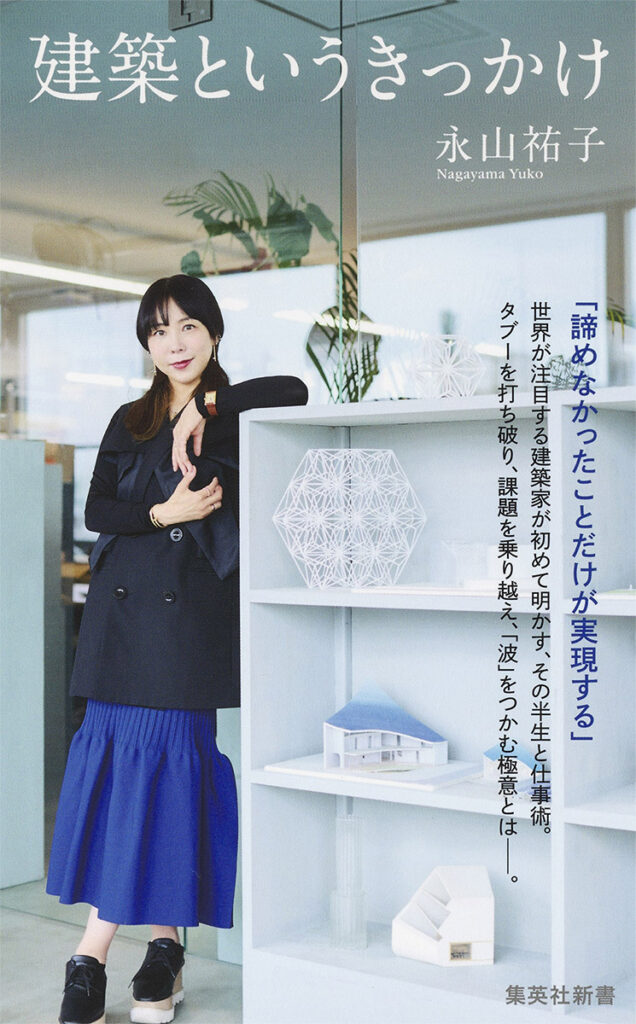










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


