とあるワークショップで出会った方の発言が私の心を捉えて離さなかった。彼女はこう言った。
「『子どもを産むことは親のエゴでは?』という発言を、中村さんは著書のなかで取り上げていらっしゃいましたが、驚いたのが、まさにそれは最近夫と話した内容だったんです」。
彼女はうつむきがちに、自分は子どもを望んでいるけれど、夫がこれからの日本はもっと悪くなるから、子どもを持つことをためらっていると話してくれた。
「子どもを産む理由が知りたい、と夫は言ったんです。自分は論理的で利己的だから、メリットデメリットで考えてしまう。特別子どもにとってメリットがあるのか。きっと子どもは自分たちより生きづらい時代を過ごすだろう。物価高も進むかもしれないし、経済状況も日本は悪くなるだろう。自分たちは子どもに選択肢を与えてあげられるだろうか。これが夫の意見でした。私は、夫がこんなにも子どものことを考えてるのか、と驚いたんです。 彼は彼なりに考えの核をもっている。こんなに考えているのであれば嬉しいという気持ちも起こったんです」
とくに最後の一言に、彼女の夫への深い想いを感じて、ワークショップが終わってから彼女のことを何度も考えてしまった。この本を書くにあたって、まずは彼女に会ってみたい、私はそう思った。
彼女は宗方さくらさんといった。
宗方さくらさんの場合 INV1
「夫とは大学で教科書を販売するバイトで出会ったんです。私は短大卒業後、一度社会人になってから教師になりたいと小学校の教員免許を取って、小学校で数か月働きました。現場を見て、これはただごとじゃないと驚きましたね。教員の働き方改革が全く進んでいなくて、先生たちの業務量が多く、余裕がなさ過ぎて、学級崩壊を起こしている。非常勤講師登録もしていたんですけど、電話がひっきりなしにかかってくるんですよね。倒れている先生とか休職者がすごく多い。学級崩壊した教室の異様な空気も感じました。教師の生存権、人権はどこにあるんだろうって、ずっと頭から離れなくて。そんな状況で、子どもを産んでも大丈夫かなとは、自分自身でも感じていました」
宗方さんはそう切り出した。現在32歳になる彼女だが、昔から子どもが欲しいと思っていたという。
「私は三人兄弟で育ったので、三人はちょっと無理でも子どもは一人じゃないな、二人持てるかな、などと思っていたんです。でも夫と出会って、最初に夫に子ども欲しいんだよねと言ったとき、『多分俺、AIでいい』って言われたんです。えっ、てなって(笑)」
宗方さんの夫は9歳年上だ。ファッション誌の出版に携わり、独立してIT関連の事業を興している。今では夫婦ともに子どもが欲しいと話し合っているそうだが、どんなふうに夫を説得していったのだろうか。
「まずは夫と出会ったことが幸せだと思っているんです。でも夫とは血はつながってないですよね。だから、私と夫のDNAを持つ子はどんな子になるんだろう、楽しみだな、会ってみたいなって。AIじゃそれはできないよねって伝えたと思います」
しかし、それを聞いた夫は「AIでもできます」と言ったという。
「でも、血が通ってないって反論したんです。そうしたら、AIに血、入れますって言って(笑)。だから、これは時間かかるなって最初から思っていました。いま考えると、夫の覚悟がまだできていなかったのかもしれませんね」
夫と出会えたことがまずは一番の幸せと言い切れる強さを、宗方さんは持っている。夫への自然な尊敬心が随所に伺えた。しかし、「AIで良い」という夫と、子どものことを笑って話せるまで、かなりの時間がかかっただろう。
宗方さんのキャリアをふりかえってみよう。都内の公立小学校へ赴任して学級崩壊に直面した宗方さんは体調を崩して現場を離れ、教育業界の人事職員として3年間働いた。その後職員として無期雇用にならず、落ち込んでしまったという。聞くところによると、将来子どもを持ちそうな女性は、永年雇用をしていないという噂だった。その後、別企業で働いたが人間関係に苦労し、今は仕事をすこし立ち止まっている状態だ。はじめに宗方さんに会ったとき、「キャリア形成が大変だった」とは聞いていたが、教育に携わりたいけれど現実は厳しく、試行錯誤を繰り返した、宗方さんの懸命の努力があったことを知った。
「三十代の女性って、すごく難しいなと思ってるんです。仕事もキャリアも築いていきたい時期だけど、子どもを持つかどうかの選択にも迫られて。でも子どもってぽんと生まれるくるものじゃないから、女性には年齢のリミットもある。夫も、男性はあんまり危機感がないから、とは言ってました。やっぱりここ数年の私の様子とかを見て、夫もわかっていったんじゃないかな。変わっていったんだと思います。男の人には、怖いというか、そういうのもあるのかもしれないですね。子を持つって、すごい大きなものを背負うわけですよね。人の人生を背負うみたいに物量感として具体的に思うのかもしれないですね」
子を持つことを、物量感をもって怖がる、この感じは私にも聞き覚えがあった。両親世代の大学教授の知り合いだが、彼はこの世界は悪くなる一方だと、厭世的な世界観を持っていた。こんな世界に子どもを生み出す責任を、僕は取れない、そんなことを話していた。結局そのご夫婦は、留学先の外国で子宝に恵まれ、大切に一人息子を育ててきたのだが。教授は厭世的な世界観を述べて、子どもに責任を取れないと言っていたが、それは「恐れ」と同義だろうと、聞いたとき思ったのだった。
「私たちが小さかったときは、トヨタとか日本の企業が世界のトップを占めていたけど、今はトップを占めるのはほとんどGAFAとかアメリカの企業になってる。この円安で、物価高だし、医療費などで私たちが今高齢の方を支えている中で、少子化が進むと、我々が産んだ子どもたちはもっと大変だと思うから、そこは悩ましいよねみたいな考えは、私も共有していました。親世代は、戦争が終わって高度経済成長があって、わーっと日本が上がるしかない状況で、その後バブルは弾けましたけど、我々三十代四十代は、子どものときにまだそこまで未来に対して悲観的ではなかった。けど、今はやっぱり日本が落ちる一方である。夫は、もし子どもを産むとなったら、やっぱり自分は責任を感じる、と。先行き明るいとはどうしても思いにくい今後の日本で、生まれてくる子どもにはメリットがあるのか。結婚しました、じゃあ結婚式挙げて新婚旅行行って、子ども産みますみたいな、そういう感じで俺はやりたくないと。もっと厳しい社会になっていったときに、親ができることは子どもに選択肢をたくさん与えてあげることかなと思っていると話してくれました」
結婚をして子どもができて……という無防備なエスカレーターのような人生観は、もう私たち世代はとっくに失っている。経済的にも自分のことだけでも精一杯で、子を持つことが端的に重荷だ、責任重大過ぎて、もう一人別の人生への責任は持てない、と考える人は増えているように思える。
私は聞いた。
「どうして子どもが欲しいの、って夫から質問をされたら、どういうふうに答えていったんですか」。
「いやあ、やっぱり教育現場に立っていても、子どもから教わることがすごく多かったんです。私自身、すごく家族に恵まれて、小さな頃の旅行とか自然体験、いろいろ連れていってくれて。そういう原体験がずっと心に残っているんです。私がもし子どもを産めたら、子どもにも同じようにさせてあげたいし、自分もたぶんそこですごく学ぶと思うんです。今は夫と二人だけど、子どもが入ることによって、たぶん見える世界も豊かに変わってくるというか、子どもを通して見える社会が、また増えていくんだと思います」
宗方さんは家族のことが心から好きだと言っていたが、宗方さんの家族の形は、徐々に変化してきた。
「父が病気で五十歳で亡くなったんです。すごいアクティブで、リーダーシップの塊のような、太陽のような人だったんですけど。その父が亡くなる少し前から、母が精神疾患を患って、思いやりがあって穏やかな母の人格が変わっていくような感じで、つらかったですね。生まれてきてくれてありがとう、と母は私たちにずっと言うんです。それから父親の名前を呼びながら、助けてと言うので、私も去年は父親が夢にすごく出てきてしまって。父がいなくなってから、私の心もやっぱり埋まらない部分があるんですよね。母の父が同じ病気で亡くなっているんです。もっと若く、四十二歳で亡くなっていて。父の病気がわかったとき、母がパパも病気になっちゃったって涙ながらに言って、二人で病院までの道を涙流しながら歩いたのが記憶に残っています」
父の死と、母の病気。家族にさまざまな葛藤が訪れたが、宗方さんの子どもを持ちたいという思いに、何か変化があったりしたのだろうか。私は気になって聞いた。
「もっと私も父と話したかったし、これからだったのになという思いはありますね。だから、そういう、いいことだけじゃない、つらいこととか、社会の理不尽とかを私も目の当たりにしたので、自分の子どももきっといいことだけじゃない部分も経験していくのかもしれない。そう思ったら、ちょっと立ち止まって考えてしまうことはありました」
それでも宗方さんはこう言葉を継いだ。
「やっぱりつらいこともすっごくいっぱいあるし、本当に不条理だな、納得いかないと思うこともいっぱいあるし、私も父親が亡くなったのは結構きつかった。だけど、やっぱりあの家族に出会えて、旦那さんとも出会って、旦那さんの家族にも出会えて、社会に出てからもいろんな人と出会ってきた。素敵な出会いも、御縁もたくさんあるので、そういうことを感じますね」
子どもを持つというと、ぱっと明るい未来が開けるようにイメージしてしまうが、一人の人間として、自分と同じように良いことも悪いことも待っている。子に降りかかるであろう苦労を想像し、すべての不安を払拭してから、準備万端で子どもを持つなんて、たぶん誰もできない。子どもを持つということは、きっともっと無節操で、無鉄砲で、無理由に、未来を信じることでもいいはずだ。
インタビューで印象的だったのが、宗方さんが、子を持つことをためらう夫に、「そんなに子どものことを考えてくれるんだ、嬉しい」とい受けとめていたことだ。未知なる出会いをあらかじめ祝うような、彼女の人間観がそうさせているのだろう。子を持つことというのは、未来を信じて祝うという態度そのものなのかもしれない。
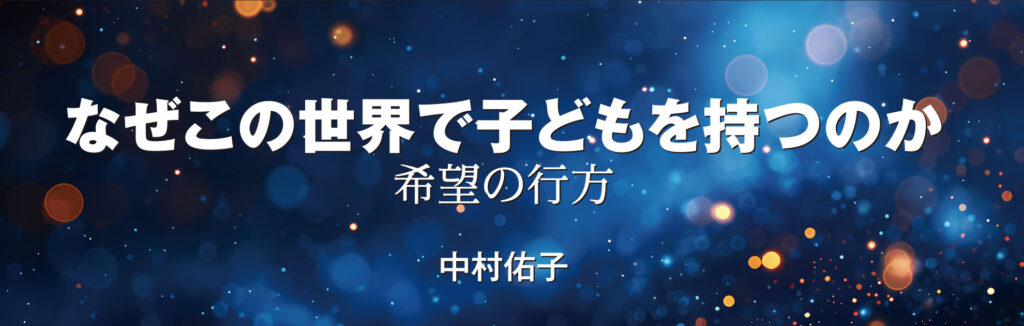
世界各地で起きる自然災害、忍び寄る戦争の気配やテロの恐怖、どんどん拡がる経済格差、あちこちに散らばる差別と偏見……。明るい未来を描きにくいこの世界では、子どもを持つ選択をしなかった方も、子どもを持つ選択をした方も、それぞれに逡巡や躊躇、ためらいがあるだろう。様々な選択をした方々のインタビューを交え、世界の動向や考え方を紹介する。
プロフィール
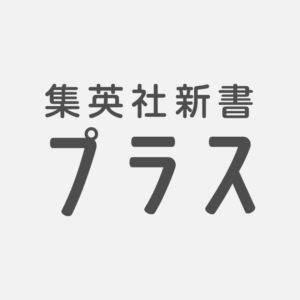
1977年東京都生まれ。作家、映像作家。立教大学現代心理学部映像身体学科兼任講師。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』が、著書に『マザリング 性別を超えて<他者>をケアする』『わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅』がある。


 中村佑子
中村佑子












