最近のメディアの世論調査には、一見ふしぎな数字が表れることがある。
朝日新聞の3月世論調査では、例の商品券配布事件を問題視する人が75%に達し、石破茂内閣の支持率は2月の40%から26%に急落、不支持率は44%から59%に上昇した。誰もが当然の数字と受け止めただろう。
ところが、この問題の責任をとって石破首相が辞めるべきかの問いに、「やめるべき」との答えは32%で、その必要はないとの答えが何と60%に達した。自民支持層に限ると「やめるべき」は20%、「その必要はない」が75%になっている。
同じような設問の他の調査でもほぼ同様の結果が示されているようだ。
商品券配布のようなお粗末なことが、先進国日本の政権交代理由となっては恥ずかしいという受け止めもあるだろう。また、自民党には今、石破首相に代わる人材がいないと思っている人も少なくない。野党に政権を渡すと言っても相変わらずバラバラで、首相にふさわしい人もいないと見られている。「辞めなくていい」という理由はこんなところだろうか。
しかし、この一件は、石破首相の首相としての能力、資質に大きな疑問を生じさせることになった。たまたま「政治とカネ」問題がかつてないほど政治の争点となっている中で、首相の“うかつさ”に驚き・不信感を抱いた人は多いだろう。事件を重大事と受け止めた「75%」の数字がそれを示している。首相の“この局面での非常識な行動”を事前に止める人事や体制も整っていなかったのかという疑問も大きい。
事件が発覚し報道される前に商品券を返還した人もいたようだ。この人たちは、少なくとも首相よりも世論の動向について正しい判断ができたということだ。
首相も人間だから独りで正しい判断を続けることは難しい。しかし、首相の場合、小さな判断ミスが国や国民に災禍をもたらすことが少なくない。特に首相の言動は事後に取り消したり訂正したりすることが困難である。うかつな首相は常に国民をはらはらさせる。
本来、首相には閣僚、党役員の支えがあり、補佐官、秘書官体制も整っている。しかし、その人たちに事前に相談しなければ自分のより正しい判断に活用することができない。また、首相の側近議員であっても判断力の乏しい人では当然逆効果になる。親族、同級生などでもよい。長年、まわりの人から信頼されている“常識人”の意見を求めることが必要だ。
なぜなら、今回の商品券配布は、常識人ならそのほとんどが大反対するだろうからだ。石破首相は「やめる必要がない」とかばってくれている人の深刻な不安に何としても応えなければならない。
私は、かつて宮澤(喜一)首相、細川(護熙)首相など何人かの首相至近にあって日常の言動について意見を求められた。「そんなことまで」と思われるほど前もって言動の是非について訊かれたこともある。石破首相は「今度から慎重を期します」ではすまされない。首相の独断に不安がつきまとうからだ。親族でも友人でもよい。首相の言動を“常識”によってチェックする周辺体制を早急に整えてほしい。あくまでも世論は、それを前提として「辞めなくてよい」と言っているのだ。
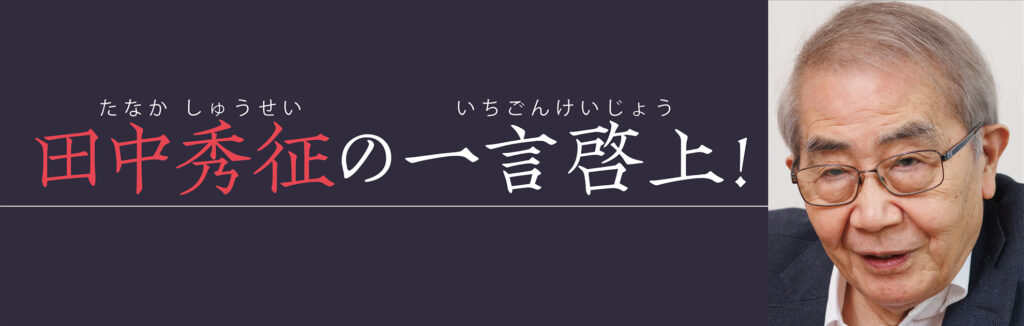
裏金、世襲、官僚機構の腐敗・暴走…政治と行政の劣化が止まらない。 この原因は1990年代に行われた「政治改革」と「省庁再編」にある。 その両方の改革を内部から見てきた元衆議院議員の田中秀征が、当時の舞台裏を解説しながら、何が間違っていたのかを斬りつつ、 今、何を為すべきなのかを提言していく。
プロフィール

(たなか しゅうせい)
1940年、長野県生まれ。東京大学文学部西洋史学科、北海道大学法学部卒業。83年に衆議院議員初当選。1993年6月に新党さきがけを結成し代表代行、細川護熙政権の首相特別補佐、第1次橋本龍太郎内閣で経済企画庁長官などを務める。福山大学経済学部教授を経て現在、客員教授、石橋湛山記念財団理事、「さきがけ塾」塾長。
著書に『石橋湛山を語る』(佐高信氏との共著、集英社新書)『自民党本流と保守本流』(講談社)『新装復刻 自民党解体論』『小選挙区制の弊害』(旬報社)『平成史への証言』(朝日新聞出版)など。


 田中秀征
田中秀征









 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



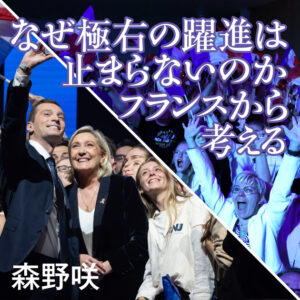
 森野咲
森野咲