三角大福中の時代と言われても、若い人はチンプンカンプンだろう。「さんかくだいふくちゅう」と読むのだが、ますます意味不明になるかもしれない。これは1970年代当時、自民党の派閥を率いて総理総裁となった五人の政治家の名前の一字を取ってつなげた言葉だ。
すなわち、三木武夫の三、田中角栄の角、大平正芳の大、福田赳夫の福、中曽根康弘の中だ。誰が言い出したか不明だが、あっという間に広まった。ここに中川一郎の中を付け加える人もいた。
この五人は、一時代を画した岸信介、池田勇人、佐藤栄作の官僚トリオの時代を通じて力をつけ、独自の派閥を築き、総理総裁を目指して激烈に覇を競った。今考えると札束が舞うような一面もあったが、派閥の政策作成や研修会は、党よりも真剣で充実したものだったと感じる。文字通り「派閥あって党なし」というものだった。そして五人は、総裁選で手を組むことはあったが、それぞれが間に合わせではない政策構想を掲げて戦いに臨んでいった。
この五大派閥は、かつての中選挙区単記制だからできたとは言えるが、対革新、対社会党という場合には、党として結束することができた。かねてから私は、この五人が創業政治家であり、世襲二世ではないことを評価してきた。あえて言えば、福田赳夫が町長の子息という利点を持っていただけだ。
もう一つ、彼らの生い立ちには顕著な共通部分がある。それは、彼らは、その選挙区で生まれ育ち、そこで初等、中等教育を受けていることだ。要するに、彼らは生粋の土着政治家で、選挙には幼い頃からの友人、知人がいる。だから、ある人が立候補すると同級生が強力な支援をするが、しばしば「あれは器ではない」と“落とす会”ができたりする。
かつて、石原慎太郎氏が参議院から衆議院に回る時、湘南から立つか東京から立つか注目されたことがある。結局彼は東京二区を選んだが、湘南から立てば「落とす会」ができたという報道もあった。故郷を選挙区とすれば、子供の頃、隣の家の柿を取って食べたことなども表に出てくる。東京の中学や高校を出ると昔の話は全く出てこない。わずらわしさはなく選挙で余計な苦労がなくなる。
しかし、選挙区制度が地域の代表、地域の代弁者を選ぶものである以上、土着性の強い人ほど適任だと言えるだろう。何よりも、それが政治家としての見識や能力を鍛える道場となるはずだ。
三角大福中がいずれも創業者で、しかも土着の人であることが、世襲政治家の追随を許さなかったのだろう。外務省のかつての高官が私に「外交は1970年代までは政治主導だった」と言ったことがある。その後は官僚主導になってしまったのか。
三角大福中は、自民党という大政党の党の枠を突破できる政治家だったと言ってもよい。また、官僚が追随できる能力を持っていたと言えるだろう。
急激な劣化が嘆かれる今、政治は優れた創業政治家の出現を待望している。
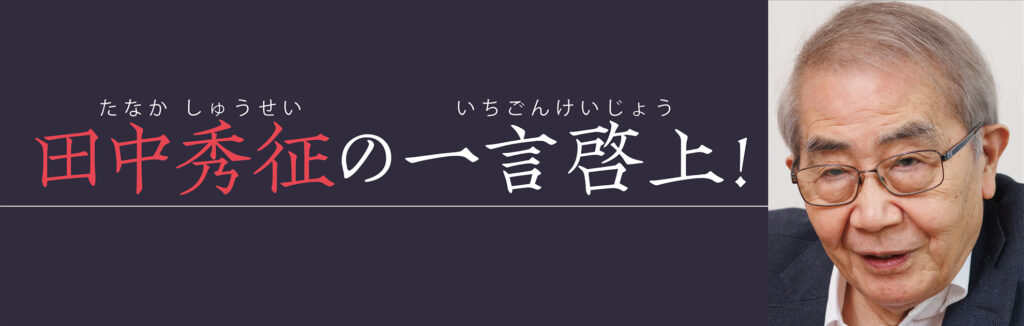
裏金、世襲、官僚機構の腐敗・暴走…政治と行政の劣化が止まらない。 この原因は1990年代に行われた「政治改革」と「省庁再編」にある。 その両方の改革を内部から見てきた元衆議院議員の田中秀征が、当時の舞台裏を解説しながら、何が間違っていたのかを斬りつつ、 今、何を為すべきなのかを提言していく。
プロフィール

(たなか しゅうせい)
1940年、長野県生まれ。東京大学文学部西洋史学科、北海道大学法学部卒業。83年に衆議院議員初当選。1993年6月に新党さきがけを結成し代表代行、細川護熙政権の首相特別補佐、第1次橋本龍太郎内閣で経済企画庁長官などを務める。福山大学経済学部教授を経て現在、客員教授、石橋湛山記念財団理事、「さきがけ塾」塾長。
著書に『石橋湛山を語る』(佐高信氏との共著、集英社新書)『自民党本流と保守本流』(講談社)『新装復刻 自民党解体論』『小選挙区制の弊害』(旬報社)『平成史への証言』(朝日新聞出版)など。


 田中秀征
田中秀征









 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


