1945年3月末からの約3ヵ月間、沖縄には米軍が上陸して激しい地上戦が繰り広げられ、軍民合わせて20万人もの命が失われた。戦後も長らく沖縄は米軍に支配され、日本に返還後も多くの米軍基地が存在している。
また、最近では近隣諸国を仮想敵として、全国で自衛隊基地の強靭化や南西諸島へのミサイル配備が進行中だ。
狭い国土の日本が戦場になるとどうなるのか?――沖縄戦の悲劇の構造を知ることで、その実相が見えてくる。
沖縄戦研究の第一人者・林博史氏は、膨大な資料と最新の知見を駆使して『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』を上梓した。
その林氏との共著『沖縄県知事 島田叡と沖縄戦』(沖縄タイムス社)を昨年2024年に刊行した沖縄戦研究者の川満彰氏が、多大な犠牲を生んだ沖縄戦の背景と、新たな戦争を防ぐために何が必要かについて語りあった。その後編。
構成=稲垣收
川満 私はもう30年近く沖縄で平和ガイドというのをさせてもらっていて、子どもたちや労働組合の前で必ず言うことがあるんです。毎年8月、特に終戦記念日の近くになると、「戦争で亡くなった人のおかげで」という言葉を政治家も言うし、マスメディアもそういう言い方にだんだんなってきています。その構造についてです。
私が戦争体験者の話を聞いている中で、あるおばあちゃんは「父ちゃん(夫)は兵隊に取られて南方で亡くなったんだ。長男は防衛隊に取られて亡くなったんだ」と言いました。「残りの子どもたちを、一生懸命畑を耕して、野菜を売って育てたんだよ。畑を耕しながら〝こんちくしょう、誰が父ちゃんを殺したんだ? こんちくしょう、誰が長男を殺したんだ?〟と思いながら耕したんだよ」と言っていました。
戦後日本の高度経済成長は「戦争で亡くなった人のおかげ」ということではなくて、生きている人たちが、亡くなった人たちへの思いを背負いながら、悔しさを噛みしめながら一生懸命生きてきて、そんな彼女たちが、生きている人たちが、高度成長を作ったんですよ。ですから「亡くなった人のおかげ」ではなく、「生きてきた人たちのおかげ」なんです。
では、なぜ「亡くなった人のおかげ」という言い方をするのか? それは戦争に対する責任逃れです。当然ですが、戦争で亡くなった人たちが生きていれば、もっと高度成長はしていたはずです。
一部を除く政治家や戦争を正当化する人たちが、「亡くなった人のおかげ」というような話をしていくと、そこでもう、亡くなった人が「英霊化」されてしまいます。英霊であり英雄ですから、誰が殺したのかという戦争責任も何もなくなってしまう。そこで、先ほど林先生がおっしゃったように、「戦争のせい」、「戦争の責任」で済ませてしまう。

でも、戦争は明らかに最悪の人災なのです。人災には責任が伴います。だからその人災という部分を、これからも追及していかなくてはいけません。林先生がおっしゃるように「二度と戦争しないためにはどうするのか?」生きている人たちの教訓も得ながら、「亡くなった人たちは、なぜ亡くなってしまったのか?」という部分もやっていかないといけない。
去年(2024年)、林先生と一緒に『沖縄県知事 島田叡と沖縄戦』という本を書かせてもらいましたが、今回の林先生の書かれた『沖縄戦』にも、この論点が明確に書かれていて、非常に分かりやすい内容になっています。
この間、「沖縄県史」では、沖縄戦をジャンルごとに分けていって、一つひとつの戦局での戦争責任みたいなこともきちんと書かれてはいるんですが、ジャンルごとで終わっていて、トータル的なイメージがしにくいんですね。
しかし今回の林先生の本では、「第32軍が動いているときに、県はどういうふうに関わっていったのか」とか、「そのときに住民はどういうふうにして排除されていったのか」とかいうことが、非常に明確に書かれています。たとえば、住民の本島北部の森林・山岳地帯への疎開や学童疎開などは、「住民や子どもたちの命を守るため」だったかのように言われることがありますが、実は軍事作戦の邪魔になるものを排除して、軍が作戦行動をしやすいようにしただけのことだった、ということがハッキリ書かれています。北部に疎開した人々が食糧不足で飢餓に苦しめられたことも記述されています。
「軍が悪かった」という言い方をされるが
戦争責任は行政・教育・メディアを含め、「軍官民」にある
林 今の川満さんの話と重なるかもしれませんが、沖縄戦だけでなく、戦後日本社会で戦争を振り返る際に、もっぱら「日本軍が悪かった」ということが語られます。でも戦争を準備し、実際に戦争を戦うことは、軍だけではできないんです。戦争を遂行するために、異論がある人々を抑圧する、言論を統制する、そして一方で人々を戦争に向けて動員する、そのために人々の意識を変えていく、という行政の役割があった。行政の役割や教育の役割も、極めて大きいのです。
そこについて検証することが、たとえば沖縄戦の場合、これまで非常に弱かった。「日本軍が悪かったんだ」というのは、沖縄では誰もが一致できるところだと思うんですが、「行政の責任」についての検証は弱かった。
今日の日本社会の問題を考えても、別に自衛隊が戦時体制を作っていっているわけじゃありません。一般の行政が、それを作っていっているのです。そこには教育もメディアも加担しています。
ですから沖縄戦を含め、かつての日本の戦時体制がどうやって作られていったのか、行政がそれをどういうふうに作っていったのかということをきちんと説明しないといけない。沖縄戦の場合、そこがすごく足りなかったと思うので、そこをかなり意識しながら今回の本では書いています。
そして、それが沖縄戦に突入するまでだけでなくて、米軍が上陸した4月、それから5月という戦闘のさなかにも、実は行政組織はずっと動き続けていて、日本軍と一体となっていました。たとえば南部だと、ガマの中に隠れているその地域の人々もそうだし、他から逃げてきて避難している人々も含めて、村長とか助役、字の区長、さらに警察とか、行政が軍と一緒になって足腰の立つ者を動員して駆り立てていったのです。そういう行政の役割をきちんと書きました。これは現在の日本の問題とも、まさに重なるので。
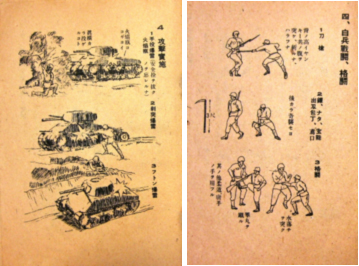
今年(2025年)は治安維持法が制定された1925年からちょうど100年なので、治安維持法の問題が少し取り上げられていますが、実は治安維持法を含めた「弾圧のための法規」を適用したのが警察官僚です。そして実は当時の沖縄の島田叡知事も荒井退造県警察部長もともに警察官僚で、特に荒井警察部長は特高(*1)の経験が多い特高官僚ですから、沖縄の行政が民間の人々を戦争に駆り立てていく上で果たした役割が大きい。それをきちんと見る必要がある。従来の沖縄戦の本では、そこがみんな弱かったと思うので、かなり丁寧に書いたつもりです。
*1 「とっこう」=特別高等警察の略。戦前・戦中の内務省管轄の秘密警察で、国体護持のために国民を監視することが任務。特に共産主義者や社会主義者、反戦論者、朝鮮半島や台湾、満州など日本の植民地出身者を監視・弾圧した。労働者の悲惨な状況を描いた小説『蟹工船』の作者、小林多喜二を逮捕し拷問で殺したことでも知られる。戦争に反対する者を逮捕・拷問・収監した。
川満 そこを本当に丁寧に書かれていますね。林先生がおっしゃるように、そもそも戦争というのは、軍だけではできっこないものです。官だけでもできません。沖縄戦の最中、「軍官民共生共死」というスローガンが使われましたが、まさに軍人も公務員も民衆も一緒にならないと、実は戦争はできない。
だから今現在も、民衆が戦争を正当化してしまうと、もう一気に戦争への道に進んでいくでしょう。沖縄戦をずっと研究してきて、今それが非常に怖い感じがします。今年は80年という節目でもあるし、ここで「軍と官と民の戦争責任」をより明確にしないと。そういった意味で今、特に沖縄県の行政の責任が明るみに出てきていますから、あと一押しが必要です。
私たちが生きている今、国は実際にいろんな法律を通しています。戦争につながる法律が「本当にいいのかどうか」という議論もまともにされないまま、どんどん通されています。でも今ここにいる私たちは当事者なのです。そういう当事者としての戦争責任という部分も、沖縄戦を通して明らかにすべきじゃないかと考えています。
戦争体験者に共感するだけでなく「なぜ戦争を防げなかったのか」
という社会科学的分析が必要
川満 今、沖縄では、あいかわらず6月23日(*2)を前後にして、各学校で子どもたちが平和教育を受ける、というのが一つあります。具体的なやり方としては、沖縄戦の体験者を探して話を聞くわけです。ただ、体験者に話をしてもらう際に、体験者に無理強いをさせているな、というのを非常に感じます。
体験者というのは、あれだけの地獄絵図を自らの目で見て体験し、本当に肌で感じた人たちです。それを学校の授業として「45分とか60分でまとめてください」と言うわけですが、はっきり言ってムリですよ。
もちろん、中にはそれができる方もいて、その方たちを私たちは「語り部」と呼んでいますが、そういう方たちは、もともと学校の先生が多いんです。だから45分とか60分とかで、話のポイントとかを自分で作りながら淡々としゃべることができている。でもそういう人たちがもう、ほとんどいなくなっています。沖縄戦体験者はいまだに多いですが、自分の体験をうまくまとめてしゃべれる語り部は、非常に少なくなってきている。
だから今後は、沖縄戦を体験していない非体験者が自分で学びながら平和学習を率先していって、ポイントとなるところを戦争体験者の方にちょっと話してもらうという、そういう形が望ましいだろうと感じます。
琉球大学名誉教授の東江平之さんは、終戦のとき14歳で、御年94歳になります。沖縄戦体験者で、(沖縄の少年兵部隊の)護郷隊で戦闘に立っていました。彼は私に、「戦争体験者がいなくなるということに対して戦争非体験者はどう思いますか? 戦争体験を継承する責任は戦争体験者ではなく、いつの時代でも戦争を
知らない世代が感性と想像力をみがいて担うべきものです」ということを話してくれました。まさしくそのとおりだ、と今本当に実感しています。
*2:沖縄県慰霊の日。1945年のこの日に牛島満司令官が自決し、沖縄における大日本帝国軍の組織的戦闘が終結したとされるため。
林 今の平和教育についていうと、沖縄戦だけではなく日本における平和教育全般に言えることですが、体験者の証言に依存しすぎなのですよね。基本的に、体験者に共感し感情移入して「こういう体験を、戦争を二度と繰り返しちゃいけないですね」というところでまとめて終わってしまう。そういう平和教育が多い。
日本の場合、加害の問題はもう、ほとんど取り上げられません。もっぱら空襲の問題とか、日本人が被害を受けた問題ばかりです。そこでももっぱら体験者に語らせて、感情移入して「戦争は二度と繰り返しちゃいけませんね」で終わらせる。それをやっている限り、政治的にどういう立場に立とうと誰もが納得するというか受け入れるので、学校にしてみれば、誰からも反発を受けないで済む。ただ、そこには社会科学的な分析が欠けていると私は思います。
「じゃあ、なぜその人たちはそういう被害を受けたのか? 当時の政治や社会や経済などの仕組みはどうなっていたのか? どうしてそれを阻むことができなかったのか?」そういうことを、当時の社会のあり方を社会科学的に分析して、「なぜこうなったのか? 二度と繰り返さないためには、どこをどう変えないといけないのか?」という議論はしないんですね。これは先ほどから言っている沖縄戦の見方と実は同じです。この間、日本社会全体が社会科学的な認識じゃなくて、ともかく「共感」とか「寄り添う」とかいうことだけで終わっている。
寄り添うということを私は全部否定するつもりはないのですが、寄り添いながらも一旦ちょっと突き放して、「何でこの人たちはこんなひどい目に遭わされたのか? なぜなんだろう?」ということを冷静に考えてみる、分析してみる、という思考がすごく大事だと思うのです。そういう訓練や教育が必要じゃないかと。ですから私は、その点も意識しながらこの本を書いてみました。
日本社会全体がもう基本的に今、感情優先になってしまっているので、そこは、同情とか共感をしつつも、冷静に分析し、人々に犠牲を強いた社会の仕組みなどをきちんととらえ、「どう自分は変えていけるのか?」「変えていくためには何をすればいいのか?」「自分には何ができるのか?」ということを考えるべきです。
そういう意味で、日本の平和教育は体験者の証言だけにずっと依拠し続けてきた。その問題が今あって「体験者がいなくなったらどうするのか?」ということも、わからなくなってしまっている。
川満 本当にそのとおりです。私たち戦争非体験者というのは、「なぜ戦争が起きたのか?」ということを調べることはできます。一方、戦争体験者の人たちは、「自分に何があったんだ」ということをしゃべってくれるわけです。だから、非体験者の俯瞰した物の考え方、見方と、体験者の「実際にこうだったんだ」という部分を、うまく組み合わせ、構成して、今の人たちにどうやってわかりやすく伝えていくかが大切だと思います。
その意味でも、戦争非体験者が大枠を作って、その中に戦争体験者のお話を入れていくという形にしたほうが、今の人たちに理解しやすいでしょう。
先ほども言いましたけど、戦争は始めてしまったら、もうダメなんですよ。止められない、本当に。だから、「新しい戦争への道」という言葉が出ている今こそ、「今じゃないと止められないよ」という認識をみんなと一緒に作らないといけないのです。
日英同盟から日米同盟まで常に“最強国”とくっついてきた日本だが
今こそ真の外交力が求められている
川満 本書でも触れられていますが、今、沖縄と南西諸島の要塞化がどんどん進められ、ミサイル配備も進んでいます。そんな中、「自衛隊の沖縄戦認識」にも問題がある、という議論があります。6月23日の慰霊の日に、沖縄の自衛隊幹部や隊員が牛島司令官をまつった「黎明の塔」に参拝に行っていたなど、戦犯に寄り添っている状況があるんです。

先ほど(前編)も話しましたが、中谷防衛大臣が牛島満の辞世の句を「平和の句」だという、とんでもない解釈をしました。そして牛島満をまつった「黎明の塔」に早朝3時とか4時に、自衛隊が隠れるようにして参拝しに行くということをしてきました(批判を受けて現在は中止)。「なぜそこまでやるんだろう?」と考えると、これから起こるかもしれない戦争を正当化しようとしているんじゃないか、ということが非常に気になります。
今、沖縄の新聞の読者投稿欄には「外交が大事だ」という声が非常によく出てきます。沖縄の人たちみんながそうじゃないと思いますが、新聞に投稿する人たちは非常に冷静に物を見ていて「なぜこんなバカげた軍備増強をやるのか? なぜもっと外交努力をしないんだ?」という問題提起をけっこう投稿しています。
「なぜ外交ができないんだろう?」ということをもう少し深く考えていくと、第二次世界大戦、アジア太平洋戦争というものを、日本政府があいかわらず正当化しているというか、自分たちが戦争したことを反省していないということがあります。しかし私は、そこをしっかり謝罪することから外交が始まると思うんです。殴られた相手、足を踏まれた相手は100年たっても痛みを忘れない。被害を受けた人は80年たっても100年たっても痛いわけですから、まずそこに対して、おわびをする。そこから本来の外交が始まって、今の問題につながっていく。
ところが、そういった加害というものにずっと蓋をしていくから、外交の基本的な部分が完全に無視されている。そして「日米同盟」としての軍備強化がまた始まっていく。そういった姿勢そのもののおかしさを、林先生のこの本や、いろんなアジア太平洋戦争の本から、みんなでもう一度学んで、「外交って何だろう?」というところから進めていった方がいいと感じます。
林 今、川満さんから外交の話が出ましたが、近代以来の日本の歩みを考えてみると、最初に、日英同盟を結ぶんですね(1902年)。つまり当時世界一強いと思われる国にくっついた。後にドイツが台頭してくると、今度はドイツとくっついて、日独伊三国同盟を結んだ。第二次大戦でそれが失敗すると、今度はまた世界一強いと思われるアメリカと組んで日米同盟だと言う。そういう意味で「日本の外交ってあったのか?」と。基本的に「一番強い国とくっついていれば何とかなる」という道だけだった。
しかしアメリカが今のように力が弱くなって、しかもトランプ政権は、もう自国のことしか考えない、となっている。だから今は「いったい日本はどういう生き方をするのか?」を本当に真剣に考えないといけない時なのです。
中国がどんどん強くなってくることはまず間違いないですが、その中で「ただ一番強い者とくっついていけばいいんだ」というのではなく、「そういう世界の中で、どうやって日本の人々の安全と生命を守るのか?」という意味で「本当の外交」が必要な時だと思うんです。
しかし残念ながらそういう議論がほとんど起きていません。ひたすら「アメリカのご機嫌をどう伺うか?」しかない。そういう意味で、近代以来の日本の生き方を根本的に考え直す、反省し直すことが必要だろうと。
そこまで言うと話が大きくなりますが、もう少し限定していくと、「戦争にならないための外交にはいろんな努力が必要である」ということと同時に、「仮に戦争になったとしても、人々の被害をできるだけ少なく、最小限にするための対策」というのを自衛隊は軍事組織として考えるべきです。
自衛隊は発足以来ずっと沖縄戦について研究していますが、1950年代ぐらいには、まだ、「日本軍のやり方はちょっと良くなかった」という反省が、少しはあったんです。自衛隊による沖縄戦史のいろいろな研究の中でも。
ところが1960年代になると、そういう反省とか「ちょっと良くなかった」というのは全部消えていった。ひたすら「日本軍は立派に戦った、勇戦奮闘した」という一色になってしまった。しかし大日本帝国憲法下の軍隊をそのまま正当化する必要はないだろうと思います。
日本国憲法の下でもし「自衛隊が必要だ」と考えるのであれば、「どうやって自衛隊が人々の生命や安全を守るのか?」ということを考えなくてはいけません。仮に自衛隊が戦うにしても、「できるだけ住民に被害を及ぼさないようなやり方」を考えないといけない。
しかし残念ながら日本社会では、そこが全然議論されていません。ですから、南西諸島でもそうですが、住民の住んでいるところのすぐ近くに自衛隊基地やミサイル発射基地を造ってしまう。しかし基地があったら、住民は基地もろとも攻撃されてしまうわけですよね。
沖縄本島自体、もう、軍と民衆が一緒に住んでいるところで、ああいう基地のあり方自体がおかしい。これは日本本土でもそうです。本土でも、自衛隊基地の本当にすぐそばに住民が住んでいますし、民間の空港や港も自衛隊や米軍が使っています。そうすると、もう日本中全てが軍事攻撃目標になってしまう。
だから、戦争を起こさせないための努力を根本的にやらないといけないのです。それと同時に、軍事組織を日本という国が持っている以上、「それは住民をいかに守るのか?」という観点で、もっと議論しないといけない。そういうことの手がかりになるようなものを、この本の中では書いたつもりです。
ですから「絶対に戦争をやらないで済むために日本をどうするか?」と。これは沖縄戦の議論を超えて、もう日本国全体で本当に真剣に議論しないといけないところだと思います。
川満 いや、本当にそうですね。政治家は基地問題や安保問題について「これは政治家の専権事項である」という言い方をします。僕はあの言葉が非常に怪しいと思っています。それを打破したのが、前沖縄県知事の翁長雄志さんです。「こういった基地問題はいわゆるイデオロギーではない」「沖縄のアイデンティティーを取り戻すために、自分たちは今そういった議論をしているんだ」と。それで、辺野古の米軍新基地建設にも反対したわけです。
しかし「基地問題や安保問題は政治問題だ」という扱い方をマスメディアがして、それを国民が真に受けて、「結局こういう安保問題や安全保障問題は、全て政治の問題だから自分たちは関係ない」と無関心になってしまう。そういう構造が最近あまりにもひどい。
でもそうではなくて、林先生が言ったように、「なぜ現在これだけ沖縄は主体性を持っているのか?」ということを振り返ってみて、沖縄の基地問題も全国の基地問題も、「これらの基地は、自分たちのアイデンティティーを守るためにあるのか? それとも政治を守るためにあるのか?」といったところから、主体性を持って議論してほしいと思います。
今もう、とにかく無関心者が増えている。それは先ほど林先生が言った、教育の問題やメディアの問題もあって、次第に「話をさせないように」という仕組みがいつの間にか出来上がってしまっているんじゃないか、ということが非常に気になります。
だからこの本のように、「あの戦争は何だったのか?」という部分をきちんと振り返ることができる本が、ぜひ読まれて行ってほしいと感じます。(了)
プロフィール

(はやし ひろふみ)
1955年、神戸市生まれ。現代史研究者、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(社会学博士)。関東学院大学名誉教授。主な著書に『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』(集英社新書)、『沖縄戦と民衆』『沖縄戦が問うもの』(大月書店)、『沖縄戦 強制された「集団自決」』『米軍基地の歴史 世界ネットワークの形成と展開』『帝国主義国の軍隊と性 売春規制と軍用性的施設』(吉川弘文館)、『朝鮮戦争 無差別爆撃の出撃基地・日本』(高文研)、『BC級戦犯裁判』(岩波書店)等多数。

(かわみつ あきら)
1960年、沖縄県コザ市生まれ。沖縄国際大学非常勤講師。2006年、沖縄大学大学院沖縄・東アジア地域研究専攻修了。 著書に『陸軍中野学校と沖縄戦』(吉川弘文館)、『沖縄戦の子どもたち』(吉川弘文館)他、共著に『戦争孤児たちの戦後史1 総論編』〈共編〉(吉川弘文館)、『沖縄県知事 島田叡と沖縄戦』(林博史との共著、沖縄タイムス社)などがある。


 林博史×川満彰
林博史×川満彰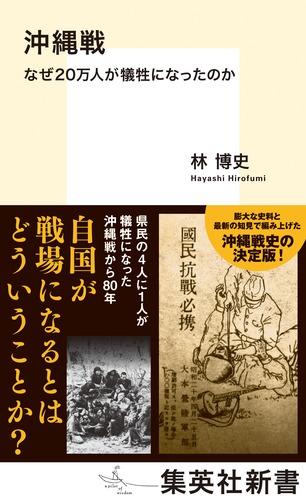
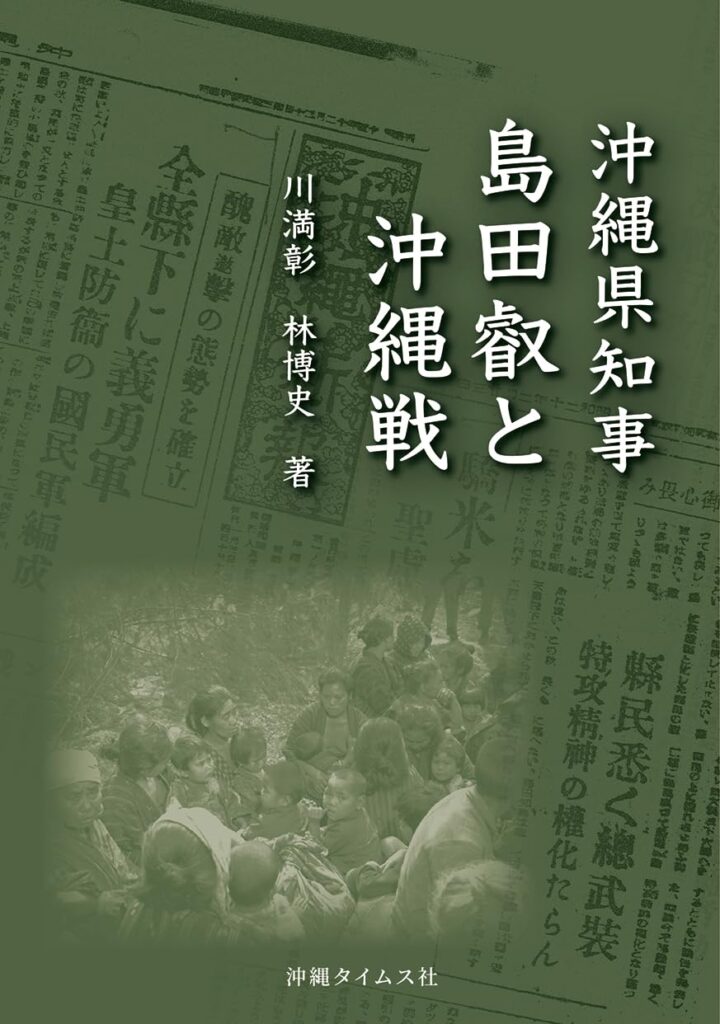










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり



