マーガレット・マレーの魔女カルト論
1921年にマーガレット・マレーは『西ヨーロッパの魔女カルト』を発表した。彼女はもともとエジプト学者だったが、1910年代から1920年代にかけて第一次世界大戦に発掘調査が困難になったことをきっかけとし、ヨーロッパの魔女裁判記録の研究に取り組みはじめた。
マレーの主張は学術界に大きな議論を巻き起こした。その理論によれば、魔女たちは13人一組の「カヴン」を形成し、角のある神や月の女神ディアナを崇拝していたという。これらの信仰が豊穣と深く関連し、季節の変わり目に祝祭を行っていたと主張したのである。彼女は魔女裁判で処刑された人々を、古代から続く組織的な異教信仰の密かな継承者だと主張した。
このマレーの「魔女カルト論」はロマンティックで一般的にも広まっており、大変根強い人気があるのだが、その後の研究により多くの批判を受け、現在では学術的に受け入れられていない。マレーの研究手法には多くの問題があった。第一に、拷問下で得られた供述を歴史的事実として無批判に採用した点である。魔女裁判の被告たちは肉体的苦痛から逃れるため、『魔女に与える鉄槌』などの悪魔学のマニュアルに沿って発言を歪められていたと考えられている。
第二に、時代も地域も異なる資料を恣意的に結びつけ、「ヨーロッパ全土に共通する古代から生き延びた魔女の宗教」という先入観に合わせて証拠を読み替えた。これも現代の歴史学では認められていない。マレーの理論は学術的な研究では完全に否定され、組織的な異教の宗教が密かに生き残って存在していた証拠は発見されず、実践は地域ごとの多様な民間信仰に基づいていたことが明らかになった。
しかし、このマレーの研究はジェームズ・フレイザーの『金枝篇』(1890年)における比較神話学的視点から霊感を得ていたと言われている。
フレイザーもまた、世界各地の神話や儀礼を比較しており、豊穣儀礼・死と再生・王殺しのモチーフを各地の祭儀に見いだし、多様な文化に共通して見られることを主張した。
ジェームズ・フレイザーの『金枝篇』
フレイザーの『金枝篇』は、1890年から1922年の間に同時代の芸術家や作家、詩人たちの想像力を強く刺激した。
フレイザーは同書で、人類の認識が呪術的思考から宗教的世界観を経て科学的合理主義へと発展すると、進化論に人間社会の発達段階を説明した。この理論は19世紀後半の社会進化論と西欧中心主義的価値観を理論的基盤としており、彼にとって「未開社会」の儀礼や信仰は文明が克服すべき過渡的段階であった。これは現在では世界中の多様な文化を単一的直線モデルに当てはめてるとして批判されているが、当時のイギリスをはじめとする知識人に典型的な考え方で、ダーウィン進化論や植民地主義と結びついた進歩史観に支えられていた。
しかし皮肉なことに、彼が体系的に収集・分析した膨大な神話や儀礼の記録は、T.S.エリオットをはじめとするモダニズム文学の作家たちに強い影響を与えた。彼らはフレイザーが「野蛮」として記述した要素の中に、むしろ近代文明が失った深い精神性を見出し、それは「失われたもの」を取り戻すための霊感の源となった。
結果的に『金枝篇』は、フレイザーの意図とは異なる形で20世紀文化に大きな影響を及ぼした。
この影響は、後の近代魔術復興運動に関わった人々にも及んだ。彼らはモダニスト作家たちと同様に、フレイザーが提示した要素の中に、近代性への対抗軸となりうる豊かな文化的資源を見出したのである。
考古学的発見と母権制社会
考古学分野でも新たな発見が相次いだ。アーサー・エヴァンスはクノッソス宮殿の発掘を指揮し、ミノア文明における女神崇拝の中心的位置を主張した(彼の発掘調査と解釈には多くの問題点が指摘されている)。また、チャタル・ヒュユクの発掘は1961年に始まり、1960年代に多くの母神像が発見された。これらは「母権制社会」の証拠として一部の研究者により解釈されたが、その後の批判的検討により、この解釈も現在では再考されている。
1929年、マレーはブリタニカ百科事典の「魔女術」項目を執筆した。証拠の恣意的選択や文脈の無視が指摘されているにもかかわらず、この権威ある媒体を通じて彼女の「魔女カルト論」は広く知られることになった。この項目は1960年代まで改訂されることなく掲載され続け、現在まで消し去ることのできない影響力を発揮している。
これらの学説には当時から批判も存在し、1970年代頃には現代魔女の実践者の一部もこれを把握した上で実践していたとまでいわれている。「魔女カルト論」の信憑性が危うくなると、マレーの説やガードナーの主張は歴史的事実というよりもウイッカの象徴的神話として考えられるようになった。現在では「魔女カルト論」をウイッカ起源神話として真に受けて実践している魔女はほとんどどいないのだが、重要なのは、こうした学術研究が失われた異教的伝統への関心を喚起し、その「再発見」あるいは「再創造」の理論的基盤を提供したことだった。
ガードナーとニューフォレスト・カヴンの接触
ジェラルド・ガードナーは、マレーの「魔女カルト論」に感化され、自らが魔女のカルトと接触したと名乗り出た。1939年、イギリス南部ニューフォレストで、ガードナーはクライストチャーチの劇場一座に参加していた。そこで「オールド・ドロシー」ことドロシー・クラッターバックと出会い、彼女を通じて古代の魔女の宗教を実践する魔女カヴン(ニューフォレスト・カヴン)を紹介されたという。これが一般的に知られているウイッカの起源神話、誕生秘話である。
後にドリーン・ヴァリアンテは「オールド・ドロシーを探して」という研究を行い、ジェラルド・ガードナーが語った「ニューフォレスト・カヴン」の中心人物とされるオールド・ドロシーの実在を検証した。ガードナーは学歴詐称問題などを起こしており、発言に信憑性がないため、ヴァリアンテ自身がウイッカの起源について調査を行ったのだ。
ヴァリアンテは公文書や戸籍記録を丹念に調査し、1880年生まれで1951年に没したドロシー・クラッターバックという女性の存在を確認することに成功し、この発見により、ガードナーの語りが完全な虚構ではない可能性が示された。しかし、この女性が実際に魔女であったか、あるいはガードナーの主張するようなカヴンの指導者であったかについては、依然として確証は得られていない。
近年、フィリップ・ヘセルトンによる研究により、ジェラルド・ガードナーやドリーン・ヴァリアンテの伝記執筆、ニューフォレスト・カヴンについての調査が進められた。ドロシー・クラッターバックは確かに実在の人物だったが、地域の保守的な政党支持者でアングリカン教会の熱心な信者だった。彼女が異教的な魔女集団を主宰していた証拠は見つかっていない。ニューフォレスト・カヴンの存在自体が現在も歴史的な議論の対象である。
ガードナーが入団した劇団は、単なる演劇集団ではなく神秘主義思想を探求するグループでもあった。この薔薇十字団劇場は、神智学者アニー・ベサントの娘メイベル・ベサント=スコットと俳優ジョージ・アレクサンダー・サリヴァンによって設立された「クロトナ・フェローシップ」が運営していた。クロトナ・フェローシップは、女性を受け入れるフリーメイソンリー「コ・メイソンリー」の流れを汲んだ神秘主義結社だった。ここにフリーメイソンや神智学とウイッカの意外な繋がりが浮かび上がる。
イーディス・ウッドフォード=グライムズ(ダフォ)の存在
最も興味深いのは、ガードナーとイーディス・ウッドフォード=グライムズとの関係である。ウッドフォード=グライムズは魔女名ダフォとして知られ、初期のガードナーの魔術実践における重要なパートナーだった。1947年、ガードナーはダフォと共に「エンシェント・クラフツ社」を設立し、セント・オールバンズ近郊のファイブ・エーカーズという自然主義者クラブに隣接する土地を購入。そこに16世紀の魔女のコテージを再現した建物を建設し、実践の場とした。
ファイブ・エーカーズはヌーディストクラブで、ガードナー自身も入会していた。初期にガードナーと実践した人々の多くがヌーディストであったことは、ウイッカの実践がスカイクラッドと呼ばれるヌードで行われることと無関係ではない。
ダフォは「ニューフォレスト・カヴン」時代からガードナーと共に実践していた唯一の人物であり、ウイッカ誕生の秘密を握っていた人物と考えられている。1952年後半、彼女はガードナーが魔女信仰の存在を公にしようとしていたことへの懸念から、カヴンから退いた。しかし、その後もダフォとガードナーは友情関係を持ち続けたと言われている。謎の多い人物だが、ドリーン・ヴァリアンテがイニシエートした時にはダフォが立ち会ったと証言されている。現在では、この女性もウイッカの設立に重要な役割を果たした人物として考えられている。
現在知られているウイッカの大部分は、1940年代後半からガードナーたちが実践を通して有機的に形成してきたものと考えられている。それは完全な創作やでっちあげではなく、当時の学術研究、フリーメイソン、神智学、民間伝承、西洋儀式魔術、ロマン主義など様々な要素が接ぎ木され、マレーの説に確信を得た彼が現代に蘇らせようとしたものだった。
19世紀の霊的探求
私が本書で紹介している現代魔女文化や現代魔女運動と呼ばれるこの運動は、19世紀から20世紀に広がった近代魔術復興運動や復興異教主義運動の影響を受けつつ、20世紀半ば以降に独自の新宗教運動・霊性運動として成立したものだと考えられている。
そもそも、近代魔術復興運動はいつはじまったのだろうか?
19世紀、産業革命の煙が空を覆い、科学の進歩が世界の神秘を次々と解き明かしていった。多くの労働者たちが都市部に移動し、時代の大きな転換点の中で、人々は新たな霊性への渇望を感じ始めていた。この時代に起こった霊的探求の諸潮流は、やがて近代魔術復興運動と呼ばれることになる。
心霊主義の興隆
心霊主義は1848年のアメリカでのフォックス姉妹によるハイズヴィル事件を契機に広まり、19世紀後半まで盛り上がった。この運動は芸術、文学、哲学といった幅広い分野に大きな影響を与え、当時のサロン文化とも深く結びついた。
19世紀ヨーロッパのサロンはエリート知識人や芸術家の交流の場として重要な役割を果たし、心霊現象の実験や降霊会が行われた。ヴィクトル・ユゴー、コナン・ドイル、アルフレッド・テニスン、美術評論家ジョン・ラスキン、世界で最初に抽象画を描いた女性として近年注目を浴びるようになったヒルマ・アフ・クリントなど、多くの知識人や芸術家が心霊主義と何らかの繋がりを持った。
心霊主義運動には女性が積極的に参加し、人前で話す機会を得たため、後に女性の社会進出を幇助したともいわれている。この運動は死者との交信や霊的現象への関心を高め、後の魔術復興運動における霊的探求の土壌を耕した。
神智学の登場と影響
1875年にニューヨークで設立された神智学は、ヘレナ・P・ブラヴァツキーによって創始され、西洋と東洋の智の融合を目指した。神智学は宇宙の霊的進化や人類の精神的成長を強調し、科学と宗教の調和を図る試みとして、当時の多くの知識人や芸術家に影響を与えた。
特に重要なのは、東洋の輪廻転生やカルマの概念、チャクラなどの知識を西洋に紹介し、西洋の秘教思想に新たな視点と概念をもたらしたことである。神智学はインドの独立運動などの社会改革運動とも結びつき、アニー・ベサントなどの女権運動家が所属していたことでも知られる。
ブラヴァツキーは数々の疑惑や批判に晒されつつも、時代を超えて大きな影響力を持った。彼女が提唱した神智学の進化論的教義は、後に極端な人種主義思想へと転用されることもあったが、一方で女性参政権運動やインドの独立運動にも影響を与えるなど、その影響力は広範であった。神智学は近代オカルティズムやニューエイジ運動、その後の多くの新興宗教の走りともなった。
エリファス・レヴィと高等魔術
1850年代のフランスで、カトリックの神学生から転じたエリファス・レヴィが魔術復興運動の中心的存在となった。1854年、レヴィは『高等魔術の教理と祭儀』を出版し、「高等魔術」という概念を確立した。
レヴィは実利的な魔術観を超えて、宇宙の真理と自己認識を探求する哲学的実践として魔術を再定義し、隠された叡智を探求する哲学的・霊的体系という意味での「オカルティズム」を思想的運動として打ち立てた先駆者である。彼は古代の魔術書や錬金術文献を読み解きつつ、近代科学や合理的枠組みによってそれらを解釈し、魔術を人間の潜在能力を開発するための体系的手法として再構築することを試みた。
黄金の夜明け団の成立と影響
1888年、ウィリアム・ウィン・ウエストコットが「暗号文書」と呼ばれる一連の文書を発見したことから「黄金の夜明け団」が設立された。ロンドンの知的サロンと古代の神秘主義が出会うこの場所で、近代オカルティズムは最も洗練された形式を獲得した。
創設者のウエストコット、マクレガー・マザーズ、ウィリアム・ロバート・ウッドマンは、いずれもフリーメイソンの上級会員であり、フリーメイソンの伝統を継承しながら、エリファス・レヴィの理論、カバラの体系、エジプトの神秘思想を統合した。
この団体には、詩人W・B・イェイツ、タロット研究家A・E・ウェイト、女優フローレンス・ファー、アイルランドの女性革命家モード・ゴン、哲学者アンリ・ベルクソンの妹でマザーズの妻モイナ・ベルクソン、アラン・ベネット、アレイスター・クロウリーなど、当時の知的エリートや文学者、芸術家たちが集い、知的サロン文化を形成していた。
黄金の夜明け団は、当時の秘密結社としては革新的で、創設当初から女性を男性と対等に受け入れていた。これはフローレンス・ファーやモイナ・マクレガー・マザーズといった女性が重要な役割を担ったことにも表れている。
同時期にフランスで始まったアニー・ベサントらによる「コ・メイソンリー (女性を受け入れるフリーメイソン)」の運動とも時代的に並行しており、西洋秘教運動全体における女性参加の潮流と見ることができる。
団の大きな遺産は、体系的な魔術訓練システムの確立である。断片的に伝えられてきた西洋魔術の伝統を実践可能な形で整理・体系化し、古代エジプトの神々の呼び出しから四大元素の精霊との交信、瞑想や儀式による自己の霊的進化まで、段階的な訓練プログラムが確立された。フリーメイソン流の儀式的要素、入門式の形式、道具の使用法、四方位の重視などは、後の魔術的実践の基礎となり、段階的な訓練システムは後のウイッカの三つの位階制度や儀式の枠組みにも影響を与えている。
発見と創造の狭間で
西洋列強による植民地支配が進展する中、これまで自文化の中で「異教」として排斥されてきた異文化の儀式や宗教が、探検や学術研究を通じて人々の目に触れるようになった。
ジェームズ・フレイザーの『金枝篇』に代表される比較宗教学の隆盛は、世界各地の神話や儀式を紹介し、西洋中心的な視点からの異文化理解を問い直す契機となった。
ウイッカを創始したガードナー自身も北ボルネオやマレーでプランテーションを営みながら、その土地の先住民から多くを吸収していたことも彼の考え方に影響を与えた。彼もまた東洋の呪術に接触し、現地の人々との交流から多くを吸収した人物だった。
神智学協会が東洋の神秘主義や古代の叡智を西洋に紹介したことも、西洋と東洋の霊的実践の融合の一つだった。異文化への関心の高まりの一方で、ダイアン・フォーチュンのようにイギリス土着の異教に深く関心を寄せる人物や、ドルイド教団といった独自の伝統を再興しようとする動きも生まれた。ウイッカもこの異教の実践の復興を志向した運動である。
近代魔術復興運動は、植民地支配という歴史的背景のもと、異文化との接触を通じて新たな視点を得る中で生まれた。それは単に異国の神秘を取り入れるだけでなく、西洋社会自身の精神的なルーツを再発見し、新たな価値観を創造しようとする複雑な運動だった。
ガードナーにおける「魔術」
ガードナーは魔術を、神々の力を借り、儀式を通じて自分自身の内なる力を引き出し、意図的な結果を得るための術だと考えていた。
ガードナーによれば、魔術における神々と人間の関係は、人間が儀式を通じて神々に力を与えるという相互的な側面を含んでおり、一方的に力を借りるという関係ではない。そして、魔女たちの儀式は儀式魔術のように、精霊や悪魔を呼び出して強制的に出来事を起こさせるような方法とは異なると考えていた。
魔女術における魔術は、『結果を得るための術』である
(ジェラルド・ガードナー『今日のウィッチクラフト』1954
Gerald B. Gardner. Witchcraft Today. Rider and Company, 1954.)
後にウイッカと呼ばれる実践のスタイルを確立することになる彼は、フリーメイソンや儀式魔術の遺産の一部を継承しながらも、より土着的な民間の魔術に関心を持ち、マーガレット・マレーの語るような古代の異教の宗教が(彼の言葉を借りると)途絶えないように明かりを灯し続けることに晩年の全精力を注いだ。
ガードナーの『影の書』にクロウリーの詩句やリーランドの『アラディア』、『ソロモンの鍵』、フリーメイソンの儀礼文言などからの引用が散見される。これについてガードナーは、1939年に参入したニューフォレスト・カヴンから受け継いだ写本が断片的なものであったため、不足部分を補完するため様々な出典から寄せ集めたとヴァリアンテに釈明している。
ガードナーにとってのウイッカは復興であったが、その手法は過去の単なる復興というよりも再解釈と再構成であり、非常に創造的だった。彼はイギリスの民間信仰や土着的な妖精信仰、所謂低級魔術にスポットを当て、異教の信仰を呼び出そうと試み、生涯吸収してきたあらゆる魔術や民俗学の知識を総動員した。
クロウリーと現代魔女術の関係
1947年、ガードナーはアレイスター・クロウリーと面会を果たし、東方聖堂騎士団へ入門している。その後、ガードナーは少なくとも四度クロウリーを訪問したが、この時期のクロウリーは既に病床にあってすでに健康が衰えており、その年の12月1日に死去した。
ガードナーが自身の実践を公に語り始めたのは、1951年のアンチ魔女術法の廃止以降である。それまでは「誰かが魔術をしている」と話すことは法律で違法だったからだ。1954年の『今日のウィッチクラフト』出版で彼は公に魔女の話を発表し、その後ウイッカの普及に専念し、東方聖堂騎士団への興味を失っていった。
ガードナーとクロウリーの関係については、長年様々な噂が流布されてきた。フランシス・キングによる、ガードナーがクロウリーに金を払って儀式文を書かせたという説は、証拠がなく完全に否定されている。クロウリー自身の日記や手紙にもガードナーのために儀式文を書いたという記録は存在しない。
ガードナーは確かにクロウリーの著作を所有しており、特に『春秋分点』の複数の写しを所有していたことが記録に残っている。しかし、ウイッカの儀式文におけるクロウリーからの引用は、公刊された著作からのものがほとんどであると現在では考えられている。
『女神のチャージ』の成立
前述したように、『女神のチャージ』はウィッカの最重要の典礼であり最も知られているのがヴァリアンテ版とスターホーク版である。この典礼の執筆にはクロウリーからの影響があるといわれている。
1953年、ドリーン・ヴァリアンテがガードナーの伝統に入門した。後に「ウイッカの母」と呼ばれる彼女の参加は、ウイッカの発展において決定的な意味を持っていた。タイプライターを使え、詩人としての才能を持つヴァリアンテは、「女神のチャージ」を改訂し、後にウイッカの個性を形作る詩的で力強いものに作り変えていった。
元々、ガードナーの『影の書』には彼のバージョンの女神のチャージの初期版『ヴェールを上げよ』が書かれていたが、そこにはアレイスター・クロウリーの影響が明確にあった。ヴァリアンテ版の女神のチャージは1957年頃に書かれたもので、この改訂の過程にはクロウリーの影響を意図的に消す目的があったのだ。
ヴァリアンテによれば、ガードナーの著書『今日のウィッチクラフト』の出版や彼の講演、テレビ出演により、多くの人々がウイッカへ興味を持つようになった。しかし、「黒魔術師」「悪魔崇拝」として悪名高いアレイスター・クロウリーの影響がウイッカにあると知れれば、ウイッカは絶対に大衆には受け入れられないとヴァリアンテはガードナーに提言した。
当時、ジョン・シモンズの評伝によってクロウリーの評判は悪名高いものとなっており、ウイッカがクロウリーと関連付けられることは、新しい宗教運動にとって不利益をもたらす恐れがあった。
ヴァリアンテはクロウリーを素晴らしい詩人であると評価する一方で、人としては「単に嫌な奴」であると評しており、複雑な感情を抱いているようだ。クロウリー自身が女性から命令されたくなかったため魔女の世界には深く関わらなかったという逸話もある。
元々『ヴェールを上げよ』として知られる女神の語りの部分には、クロウリーの影響が色濃く反映されていた。
実際、この文書にはクロウリーの『法の書』におけるヌイトの言葉や、彼の詩からの引用が含まれており、さらにはグノーシスのミサへの言及も見られた。「グノーシスのミサ」は、アレイスター・クロウリーが1913年に作成した儀式文書で、東方聖堂騎士団の公式典礼として位置づけられたものである。
ガードナーはヴァリアンテにテキストの書き直しを依頼し、ヴァリアンテは当時の世間体を考慮して『影の書』を書き直すことに着手することとなった。彼女は1899年のチャールズ・ゴッドフリー・リーランドの『アラディア、あるいは魔女の福音』からの要素を「より伝統的」なものとして残しつつ、クロウリー的な要素の大部分を自身の言葉で置き換えた。最初は詩の形式で、その後カヴンのメンバーの希望により散文形式で書き直された。こうして生まれた『女神のチャージ』が、今日に至るまで、ウイッカの精神性を最も崇高に表現したテキストとして受け継がれている。
クロウリーの影響はウイッカの典礼の中に確かに存在するが、それは黎明期にウイッカが今後多くの人に受け入れられていくために、相応しくないものとして意図的に削られた複雑な経緯があった。ウイッカの魔女たちは自分たちの実践をクロウリーの魔術の延長とはみなされたくなかったのである。
現代の魔女たちのアレイスター・クロウリーに対する関心は人によって大きく異なるが、それぞれの魔女がクロウリーと自分の実践をどの程度結び付けて考えているかは、彼らの「魔術」の綴りを見ればわかるだろう。
現代ペイガン・魔女の学術的研究
カナダの歴史家エリオット・ローズは、1962年の著作『山羊のための剃刀:魔女術と悪魔崇拝史の諸問題』において、ウイッカ研究に批判的な視座を提供した。彼はマーガレット・マレーの魔女カルト論に批判的で、ジェラルド・ガードナーが古代から続くカヴンを発見したという主張を検証した。ローズはウイッカを明らかに最近の文学的創作であると結論づけた。この研究が、初期のウイッカの歴史的主張に対する学術的懐疑主義の端緒となり、60年代から徐々にマレーやガードナーの主張は信頼性を失っていく。これがウイッカの実践者たちの起源神話の捉え方に影響を与えていくこととなった。
アメリカの魔女でありジャーナリストのマーゴット・アドラーが1979年に『月神降臨』を出版した。マーゴット・アドラーは「アドラーの心理学」で知られるオーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーの孫である。この著書は学術書ではないが、米国の現代ペイガン運動に関する広範な調査に基づき、彼女自身が実践者の立場から100人以上の実践者へのインタビューを行い、コミュニティの内部から執筆された。この本が東海岸で出版されたソーウィンの日、西海岸ではスターホークの『スパイラルダンス』が出版されたという面白い逸話が存在する。この本は現在でも実践者に広く読まれている。学術的な研究がウイッカや現代ペイガンを対象とするのは、ここから10年も後のことである。
アメリカの人類学者ターニャ・ラーマンは、1989年に『魔女術の説得力』という画期的でありながら議論を呼ぶ研究を発表した。この研究はロンドンの儀式魔術団体とウイッカンのカヴンの両方で行った博士課程の研究に基づいていた。ラーマンは「なぜ教育を受けた中流階級の人々が、一見『奇妙な』魔術や魔女術の慣行に惹かれ、コミットするようになるのか」を理解しようと試み、ロンドンの様々なカヴンや魔術グループに潜入調査を行った。これは学術的には初の試みであり、ラーマンは複数の魔術グループのイニシエーションまで受けていた。
しかし、彼女は出版した著作の中で「入会儀礼を受けたが、私は魔女でも魔術師でもない」と断言し、「魔術を信じてはいない」と明確に述べた。この研究の発表後、協力した実践者たちの多くが「裏切られた」と感じることとなった。特に、儀式が物質世界に影響を与えないという彼女の主張は、実践者たちの生きた経験を還元主義的に否定するものとして受け止められ、インフォーマントたちの感情を大きく逆撫ですることなった。
彼らは、ラーマンが信頼を得るために彼らのコミュニティに入り込みながら、最終的に彼らの信念を否定し、秘密を漏洩し、裏切られたと感じたのだ。彼らにとって神聖な体験や秘儀的知識が、「自己説得」「心理的効果」といった学術用語で分析され、単なる心理現象に還元されたことへの失望と怒りは大きく、このスキャンダルは魔術の実践者たちが研究者に対する警戒心を強める結果となった。
また、彼女の研究の批判者たちは、ラーマンが魔術実践の「なぜ」を説明していないと指摘した。彼女の理論は個人が新しい信念を採用する心理的プロセスに焦点を当てたが、人々が魔術を実践する深い動機や、それが彼らの人生にもたらす意味については十分に探求していなかった。
この研究は魔術の世界に激しい論争を引き起こしたが、現代の魔術実践やペイガン研究という学術分野の重要な先駆けとなった。この「ラーマン事件」は、学術界では一定の評価を得たものの、重要な教訓をもたらした。研究者が対象コミュニティにどの様に関わり、彼らの信念体系をどのように解釈し、表現すべきかという根本的な問いを提起することとなった。
ラーマンの研究への反発は、その後の研究者たちに大きな影響を与えた。その後の研究者たちは、より内省的で参加型のアプローチを採用するようになる。彼らは自身の個人的経験や感情を考慮に入れ、実践者の見解を真剣に受け入れようとした。
1991年には、NROOGD共同創設者エイダン・A・ケリーが『魔術の技を創り出す』において、ガードナーの『影の書』の初期バージョンを分析し、年代順に整理した。ケリーの研究の結果、『影の書』は1945年頃から1964年の間に構成されたものであり、ガードナーが主張したニューフォレスト・カヴンから受け継がれたものではないと発表した。多くの実践者はこれに反発しており、特に「ガードナーが鞭打ちによって性的に興奮していた」という根拠のない言説はこの本から広まったとされている。しかし、この研究は、ウイッカの起源神話をペイガンの実践者自らが揺さぶる重要な契機となった。
1999年、歴史家ロナルド・ハットンは『月の勝利:現代ペイガン・ウィッチクラフトの歴史』を出版し、ウイッカの歴史研究に新たな地平を開いた。ハットン自身もペイガンの母親に育てられた人物である。90年代前半、ハットンは英国伝統派ウイッカの魔女たちがウイッカの起源に関する伝統的な魔女カルトの物語を、文字通りの歴史ではなく神話や比喩として説明していたことに気付いた。明らかに、ウイッカン・コミュニティ内には、マレーの研究が信用を失い、自分たちの宗教の歴史はガードナーが提示したものとは違うと気づいているウイッカンたちがいたのだ。そのことに気が付いたハットンは、ウイッカの歴史を厳密に検証し、現代ペイガン・ウィッチクラフト研究を切り開くことになる。
ハットンは、現代ペイガニズムとウイッカの成立を詳細に分析し、それが20世紀に新たに作られた新しい宗教運動であることを明確に示した。しかし同時に、ウイッカを単なる20世紀の「でっちあげ」として切り捨てるのではなく、実践者たちにとっての宗教的意味と精神的価値を高く評価し、現代社会において意義あるものとして認めた。この学術的誠実さと敬意ある姿勢ゆえに、ハットンの研究は多くのペイガン、ウイッカ実践者からも受け入れられている。
生きた実践としての現代魔女文化
ここまで、ウイッカという宗教が成立した背景や最新の学術的な研究を紹介したことで、神秘性が失われたように思う人がいるかもしれない。しかし、ここに書いた多くのことは既に数十年前に出版されている内容で「魔女カルト理論」が学術的に否定されていることなどは、現代魔女文化に関わる人にとって自明のことである。
私はウイッカが生まれたこのロマンと人間臭い創造のプロセスそのものが、現代魔女文化の魅力であると思っている。
それに、もしあなたが霊的な実践や魔術と付き合っていくなら自分のしている実践やその歴史に対しシニカルな疑り深さが必要だろう。それでもなお色褪せることのない儀式の体験、言葉にはできない恍惚や悦び、驚き、出会いが魔法なのかもしれない。
私は現代魔女たちが自分たちの実践に対して常に非常に自己批判的で、歴史に対して情熱的に、懐疑的に研究し、民俗学を愛し、そして何よりクリエイティブに献身するところが好きだ。
それは文化人類学者や歴史家が外部からこの文化を研究対象とする以前から、ファーラー夫妻やエイダン・ケリーやマーゴット・アドラーといった実践者によって詳細な研究が進められてきた。
現代魔女とは本質的に吟遊詩人的な実践である。詩と踊りを介して彼らの物語は有機的に語られる。
現代魔女文化に参入するということは、人々が語ってきた神々や妖精の物語や民間伝承の謎に想いを馳せ、より心動かされる面白いものを見つけ、自分の人生を重ね合わせ、時には学術的研究までも飲み込みながら、古いものを時代にあった新しいものに編みなおしていく実践である。現代の魔術の実践者たちは単に盲目的に何かを信じている人々なのではなく、学術的な研究などからも影響を受けながら70年以上続き、この文化が様々な形の楽しまれ方をしていることを知っていただけたら嬉しい。
ウイッカの形成は「復興の意図」と「再創造」が複雑に絡み合う過程だった。ガードナーは確かに既存の様々な伝統から多くを借用したが、それらを独創的に再構成し、それが後にヴァリアンテやファラー夫妻、スターホーク、ヴィヴィアン・クロウリーといった詩的才能のある司祭たちに手渡され、20世紀の人々の知的好奇心や欲求に応える新しい「生きた」実践として生まれ変わっていくのである。
(次回へつづく)
参考文献
スターホーク『聖魔女術 スパイラル・ダンス』(鏡リュウジ+北川達夫訳、秋端 勉 監修、国書刊行会、1994年)
マリアン・グリーン『やさしい魔女 宝瓶宮時代の魔法修業』(ヘイズ中村訳、秋端 勉 監修、国書刊行会、1994年)
マーガレット・マレー『魔女の神』(西村稔訳、人文書院、1995年)
ドリーン・ヴァリアンテ『魔女の聖典』(秋端 勉 訳、国書刊行会、1995年)
レイモンド・バックランド『サクソンの魔女』(楠瀬啓訳、秋端 勉 監修、国書刊行会、1995年)
ジャネット・ファーラー+スチュワート・ファーラー『サバトの秘儀』(ヘイズ中村訳、秋端 勉 監修、国書刊行会、1997年)
マーゴット・アドラー『月神降臨』(江口之隆訳、秋端 勉 監修、国書刊行会、2003年)
イーサン・ドイル・ホワイト『Pagans 多神教表象大全』(河西瑛里子日本語版監修・訳、定木大介訳、東京書籍、2024年)
Gerald B. Gardner. Witchcraft Today. Rider and Company, 1954.
Doreen Valiente. An ABC of Witchcraft Past and Present. Robert Hale, 1973.
Doreen Valiente. The Rebirth of Witchcraft. Robert Hale, 1989.
Vivianne Crowley. Wicca: The Old Religion in the New Age. Element Books, 1989.
Ronald Hutton. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. Oxford University Press, 1999.
Aidan A. Kelly. Inventing Witchcraft: A Case Study in the Creation of a New Religion. Thoth Publications, 2008..
Ethan Doyle White. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Sussex Academic Press, 2015.
Ronald Hutton. The Witch: A History of Fear, from Ancient Times to the Present. Yale University Press, 2017.
Philip Heselton. In Search of the New Forest Coven. Fenix Flames Publishing Ltd, 2020.

フィクションの世界のなかや、古い歴史のなかにしか存在しないと思われている「魔女」。しかしその実践や精神は現代でも継承されており、私たちの生活や社会、世界の見え方を変えうる力を持っている。本連載ではアメリカ西海岸で「現代魔女術(げんだいまじょじゅつ)」を実践しはじめ、現代魔女文化を研究し、魔術の実践や儀式、執筆活動をおこなっている円香氏が、その歴史や文脈を解説する。
プロフィール

まどか
現代魔女。アーティスト。留学先のLAでスターホークの共同設立したリクレイミングの魔女達に出会い、クラフトを本格的に学びはじめる。現在はモダンウィッチクラフトの歴史や文化を日本に紹介している。未来魔女会議主宰。『文藝』『エトセトラ』『ムー』『Vogue』『WIRED』などに現代魔女に関するインタビューや記事を掲載。2023年から逆卷しとねとキメラ化し、まどかしとね名義でZINE『サイボーグ魔女宣言』を発売。笠間書院にて『Hello Witches! ! ~21世紀の魔女たちと~』を連載中。


 円香
円香




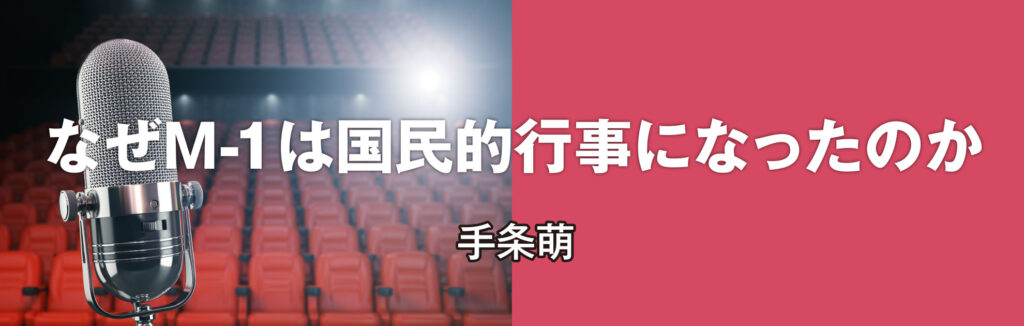




 菱田昌平×塚原龍雲
菱田昌平×塚原龍雲


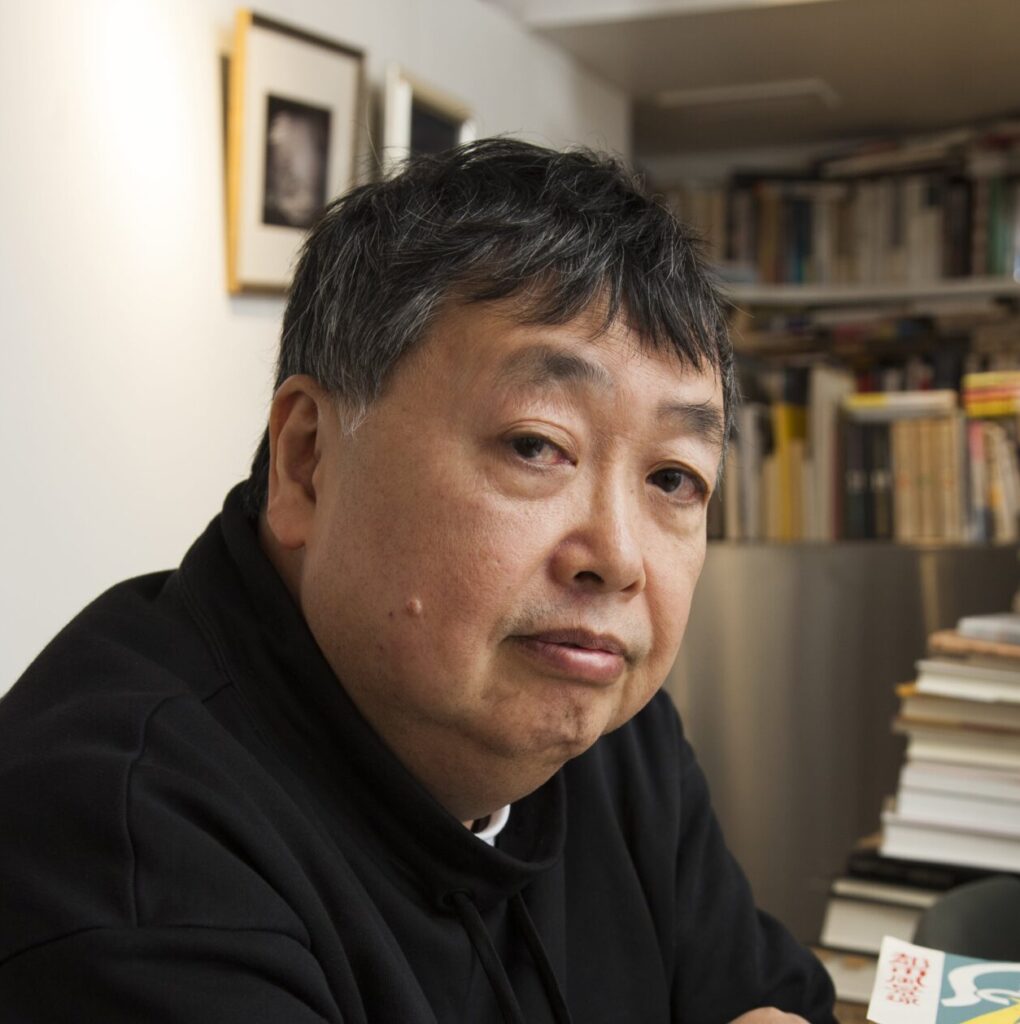
 大塚英志
大塚英志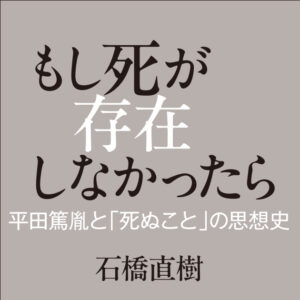
 石橋直樹
石橋直樹