1.なぜ働いていると病院が遠くなるのか
なぜ夫は病院に行かないのか!?
という話題でしばしば盛り上がる。主に女友達の飲み会において。夫が病院に行かない。筋トレやサウナ通いは熱心にしてるのに、健康への意識はなぜか低い。整体や風邪薬にはやたら詳しいのに、風邪ひいて病院へ行く選択肢がすっぽり抜け落ちている。まずは風邪をひいたら風邪ひいた気がする、という予感をもって対策しているところを見たことがない。
ーー辛辣な意見も冗談のようなものも含め、さまざまな見解や持論が飛び交う。そのどれもが、言われてみればわかる気がする。もちろん主語が大きいのは百も承知だが、病院へ行かない夫の健康をケアするのはたいがい妻の役割である。パートナーにはできるだけ健康でいてほしいし、自分の体の不調には自分がまず一番敏感であってほしい。その切実な願いが「なぜ夫は病院に行かないのか」という言葉に集約されているのである。聞いてますか全国の夫の皆様。
……と、書いたところで、白状したい。
私も正直、病院って面倒だ、と思っている。
いや、思っていた。とくに会社で働いていた時。病院が本当に遠かった。
―会社にいると、病院へ行く、という行動がやたら億劫になった。
病院は24時間空いているわけではない。ジムに行くのは深夜でも可能だが、病院へ行くのは日中しか無理である。風邪薬を売るドラッグストアよりも、病院のスケジュールは、会社員に合わせてくれない。
コロナの検査をすることになって、人生ではじめて、病院へ行くためだけに会社の午前休をとった。会社で働いていた頃、そう語っていた先輩がいた。たしかに、そういう意味ではコロナは革命だった。コロナ禍を経て、体調不良で会社を休みやすくなった。体調不良で会社に来るということがむしろ悪いことになった。
それにしても、むしろコロナ禍くらいの社会的衝撃がなければ。「会社にいると病院が遠くなる」という事態は変わらなかったのだ。
なぜ働いていると病院が遠くなるのか。
メンテナンスも働く人にとっては大切なはずなのに。
2.怪我してコートに立つ桜木花道は、かっこいい
考えてみれば、会社にとっても、体調不良の従業員は病院に行ってくれたほうがいいはずだ。本当に利益を出したいなら、熱を出した状態で働くよりは、普通に熱を治してから働いたほうが生産性が上がるのではないか。……とマジレスしてみたものの、それがなかなか難しいことはよくわかっている。
自分の担当している仕事があるとそのスケジュールが後ろにずれ込むのは嫌だ。休むことで他人に迷惑をかけたくない。休むといろんな判断が後回しになってしまう。体調不良によって仕事の流れを止めたくない。そう考えると、病院に行かないほうが楽だと思ってしまう。
他人とやっている仕事の流れを、体調不良によって、自分のところで止める。そのような状況はなにより面倒だし、できれば避けたい。
ーこの、他人、というものが厄介だなあと感じる瞬間がある。
当たり前だが仕事とは他人と協働するものだ。他人との関係のなかに仕事はある。すると、他人は平常運転で働いているのに、自分だけ病院へ行っている、ということがなんだかとても誰かの足を引っ張っている気がするというか、ぶっちゃけ避けたい状況になってしまうのだ。
自分のところで仕事の流れを止めないためには、病院になんか行ってられない。
こういうことをぼんやり考えていると、ふと思い出す台詞がある。
「オヤジの栄光時代はいつだよ…
全日本のときか?
オレは今なんだよ!!」
(井上雄彦『SLAM DUNK』31巻、集英社)
1990年〜1996年に『週刊少年ジャンプ』で連載されていた、バスケットボールに青春を打ち込む高校生たちを描く漫画『SLAM DUNK』の台詞である。
スラムダンクの主人公・桜木花道は不良少年。もともとバスケットボールなんて経験したことがなかった。ひょんなことから彼はバスケ部に入部し、目覚ましい活躍を遂げていく。そして流川楓ら仲間と共に、夏のインターハイ制覇を目指すことになる。
桜木は、作中で描かれる、とても大切な試合において大きな怪我をしてしまう。背中に負傷を抱え、少し動くだけで猛烈な痛みを感じるようになってしまったのだ。だが、彼は痛みを我慢して、試合出場を続けようとする。
もちろんコーチをはじめ皆、彼を止める。怪我は怖い。バスケットボール選手人生を左右するような負傷かもしれない。これ以上試合出場を続けないほうが君の未来のためなのだ。皆そう説得する。だが、彼は言うのだ。
「オレは今なんだよ」と。
つまり今この瞬間のために、怪我をしてでも、未来がどうなっても、それでも、試合に出たい。今は今しかない。この試合に出られなかったら、一生後悔するのだ、と。彼はそう語る。
ー正直、こう述べる桜木は、かっこいいのである。
傷を負ってでも試合に出ようとする桜木花道はかっこいい。どう考えてもスラムダンクにおける名シーンだ。今この戦いから逃げたら後悔する。……ここで桜木花道が自分の怪我を治すために病院に行ったら興醒めである。そう感じる読者は多いだろう。
怪我を我慢し、無理をするから、桜木花道はかっこいい。
不思議だ。なぜ怪我を我慢して試合に出る桜木花道はかっこいいのだろう?
3.なぜ表現より競争を優先させてしまうのか
痛みを麻痺させ、試合から逃げずに、動き続ける桜木花道はかっこいい。彼の姿に、私はどうしても心を動かされてしまう。
彼の姿は、こう言い換えることもできる。試合のトーナメント戦、という競争の場において。自分の痛みよりも仲間との競争を選択する桜木花道はかっこいい。
『SLAM DUNK』の魅力のひとつは、二度と同じメンバーでは試合に出られない仲間たちが、一瞬に賭けて無理をしてでも仲間との試合を選択する姿である。
ここでいうトーナメント戦という名の競争に参加する意味は、決して自分のためだけではない。桜木花道は自分だけが勝ちたいから試合に出ているわけではない。それは仲間のためでもある。といっても単純な利他精神ではない。仲間に負けたくない、というライバル心も存在している。仲間との友情とライバルとしての葛藤の双方を抱え、仲間と共に桜木花道がコートに上がるからこそ、感動的なのだ。
仲間と共に、競争の場に居続けること。自分の感情よりも、仲間や勝利を選択し続けること。その姿自体が人々の胸を掴む。『SLAM DUNK』は世界中で売れており、現在の部数は一億部を超えている。
自分の痛みよりも、仲間との競争を選ぶ。
桜木花道のこの選択自体が何か私たちにとって大切なものを表現しているのではないだろうか? 私にはそう思えてならない。
桜木の姿は、病院よりも会社の仕事を優先させる人々の姿と、どこか重なるものがある。
痛みや病気とは、自分自身だけのものだ。仲間をはじめ、他人と共有することはできない。他人を介在させない、自分だけの最も原始的な感情かもしれない。
しかし、仕事や試合は、他人と協働するものである。だから会社を休めないし、怪我の痛みを麻痺させてしまう。
つまりここにある問題は、以下のように言い換えられる。ーなぜ私たちは、自分の感情表現よりも、仲間との競争参加を優先するのだろう?
というか、このように問うてもいいかもしれない。なぜ、自分の感情よりも仲間との競争を優先させる姿が、私たちにとって「かっこよく見える」のだろう?
本連載では、このような問いを考えてみたい。競争を優先する姿にはどこか中毒性のような、適正以上の摂取量を求めてしまう何かがあるのではないかと私は思えてしまう。つまり競争とは、本来の必要以上に、怪我を我慢したり痛みを麻痺させたりしてしまうほどに競争を「やりすぎる」特性があるのではないかと感じてしまうのだ。
この連載では、表現と競争の関係について、日本の近現代の会社史と漫画史を追いながら考えてみたい。
(なぜまた歴史を追うのか? それは次回に説明しよう)
私はただ、スラムダンクのかっこよさって何なのだろう、ということを考えたいだけなのだ。
なぜ私たちは、スラムダンクの桜木花道に感動してしまうのだろう。ーそれはきっと、近現代以降の私たちの生きる姿におけるなにか大切なものを、表現しているからではないだろうか。
(次回へ続く)

体調が悪くても会社に行ってしまう。休んで自分のところで仕事を止めることに罪悪感がある。サウナや筋トレは好きなのに、体調のケアは億劫になる……このような悩みを抱えている働く人は少なくないのではないか。なぜ我々は、組織や集団にいると、休むことが難しくなるのか。文芸評論家の三宅香帆が、働く人たちを熱狂させてきた作品や国民的な少年漫画を歴史からひもとくことで、その源流を探る。
プロフィール

みやけ かほ 文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』、『娘が母を殺すには?』、『30日 de 源氏物語』、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』、『人生を狂わす名著50』など多数。


 三宅香帆
三宅香帆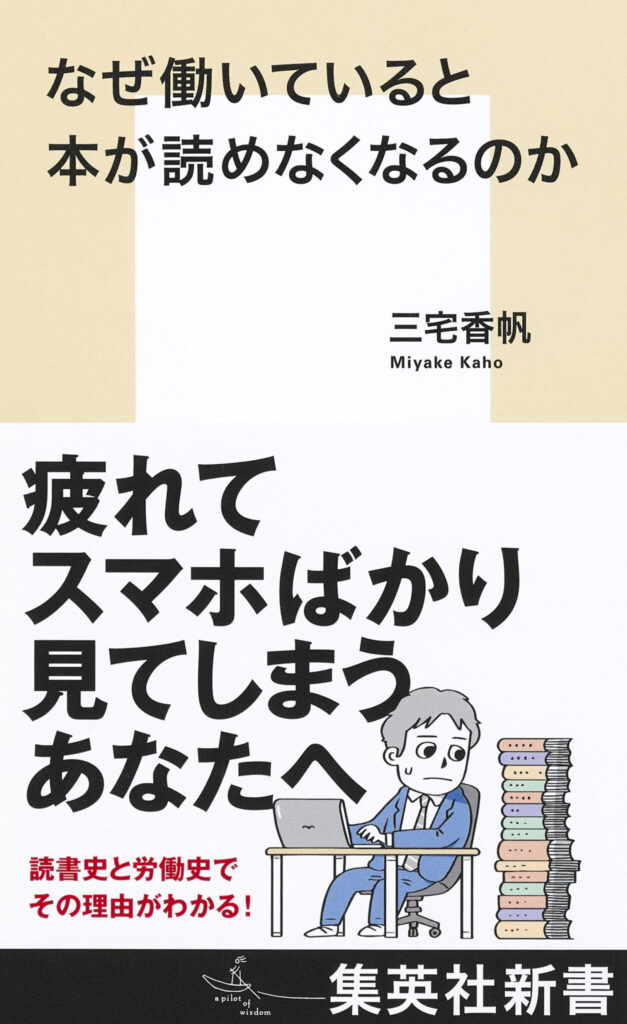










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


