浅草キッドの水道橋博士は、タレントや作家の顔を持つ一方で「日記を書く人」としても知られています。
小学生時代に始めたという日記は、たけし軍団入り後も継続、1997年からは芸能界でもいち早くBLOG形式の日記を始めた先駆者となり、現在も日々ウェブ上に綴っています。
なぜ水道橋博士は日記を書き続けるのか? そこにはいったいどんな意味があるのか?
そう問うあなたへの「日記のススメ」です。
偉大なる先人がいた
10月18日にスモール出版からボクの新刊『藝人春秋Diary』を上梓しました。
題名に「Diary」と銘打つとおり、ボクの日々の「日記」をベースにした著作です。
この本の一風変わった趣向は、日記形式ですのですべての逸話に日付の入った、芸人のエッセー風のように見えますが、ベースは『週刊文春』の一年強の連載を一本も残さずまとめたものであり、同時に江口寿史先生の挿絵を60枚も完全掲載した画集でもあります。
また、テレビに出演する芸人交遊録だけでなく、文化人、政治家を揶揄する章もあるので、ウラドリを経たジャーナリスティックな手法で、芸能界の2017年から2018年をボク視点で描いた、ルポルタージュとしても綴られています。

そして、この本の冒頭でボクは「日記芸人」宣言をしています。
芸能史上初の「日記芸人」の肩書にも思えますが、既にこの分野には偉大なる先人がいます。
その人の名は、浅草喜劇の大先輩にして「日記芸人」の鼻祖・古川ロッパ先生です。
この本の巻頭にエプグラフとして引用しているのが『古川ロッパ昭和日記』からの言葉です。
「日記は俺の情熱、そして業。」
巻末にはエピグラムとして「俺は日記をつけるために生きてるのだ。」とロッパ先生の言葉で締めています。
しかし、令和の時代に、古(いにしえ)に「エノケン・ロッパ」と謳われた、昭和の喜劇王・古川緑波を語る人は数少ないでしょう。
ロッパは明治36年(1903年)に生まれ、昭和36 年(1961年)、57歳の若さで夭折しています。
昭和37年生まれのボクは彼の活躍を見たことがないし、現存する映像も少なく、同時代を生きた人も今や数少なくなっています。
ロッパの経歴も異色です。
幼少の折から文才に長けており、学生時代から映画の同人誌を発行して、映画評論家として、早熟ぶりを発揮。早稲田の学生時代に文藝春秋社を創立した菊池寛に招かれて、雑誌『映画時代』の編集者になり論壇デビューを飾ります。
当然のことながらインテリであり、批評を表現、芸風のベースにしています。
その後、講談、声帯模写(ロッパの造語)の腕を買われて、30歳を超えてから喜劇の世界にデビューします。
そこで、今までの「緑波」の名前を筆名にして、「ロッパ」の名前を芸名にすることにしました。
ロイド眼鏡と太った身体をトレードマークにして、一世を風靡しています。
この遅咲きの経歴は、早稲田出身の森田一義こと、タモリさんにそっくりというより、タモリさんが意識的にロッパの人生を辿っていたようで、以前には、ご本人がロッパとの共通性を何度も言及しています。
(また、その芸風は同じく早稲田出身で出版社経由のいとうせいこうや、早稲田出身でジャーナリスティックな声帯模写を得意とする漫才師・米粒写経の居島一平にも似通っています)
「エノケン・ロッパ」と謳われた全盛期は、1930年代から40年代にかけて。今から70〜80年も昔の話です。
小林信彦はライフワークになった喜劇史のクロニクル『日本の喜劇人』(最初は1975年晶文社刊)の第一章、つまりイの一番に古川ロッパを取り上げています。
興味深いところの一節を引いておくと、
ロッパは昭和28年に『劇書ノート』という、演劇に関する書物の批評を集めた文集を出版しているが、たとえば、安藤鶴夫の『随筆舞台丁帖』を評して、「面白く読んだ、然し、何となく総体に、一流の劇評を読んでいるやうな気がしなかった……」と鋭いところを見せている。
つまり安藤鶴夫を劇評家ではなく、エッセイストとして認めているわけである。
「ロッパぐらい(口)で芝居している者はいない。……ロッパは、この口八丁に引き代へて、その他の手、足、身体全体は口程には彼のいひなりになっていず、特に下半身から足にかけては寧ろ甚だ大根役者である」という安藤評に対しては、「この位ピッタリ言ひ当てられては一言も無い」と、ロッパは記している。こうなると、どっちが批評家だか、わからない。
これは一例だが、私はロッパという人は大ジャーナリストの器であったと考えている。
あとは余技で終わるかも知れなかったのである。
ボクのような喜劇史ファンには、この表現者と批評家の丁々発止がたまらないのです。テレビもない時代であり、多くの人は、この浅草軽演劇全盛時代、エノケン・ロッパが大看板であった頃は、忘却の彼方のはずなのですが、自らが、その頃も詳細に記した『古川ロッパ昭和日記』全4巻(晶文社)は、昭和の文士・永井荷風の『断腸亭日乗』に並び、現代の読書家、好事家には読み継がれています。

ボクもその題名と日記の存在は長く意識していましたが、一昨年の体調不良の休養期間に文字通り読み漁りました。
実在した芸人が、全盛期を経て、人気が陰り、老いさらばえてくる衰退期に、日々何を考え、何を書いているのか興味が尽きなかったのです。
ちなみにロッパの日記魔ぶりは、若い頃も旺盛で、そして老いてなお盛んであり、昭和9年から昭和36年を通して、当用日記10冊と大学ノート95冊にも及びます。
特に昭和20年以降は1日分が大学ノートに2〜4頁、万年筆を裏返しに使った細かい字でびっしりと記され、1日たりとも付け落ちた日がないという完璧ぶりなのです。
日記の総量は400字詰め原稿用紙3万枚以上というのですから驚きです。
現代のブログ文化と違うのは、他人の目を意識することなく、あくまで自分が読み、自分が書き残す、そのことの“愉悦”のために日記が書き続けられたことです。
芸とは虚と実の間にあるもの
ボクは自己承認願望と共に自己満足こそが“日記の愉悦”であると確信します。
ボクは、オフィシャルブログを長く続けていますが、他人が読むことを意識して、悪口やため息は封印するというルールを課しています。
その点、ロッパの日記は、公開されることを前提としていません。
時の政権から同業者、身内までの悪口、陰口の連続、赤裸々な妬み嫉み恨みが赤裸々に綴られ、芸人の生々しい肉声として心に刺さります。
病魔に侵され、明日の生活の不安と死への歩みの音まで聞こえてくると、やるせない気持ちになると同時に、かたくなに本音にこだわり、偽善を嫌うロッパの気性に妙な共感も感じ入ります。
この本を読み通すと、当時の喜劇人や文学者、劇作家、政治家など次々と登場する、多士済々の有名人の月旦評などがわかるだけでなく、芸人が持つ特異な心象風景、嫉妬深いメンタリティ、また興行界であった浅草の賑わいや風俗、楽屋風景、舞台裏、三食のメニューの味や値段、昭和グルメに至るまで描き尽くされていて、過ぎ去りし「昭和」という時代が脳内にくっきりと浮かび上がります。
今では第一級の昭和芸能史の資料であり、手前味噌ながら、まるで知られざる『藝人春秋エピソードゼロ』とさえ思えます。
逆に言えば、ボクの『藝人春秋Diary』も古川ロッパから続く、芸能の「語り部」役を任じられた日記の延長とも言えましょう。
今回の『藝人春秋Diary』は、このロッパの日記の強い影響下に書かれています。
ロッパの日記に倣い、ボクも『藝人春秋』を媒体を変えても、休むこと無く延々と書き継ぎ、今後もシリーズ化して続けることに決めました。
藝人春秋シリーズの登場人物はボクが共演歴のある方々で、従来通りジャンルは演芸界とは括っていませんが、皆、人前=表舞台に登場する人々であります。
時代の脚光を浴びる芸人の同時代人による批評・分析でもあり、また「芸人という病」のカルテにもなっているでしょう。
平成のネット時代、「ブログ」の登場と共に、日記のあり方は大きく変わりました。
「表現」という言葉をもじって、ボクの造語で言えば──
日記というものは人間の表裏一体のなかで、本来、表には見せない、自己の内面世界を覗きみる、「裏現」(りげん)だったのかもしれません。
「芸とは虚と実の間にあるものである」と定義した「虚実皮膜論」は観阿弥の息子、世阿弥が能を批評した「風姿花伝」というものの中で伝え、次世代の近松門左衛門へとその思想が受け継がれていったものです。
芸とは虚と実の間にあるものである。
芸能人の「日記=ブログ」とは、この虚実の皮膜を自分の手で剥がし、表と裏の世界を顕にする行為のことなのかもしれません。
『藝人春秋』は生来の人見知りで裏方志向のボクが、座右の銘「出会いに照れない」を自分に言い聞かせながら、実際に起きた出来事に日付を残した交遊録です。
560頁に及ぶ大著を是非、この読書の秋の一冊としてご堪能ください。
プロフィール

1962年岡山県生れ。ビートたけしに憧れ上京するも、進学した明治大学を4日で中退。弟子入り後、浅草フランス座での地獄の住み込み生活を経て、87年に玉袋筋太郎と漫才コンビ・浅草キッドを結成。90年のテレビ朝日『ザ・テレビ演芸』で10週連続勝ち抜き、92年テレビ東京『浅草橋ヤング洋品店』で人気を博す。幅広い見識と行動力は芸能界にとどまらず、守備範囲はスポーツ界・政界・財界にまで及ぶ。著書に『藝人春秋』(1~3巻、文春文庫)など多数。
水道橋博士の日記はこちら→ https://note.com/suidou_hakase


 水道橋博士
水道橋博士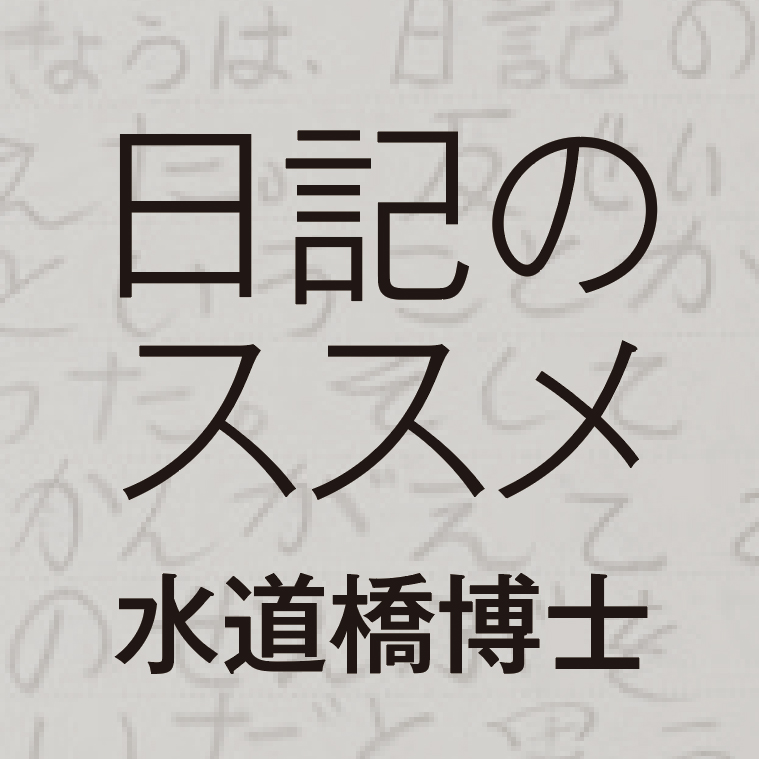










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


