ひ弱なリベラリズムへの共感
綿野 確かにアイデンティティは生得的なところがある一方で、僕たちみずからが解釈して物語化していくわけです。アイデンティティをどういうふうに位置づけるかを決めるのは社会です。そういう意味では相対化できるものでもある。このあたりは、「逞しきリベラリズム」の井上達夫先生の「自己解釈的存在」が参照されるわけですが、荒木さんは他者との「会話」を通じて自分のアイデンティティをめぐる解釈のちがいを発見する場として「サークル」の可能性を見ていらっしゃる。実体化してしまいがちの「種」=「アイデンティティ」のこわばりを解除する場としてのサークルですね。なんとなく感じたことですが、荒木さんが思い描いているのは、「逞しきリベラリズム」というよりは、もうちょっと緩いリベラルな主体という感じでしょうか。
荒木 井上達夫さんはまさしく自分のリベラリズムが「逞しきリベラリズム」であると主張していますね。アイデンティティによる拘束を認めながらも、それが会話のなかで変わっていくことを承知してなお他人と対峙せんとするリベラリズムです。
それに対して、かつて稲葉振一郎さんが「ひ弱なリベラリズム」ということを提唱されていましたが、その二つの対でいうと、どちらかといえば私は稲葉さんの立場への共感のほうが強いです。それが「緩いリベラル」かどうかは別にして。
もちろん、井上さんが主張するような「逞しき」も否定すべきものであるとは考えてはいません。実際、肯定的に引用してますしね。ただ、私も含めた多くの日本人が、井上さんが念頭にするようなリベラリズムのさまざまな討論に耐え得るような能力を持っているかといえば、はなはだ疑問です。
そう考えてみたときに、サークルでの、時に間違えてもいい、間違ったことを言ってもそれで𠮟責されないような、そういう領域の中で自分の言葉を放っていく、試していく……そんな訓練が大切なのではないかと思ったわけです。リベラリズム以前のリベラリズムのレッスンが必要だと考えるわけです。
井上批判をしたいというよりも、井上的な理想をかなえるためにも、その前段階を固めなければならないと考え、サークルに注目したわけです。
愛の重要性について
荒木 リベラリズムについての話が出ましたが、私の本は普通のリベラリズムの議論と違って、制度より心を問題にしていると思います。いま様々なマイノリティの差別問題が噴出している最中です。そのなかで、たとえば数の比を整えるクオータ制のような発想が有力視されています。ですが、いくら制度の面で平等性を確保しても、結局心が開くというようなことがなければダメで、サークルとは本来、その心の開き方に関する技法であったという想いが強いわけです。
逆に言うと、心が硬直した仕方でサークルを運用すると、みんな通り一遍のことしか言わないわけですね。自分の発言が何かのきっかけで外部に流出したら政治的に意識の高い人に突っ込まれるだろうと考え、防御的に振る舞ってしまう。
そういった現実について、十分に考慮しなければ、偉い先生方が言ってる民主主義なるものもやっぱり有名無実というか、ハリボテになってしまうんじゃないか。
そこで大事になってくるのが、「愛」なのです。『サークル有害論』にも書きましたが、フランスの哲学者であるアンリ・ベルクソンも閉ざされたものを開くのは結局、「愛の飛躍」なんだと主張しているわけです。ここでベルクソンが主張している愛というのは、いわゆる異性愛とか、故郷への愛とか、そういうものではない。ベルクソンが考えているのは、もっと全人類に広がるような、普遍的な愛です。敵さえ友として受け入れる普遍的に包摂的な感情のことです。
ベルクソンの愛の理論に対して、田辺元などは「そんなものはお題目に過ぎない」と批判しているわけですが、私はベルクソンの主張のほうが正しいと論じた。しかし、新刊『「逆張り」の研究』を読んでみて思ったのですが、綿野さん的にはそういう美辞麗句はちょっと甘ったるいのでは?
綿野 ぼくが新型コロナ禍でリモートワークやテレワークが流行したときに思ったのは、これはハラスメントを防止する最大の仕組みだなということでした。テクノロジーを通じて映像や音声をやりとりするわけだから、記録やログが残るので抑止効果がある。NGワードを感知してバンしたりミュートしたりすることもいまの技術であれば簡単でしょう。もちろん、ハラスメントや嫌がらせがなくなることは良いのですが、しかし、その究極の先にあるのは「ひとりエコーチェンバー」というべき他人を消去した自分だけの空間です。
そもそも他人と集まらなければ、ハラスメントや嫌がらせは起きません。といっても、企業では多くの人が集団で働く必要がある。しかし、集団がはらむ「有害性」は企業にとってリスクでしかない。なので、こうやってテクノロジーによって監視して記録してゾーンニングして、小集団の持つ「有害性」を「リスク」としてなくそうとする大きな流れがあると思います。
しかし、そういう流れが一般化すると、他人との深いつながりを作れなくなる。迂闊なことや間違ったことはログに残って、下手すればネットで晒されるので、腹を割って話すこともできなくなる。信頼関係もつくれない。適当なことを言いますが、最近のサウナブームもテクノロジーによって監視され記録されないプライベートな空間を人々が求めているところもあるんじゃないでしょうか。
そういう大きな流れがあるなかで、「集団の毒を集団を持って制す」というべき荒木さんサークル論はとても興味深く思いました。一方で、ぼくとしてはそこまで集団に対する執着がないんですね。そもそも集団の同調圧力が大嫌いな「逆張り」ですし、集団の毒にあてられる前に「逃げ出せ」と思ってしまう。たとえば、労働組合を結成して職場を変えていく。自治会を通して大学を変えていく。それが民主主義というものです。しかし、集団全体を変えるべく集団のなかで闘っていくためには、集団に対する最低限の愛がないと難しい。愛社精神だったり、愛校精神だったり、左翼に意外と愛国者が多い理由はこれだと思います。ぼくはそういう愛がないので「さっさと逃げる」を選択します。
ちょっと話が大きくなりましたが、ぼくはサークルという小集団においてもスタンスは同じなんですね。このあたりが荒木さんとの大きな違いです。とはいえ、一方で、そういう集団から「逃げる」という選択が、転職エージェントといった資本に絡めとられている、という現実もあるんですが。
荒木 綿野さんのサウナの話で思い出しましたが、今の大学では、セーフ・スペースというものが取り入れられていますよね。様々な属性の方々が自分の自尊心みたいなものを傷つけられずにコミュニケーションができるような場所です。
大学のような公的な場ではセーフ・スペースのようなものが必要であるという構想も分からんじゃありません。ただ、これは非常に言葉を選ばなきゃいけないんだけれども、サークルというのはそういう傷つきの経験をできる場所でもあるし、その可能性の芽を全て摘んでしまうのは、やっぱりちょっと怖いなっていう直感があるんです。そこまで管理されてしまっていいのだろうか。
綿野さんから先ほど「腹を割って話す」っていう表現がありましたよね。「腹を割る」っていう、この身体性がやっぱり重要かなと私は思っています。あるいは、「腹に落ちる」っていう経験もあるわけです。同じような知識でも、その知識の受容の在り方が全然違うものになりうるし、身体性がある学習は、やっぱり後々生きていくものになる。言葉だけではどうしようもない。本のなかで、「言葉」じゃなくて「態度」が重要だと書いたのはそういう意味です。

プロフィール

荒木優太(あらき ゆうた)
1987年東京生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。明治大学大学院文学研究科日本文学専攻博士前期課程修了。2015年、第59回群像新人評論賞優秀作を受賞。主な著書に、『これからのエリック・ホッファーのために』『無責任の新体系』『有島武郎』『転んでもいい主義のあゆみ』など。編著には「紀伊國屋じんぶん大賞2020 読者と選ぶ人文書ベスト30」三位の『在野研究ビギナーズ』がある。最新刊は『サークル有害論』(集英社新書)。
綿野恵太(わたの けいた)
1988年大阪府生まれ。出版社勤務を経て文筆業。詩と批評『子午線 原理・形態・批評』同人。「厚揚げは貧民のステーキ」(『絓秀実コレクション2 二重の闘争――差別/ナショナリズム/1968年』)「雑に飲んで、雑に死ぬ」(『B面の歌を聞け』2号)など評論やエッセイを多数執筆。著書に『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)、『みんな政治でバカになる』(晶文社)がある。最新刊は『「逆張り」の研究』(筑摩書房)。


 荒木優太×綿野恵太
荒木優太×綿野恵太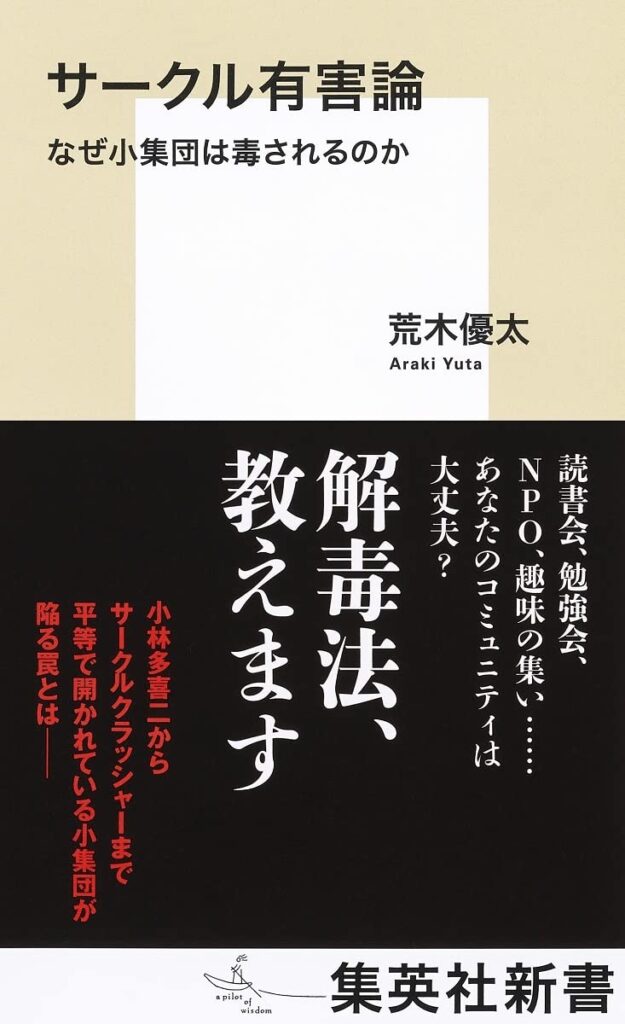










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

