就職先として「コンサル」が人気を博し、「転職でキャリアアップ」「ポータブルスキルを身につけろ」などの勇ましい言葉がビジネスパーソンに浴びせられる昨今。いまの日本にとって働くこととはどのようなものなのだろうか。
『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』などで知られる批評家・会社員のレジー氏が、「成長」をキーワードに現代のビジネスを取り巻くことばを分析したのが『東大生はなぜコンサルを目指すのか』である。
本記事では、『コンサルティング会社完全サバイバルマニュアル』の著者であり現在も医療系のベンチャーで働くメン獄氏との対談を通して、「仕事」と「成長」との向き合い方を考える。
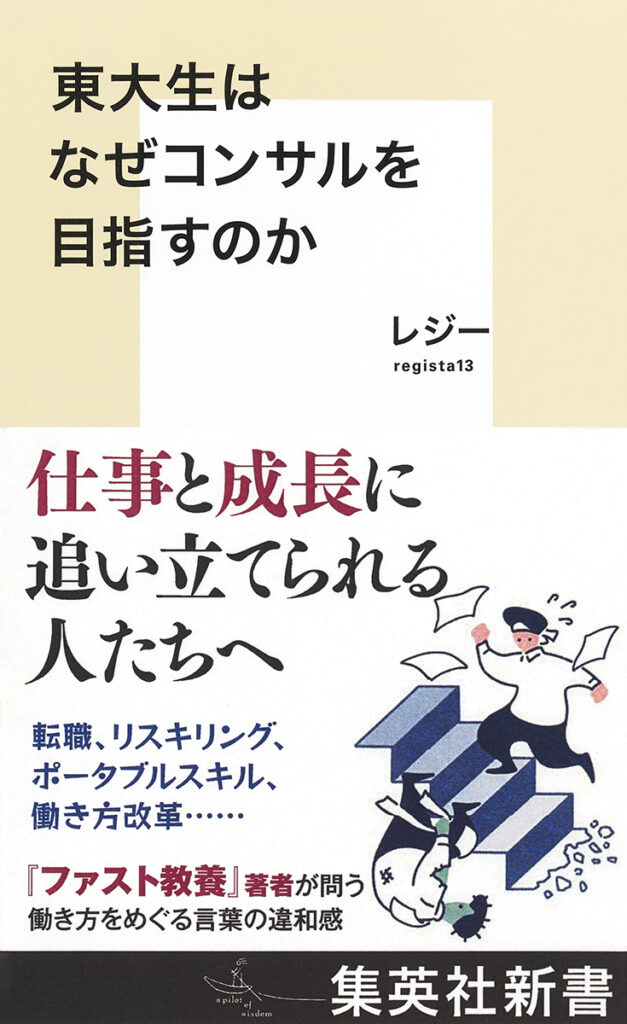
PayPayの営業こそDXの本質である
レジー 前半は、現在の「コンサル」をめぐる状況についてメン獄さんとお話をしながら、「成長」神話に囚われすぎていることや、ポータブルスキルを身に付けることだけに価値が置かれてしまっている現状について見てきました。後半はこうした現状を踏まえながら、これから私たちはどのように働いていけばいいのか、というのを考えていきたいと思います。
メン獄さんは転職されたあと、医療系のベンチャー企業に行かれていますが、転職後にコンサルで培ったスキルは活かされていますか?
メン獄 正直いえば、コンサルの時に身に付いた癖を取り除こうとしていると思います。もともとは、すぐにエクセルやパワポを叩く癖があったんですが、今はもっとアナログなことを大事にしていて、人に会いにいくとか、喋りに行く、みたいなことを積極的に行うようになりました。
ちょうど昨日は、仕事で北海道に行っていて役所の人と話していたんです。北海道は180ぐらいの基礎自治体があるんですが、それぞれの場所の特徴にあった診療の形を提案したくて。そのためには、僕は180の自治体ぜんぶ回りたいと思ってるんです。そう言うと同僚から驚かれるのですが、フレームワークを使ったりパワポを作成するより、現場に足を運ぶ方が価値がある。それに、各自治体を回りながらリモートワークを車の中でやれば、それも無茶ではなく出来るんです。そういう意味で、アナログとデジタルを上手く組み合わせるのが大事じゃないかと。
レジー やっぱり、仕事でもなんでも一次情報を取りに行くのって、すごく大事じゃないですか。そうは言いつつ、20年前の自分にそのことの大事さを理解できるかはわからないとも思います。元々僕はメーカーに勤務していましたが、最初に希望してマーケティング部門に配属されたあと、営業を経験することなく辞めているんですよね。この年齢になって、あの時営業をやっていたらまた違った景色も見えていたのかな……とも考えます。
メン獄 コンサルだと本当にデスクワーク主体になっちゃうんですよね。ただ、実際はお客さんに会いに行った方が、お客さんの状況への理解も深まるし、提案内容も外さないと思います。それに社会が複雑になって「真実」が何かわからなくなっている状況では、自分の足で見たり聞いたりした情報の信憑性は非常に高まっているように思います。
レジー 「アナログ」の大事さですよね。
メン獄 そうそう。仕事における「アナログな部分」を人間が軽んじすぎている気がしますよ。DXの話でいえば、1から100のDXって簡単なんです。つまり、インターネットにさえつながっていれば、もはやAIがあるからなんとでもなる。ただ、0から1を作るのは、絶対に物理的にやるしかないんです。でも、世の中の課題の99%はこの0を1にする部分にある。それこそPayPayだって、あれはあらゆるお店に人力で営業をして導入してもらっているからこそあれだけ普及したわけで。これこそがDXの本質なんですよ(笑) なのに、ほとんどの知的労働者の生産性は、1から100のDXに注ぎ込まれていると思うんです。
レジー それはとても分かります。元マッキンゼーの安宅和人さんの著作『イシューからはじめよ』では、いいイシューを見分ける基準の1つとして「答えを出せる課題かどうか」が大事と書いてありますよね。それでいえば、もはや0を1にする作業は解決できる課題とさえ見なされずに無視されていく。
メン獄 そう思います。そこを見ていない。アクセンチュアの新卒を各都道府県に一人ずつ配置して、インターネットをわかっていないおじいちゃんとかおばあちゃんに触らせた方が、デスクワークをずっとさせておくよりも、よっぽどいいと思います
コンサルの提案でも、なんでもSaaSのプロダクトを入れて業務効率化をしたように見せかけていますが、多額のお金をかけてやるぐらいだったら実は派遣のスタッフを100人入れてやってもらったほうが絶対に安いし生産性が高いんです。人間をなめてるんですよ。人力でやったらかなりの生産性が出るところを、今はそれをスポイルしようとする文化的土壌ができてきてしまっている。AIマッチングみたいなシステムで需要と供給をマッチングさせるのも、アナログで現場に行って需要と供給をマッチングさせた方が早いし、確実性が高い。
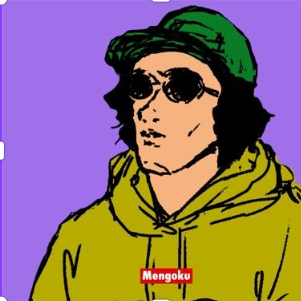
「シンプルに」ではなく「迷いながら」考えよ
メン獄 それと、コンサル業界から転職して意識しているのは、タイパを意識する仕事の仕方をやめたことですかね。何がなんでも今日アウトプットを出さなきゃ、と思わないようにしました。その代わり、物事をじっくり考える時間や、事業に直接は関係ないかもしれない人の話を聞いてみたり、そんなことをしています。
僕は今、ありとあらゆる開業医の先生方に会ってるんです。地元で評判のお医者さん……と聞いたら仕事と関係なく行くようにしてみている。それがお金になるかはわからないけれど、そうやってさまざまなお医者さんに話を聞き続けることで何か言えることはあるんじゃないかと思っているんです。何になるのかと聞かれるとわからないのですが、とりあえずはやってから考えてみようと(笑)
レジー 「やってみてから考える」というのは、今の社会ではすごく許容されづらいですよね。よくDXの文脈で「ただがむしゃらにデータを集めるのは良くない。まず目的があって、そこに対して必要なデータをとるべき」という話がありますが、こういう考え方があらゆる場所に染み出しすぎていると思う時があります。
コンサル的な優秀さにおいては「シンプルに考える」こと至上主義いうか、とにかく「迷う」機会が全てカットされている気がします。ロジカルに課題を見つけて整理して…みたいなプロセスは当然大事なのですが、その過程で切り落としているものは本当に重要じゃないのかな、とか。
メン獄 医療っていろんな人のいろんな思惑が重なるので答えが一つに定まる話じゃないんです。でも、コンサルだと、そこに明快な答えを出さないといけないじゃないですか。それがあまり正しいことだとは思わなくなった。「迷いながら考える」ことを意識するようになりました。
レジー それはいいですね。コンサルの世界の外に行くと、結論を一気に決めすぎない、みたいなのが大事になるじゃないですか。仮説を立ててそれに向かって進んでいく思考とは真逆ですよね。コンサル化しすぎている社会において「迷いながら決めていく」というのは一つのヒントになる気がしますね。
メン獄 そうですよね。僕は最初からそれが意味があって、ビジネスになるかを考えると、どんどんつまらなくなってくるんですよ。興味があることだったら一度やりこんでみて、そしたらある時突然、それがビジネスになるフェーズがやってきたりする。ただ、そこまでは半分、自分の趣味としてやってみる。コスパが重視される世界なので、周りの友達にそれを言っても「それ意味なくない?」と言われるんですけどね(笑)
だから、みんなにとっては意味がないから勧めないけれど、自分自身はやる。その心を持ち続けるしかないと思います。
レジー 急に仕事として実りが生まれるというのは、本当にそうだと思います。仕事って、常に右肩上がりを求められることがあるじゃないですか。でも、実際はタクシー料金型で成長していくというか。関係ないと思っていたことが作用して、突然実ることがある。

属人的なこだわりを取り戻す
メン獄 コンサルの仕事の進め方は、自分たちの結論に自信を持って、それにとにかく従わせる、みたいなことが多いじゃないですか。でも、意外とその事業にとってキーになるのは、一人の職人の考え方だったりする。マニュファクチャーの考え方ではそういう属人性はなくしたほうがいいんだけど、そこは本来「味」だったりするわけです。それがない世界にみなさん行きたいですか、というのを良く考えた方がいいと思います。
レジー 今、マニュファクチャーっていう言葉を出していただいたんですが、僕はマニュファクチャーとクラフトマンシップ、つまり「職人としての属人的なこだわり」が対になる気がしています。単にポータブルなスキルを身に付けるだけではなくて、その人なりのクラフトマンシップをどう持つのかが大事だと思うんです。仮説思考とフレームワークで結論ありきでやっていると、それが削ぎ落とされてしまうのではないか。
メン獄 AIに経営の意思決定プロセスを任せる「AIドリブン」という言葉がありますよね。別にそれはやればいいとは思うけど、ただそこには人間に対するリスペクトがないような気がして。やはり「人間」というものの価値をもう一度考える必要があると思います。
レジー そうですよね。今は、人間の複雑性をどんどんカットする方向に進んでると思うんです。MECEという考え方が最たる例だと思うんですが、人間とか社会について、なんでも漏れなくダブりなくわけられるわけがない。仕事してそういう分類が必要だとしても、何らかの畏れは持っていないといけないんじゃないかなと感じます。
メン獄 僕がXのアカウントをやっているのは、サラリーマン的な生き方に対するささやかな抵抗なんです(笑) サラリーマンは会社から生産性をずっと背負わされていて、無駄なことをしてはいけないという圧力がある。僕があのアカウントでやっている活動は本来は仕事と関係ないことで、会社からすれば歓迎できるものではないのだけれど、明らかにそれは会社での活動にフィードバックされてつながる、ということがあるんです。
だから僕の働き方は、三宅香帆さんが言ったような「半身」の働き方を24時間ずっとやっているようなものなんですよね。ある意味でプライベートが無いというか。働き方改革で「それも働くことになるのでやめてください」と言われちゃうと、僕は逆に窮屈だと思ってしまいます。
レジー 確かに。そもそも僕が今のような活動をしているのも、会社員をやりながらブログを適当に始めて、それがたまたまうまく進んだ結果でしかないんですよね。あらかじめ予想したり計画したりしていたわけではななかったし、仕事につながるとかどうとかは当然考えていませんでした。だから、コントロールできないものを排除しすぎないというのは重要だと思います。
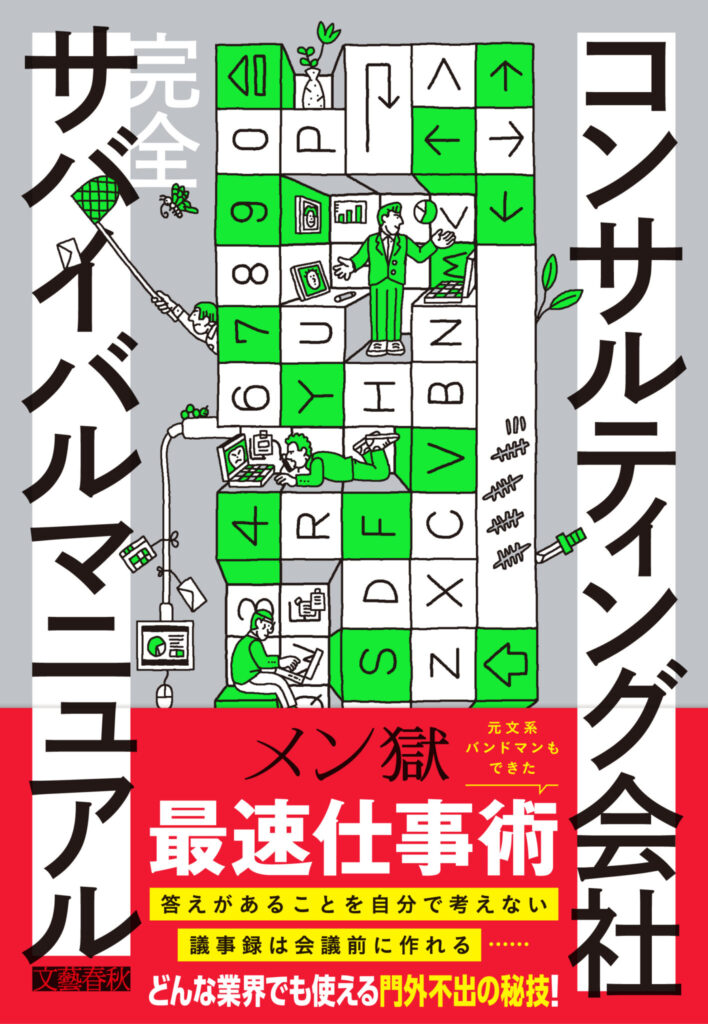
仕事の不条理が一番面白い
レジー そういえば、かつて働いていた会社で腹立たしいことがあって、その件について上司に怒りのメールを長文で送ったところ、「なんだかお前のメールは長いけど最後まで読めてしまう」と言われたことがありました。この経験は「自分がブログを始めたら読んでもらえるかもしれない」と思ったきっかけの1つだったりします(笑)
メン獄 いい話すぎる(笑) なぜ自分が怒っているのか、というのを文章にして読み返すと面白すぎますよね。
レジー 会社員のロックンロールが発動しているのかもしれない(笑)
メン獄 キレるための理由が会社員には必要じゃないですか。それを理路整然と書いているうちにあまりにもそれが不条理で笑えてくるんですよね。
かつて、僕は会社でのいろんな出来事を見ていて、なぜこんなに優秀な人たちが集まって、ここまで意味のわからないことが起こるのだろう?と思ったことがあって。そういう状況がすごく好きなんですよ。
レジー 演劇とか音楽の特等席に座ってるみたいなものですね。
メン獄 そうそう。その人が、それを言わざるを得ない状況に追い込まれている理由を分析していくと、やっぱり人間はめちゃくちゃ難しいなと(笑) そんな面白いこと、今はなかなかないですからね。
だから僕は、仕事しか面白いものがないんだから、仕事をいろんな角度から楽しむしかないじゃん、と思っている。どうせやるなら面白いと思える仕事をした方がいいなと。
レジー 確かに。「仕事を楽しむ」というと、これまでは「自己実現」とか「好きなことを仕事に」みたいなことがイメージされていたけれど、「不条理を楽しむ」みたいな方向も大事かもしれない。
メン獄 そうやって不条理を楽しむと、働く中で出会うストレスに対するレジリエンス(回復力)にもなるはずなんですよ。現在は、会社だけでなく、社会全体で不条理なことが起きるじゃないですか。例えば最近のトランプ関税でも、あの決定にいちいち一喜一憂していても仕方のない部分も大きい。だから、その状況自体を俯瞰して楽しんで、大きく構えていればいい。
レジー コンサル的な思考だと、「不条理」そのものを合理的に無くしていこうという発想になると思うのですが、そうではなく不条理な状況そのものを楽しむことに、これからの働くことに関するヒントがあるのかもしれませんね。
(構成:谷頭和希)
プロフィール

レジ―
批評家・会社員。1981年生まれ。一般企業で経営戦略およびマーケティング関連のキャリアを積みながら、日本のポップカルチャーについての論考を各種媒体で発信。著書に新書大賞2023入賞作『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)のほか、『増補版 夏フェス革命 -音楽が変わる、社会が変わる-』(blueprint)、『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア、宇野維正との共著)。X(旧Twitter) : @regista13
メン獄
コンサルタント。1986年、千葉県生まれ。上智大学法学部法律学科卒業後、2009年に外資系大手コンサルティング会社に入社。システム開発の管理支援からグローバル企業の新規事業案件まで幅広く手掛ける。2021年に退職後、医療業界全体のDX推進を目指すスタートアップ企業にDXコンサルタントとして就職。主に大企業のテクノロジーを用いた業務改革の実行支援・定着化、プロジェクト管理、運用設計が専門領域。コンサルティング業界の内情やDXトレンドを紹介し、仕事をよりポップな体験として提案するTwitter、noteが人気を博す。著書に『コンサルティング会社完全サバイバルマニュアル』(文藝春秋)。
仕事はどう楽しめばいいのか?『東大生はなぜコンサルを目指すのか』著者と『コンサルティング会社完全サバイバルマニュアル』著者が考える


 レジー×メン獄
レジー×メン獄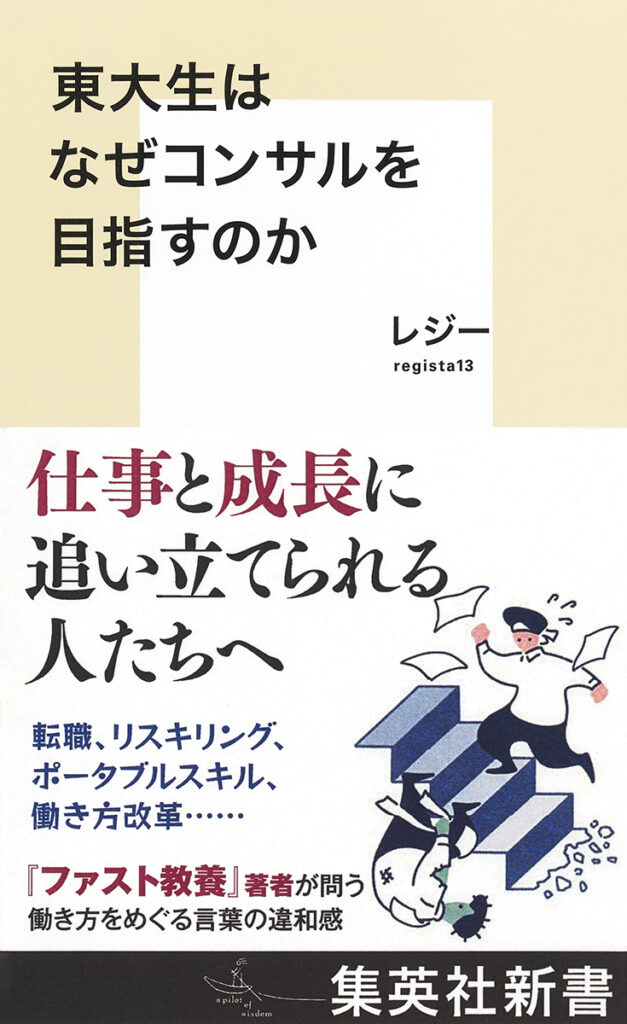










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


