「働いていると読書ができなくなる」。読者のシンプルな悩みをひもとき、新書年間ランキング1位になった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』。著者の三宅香帆氏は、発売以後さまざまな職業の人々と「働きながら本を読むためにはどうすればいいのか」ということについて考えてきた。「プレバト!!」や「林先生が驚く初耳学(現・日曜日の初耳学)」、「トキトケトーク」など幅広いテレビ番組を制作している毎日放送の水野雅之氏は、「自分のOSをアップグレードするため」にテーマを設けて読書をしているという。本対談では、ものづくりをしながら読む二人が、読書の創造性について語り合う。
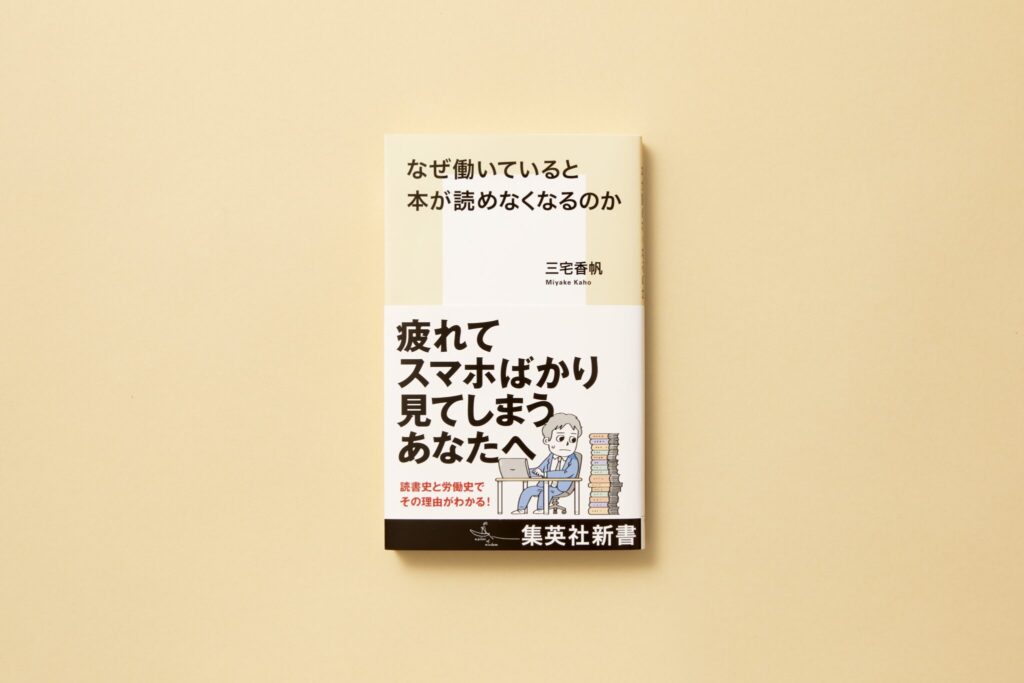
読書はOSをアップデートさせる
三宅 水野さんは、本もかなりいろいろ読まれていますよね。
水野 そうですね。ちょうど昨日まで辻村深月さんの『傲慢と善良』を読んでいました。それを読んでいても「テレビとして離脱させないとしたら、こういうフォーマットになるな」ということを考えてしまって(笑) それこそ、村上春樹さんの『海辺のカフカ』も「ここ、カットバックもういいから、さっきの話続けて欲しいな」ってなったりして(笑)
三宅 最近の小説を読んでて思うんですけど、私的にはそこまでカットバックいらないって思うことが多いなと(笑) もっと物語を進めて欲しい、と思ったりしてしまいます。
水野 実はそれ、テレビも一緒なんです。ディレクターとしてはどうしても回想シーンって入れたくなっちゃうんですよね。編集している感が出しやすいし(笑)
三宅 出版でもテレビでも同じ現象が起きている!いろいろな本を読まれていると思うのですが、そうした読書体験がテレビ番組を作るときに役立っている実感はありますか?
水野 たまに、面白いコンテンツを作るために読書が必要かどうか聞かれるのですが、実は僕はどちらでもいいと思ってるんです。というのも、読書をしているだけで面白いものが作れるわけではないからです。もしも読書をインプットの手段と捉えているなら、絶対に不可欠なものではない。我々が作るような映像は「語彙力」が増えるだけでは視聴者を惹きつけることはできないし、ネタが欲しいならリサーチャーに頼めばいいと思います。
ただ、読書自体はとても稀有な体験であることも確かです。というのも読書が趣味になっている人は、人間としての内面とか考え方、価値観を深掘りできる。僕はよくこれをOSとアプリで例えるんですが、インプットと捉えている人にとっては読書はアプリなんです。だったら熱中できる趣味や目の前の仕事を頑張ることで先にOSをアップグレードした方が、読書という「アプリ」は簡単にインストールできるようになります。一方で、読書が趣味という人は本を読み重ねることによって「OS」をアップグレードできますよね。って考えると、読書が好きなら読めばいいし、その気分じゃないならまだ読まなくていいと思います。ただ、本はすごい才能を持っている人たちが書いていることが多いので、知識や価値観、時代感覚を高濃度で摂取できる貴重なメディアだと思います。
三宅 すごくわかります。先日ノーベル文学賞を受賞されたハン・ガンさんを読んでるときも、何となく彼女の世界観を摂取してる気分になりました。あらすじとか、そこで起こったことを情報として読んでるんだけど、同時にその人の言葉の世界観というか、考え方・ものの見方・世界の見方自体を取り入れてる感覚が割と強いんです。本は一人で読むことが多いからこそ、内面に何かが入ってくる感じがある。
水野 確かに。それこそハン・ガンさんの作品を読んだとき、あらすじだとか細かい描写というよりも、それを読んだことによる空気感というか、自分の中の感覚が変わっている、みたいなことを感じますよね。

遠いものを掛け合わせて面白いものを作る
三宅 それに、読書はお金がかからないので、割といろいろな本を読んで、さまざまな考え方と簡単に出会えるんですよね。それもいい。
水野 僕自身、もともと読書が趣味だったわけではないのですが、特にここ数年、自分の日常生活では絶対に出会わないものに触れてみたくて仕方なくて、いろいろな本を読んでいたんです。そこで触れた未知の世界とか物の考え方がどこかのタイミングで自分の番組に影響を与えるだろうな、という感覚は絶対にあって。それこそ、三宅さんの言う「ノイズ」がどこか活かされている気がします。
三宅 分かります。私もそうですね。やはり「ノイズ」的なものがないと、アイデアも出てこない感覚があります。そうした「ノイズ」を摂取するときに読書はすごくいいと思うんです。
水野 アイデアの話をするときによく挙げるのが、厳島神社の話です。鳥居をどこに建てようか、何人かが集まって話し合ったそうなんですが、全体が神の島と崇められていた島には建てられない。だから海に鳥居が建てられたそうなんですが、結果的にそれが1400年以上にわたって多くの人を惹きつける風景となった。つまり、試行錯誤の結果生まれたアイデアが「海と鳥居」という意外な掛け合わせになったんですよね。多くの人を魅了する企画には意外なもののかけ合わせが存在しているという事実が、いかに普遍的かというエピソードですよね。これはオリジナリティーがある実体験をまず言語化してから季語とかけ合わせると良い作品が生まれる俳句と似ているかもしれません。
三宅 その話を聴きながら、すごくそう思いました。
水野 これはテレビ番組の企画を考える時も一緒なんです。たとえば、企画を作るために本をいっぱい読んでいても、良いアイデアは生まれない。テレビ番組で使えそうなネタないかなっていう目線で情報を探しにいく時点で、もう意外性があるものには出会えないんですよね。だけど、仕事と関係ないくらい遠くにあるものに触れていると、自然と仕事に結びつくことがあるんです。それこそスピノザ哲学とか元素記号の周期表とか。
三宅 面白い。それが多くの人に届く番組のコツにもなっているわけですね。
水野 読書でノイズに触れていると、読んでいるときには全く意識していなかった1行が突然、企画の掛け算の要素になることがあるんですよね。藤原辰史さんの『分解の哲学』に、幼虫はサナギのなかで一旦、体をドロドロに溶かしてから、全く別の生物に羽化する、と書いてあるのですが、読書で触れたノイズを自分の体内でドロドロに溶かしておくと、それがいつしか企画という形になる……みたいなイメージだと思います。
三宅 まさに「ノイズ」が広い層に届くコンテンツを作ることに役立ってるわけですね。

演者と企画をいかに掛け合わせるか
三宅 今のお話は、番組での「キャスティング」の話にもつながっていると思います。『プレバト!!』もタレントさんの「ここがすごい」という能力を捕まえるのがとても上手だと思うんです。
番組を作るとき、タレントさんの特性と番組の方向性のすり合わせはどのようにされているんですか?
水野 どうでしょうね。通常はまず企画を考えて、その企画を誰がやると面白いかな、と考える。それでキャスティングが決まったら、その2つが馴染むようにチューニングをしていきます。一方で、『プレバト!!』の場合は、浜田さんがMCということは先に決まっていたので、浜田さんがやる企画なら何がいいか、をすごく考えた。どちらのアプローチでも「出演者が誰でもいい」という状態では企画が緩いので、「この番組はこの人だから面白いよね」と言ってもらえる番組になるまでスタッフみんなで悩みまくることが大切ですね。
三宅 例えば、水野さんがプロデュースされている『トキトケトーク』もコテンラジオの深井龍之介さんとダウ90000の蓮見翔さんでなくてはいけなかった?
水野 そうですね。まず、深井さんという歴史を深く語れる人がいる。そこに蓮見さんという、人の話をきっかけにトークを広げることができる人を組み合わせて、その2人にしかできないトーク番組をやりたかった。『初耳学』もそうですね。高校時代に授業を受けていた僕だから知っていた林先生の論理的な話術とシニカルな性格をフィーチャーして演出していきました。初耳学が始まるまでは、林先生のあの人柄はテレビで出ていなくて、ただ「頭がいい人」という印象だけだったんですよね。
三宅 面白いです。私がフィールドとする書籍の世界だと、どちらかというと「作家は書きたいことを書く」と言われがちなんですが、それこそ誰がどのタイミングで何を書くか、という「キャスティング」もすごく重要だと思っていて。
編集者の方でそれを考えている人も多いですし、私もずっと考えているので、すごく参考になります。

さまざまな視点を取り入れるために「外」に出る
三宅 そういえば水野さん「女性作家しか読まない」みたいな縛りをご自身で作っていたときありましたよね?
水野 1年間「女性作家縛り」をやってました。少しずつ改善されていますが、テレビ業界にはやっぱり昭和らしいホモソーシャルな空間が存在しています。そんな環境で20年以上やってきた自分が、それこそジェンダー感覚をアプリ的にインストールして番組作りに反映しようとしても付け焼き刃でしかないだろう。自分の中に令和版のOSも新しく搭載しないといけないなと。そんなことを思った結果、1年間、読む本を女性作家に縛ってみたんです。そしたら、ネタ選びも編集も仲間とのコミュニケーションも変化を実感しました。あと、これは本だけじゃなくて映像を見たあとでも同じなんですけど、どんな作品を見たかで言葉選びってすぐに変わりますよね。『ボーイフレンド』を見たときは少しゆったりした話し方になるけど『地面師たち』を見たあとは会議でめちゃくちゃ強気なことを言ったり。この2作品はほぼ同時期に配信を開始していたから、その日ごとに僕が進める会議の雰囲気がちょっと違ったはずです(笑)
三宅 (笑) でも、それってすごいことですよね。OSのアップデートは「しなきゃ」と思う人の方が少ない気がするんです。それに、別にアップデートしなくても仕事は進むじゃないですか。
水野 そうですね。
三宅 それでもアップデートしようと思う、そのモチベーションはどこから来るんですか?
水野 やはり、周りの人たちがすごいからじゃないかな、と思います。三宅さんも僕の中ではそうなのですが、いろいろなことを一生懸命に取り組まれていて、その活躍を見ていると「自分も今のままじゃだめだ」と思うんです。
三宅 そう思えるのがすごいですよね。
水野 幸いにして、僕の周りにはテレビ業界の中にも外にもトップランナーがたくさんいて、刺激を受けてばっかりです。テレビのあり方が時代の変化に追いついていないところは確かにあるけど、他の番組の演出家のアイデアには今もしょっちゅう感服しているし、歴戦の先輩テレビマンの制作力やタレントのスター性を目の当たりにすると、もっと頑張ろうと思います。テレビ業界の外の友人と接すると、自分より10歳以上若い女性クリエイターが遠慮なくダメ出ししてくれたり、斬新なアドバイスをくれたり……特に広告業界は世代交代がとてもスムーズに進んでいることを実感します。

対極な世界を知ること
三宅 今のお話を聞いていて、その開けた感じが『プレバト!!』の番組そのものだなと思いました。
人間関係にせよ、読書から得られる「ノイズ」にせよ、常にオープンでいることが、面白いコンテンツを作る一つのコツなのかもしれませんね。
水野 実際、ハン・ガンさんの『少年が来る』も最初、何を言っているのかわからなかったり……という経験もしています(笑)
三宅 あれは、ほとんど詩のようなものですからね。
水野 そうですよね。その言葉の奥を自分で解釈していく必要があって、何十年もわかりやすさ至上主義でやってきているテレビではできないことだなと。
三宅 『菜食主義者』なんて、ある意味テレビの対極だな、と思ったり(笑)
水野 確かにそうですね。でも、やっぱりそういう世界の捉え方もすごく重要だと思いますし、それが映像を作るときの糧の一つになっている感覚がありますね。

(構成:谷頭和希 撮影:内藤サトル)
プロフィール

みやけ かほ
文芸評論家。1994年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。累計発行部数30万部(電子版含む)突破のベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)が、新書ノンフィクションベストセラーランキング1位(日販・トーハン・オリコン)を獲得したほか、「新書大賞2025」「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞」「ビジネス書グランプリ2025リベラルアーツ部門賞」を受賞した。そのほかの著作に『「好き」を言語化する技術』『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。
みずの まさゆき プロデューサー・演出家。愛知県春日井市出身。慶應義塾大学商学部卒業後2000年に毎日放送入社。現在は「プレバト!!」の総合演出を担当。「林先生の初耳学」「教えてもらう前と後」の企画、演出、プロデューサーとして現在のゴールデン・プライム帯における毎日放送制作の全番組を手がける。


 三宅香帆×水野雅之
三宅香帆×水野雅之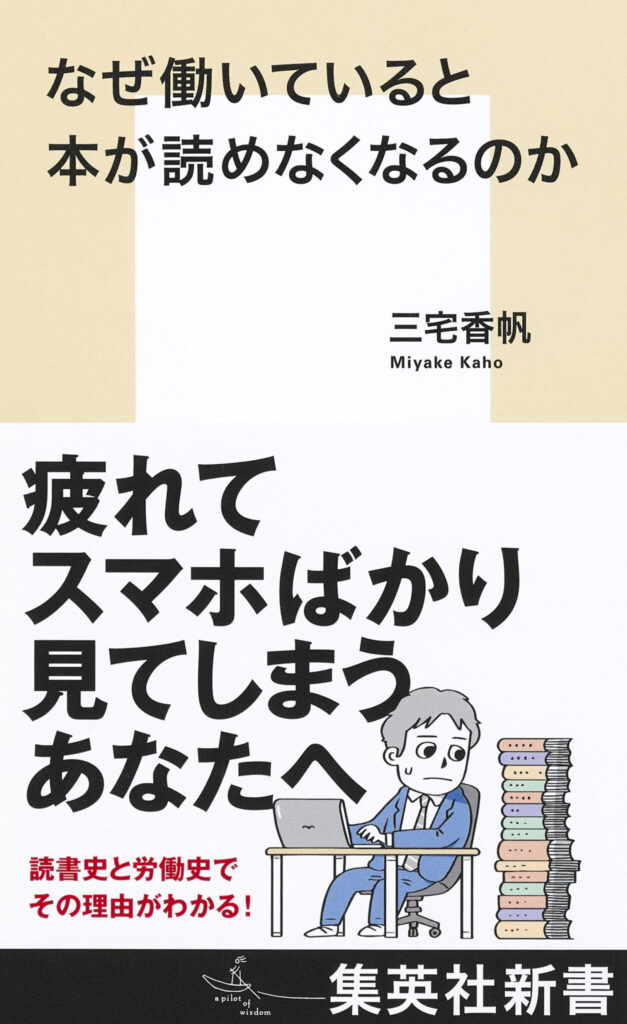










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


