既存メディアは危機的状況で、ウォッシングすらできなくなる?
西村 スポーツメディア批判ということで言えば、堂場さんのスポーツ小説では、登場人物たちがスポーツ中継や報道を「薄っぺらで表面的だ」と批判することが多いじゃないですか。あれはどこまで堂場さん自身の考えが反映されているんですか。
堂場 ほぼ100パーセントです。でも、その反面では、取材される側が「取材をするプロフェッショナルがいる」という事実を理解してないのではないか、と感じることもあります。熱心に勉強して、いろんな選手や関係者の話を聞いてきたプロフェッショナルの取材者よりも、競技の経験者や身内のほうが自分たちのことをよく理解してくれる、と思い込んでいる選手たちもいるように思います。
一方では取材する側にも、プロフェッショナルどころか、仕事でいやいや取材している、というような態度の人もいる。そんなふうに、取材する側とされる側の双方にリスペクトがない状況だから、マスコミ不信がさらに深まって、不健康な関係にさらに拍車がかかるのでしょうね。
取材する側とされる側の関係については面白いエピソードがあって、スピードスケートで清水宏保さんのライバルだったジェレミー・ウォザースプーンという選手がいて、そのウォザースプーンが長野オリンピックで清水さんに負けたんです。そのときに、日本人ではないある記者から「どうしたんだい?」という質問が出た。するとウォザースプーンがひとこと、「疲れちゃったんだよ」と答えたんです。とても納得のいく言葉で、ああいう自然な取材をなぜ日本の人たちはできないんだろう、と思いました。
西村 そういう質問を投げかけて答えてもらえる信頼関係を、いかに選手と取材者の間に構築するか、ということなんでしょうね。
堂場 一方では、一発勝負の取材もあって、特に大きな大会ではミックスゾーンで知らない選手にひと言しか聞く時間がない、という状況もあるじゃないですか。
だから、取材にはふた通りあって、普段からしっかり付き合って「いつでも1時間のインタビューをできますよ」と信頼関係を構築する場合と、一発勝負で短い時間に1回しか聞けない場合、このふたつをうまく使いわけるのが実は結構難しい。あとは、その取材の報じかたという部分で言えば、「こういう報道のしかたはちょっとどうなんだろう」という違和感をテレビに対しておぼえることはやはり多いですね。
本当に怖いのは、自分たちがスポーツウォッシングをしている自覚がメディアにないことなんですよ。もしも自覚があってやっているのなら、もっと怖いですけれども。でも、現実はおそらくそういう露骨なことでもなくて、なんとなく阿吽の呼吸のように、いろんなものごとが進んでいるのだろうと思います。
西村 関わっている人たちが、自分たちがそういう行為に加担していることに気がつかないままウォッシング行為に関わっている、という状況ですね。そういう状況を、ある競技団体の人が「うっかりウォッシング」という表現で関係者に注意を促していました。

堂場 だからこそ、若い記者の人たちにがんばってほしいんです。何も気づかないままでいると、ウォッシングの波に飲み込まれて社会人生活の40年間が終わってしまうよ、若いんだから柔軟に勉強しようよ、と思います。
西村 とはいえ、そういう所へ踏み込んでいかない方が、処世術的には安泰だろうし、業界としても安全なのかもしれないですね。
堂場 でも、旧来のメディアはもはや経営的にも危機的な状態で、そんなことをやっていたらどんどん先細りになっていく一方で、もう持たないんです。影響力が小さくなりすぎて、もはやウォッシュしてもらいたい相手ではなくなっていく。スポーツ新聞なんて、部数は激減しています。テレビだって今まで以上に、生中継はもう見てもらえない状況になっています。では次に何を使ってウォッシングするのかというと、ネットになるわけです。
西村 『独走』にしても『オリンピックを殺す日』にしても、その視点と要素はたしかに入っていますね。既存メディアはこれからどうするのか、今のままじゃもうダメだ、という状況のなかでネット企業が出てきて、それがオリンピックに対抗するメガスポーツイベントを企画し主催して、しかも自分たちのネットワークでイベントを中継する社会。
堂場 アテネオリンピックの頃から、ネットをどう利用するかという議論が活発化して試行錯誤したようですが、我々が想像していたほどの積極的な活用は現在もされていませんね。依然として、テレビと巨額の放映権料が中心になって物事が動いていく。あれは本当に不思議な話で、ネットの方がいろんなことをできる可能性があるはずなのに、せいぜい利用したとしても見逃し配信程度。ひょっとしたら何かウラがあるのかな、と想像しちゃいますよね。
プロフィール

西村章(にしむら あきら)
1964年生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。2010年、第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞。2011年、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。著書に『MotoGP最速ライダーの肖像』(集英社新書)『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』『MotoGPでメシを喰う』(三栄)など。
堂場瞬一(どうば しゅんいち)
1963年、茨城県生まれ。新聞社勤務のかたわら小説を執筆し、2000年、『8年』にて第13回小説すばる新人賞を受賞。主に警察小説とスポーツ小説というふたつのフィールドで活躍し、警察小説では「刑事・鳴沢了」シリーズや「警視庁失踪課・高城賢吾」シリーズ、「警視庁追跡捜査係」シリーズがある。スポーツ小説は箱根駅伝を扱った『チーム』、高校野球を題材にした『大延長』、ラグビー『二度目のノーサイド』、プロレス『マスク』、フリークライミング『天空の祝宴』など。他にも多くの作品がある。


 西村章×堂場瞬一
西村章×堂場瞬一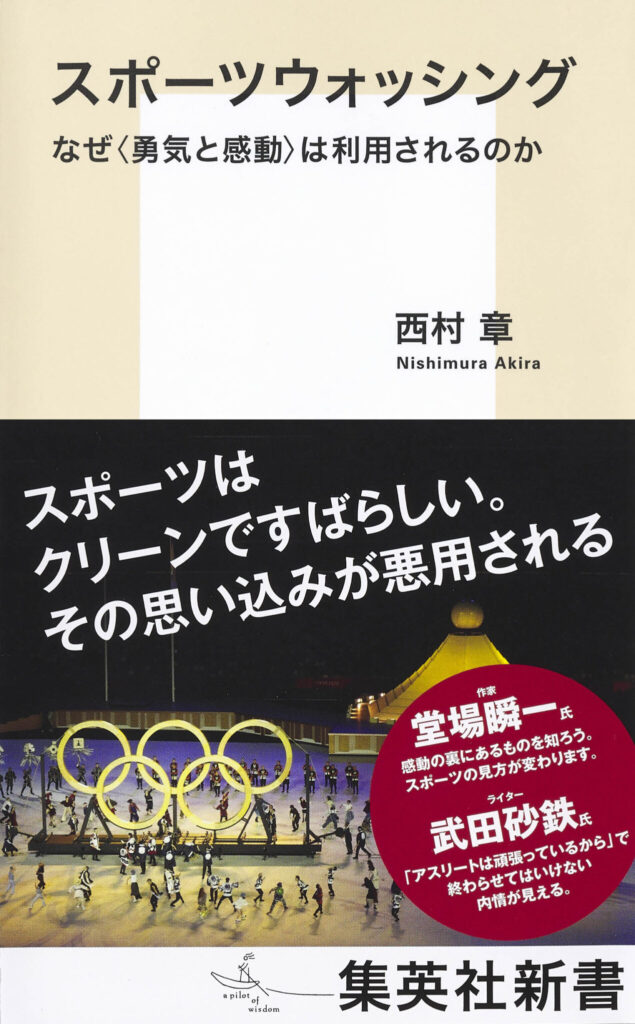










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

