あと数年でスポーツを題材にした小説を書かなくなるかも
西村 オリンピックは今のままの状態だともう立ち行かなくなるであろうことは、なんとなく皆が想像していると思うんですが、「でも、あんなに巨大なイベントがそう簡単に潰れたりはしないでしょう?」という、何となくの信頼のようなものも、やはり根強いように見えます。
堂場 オリンピックは絶対にあるもの、4年に1回必ずやってくるものだと思っている。でも、冷静に考えたら、今もどんどん拡大する一方のこんなやり方を続けていると、絶対に持つわけがないんです。拡大するということは、それだけお金かかるということですから。開催地として手を上げる都市がほとんどなくて、お金を出す人もどんどんいなくなっていて、本当にもうあとがないくらいの状態だけど、このままの状態でやっていても何とかなる、と皆がなんとなく思っている。
西村 オリンピックをやる側はそれがビジネスだから、今のやり方を何としても維持したいと考えるのでしょうが、そこに参加する側が、「あ、私たちはひょっとしたら猿廻しの猿のように利用されているのかもしれない」と気づいたときが、本格的にヤバくなるときなんでしょうね。
堂場 選手たちがそこを疑問に思わないのは、すごく不思議なんですよ。利用されているという感覚は無いんですか、と本当に訊ねてみたい。とくに若い選手たちに。
西村 彼らにとってオリンピックはもはや至上の大会では必ずしもなくて、若いアスリートたちがもっと重要だと位置づけているものは、きっと他にいくらでもあるんじゃないか、と思います。もちろんオリンピックの歴史と伝統に裏打ちされた価値は理解したうえで、でも他にも価値が高いものがある、という視野が広い柔軟な考え方は、若い世代になればなるほど浸透しつつあるのではないでしょうか。
堂場 そこに若干の救いというか、オリンピック偏重主義から抜け出す可能性があるのかなと思いますね。なんかおかしいなあ、と思うことは本当にいっぱいあって、「スポーツウォッシング」と言語化されることで納得したものもあるけれども、他にも割り切れないことはたくさんあるわけです。それをうまく小説で言語化して問題提起したいと思っているんですが、「スポーツはもういいや」という気持ちも、正直なところあるんですよ。あと数年で自分はスポーツを題材にした小説を書かなくなるんじゃないか、という気もします。

西村 え、そうなんですか。
堂場 だって、明るく楽しく書けないじゃないですか。
西村 創作のモチベーションをもはや持ち得ない、ということですか?
堂場 以前は私の中にも「オリンピックは世界最高峰の国際大会だ」という意識があったけれども、オリンピックがこういう体たらくになってしまうと、もう夢も希望もない。だから、あと数年でひょっとしたらこのジャンルからは手を引くかもしれないです。
西村 『チームⅢ』の文庫版あとがきでは、東京オリンピックに合わせて作品を次々と刊行する〈DOBA2020〉プロジェクトを後悔している、とお書きになっていましたね。
堂場 やるべきじゃなかった、ああいうものに乗っかるべきじゃなかった、と非常に反省しているんです。
西村 『オリンピックを殺す日』には、堂場さんのスポーツ小説の名キャラクター、藤原雄大や山城悟、浦大地、といった個性の際立った人物が何人か出てきますね。あれは最初、読者サービスの一環だと思っていたんですが、『チームⅢ』の文庫版あとがきを読んだときに「こうやっていろんな登場人物を出すことで、堂場さんが今まで書いてきたスポーツ小説のありかたを総括しようとしているのかな、何かに決着をつけようとしているのかな」とも感じました。
堂場 「おれはオリンピックのようなものに便乗してしまった」「スポーツに対する向き合い方を間違えていた」と反省して書いたのが、あの作品なんです。それこそ本当に、カタをつけるというか、決着をつけようという気持ちは確かにありました。そう考えて作品を書いていくと、今まで出てきた個性が強めのキャラクターたちに助けてもらわないと、ただの救いがない話になっちゃうんです(笑)。
あの小説を書いた時点では、自分はオリンピックをこれからどう見ていけばいいのだろうということがわからなくなりかけていて、その自分の気持ちに折り合いをつけて総括してやろうという気持ちで書きあげました。要するに、オリンピックは一人の作家のスポーツに対する純粋なマインドを歪めてしまった、ということですよ(笑)。
西村 僕らが子供の頃から見てきた、例えばスポ根漫画やドラマの中では、オリンピックはいつも究極の目標であったわけです。でも、これからの小説や映画の世界では、オリンピックはもはや憧れの対象にはなりえないし、そういう舞台としても機能しないということですね。
堂場 きっと後ろで金勘定をしているんだろうな、と想像しちゃうんですよ。スポーツはものすごい大金が動く世界だけど、でも、できればスポーツとお金はあまり関わり合ってほしくないという気持ちは、今でもやはり自分の中にあるんです。ただ純粋に名誉と夢のためだけに戦う、我々からしたら本当に憧れの世界があってもいいじゃないかと思う反面、でも「たぶん本当は違うんだろうな……」ということも今では多くの人が見抜いていますよ。
西村 ノワールのようなスタイルでオリンピックを描いても、それはそれで面白そうな気もしますけれども、そこには夢も希望もないわけだから、スポーツ小説として成り立たないだろう(笑)、という。

堂場 これからフィクションの形でオリンピックを描くとしても、そもそも誰も東京オリンピックを総括していないじゃないですか。あれは一体なんだったんだ、ということがうやむやになったままだから、このままだときっとまた何か起きますよ。
西村 それが今また形を変えて現在進行形になっているのが、大阪の万博ですよね。
堂場 なんだか同じ臭いがしますよね。オリンピックも万博も同じ臭いがするのは一体何なんでしょうね。万博で何かのウォッシングをしようとしたのかな。大阪府民や市民の気持ちを万博に向けようとしたのかもしれませんが、どうなんでしょうか。開催費用が膨らむばかりですしね。
スポーツの世界に話を戻すと、国家に依拠しないクラブ単位で世界一を競うありかたという意味では、サッカーのクラブワールドカップが一番正しい形じゃないかと思うんです。ただ、個人競技の場合だとなかなかそうもいかない。『オリンピックを殺す日』でも、個人競技の扱いをどうすればいいかということが難しくて、国を背負わないで世界的な大会に参加するなら、経費は全部自腹になってしまうのかな、という問題にも直面しました。でも、そういうものとそろそろ真剣に向き合って考えてもいいと思うんだけど、誰も何も言わない。なんでだろう。今の状態を普通だと思っているということなんですかね。
西村 自分が強くなりたい、高みを目指したいという願望を優先するのか、それとも周りの環境や自分を取り巻く人々のことを考えて調和を優先するのか。現実のスポーツの世界でも必ず出てくる課題ですが、例えば堂場さんの『チーム』サーガで言えば、山城悟と浦大地の違いは、まさにそういうところですね。
堂場 現実には、誰も山城のような行動はできないんです。でも、浦のようなキャラクターは、日本のスポーツ界の制度に順応して、選手育成や監督に向いているんですね。日本のスポーツ界を取り巻く問題は、この『スポーツウォッシング』で言語化されていて、それを読むことで私自身はかなりすっきりしたんですが、逆に問題が明確化されたことでかえって「ああ、どうしたらいいんだ……」といろいろ考えてモヤモヤしてしまい、まだまだ何か書けそうだけれどももう書きたくない、みたいな気持ちになってすごく困っています(笑)。
西村 パンドラの筺を開けちゃいましたかね。
堂場 だから、この「スポーツウォッシング」という言葉がもっと認知されるようになってほしいですね。いまみんなが当たり前のように見て体験していることに、「それって本当に正常だと思いますか?」って問いかけたい。東京オリンピックはそのいいチャンスだったにもかかわらず、誰も立ちどまって考えようとしませんでした。このままでいいのだろうか、本当に大丈夫なのだろうか、と思います。
西村 しかも、次のオリンピックはパリだから、日本人にはまったくの他人ごとになっているのが現状ですね。
堂場 皆でちょっと立ち止まって考えてみることが、きっと今は必要なんです。「オリンピックに出たくない」とかいう選手がいたりすると、そのいいきっかけにもなって面白いと思うんですが。
西村 堂場さんの作品には出てきますね。
堂場 現実にはそんな選手はなかなかいないのかも。
西村 自分が誰よりも速いことを証明したい、強いヤツと最高の舞台で競いあいたい、という純粋なモチベーションを実現できる舞台が、『オリンピックを殺す日』の〈ザ・ゲーム〉や『独走』の〈UG(The Ultimate Game)〉ですが、それが現実の世界で実現すれば、観戦する側ももっと競技を楽しめるでしょうね。
堂場 ただ、それをどう伝えるか、ということも大きな課題です。メディア的なヒーローを演出するだけの英雄譚にしてしまっていいのか、という問題もありますから。
今のスポーツを取り巻く環境は俯瞰した視点から見るとけっして良い状況とはいえないと思います。現在のような状態がいつまでも続くわけがない。ではこれからどうすればいいのか。10年後20年後を視野に入れて、我々はスポーツとどう関わっていくべきなのか。そういったことを考えると、やはりまずは「スポーツウォッシング」という言葉をもっと広く認知してもらうところから始めていきたい。……というような締めくくりでどうでしょうか。
西村 綺麗に締まりましたね。
堂場 どうしても綺麗に締めたくなるのが、私の悪癖なんです(笑)。
撮影/五十嵐和博
プロフィール

西村章(にしむら あきら)
1964年生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。2010年、第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞。2011年、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。著書に『MotoGP最速ライダーの肖像』(集英社新書)『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』『MotoGPでメシを喰う』(三栄)など。
堂場瞬一(どうば しゅんいち)
1963年、茨城県生まれ。新聞社勤務のかたわら小説を執筆し、2000年、『8年』にて第13回小説すばる新人賞を受賞。主に警察小説とスポーツ小説というふたつのフィールドで活躍し、警察小説では「刑事・鳴沢了」シリーズや「警視庁失踪課・高城賢吾」シリーズ、「警視庁追跡捜査係」シリーズがある。スポーツ小説は箱根駅伝を扱った『チーム』、高校野球を題材にした『大延長』、ラグビー『二度目のノーサイド』、プロレス『マスク』、フリークライミング『天空の祝宴』など。他にも多くの作品がある。


 西村章×堂場瞬一
西村章×堂場瞬一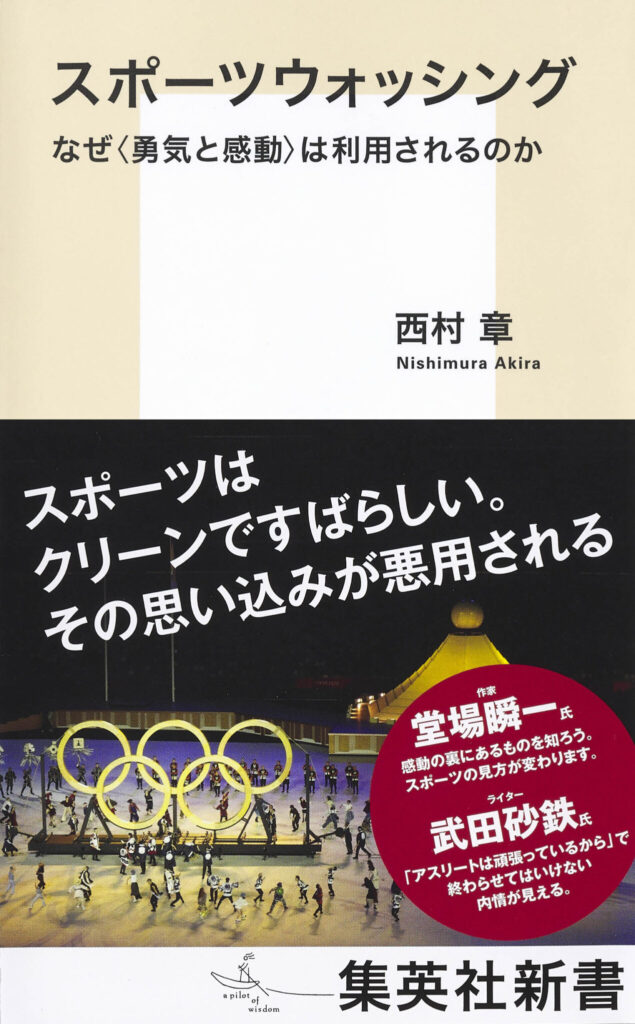










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


