東京オリンピック2020が様々な混乱の中、開幕した。体操の内村航平や競泳の瀬戸大也が予選落ち、重量挙げの三宅宏実が引退など、初日から日本選手に波乱が起きているが、そんな中、25日からある注目の戦いが始まる。水球日本男子“ポセイドンジャパン”だ。なぜ彼らが注目なのか? その理由をスポーツライターの小林信也氏が短期集中で解説していく。

水球日本男子代表、通称ポセイドンジャパンの選手・監督・コーチたち。右端が監督の大本洋嗣氏
東京オリンピックで私が最も楽しみにしている競技は「水球」だ。
メダルが獲れそうなのか? と訊かれたら、「獲れる可能性は『ない』とは言わないが、確率は低い」。それでも水球男子日本代表が楽しみなのだ。なぜなら、日本代表が世界の水球を変えている。世界に衝撃を与える彼らの試合を、オリンピックの機会に多くの日本人たちに目撃し、その魅力に触れてほしいからだ。
水球男子日本代表の魅力を、日本人はまだ知らない、世界は知っている、そう表現してもいいだろう。
いま水球男子日本代表は、世界の水球に衝撃を与え、東京大会で「台風の目」と警戒されている。つい数年前まで、日本はノーマークの存在。世界の強豪国にとって日本は、控えメンバーを先発させても負ける心配のない相手だった。ところが、いまは違う。金メダル候補の各国も、日本に足下をすくわれる可能性を案じ、戦々恐々としている。
最大の要因は、「パスライン・ディフェンス」と呼ばれる独自の戦術にある。
水球の試合では、相手が攻めてきたら自軍のゴール前に壁を作って守るゾーン・ディフェンスやマンツーマン・ディフェンスが主流だ。ハンドボールにも似たゴール前の光景を思い浮かべることのできる人も多いだろう。攻撃側はパスを回しながらチャンスを窺い、隙を突いてシュートを放つ。ところが、日本はこうした光景を「できるだけ作らない」ことに活路を見出した。
「高さでは絶対世界に叶わないので、高さで勝負しない道を選んだのです」

パスライン・ディフェンスという超攻撃型戦術で、体格に劣る部分を補い、世界トップに迫りつつある日本チーム
2012年から日本代表を率いる大本洋嗣監督が言う。就任要請を受けたのは、ロンドン五輪予選に惜敗した後だった。当時、日本代表は歴代最強と呼ばれ、1984年ロス大会以来の五輪出場の悲願を達成するだろうと水球ファンは胸をふくらませていた。ヨーロッパのプロリーグで活躍する青柳勧を中心に、長沼敦、塩田義法、竹井昂司ら実績のあるベテラン選手が揃うチームは、前年の世界選手権でも過去最高の11位に入るなど手応えも十分だった。しかも最終予選は日本での開催。ところが、悲願を前に日本は中国とカザフスタンに敗れ、オリンピック出場はまた遠い幻となった。
「これだけのメンバーがいて、有利なはずの自国で開催しても勝てないのか……。私はすごくショックを覚えました」
その時の心境を大本は後に自著の中でこう書いている。
『悔しかったのか悲しかったのかはわからないが涙が出た。』

水球日本男子代表チームの監督、大本洋嗣氏。2001年に一度目の代表監督就任。2012年に再び監督となり、2016年のリオでは32年ぶりのオリンピック出場を果たした
世界がいっそう遥か彼方に遠ざかっていく、そんな実感が大本を深い谷底に突き落としたのだろう。その直後、監督の要請を受けた。監督の仕事は言うまでなくチームを勝たせること。だが、その時の大本には、日本を世界で勝たせる道がほとんど描けていなかった。いや、大本だけではない。日本の水球関係者のほとんどが、そして選手たちも世界に肩を並べる糸口さえ見えていなかった。
そんな状況で、大本の脳裏に浮かんだのが「パスライン・ディフェンス」という戦法だった。従来のマンツーマン・ディフェンスではなく、ボールを奪ったらすぐ速攻に転じることができる守備体形。日本でも一部の高校などで採用されていた。
(背の高いヨーロッパのチームがゴール前で壁を作る前に、速攻で相手のゴールにシュートを打つ!)
そうすれば、高さと真っ向勝負せず、新たな活路が見出せる。そう考えた大本は、パスライン・ディフェンスを日本の生きる道に選んだのだ。当初は選手たちから猛反発を食らった。オーソドックスな戦法ではなかったからだ。試合の中で悪いリズムを変えるため、一時的に採用するのは有効だと理解できるが、これをメインに据えるなど、選手たちにも到底納得できなかった。ところが、大本は大真面目に、これを日本代表のスタイルにすると宣言した。つまり、一時的な策でなく、1試合を通じて、「パスライン・ディフェンスで戦う、それが日本の生きる道だ」と宣言したのだ。
下手をすれば、監督と選手の間に大きな溝ができてしまいかねない状況があった。けれど、大本は溝を深くさせなかった。そこが、大本監督の器、リーダーとしての才覚と言っていいだろう。
古いタイプの日本の指導者なら、「黙ってオレの言うとおりやれ!」と選手に強いるだろう。だが、大本は違った。
「パスライン・ディフェンスがいいと思うけど、オレだってどうしていいのか、わからない。お前たちが試行錯誤して、世界に勝てるパスライン・ディフェンスを作り上げてくれ!」
選手に半ば丸投げしてしまったのだ。ベテランの域に入っていたゴールキーパーの棚村克行は、そのいい加減さに半ば呆れながら、積極的にパスライン・ディフェンスの完成に熱を入れ始めた。何しろ、ゴールキーパーがこの戦法の生命線と言っていい。自分に半分、「勝負のカギを預けてくれた」という戦法だから、燃えないわけにいかない。

ゴールキーパーを務める棚村克行選手。パスライン・ディフェンスの生命線となる選手だ
筑波大出身の棚村は、水球を深く考え、知的に、論理的に攻守を分析するのが誰よりも好きな選手だ。その棚村に、パスライン・ディフェンスという投げかけは、この上ない挑戦課題、噛んでも噛んでも味の出るスルメのようなテーマだった。
さらに、主将を務める攻撃の要・志水祐介、守りの中心となる志賀光明らも、半信半疑ながら、他に世界に勝つ方法が見つからないのだから「やってみるか」と開き直り、前途の見えない船出が始まったのだ。

主将の志水祐介選手

守りの中心、志賀光明選手
パスライン・ディフェンスとはどんな戦術なのか。大本監督に簡単に説明を求めると、「守るのをやめるようなもの」と、笑いながら言った。
「相手が攻めてきたら、何としてもこれを抑えようとするのでなく、ボールを奪い取ることを想定して、先に攻める体制を整えておく」
もう少し説明しよう。相手がボールを持って攻めてきたら、普通はゴールを背にして両手を広げ、相手の攻撃をガードする。全員がそうすることで、結果的にゴール前に壁ができる。ところが、日本はそのスタイルを捨てた。相手が攻めてきたら、相手より前に出る。ゴールを守るのはゴールキーパーひとりだけ、といった状況になるが、取られたら仕方がない。もしキーパーが止めてくれたら儲けもの。その時はすぐ速攻に転じ、素早くボールを展開してシュートを決める。それが「超攻撃型」と呼ばれるパスライン・ディフェンスの狙いだ。つまり、ボールを奪えたら、その時点で日本選手は相手より前(相手ゴールに近いポジション)にいる。相手がゴール前に壁を作る前にシュートを打てれば、高さに負ける心配がない。
守らないというのは少し言い過ぎた。相手より前に出て、相手が回るパスのラインを抑える。パスをカットする守り、という意味でパスライン・ディフェンスと名がついているのだ。しかし本当の狙いはパスをカットすることでなく、速攻に備えた態勢づくりにある。
「最初からうまく行ったわけではありません」
監督も選手も口をそろえる。だが徐々に、ごくまれにだが、強豪相手に接戦を展開、あわよくば勝てるという試合ができ始めた。すると、選手たちに自信が芽生え、「パスライン・ディフェンスを完成させたら、オレたちも世界の強豪を互角以上に戦えるんじゃないか」、そんな雰囲気がチーム内に高まり始めた。
そして2018年、ハンガリーのブタペストで開催されたFINA(国際水泳連盟)ワールドリーグ・スーパーファイナル2018で日本はグループリーグを勝ち上がり、準々決勝でアメリカを11対10で破る大金星をあげ、準決勝ではハンガリーに11対9で惜敗。3位決定戦でもスペインに12対7で敗れたものの4位に食い込んだ。
選手たちが改良を加え、独自のスタイルに作り上げた日本代表のパスライン・ディフェンスが世界に通用することを自他ともに確信した。
それから3年、さらに進化を加えたパスライン・ディフェンスを引っ提げて、日本代表はオリンピックの舞台に立つ。
東京オリンピックの出場チームは計12チーム。AB2組に分かれてグループリーグを戦い、各組上位4チームが決勝トーナメントに進む。日本はグループA、25日から1日おきに計5試合。まず25日にアメリカ、27日ハンガリー、29日ギリシャ、31日イタリア、8月2日に南アフリカと対戦する。勝ちあがるには最低2勝が必要。3勝すれば間違いない。
「最低でも2勝、あわよくば3勝」を固く誓って、日本はグループリーグに挑む。野望を果たせれば、2019W杯ラグビーでさくらジャパン(ラグビー日本代表)が巻き起こした興奮と歓喜を、水泳男子日本代表(ポセイドンジャパン)が再現できる。そしてもうひとつ、準々決勝に勝利すれば、夢のまた夢と多くの人が遠くに見つめていた「メダル獲得」が現実のものとなる。
(つづく)

取材・文/小林信也 写真/大杉隼平 図版/海野智
プロフィール

小林信也(こばやし のぶや)
1956年、新潟県生まれ。Number編集部を経て、スポーツライターとして独立。テレビのコメンテーターとしても活躍。『野球の真髄』(集英社新書・2016年) 『生きて還る 完全試合投手となった特攻帰還兵 武智文雄』(集英社インター・2017年)


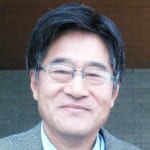 小林信也
小林信也









 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


