9・22書泉グランデのターザン山本戦
2023年9月22日——。
神田神保町の書泉グランデで、ボクとターザン山本との対談がマッチメイクされた。
かつて『週刊プロレス』で黄金時代を築いた名物編集長は現在77歳の老齢だ。
1996年にプロレス業界の軋轢から出版社を石もて追われ、フリー転身後にはケセラセラのデタラメ人生を歩む。
ボク達と一緒に芸人活動をしていたこともあるが、歳を重ねるごとに零落し、週末の競馬に耽溺、日々の物乞い生活を「タカリ道」と公言し、唯一の取り柄の筆先も湿りがち、周囲の顰蹙を買いながらも、まだ生き延びているのだ。
この日のターザンは、入れ歯の具合のせいか、滑舌が悪く聞き取りにくいが、往年の咆哮スタイルで2時間を語り切った。
「博士はたけしさんと猪木さんが2大神じゃないですかァ、このひと、自分の神に何か色々なことがあるとドーーンと落ちるんですよォ。でも博士の鬱は最初フェイクだと思っていましたよォオ!! でも、あれホンモノの鬱だったね!!」とボクを指差しニヤリと嘲笑する。
デリカシーが無い事、この上ないスタートだった。
そして、この日のために書き上げた、直筆の殴り書き『猪木論』の原稿200枚をテーブルに叩きつけて、
「もう“書く書く詐欺”とは言わせませんよォオ!! 飲まず食わずで5日間で書き上げましたよォオオ!!」と、どや顔で獅子吼した。
そして、後半、ホワイトボードにマジックで線をおもむろに5本引き出すと、概ねこのような話をする。
「猪木の時間軸、そこには5人のキーパーソンがいるんですよォ。第一の時間軸は終生の最大の敵・ジャイアント馬場、ふたりは表で闘い続けます。でもその裏でも時間軸が流れているんですよォ。2人目が直木賞作家の村松友視、3人目は古舘伊知郎、4人目は『週刊ファイト』の井上義啓編集長、そして最後の5人目、いよいよ真打ち登場!私、『週刊プロレス』編集長のターザン山本ですよォオオ! 馬場が先に亡くなり、今度は自分の体力が衰えていくなか、猪木ブランドの延命策は、この活字プロレスの4人が支えていたわけですよォオオオ!!」
まるで壊れた講談師のようなノンストップの語り口を決めると、自画自賛のご満悦な表情を浮かべた。そして最後にこう言い残した。
「博士ェ!! こんなボクでも人生にはネクストがあるんですよォオオオ!! それが猪木イズムです。『行けばわかるさ!』は人生のネクストにチャレンジすることなんですよォオオ!!」
部下に妻を寝取られての離婚、業界追放、失職、ローンが払えず自宅の売却、人生で何度も底を打ちながらも、このプロレスゾンビは、身に降りかかるあらゆる不幸を「どうってことねぇですよ!!」と猪木イズムで己を駆り立て、何度でも窮地から蘇る。
そして恥ずかしげもなく老醜を晒し切る姿を目の当たりにすると、ボクはこのライブで俄然、元気が沸いてきた。やはり「元気があればなんでも出来る」のだ。
この日の模様は、ボクのYouTube『博士の異常な対談』に残している。
かつてはプロレス論壇を席巻した稀代のアジテーター・ターザン山本の見納め、最後の遺言だと思って読者には是非見ていただきたい。
(因みに、あの200枚の原稿を引き受ける出版社はいまだに決まっていない)

10・28 LOFT9の松原隆一郎&吉田豪戦
そして出版記念対談の第二戦が組まれた——。
10・28、渋谷のLOFT9だ。
ボクの対戦相手は吉田豪、そして松原隆一郎。
この三者の鼎談は初めてであり、猪木語りの座組としては新鮮な顔合わせだった。
試合に先駆けて、ボクは出演者にふたつの事前準備をお願いした。
ちょうど、10月6日に公開された、映画『アントニオ猪木をさがして』は賛否両論、議論百出、ファンの間で大きな話題になっていた。
ライブの前々日には、髙田延彦が辛口の批評をXにポストして業界内もザワついていた。
そして、出版界でも一周忌に合わせて、この時期に2冊の猪木追悼本が上梓された。
木村光一『格闘家 アントニオ猪木』(金風舎)、プチ鹿島『教養としてのアントニオ猪木』(双葉社)である。
多忙な二人が共にボクの意図を認めて、前日に映画を鑑賞、2冊の本を読了直後で本番当日を迎えた。
冒頭、ボクの方から3人の関係性を語った。
松原隆一郎先生は67歳、現在は放送大学の教授だが、もともとウルトラエリートで、灘高から東大、東大教授、東大大学院教授の経歴。一方で文武両道を極め、大道塾五段、講道館三段、東大柔道部の監督も歴任。プロレス語りの文化人のなかでも猛者中の猛者だ。
ボクは20年近く前に一時足繁く通っていた高円寺の格闘技ジム「スネークピット・ジャパン(蛇の穴)」で知遇を得た。当時もアラ50(フィフ)ながら鬼コーチの大江慎が指導するキックのプロ練習に参加し壮絶なスパーリングを繰り返す姿を傍観していた。その後、謦咳に接するようになり、ボクが編集長をつとめていた『メルマ旬報』でも連載を引き受けてくださり、約10年間に『メルマ旬報』発の2冊の単行本を上梓した。
吉田豪は、『紙のプロレス』編集部所属時代から既に30年を超える付き合いであり、ボクのライブ出演復活となる8・18高円寺『パンディット』で開催した「水道橋博士61歳生誕祭」ではマン・ツー・マンの相手役をつとめてくれた。
病み上がりの精神疾患患者の聞き役など、気を遣い、実際には腫れ物に触ることであるのだから、対談相手を引き受けてくれただけでもありがたかった。
吉田豪らしく容赦なくも配慮ある司会進行で3時間を2人で過ごした。
あの日、ボクはまだ本調子ではなかった。しかしテレビ・ラジオのレギュラーを失い自らのオワコンぶりを危機感と共に自覚していたボクが、タレントではなく、芸人として新たなる道を見出した気がした。猪木流に言えば「ジャングルが絶滅の危機なら守るのではなく新たに作れば良い!」のだ。
実際、その後は思案していた転職を諦め、この高円寺のライブハウスを主戦場に、ボクの企画と主催で手打ち興行を仕掛けていくことにした。
映画『福田村事件』で共演した東出昌大さんを迎えた9・26のライブでは、満席の観客の多幸感溢れる笑顔に包まれ、自分の魂が生き返り、自分の天職が何なのか、それは客前のライブこそ芸人が生きていくこと、そのものであるとの実感を得たのだった。
さらに芸人にとって主催興行ライブとは、プロレス興行に似通うことも痛感した。
吉田豪が今や連日の信じがたい試合数(ライブ配信)をこなしながら、東京ライブシーンの主として君臨し続けるのは、モットーの「死ぬまで現状維持」の実践であり、また多岐にわたるエンタメシーンを把握して、その点と点を線に結びつけ、物語化する、いわばプレイヤー兼マッチメーカーのポジションを確立しているからだろう。
そして、近年は「誰の挑戦でも受ける!」姿勢で、「5の力の相手から6を引き出し7の力で倒す」猪木の風車理論のような対話をしながら、本来なら、お門違いの対戦相手との試合を量産していることも、全盛期の猪木のストロングスタイルを彷彿とさせるのだ。
猪木を通った人にとって基本的にライブ=客前とは興行なのだ。

プロフィール

1962年岡山県生れ。ビートたけしに憧れ上京するも、進学した明治大学を4日で中退。弟子入り後、浅草フランス座での地獄の住み込み生活を経て、87年に玉袋筋太郎と漫才コンビ・浅草キッドを結成。90年のテレビ朝日『ザ・テレビ演芸』で10週連続勝ち抜き、92年テレビ東京『浅草橋ヤング洋品店』で人気を博す。幅広い見識と行動力は芸能界にとどまらず、守備範囲はスポーツ界・政界・財界にまで及ぶ。著書に『藝人春秋』(1~3巻、文春文庫)など多数。
水道橋博士の日記はこちら→ https://note.com/suidou_hakase


 水道橋博士
水道橋博士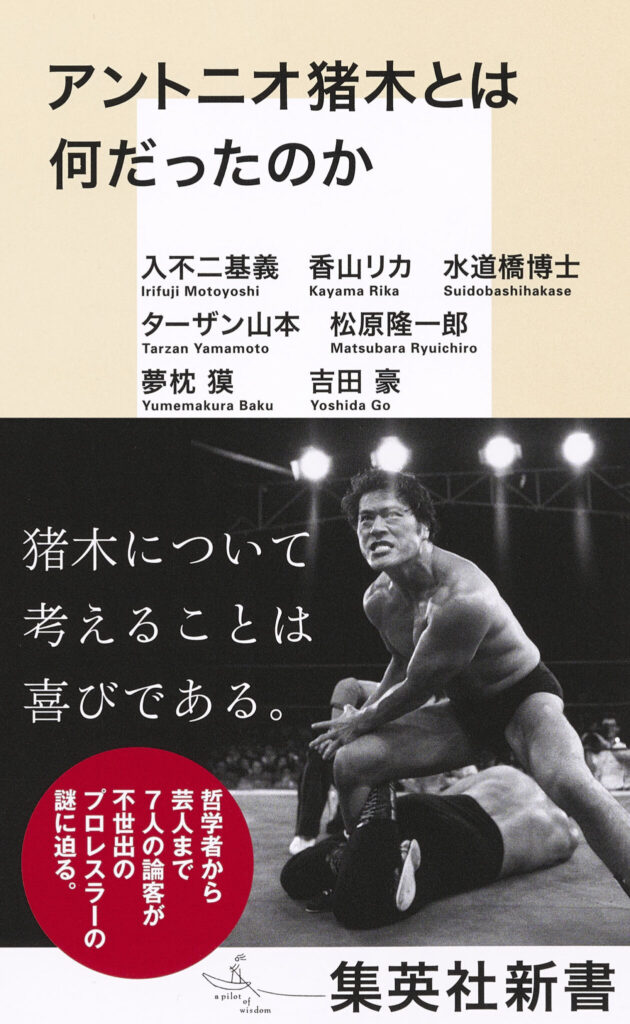










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


