新型コロナウイルスのパンデミック、そしてロシアによるウクライナ侵攻と、近年、セキュリティの強化を強く意識せざるを得ない出来事が続いている。しかし、コロナ禍では感染症対策の名の下で行動制限や営業自粛を余儀なくされるなど、セキュリティの重視は容易に個人の自由を制限する方向に進みがちだ。
5月17日に刊行された集英社新書『自由とセキュリティ』は、6名の政治思想家の名著をアクチュアルな視点で読み解きながら、セキュリティに傾きがちな風潮の中、自由の価値について再考を促す一冊である。
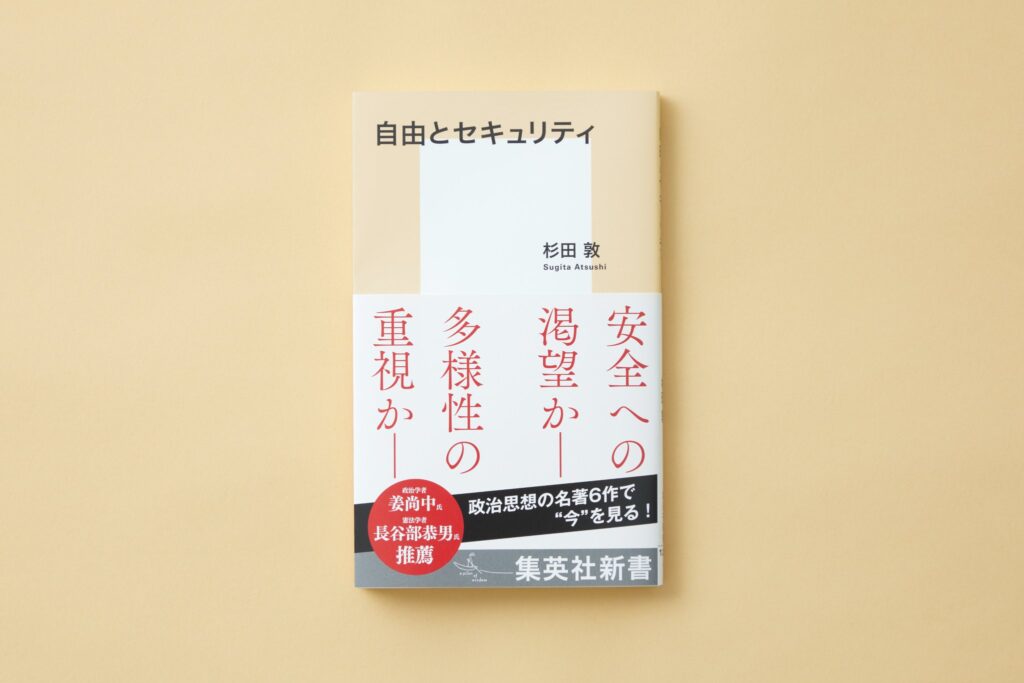
著者の政治学者・杉田敦氏(法政大学教授)と政治思想史を専門とする宇野重規氏(東京大学教授)が、今こそ考えたい「自由とセキュリティ」の関係を語り合った。
セキュリティーをより重視するリベラル
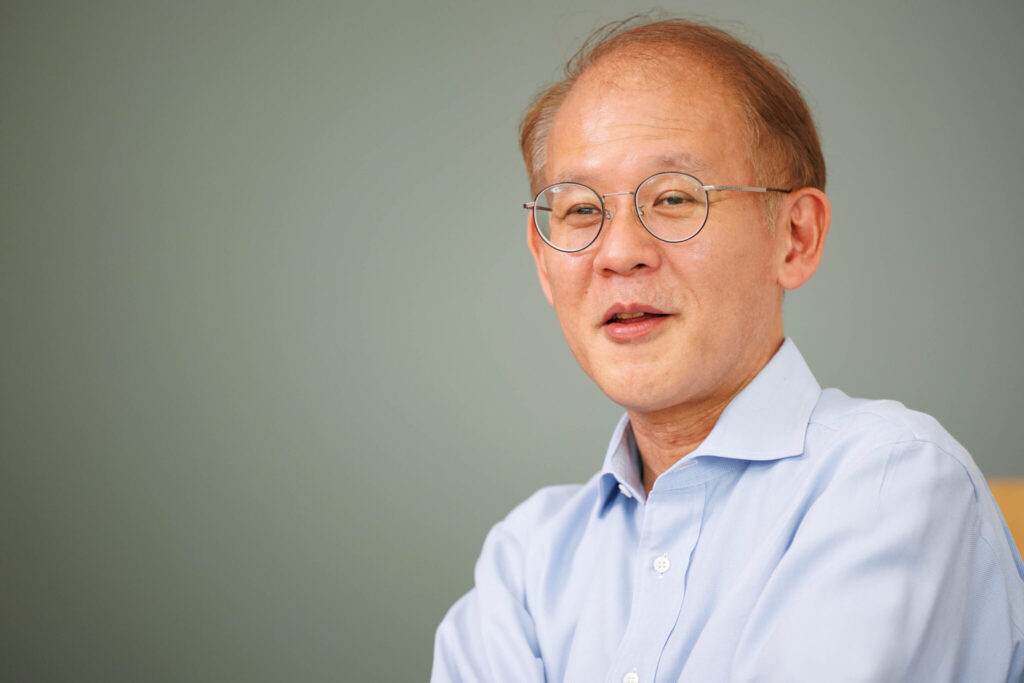
宇野 『自由とセキュリティ』の「プロローグ」には、コロナ禍が執筆のきっかけになったと書かれています。
セキュリティは「安全」とも言い換えられますが、パンデミックの危機において、日本も含めた世界の多くの国で社会の安全を守るために個人の自由が著しく制限されました。
その際、たとえばドイツのメルケル首相(当時) が「移動の自由」の重要性を強調しつつ厳しい行動制限に理解を求めたように、ヨーロッパでは「安全」は「自由」と対比するものとして語られていたと思います。
また、激しい批判は浴びたものの、移動の自由を自由の根本と捉え、それを制限することに対し強硬に異を唱えたイタリアの哲学者、ジョルジオ・アガンベン の議論も非常に注目されました。
杉田 セキュリティの確保は、人々の生活を守るという福祉国家の課題でもあるため、実は自由放任主義的なリベラル右派よりも、社会民主主義的なリベラル左派の側がよりセキュリティを重視する傾向にあります。
新型コロナウイルスが大流行していたとき、トランプ派が反ワクチンだったのに対し、バイデン政権はワクチン接種を推し進めましたし、ドイツでも社会民主主義的な勢力や緑の党のような革新勢力がウクライナ支援を強く支持しています。
宇野 それは重要な論点ですね。アメリカでも、リベラルと見られていたオバマやクリントン政権が、国際的にもかなり強硬なことをやっていたことを思い出します。
しかし、日本ではこうした「自由と安全」についての議論そのものが非常に弱かったと言えるでしょう。
それに加え、日本の場合は国が制限の範囲を明確に定めるというより、ある種の同調圧力が働いて、一見、自発的に協力しているかのようなかたちをとりながら、実質的には相当、個人の自由が制約されました。
このことがはらむ危険性を指摘するよりも、強制力がない中でうまく安全管理ができたと、むしろ評価する声すら挙がっています。このような日本の状況において、「自由とセキュリティ」というテーマで議論を立て直すという本書の試みは大変興味深いですね。
本書を読むと、ヨーロッパの思想史が「自由対セキュリティ」という問題意識で貫かれているということに改めて気付かされます。ミル、ホッブズ、ルソー、バーリン、シュミット、フーコーが取り上げられていますが、なぜこの6人だったのでしょうか。

杉田 セキュリティのために自由を制限するという動きが近年顕在化している背景には、パンデミックや戦争という現象の存在だけではなく、ジョン・ロールズらに代表される最近の政治哲学が往々にして、自由の条件としてのセキュリティの確保に注目してきたことも大きいのではないかと思います。
セキュリティがなければ自由も何もないということは確かにあります。しかし、そういう話だけに集中していくと自由は見失われてしまうのではないか、という違和感を、私は以前から持っていました。
そうした問題意識を持ちながら、コロナ禍で自由が制限されている中、改めて自由について論じている昔の本でも読もうかとミルの『自由論』を手に取ったことが、本書につながっていったということです。
なぜミルだったかというと、自由の内在的価値、つまり自由はそれ自体としての価値があり擁護されなければならないということについて最もわかりやすく述べているのは、やはり『自由論』ですからね。
自由を強調するミルの政治理論に対し、セキュリティを強調した思想家の代表格と言えばホッブズということになります。
現代に至るまで、自由とセキュリティの問題をめぐる議論は、すべてホッブズに発していると言えますし、彼以降の思想家たちの念頭には、ホッブズをどう捉えるかということがあったでしょう。
ルソーについては後で述べますが、バーリンはホッブズとミル、それからルソーを中心に論じていますし、ホッブズの継承者を自認していたであろうシュミット、そしてシュミットを読む中でホッブズ的な文脈を批判しているフーコーの『社会は防衛しなければならない』に至りました。
宇野 ミルは19世紀、ホッブズは17世紀、ルソーは18世紀の人物です。
それぞれの思想家たちを時代順ではなくミルから始まる並びにしたことには、どのような意図があったのでしょう。
杉田 思想史的な流れに沿うというより、自由とセキュリティ、それぞれを強調する思想家たちを時空を超えて「対話」させようとした結果、こういう順番になったということですね。
カントやハンナ・アーレントのような人々を加えても良かったかもしれませんが、この6人の「対話」によって大体のことは論じられたのではないかと考えたのと、政治思想史を今では専門とせず、規範的な政治理論を勉強している私としては、正直、そこで力尽きたということです。
「自由とセキュリティ」は「多元主義と一元主義」
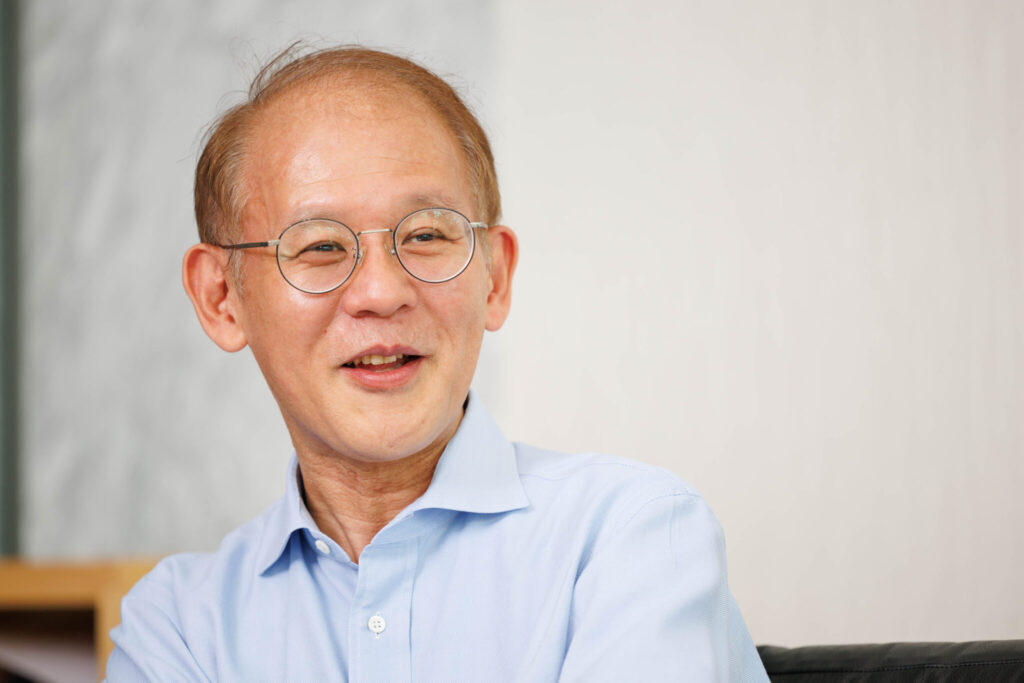
宇野 ホッブズについては、強固なリヴァイアサンを擁護しつつも、実はかなり個人主義的で、ある意味リベラルな論理も内在しているという面白さもありますよね。
それでも、セキュリティ優先の思想家の極北としてのホッブズを強調し、これと戦うという図式をつくるために、ホッブズのリベラルな面にはあえて目をつぶったということでしょうか。
杉田 そのとおりです。
本書では、ひとりの思想家につき原則、一冊の著作を取り上げて「自由とセキュリティ」というテーマを掘り下げています。
もちろん、それぞれの思想家の他の著書を読めば、さらにさまざまな側面が見えてくるわけですが、今回出てくるような古典的な本になると、それ一冊でいわばひとつの小宇宙が成り立っていますから、著者の論理は一応、そこで完結しているという前提で議論を組み立てました。
完結させようとしているけれども実は破綻しているというところには、私なりに「突っ込み」を入れてはいますが。
宇野 その突っ込みのひとつが、真理に到達したら自由は必要でなくなるのではないかという命題についてミルの考えを論じている箇所ですね。
ここは、自由とは何かを考える上で非常に重要な議論だと思います。
杉田 ホッブズについて言えば、彼をもっと自由主義的に解釈する研究もあることは承知しています。
しかし結局のところ、ホッブズは秩序思考であり、非常事態には百家争鳴、多事争論では対応できない、多様性よりも異論がない方がいいという立場の人間です。
自由とセキュリティという本書の対立軸を別の言い方で表すならば、多元主義と一元主義ということになるかもしれません。
ホッブズの「後継者」であるシュミットはもちろん、ルソーの一般意志論にしても、少数派は多数派に合わせることで自由になれるとみなしており、やはりホッブズとのつながりで捉えられると私は考えています。
宇野 なるほど。ミルとホッブズという、多元主義と一元主義をそれぞれ象徴するふたりが最初に出てくることによって、本書の議論のベースが設定されているということですね。
ルソーはホッブズの側だという話も出ましたけれども、多数者の専制を支持する一般意志論の一元主義的なところを見れば、確かにその通りです。
とはいえ、ルソーは人民集会という、それこそ秩序を大混乱に陥れるような政治制度を重視するなど、極めて両義的な存在とも言えますね。
もうひとつ、「社会契約論」の一節や「戦争法原理」を引いて、ルソーがホッブズの戦争状態としての自然状態論を批判していたことを取り上げるなど、戦争論の比重が高いというところも本書のルソー論の特徴です。
杉田 「戦争法原理」の冒頭には、戦争をもたらす惨禍に対するルソーの怒りが表明されていますが、彼の言葉はウクライナやパレスチナの惨状に接する現代の私たちの思いにも通じます。
共同体の防衛のためには死ぬ覚悟をせよと述べる「社会契約論」との整合性は問われるものの、戦争は「物と物との関係」、つまり国家という法人相互の関係であって、人民と人民の対立関係ではないというルソーの議論は、今こそ参照されるべきでしょう。
「自由の伝統がない社会」という難問

宇野 その次のバーリンの章で論じられるのは、「二つの自由概念」です。
ルソー、カント以降強調されてきた積極的自由に一元的な危険性を見たバーリンは、むしろ外的な拘束がないという消極的自由を擁護します。
杉田先生はそうした彼の議論を好意的に捉えつつ、バーリンが消極的自由の定義を途中で変えている点に注目していますね。
杉田 バーリンについては、宇野さんに質問したいことがあるんです。
バーリンは、自由な社会とは自由な伝統がある社会である以上、自由主義とは一種の保守主義でもあるという趣旨のことを言っているように私は思いますが、保守主義についての著作もある宇野さんは、この辺り、どう考えますか。
宇野 「保守思想の父」と言われるエドマンド・バークもある種の自由主義者で、自由を尊重するイギリスの国制を擁護していましたし、むしろ自由の伝統がないところで保守主義を掲げるというのは、非常に空疎だと思います。
では、日本も含めた自由の伝統がない国はどうすればいいか。
この難問の答えは私にもありませんが、本書の随所で浮かび上がる、そもそも自由の伝統がない国において自由を論ずることの難しさは常に感じています。ただ、原理的に自由を擁護されるイメージがある杉田先生の中にこういう論点があったということに対しては、やや意外な気もしました。
杉田 そこは宇野さんの『保守主義とは何か 反フランス革命から現代日本まで』(中公新書)などに学んだのかもしれません(笑)。
宇野 そうでしたか(笑)。
それはさておき、先ほど、政治思想史は専門でないとおっしゃいましたが、本書で取り上げられた6人の思想家の著書はいずれも新しい翻訳で紹介され、最新の知見や研究動向も取り入れながら、非常に正統的な読み方をされていると思います。
その一方で、これまでの話にもあったように、新しい角度からそれぞれの思想家に切り込むということも意欲的にやっていらっしゃいますよね。6人の内の残りのふたり、たとえばシュミットに関しては『政治的なものの概念』の1932年版と1933年版の違いが強調され、フーコーの章では『社会は防衛しなければならない』という、ちょっと特異な位置にある講義録を丁寧に論じています。
また、6人の思想家で最後に登場するのがシュミットとフーコーというのが非常に面白いと思います。ミルが多元主義、ホッブズが一元主義、ルソーは極めて両義的、それを経てバーリンの「二つの自由概念」で整理がつくというところで終わらせることもできたと思いますが、締めにこのふたりを持ってきた理由をうかがえますか。
杉田 まずシュミットは、ホッブズが考えた問題を現代において改めて真剣に考えた人という位置付けで選んだのですが、「そういえば、『政治的なものの概念』の議論と一見似ているけれど全然違う話をフーコーはしていたな」と思い出し、手に取ったのが『社会は防衛しなければならない』だったんです。
確かに、フーコーを論じるときにこの本を取り上げる人はあまり多くないでしょうね。
『政治的なものの概念』は、要するに政治とは戦争であるということが書かれている本であって、こういう政治観とは異なる考え方をシュミットは自由主義とひとまとめにし、批判します。
ホッブズを「最高の政治学者」と賞賛し、政治の戦争・闘争としての側面ばかりを見たシュミットは、戦争をするには個人の自由を放棄して異論を抑圧し、内部を一元化しないといけない、と主張するわけです。
一方、フーコーの『社会は防衛しなければならない』は、戦争や闘争の問題、そしてホッブズを大きく扱っている点では、『政治的なものの概念』と共通しています。
しかし、内戦を何よりも嫌ったシュミットに対し、フーコーは「内戦の擁護」を展開していきます。
それは、主権の一元性の相対化ということです。本書は基本的にミル以来の言論の自由が大切だという話をしているのに対し、フーコーは言論闘争というより、武力闘争の話にまでなってますが(笑)。
宇野 フーコーはブーランヴィリエのような「貴族的反動」と呼ばれる17世紀末以来の歴史家の著作を読み直し、中世の封建的な関係の中に主権に対抗する契機を探すなど、内戦を既存の秩序を掘り崩す契機と捉えていますね。
そんなフーコーを杉田先生はかなりポジティブに読んでいらっしゃるように思います。対抗的な闘争としての政治に注目し、言論闘争だけではなく武力を用いた戦いの可能性すら示唆するフーコーの議論は、現代の戦争の状況を考えれば、非常に示唆的です。
取材・構成:加藤裕子 撮影:五十嵐和博
後半は、映画『オッペンハイマー』やセキュリティクリアランス制度から、議論すべき論点を語り合う。
プロフィール

1967年東京都生まれ。東京大学法学部卒業後、同大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。千葉大学助教授などを経て、東京大学社会科学研究所教授。専門は、政治思想史、政治哲学。著書に『政治哲学へ』『トクヴィル』『民主主義とは何か』『実験の民主主義―トクヴィルの思想からデジタル、ファンダムへ』。編著に『フランス知と戦後日本:対比思想史の試み』など。
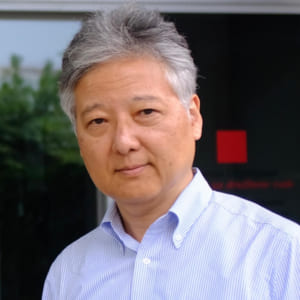
1959年生まれ。政治学者。東京大学法学部卒業後、東京大学助手、新潟大学助教授などを経て、法政大学法学部教授。専門は政治理論。著書に『権力の系譜学』『権力』『デモクラシーの論じ方』『政治への想像力』『境界線の政治学 増補版』『政治的思考』『両義性のポリティーク』。編著に『丸山眞男セレクション』など。


 宇野重規×杉田敦
宇野重規×杉田敦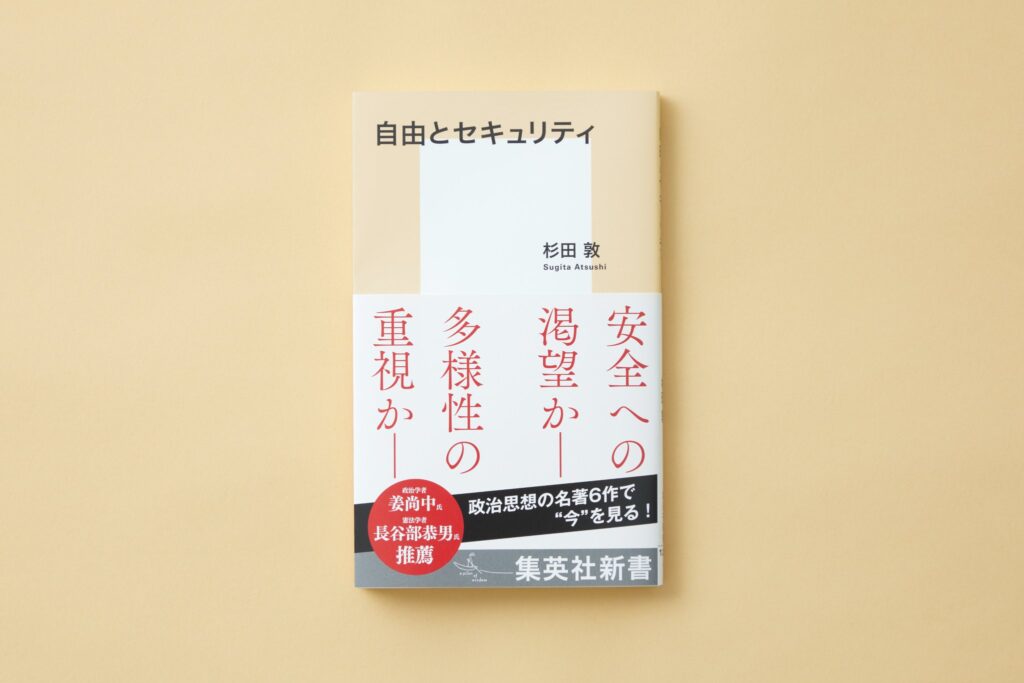











 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


