音楽はなぜ数学なのか
リベラルアーツ(自由技芸)のうち、数学的といわれる四科(クアドリウィウム)をボエティウスは「大きさのあるもの(マグニチュード)」と「多さのあるもの(マルチチュード)」に大別しました。これはそれぞれ、いわば「数えられないもの(連続的なもの)」と「数えられるもの(隔てられたもの)」です。ボエティウスはこの2つをさらに2つずつ、計4つに分けました。それがクアドリウィウムです。まず「大きさのあるもの=数えられないもの」は、「動いている大きさ」を扱う学問つまり天文学と、「動かない大きいもの」を扱う学問つまり幾何学に、そして「多さのあるもの=数えられるもの」は、数そのものを扱う学問である算術と、「数えられるもの」同士の比例関係を扱う「音楽」に分類しました。
「大きさのあるもの」はいわば環境のスケール、「多さのあるもの」はいわばパーソナルなスケールにあたる、と前回書きました。天体や大地を相手にする天文学や幾何学が環境のスケールなのは直感的によくわかると思います。算術は、たとえば手指でものを数える様子を想像すればわかりやすいでしょう。ボエティウスのいう「音楽」は、ピタゴラス以来の数と比例に対する神秘的な思想を知れば理解しやすくなります。比例とはつまり、数と数とのあいだの関係のことです。
興味深いことにボエティウスは、「ある長さの弦を単純な整数比で押さえるとその響きが調和する」という器楽的な音楽だけでなく、天体の運行が調和する「天上の音楽」というものを想像していました。星々のあいだには調和した秩序があると考えていたのです。ボエティウスは、その音楽観を詳細に解説した『音楽教程』で「天上の音楽」に言及しているのですが、手元で演奏できる「楽器の音楽」について解説した部分だけが現存しており、「天上の音楽」の詳細についてはそもそも執筆されなかったか、書かれていても写本が継承される早い段階で失われたと考えられています。楽器という個人の手元のスケールにおさまる「音楽」と、天体という環境のスケールの「音楽」を、ボエティウスがどのように結びつけていたのか、詳細な資料が現存していないのは残念なことです。
ピダハンと数の文化
ボエティウスは「数えられるもの」と「数えられないもの」を区別しましたが、そもそもこの区別をするためには数の概念が必要になります。しかし、数の概念を持たない人々がいる、あるいは数を持たない「文化」が存在する、という説があるのです。
『数の発明』の著者ケイレブ・エヴェレットの両親は、言語学者・人類学者です。『数の発明』のなかでも触れられていますが、ケイレブの親たち、特に父親のダニエルはブラジルのアマゾン川流域に住む数百人の少数民族ピダハンの研究で有名になりました。ダニエルの研究によると、ピダハンの使う言葉はとても特徴的なものでした。彼らは3以上の数を持たず、また過去形や未来形がない、とダニエルは主張しました。「3以上の数を持たない」というより、数の概念がなく、「多い」か「少ない」か「より少ない」かという相対的な違いがわかるだけ、という方が正確かもしれません。ピダハンは数を理解しないために外部の集団との商取引で損をしていると考えたため、ケイレブの両親に数について教えて欲しいと頼んできたそうです。残念ながらその後、ダニエルたちの講義ではピダハンたちは数や計算を覚えることができませんでした。もっとも現在はブラジルの義務教育の施設が導入され、数についてダニエルが報告した「文化」は失われつつあります。
数の概念がなければ、当然ながら「1,2,3……」のように、つまり普通の意味で「数える」ことはできません。数えるとは、ほとんどの現代社会で当たり前のこととされているため、それができないひとは知的に劣っているとみなされがちです。数学嫌いは世の中にとても多く、たとえば三角関数を理解していないことをもって蔑まれるようなことはあまりありません。しかし、ピダハンについて現代の日本人が話題にするとき、どこか彼らを見下すニュアンスが含まれるのはなぜなのでしょうか。
ひとつには、漠然とした進歩史観の影響が考えられます。人類の歴史は「進歩」に向かってまっすぐに発展してきており、「より進んでいる」文化圏と「より遅れている」文化圏がある、という考え方です。その考え方をもとにすると、数のような基礎的な概念的道具を持っていないピダハンは、「より遅れた」文化圏に属している、ゆえに蔑むべきであるということになります。ピダハンたちも自らが商取引で「損をしたくない」と考えてダニエルたちに講義を依頼したことや、明確な数を持たないという人類学的に貴重な「文化」を持っていながら、国の義務教育を受けてその「文化」を消滅させつつあることから、その「進歩」をピダハンたちも受け入れつつあるとも言えるでしょう。
ケイレブ・エヴェレットは『数の発明』のなかで、ピダハンたちはしかし、そのような不利な「文化」を、敢えて意図的に保存してきた可能性があることを示唆しています。
ダニエル・L・エヴェレットはピダハンの言語に数が存在しないのは、ピダハンが直接的に見聞きしたものについてしか話さないからだ、と考えました。たとえば「今が何年の何月何日の何時である」のような抽象的な表現をしないのです。日付のような抽象的な捉え方をするためには、そのときそのときに過ぎ去っていき、決して繰り返しをしない時間や「年月日」に名前をつけ、実際には繰り返していないにもかかわらず、仮想的な繰り返しのなかで、その時間や「年月日」を捉え直すことが必要になります。
たとえば、右手の人差し指と中指を立てるジェスチャーは、「右手の人差し指」と「右手の中指」という個別の身体部位を必要とします。このジェスチャーを「2」という数字を示すものとして捉え、たとえば「左手の人差し指と中指」による同様のジェスチャーと同じ数を示しているとか、「2」人の子供たちを意味している、などのように認識するためには、「2」という数を、そのジェスチャーにたびたび呼び出して結びつける必要があります。
あらゆる言語は、その言葉の指し示す対象と、その対象を呼ぶ言葉とを結びつけるために、このような「繰り返し言葉を呼び出す」行為を発話者に求めます。ピダハンは、なぜかこの「繰り返し言葉を呼び出す」行為を最低限にとどめているようなのです。
直感と論理
なお、近年の脳科学の研究により、言語を持たないほかの動物でも3つまでは数えられると言われています。逆に言えば、それ以上の数の扱いは、言語の介入を必要とするということです。究極の数学嫌いであるかのような印象を与える、かつての数を持たなかったピダハンたちも数に関する言語を持たないことで3,4以上の数の扱いをしないようにしていたとも考えられるのです。
多くの人間が直感的に捉えられる数が3までであるということは、目の数に関係しているかもしれません。左右についた目は前後左右という水平の広がりの認識を可能にします。この水平方向の広がりに加えて、垂直方向を加えた3次元までは、人間は比較的容易にイメージすることが可能です。水平に垂直を加えた3次元に、さらに時間の軸を加えた4次元も多少の困難を感じるものの、イメージすることは可能です。しかし、さらに軸を増やした5次元以上の世界はほとんどのひとがイメージできません。
また、ひとは巨大な数も具体的にイメージすることができません。世界人口は80億人以上と言われていますが、誰もこの人数を一望のもとに眺めたことはないのです。仮に80億人を一望できたとしても、ひとりひとりを識別することはできないでしょう。それでも「世界人口は80億人」との認識が可能なのは、「億」という数の単位があるからです。
「億」という単位は「10に10をかける」という計算を7回繰り返したときに現れます。仮に、直感的に3までしか把握できないとしたら、3と2を足したものに2をかけた数(10)どうしを、3と3と2を足した回数(8回)だけ繰り返し掛け合わせるということになります。わざわざこんなややこしい書き方をしたのには理由があります。というのも、この手順は少しも直観的ではないからです。直感的ではないからややこしいと感じる。しかし、私たちは直感的に把握できない億の単位の数を、世界人口という対象については使うことができます。これは「億」という単位が、上記のややこしい手順を省略してくれるからです。
複素数
1から3までの直感的に把握できる数から始めて、それを組み合わせれば容易に直感で把握できない大きな数を作ることができます。また、紀元前にすでに発見されていた幾何学の定理に「三平方の定理」があります。これは直角三角形の3つの辺のうち、斜辺の長さの自乗が、残りの2辺それぞれの自乗した値を足したものと等しくなる、というものです。
たとえば、2つの辺の長さが1である直角二等辺三角形を考える場合、斜辺の長さを自乗した値は、「1の自乗+1の自乗」なので2になります。つまり、2つの辺の長さが1である直角二等辺三角形の斜辺の長さは、自乗すると2になる数です。「自乗すると2になる数」は√2と書きます。2の平方根です。√2は、1よりは大きく、2よりは小さいのですが、小数や分数を使って表現できない数です。小数として書くと具体的には1.41421356……と小数点以下に無限に数が続くことになります。このように、整数でも分数でも表現できない数は無理数と呼ばれます。数学的な計算を経て初めて理解できる、非直感的な数です。直感的ではない数として、あるものを数えるときに使える正の数に対して足りない数を数える負の数をあげることもできるでしょう。負の数をもとに、先ほどの√2のように平方根を考えると「自乗するとマイナス1になる数」を考えることができます。「虚数(imaginary number)」と呼ばれ、通常は「i」で表記されます。イマジナリーというのは「想像上の」という意味です。
虚数iを「虚数」と呼ぶとき、対比されるのはリアルな数という意味の「実数(real number)」で、虚数と実数を組み合わせた複素数は現代数学の基礎とされています。
実数を横軸に、虚数の係数を縦軸に対応させて座標を描くと、実数と虚数を組み合わせた点が移動する平面があらわれます。これを複素平面、もしくはこの平面を考案した数学者としてもっとも著名な人物の名前を冠してガウス平面と呼びます(他の呼び方もあります)。複素平面は、音や電波のような周期性のある物理現象の記述と相性が良く、有名なアインシュタインの相対性理論も複素数の考え方と無縁ではありません。
相対性理論とリーマン幾何学
アインシュタインの相対性理論が依拠したのは、リーマン幾何学と呼ばれる数学でした。リーマン幾何学は、かつてアレキサンドリアの学術都市で活躍したエウクレイデス(ユークリッド)の理論に複素平面の考え方を適用して拡張したものです。
ユークリッド幾何学には作図のための5つの公準が示されています。いずれも、ほぼ直感的に当たり前のことなのですが、念のため書き出しておきましょう。
- 任意の点から任意の点へ直線をひくこと
- 有限直線を連続して一直線に延長すること
- 任意の点と距離(=半径)をもって円を描くこと
- すべての直角は互いに等しいこと
- 一直線が二直線に交わり,同じ側の内角の和が二直角より小ならば、この二直線は、限りなく延長されると、二直角より小さい角のある側において交わること
1は、直線が2点を繋ぐものであることを意味します。2は、直線というものが途切れず真っ直ぐであることを意味しています。3は、ある中心から同じ半径で描かれたものが円であることを意味します。そして4は、そのままの意味です。ここまでは本当に至極当たり前のことに思われるかもしれません。それだけ、ユークリッド幾何学の現代社会への影響が大きいということでもあります。
しかし問題は5番目です。一見してわかるとおり、5番目の公準だけ、言葉の分量が多く、複合的です。
射影幾何学
私たちが2つの目で世界を眺めている日常的な感覚で言えば、近くにあるものは相対的に大きく、遠くにあるものは近くにあるものより小さく見えます。十分に遠くにあるものは、小さくなりすぎて見えなくなります。この視覚的な条件から、十分遠いある地点を消失点として設定し、その消失点を始点として放射状に直線が広がるような空間を想定するのが遠近法や透視図法という手法です。手前では平行線のように見える直線が、視覚的には消失点まで延長すると交わってしまう。このような空間における幾何学は、射影幾何学と呼ばれ、ユークリッドの時代でも研究されていました。ユークリッドが『原論』で論じた空間に、消失点(無限遠点)を加えることで、遠近法的な射影幾何学の空間があらわれます。射影幾何学の空間は、遠近法的な見せかけの図形と、その図形が描かれる空間のいわば背後にある射影変換がセットになります。
たとえばある建物が描かれるとき、その建物の図像がどう描かれるかは、射影変換のルールに依拠します。ここで重要なのは、見せかけの図像という直感と、その直感的な見せかけの背後に直感的な図像とセットになるルールの存在を想定しているということです。
この直感とルールのセットを前提とするとき、ルールに手を加えることで、見せかけの図像がそれまでとは違ってくる、つまり変化すると考えられるようになるのです。
これは、レンズやフィルターを組み合わせ、さまざまなパラメーターを操作して、「見せかけの図像」つまり射影である画像を変化させる、現代のデジカメの感覚に近いといえるでしょう。
無限とゲーム理論
遠近法的な射影幾何学空間は、初歩的なユークリッド空間に消失点つまり無限遠点を加えたものでした。そして、性質としてはほとんど無関係ですが、√2は1.41421356……と小数点以下が「無限」に続く数です。このように、数学はすぐに「無限」に出逢います。ユークリッド幾何学でも、問題の第5の公準には「二直線を限りなく延長する」という無限の操作が登場します。
いくつもある数学の諸分野のなかで、無限が登場するもうひとつの分野がゲーム理論です。コンピューターの父と呼ばれる何人かの人物の、もっとも著名な1人、ジョン・フォン・ノイマンが創設したこの分野は、2人以上のプレイヤーの互いの利益が互いの行動に依存する戦略的状況を対象として研究します。「ゲーム」と聞くと楽しそうな名前ですが、統計学や経済学と結びつき、商品やサービスの価格設定などの企業経営から、国家間の安全保障までをも含む幅広い現実に適用できます。ゲーム理論が対象にしている戦略的状況とは、たとえば私と他の誰かが、それぞれの利益のために行動をしようとするときに、互いの行動によって得られる利益が変わってくるというものです。
私と他の誰かは、それぞれ自分の利益のために行動します。どう行動すれば、より利益を得られるか。それは相手の行動に依存しています。それでは、相手はどう行動するでしょうか。相手の行動は、今度は相手からみた相手、つまり自分の行動に依存しています。しかし自分の行動は、先ほど書いたとおり、相手の行動に依存するのです。このように、ゲーム理論では互いに互いの行動を「無限」に読み合うという事態が成立します。それじゃあ考えても無駄じゃないか、終わりがないのだから、と思ってしまうかもしれません。しかし、各プレイヤーが合理的に振る舞うならば、最適な行動は限定できる、という理論が発表されました。これが有名なナッシュ均衡です。
映画『ビューティフル・マインド』で物語化されたアメリカの数学者ジョン・ナッシュが発表したナッシュ均衡の理論は、囚人のジレンマなどの例とともにいまや世界的に知られています。ナッシュはこの理論でノーベル経済学賞を受賞しました。ノーベル経済学賞を受賞したのだから経済学者なのだと思われがちですが、ナッシュの専門は数学であって、経済学はその応用に過ぎません。『ビューティフル・マインド』では、ナッシュが研究に没頭して精神のバランスを失う様子が描かれますが、それもナッシュ均衡のような経済学上の業績のための研究ではなく、数学上の問題に取り組む過程のことでした。
ナッシュとリーマン幾何学
それでは、ナッシュが取り組んでいたのはどのような数学だったのでしょうか。実はナッシュは、ノーベル経済学賞のほかに、「数学のノーベル賞」と言われるアーベル賞も受賞しています。ナッシュがアーベル賞を与えられたのは、「ナッシュ埋め込み定理」を含む研究に対してです。
ナッシュ埋め込み定理は、アインシュタインが相対性理論で依拠したのと同じリーマン幾何学に関する定理です。ユークリッド幾何学では、ある点と点の距離は、その2点を繋ぐ直線の長さと同じになります。ごく当たり前のことですが、ここで直線といっているものは曲がっていません。しかし、さきほど射影幾何学に触れた際に書いた通り、直感=見せかけは、セットになっているルールに規定されています。遠近法的な空間では、手元で平行に見えた2つの直線が無限遠点で交差するという、単純なユークリッド幾何学ではありえないことが起こります。直線や平面といった概念は、直感的な見せかけと、その背後のルールにいわば分解されます。
19世紀の数学者でガウスの弟子だったベルンハルト・リーマンは、曲がった面の上の距離を考えることを可能にする幾何学を考案しました。遠近法的な視界で平行線が無限遠点で交わる射影幾何学の方が、平行線が無限に交わらないユークリッド幾何学よりも直感的であるように、3次元図形の球体に近い形の地球の上にいる私たちが直感的に認識している図形は、実は全て少しずつ球面に沿って曲がっています。それこそ、私たちの手前では互いに交わらないように思われる平行な2直線は、球面に沿って延長していけば、球の反対側で交わってしまうのです。遠近法的な射影幾何学空間とはまた別の非ユークリッド幾何学空間こそ、私たちのいる世界により近いものなのです。
地図のことを考える場合、様々な図法が存在します。3次元の球体の表面を、2次元の平面に投影するので、曲面上の地形などがどうしても歪んでしまいます。現代でも世界地図にいろいろな形があるのは、次元間の変換ゆえの仕方のないことなのです。
わたしたちが地球上を移動しようとするとき、だいたいは地図を開いて移動を始める点と目的地点の2点を選び、そのあいだを最短で繋ぐルートが最短であると考えます。日常生活のレベルでは、おそらくこれでそんなに、問題はありません。しかし、さきほど書いた通り地図上の地形は、3次元から2次元への投影によって歪んでいます。つまり、地図の上で容易に最短距離だと思われた2点間の距離は、実は歪んでいて正確ではないのです。
ナッシュ埋め込み定理は、非ユークリッド幾何学の空間であるリーマン幾何学の図形を、ユークリッド幾何学の空間に「埋め込む」ことを可能にする定理です。
アインシュタインが相対性理論でリーマン幾何学を採用したのは、宇宙空間という大きな領域で、1秒間に約30万キロメートルを進む光の運動をも議論しようとしたからです。
幾何学の役割
ほとんどの人間が、直感的には3までしか数を捉えられないのだとすれば、そこまでがパーソナルなスケールの数だといえるでしょう。直感的に捉えられない4以上の数は、後天的に学習するものであり、共同体から与えられた記号を使って理解していく共同体のスケールに属するものだといえます。
日常的な視界、つまり遠近法的な視界は直感的でパーソナルなものですが、その直感的な視界を数学で扱おうとする射影幾何学は共同体のスケールだといえるのではないでしょうか。あらゆる自然科学は、自然現象という環境のスケールを、学問という共同体のスケールで理解しようとするものです。それゆえに、ユークリッド幾何学も射影幾何学もリーマン幾何学もすべて共同体のスケールと環境のスケールに関わっています。
重力や光といった宇宙全体にあまねく適用できるアインシュタインの相対性理論はまったく直感的ではないという意味ではパーソナルなスケールでは捉えられません。文字通り環境のスケールの理論だといえます。
もちろん、アインシュタインもリーマンもナッシュも、それぞれの人生を生きた個人でした。彼らの研究はパーソナルなスケールで営まれ、そのイノベーションは学会のような共同体のスケールを経由して、世界や宇宙という環境のスケールへとアクセスしていたのです。また、私たちがその上に立ってパーソナルなスケールの生活をしている地球という球体に近い物体の、私たちが暮らしている地表という曲面を扱おうとするとき、幾何学は環境のスケールから記号や理論といった共同体のスケールを経由して、パーソナルなスケールに触れてきます。
(次回に続く)
参考文献
「幾何学基礎論――ヒルベルトからタルスキへ」足立恒雄、数理解析研究所講究録別冊
『相対性理論入門』内山龍雄、1978年、岩波新書
『数の発明――私たちは数をつくり、数につくられた』 ケイレブ・エヴェレット、屋代通子 訳、みすず書房、2021年
『ピダハン――「言語本能」を超える文化と世界観』 ダニエル・L・エヴェレット、屋代通子 訳、みすず書房、2012年
『無限と連続』遠山啓、岩波新書、1952年
『音楽教程』ボエティウス、伊藤友計 訳、講談社学術文庫、2023年

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)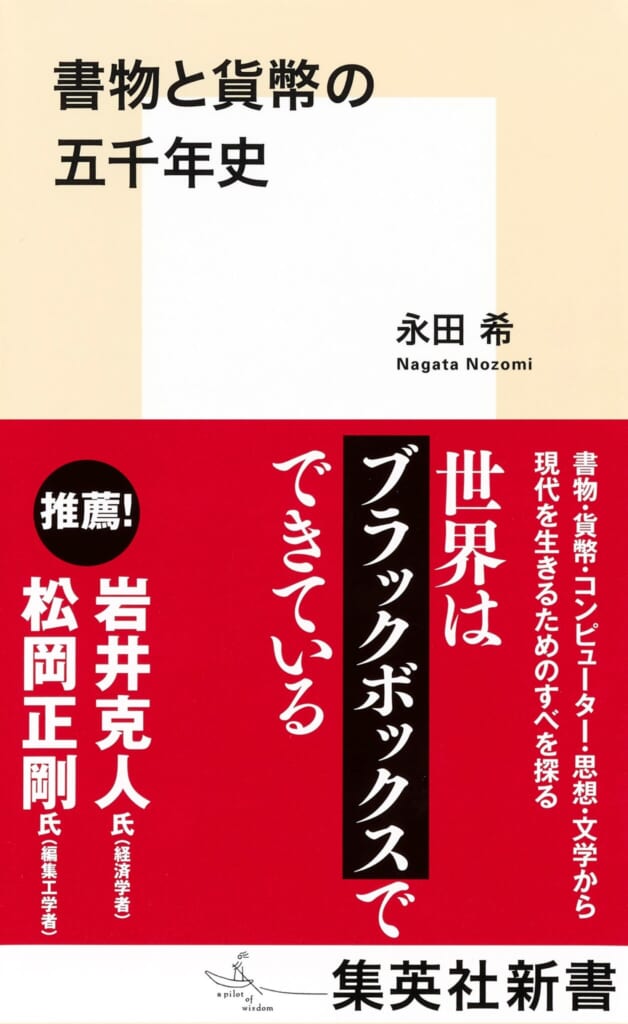










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理




 森野咲
森野咲