天文学、幾何学、音楽、算術
この連載で何度も書いてきたことですが、教養とはよくわからないものです。よくわからないなりにその由来を調べてみると、中世ヨーロッパでリベラルアーツやアルテスリベラレスと呼ばれていた科目に行き当たります。自由学芸や自由技芸と訳されるこのリベラルアーツも、その実態や輪郭はあまりはっきりしていません。
しかしリベラルアーツ(アルテスリベラレス)が、古代ローマ帝国からヨーロッパに継承された考え方であり、さらにその前身として古代ギリシャの文化があったことはひとまず確かだと言えます。東西に分裂したローマ帝国の西側、いわゆる西ローマ帝国の末期に活躍した政治家にボエティウスという人物がいます。ボエティウスはローマ貴族の名家に生まれ、古代ギリシャに創設され900年続いたプラトンのアカデメイアに留学し、その後は帝国の重臣となったものの、帝国崩壊の渦中で反逆罪に問われて刑死しました。ボエティウスは、先行する思想家たちの主張をまとめ、後世に伝えたという業績があります。
このボエティウスは「最後のローマ人にして最初のスコラ学者」と呼ばれました。スコラ学者とは、ローマ帝国滅亡後のヨーロッパで営まれた、教会や修道院での研究活動に従事した人たちのことです。ボエティウスは、天文学、幾何学、音楽、算術の4つの科目(四科=クアドリウム)を重視しました。ボエティウスは、古代ギリシャの哲学者ピュタゴラスの思想を参照して、世界の存在を次の2つに分類します。すなわち、連続した量(大きさ、マグニチュード)と、隔てられた量(多数性、マルチチュード)です。四科のうち、動きを伴う大きなものを扱うのが天文学であり、動かない大きなものを扱うのが幾何学だとされます。三角定規や分度器で紙の上に図形を描いたり、パソコンやタブレットの画面上に図形を描くことができる現代では幾何学が「動かない大きなものを扱う」というのは違和感があるかもしれませんが、幾何学はgeometryであり、語頭の「geo」が大地を意味する「ガイア」に通じており、もとは測量から発生した分野であること、また地理学(geography)にも関係していることを考えれば、このことは理解できるでしょう。これに対して、「連続量ではない=隔てられた」ものであり、数えることのできる数を扱うのが算術と音楽です。数そのものを扱うのが算術であることは容易に理解できますが、なぜここに「音楽」が登場するのか、これも直感的には理解が難しいかもしれません。
ボエティウスが依拠したピュタゴラスは「万物は数である」と主張していました。そして、ある長さの弦を弾いた時の音が、その半分の長さの弦の音や、三分の一の長さの弦の音と快く調和することに注目しました。ここでピュタゴラスが注目した調和と比例という要素が、ボエティウスのいう「音楽」を算術から分離し、独立した科目として重要な位置を与えます。その響きが調和していることにより、それを耳にした人は快さを感じます。単に快さを感じるだけではなく、調和した音楽によってひとびとは暴力性を制御し、穏やかで思慮深くなる、とボエティウスは主張しています。この音楽観は、かつて秘密結社として危険視されたために解散を宣告されたピュタゴラスの教団でも信じられ、また「幾何学を学ばざる者、この門をくぐるべからず」と数学を基礎教養として重視していたプラトンのアカデメイアでも採用されていました。プラトンの後、900年も続いたアカデメイアの最後期の学生でもあったボエティウスは、この考え方を引き継いだのです。
調和した音に快さを感じるのは古代でも現代でも変わりません。しかし、ボエティウスやピュタゴラス、プラトンは、音楽の根幹に比例関係を認め、それを重視しましたが、その演奏にはまったくといっていいほど関心を払いません。個々の奏者による名人芸や激しい感情表現は、むしろ調和を乱すものとして退けられていたと考えられます。よく「ボエティウスの論じた音楽は、現代の一般的な音楽とは違う」と言われるのはこのためです。しかし、ちまたでよく耳にするいわゆるエモい音楽が各種の産業と結びついており、その商業主義的な側面が繰り返し批判されてきたことを考えれば、ボエティウス的な音楽観はいまだにその有効性を失ってはいないといえるかもしれません。もっともボエティウスには、仮説検証を不可欠な要素とする実証主義的な近代以降の学問とは異なり、先人の学説を無批判に尊重してしまうという厄介な側面があります。実際にはありえない物理的な現象について主張をまことしやかに書き立て、その主張のうえにまさに砂上の楼閣のごとき空論を展開している箇所があることは認めざるをえません。
そもそも、ピュタゴラスやプラトンは音楽が人の心を穏やかにし、ひいては社会集団を調和させるとときましたが、ピュタゴラスが作った教団は解散させられていますし、プラトンの作ったアカデメイアも900年も続いたものの、キリスト教を国教としたローマ帝国の政府によって、異教性を嫌われ解散させられました。ボエティウスが留学したのはその解散前夜の末期アカデメイアだったのです。ボエティウスもまた、先述のとおり、西ローマ帝国滅亡の過程で刑死しています。つまり、音楽の「効用」がなんら実証性を持っていなかったのです。
証明の誕生
ボエティウスはいまから約1500年前、ピュタゴラスは約2500年前の時代を生きた人ですが、数の起源はさらに遡ります。人類学者のケイレブ・エヴェレットが数の起源や文化的な多様性を論じた『数の発明――私たちは数をつくり、数につくられた』(屋代通子 訳、みすず書房)によれば、数の発祥として見なすことのできる痕跡があるのは、アフリカ大陸のほぼ南端にあるピナクルポイントと呼ばれる地域です。17万年前から4万年前に、まだアフリカ大陸を出ていなかった人類は、原因不明の寒冷化によりその総人口を激減させたと考えられています。急激な気候変動を生き延びた人類はこの地域に移動し、狩猟採集生活を営みました。ケイレブ・エヴェレットは、人口激減という現象からは想像できないくらい、ピナクルポイント時代の人類の暮らしは豊かだったと考えられる、と書いています。数以外にも、人類史に残る「発明」がこの地の遺跡から発見されているからです。
もっとも、ピナクルポイントで発見された原初的な「和の痕跡」はあまりに古いため、それが本当に数の最初の姿なのかは判断が難しいものです。単に偶然、木片に傷が規則的に付けられただけかもしれません。
なお「数える」という行為と、「数」という文字や概念とは別のものです。数の概念が生まれる前に、数えたい対象と対応する目印を木片に刻むということが行われたと考えることは可能です。ピナクルポイントからかなりあと、四大文明と言われる時代になると、数えることと不可分に結びついた数の概念ははっきりと痕跡を残しています。その代表的なものが、メソポタミア文明を築いたシュメール人の楔形文字を刻んだ粘土板です。数千年前に記されたこれらの粘土板には、税の取り立てのための帳簿と思われるものが多数存在しています。
古代ギリシャのピュタゴラス以前に、世界の数学的な知識の最前線にあったのは、シュメール人から知識を継承したメソポタミア(現在の西アジア)と、やはり四大文明のひとつだったエジプトでした。四大文明の残りのふたつ、つまりインダス文明と黄河文明については、史料が残っていないためか、存在感が薄いのが現状です。インダス文明では、板の上にまいた砂のうえで計算をしていたために記録が少ない、黄河文明以降の中国では算木が使われたために記録が少ない、とも言われています。
ピュタゴラスは、当時の最先端だったエジプトとメソポタミアに留学し、数学的な知見を収集しました。古代ギリシャでは、単に数を計算するだけではなく、その計算を論証するというスタイルが確立されます。問いと解決とその証明、がセットになることにより、古代ギリシャから古代ローマ、そして中世から近代以降のヨーロッパの数学は、他の地域に対して求心力を持つに至ったともいえるでしょう。これは、科学的な客観性に裏付けられた進歩史観の基盤になるものです。
各国の歴史ではない国際的な歴史という意味で「世界史」が語られるとき、古代ギリシャから古代ローマ、そしてヨーロッパの歴史が特権的に語られることが多いことには複数の理由がありますが、数学(学ぶべきもの)を軸とする「知識の継承」として歴史を捉える考え方が大きな役割を果たしています。
抽象と数
ところで、世の中には「数学嫌い」「算数嫌い」を自称する人が相当の数で存在しています。そんな人たちが、なぜこんなにも多いのでしょうか。
数学や算数に苦手意識を持つ人には女性が多いとされています。これは今後は変化していくかもしれませんが、次の理由により、現在でも根強い傾向です。女性は、文化的に「数学から遠ざけられる」機会がとても高いことが知られています。幼少期に「女の子なのに算数ができてえらい」というような言葉をかけられることがあります。保護者や教師、あるいは親戚からのこの言葉は、褒めているようで、暗に「女の子は数学をやらない」というバイアスがかかった規範を教えることになります。「女の子は数学ができなくてもいい」「数学ができない女の子はかわいい」「数学ができる女の子はかわいくない」というような、より積極的なバイアスもあります。女性数学者が珍しいことの原因として、家庭や教育機関にいまだにバイアスが強く残っていることがあるのはまちがいないでしょう。
次に、さきほど書いたばかりの西洋中心主義的な数学史の経緯があります。数学のシステムが古代からヨーロッパ的なものに規定されていることにより、非ヨーロッパ人に数学へのハードルが設定されているのです。
数学へのハードルは、ジェンダーや西洋中心主義によるものだけではありません。元来、世界に存在するモノを扱うための知見であったはずの数学は、発展の過程で抽象度を高めてきました。もとを辿れば、数える対象の個別具体性を「捨象」することで抽象的な「数」は得られます。数学(mathematics)は、ギリシャ語の「学ぶべきもの」に由来しているのですが、対象の個別具体性を離れた知識を、抽象的な知識として「学ぶ」ことが数学の本質なのです。
前述しましたが、かつてプラトンのアカデメイアの門には「幾何学を学ばざる者、この門をくぐるべからず」と刻まれていた、という有名な逸話があります。アカデメイアは、現代の大学の起源のひとつなのです。いわば文理が分かれる前の時代、哲学を学ぶ学校においては、数学を学ぶのは大前提だったのです。プラトンのアカデメイアが滅びて以降、「学ぶべきもの」だったはずの数学はなぜ、その本来の性格を忘れられてしまったのでしょうか。なぜ、哲学以前に「学ぶべきもの」だったはずの数学は、文理の区別により、学ばなくても良いものになってしまったのでしょうか。
その答えは複数考えられます。一筋縄では行かない問題なのです。複数ある答えのうちで、しかしもっとも大きなもののひとつとして挙げられるのは、近代哲学の開祖とされるルネ・デカルトの登場でしょう。
デカルト以前の数学史
デカルトの功罪を紹介する前に、ボエティウス以降の学問の状況を概観してみる必要があります。ボエティウスがクアドリウィウムを提唱したのが紀元5世紀前後、デカルトが活躍したのが17世紀なので、このあいだの約1200年を早足で辿ることになります。
まずボエティウスの生涯は、すでに書いたとおり西ローマ帝国の滅亡期と重なります。ボエティウスがまとめた古代ギリシャ由来の知識は、ヨーロッパにおいては中世スコラ学として修道院で研究され後世に伝えられていきます。なお東方でビザンツ帝国として西ローマ帝国よりも約1000年ほど長く続いた東ローマ帝国は、西アジアに発生して地中海の南側(北アフリカ)を経由してイベリア半島にまで勢力を拡大したイスラム文化圏に圧迫されるようになります。
イスラム文化圏はアラビア半島を中心に、インドにも勢力を広げます。西はイベリア半島、アフリカ大陸、東はインドから東南アジアまでを版図に含めたイスラム文化圏では、エジプトに建設されていたアレキサンドリア図書館(ムーサイオン)の蔵書からユークリッドの『幾何学原論』がもたらされ、またインドからはゼロを含む算用数字を吸収しました。ユークリッドは、プラトンのアカデメイアで研究されていた数学の知識を『幾何学原論』で集大成した人物です。
算用数字はよく「アラビア数字」と言われる「1,2,3……」という数字です。「I,II,III……」と書くローマ数字や「一、二、三……」と書く漢数字と対比されます。もっとも、ヨーロッパに算用数字をもたらしたのがアラビア商人だったことからアラビア数字という呼び方が定着しただけで、アラビアではインドから来たことで「インド数字」と呼ばれていました。
政治的には主に敵対関係ばかりが歴史に記されるヨーロッパ(キリスト教圏)とイスラム文化圏ですが、経済的には常にやり取りがあり、また学問的にも研究者の行き来がありました。地中海のイタリア半島やイベリア半島を経由した文化的、学問的な知識の輸入により、14世紀ごろからルネサンスと呼ばれる運動が起こります。再生を意味するルネサンスは、ギリシャ・ローマ的な文化を古典として復興再生するものと考えられました。この時期にヨーロッパで利用されるようになった活版印刷、火薬、羅針盤はルネサンスの三大発明と呼ばれていましたが、人類史的な視野で見るとこれらはいずれも中国で生まれ、ルネサンスの時期にヨーロッパに受容され改良されたものです。
ともあれ、活版印刷により知識の蓄積と流通がかつてなく加速するようになりました。また羅針盤の活用により、いわゆる大航海時代(大発見時代)の幕が上がります。大航海時代の背景には、羅針盤だけではなく、宗教改革によるプロテスタント(新教)の登場があります。従来のカトリック(旧教)のヨーロッパ本土での権威が相対的に失墜していくのに対して、ヨーロッパの外へと進出することでプロテスタント勢力を拮抗させようという動機です。
デカルトの心身二元論
15世紀以降のヨーロッパでは、羅針盤によって外洋の航海が可能になりました。陸地を目視できない遠洋の航海では、天体観測によって自分の位置を測ることがきわめて重要になります。このような天測航法が発達する一方で、当時のヨーロッパの暦法は天動説に基づいていたため不正確でした。天体観測の精度が増すほどに、天動説に基づく暦法の誤差は目立つようになります。
当時カトリックの司祭だったコペルニクスは、プラトンのイデア思想の影響から、より精度の高い暦法の必要性を感じ、地動説の基礎になる理論を発表しました。コペルニクスの説を支持したガリレオ・ガリレイは、当時最先端の技術的あった望遠鏡をみずから改良し、天体観測をおこないました。金星の満ち欠けから地動説を確信したガリレイですが、当時の政争に巻き込まれ異端として告発されてしまいます。コペルニクス以来の地動説を踏まえた著作を準備していたデカルトは、ガリレイの裁判を知り、その著作の内容を変更したと考えられています。
デカルトは『方法序説』によって近代哲学の基礎をなした人物とされていますが、若い頃にイエズス会というカトリック系の修道会の学校で学んでいます。ボエティウス以来のスコラ学をしっかりと習得しているのです。イエズス会は、ルネサンスの影響を受けた修道士イグナチウス・デ・ロヨラらによって創設されました。ロヨラとともにイエズス会を創設したフランシスコ・ザビエルは日本への宣教でも知られています。「神の軍隊」と呼ばれたイエズス会は軍事的な性格も強く、会士たちは軍隊的な規律で教育されました。日本では、当時の最高権力者であった豊臣秀吉が「伴天連追放令」を出してイエズス会を警戒しましたが、実際にカトリックに改宗したキリシタン大名を通じた軍事侵攻を計画していた記録が残っています。大航海時代以降の、ヨーロッパ各国を宗主国とする植民地政策の一環として、イエズス会はヨーロッパ中心の「世界」を建設するための尖兵という役割を担っていたのです。
そのため、イエズス会はカトリック教会の一部であり、かつボエティウス以来のリベラルアーツの伝統を継承しつつ、実学的な研究も積極的にすすめていました。デカルトは、「進歩的な保守的組織」とでもいうべき矛盾した性格を持つイエズス会で学んだのです。そして、この矛盾は『方法序説』の有名な「我思う故に我あり」という一節に結実します。この一節は、世界のあらゆるものを疑うとしても、「思う我」だけは疑えない、という意味です。ここに、「思う我」ではない「思考しない世界」と、「思う我」を含む「思考する世界」という、二重の世界が現れます。「思考しない世界」つまり「モノの世界」は人間によって操作される世界であり、「思考する世界」は「ヒトの世界」つまり人間自身の世界です。文理の区別には諸説ありますが、「思考しない世界」という人間に操作される世界を対象にするのがいわゆる理系の学問であり、「思考する世界」を対象とする学問を文系とする区別がここから生じます。
3つのスケールと数学
さて、ではこれまで主張してきた「3つのスケール」つまり環境/共同体/パーソナルのスケールと数学はどのように関わっているのでしょうか。まず、数学は世界の秩序を研究するものです。その意味では、デカルトのいう「思考しない世界」(物質)、つまり環境のスケールに関わるものだと言えるでしょう。これは、ボエティウスのいう「連続した大きなもの」つまり天文学や幾何学が該当します。これに対して、デカルトが「思考」(精神)と呼んだものは何でしょう。ボエティウスのクアドリウィウムの残り2つ(算術・音楽)がこれに該当しそうです。デカルトとボエティウスの分類がきっちりと互いに対応すると考える必要はありませんが、このあたりはパーソナルなスケールにあたると考えていいでしょう。しかし、実は数学に関しては、環境のスケールの現象(天体の動きや、地上の地理的様相)も、パーソナルなスケールの現象(手元で数えられる物事や心理)も、どちらも計測して数で表したり、その関係を数式で記述できるという「記号」の問題であり、その限りで共同体のスケールの性格を無視することはできません。その計測や計算の仕方こそが、記号で表現され、ピュタゴラス学派では口述で継承され、それ以外の共同体では写本のかたちで保管され研究されてきたのです。
環境のスケールやパーソナルなスケールと向き合って、その様子をただ眺めているだけでは数学になりません。共同体の吟味に晒すことで初めて、他の誰かによっても「学ぶべきもの」なのかどうか、それが数学なのかどうかが問われるのです。この数学の数学たる所以は、しかし、他のあらゆる学問に共通したことのように思われるかもしれません。ここまで読まれた方にはもう自明のことかもしれませんが、数学は「数の学」である以前に、「学ぶべきもの」として継承されてきた体系でした。つまり、数学こそが学問の基礎なのです。これは、四則演算にはじまるあらゆる「計算」や、さまざまな数式が他の学問でも使える、というような話ではありません。それは小手先の、表層の話に過ぎないのです。
世の中に「数学嫌い」がたくさんいるのは、このような小手先の操作を、幼少期にとにかく「学ぶべきもの」として押しつけられる経験からくる苦手意識に起因するのではないでしょうか。もちろん、何をなぜ学ぶべきなのか、という問題はとても難しいものです。学んでみてからでなければ、それを学ぶべき理由がわからない、ということもあるからです。しかし「数学とは共同体が学ぶべきものとして継承してきた体系である」ということを知らなければ、共同体がそれを継承してきた理由を考えることもできず、またそもそもそれを継承してきた共同体について考えることもできないのです。
次回は、デカルトの二元論以降の近現代の数学史を瞥見していきます。
(次回へ続く)
参考文献
『数の発明――私たちは数をつくり、数につくられた』 ケイレブ・エヴェレット、 屋代通子 訳、みすず書房、2021年
「証明の発明と発展 ギリシャ数学の創始・発展とその遺産」斎藤憲、2020年
「初期ギリシア数学史の再検討」斎藤憲
「数学史講義(第2回) : ユークリッド『原論』,論証学問の成立」林知宏、2008年
「セブンリベラルアーツとはどこから来た何ものか」半田智久、2010年
『数学の思想』村田全、茂木勇、NHKブックス、1966年
『東西数学史』三上義夫、科学図書館叢書、2018年

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)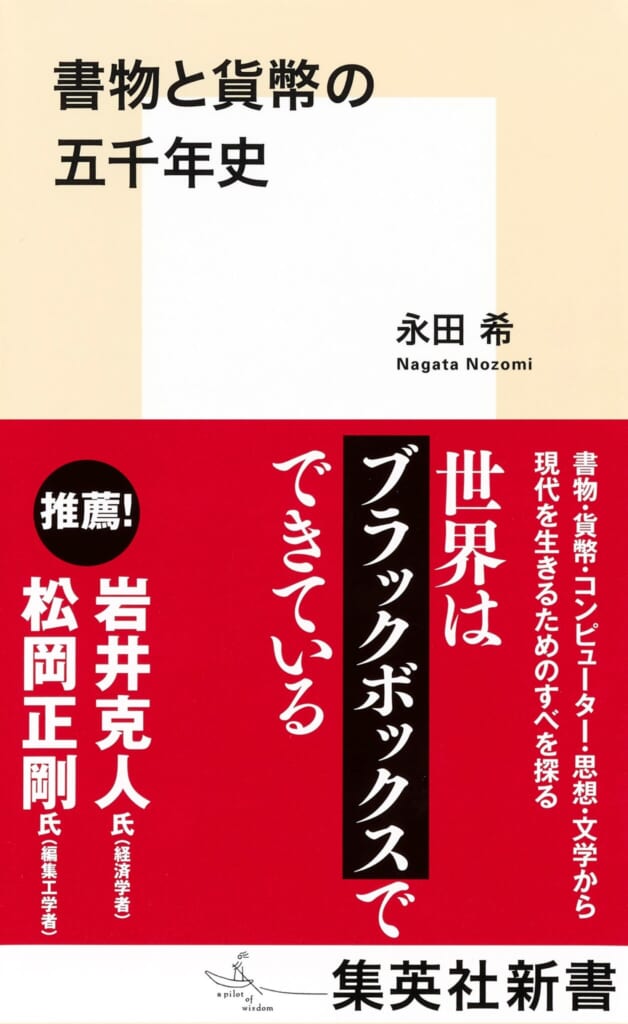










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


