ピダハンとキリスト
『数の発明』の著者ケイレブ・エヴェレットの父ダニエルは、アマゾン川流域に暮らす「ピダハン」という少数民族の言語と文化を研究し、その論文は学界で大きな議論を巻き起こしました。ダニエルがピダハンたちのもとに赴いたのは、研究を目的としていたというより、伝道師(宣教師)としてピダハンたちにキリスト教を伝道するためでした。
キリスト教に救われたと信じていたダニエルは、その「救い」をピダハンたちにもたらすべく、アメリカ合衆国からアマゾンのあるブラジルに向かったのです。アマゾンに入ったダニエルは、当時まだほとんど誰も理解できなかったピダハンの言語を手探りで学び、聖書をピダハンの言語に翻訳することを試みます。ダニエルが言語学会に発表することになる「発見」は、聖書をピダハン語に翻訳する過程で得られたものだとも言えます。
しかし、ピダハンは数の概念を持っていないだけではなく、自分たちが直接に経験したことだけを信じるという文化を強く持っていたため、キリストの言葉や物語に意味を見出すことはありませんでした。ピダハンたちはいうまでもなく、伝道師であるダニエルすら、イエス・キリストと「直接会った」わけではないのです。ダニエルの伝道は困難をきわめました。
ピダハンの「見たことしか信じない」態度は、「自分で見たことしか信じない」と胸を張る現代人と共通する部分があります。ここで興味深いのは、ピダハンたちはダニエルや彼の家族には見えない「妖精」の存在を信じており、自分たちは妖精が見える、と主張していることです。現代でも、自分で見たことしか信じないと言いつつ、陰謀論や超常現象を信じる人がいるのに似ているような気がします。
ピダハンたちと暮らすようになる前に、伝道の経験を積んでいたダニエルも、やがて信仰を捨てることになります。ダニエルの著書『ピダハン』には、信仰をやめる過程こそはっきりとは書かれていないものの、キリスト教とピダハンの考え方の間でダニエルの思想がどのように揺れ動いたかが綴られています。
フィールドワークとマリノフスキ
ダニエルがピダハンと暮らすようになったのは1970年代です。ダニエルはキリスト教の伝道師としてアマゾンに入りますが、さきほど触れたとおりピダハンの教化を断念します。教化断念後のダニエルは、ピダハンの言語を研究し、ピダハン語の第一人者として国際的な知名度を得ていきます。したがって、ダニエルは元伝道師であり、言語学者である、と言えます。また言語学的な観点からピダハンを研究するだけではなく、ピダハンの居住域でフィールドワークをする人類学者であるとも言えます。
フィールドワークとは、さまざまな学問分野でそれぞれの意味を持ちますが、人類学や社会学では、研究対象者の暮らす社会(フィールド)に身を投じ、研究対象とともに生活しながら研究をする手法を指します。人類学におけるフィールドワークは、ポーランドの人類学者ブロニスワフ・マリノフスキの実績が特に有名です。1880年代生まれのマリノフスキは、1910年代にオーストラリアやパプアニューギニアに滞在し、現地の先住民の暮らしを研究しました。
「安楽椅子の人類学者」とフィールドワーク
マリノフスキ以前の人類学は、『金枝篇』で知られるイギリスのジェームズ・フレイザーのように、「人類」についての文献を収集し陳列するのが普通でした。マリノフスキ以後の人類学者と区別して、フレイザーのようなマリノフスキ以前の人類学者のスタイルを「安楽椅子の人類学者」と揶揄することもあります。
欧米の白人中心主義的な思想に基づき、周縁的な地域の「人類」を未開あるいは野蛮とみなす考え方がその背景にはありました。この考え方は、資本主義によって近代化を果たした欧米の白人は人類の先端を進む先進的な存在であり、それ以外の人々は遅れているとみなします。この考え方のなかで自分たちの社会を相対化しようとするとき、「遅れている」地域には、「先を進んでいる」自分たちの社会が失ってしまった何かが保持されている、という発想が生まれます。かつての人類学は、欧米諸国の知的エリートが、周縁地域の未開社会のなかに保持されているものを探る、というものだったのです。
文明の進化論
人類学に由来する、先進的な文明と後進的な未開社会、という考え方はかなり根深いものです。さしあたり、この種の考え方を「文明の進化論」と呼びましょう。ある社会の人々が未開であり後進的である、という考え方は、つまるところ「彼らも我々のような先進的な文明に追いつくべきだ」という押し付けがましい倫理観に裏打ちされています。
この倫理観のうえで、「彼ら」に先進的な文明のメンバーになるための教育をするという道もありますが、その前に、人類史が辿ってきたどこかの段階にとどまっている「彼ら」の姿から、先進的な文明が失ってしまった何かを学ぶことができるかもしれない。自分たちの社会をさらに進歩させるために、他の社会から学ぼう、という姿勢は殊勝なように見えるのですが、しっかり考えればわかるように、他の地域に暮らしている他の社会の人々の文化は、いわゆる生きた化石のようなものではなく、そこで彼らなりに時を重ねて独自に発展してきたものです。たまたま「彼ら」から学べるものがあるとしても、それは「彼ら」が、「私たちの社会が失ったもの」を保持しているからではないのです。
安楽椅子と呪術
安楽椅子の人類学者フレイザーは、名著『金枝篇』において、世界中の各地にみられる「神殺し」風習を収集、開陳しました。もともと古典学者だったフレイザーは、古典の文献を収集して読解するように、世界中の風習の資料を漁ったのです。なお『金枝篇』には日本の天皇についての事例も収集されています。
フレイザーは、19世紀末のヨーロッパが体現していた近代社会の合理主義の前段階として一神教的宗教があると考え、そのさらに前の段階に呪術がある、と考えました。
フレイザーにとって呪術とは、樹木を精霊や神に見立てたり、そのような神聖な樹木を祭司が代理したりすること、その樹木や祭司に水をかけるなどして雨乞いをしたり豊作や多産を願ったりするようなことを指します。『金枝篇』から、少し長くなりますが一例を引きましょう
オラオン族〔インド中部のドラヴィダ語系言語を話す民族。別名クルク族〕は、サラソウジュの木々が花を咲かせる時期に春の祭りを行う。これは彼らが、この時期に大地の結婚が行われ、サラソウジュの花はその儀式に不可欠である、と考えるからである。ある特定の日に、村人たちは祭司とともに聖なるサルナ(Sarna)の木立に行く。この地は、女神サルナ・ブーリ(Sarna Burhi) すなわち「木立の女」が住んでいたとされる、古いサラソウジュの森の名残である〔Sarna はサールナート Sarnath のことであるかもしれない。これはインド北部にある仏教の聖地で、ブッダが最初の説教を行った地とされる。
漢訳では「鹿野強」。この女神は雨に多大な影響力を持っていると考えられた。
(中略)翌日祭司は集めた花を大きな籠に入れ、村の一軒一軒に配る。どの家でも、女たちは、祭司が近づいてくるとその足を洗うために水を持って出てくる。そして跪き、彼に恭しくお辞儀する。つぎに祭司は女たちと踊り、サラソウジュの花をいくつか、家の戸の上と女たちの髪に挿す。
これが終わるとすぐに、女たちは水差しの水を祭司の頭上に空け、ずぶ濡れにさせる。その後宴となり、若者たちは髪にサラソウジュの花を挿し、一晩中村の緑地で踊り続ける。ここでは、花を抱えた祭司が、花開いたサラソウジュの木の女神と等価であることは、明白である。女神は雨を降らす力を持っていると考えられたのであったし、祭司を水浸しにすることは、(中略)雨乞いの呪術である。したがって祭司は、あたかも彼が木の女神そのものであるかのように、家の一軒一軒に雨を分配し、多産性を授ける。しかも、とりわけ女たちに授けるのである。
(『金枝篇』)
このような呪術には、近代的な意味での合理的な因果性はなく、またキリスト教における神学のような体系性もありません。フレイザーはフィールドワークをせずに収集した資料から、自説を支持しうる例だけを膨大に抜き取ったため、現代的な学問としては水準を満たさないと批判されるのですが、その恣意性をいったん忘れてみれば、世界中のあちこちに住む人々がどのようなことを願い、生きるために何を試してきたのか、また何を信じてきたのか、それを一望できるかのような気持ちになれる、『金枝篇』はそんな強烈な魅力をもった仕事です。
フレイザーは『金枝篇』で、一神教のように体系化はされていないものの、各地に伝わる呪術的な風習には、何らかの論理があると仮定しました。
たとえば、誰かに水を浴びせる場合、「濡れている」状態になりますが、これは旱魃で困る農家が期待する「雨」が降るときと類似しています。合理的に考えれば、それは類似していないとは言えない、という程度の類似ですが、この類似が「雨」という現象に帰結する、少なくとも呪術を実践する人々はそう信じている、とフレイザーは考えました。これをフレイザーは「感染」とか「共感」と呼びます。
人間の暮らしは自然に依存しており、自然はときに人間に不都合な旱魃や災害をもたらします。呪術は、この不都合な自然のありかたに人間が干渉するために、超自然的な存在を想定して行うものです。
超自然的な存在である神は、先ほどの樹木の例のように、人間に見立てられます。人間に見立てられることにより、その神は罰したり、極端な場合には殺害することも可能になります。
近代的な合理主義の目で見れば、そこには神はいないし、不在なのだから当然ながら殺害などされていないわけですが、神に類似している、もしくは、神に見立てられた人、あるいは他の依代を用意することによって、「神殺し」が呪術的に可能になる。このような「論理」を、呪術的な段階の社会は採用していたのではないか、とフレイザーは考えたのでした。
近代的な意味での合理性は認められないものの、呪術的論理とでもいうべきものをフレイザーは見出しており、それは近代社会の論理に先立つものだったといいます。フレイザーは「文明の進化論」に依拠するため、未開社会に暮らす人々を蛮人と呼びます。
われわれが真実と呼ぶものは、もっとも効果的に機能することの判明した、ひとつの仮説に過ぎないのである。それゆえ、われわれより野蛮な時代と民族の、意見や慣習を検討する際には、彼らの誤りを、真実の探求の途上では避け難かった躓きとして、寛大に見据えるのがよい。そしてわれわれもまた、いつの日か自らに必要となるであろう寛大さという恩恵を、いまは彼らに与えておくのがよいのである。
(『金枝篇』)
マリノフスキとクラ
そのフレイザーの強い影響を受けつつ、フィールドワークに基づく人類学を確立したのがマリノフスキでした。19世紀末のイギリスという覇権国家の安楽椅子に座っていたフレイザーと違い、マリノフスキの出自はヨーロッパのなかでも比較的周縁に位置していたポーランドです。ポーランドは近代になって急速に台頭しつつあったドイツとロシアという2つの帝国に挟まれ、侵略されたり分割されたりと、マリノフスキ以後も地政学的に災難に苦しめられてきました。
マリノフスキは、ポーランドの古都クラクフで物理学と数学を学んだのちライプツィヒにうつり、心理学をヴィルヘルム・ヴント、社会学者ゲオルク・ジンメルのもとで研究、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに籍をおくことになりました。
マリノフスキは、フレイザーだけでなく、当時ヨーロッパで新進気鋭の思想家として話題になっていたジークムント・フロイトの精神分析にも耽溺した、と『未開社会における性と抑圧』で述懐しています。書名からして「文明の進化論」に依拠しているこの論考において、マリノフスキはフロイトの有名なエディプスコンプレックスの普遍性を批判しています。
フロイトは心理学者であり精神分析理論の開祖ですが、その思索の過程で、人間の精神の基層を探求しました。その探求の一環として、フロイトなりの人類学的見地から、ギリシア神話に登場するオイディプスに代表される「父殺し」のパターンが、やはり世界中のあらゆる社会で見出せると主張していたのです。マリノフスキはこの考え方をある時期までは支持していたのですが、彼のフィールドワークで目にした太平洋の「未開社会」には、エディプスコンプレックス的な心理を持っていない文化があるように見えたのでした。
マリノフスキが太平洋の「未開社会」に見出したのは、エディプスコンプレックスの不在だけではありません。のちにマルセル・モースが注目し、『贈与論』の元ネタになる「クラ」と呼ばれる風習が有名です。
モースの贈与概念
『贈与論』で知られるマルセル・モースが、社会学者のエミール・デュルケムの甥であることは有名です。モースは、デュルケムの姉の息子なのです。デュルケムは、フレイザーと同時期に活躍し、社会学の基礎をつくった人物です。単なる親族であるというだけでなく、デュルケムとモースは師弟の関係でもありました。
デュルケムは『自殺論』ですが、社会の構造があり、そしてそのなかで何かの機能があり、その機能ゆえに何かしらの社会現象が起きる、という構造機能主義を提唱していました。デュルケムらが創始した社会学は、新しい学問として盛り上がりを見せていましたが、不運なことに第一次世界大戦が勃発し、将来を嘱望されていたデュルケムの弟子たちはその多くが命を落としてしまいます。
モースは、そのデュルケムの思想を受け継いで、人類学の研究に役立てました。先述のマリノフスキはデュルケムも受けていて、あとで触れるレヴィ=ストロースから辛辣な批判を受けることになるのですが、それについてはここではおいておきます。
さて、モースの『贈与論』はマリノフスキの『西太平洋の遠洋航海者』を下敷きに、贈与交換とモースが呼ぶ行為について論じています。モースはマリノフスキ以後の人類学者ですが、いわばフレイザー型の人類学者で、他人が書いたものを収集して自説を構築するというスタイルです。フレイザーは、のちにルネ・ジラールが注目して社会学的な理論に発展させた「犠牲の羊(スケープゴート)」の風習についての考察でも有名なのですが、安楽椅子人類学者として、人類学者のあいだでスケープゴートにされている、という皮肉もあります。ともあれ、モースは『贈与論』の冒頭で、アメリカ先住民から中国、古代ローマにいたるさまざまな地域の風習を紹介し、さまざまな社会で「贈与」が見られると喝破します。別々の社会集団の代表者が、互いに贈り物を交換する風習が発展して、自分の持ち物のなかの貴重なものを自分で破壊して見せる「ポトラッチ」にも言及しています。
マリノフスキとモースが注目した「クラ」がどのような風習かというと、モースによれば、ポトラッチの性格をもっとも純粋に観察できる事例ということになります。ポトラッチはもともとアメリカ先住民の言葉であり、クラは西太平洋の島嶼地域の風習なので、直接の影響関係は少なくとも簡単には指摘できません。モースは人類の精神的な「岩盤」を観察するために、ポトラッチやクラに注目しているといいます。
つまり、フレイザーが呪術に注目し、フロイトがエディプスコンプレックスを指摘したように、モースはポトラッチやクラ、つまり贈与と交換が、「文明の進化論」的な意味で過去から残存(遺存survive)している制度である、と考えたのです。
クラとは、ごく単純化して言えば、貝殻で作った首飾りと腕輪を特別な贈り物として扱い、複数の島のあいだで首飾りや腕輪を贈与する、というものです。こう書いてしまうと、何やら単純にみえますが、首飾りや腕輪は普段は着用されず、特別な儀式でしか身につけられない、とか、首飾りと腕輪を贈与された際には返礼が求められるが、その際に通常の取引のような駆け引きをすることが忌避される、とか、首飾りと腕輪はそれぞれ贈与される方向が定められている、とか、詳細に記述しようとすると途端に膨大なディテールがあることに気付かされることになります。
フィールドワークで現地に身を置いてクラを目にする機会があるとしても、何やら不可解な理由で貝殻の装飾品をありがたがっている、謎の風習としか思えないのではないかというくらい、クラの交易圏は広く、また首飾りと腕輪が循環する期間は長いのです。
クラは通常の物品の取引とは区別されている、といましがた書きました。モースが注目するのはこの点です。その主著の書名にしている「贈与」を、他の取引、つまり「交換」と区別して捉えること、これをモースは試みました。
モースにとって贈与とは、アメリカ先住民にとってのポトラッチと同様に、目先の利益のためではなく行われるものです。しかしこれも先ほど触れた通り、クラにおいて首飾りや腕輪を贈与された側は返礼を要求されます。この意味でこの贈与は交換でもあります。つまり贈与とは、特別な交換ということになります。
のちにジョルジュ・バタイユやジャック・デリダは、モースの議論における贈与の概念を純粋化・抽象化して、交換ではない「不可能な贈与」を想定するのですが、それについては今は深追いせずにおきます。
レヴィ=ストロースのモース批判
モースは『贈与論』で、マオリ族の「ハウ」という概念を参照しつつ、贈与の危険性を指摘しました。モースが参照した資料によると、「ハウ」とは「森の神」であり、贈与に対して返礼をしないと「ハウ」が怒り、返礼をしなかった者は罰せられてしまう。
この「ハウ」の扱いについて、モースの『社会学と人類学』への序文を書いたレヴィ=ストロースは、その序文のなかでモースが研究対象による「こじつけ」に「ごまかされ」たのではないか、と書いています。
レヴィ=ストロースと構造主義
クロード・レヴィ=ストロースは20世紀後半に、構造主義と呼ばれる流行を代表することになる人類学者です。モースの『贈与論』に依拠しつつ、オーストラリアのとある先住民の婚姻関係を分析し、そこに数学的な規則があることを指摘しました。
この数学的な規則が「構造」であり、その構造が規則を採用している社会に暮らし、生きている人々に意識されていない、解析を必要とするものであることをレヴィ=ストロースは強調します。このような、暮らしのなかでは見えてこないもの、つまり「構造」を析出していこうというのがレヴィ=ストロースのスタンスです。
マリノフスキに対するレヴィ=ストロースの批判は、マリノフスキがデュルケム流の機能主義者であり、ある社会現象はしかじかの機能のために起きている、と説明する点に向けられました。レヴィ=ストロースにとって、何かしらの社会現象が生じるのは、普段は見えることのない「構造」によるものであり、機能によって説明できるとは限らないのです。
レヴィ=ストロースは、クラという交易の風習に複雑な規則があったように、婚姻関係にも複雑な規則があるのではないかと考えました。そこで、当時の数学界を席巻していたブルバキのメンバーに「構造」の解析を依頼したわけです。その結果、暮らしのなかで人々が認識できるしきたり(見た目)と、そのしきたりの背後にある「構造」(ルール)が結びつきつつ別々に指摘できることがわかりました。
何が移動しているか
マリノフスキとモースが着目したクラにおいては、島々のあいだを貝殻で作られた首飾りと腕輪が循環していました。ある集団からほかの集団へ、ある代表者から別の代表者へ、首飾りと腕輪は別々のルートを辿って贈与され、移動していきます。
レヴィ=ストロースが「構造」を指摘した婚姻関係についても、ある親族から別の親族への「女性」の贈与交換であることが重要でした。ある親族において、誰かの娘であり、別の誰かの姉や妹であり、さらにまた別の誰かにとっての姪や叔母であるような1人の人物が、他の親族集団へと贈与され、移動していく。
さて、クラにおいては首飾りと腕輪が、婚姻については「女性」が贈与されて移動しているのですが、ここで「移動」しているのは首飾り・腕輪・女性だけでしょうか。
いったん「贈与」ではなく「移動」に注目してみるとき、わたしたちが見落としている存在がいることに気が付きます。わたしたちが目にしていながら、無視していたのは何者でしょうか。
たとえば、マリノフスキはポーランドから西太平洋に「移動」してフィールドワークをしました。レヴィ=ストロースは、フランスから南アメリカ大陸に「移動」しています。安楽椅子人類学と揶揄されたフレイザーも、彼自身は「移動」していなくとも、彼の元へとさまざまな資料が「移動」してきたはずです。フィールドワークをどれくらいしていたかによらず、古今東西の資料を収集して比較するのは、人類学に限らず多くの学問では当然のことです。では人類学者たちが、世界中の人類のさまざまな社会についての文献や資料を収集することになるのは何故なのでしょう。当たり前のことですが、かつて人類がまず世界中に「移動」してきたからです。地球上のほとんどあらゆる場所に、何万年もかけて人類が「移動」してきたからこそ、その資料は世界のほとんどあらゆる場所から得られるのです。
資料のいわば産出地が世界中にあることはこれで理解されました。では、生産された資料が「移動」する先はどこでしょうか。
それは、「文明の進化論」でいう最先端にある領域、つまり近代合理性が支配する社会、すなわちヨーロッパということになります。
エドワード・サイードが『オリエンタリズム』で「西洋と東洋」について指摘し、ガヤトリ・スピヴァクが『サバルタンは語ることができるか』で欧米と旧植民地について指摘した「構造」が、人類学そのものの不可視の部分に存在しているのです。
レヴィ=ストロース以降の人類学は、少なくとも一部の人類学者たちは、この不可視の領域をどうにか視野に入れながら「人類」を捉えようとしています。次回はその様子をご紹介することになるでしょう。
(次回へ続く)

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)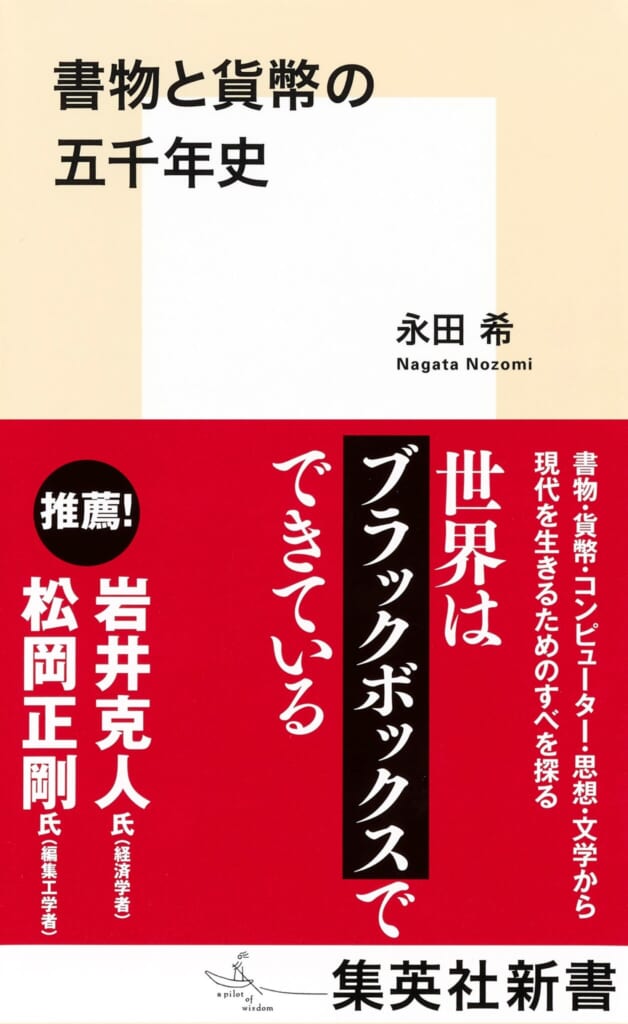










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

