昨今若者の間で広まる「界隈」という言葉。インターネット空間上を通して広まったこのフレーズは、いま若者たちのゆるい繋がりを表すものとして、注目を集めている。この「界隈」の誕生は、現代の文化においてどのような意味合いを持っているのだろうか。本連載ではインターネット上の若者集団をウォッチし続けてきたメディア研究者の山内萌が、さまざまな場所で生まれる「界隈」の内実を詳らかにしていく。
「界隈」が持つ独特なニュアンス
インターネットなどで昨今よく見かけるようになった「界隈」という言葉。特定の単語を前に置くことによって、(おもに)若者たちのゆるいグルーピングを示す表現である。
有名なのは、2024年4月にXで話題になった「風呂キャンセル界隈」である。これは文字通り「風呂をキャンセルする(=風呂に入らない)」人々を指し、ハッシュタグとともにXに投稿されていた。これを新聞やテレビなどのマスメディアが取り上げた。
もともと、界隈は場所と結びついて使われる言葉だった。たとえば銀座の賑わっている地域を指して「銀座界隈」というように、界隈の前にくるのは地名だった。それが今では、趣味や行動様式を表す言葉が入るようになった。
かつて若者たちの文化集団は「◯◯族」や「◯◯系」と表現されていた。日本の戦後若者文化では「太陽族」(1950年代)「みゆき族」(1960年代)「アンノン族」(1970年代)といったようなグルーピングが用いられていた。1990年代になると「渋谷系」「裏原系」「アキバ系」などの「◯◯系」という表現が使われるようになる。この文脈のうえで理解すると「〇〇界隈」は、同一の趣味や行動様式を基に集まった若者たちの集団を示す表現の2020年代版といえるだろう。
昨今の「界隈」という表現が帯びる独特のニュアンスを指摘しているのは、ラッパーのTaiTanと音楽家の玉置周啓である。彼らのポッドキャスト『奇奇怪怪』の「界隈ってなんなん」という回において、二人は族、系、クラスタ、トライブを挙げつつ、これらの集団を指す言葉に比べると界隈は「一番嫌味っぽい」とする。そして界隈が使われる理由をこう説明していた。「界隈とは結界である」と。つまり界隈の外側から、理解できないものに結界を引いて閉じ込めているのではないか、そうすることで観察可能な対象にしているのではないか。このように、界隈を外/内の区別から説明しようとする彼らの感覚は鋭い。特に以下の発言はクリティカルだ。
マイナーなコミュニティはメジャーに対しては多少気を張るよね。その様が、滑稽なんでしょ、マジョリティからしたら。滑稽っていうかさ、腹が立つんだよな。知らない世界で楽しんでるやつのあれこれっていうのは。
「族」から「系」へ
社会学者の難波功士は、自身の著作『「族」の系譜学 ユース・サブカルチャーズの戦後史』において、若者文化を定義している。それを筆者なりに要約すると、若者文化は「『私たちは、あえて◯◯と名乗る(名指されざるをえない)存在である』ことを社会に呈示する文化」である。若者たちとは、社会(=大人たち)に対して「私たちは◯◯する若者だ!」と宣言する存在なのである。
この定義に基づいて、難波は80年代から90年代に起こった「◯◯族」から「◯◯系」への変遷の社会的背景を説明する。戦後日本の若者には、社会から要請される「あるべき姿」、すなわち大人になることに反発する者たちがいた。アメリカ文化と映画の影響を受けて形成された若者文化に属する「太陽族」を始まりとして、1970年代頃まで使われた「◯◯族」は社会からの逸脱や非行と見なされる性格があった。
1980年代になると若者文化が社会全体に広がっていき、若者文化に浸りつつ大人になることが可能となった。そして社会の側にあった、若者に「大人になれ」と強制する規範も薄れていく。もはや「若者である」ことに逸脱的なイメージや特別な意味がなくなり、「私たちは◯◯する若者だ!」と宣言することで生まれるアイデンティティとの強固な結びつきも成立しなくなった。
代わりに登場したのは、細分化された若者文化とそれらをキャラのように使い分ける行動様式だ。「ギャル系」「コギャル系」「コンサバ系」といった女性ファッション雑誌上のカテゴリーから、「体育会系」「ジャニーズ系」など男性のタイプまで、1990年代以降は「◯◯系」が若者言葉として多用された。と同時に、マスメディアで大きく取り上げられることによって、マーケティングのターゲットにもなっていった。
どの「◯◯系」を選ぶかは完全に個人の選択となり、ある時は「ギャル系」、ある時は「ロリータ系」のように、気分によって個人の中で切り替えるものとなったのだ。難波はこれを「若者としてありながら、かつ他の若者と同じではないために、『あるユース・サブカルチャーを採択・使用する』という方略」と表現している。
つまり「◯◯族」から「◯◯系」への変化は、「大人になることへの拒否」から「他人とは違う(しかしメディアによって与えられた選択肢であるような)個性の選択」への変化なのだ。
「地雷系」と「トー横界隈」
だとすると、「◯◯界隈」の台頭はどのように位置づけられるだろうか。「界隈」はマーケッターからすでに捕捉されていて、博報堂が「界隈消費」と名付けてレポートを発表している。また、SHIBUYA109 lab.による「トレンド予測2023 ファッション・コスメ部門」では「水色界隈・天使界隈」というワードが挙がっている。「水色界隈・天使界隈」が指すのは、水色や白を基調としたファッションスタイルで、ジャージ素材を使ったスカートやパーカー、ヘッドドレスといったアイテムが特徴である。アパレルブランド「ililil(イルイルイル)」は自分たちが「天使界隈」という表現を作ったとし、その経緯をこう説明している。
実は「天使界隈」という言葉を作ったのは我々なんです。インスタグラムなどのSNSで「#水色界隈」が流行していることを知り、当時はこの界隈での共通言語がなかったため「新たに名前を付けて流行らせよう」と仕掛けたのです。
ラジトピ(2023)「Z世代に人気の水色界隈/天使界隈って? ブランド担当者→『推し活・Y3Kから派生した新ファッション』」
ここで注目したいのは、「水色界隈・天使界隈」が「地雷系」(系!)ファッションと結びついている点である。「地雷系」の若者たちは、「地雷メイク」といわれる、涙袋をラメでぷくぷくさせて、目尻にアイラインを長く引いた特徴的なメイク、ふりふりした黒のミニスカートに、リボンがついたくすみピンクのブラウスを合わせて、MCMのリュックを背負う。髪型はだいたいツインテールで、黒髪ぱっつんの前髪。「水色界隈・天使界隈」は、これらの特徴を押さえつつ、水色や白に特化しサイバーモチーフを取り入れたスタイルになる。
「地雷系」ファッションのブランドは、都内のショッピングビルでは渋谷109やラフォーレ原宿に一通り揃っている。前者は「ギャル系」、後者は「原宿系」のメッカであるが、「地雷系」はまさにギャルファッションとロリータファッションの要素、さらに「アキバ系」的なコスプレ風のディテールをミックスさせたデザインが特徴だ。2012年にはライターの松谷創一郎による『ギャルと不思議ちゃん論 女の子たちの三十年戦争』という1980年代以降の女の子文化をまとめた本があったが(著者は今ではすっかり「リベラル知識人」となりこのテーマを忘れてしまったようだが)、令和の今は「ギャルと不思議ちゃんとオタク少女」が「地雷系」に集約されたのである。
察しのいい読者は「地雷系」のファッションが、歌舞伎町の東宝周辺の広場に集い社会問題化した「トー横界隈」の若者たちの特徴と重なることに気づくだろう。この「トー横界隈」は「地雷系」の文化から派生した。歌舞伎町でフィールドワークを行う佐々木チワワによれば「トー横界隈」は、「自撮り界隈」としてつながっていたアカウント同士が、新宿・歌舞伎町の東宝ビル横という現実空間で集まりだし、路上飲みする様子などを投稿することによって広まっていった。つまり、「地雷系」の若者たちが「自撮り界隈」という言葉のもとに集い、それが歌舞伎町の現実空間において可視化されたことにより名指さされたのが「トー横界隈」なのである。
社会学者の南後由和は、若者がハロウィン当日に渋谷スクランブル交差点という現実の広場に集まって群衆を形成しつつ、その様子を撮影しSNSに投稿して情報空間上でもコミュニケーションする様を「離接的群衆」と名付けた。トー横に集まる若者はまさに「離接的群衆」だが、ハロウィンに集まる若者ほど「陽キャ」には見えない。むしろ「陰キャ」が「陽キャ」のように集まって騒げるコミュニティとして機能している。
実際に、トー横に集まる若者が家庭環境や生活に問題を抱えて、逃避するように歌舞伎町へ来ていることは各種報道でも明らかになっている。今年2月には、東京都が設置した歌舞伎町の相談窓口を6000人以上が利用し、その8割が24歳以下だったと報じられた。「トー横界隈」は日常に困難を抱えた若者たちの避難先でもある。
結界の中の少女たち
家庭や学校から逃れて「トー横界隈」に避難する若者たちは、お互いが仲間である証のように「地雷系」ファッションをまとう。マスメディアによって与えられる個性の選択肢であった「◯◯系」は、ここではむしろ強固にアイデンティティと結びついている。「トー横界隈」に逃避する「地雷系」の若者は、大人になることに反抗し、あえて逸脱していた「◯◯族」ほど無鉄砲で強くはない。「地雷系」のアイデンティティは、結界の内側に入ることによって弱い自分とつながっている。
筆者は2010年代後半にTwitter(あえてこう書こう)に張りついて「地雷系」や「自撮り界隈」の若者たちを観測していた。その実感からも、この二つの集団のアイデンティティは、メンタルヘルスの問題と強く結びついていた。「地雷系」の女の子のイラストには大量の薬剤とリストカットした腕が描かれているし、リストカットの写真を投稿する「自撮り界隈」の子も少なくなかった。「#自撮り界隈」と「#病み垢界隈」が並列された投稿も多い。
しかし「自撮り界隈」が若者たちに悪影響を与えていると結論付けるのは早急だ。むしろ「自撮り界隈」や「病み垢界隈」は、孤独で死にたい夜を過ごす少女たちを迎えてくれる情報空間上の避難所としても機能している。「トー横界隈」はその現実空間へのあらわれなのだ。
冒頭、ポッドキャスト「奇奇怪怪」における発言を引用し、「界隈とは結界である」という話を紹介した。この文脈では、界隈の外側から結界を張って界隈の中を対象化するという意味合いであった。確かにそう見ることもできるだろう。特にマスメディアで取り上げられるような、マーケティングの対象としての界隈はそうかもしれない。
しかし本連載では界隈の避難所としての側面、すなわち「外の世界から自己を守るために内側から張られた結界」として界隈をとらえてみたい。本連載のタイトルに付された民俗学という学問は、ある集団の文化の中に自ら身を置いて理解しようとする参与観察を主な調査方法とする。だから本連載も、外側から結界を張ってよくわからない文化を封じ込めて観察するのではなく、内側に分け入って参与観察をしてみる。そして、特にインターネット上の女の子文化としての「◯◯界隈」に着目していくことで、社会の中で少女たちが何に傷つき、結界の中でどのように自己と向き合っているのか明らかにしていきたい。
界隈民俗学が目指すのは、インターネットの少女民俗学である。
(次回へ続く)
参考文献
博報堂・SHIBUYA109 lab.(2024)「界隈消費――生活者発のコミュニティ起点で起きる、未来の消費とは?」『Future Evangelist Report』Vol.3
奇奇怪怪(2024)「界隈ってなんなん」
松谷創一郎(2012)『ギャルと不思議ちゃん論――女の子たちの三十年戦争』原書房
三浦展・藤村龍至・南後由和(2016)『商業空間は何の夢を見たか――1960~2010年代の都市と建築』平凡社
難波功士(2007)『族の系譜学――ユース・サブカルチャーズの戦後史』青弓社
NHK(2025)「都の『トー横』相談窓口に想定以上の利用者 支援体制強化へ」
ラジトピ(2023)「Z世代に人気の水色界隈/天使界隈って? ブランド担当者→『推し活・Y3Kから派生した新ファッション』」
佐々木チワワ(2021)『「ぴえん」という病 SNS世代の消費と承認』扶桑社
SHIBUYA109 lab.(2022)「トレンド予測2023」

昨今若者の間で広まる「界隈」という言葉。インターネット空間上を通して広まったこのフレーズは、いま若者たちのゆるい繋がりを表すものとして、注目を集めている。この「界隈」の誕生は、現代の文化においてどのような意味合いを持っているのだろうか。本連載「界隈民俗学」では、インターネット上の若者集団をウォッチし続けてきたメディア研究者、山内萌がさまざまな場所で生まれる「界隈」の内実を詳らかにしていく。
プロフィール

やまうちもえ メディア研究者。1992年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。同大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(学術)。単著「『性教育』としてのティーン雑誌──1980年代の『ポップティーン』における性特集の分析」『メディア研究』104号(2024)、「性的自撮りにみる「見せる主体」としての女性」『現代風俗学研究』20号(2020)。共著『メディアと若者文化』(新泉社)。


 山内萌
山内萌



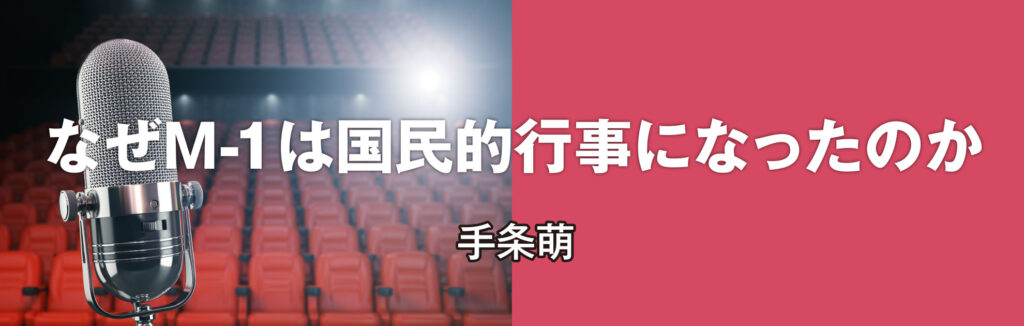





 菱田昌平×塚原龍雲
菱田昌平×塚原龍雲


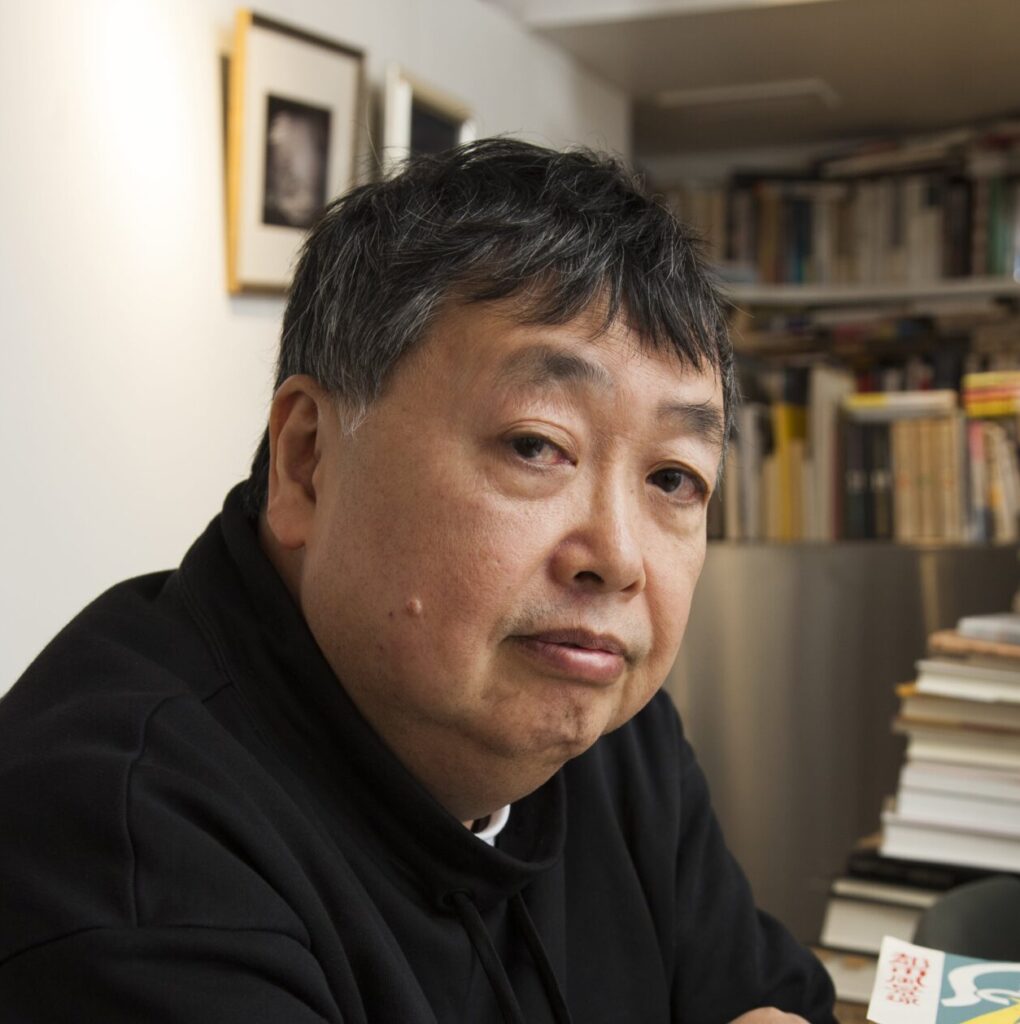
 大塚英志
大塚英志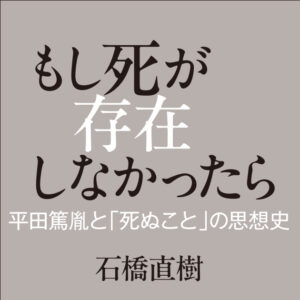
 石橋直樹
石橋直樹