大学生や転職を目指す若手会社員にとってのメジャーな就職先としてここ数年で一気に定着した「コンサル」。この職業が、若者に限らず「キャリアアップ」を目指すビジネスパーソンにとっての重要な選択肢となったのはなぜか?その背景にある時代の流れは、誰のどんな動きによって作られてきたのか?『ファスト教養』の著者が、「成長」に憑りつかれた現代社会の実像を明らかにする。
第3回は「会社を辞める若者」の今昔を比較します。昨年話題になったネットミームと、17年前のベストセラーから解き明かす「若者たちの焦り」の本質とは。

「何で商社辞めてベンチャー行ったの!」
前回の記事では2023年の上半期にヒットした2冊の「コンサル本」、高松智史『コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト』とメン獄『コンサルティング会社サバイバルマニュアル』を取り上げて、そこで語られている仕事の進め方やタイトルと帯で使われている「マニュアル」という言葉について考察した。また、著者たちが身を持って体験してきた長時間労働に関する記述から、本連載のキーワードでもある「成長」という概念を働き方改革以降とも言える2020年代の労働観と正しく結びつけることの難しさについても論じた。
さて、本連載では過去2回の記事で「コンサル」という職業について注目してきたが、コンサルと同じく高学歴の若者たちが新卒で門をたたく企業の代表例として総合商社がある。業界としての平均年収は上場会社に限ればコンサル業界を上回り(『会社四季報 業界地図 2023年版』より)、2023年3月期の決算では大手商社が軒並み最高益を叩きだすなど、相変わらずこの世の春を謳歌している。日本の外で行われる事業が多く、若くしてグローバルな仕事に関われそうなイメージも就職活動中の大学生には魅力的なものとして映ると思われる。 一方で、厳しい競争を潜り抜けて晴れて商社の一員になったとしても、入社からしばらくの間直面するのは大きな組織における下働きである(もちろん程度の差はある)。華やかなイメージとは裏腹に、そこにはひとりの若者の力だけで乗り越えるには難しい企業の論理というものがある。コロナ禍がまだ色濃いタイミングで在宅勤務を縮小する動きが早期に見られたのもこの業界だった(「伊藤忠が在宅勤務縮小、原則出社 社員は「エッセンシャルワーカー」」産経ニュース、2020年10月16日)。そのような環境に対してフラストレーションを溜めてしまうと、「果たして自分はこの会社に就職して正しかったのだろうか?」という気持ちが沸々とわいてくる。
そんなときに、どうにも魅力的に見えてしまうのが「ベンチャー」という企業形態である。自分と近い世代の経営陣がスピーディーな意思決定を行っている、ユニークなテクノロジーに基づいたプロダクトを扱っている、社会課題の解決に取り組みながら自社としてはIPOを目指すという大きな夢に向かって進んでいる、裁量権を持って自由な働き方ができる…そしてそういった会社は、「ここに来れば若いうちから経営に関わることで成長できる」という今の時代の決め台詞を繰り出してくるのである。
こうして、誰もが羨むはずの椅子を手にしたはずの若い「商社マン(※この言葉が一般化しているのでそのまま使用するが性別は問わない)」は、「成長スピード」「裁量権」といった言葉とともに「商社からベンチャーへ」という大きな決断を下す。決められたレールから自分で降りる高揚感は、給料が下がるという重要な事実も帳消しにする。
しかし、会社として大きなビジネスを動かしている総合商社を踏み台にしてまで進んだ先に、自分が求めていたものは本当にあるのだろうか?仕事をする以上お金は重要であり、「いずれストックオプションで回収できる」という話も空手形にすぎない。大企業のような研修制度は存在せず、わけもわからず日々の業務に巻き込まれる中で、体系的なスキルを身につける余裕をねん出するのは時間的にも精神的にも難しい。何より、事業の基盤がしっかりしていない状況で中長期的な視点を持てるわけもなく、短期的にキャッシュを生み出すための施策の優先順位がどんどん上がっていく。
もともと在籍していた会社よりも恵まれない待遇で、実はスケールの大きくない仕事と毎日向き合いながら、ふと気がつく。仮に下働き的な側面があったとしても、商社が世界で進める事業に関わりながらいろいろな経験を積んだ方が、むしろ自分の成長につながったのでは?そういう体験を高い給与水準と比較的安定した環境でしていたほうが、人生として豊かだったのでは?「あれ、自分はなんで商社を辞めたんだっけ?」
ここまでの話を踏まえて、昨年の夏にバズったこちらのツイートを見ていただきたい。
ネットミームと化しているウォルター・モリノのイラストに「何で商社辞めてベンチャー行ったの!」というコメントがついたこのツイートは、「商社マンをゲットしたはずの女性側の怒り」をコミカルに表現したもののはずである。ただ、実は花束で殴られている側の男性にも、「こんなはずじゃなかった」という気持ちが去来している可能性は大いにある。
「成長」への熱は、自身のキャリアに関する決断を時として誤らせる。そして、今の時代には、その熱を加速させる燃料がいたるところに転がっている。前回紹介したコンサル本も、「あの本に書いてあるような仕事のやり方を今の自分の職場には持ち込めない」と思った瞬間に、成長できる環境を探し始めるトリガーとして機能するようになるだろう。あらゆる情報に取り囲まれた中で、長期的な幸せと今やりたいことのバランスをとりながら的確な意思決定をすることは、決して簡単ではない。
2023年に改めて読む『若者はなぜ3年で辞めるのか?』
「大手有名企業を辞めて、創業数年で成長中のベンチャーに転職する動きが増えている。就職活動の人気企業ランキングで長年、上位を占めてきた総合商社からも、大量に人材流出しているというツィートが話題になるなど、人気企業も例外ではないようだ。その背景には何があるのか。」
「できるだけ早く成長したかった。30歳までに子どもを産みたいと考えると、意外と残り時間は少ないのに、同じ仕事を3年も繰り返していたら(想定までに)新しいサービスを普及させせる力、それで稼ぐ力がつかないな、と」
(「総合商社も直面する「人材流出」27歳女子がベンチャー転職を決めた本音」2017年12月11日 BUSINESS INSIDER)
終身雇用が一般的だった時代であれば、基本的にはあり得ない決断だったはずの「商社→ベンチャー」というキャリアチェンジ。その背景にあるのはやはり「成長」である。大きな組織で少しずつできることを増やしていく、という時間軸で自身のキャリアを考えることは成長への遠回りと認識されつつある。
こういった発想は、そもそもどのタイミングから広く浸透したのだろうか。そんなことを考えるうえで注目したいのが、2006年に刊行された城繁幸『若者はなぜ3年で辞めるのか? 年功序列が奪う日本の未来 』(光文社新書、以下『若者はなぜ3年で辞めるのか?』)である。
若いうちにさんざん下働きさせられたうえ、子供すら作れず、四〇を超えてから「騙された」と後悔するくらいなら、自分の足でレール以外の道を進んでみるべきだ(少なくとも、そのチャンスは与えられるべきだろう)。
(同書より)
この本で語られていることをシンプルにまとめると、「年功序列と終身雇用の限界」「決められたレールに乗り続けることなく自身でキャリアを選ぶことの重要性」である(先ほど触れた商社からベンチャーへの転職のケースでも「決められたレール」という表現を使ったが、同書にはたびたび「レール」のメタファーが登場する)。「自分の職場を見ると、今後の自分の人生がよくわかる」といった状況をネガティブに捉えて、新卒で大きな会社に入っても若いうちは年功序列に甘んじて同じことを繰り返すだけになりがちな環境を「「若いうちは我慢して働け」と言う上司は、いわば若者をそそのかして人生を出資させているようなものだ」とまで言い切る。そして、そんな現状に背を向けて、「レールの先にはどうやら明るい未来は少なそうだが、代わりにどこでも好きな方向へ歩いていけばいいのだ」とアジテーションする。

『若者はなぜ3年で辞めるのか?』は、若年層の労働環境についてタイトルの問いに対して答えていくという本ではない。むしろ、早期に大企業を辞めることでキャリアプランを自らの手に取り戻すことを積極的に推奨するという明確なポジションが示された内容になっている。キャッチーなタイトルを起点に時代風俗について切り取る光文社新書の最近の作品と言えば稲田豊史『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』が思い浮かぶが、稲田の本があくまでも現状の分析と問題提起に本のスコープを意図的にとどめているのに対して、『若者はなぜ3年で辞めるのか?』は「こうすべき」を積極的に打ち出している。
この「こうすべき」は、2023年現在において必ずしも刺激的な考え方ではなくなった。転職という行為自体が眉をひそめられるものではなくなり、同じ会社で働き続けるキャリアはあくまでも選択肢の1つとして相対化された。そして、そういった考え方を当たり前のものとして受け取る若者たちが、「成長」を旗印に自分にとってベストの職場を探してさまよっている。
一般論として、選択肢が増えることは歓迎されるべきことである。一方で、選択肢の増加はそれを目にする人たちの迷いを呼び起こす。「自分が選ばなかったオプションが良い結末につながっているのでは?」と考えてしまうのは仕方のないことだろう。
終身雇用も年功序列も、この先あらゆる会社で無条件に続いていく仕組みだとは考えづらい。しかし、それらが崩れていくスピードは、当然企業にとってグラデーションがある。また、未来への不安をある程度棚上げして目の前の業務に打ち込める環境というのは必ずしもネガティブなものではない。終身雇用だから悪、年功序列だから悪、といった考え方は、これまでの慣行を絶対視するのと同じレベルでの思考停止である。「成長のために環境を変えなくては」という発想は、こういった是々非々の思考プロセスを結果として放棄することにつながってはいないだろうか。
『若者はなぜ3年で辞めるのか?』で描かれる世界は、当時支配的だった労働観のカウンターとして魅力的に映るものだった。ただ、やはり「カウンターとして魅力的」なアクションや考え方には、冷静に見ると何かしらの穴があることが多い。同じ会社でじっくり勤め上げる方が向いているはずの人までが転職してしまうと、目先の満足も長期的なキャリアの蓄積も見込めなくなる。転職するのが普通になりつつある時代だからこそ、冷静な決断を呼び掛ける言説が必要になる。
ちなみに、『若者はなぜ3年で辞めるのか?』では、大企業からの転職先としての外資系コンサルティング会社を「担当するプロジェクト内容は同じでも、業務の割り振りから人員構成、予算まで、あらゆることが一八〇度変わりました。ちょっとしたカルチャーショックですね」「基本的に能力が軸であり、年齢はほとんど関係ない」「仕事内容で給料が決まる以上、誰がどこまでの仕事を担当するのか、その切り分けが非常に明確にされている」と持ち上げている。大企業からコンサルへというルートが2006年時点で理想的なキャリアアップのルートとして取り上げられており、昨今のコンサル人気を考えると非常に示唆に富んだ記述である。
ゼロ年代前半のパラダイムシフト
もっとも、『若者はなぜ3年で辞めるのか?』に煽情的な文章が踊っていることを考えるにあたっては、当時の時代背景にも目を向ける必要がある。この本が刊行された2006年は、「既得権益を壊す」「自己責任で稼ぐが勝ち」といった思想が世の中に一気に広がっていった時期の真っただ中でもあった。
詳細は拙著『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』に譲るが、イラクにおける日本人の人質事件と小池百合子の言動によって「自己責任」という言葉が流行語大賞になったのが2004年。堀江貴文がプロ野球への新規参入を目指したことでライブドアとともに時代の中心に躍り出たのも同じく2004年。堀江がフジサンケイグループに買収を仕掛け、衆議院議員選挙に出馬したのが2005年。そしてこれらの背景にある、小泉純一郎が進めた構造改革。この時代において、20世紀から存在する価値観というのはぶち壊すべき対象ということになっていた。
「二十代は一方的に搾取されるだけなのです。優秀な若者は旧来の社会システムに乗るだけ損なのです。」
「だから僕は、もう一回大きなリセットが必要なのかもしれないと考えています。」
「いま必要なのは、そうした大きな変化です。旧世代から引き継いだばかばかしい社会システムを壊すことです。」
(堀江貴文『稼ぐが勝ち』知恵の森文庫、2005年)
堀江は自著『稼ぐが勝ち』において、これまでのシステムを壊すべきだというメッセージをはっきりと発信している。当時30代前半だった堀江は、自身を「若者側の代表」に位置づけることで社会のあり方に対する異議申し立てを行った。プロ野球への参入で渡辺恒雄を、衆議院議員選挙で亀井静香を仮想敵としていたこと、そして森喜朗が当時から堀江の言動に不快感を示していたことは、彼のポジショニングを考えるうえで非常にわかりやすい。
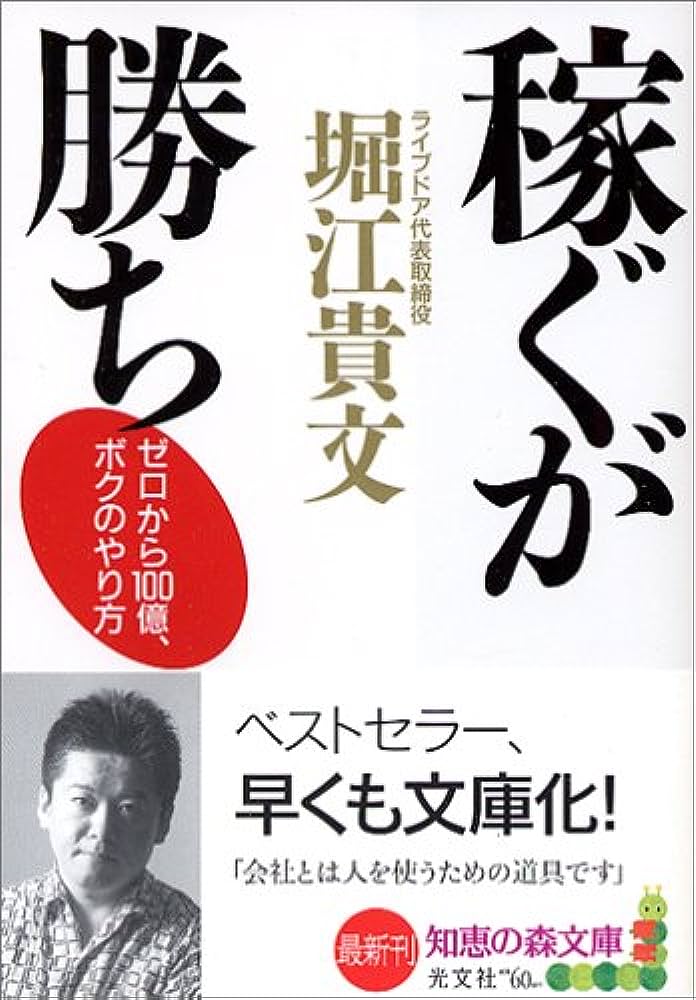
『稼ぐが勝ち』堀江貴文(知恵の森文庫)
堀江とライブドアをきっかけにして「ITで一発当てる」といった思考が広がり、出版社も従来の教養主義から実用書を起点としたビジネスにシフトしていく。『若者はなぜ3年で辞めるのか?』が刊行されたのは、まさにそんなタイミングだった。
考えるべきは、先ほども述べた通り「カウンター」だったはずの反動的な意見が、発信されてから15年以上経った今では「ベタ」に受け入れられていることである。ゼロ年代の初頭から半ばにかけて日本の社会はスクラップ&ビルドの一歩目に足をかけたタイミングであり、その時期において多少先鋭的でも何かを突き崩すための動きが価値を持つ側面もあった。『若者はなぜ3年で辞めるのか?』も、そんな流れの中の1つの産物と整理するのが自然だろう。そして、そういったラディカルな意見やアクションは一時的なものであるべきで、その後にくる「ビルド」のための方針があってこそ意味を持ち得るはずだった。
にもかかわらず、同書が掲げたメッセージは、大枠では2023年現在においても普通のものとして受け入れられている。「成長のためにレールを降りる」ことは推奨されても、降りた後に起こり得るリスクについて語られることは少ない。「リスクをとらないとリターンは望めない」というのも一理あるだろう。しかし、レールを降りた後に何があったとしても、レールを降りることを煽る人たちは決して責任をとってくれない。
「自己責任で稼ぐが勝ち」が掲げられた2004年からまもなくちょうど20年が経つ。自身のキャリアを考えながら成長のユートピアを探す2023年の若いビジネスパーソンは、ゼロ年代前半に猛威を振るった極端な考え方がその後じわじわと社会の根幹にまで浸透していく過程とともに大人になっていった。一方で、この20年はそんなアグレッシブな掛け声と裏腹に日本という国としての成長がどんどん停滞していった時代でもある。このアンビバレントな状況が、連載初回で述べたような「安定したい、だから成長したい」という一見すると歪な価値観につながっている。成長に囚われる人たちはどこか滑稽に見えるが、そこにはそうやって囚われざるを得ない理由が存在する。
(次回へ続く)

大学生や転職を目指す若手会社員、メジャーな就職先としてここ数年で一気に定着した「コンサル」。この職業が、若者に限らず「キャリアアップ」を目指すビジネスパーソンにとっての重要な選択肢となったのはなぜか?その背景にある時代の流れは、誰のどんな動きによって作られてきたのか?『ファスト教養』の著者が、「成長」に憑りつかれた現代社会の実像を明らかにする。
プロフィール

ライター・ブロガー。1981年生まれ。一般企業で事業戦略・マーケティング戦略に関わる仕事に従事する傍ら、日本のポップカルチャーに関する論考を各種媒体で発信。著書に『増補版 夏フェス革命 -音楽が変わる、社会が変わる-』(blueprint)、『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア、宇野維正との共著)、『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)。Twitter : @regista13。


 レジー
レジー










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

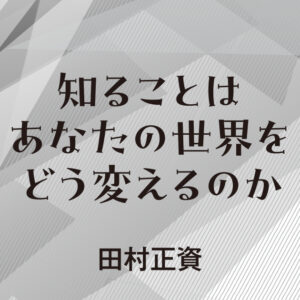
 田村正資
田村正資