西洋と東洋(中国と日本、シルクロード)で、産業革命よりも前にどのようなブラックボックスが生まれ、何が不可視化されたのかを辿っていきましょう。
まずは産業革命や現代の株式会社のもとになる制度を生み出した西洋の書物と貨幣、とりわけ紙幣の誕生を紹介し、次に産業革命前に人類史上最大の経済大国であった中国で紙幣が生まれたこと、当時の文学や出版の状況を概説します。そして東西を繋ぐ交易圏として、有名なシルクロードを捉え直します。シルクロードの東端として、奈良時代から平安時代の日本の姿も、見え方が変わってくるかも知れません。
産業革命以前のブラックボックス
現在のように書物が大量に印刷され、製本され、全国的な流通経路に乗って配本されるようになる前には、書物は大変に高価なものでした。流通経路が開拓されたのは日本では今から100年以上前、鉄道が整備され、新聞や雑誌と抱き合わせるかたちで割引き費用で鉄道の輸送に乗ったことがきっかけでした。書物の大量生産には、活版印刷技術とその技術の産業化が必要でした。産業が発展するためには、資本を効率よく掻き集めるための減価償却の発想が必要でした。その資本をもとに立ち上げられた会社が印刷や製本のコストを負担する出版の主体となっていきます。この「会社」、より正確にいえば株式会社が生まれたのは産業革命よりも前のことでした。
こうして産業化された出版業では、携帯可能な手のひらサイズの書物がたくさん製造されるようになります。この「手のひらサイズの書物」はルネサンス期の発明で、それ以前の書物はページ番号もふられていない、大型で持ち歩きにくい重厚なものでした。そもそもイスラム文化圏と地中海貿易や十字軍遠征などでかかわるなかでヨーロッパに植物性の紙が伝わってくるまでは、ヨーロッパでは羊や山羊などの獣の皮を薄く伸ばしたり削ったりして作る羊皮紙が書物の素材としては一般的でした。
羊皮紙は公文書や典礼書の書写などにも使われました。そのほか、古代から使われてきたパピルスの巻物を覆うための、冊子本における「表紙」のような使われ方もあったようです。パピルスは湿度変化に弱くいたみやすかったからです。
羊皮紙時代の書物についてもっとも知られた例は、世界的なベストセラーになり、名優ショーン・コネリーを主役に映画化もされたウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』でしょう。『薔薇の名前』の映画版には、キリスト教世界最大と言われる図書館(修道院の施設として登場します)の、小部屋を入り組んだ階段がつなぐ内部の様子が描かれています。その小部屋のそれぞれには、作品の舞台となった14世紀ヨーロッパキリスト教の主流派とは異なる思想を背景として描かれた書物が収められています。それらの書物のほとんど全てが巻物(巻子本)ではなく、1冊ごとに同じ判型のページからなる、ページの一辺を束ねて綴った本(冊子本)であることが、映画を見るとよくわかります。
『薔薇の名前』はその舞台こそイタリアにある修道院という閉鎖空間ですが、その図書館にはギリシャという異国から伝来した書物が保存されており、また主人公を含めさまざまな外国人が移動してくる場所でした。修道院という閉鎖空間は、書物と文化によって人々を引き寄せる場所であり、修道院がそのような場所になるためには、異国という別の場所、別の時代から、人々と同様に書物が掻き集められるということが必要でした。いわば修道院およびその図書館はブラックボックスであり、そこに書物や人々が滞在することで、そこに彼らが掻き集められる「過程」が不可視化されることになったのです。
書物が羊皮紙によって作られていた時代の西洋では、当然ながら紙幣も使われていません。紙幣が西洋に登場するのは17世紀になってからであり、それ以前の西洋の経済は硬貨を中心に営まれていました。『薔薇の名前』にも修道士が人々から税を徴収する場面が出てきますが、硬貨をジャラジャラと受け取っている様子です。
紙幣がヨーロッパで初めて登場したのは北欧のスウェーデン王国でした。当時のスウェーデンは30年戦争に参戦し、戦費に国の財政が圧迫されるようになっていました。30年戦争はフランス王家(ブルボン家)とハプスブルク家の対立に端を発し、カトリックとプロテスタントの宗教対立をも巻き込んで、ヨーロッパのほぼ全地域が参戦した戦争です。この30年戦争に参戦し、戦費のために金銀が不足したスウェーデン国内では銅貨が流通するようになっていましたが、銅貨はかさばるため、ストックホルム銀行が銀行券を発行してこれに代えたのです。これが西洋における紙幣の始まりです。
紙幣が生まれたのは、製紙法と同じく中国です。次は紙幣が生まれた頃の中国に目を向けてみましょう。
その頃の中国のブラックボックス
ヨーロッパ最初の紙幣の発行の経緯は、世界で初めて紙幣を発行した中国の経緯と酷似しています。人類初の紙幣は、10世紀中国(当時の王朝は宋。のちの南宋に対して北宋ともいいます)の四川地方で生まれました。この地域では銅の産出量が少なくつねに銅が不足していたため、代わりに鉄の硬貨(鉄銭)を使っていました。銅よりもさらにかさばる鉄銭は、少額の取引ならばまだ良いとしても、高額の取引にはまったく不向きでした。そこで、硬貨を預かって、その硬貨を預かった証として手形(交子)を発行する「交子鋪」が登場します。この交子が人類初の紙幣です。交子は木版で印刷されており、政府のお墨付きを得ることで単なる預かり手形ではなく、紙幣として機能するようになったのです。
交子の発行は政府の官業とされ、その発行益は政府の重要な収入源となったため、贋札づくりは大罪とされました。元日本大蔵省印刷局の植村峻の著書『贋札の世界史』には、世界初の紙幣誕生の直後から贋札づくりが横行した様子が描かれています。同書によれば、交子発行の背景には当時の反乱のために武器の製造が必要になり、それにともなって鉄の需要が高まり、鉄銭の製造が停止されたこともあったようです。
交子はたいへん便利だったため、また先に触れた発行益を政府が得られるため、流通量が次第に増えていきます。ある地域で流通する通貨量が増えると、一般的に物品の価格(いわゆる物価)が上昇し、これにともなってさらに通貨の発行が求められるという事態に陥ります。北宋政府は当初、四川産の高級紙を使って紙幣を印刷していましたが、やがて四川産高級紙の供給が追いつかなくなり、他の地方の質の悪い紙を原料に使うようになります。贋札の増加は、紙幣の原料紙の質が低下したことによって加速されることになったのでした。
ブラックボックスとしての交子が不可視化した要因は、ひとまず銅の不足や鉄銭の扱いにくさだったといえます。このことは、のちにヨーロッパで紙幣が生まれ、紙幣を発行する政府に準備金(紙幣と兌換するための金)が不足している状況が不可視化されたことに共通します。この時期に中国とヨーロッパとで、東西の空間的隔たりと、数世紀の時間的隔たりをこえて共有される不可視化は、現代に生きる私たちが日常的に使用している紙幣にまで受け継がれています。ブラックボックスである紙幣は、現代でもなお、その歴史を不可視化しています。
人類最初の紙幣を生んだ宋王朝が成立するよりも前に中国を支配していたのは唐王朝でした。唐の時代には、不思議な出来事を描く「伝奇小説」と呼ばれるフィクションのジャンルが生まれます。これらは「唐代伝奇」、あるいは宋代のものも含めて「唐宋伝奇」と言われたりもします。
この伝奇小説を元ネタに1920年に日本の芥川龍之介が発表したのが、童話として今でも広く親しまれている名作『杜子春』です。
『杜子春』は、中国経済の拠点だった洛陽とその近郊を舞台に始まります。裕福な家に育った主人公の杜子春が、財産を使い果たしてしまい途方に暮れていたところ、のちに仙人だということが判明する見知らぬ老人に声をかけられ、ある場所を掘ると黄金が手に入ると教えられます。言われるままに土を掘り返し黄金を得た杜子春ですが、数年でその財も濫費し尽くします。ふたたび途方に暮れているとまた老人が現れ、杜子春は黄金の場所をまた教わります。今度得られた財も数年で使い果たした杜子春は、またしても老人と出会い、黄金の場所を教わるのです。
しかしこのとき杜子春は「黄金はもう要らない、弟子にしてくれ」と老人に頼みます。このあと弟子入りを許された杜子春は、竹棒に老人と相乗りして四川省にある霊峰「峨眉山」へと向かいます。師匠となった老人は杜子春に「妖怪が現れても声を発してはならない」と言い置いて杜子春のもとを離れます。老人が不在にしている間に現れた妖怪によって地獄に落とされた杜子春は、痩せ馬に転生させられた両親に引き合わされ、なお声を発することを拒みましたが、息子を思う母親の言葉に思わず声を発してしまい、気がつくと竹棒に乗る前の洛陽近郊に戻っている、というお話です。
芥川が書いた『杜子春』は、唐代に書かれた同名の伝奇小説をもとにしています。岩波文庫『唐宋伝奇集』巻末に解説を書いた今村与志雄によれば、唐の時代までの小説(中国では「古小説」と呼ばれる)の作者は、その多くが歴史家でもあり、妖怪が出てくるファンタジー的な作品でも、当時の読者には現実と地続きのものとして受け止められていました。伝奇小説の成立過程でようやく、虚構と現実が分離し始めたというのです。
唐代の『杜子春』の作者は牛僧孺という政府の高官(宰相を歴任)で、同作者による『杵、燭台、水桶、そして釜』は主人公の名前を「元無有」つまり「元から何も無い」といって、虚構であることを明示しています。
実は牛僧孺の『杜子春』にも元ネタがあります。唐代の『杜子春』の元ネタには、のちに成立する『西遊記』で有名な三蔵法師玄奘が関わっています。玄奘は7世紀に唐から現在のインドのベナレスへ巡礼し、多数の書籍を持ち帰りました。『杜子春』はその玄奘が伝説を記して持ち帰ったものをもとに翻案して中国で書かれた作品群を参考にしているのです。また牛僧孺の『杜子春』の舞台は、唐代の洛陽を舞台にした芥川の『杜子春』からさらに500年ほど遡った6世紀(北周から隋)頃、政治の中心だった長安に設定されています。
なお牛僧孺の『杜子春』で描かれる貨幣は硬貨です。牛僧孺が生きた時代にはまだ紙幣が発明される前なので当然のことです。木版印刷で人類初の紙幣を作った宋の時代には出版文化が隆盛をきわめました。店舗を構えて書物を商う、いわゆる「書店」は、書肆や書賈などと呼ばれ、この宋朝後期(南宋)に中国の歴史で初めて登場しました。
ともあれ、芥川龍之介の『杜子春』も、牛僧孺の『杜子春』も、その作品を読んだだけでは、それぞれに元ネタがあることはわかりません。しかし芥川版では洛陽から峨眉山、牛僧孺版では長安から華山と、都市部から霊峰へ向かう移動が描かれています。霊峰で杜子春は死を経験し、地獄の閻魔大王の裁きを受けることになります。牛僧孺版では、芥川版よりさらに「移動」がワンステップ多く、女性に生まれ変わるところまで進みますが、『杜子春』のような短編でも物語や書物であれば、現実には不可能な移動が可能になるということが重要です。言うまでもなく、そこでは物語というブラックボックスが「移動」の現実にともなう肉体的、技術的な不可能を不可視化しているのです。そして、この不可視化の機能が唐代に伝奇小説を現実から乖離させることを可能にしたのでした。
日本、中世のブラックボックス
このようにしてユーラシア大陸の東側の中国で製紙法と印刷が発明され、大陸の西側のヨーロッパに伝わり、産業革命を経て出版産業が興隆するまでのあいだ、中国のさらに東に位置する日本では何が起きていたのでしょうか。
活版印刷術は16世紀にキリシタンの手により一度日本に持ち込まれますが、一般化することはなく、本格的に日本に伝わるのは開国直前の江戸時代末期、長崎でのことでした。
日本ではそれまで長らく木版印刷により、書物が作られてきました。そのルーツは8世紀に木版によって印刷されたロール状の経文、『百万塔陀羅尼』です。『百万塔陀羅尼』は現存する世界最古の印刷物です。
『百万塔陀羅尼』の事業の背景として、唐代の中国でつくられた「無垢浄光塔」という慰霊塔のことが、唐に留学していた僧から日本に伝わったのではないかと言われています。しかし、『百万塔陀羅尼』事業を開始した称徳天皇が崩御し次の光仁天皇が即位すると、この事業は継続されることなく中断されてしまいます。
高名な歴史学者でもある樺山紘一が館長を務める印刷博物館の『日本印刷文化史』では、称徳天皇で天武天皇系の皇統が途絶え、代わって現代まで続く天智天皇系の皇統になったこと、そして光仁天皇の次の代の桓武天皇による長岡京と平安京への遷都を『百万塔陀羅尼』事業中断の理由のひとつと見ています(「平安時代の印刷──ミッシング・リンク、宋版輸入、仏教版画」の章)。また桓武天皇の時代には、中国の唐王朝は衰退期に入っており、唐の影響下で始まった『百万塔陀羅尼』事業の意義も軽視されるようになったと考えられます。
9世紀に遣唐使を中断させた日中の文化的交流は、唐滅亡後の五代十国時代の混乱を経て、10世紀に中国を再統一した宋王朝の時代に再開されます。貴族や軍人を排して文治主義を行った宋王朝では文臣が文化を爛熟させ、先述のとおり木版印刷も隆盛をきわめました。この宋王朝の印刷文化と印刷物は海を越えて日本にも伝来したのです。このとき伝来した書物は「宋版」と言われて、その完成度の高さから珍重されました。
『源氏物語』のモデルとも言われ、摂関政治によって権勢をほしいままにしていた藤原道長は、この宋版をときの天皇である一条帝に献上しています。この一条天皇は学才に秀でた人物として伝えられており、その寵愛を受けるにあたって、宋版を献上するのは実に的確な贈り物だったといえるでしょう。その治世に『源氏物語』の紫式部や『枕草子』の清少納言が活躍したのも自然なことでした。
平安時代の日本では、たんに書物といえば「写本」(手写本)のことであり、印刷された本は「摺本」と呼ばれて区別されていました。日本では出版文化が未成熟だったため、「摺本」とは内容だけでなく見た目も美しい宋版のことだったのです。『百万塔陀羅尼』を平城京ごと捨て去って建設された平安京で、200年ぶりに印刷文化が再開されるのはこの頃以降のことになります。
『百万塔陀羅尼』も宋版も、海を隔てた中国の文化を帯びていることが重要です。どちらも、その知識のないものが見れば単なる紙でしかありませんが、その文字が中国の漢字であることや歴史的経緯を知る者にだけわかる情報が不可視化されて込められたブラックボックスだと言えるでしょう。
宋版は、日中貿易における中国(宋)側の主要商品のひとつでした。そしてこの頃の日本が宋から輸入していたもののなかには宋銭(銅で鋳造された硬貨)も含まれていました。末法思想の流行にともない、多くの仏具が求められ、その製造原料となる銅が大量に必要だったからです。
当初は硬貨に含まれる銅を求めていた日本でしたが、やがて12世紀に平清盛が台頭すると日宋貿易を振興し、さかんに宋銭を輸入して日本国内でも通貨として流通させるようになります。この時期、朝廷は絹を基準にしていたため、宋銭を基準にした平家と、従来の経済構造に依拠する朝廷との間で緊張が高まり、のちの平家滅亡の遠因のひとつになったとも言われています。
なお、宋銭が流通するようになるよりも前に日本には硬貨を鋳造する「鋳銭司」という役職があり、国産の銅貨や銀貨が作られていました。有名な和同開珎が作られたのは8世紀のことで、それまでは物でおさめることが義務付けられていた税に硬貨を含めることが許されるようになりました。
しかしこののち、硬貨の流通によって物価が上昇し、硬貨の流通量が追いつかなくなって硬貨の発行は停止されることになります。平清盛が宋銭を大量に輸入するようになるまで、日本の経済は硬貨を中心としない物品経済へと逆戻りしてしまいました。ただし、租税の物納や日本国外との貿易の価格や交換の基準として価格を定める法律(估価法)は存在し続け、物品経済に逆戻りしていた時期にも、価値の尺度としての通貨の役割は維持されていました。
シルクロードと旅するブラックボックス
平清盛が輸入して流通させた宋銭は、日本以外にも宋の周辺各国で広く利用されていました。宋本国ではすでに紙幣の流通が急速に発達しており、硬貨を他国に輸出しても問題がなかったのです。またなんといっても中国という大帝国のお墨付きがある硬貨であり、信用度が高かったものと考えられます。
もちろん、日本で宋銭を流通させようとした平清盛が、反対勢力である朝廷から「自国で製造していない貨幣を流通させるのは贋金を使うのと同じだ」という批判を受けたことは無視できません。清盛は反対派を弾圧し、あくまで宋銭流通を推進したのでした。宋銭の流通は鎌倉時代になってますます盛んになり、室町時代になっても当時の中国の王朝である明の硬貨(明銭)より信用されたと言われています。
さらにこの宋銭はユーラシア大陸の西方面、現在のイランにあたるペルシアやアフリカ大陸にまで渡っていました。これは唐の時代に確立したいわゆるシルクロードを往来した各国の商人達の手によるものです。
唐宋時代の伝奇小説には、ペルシアの影響を感じさせる作品が含まれています。唐はヨーロッパを含む当時の人類最大の経済大国であり、ペルシアから渡来してきた商人のための地区を設けたり、北方や西方の異民族とも積極的に交易を行っていました。唐の次の王朝が宋で、そのさらに次の王朝となるモンゴル系の元王朝には『東方見聞録』で有名なイタリア人マルコ・ポーロが、そしてその数十年後にモロッコ出身の旅行家イブン・バトゥータがそれぞれ訪れています。
マルコ・ポーロは中国へ向かう時には陸路、帰りには海路を使いました。イブン・バトゥータはアジアへの旅は海路が中心でした。イブン・バトゥータは自分が持参した金貨が、モンゴル帝国の首都では紙幣に両替しないと使えないことに驚いています。宋の後の時代なので、既に紙幣が普及していたのです。
ところで、シルクロードというともっぱら砂漠を行く「オアシスの道」が有名ですが、このほかに「草原の道」や「海の道」などがあります。旅行家たちが使った海路は「海の道」です。歴史家の森安孝夫はシルクロードを東西を繋ぐ単なる線状の「ロード」ではなく、南北の移動をともない無数の中継点をもつ面を構成するネットワークとして捉えることを提唱しています(『興亡の世界史 シルクロードと唐帝国』)。
もっとも、本国以外の土地で自国硬貨が流通するのは宋に始まったことではありません。紀元前8世紀に始まる春秋戦国時代(秦による統一以前の時代)から、鋤や刀のかたちをかたどった「鋤貨」「刀貨」が中国で鋳造され、周辺地域で流通していました。当時はそもそも現代のような1国1通貨の制度が普及しておらず、有力な王権が貨幣を発行して発行益を得つつ、その権威のもとで貨幣を流通させていたのです。
イブン・バトゥータを驚かせた紙幣はモンゴル皇帝の、そして紀元前の古代王朝の硬貨はその王朝の、それぞれの権力を秘めた「ブラックボックス」として、当時の人々のあいだで流通していたのではないでしょうか。貨幣たちは、権力を背景に帯びながら、しかしその権力との結びつきは明らかにせず不可視化しているのです。
近代化、現代化を通して、精度や技術を洗練させるなかで現代の私たちが手にしている書物や貨幣(あるいは電子機器を通して使用する書物や貨幣)は、このような来歴を不可視化して内包したブラックボックスだと言えるでしょう。
※次回は12月29日配信予定です。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


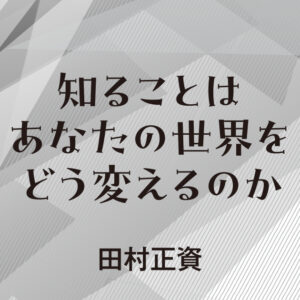
 田村正資
田村正資