
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第1回 池内了 「学問の自由」と軍事研究
最近もっとも注目を集めた「自由」に関する危機といえば、昨年10月に明るみに出た「日本学術会議の委員任命拒否」に端を発する「学問の自由」だと言えるでしょう。推薦された6名の新会員候補が、菅義偉首相により任命を拒否され今日に至っています。
この事件は多くのメディアによってセンセーショナルに取り上げられましたが、問題の核心はどこにあるのでしょうか。また、渦中の日本学術会議に対して、政府は研究成果が民生と軍事の両面で使われるデュアルユース(軍民両用)について検討するようにと要請を出し、揺さぶりをかけています。軍事研究は私たちの「自由」をどのような仕方で脅かすことになるのでしょうか。
シリーズ初回では、これらの問題について、様々な形で軍事研究に警鐘を鳴らしてきた物理学者の池内了さんにお話を伺いました。
明確ではない任命拒否の理由
日本学術会議の新会員6名の任命拒否問題について、私は菅義偉首相が任命拒否の理由を明確にしていないことに注目している。過去には1933年に滝川事件、すなわち当時の京都帝国大学教授であった滝川幸(ゆき)辰(とき)の著書『刑法読本』等を、政府が危険思想として名指しして同書を発禁処分にし、滝川教授を休職処分とした事件があった。だが、今回の任命拒否問題は、そのように政府側が何らかの理由を示して学問の自由を弾圧したというものではない。むしろ理由を明言しないことによって、我々に政権の意図を、積極的に忖度することを仕向けているように見える。マスメディアも含めて、首相の意図をあれこれと推測した挙句、任命拒否されたあの6名の思想・信条・行動が問題なのであろうという議論になってきたことがそれを証明している。
つまり、私の見方は、我々があれこれ忖度をさせられている現状は、任命拒否の理由を明確にしない菅首相の作戦に見事に引っ掛かっているのではないかというものである。
学術会議の知名度の無さ
菅首相の作戦と言ったが、これが考え抜かれて打たれた手なのかどうかは疑わしい。たまたまそのような流れになっただけの可能性がある。しかし、それが結果として、人びとやマスメディアに、日本学術会議の側に何か落ち度があったから拒否されたのではないかと忖度をさせてしまっている。ここにポイントがある。
日本学術会議が政府に批判的な団体だから忌避されたという議論があるが、その指摘はあたらないだろう。むしろ、政府にとって日本学術会議はこれまで便利な存在でもあったはずだ。例えば2010年、内閣府原子力委員会委員長は日本学術会議に対して「高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組みについて」と題する審議依頼を出した。これに対する日本学術会議の回答「高レベル放射性廃棄物の処分について」では、「いきなり最終処分に向かうのではなく、数十年から数百年程度のモラトリアム期間を設けて暫定管理せよ」という提案を出している。
このように、政府として直接の回答を出しづらい、扱いに困るような厄介な問題については、政府は日本学術会議にいわば下駄を預けることで落としどころを見つけることができた。これは政府にとっても好都合だったはずだ。最近では、費用負担が大きいILC(国際リニアコライダー)を断るのにも日本学術会議を利用している。だから、日本学術会議は学者たちによる独立性があり、第三者的に政策などの検討・批判ができるという意味で、あくまで政府にとって使い勝手のよい組織としてあり続けてほしい、というのが政府の思惑でもあると思う。これが民間団体となると、その提言は説得力を欠くものになってしまうからだ。
日本学術会議はこのほかにもいろいろな答申や提言を出している。しかし、社会にはそれが全くと言ってよいほど知られていない。そもそも、今回の問題が起きて初めて「日本学術会議」の存在を知ったという人も大勢いる。この知名度の無さが今回の任命拒否問題についての議論の錯綜や、その根底にある疑心暗鬼に拍車をかけているようにも思う。
軍事技術と民生技術
任命拒否問題が起きてから、政府はあたかも日本学術会議に揺さぶりをかけるかのように、「時代の変化に合わせて」デュアルユースについて再検討せよと日本学術会議に対して求めたようである(2020年11月17日、参院内閣委員会での井上信治科学技術担当相発言)。この件は、今回の任命拒否問題とは本来直接の関係はないはずだが、日本学術会議をめぐる議論に何らかの影を落とし始めているようなので、ここで検討してみよう。
デュアルユースとは、科学技術の用途の両義性、つまり科学技術が軍事的にも、民生的にも、両面に使えるということで、通常「軍民両用」と訳している。デュアルユースの代表例としては、軍事レーダーに使われていたマイクロ波が食品を透過加熱できることを利用して開発された電子レンジ、潜水艦や軍隊や人工衛星の位置を確定するためにつくられたGPSなどが典型であろう。
デュアルユースについては、軍事技術を民間にも活用できるからよいのだという議論もあるが、電子レンジもGPSも、必ずしも軍事技術としてでなければ開発できなかったものではないことを指摘しておかねばならない。むしろ、軍事用に開発された技術は軍事機密とされてきたため、その技術が公共財としてオープンになるのが遅れたといえる。
つまり、デュアルユースの実態とは、軍が開発した技術のうち、もはや秘匿の必要のない、いわば賞味期限の過ぎたものを一般に開放しているだけなのだ。マイクロ波の技術もGPSも、初めからオープンにしていたら、もっと早くから電子レンジやカーナビが作られていたのではないだろうか。軍事用であれ、そもそも税金を注ぎ込んで開発された技術なのだから、秘匿される筋合いはないと言うべきだ。
軍は国防を理由にして、政府から金をもぎ取って潤沢な研究費を有している。その金を集中的に投資するのであるから、いろいろな発明品がつくれるのは当然のことと言える。マイクロ波利用やGPSが開発されたのは、軍用だったからこそというわけではなく、単に資金が潤沢にあったからにすぎない。その金を、例えば政府が、日本学術振興会を通じて基礎研究のために出したら、もっと使いやすい成果がもたらされたはずだ。つまり民生用の科学研究のための予算とすればよいわけであって、戦争や軍事開発を目的にしなければならない理由はないのである。
科学と資金
デュアルユースに前向きな研究者もいる。その最大の理由は研究資金であろう。
日本では大学等に提供される基礎研究に対しての資金が非常に少ない。日本学術会議の年間予算10億円というのも、政府の予算規模からすれば大した金額ではない。2020年2月以降に全世帯に向けて配られた「アベノマスク」は予算総額が約466億円で、日本学術会議のおよそ46年分にあたる。Go Toキャンペーン全体の補正予算も含めた総予算は約2.8兆円とのことだが、その金のいくらかでも科学技術振興に使おうという考えが見えない。これは学問と、より広く言えば文化をバカにしているということではないか。
芸術の分野でも事情は同じだろう。例えば文化庁が愛知トリエンナーレに出した補助金は6600万円である。文化に対する国の支えは非常に弱く、薄い。そうした中で日本の文化人たち、すなわち個々の演劇人、映画人や美術家たちが相当な努力をして、国際的な評価を得ているのである。日本の文化は個々人の努力によって辛うじて支えられている。
科学者の場合、産学協同で企業からの委託研究費が得られるプロジェクトにはそれなりに潤沢な資金が流れているようだ(税金が控除されるためもある)。しかし、産学協同のプロジェクト、つまり企業がスポンサーとなる競争的資金には3年や5年などといった期限があり、その期限内に成果を出さないと契約が更新できない。となれば、おのずと「期限内に成果が出るテーマ」しか選ばなくなるため、本来はクリエイティブであるはずの研究が、ハードルのさほど高くない「練習問題もどき」ばかりになり、研究のスケールも小さくなっていく。だからこそ日本の国際的な論文競争では論文数が減り、引用数の多さでも順位が落ちている。構造的に質の高い仕事がしにくくなっているのが、日本の科学界の現状だ。
科学者には、与えられたプロジェクトばかりをこなす以外の、独自の研究をしたいという気持ちがある。実は、そうした研究者が本当にやりたい基礎的な研究の予算は数百万円程度で済むものが多いのだが、現状ではその予算確保が難しい。ましてや、理工系や生命科学系の実験設備を必要とする研究で、予算が1千万円や3千万円などという規模になると、日本学術振興会の科研費も非常に競争率が高く、応募するだけでも大部の書類を準備しなければならない。
こうした規模の研究費を比較的容易に出してくれるのが防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」(2020年度予算は95億円)である。軍事装備品の性能は戦争の勝敗を左右するため、最先端の軍事技術の開発には惜しむことなく費用が注がれるのである。この制度に採用されれば、プロジェクトによっては20億円単位の資金が提供される。そこで、軍事に利用されるデュアルユースでもいいじゃないか、研究さえできればいいのだから、という気持ちで応募するのである。
なぜ人文社会科学系が標的とされたのか
科学者が軍事研究に取り組むことについては、日本学術会議では検討を行い、2017年に、軍事研究に対する声明「軍事的安全保障研究に関する声明」を公表している。
声明では、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度について、「将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の専門家でなく同庁内部の職員が研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究への介入が著しく、問題が多い」と指摘し、「研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的のためにも使用されうるため、まずは研究の入り口で研究資金の出所等に関する慎重な判断が求められる」と述べている。
つまり、デュアルユースには軍事転用の危険性があり抑制的であるべきだというのが、日本学術会議の姿勢であった。このような経緯を踏まえると、今回、政府が日本学術会議に「時代の変化に合わせて」デュアルユースの再検討をするように求めてきたというのは、この声明を変更せよという意味だと受け取れる。
この要請(圧力?)にどうこたえるか。先に見たように、研究資金不足に悩む理工系の研究者たちからデュアルユースもやむなしの声も上がる中、日本学術会議は難しい問いを突き付けられたことになる。ここで新会員6名の任命拒否が結果として重要になってくるように思われる。
日本学術会議は、人文・社会科学系の会員から成る第一部と、生物学・医学などの生命科学系による第二部、理学・工学系の第三部から構成されており、自然科学系の第二部・第三部と人文・社会科学系の第一部とでは議論の傾向が違う。
今回、任命拒否された6名は、それぞれ歴史学、キリスト教学、政治学、憲法学、行政法学、刑事法学を専門とする、いわゆる人文・社会科学系の研究者であり、全員が第一部に所属する予定だった。もちろん、軍事技術に直接かかわる人たちではない。しかし、科学技術政策も含めて、さまざまな施策に対する批判や異論などの提言が出されるのは、人文・社会科学系の学者たちが属する第一部の部会からであることが多い。
先に触れた日本学術会議の「軍事的安全保障研究に関する声明」は、全分野から研究者たちが「安全保障と学術に関する検討委員会」を組織して議論をとりまとめて声明文をつくったのだが、こうした仕事は一般には理工系の人間の苦手とするところで、人文・社会科学系に知恵者が多い。デュアルユース問題の再検討でも働きが期待される人々である。
こうしてみると、政府が、人文・社会科学系の6名を任命拒否したのは直接の「思想の弾圧」というより、日本学術会議を弱体化させるために、あらかじめ知恵者を切っておく意味があったのではないかと邪推してしまう。菅首相が理由を明確に述べない以上、その真意を忖度しても仕方がないが、少なくとも結果として、そうした事態を招きかねないことは確かである。
学問の自由と公共財としての知
学問は自由なのだから軍事研究をしても構わない、むしろそれを抑制することこそが「学問の自由の侵害」にあたるのではないか、と言う方がおられるかもしれない。そうした方には次のような問いを投げかけたい。「ならば、あなたは人体実験や優生学であっても許容するのですか?」と。学問の自由とは、単に個人の好き勝手な研究を無制限に許容するということではない。社会的な合意や研究者自身の良識により、そこには一定の規範・節度が必要とされるべきだ。そして、軍事研究はそうした規範に照らして批判的検討を行うべき領域に他ならない。
もともとの「学問の自由」の出発点は、学問研究に権力からの圧力や介入が無いということである。だからこそ大学の自治は学問の自由の大きな要素なのである。言い換えれば、権力からの干渉を少しでも招くような行為は、学問の自由を壊すことにつながる。防衛装備庁からの委託で軍事研究を行うと、必ず干渉があり、同庁はその成果を軍事機密として秘密にしようとするだろう。それは学問の成果が公共財としての知、「公共知」であることに反するということを意味し、学問の自由は窒息させられるのである。
学問と国家の関係をやや単純化して言うならば、国家は「金は出しても口は出さない」というのが学問にとって、また社会にとって望ましいあり方だろう。軍事に限らず、国家が何かに役に立つことを学問に求めると、学問が歪む。学問には役に立つものもあるし、すぐには役に立たない分野もある。後者の役に立たないように見える分野も含めて学問であり、国は干渉・介入すべきではない。
今、子どもたちに一番人気のある科学の分野は、宇宙と恐竜だという。博物館が展示のテーマに困ると「宇宙展」か「恐竜展」を企画するらしい。宇宙を扱う天文学も、恐竜を扱う古生物学も、ある意味では「役に立たない」分野だ。また、数学や哲学などの理論的な学問も、一見すると何の役に立つのかわからない。しかし、宇宙の果てや太古の生物に思いをはせたり、抽象的な理論をアレコレ自分で考えたりすることは、「役に立つ」と宣伝されていることよりも往々にして面白く、また誰に対しても間口が広い。市民の知的関心をかきたてる知識こそが本当の「公共知」と言えるのではないだろうか。
大学の研究者は、市民から「公共知」の創造を負託されており、学者が生み出す知的成果は公共財として人々が自由に使えるようにしなければならない。学問は市民とのそうした契約関係の上に成り立っている。市民の負託にこたえることこそが大学の存在意義であり、研究者の使命なのではないか。
構成:広坂朋信
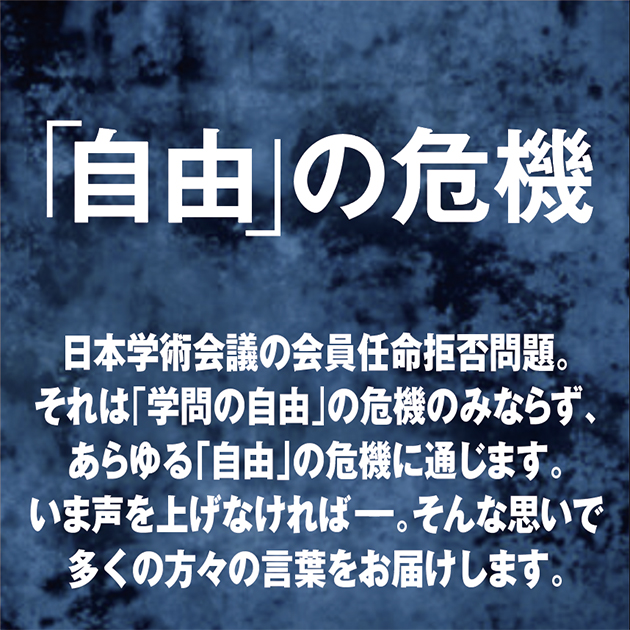
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール

1944年兵庫県生まれ。京都大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。名古屋大学名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。『科学の考え方・学び方』で講談社出版文化賞科学出版賞(現・講談社科学出版賞)を受賞。著書多数。


 池内 了(いけうち さとる)
池内 了(いけうち さとる)









 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


