
集英社新書編集部では、「自由の危機」と題して、いま、「表現の自由」「学問の自由」「思想信条の自由」「集会の自由」など、さまざまな「自由」が制限されているのではないか、という思いから、多くの方々にご参加いただき、広く「自由」について考える場を設けました。本企画の趣旨についてはこちらをご覧ください。
コロナ禍という特殊事情もあり、「自由」はますます狭められているように思います。こうした非常時の中では、それについて考える余裕も奪われていきますが、少し立ち止まって、いま、世の中で起きている大小さまざまな「自由」の危機に目を向けてみませんか? それは、巡り巡ってあなた自身の「自由」に関わってくるかもしれません。
第2回 阿部公彦 国策は学問を育てられるのか――「親子関係」の行き着くところ
2020年秋、日本学術会議問題とほぼ同時期に東京大学で、総長選挙をめぐり異例の混乱が生じていました。
大学と言えば「学問の自治」や「自由」の象徴的存在です。そのため、この出来事は、とりわけ大学関係者の間で衝撃をもって受け止められました。
総長選挙の混乱はどこに原因があったのでしょうか。これは日本学術会議の会員任命拒否問題に通底するところがあり、まさに「自由」の危機そのものと言えます。近年の「大学」を取り巻く社会的・政治的圧力とは、いかなるものなのでしょうか。そして、21世紀の大学はいかなる存在であるべきか。東京大学文学部教授の阿部公彦さんに論じて頂きました。
東京大学は「国策大学」なのか
2019年は大学入試が大混乱した年だった。すでにその数年前から制度の是非をめぐってさまざまな声があがり、大学側の対応も紆余曲折している。そんな中、政策を主導する立場にあった安西祐一郎・中央教育審議会元会長が、「読売新聞」のウェブ連載で東京大学を厳しく批判するという一幕がある。
「改革」の目玉政策の一つは英語民間試験の活用だったが、東京大学はいくつかの未解決の問題があるとして活用をためらった。安西氏は苛立ちを隠さず、下記のような発言を行っている(異見交論55「東大の見識を疑う」安西祐一郎・中央教育審議会前会長 https://kyoiku.yomiuri.co.jp/rensai/contents/55.php)
「東大は国民の負託を受けて多額の税金が注入されている明治以来の国策大学だ。(中略)東大は国家のための大学として、世界の転変の中でわが国と世界の未来を創っていく、またそのためにリーダーシップを取れる卒業生を多数輩出して世界の一流大学として人材ネットワークを創り上げていく、その牽引者たるべき責任がある。現状の東大入試は、この大きな責任を全く果たせていない。
安西氏は、東大が英語民間試験を採用しないことを理由に「大きな責任を全く果たせていない」と考えたようだ。しかし、民間試験の活用はその後、さまざまな構造的欠陥があることが明らかになり、実施直前になって中止に追い込まれる。皮肉なことに東大は民間試験の採用に慎重さを示すことで「責任」を果たしたとも言えよう。しかし、今、問題にしたいのはそのことではない。
仮にも中央教育審議会の会長だった人物が、「国策大学」という言葉をこうした形で平然と使ったのである。衝撃を受けた人も多かった。まるで明治時代に逆戻りしたかのような「富国強兵」のレトリックがそこには垣間見える。もし、こうした考えに違和感を抱かない人が再び増えているのだとしたら、あらためて立ち止まり、私たちの今いる地点を見つめ直すべきではないだろうか。以下、本稿ではこうした「国策大学」的な発想こそが、大学政策の混乱と迷走を引き起こし、ひいては大学の健全な発展をさまたげていることを示したい。その理解の助けとするべく使うのは、「親子関係」という補助線である。
東京大学の「負の遺産」
東京大学には「東京大学憲章」なるものがある。大学のいわばマニフェストであり、その精神的な土台を形成する重要な文言だが、通常、教職員も学生もほとんどその存在に注意を向けない。東京大学憲章があらためて注目を浴びるのは「有時」のときだけである。今、まさにその有事が訪れたと言えるだろう。
その前文には次のような一節がある。
東京大学は、1877年に創設された、日本で最も長い歴史をもつ大学であり、日本を代表する大学として、近代日本国家の発展に貢献してきた。第二次世界大戦後の1949年、日本国憲法の下での教育改革に際し、それまでの歴史から学び、負の遺産を清算して平和的、民主的な国家社会の形成に寄与する新制大学として再出発を期して以来、東京大学は、社会の要請に応え、科学・技術の飛躍的な展開に寄与しながら、先進的に教育・研究の体制を構築し、改革を進めることに努めてきた。
「それまでの歴史から学び、負の遺産を清算して平和的、民主的な国家社会の形成に寄与する新制大学として再出発を期して……」を読めば、安西氏の唱える「明治以来の国策大学」という構図が明確に否定されていることははっきりしている。そして前文は下記のような一節で締めくくられる。
日本と世界の未来を担う世代のために、また真理への志をもつ人々のために、最善の条件と環境を用意し、世界に開かれ、かつ、差別から自由な知的探求の空間を構築することは、東京大学としての喜びに満ちた仕事である。ここに知の共同体としての東京大学は、自らに与えられた使命と課題を達成するために、以下に定める東京大学憲章に依り、すべての構成員の力をあわせて前進することを誓う。
ここでは、かなり意識的に「開かれ」「差別から自由な知的探求の空間」といった表現が使われていることが重要だ。開かれていることと、そして自由であることこそが、「負の遺産」を清算するための最大の理念となったのである。もちろん、これは東大に限ったことではない。日本の大学は――そして学問と知は――このような形で新しい出発を果たしたのである。
国策大学に未来はあるか?
では、なぜ決別したはずの「負の遺産」がいまだに亡霊のように頭をもたげるのだろう。なぜいまだに、国策大学として国家権力に盲従し、国益の増大に資するのが大学だといった論調がまかり通るのだろう。
スペースを節約するために、ここで箇条書きで論点を整理してみたい。どこで議論がねじれているかが明確になるはずだ。以下、安西氏の奉ずる「国策大学」という理念を立て、それと連動する考えをならべてみる。
国策大学は……、
国家の利益を最優先する。
国家の利益は権力者の主導の下に示され、追求される。
国家の利益は、結果的に国民を幸福にする。
国家の利益はときに、他の国家の利益とは対立する。
国家の利益を追求する権力者は、その目的を達成するために権力遂行を阻害する者を排除する。
国家は大学に資源をつぎ込むのだから、当然、大学は国家に対し相応の役割を果たす、つまり「恩返し」をすることが期待される。
グローバル化の時代にあって、大学は日本という国家の国際競争力を高めることでその役割を果たす必要がある。
国策大学という看板をかかげるときに、こうした思考が付随的に連鎖することには異論はないだろう。はっきりするのは、国策大学という理念が「国家の利益」という概念を設定することなしには成り立たないことである。国策大学という理念に賛成する人もそこには反論しないはずだ。
しかし、国家の利益とはいったい何だろう。国益という考えはときに「グローバル化」という言葉の連呼とともに唱えられることが多いが、そうした「グローバル化」というフレーズの連呼でイメージされるのは、国際舞台に日本という国が飛び出していき、オリンピックに出場する選手さながら日の丸を背負って、より多くの金メダルの獲得を目指すという構図である。
残念ながら、そんなグローバル舞台はどこにもない。誰もが実感しつつあるように、グローバル化の正体は、もはや実質的には「母国」をもたない(つまり「母国」にそれほどの税金も払わなければ、「母国民」を大量に雇用することもない)多国籍企業の巨大化であり、ライバルと目される他国の企業にも部品を提供する複雑な供給システムの広がりである。人材の流動化は進み、たとえ「日本の企業」であっても、日本で生まれたのでもなければ日本国籍もない、あるいは日本語を母国語ともしない社員の力なくして機能しなくなりつつある。東大でも、もっとも大きな工学系研究科では、博士課程に在籍する学生の半数は外国人学生なのである[i]。こうした事例からもわかるように、もはやどこまでが「日本」という国なのか、その線引きができなくなりつつあるのが現実なのだ。
そんな中で、まるで日本という国が一丸となって他の国と競争し、「国益」を追求しているのだ、といった見方に執着することにどんな意味があるのだろう。むしろ、こうした状況で「国益」にとらわれることには弊害の方が大きく、それがもっとも如実にあらわれるのがまさに大学なのである。大学に集まる人材の多くは、将来、日本の国益を増進しようなどとは全く思っていないだろうし、そんなことを「義務」として押しつけたら、人材は集まらなくなる。ところが大学を改革すると称する議論は、いまだに旧態依然とした「国益」理念を隠し持ち、そのためにさまざまな制度に歪みや矛盾が生ずることになる。
悪名高い「改正国立大学法人法」
その歪みの典型が、大学の学長選考について規定を設けた「国立大学法人法」(2014年改正)である[ii]。この法律はかねてから問題点が指摘されていたが、2020年、あらためて注目を浴びることになる。この年、東京大学や筑波大学で学長選考が行われたのだが、その透明性や公平性をめぐってさまざまな批判が起きた。東京大学では総長選考会議の秘密主義や候補者選出の不透明さが問題となり、さまざまなルートから公開質問状や要望書が出された上、選考会議の音声まで流出し大きな混乱が起きた[iii]。筑波大学では、現役の学長が学長任期を撤廃、しかも教員による意見聴取(意向投票)を無視し、学長自身が選んだ選考会議メンバーによって自ら学長として再任されるという驚くべき事態も起きている。いずれの場合も波乱の要因となったのは、学長選考会議への過度な権力の集中だった。それを可能にしたのが、悪名高いこの「国立大学法人法」だったのである。
法律でとくに問題となるのは、学長選考の方法を規定する「留意事項」の記述である。この箇所、実にわかりにくく書かれているのだが、この「わかりにくさ」が、まさにこの法律とその背後にある考え方の歪みを間接的に示していると思われるので、まずは原文そのままの引用を示す。是非、その「わかりにくさ」を味わっていただきたい。
なお,選考の過程で教職員による,いわゆる意向投票を行うことは禁止されるものではないが,その場合も,投票結果をそのまま学長等選考会議の選考結果に反映させるなど,過度に学内又は機構内の意見に偏るような選考方法は,学内又は機構内のほか社会の意見を学長又は機構長の選考に反映させる仕組みとして設けられた学長等選考会議の主体的な選考という観点からは適切でない(以下、略)。
あまりにわかりにくいので、英文解釈教室風の整理をしてみよう。挿入的な部分を括弧に入れ、フォントの色を変えると以下のようになる。
なお,(選考の過程で教職員による,いわゆる意向投票を行うことは禁止されるものではないが,その場合も,)投票結果をそのまま(学長等選考会議の)選考結果に反映させる(など,過度に学内又は機構内の意見に偏る)ような選考方法は,(学内又は機構内のほか社会の意見を学長又は機構長の選考に反映させる仕組みとして設けられた学長等選考会議の主体的な選考という観点からは)適切でない(以下、略)。
挿入部分をいったん取り除いてみれば、何のことはない、要するに「投票結果をそのまま選考結果に反映させるような選考方法は、適切でない」というごくシンプルな文なのだ。ところがこのシンプルな文にあれこれと挿入が入っている上、言葉の重複もあって、日本語母語話者が読んでも眩暈がしそうな文章になっている。
なぜこのようなことになったのか。それはおそらく、「投票をしてもいいが、その結果は無視せよ」という文言をそのまま出すと、さすがに理屈が破綻していると思われてしまうからだと考えられる。それを避けるために、あれこれ言い訳めいた挿入が入れられた。たとえば教職員による「投票」には、「過度に学内又は機構内の意見に偏る」といった修飾語をつけ、あたかもそれが偏向しているかのように貶める。逆に「学長等選考会議」には「学内又は機構内のほか社会の意見を学長又は機構長の選考に反映させる仕組みとして設けられた」といった説明をつけることで、その正当性を強調しようとする。ところが、こうしたレッテル貼りや正当化が、わかりやすく納得のいく文章として形になってはいない。その原因は単にこの一節の執筆者が文章が下手なためだけではなく(それも一因かもしれないが)、そもそも書き表そうとしている内容に無理があるからだ[iv]。
「社会」と「主体」には要注意
とくにその言い訳めいた正当化で鍵になるのは、「社会の意見」とか「主体的な」といった文言だ。教職員による投票よりも選考会議の判断が優先される根拠として、選考会議が「社会の意見」を反映するかのような言い方がされているが、筑波大学の例を見てもわかるように、学長を選ぶ会議のメンバーを学長自身が選んでいるわけだから、「社会」どころか、ごく少数の構成員からなる集団がほとんど権力を私物化するようにして学長選考を行っていると言ってもいい。
選考会議に過大な権限を与えるに際し「主体的な」という言い方がされるのも奇妙である。教職員の意見は取り入れないと言っているわけだから、大学の自治は限りなく抑圧している。その一方、選考会議には絶対的な権限を与えるという。そこで使われるのが、うっすら道徳性をにじませた「主体的」という言葉なのである。
「主体的」という言い方をわざわざするからには、その背後に明確に「主体」が見えるべきだろう。しかし、肝心のその部分は実にあいまいだ。そもそも選考会議とはいったいどのような「主体」なのか。この会議はあくまで大学という機関に奉仕すべき存在ではないのか。ところがいつの間にか、この会議には「主体」という名の下に絶対的な、ほとんど独裁的なほどの権限が与えられることになる。どうしてこういうことになるのだろう。前出の「社会の意見」なる表現が、実体不明のまま選考会議の権限を支えるのに都合良く使われていることにも注意したい。「社会の意見」を反映させるというのならまずは多様な声に耳を傾けることから始めるべきだ。ふつうに考えるなら、その第一歩としては大学構成員の意見に耳を貸すことになるはずだ。
本来の「主体」がどこにあるかを慎重に考えることなく、「主体的」といった言い回しを粗雑に使うことで、今や、学長選考会議なる組織が大学の「主体」を代表しうるかのように誤解されつつある。もちろん、会議にはそれほどの権限はないはずだ。しかし、「主体」という概念を半ば意図的にあいまいにしてきたために、学長選考会議やこの会議で選ばれた学長の権力ばかりが、制動装置の外れた権力機関のように暴走しつつある。
強制された主体性の裏にあるもの
そもそも主体性なるものは、上から強制されるものではない。こうした強制された主体性には、表には出ない「内面化された従属意識」がまぎれこみ、本来の主体性とは程遠い、権力者の顔色をうかがうような忖度へとつながる。実際、東京大学や筑波大学を含め各地の国立大学で起きている選考会議の迷走から見て取れるのは、選考会議のメンバーが政権に近い人物たちから構成されることが多く、しばしば偏った判断をする上、それを強行しようとして学内の反発を呼んでいるということである[v]。
あらためて問おう。なぜ、選考会議のイニシアティブがそれほど重要なのか。限られたメンバーによる決定では、かえって恣意的な判断が行われ、党派的な利害関係が優先されたり、場合によってはメンバーの能力不足からまったく適切でない決定に至ったりする危険はないのか。にもかかわらず、なぜそのような権限の集中を行うのか。理由として考えられるのは、一部の人間が恣意的な判断を行えるような枠組みをつくれば、上からのコントロールが容易になるということだ。つまり、この法律の下では大学の主体性は形骸化し、上位の権力に従うことでしか「主体」のあり方が保証されなくなる。しかも、「社会の意見」とか「主体的」といった言葉をちりばめることで、そうした権力の痕跡も見えなくなっている。
主体性を上から強制するという矛盾に満ちたジェスチャーには、こうした目論見が透けて見える。その背後には明治以来の大学像が依然として残っている。親としての国から命を受けた大学が、もはや親には計り知れない知の領域を「主体的」に開拓しつつ、親の恩は忘れずにその意志を「主体」の中に内面化し、最後まで従属意識は捨てずに親の役に立とうとするのである。
しかし、「国立大学法人法」の「留意事項」のおさまりの悪さからはからずも露呈したように、もはやこうした大学像には無理がある。私たちにはより新しい大学像の構築が必要なのである。国家権力が大学に対し、まるで親が子に対して育てたことの恩返しを求めるような、つまり疑似親子関係を盾に服従を要求する時代は遠く過ぎ去った。権力は、もはや「日本」というわかりやすい「利益集団」を代表しえなくなったし、大学の「責任」も国益や日本といった単位に向けられるべきではない。「国立大学法人法」にとってつけたように組み込まれた「社会」という理念を精査し、よりわかりやすい形で大学をめぐる議論に生かす必要がある。
大学の未来像
では、具体的にはどうすればいいか。東京大学憲章にすでにその答えは書かれている。大学というのは「場」にすぎないのである。国家のために「知の兵隊」を供給する練兵場でもないし、敵が攻めてきたときに防衛を担う「知の防塁」でもない。さまざまな人が訪れ、滞在し、交流し、やがては去っていく通過点なのだ。それがまさに知のグローバリズムなのである。ここには国家という枠とは異なる、「公共」という理念が必要だろう。国際競争ということを言うなら、日本チームが何位にくるかを競うよりも、大学が公共の「場」として、世界に向けどれくらい魅力的に見えるか、どれくらい人々が「通り過ぎたい」と思うかを考えるべきなのである。
繰り返すが、大学政策にはもはや「親子関係」モデルは通用しない。国立大学法人法には明らかに「子」を指導するかのような「親」の態度がありありと出ているが、強制された偽りの主体性は一部権力者、利権者の意思を大学運営に反映させる装置となるにすぎない。東大、筑波大などの学長選考の混乱から見えたのも、一部の狭いサークルの人物たちが大学の運営を支配しようとするという構図である。グローバル化といいながら、まるで明治時代のように国と大学が一体化して国威を発揚するかのような姿勢がそこに確認できるとしたら驚かざるを得ない。グローバル化した世界で、これほど奇妙なふるまいはないだろう[vi]。
大学の学長がどれくらいの激務かは、少しでもその近くにいたことのある人間ならすぐにわかる。大学は巨大化し、その業務はどんどん複雑化している。それぞれの業務の専門化も進んでいる。「リーダーシップ」の名の下に権力を集中しようとすればするほど、権力は機能不全に陥る。むしろいかに上手に権力を分散するかが組織の安定には求められているのだ。分散しつつもバランスをとり、不必要な停滞を避けつつも、過度の性急さや偏りを避ける、そんなシステムの構築が必要なのである。
国家の線引きがあいまいになり、国民なる概念が自明のものでなくなっていけば不安になる人も多い。そんなときにもっとも手軽に「国らしさ」を誇示するのは軍事力だろう。野球チームと同じで何より重要なのは指揮系統。軍隊は集権的なシステムなしには機能しえない。だからこそ、権力者は軍事力にこだわる。これほど国家権力の存在感を示すものはないのだから。そしてそれが彼らの支持率にもつながるのだから。
権力にとどまるために政治家は、権力そのものの演出をせざるをえなくなってきた。粛々と法に従っていては、権力は権力に見えなくなる。むしろ法を踏み越え、ときには破ること。そのことではじめて権力らしさを見せつけることができる。そういうふるまいこそが、権力者に権力者らしくふるまってほしいと思う人びとを魅了することを彼らは知っている。そういう意味では、彼らにとって日本学術会議の任命拒否は一石二鳥だった。軍事研究に第一歩を大きく踏み出すための示威行為であるとともに、権力そのものの自己演出だったのだから。もちろん、これが非常に危険な火遊びであることは間違いない。
【注】
[i] 工学系の博士課程在籍者1156人のうち外国人学生は559人(2020年11月1日現在)。人文社会系研究科でも、とくに日本関係の研究をしている分野では外国人学生の比率は高く、年度によっては半数以上が外国人学生ということもある。
東京大学HP「学生数の詳細について」https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400150866.pdf (2020年11月22日閲覧)
[ii] https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351814_7.pdf 参照。(2020年11月22日閲覧)
[iii] 東京大学総長選考の混乱については「2020東京大学総長選考を考える」に詳しい。当時の記事へのリンクもある。http://2020sochosenkofrage.mystrikingly.com/ (2020年11月22日閲覧)
筑波大学の状況については「筑波大学の学長選考を考える会」を参照。https://www.2020tkbgakucho.net/ (2020年11月22日閲覧)
[iv] 2020年12月23日に「国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて~社会変革を駆動する真の経営体へ 最終とりまとめ(案)」が公表された。そこには、本稿で注目した学長選考をめぐる「留意事項」の記述と同趣旨の内容を述べた一節があるが、下記のようにかなり表現が調整されているのが興味深い。
国立大学法人の学長は、学長選考会議が、その責任と権限の下、自ら定める基準により主体的に選考することとされている。したがって、学長選考会議が意向投票の結果に拘束されることがあってはならず、例えば、候補者のうちの一人が過半数を獲得するまで意向投票を行うことにより、学長選考会議が、意向投票の結果をそのまま選考結果に反映させ、過度に学内の意見に偏るように受け取られることは避けるべきである。また、学長選考会議が、意向投票を一つの手段として活用する場合には、学長候補者が学内構成員と確固たる信頼関係を築き、その下で強力なリーダーシップを発揮できる能力を有するかどうかの確認の参考とするなど、実施目的や位置付けを明確にして、説明責任を果たすべきである。(下線部引用者)
全体としては、あいかわらず「親子関係」を彷彿とさせる権威主義的な口調が読み取れるものの、下線部などでは各地で多発する学長選考をめぐる混乱への意識も見え隠れする。つまり、筑波大の例にも典型的にあらわれていたように、意向投票の結果を無視し学長選考会議の「責任と権限の下」で選ばれた学長候補者が、学内構成員の信頼を得られず、大学の運営に支障が生まれていることが危機感をもって受け取られつつあるのである。こうした文言の「調整」は、まさにそれが「調整」であるがゆえに全体の枠組みを正すまでには至っていないが、将来的には、こうした視点が「強力なリーダーシップ」といった耳に聞こえのいいフレーズを相対化し、精査するきっかけになることを願っている。
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20201222-mxt_hojinka-000011872_2.pdf
(2020年12月24日閲覧)
[v] 福岡教育大の学長選考会議の問題については、次のような報道がある。https://www.data-max.co.jp/article/24820/ (2020年11月22日閲覧)
[vi] 学長選考会議は、東大は16人のメンバーで構成され、筑波大は24人。決して多いとは言えない数だが、この二つの大学の会議に小林喜光氏(三菱ケミカルホールディングス取締役会長)と岸輝雄氏(新構造材料技術研究組合理事長/外務大臣科学技術顧問(外務省参与))の二名が重複して参加している。とくに小林氏は経済財政諮問会議の議員をつとめ(2013年~2014年)、産業競争力懇談会では理事長(2015年~2018年)も務めた人物である。東大の選考会議議長の小宮山宏氏も教育再生会議をはじめさまざまな政府の委員をつとめてきた。果たして、これらの人物たちが政権と「近い」のかどうか、こうした顔ぶれが一部財界人等の意向を大学の人事に反映させることにつながるかなどの判断はここでは差し控えるが、メンバー構成を継続的に注視する必要があるのはまちがいない。
東大メンバー https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400147177.pdf (2020年12月21日閲覧)
筑波大メンバー https://www.tsukuba.ac.jp/public/meeting/gakusen/2020gakusen-namelist.pdf (2020年12月21日閲覧)
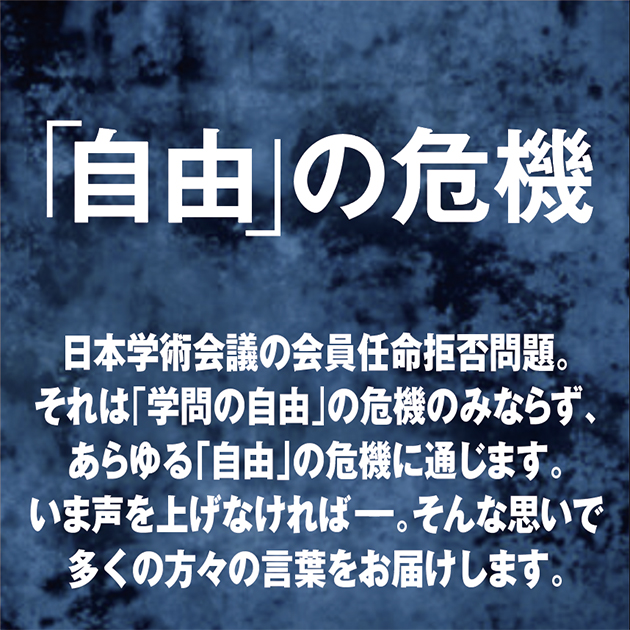
日本学術会議の会員任命拒否問題。 それは「学問の自由」の危機のみならず、あらゆる「自由」の危機に通じます。 いま声を上げなければ−−。そんな思いで多くの方々の言葉をお届けします。
プロフィール

英米文学者。東京大学大学院人文社会系研究科教授。1966年神奈川県生まれ。専門は近代英米文学・英米詩。東京大学大学院修士課程修了、ケンブリッジ大学大学院にて博士号取得。訳書に『フランク・オコナー短篇集』(岩波文庫)、共著書に『ことばの危機 大学入試改革・教育政策を問う』(集英社新書/東京大学文学部広報委員会・編)、著書に『史上最悪の英語政策 ウソだらけの「4技能」看板』(ひつじ書房)、『英詩のわかり方』『英語文章読本』(共に研究社)、『理想のリスニング:「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界』(東京大学出版会)など。
(※プロフィール写真提供:川合穂波)


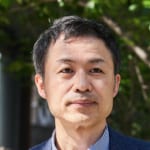 阿部公彦
阿部公彦









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

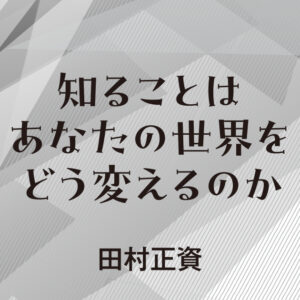
 田村正資
田村正資